すでにありますトピック、
http://
の中で、精神疾患などの話題も少し出てきたので、そういった類のものはこちらで展開した方が、分類上わかりやすいのではないかと思い、トピック作成致しました。
ここでは、精神疾患・精神保健・福祉・心理といった分野を中心に書き込み頂ければと思います。
厳密な線引きはありませんので、少々範囲が広くなっても構いません。
上記トピックにすでに記載頂いているコメントへのレスポンスもOKです。
少々堅苦しいイメージ?がある内容かもしれませんが、どんな事でも良いので、お気軽にお願い致します(^^)
ドキリコ
(2007/12/02 22:39↑
added sentence & picture: w a r m a r t ;ID1098147↓
心や神経を傷めたり、患ってしまっている方は、今やたくさんいます。
あなたの身近や、あなた自身はどうでしょう。
医者へかかりづらい/通院していてもよくわからない/薬を使ううち薬がなくてはならなくなっている..。
http://
当事者としての心持ちや、そばにいる者としての心配り。
千差万別ながら、知っておく基本は、何でしょうか?
経験を持ちよったり、専門的な助言が聞けたらと思います。
password 1...184
うつ病 鬱病 遺伝子 医薬産業 オーバードーズOD カウンセリング 格差社会 覚醒剤 『監獄の誕生』 キチガイ 抗精神病薬 差別 自己同一性 自殺未遂 自立支援法 心理士 睡眠薬 ストレス 精神医学 精神科医 精神障害者 精神病 精神分裂病 精神保健福祉教育 セカンドオピニオン 障害者年金 躁鬱 中毒 統合失調症 脳内伝達物質 非定型 副作用 ヘルマン・ヘッセ ミシェル・フーコー メンタル ラピッドサイクラー 離人症 リタリン リハビリテーション レーガノミックス
http://
http://
|
|
|
|
コメント(343)
>303 w a r m a r t さん、
お見舞いありがとうございます。長年の各国の多くの医師たちとの経験および自ら調べたりしたことから、薬に関しては詳しくなり、またその他の手段もいくつか試みた結果、症状は緩解してきています。
イギリスの制度やフランス、アイルランドの医師たちのこと、さらに(229)のイタリアのことなど、あらためて知っていることをまとめて書いたほうがよさそうですね。ちょっと(302)の説明では舌足らずでした。そのうち機会/時間があれば書き込みます。日本の医師たちとの付き合いも長かったので日本の現状と過去を比較することもできるかもしれません。ただし、専門的にリサーチするほどの時間はとれないのであくまで個人的な経験談になると思います。
今日はちょっと例外で今から薬を飲んで眠ります。昼間働いている友人宅にお世話になっているので、帰国してからは基本的にはできるだけ彼に合わせて眠るようにしています。
お見舞いありがとうございます。長年の各国の多くの医師たちとの経験および自ら調べたりしたことから、薬に関しては詳しくなり、またその他の手段もいくつか試みた結果、症状は緩解してきています。
イギリスの制度やフランス、アイルランドの医師たちのこと、さらに(229)のイタリアのことなど、あらためて知っていることをまとめて書いたほうがよさそうですね。ちょっと(302)の説明では舌足らずでした。そのうち機会/時間があれば書き込みます。日本の医師たちとの付き合いも長かったので日本の現状と過去を比較することもできるかもしれません。ただし、専門的にリサーチするほどの時間はとれないのであくまで個人的な経験談になると思います。
今日はちょっと例外で今から薬を飲んで眠ります。昼間働いている友人宅にお世話になっているので、帰国してからは基本的にはできるだけ彼に合わせて眠るようにしています。
>304
まったく矛盾するようで恐縮ですが、断片的な情報をたまたま見つけたので1つ。3月1日付けのBBCの記事です。
http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/7915727.stm
つまり、イギリスでは公共医療制度では国民1人1人は1人の GP(一般医、ホームドクター:とりあえずまずこの GP の診察を受けてから、必要に応じて専門医が紹介される仕組みです)にしか登録できませんし、その GP がいる医院 (surgery) が小規模で1人のGPしかいなければそのGPにまず診察を受けることから医療行為が始まります。もっとも surgery の規模が大きければ、複数の GP がいるので自分の登録していない GP の診察を受けることも普通です。
で、上の記事はそれを改善してとくに問題の多い糖尿病などの専門医も地域に密着した形で常駐している polyclinic なる総合病院 (hospital) と医院 (surgery) の中間に位置する医療施設をコミュニティーの大きさに合わせて作る。そうした上で、登録してある医院のみならず polyclinic にも GP を通さずに診察を受けにいくことができるようにすれば医療効率もあがるという政府の政策提言をあつかっています。それに対して、専門家グループの調査では、polyclinic をつくっても実質的な効果がないという調査報告が報道されています。
イギリスでも医療の問題は最大課題の1つで日々、試行錯誤がなされているようです。
まったく矛盾するようで恐縮ですが、断片的な情報をたまたま見つけたので1つ。3月1日付けのBBCの記事です。
http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/7915727.stm
つまり、イギリスでは公共医療制度では国民1人1人は1人の GP(一般医、ホームドクター:とりあえずまずこの GP の診察を受けてから、必要に応じて専門医が紹介される仕組みです)にしか登録できませんし、その GP がいる医院 (surgery) が小規模で1人のGPしかいなければそのGPにまず診察を受けることから医療行為が始まります。もっとも surgery の規模が大きければ、複数の GP がいるので自分の登録していない GP の診察を受けることも普通です。
で、上の記事はそれを改善してとくに問題の多い糖尿病などの専門医も地域に密着した形で常駐している polyclinic なる総合病院 (hospital) と医院 (surgery) の中間に位置する医療施設をコミュニティーの大きさに合わせて作る。そうした上で、登録してある医院のみならず polyclinic にも GP を通さずに診察を受けにいくことができるようにすれば医療効率もあがるという政府の政策提言をあつかっています。それに対して、専門家グループの調査では、polyclinic をつくっても実質的な効果がないという調査報告が報道されています。
イギリスでも医療の問題は最大課題の1つで日々、試行錯誤がなされているようです。
> arakunさん ; 304
ご自身で症状を少しでも管制できるようになったのは何よりですね。
個人差を突きとめるまでの各人の苦労が、広い情報共有で省力化されるといいのにと感じます。
医療に限らず、当国の事情や課題をよく知るためには他国との比較が役に立ちます。
でも、インターネットが発達したとはいえ、まだその歴史も20年など浅いせいか、
他国の詳細を知るにもまだ、報道や比較資料あるいは手間を要する書籍情報などに限られるなか、こうしたインターネットを通じた経験談は貴重だと感じます。
306、紹介ありがとうございます。
イギリスのGPとはつまり、主治医を地域で自動的に指定されるということだとすると、
患者としての総合的な情報把握に貢献する制度だと感じました。
人口と医師人口との不均衡という課題はありながら、
それは個人別の情報集約という制定をする/しないに係わらない別問題かとも思うとその点、イギリスは進んでいるように感じました。
そのポリクリニックとは、日本での市民病院みたいな中・大規模の公共施設を指すのだとしたら、
従来イギリスには市民病院のようなものが少ないということでしょうか、
だとしたら心象を外れる驚きです。
>308 w a r m a r t さん
イギリスの医療制度の話の続きですが、ちょっと気になったのでイギリスの医療サービスの本家本元の統括組織である NHS (National Health Service) のサイトを見ていたら、精神医療に関して及び患者による医療機関の選択に関しての双方に関わることが書かれているページがちょうどありました。
http://www.nhs.uk/choices/Pages/Aboutpatientchoice.aspx
簡単に言えば、2008年4月から患者は GP を通してではありますが、専門病院や総合病院の自主選択の権利を持てる制度に移行中ということです。ただし、最後のところに書かれているように、精神医療と出産に関しては選択権はないままとなっています。
基本的には、イギリスの医療制度(正式には、England, Wales, Scotland, Northern Irelandは別組織ですが)に関しては、
http://www.nhs.uk
で把握できます。
また、公共医療が無料かどうかに関しては<302>で書いたように処方箋代が1薬剤あたり現行 7.1ポンドかかりますが、実際には89%の人々は England に関しては支払う必要はありません。すなわち、低所得者、フルタイムの学生(日本人でも)、老人、子どもなどは免除ですし、長期にわたる特定の病気などのいくつかに関しても処方箋料金は発生しません。私のようにそれらに該当しない立場ですと支払っていたということです。因みに、Wales, Scotland, Northern Ireland では処方箋料金制度はありません。すべて無料です。England でもすべて無料に戻すべきだという世論や専門家の意見は最近とみに強くなっています。それに関しての記事は、
http://www.guardian.co.uk/society/2009/mar/05/prescription-charges-england
でまさに今日報道されています。このガーディアン紙によれば、イングランドの医師の団体(日本でいう医師会)が病気の種類によって処方箋料金を徴収するしないを決定することには医学的な根拠に乏しい、また、89%の人が支払っていない現状で社会公正の点でも公正さを欠く(つまり処方箋料金を徴収するせいで医療機関に行かない選択をする病気の人もいる。たとえば低所得とは認定されないが実際には貧しい人たちなどがいる)として全面的に処方箋料金はなしにせよと訴えています。
ところで市民病院のようなものというのが実は私にはイギリスとの比較でよく分からないのですが、イギリスにももちろん大中規模の病院はおそらく日本並みにあります。決定的な日本との違いは何度も繰り返すことになりますが、そこに GP の紹介なしに患者が直接診察を受けに行くことができないということです。そしてその予約のために恐ろしく長期間にわたって待たされることも日常的だということです。また、<306>でも書いたように GP が複数いる大きめの surgery は日本でいえばそこそこの規模(中規模)の病院のような感じでもあります。という意味では「市民病院」らしきものとそれを言ってもいいのかも知れません。ここでも、また、ただしとなりますが、それはあくまで病院ではなく、surgery ですので専門医がいるとは限りません。やはり、必要に応じてそこから専門医のいる病院を紹介される訳です。primary care と secondary care がかなり厳密に分かれているということです。
ただし、救急病院としての機能は大中の病院 (hospital) が果たしていますので、救急車に乗るような事態、乗らなくても緊急であれば直接そこに行くことはできます。ただし、現状では、血を流しながら数時間待っている緊急患者が放置されているということもしばしば起こっているのが現実です。
イギリスの医療制度の話の続きですが、ちょっと気になったのでイギリスの医療サービスの本家本元の統括組織である NHS (National Health Service) のサイトを見ていたら、精神医療に関して及び患者による医療機関の選択に関しての双方に関わることが書かれているページがちょうどありました。
http://www.nhs.uk/choices/Pages/Aboutpatientchoice.aspx
簡単に言えば、2008年4月から患者は GP を通してではありますが、専門病院や総合病院の自主選択の権利を持てる制度に移行中ということです。ただし、最後のところに書かれているように、精神医療と出産に関しては選択権はないままとなっています。
基本的には、イギリスの医療制度(正式には、England, Wales, Scotland, Northern Irelandは別組織ですが)に関しては、
http://www.nhs.uk
で把握できます。
また、公共医療が無料かどうかに関しては<302>で書いたように処方箋代が1薬剤あたり現行 7.1ポンドかかりますが、実際には89%の人々は England に関しては支払う必要はありません。すなわち、低所得者、フルタイムの学生(日本人でも)、老人、子どもなどは免除ですし、長期にわたる特定の病気などのいくつかに関しても処方箋料金は発生しません。私のようにそれらに該当しない立場ですと支払っていたということです。因みに、Wales, Scotland, Northern Ireland では処方箋料金制度はありません。すべて無料です。England でもすべて無料に戻すべきだという世論や専門家の意見は最近とみに強くなっています。それに関しての記事は、
http://www.guardian.co.uk/society/2009/mar/05/prescription-charges-england
でまさに今日報道されています。このガーディアン紙によれば、イングランドの医師の団体(日本でいう医師会)が病気の種類によって処方箋料金を徴収するしないを決定することには医学的な根拠に乏しい、また、89%の人が支払っていない現状で社会公正の点でも公正さを欠く(つまり処方箋料金を徴収するせいで医療機関に行かない選択をする病気の人もいる。たとえば低所得とは認定されないが実際には貧しい人たちなどがいる)として全面的に処方箋料金はなしにせよと訴えています。
ところで市民病院のようなものというのが実は私にはイギリスとの比較でよく分からないのですが、イギリスにももちろん大中規模の病院はおそらく日本並みにあります。決定的な日本との違いは何度も繰り返すことになりますが、そこに GP の紹介なしに患者が直接診察を受けに行くことができないということです。そしてその予約のために恐ろしく長期間にわたって待たされることも日常的だということです。また、<306>でも書いたように GP が複数いる大きめの surgery は日本でいえばそこそこの規模(中規模)の病院のような感じでもあります。という意味では「市民病院」らしきものとそれを言ってもいいのかも知れません。ここでも、また、ただしとなりますが、それはあくまで病院ではなく、surgery ですので専門医がいるとは限りません。やはり、必要に応じてそこから専門医のいる病院を紹介される訳です。primary care と secondary care がかなり厳密に分かれているということです。
ただし、救急病院としての機能は大中の病院 (hospital) が果たしていますので、救急車に乗るような事態、乗らなくても緊急であれば直接そこに行くことはできます。ただし、現状では、血を流しながら数時間待っている緊急患者が放置されているということもしばしば起こっているのが現実です。
途中からの割り込みで失礼します。
≫301 2009年03月01日 14:00 warmartさん
オレも この番組を拝見しました。
精神科医の間でも、今まで投薬療法のガイドラインや治療方針にバラツキがあることも取り上げられていたので、それなりに 日本の精神科医療の実態を知る参考になりました。
イギリスのケースは、日本よりも現状は進んでるように見受けられましたが、(臨床心理士との併用などを含めて公的なサービスとしての拡充)、arankunさんの詳しい現地での実態をうかがってると、十全な対応には まだ不充分なようですね。
精神治療は発見するだけでも難しいですし、諦めずに気の長い取り組みが必要だと思いますが、治療効果と 周囲の理解の重要性については、まだホンの少し光が当てられたにすぎない段階という事でしょうか。
すでに5年以上、闘病している知人がおりますが、一向に改善されないような話を聞くと、切実に悩む人達のためにも せめて統一した”信頼できる”情報が必要だという思いを強くしました。
同じ精神症に起因する病名でも 人によって症状も様々ですし、通院そのものにも、大きな抵抗感があるようです。
また、微細な症状の見落としや誤診率も高く、自己診断で悩みを抱えられておられる人が多いのは、本当に心が痛みます。
しかも、従来とはまた別の 新たな症例まで見つかるといった堂々巡りの状態が、少しでも「改善」される事を願ってやみません。
ここで、さらに突っ込んだ内容が伺えて非常に参考になりました。
ありがとうございました。
≫301 2009年03月01日 14:00 warmartさん
オレも この番組を拝見しました。
精神科医の間でも、今まで投薬療法のガイドラインや治療方針にバラツキがあることも取り上げられていたので、それなりに 日本の精神科医療の実態を知る参考になりました。
イギリスのケースは、日本よりも現状は進んでるように見受けられましたが、(臨床心理士との併用などを含めて公的なサービスとしての拡充)、arankunさんの詳しい現地での実態をうかがってると、十全な対応には まだ不充分なようですね。
精神治療は発見するだけでも難しいですし、諦めずに気の長い取り組みが必要だと思いますが、治療効果と 周囲の理解の重要性については、まだホンの少し光が当てられたにすぎない段階という事でしょうか。
すでに5年以上、闘病している知人がおりますが、一向に改善されないような話を聞くと、切実に悩む人達のためにも せめて統一した”信頼できる”情報が必要だという思いを強くしました。
同じ精神症に起因する病名でも 人によって症状も様々ですし、通院そのものにも、大きな抵抗感があるようです。
また、微細な症状の見落としや誤診率も高く、自己診断で悩みを抱えられておられる人が多いのは、本当に心が痛みます。
しかも、従来とはまた別の 新たな症例まで見つかるといった堂々巡りの状態が、少しでも「改善」される事を願ってやみません。
ここで、さらに突っ込んだ内容が伺えて非常に参考になりました。
ありがとうございました。
『精神疾患: 血液で判断
たんぱく質データ判定 大阪市大院』
大阪市大大学院医学研究科の関山敦生・客員准教授(43)=心身医学、分子病態学=が兵庫医科大と共同で、
うつ病や統合失調症などの精神疾患を判定できる血液中の分子を発見、血液検査に基づく判定法を確立した。
問診や行動観察が主流だった精神科診療で、客観的な数値指標を診断に取り入れることができる。
疾患の判定だけではなくストレスの強度や回復程度もわかるという。
関山准教授は27日午後、京都市の立命館大学で開かれる日本心理学会で発表する。
関山准教授によると、ストレスや感染などを受けて、生成し分泌されるたんぱく質「サイトカイン」の血中濃度データの差異を積み上げて分析。
データをパターン化することで、心身の変調やうつ病、統合失調症などを判定できることが分かった。
うつ病や統合失調症について3000人近くのデータから疾患の判定式を作成。
別の400人の診断に用いた結果、うつ病の正診率は95%、統合失調症は96%に達した。
精神疾患の判定だけではなく、健常者に対するストレスの強度、疲労からの回復スピードも数値化した。
80人の男女を対象に、計算作業で精神的ストレス、エアロバイクなどで身体的ストレスを加える実験を実施。
いずれのストレスを受けたか100%判別することに成功し、ストレスの強度を数値で評価できる方法もつくり出したという。
【深尾昭寛】
毎日新聞 2009/08/26 02:30
http://mainichi.jp/select/science/news/20090826k0000m040145000c.html↑
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=940705&media_id=2
NHK『日本の、これから』
http://www.nhk.or.jp/korekara/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E3%80%81%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%8B%E3%82%89
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=47182043
第28回テーマ 『自殺』
12/4(金)22:00‐23:30 総合ch
http://www.nhk.or.jp/korekara/nk28_j/enq.html↓
Q1
自殺願望について
あなたは、死にたいと思ったことはありますか?
「ある」という方はそのときの状況を、「ない」という方は自殺しようとする人のことをどう思うか、お書きください。
1)ある
2)ない
Q2
自殺に対する考え方について
日本では「切腹」、「心中」など歴史的・文化的に自殺が許容されてきた側面がありますが、あなたは自殺そのものについてどうお考えですか?
理由とともに具体的にお書きください。
1)どんな理由であれ自ら命を絶つことは許されない
2)やむを得ない自殺もある
Q3
自殺者増加とその原因について
自殺を巡る現状とその原因についてうかがいます。
A.自殺者が毎年3万人出るのは、どこに問題があるのか
B.自殺する人はなぜ自ら死を選んでしまうのか
A・Bそれぞれについて、あなたのお考えを自由にお書きください。
Q4
自殺の対策について
国は平成28年までに、自殺死亡率を20%以上減らすことを目標に、
相談窓口の充実や、駅ホームに柵を設置するなど、様々な施策を打ち立てています。
※参照:内閣府自殺対策ホームページ
http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/jirei/jirei.html#d6
番組では、こうした施策に加え、国、社会、地域、企業やあなた自身ができる自殺者を減らすための画期的なアイデアを募集します。
あなたが考える自殺対策を具体的にお書きください。
集まったアイデアの中から、いくつか番組内で紹介させていただく予定です。
※対策はすべきではない、あるいは、しても効果が無いとお考えの方は、その理由をお書きください。
Q5
自殺への疑問やご意見、体験談など
自殺に関しての素朴な疑問や、ご意見などがあればご自由にお書きください。
またご家族や友人など、身の回りで自殺や自殺未遂をした方がいらっしゃる場合はその体験や、そこからあなたが感じたことなどもお書き下さい。
>路上生活者の6割が精神疾患
ないと思うのが不自然なぐらいですね。
例えば、AD/HDとか。
私は最近これを知ったのだけれども、自分はこれじゃないかと思っている。
まあ、知った時には誰でもそう思うらしいが。
ただまあ、調べるつもりはない。
今更知った所で、何の意味もないし。
もう、占いで自分で食っていけるし、対人関係ではクライアントとの関係にのみ気をつければ、仲間なんて似た様な奴らばかり。
だが考える。
私がもし、無理に会社生活を続けていたらどうなっていたであろうかを。
まあ、間違いなくドロップアウトして、路上生活の仲間入りだろう。
抵抗も少ないし。
今ならアレか、ネカフェ難民ってやつ?
でも、人によっては幸せは家でないだろうし、仕事でもない場合があるだろう。
明日に道を聞かば夕べに死すとも可なり、ともいう。
だから、救済措置を持ってあたるのも良いが、全員を私達の価値観で助けようとしてはいけない。
ないと思うのが不自然なぐらいですね。
例えば、AD/HDとか。
私は最近これを知ったのだけれども、自分はこれじゃないかと思っている。
まあ、知った時には誰でもそう思うらしいが。
ただまあ、調べるつもりはない。
今更知った所で、何の意味もないし。
もう、占いで自分で食っていけるし、対人関係ではクライアントとの関係にのみ気をつければ、仲間なんて似た様な奴らばかり。
だが考える。
私がもし、無理に会社生活を続けていたらどうなっていたであろうかを。
まあ、間違いなくドロップアウトして、路上生活の仲間入りだろう。
抵抗も少ないし。
今ならアレか、ネカフェ難民ってやつ?
でも、人によっては幸せは家でないだろうし、仕事でもない場合があるだろう。
明日に道を聞かば夕べに死すとも可なり、ともいう。
だから、救済措置を持ってあたるのも良いが、全員を私達の価値観で助けようとしてはいけない。
注意欠陥・多動性障害(ちゅういけっかん・たどうせいしょうがい、英語: AD/HD: Attention Deficit / Hyperactivity Disorder)は多動性、不注意、衝動性を症状の特徴とする発達障害もしくは行動障害。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%A8%E6%84%8F%E6%AC%A0%E9%99%A5%E3%83%BB%E5%A4%9A%E5%8B%95%E6%80%A7%E9%9A%9C%E5%AE%B3↑
僕自身もそういう傾向があるんじゃないかと感じました。
私達の価値観とは?
PC:comment=7
http://mixi.jp/view_bbs.pl?&page=1&id=47292586
MB:comment=7
http://mixi.jp/view_bbs.pl?&page=2&id=47292586&readmode=start
それはそうですね。
同意です。
> ホームレスという群像に対する支援の要不要という分類があれば、強制退去か移動指導かに分かれるとも考えます。
> 好況期・バブル期にもホームレスはいました。
> いわゆる完全失業者ではない、むしろホームレスを積極的に生業とする人々です。
> (少し文脈がずれますが、経済成長や自由主義経済の加速が環境問題や飢餓など国際問題を生む遠因となっていると僕は考えるので、勤労の義務かつ権利について疑問を抱いてはいるのですが、)
> この職業ホームレスという人々への社会的対応という疑問が残りつつも、まずは彼らを支援する必要はないでしょう。
> しかしリストラなどから段階的に職や住居や財産を失い、ホームレスにならざるを得なかった完全失業者方には、
> 公的な支援を確立するよう政治へ求めてゆかなくてはならないでしょうし、民間や地域での支援も推奨されてしかるべきです。
> ただし、完全失業ホームレス方であっても法は守ってもらわねばならない。
> また、完全失業者方の一部に、失業や生活困窮のなか、求職や勤労の意欲を失ったり・職業ホームレスへ傾倒してゆく人々、
> つまり “境界型ホームレス” の増加が懸念され、これは新たな課題のように感じられます。
PC:comment=230
http://mixi.jp/view_bbs.pl?&page=12&id=40859489↑
MB:comment=230
http://mixi.jp/view_bbs.pl?&page=46&id=40859489&readmode=start↑
PC:comment=247
http://mixi.jp/view_bbs.pl?&page=13&id=14503467
MB:comment=247
http://mixi.jp/view_bbs.pl?&page=50&id=14503467&readmode=start
脳はすばらしい器官。
朝起きた瞬間から活動を始め、止まることを知らない。
会社に行くまでは。
ロバート・フロスト
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%88↑
新型うつ病の症状
1. 自分の好きな仕事や活動の時だけ元気になる
2. 「鬱」で休職することにあまり抵抗がなく、新型は逆に利用する傾向がある
3. 身体的疲労感や不調感を伴うことが多いのが新型
4. 自責感に乏しく、他罰的で会社や上司のせいにしがち
5. どちらかというと真面目で負けず嫌いな性格
「3」と「5」は従来と同じ症状ですが、新型うつ病と呼ばれている場合の違いは
☆ 嫌な時だけ気分が悪くなる
☆ 自分でなく他人の責任にするのが新型の特徴
☆ 20‐30代前半の若い世代に発症して、逃避型や回避型などと呼ばれている
もともと症状や病気になる過程によって「メランコリー型」「双極性障害」「気分変調症」「非定型」の大きく4つに分類される。
「新型うつ病」と呼ばれているのが「気分変調症」「非定型」に当たるのだといわれてます。
新型うつ病急増の理由
医師が「うつ病」と診断する際の基準は、世界的に2通りあります。
今までは米国型の従来の診断基準が主でした。
もう1つ「軽症」の診断基準があり、そちらに当てはまる患者が多数いたことが最近になって判明した為に患者数が急増したように見えてるのが「新型うつ病急増」の背景です。
「気分変調症」「非定型」の患者数が増えた訳でなく、つまり診断基準が広くなった為に「新型うつ病」の患者が急増しているように見えるだけです。
気分変調症・非定型 診断基準
「うつ病」の自覚がある人で診療機関に受診したのは24%
年々増加する患者数。
2008年最近のインターネット調査で12%の人が「うつ病」の自覚症状があると答えております。
しかし、ほとんどの方は診療機関に赴くことなく受診率が低いです。
主な理由としては「周囲人に相談しにくい」ということです。
しかし最近では、うつ病は社会的に認められていている病気です。
休職制度・傷害手当金・障害年金ときちんとした制度が確立しつつあります。
早期に診療機関に受診されることと、周囲の家族に相談されることをお勧め致します。
新型うつ病かと思われたら、無理に頑張って、その後治療するのに時間が掛かるよりは早期診断が良い選択です。
例えば、会社勤めで厚生年金に加入している方が鬱となり労働が困難になった場合、 障害年金2級に申請して受給できれば、年間に140万円ほど国から年金を受給でるようになってます。
国民健康保険を減免
新型うつ病でも、年金と違い国民健康保険を減免してもらえるのは、「ある一定の収入以下の場合」と言われてます。
基準は世帯ごとの年収で決まります。
2割軽減
世帯の合計基準所得が、33万円以下
5割軽減
世帯の合計基準所得が、33万円+24万円5千円×被保険 者数(世帯主を除く)以下
7割軽減
世帯の合計基準所得が、33万円+35万円×国保加入者以下
http://heartland.geocities.jp/singatautu/↑
http://www.fuanclinic.com/byouki/imidas.htm
“自殺者:
遺族らを2次被害から守る
全国で署名活動へ”
自殺に対する偏見や理不尽な損害賠償請求から遺族や未遂者を守ろうと専門家や遺族が3日、国に「二次被害者保護法」の制定を求めて全国で署名活動を始める。
3日は東京都内でシンポジウムも開き、遺族らの置かれた状況を訴えて協力を呼び掛ける。
活動を進めているのは、全国自死遺族連絡会の世話人で、仙台市の自助グループ「藍の会」代表の田中幸子さん(61)や、精神科医で聖学院大学大学院(埼玉県上尾市)の平山正実教授(71)ら。
06年に施行された自殺対策基本法は「未遂者や遺族の名誉に配慮し不当に侵害してはならない」と規定した。
しかし田中代表によると仙台市の父親はアパートの自室で娘が自殺したため不動産業者に火葬場まで押しかけられ家賃補償や「おはらい料」など計1000万円を要求されるなど法施行後も精神的、経済的に追い込まれる例が後を絶たないという。
このため、
(1)医療施設や公的機関での遺族、未遂者への人権配慮
(2)遺族らへの不当請求の禁止
(3)一元的な支援窓口の設置−−などを柱とする保護法の制定を求め、11年3月までに15万人分の署名を目指す。
【百武信幸】
2010/06/02 毎日新聞
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100602ddm012040104000c.html
“自殺を予防する自殺事例報道のあり方”
自殺を予防する自殺事例報道のあり方(じさつをよぼうするじさつじれいほうどうのありかた)は、2000年に『自殺予防に向けた学校の教職員のための資料』(Preventing Suicide, A resource for teachers and other school staff)と同時に発表された自殺防止を目的にした世界保健機関(WHO)の勧告である。
根拠
1984年から1987年にかけて、オーストリアのウィーンでは、ジャーナリストが報道方法を変えたことで、地下鉄での自殺や類似の自殺が80%以上減少した。
また、自殺率を減らす効果があった。
さらに教員やスクールカウンセラーのために作成された『自殺予防に向けた学校の教職員のための資料』では世界的に15歳から19歳までの年齢層の死因に自殺が多いことを指摘している。
すべきこと
事実の公表に際して保険の専門家と密接に連動する
自殺は自殺成功とではなく自殺既遂と呼ぶ
関連する情報だけを中面記事として公表する
自殺に代わる手段を強調する
電話相談や地域の支援機関に関する情報を提供する
危険指標や危険信号について周知させる
すべきではないこと
写真や遺書を公開しない
具体的で詳細な自殺手段を報告しない
単純化した理由付けをしない
自殺を美化したり、扇情的に扱わない
宗教的な固定観念や文化的固定観点を用いない
悪人探しをしない
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E6%AE%BA%E3%82%92%E4%BA%88%E9%98%B2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%87%AA%E6%AE%BA%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E5%A0%B1%E9%81%93%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8A%E6%96%B9
“「障害」を「症」に 精神疾患の新名称公表”
日本精神神経学会は28日、米国で昨年策定された精神疾患の新診断基準「DSM−5」で示された病名の日本語訳を公表した。
子供や不安に関する疾患では「障害」を「症」に改めるなど、差別意識を生まないよう配慮した。
主な例では「注意欠陥・多動性障害(ADHD)」は「注意欠如・多動症」に、「性同一性障害」は「性別違和」に変更。
「アスペルガー症候群」は単独の疾患としての区分はなくなり、「自閉スペクトラム症」に統合された。
医療現場では旧版の「DSM−4」などを診断に使い続ける医師もおり、当面は病名が混在する可能性もあるが、学会では「徐々に浸透していくことを期待している」としている。
2014/05/28-18:44 産経新聞 http://sankei.jp.msn.com/life/news/140528/bdy14052818440002-n1.htm CP:http://zhp.jp/OLIj
>>[322]
“『DSM-5 病名・用語翻訳ガイドライン』に見る「障害」表記をめぐる議論の行方”
日本精神神経学会は5月28日に『DSM-5 病名・用語翻訳ガイドライン』を公表し「学習障害」を「学習症」に改める(ただし、以前の訳語がある程度普及しているものに関しては「パニック症/パニック障害」のように旧訳を並記する)など、これまで多くの用語において「障害」と訳されて来た“disorder”の訳語を「児童青年期の疾患と不安症およびその一部の関連疾患」を中心に「症」に改める等の方針を打ち出しました。
毎日新聞や共同通信がこのニュースを報じた当初から 『Twitter』などでは2000年以降に多くの地方自治体で採用されている交ぜ書きの「障がい」と同様の「過剰な“言葉狩り”ではないか」との批判も出ていますが、今回のガイドラインが公表された背景を考えるに当たっては今回公表されたガイドラインの「はじめに」でも disorder を「障害」とすると、 disability の「障害(碍)」と混同され,しかも“不可逆的な状態にある”との誤解を生じることもあると指摘されているように、そもそも disorder、disability、impairmentなど英語ではそれぞれ意味合いが異なる単語を翻訳する際に「障害」の一語で乱暴に包摂して来た経緯を考える必要があるでしょう。
日本では1946年の当用漢字表告示を機として文字通り“一掃”された「障碍」は繁体字表記を「障礙」と書くことからもわかるように、元来は「道をふさぐように置かれている石を疑う」と言う意味を持つ漢字です。
現在も中国では「障碍」、また香港や台湾では「障礙」表記が、漢字が日常的に用いられなくなった韓国でも「障碍」を由来とする??(チャンエ)が使用されていますが、対する「障害」は日本で明治初期に disorder の訳語として考案された医学用語が起源とみられるものの中国や香港、台湾では使用されていません。
韓国では日本統治時代に入って来た「障害」が??(チャンへ)として医学用語の分野では現在も使われていますが、この語が日本の「障害」のような disability の意味で使われることはまずありません。
過去にも「痴呆症」が「認知症」、また「精神分裂病」が「統合失調症」と改名されて来た経緯があるように当初の名称が症例を表す際に不適切なものであったり、主として完治の見込みが無いと言う不可逆的なものであると言う誤解を生じさせる場合の用語の見直しは常に行われて来ました。
日本精神神経学会が公表した今回のガイドラインに対しても、短絡的に「言葉狩り」と決め付けるのではなく、これまで余りにも多くのニュアンスが異なる英単語を「障害」で一くくりにして来たことが本当に訳として適切であったのかを、多くの要望がありながらも文化庁が今なお拒絶し続けている「碍」の常用漢字追加を含めて考え直す契機とする必要があるでしょう。
DSM-5 病名・用語翻訳ガイドライン(日本精神神経学会) http://www.jspn.or.jp/activity/opinion/dsm-5/ CP:http://zhp.jp/HJhO
(84oca ウェブライター)
↑ 2014/06/02-17:00 ガジェット通信 http://getnews.jp/archives/588857 CP:http://zhp.jp/XKEi
“『DSM-5 病名・用語翻訳ガイドライン』に見る「障害」表記をめぐる議論の行方”
日本精神神経学会は5月28日に『DSM-5 病名・用語翻訳ガイドライン』を公表し「学習障害」を「学習症」に改める(ただし、以前の訳語がある程度普及しているものに関しては「パニック症/パニック障害」のように旧訳を並記する)など、これまで多くの用語において「障害」と訳されて来た“disorder”の訳語を「児童青年期の疾患と不安症およびその一部の関連疾患」を中心に「症」に改める等の方針を打ち出しました。
毎日新聞や共同通信がこのニュースを報じた当初から 『Twitter』などでは2000年以降に多くの地方自治体で採用されている交ぜ書きの「障がい」と同様の「過剰な“言葉狩り”ではないか」との批判も出ていますが、今回のガイドラインが公表された背景を考えるに当たっては今回公表されたガイドラインの「はじめに」でも disorder を「障害」とすると、 disability の「障害(碍)」と混同され,しかも“不可逆的な状態にある”との誤解を生じることもあると指摘されているように、そもそも disorder、disability、impairmentなど英語ではそれぞれ意味合いが異なる単語を翻訳する際に「障害」の一語で乱暴に包摂して来た経緯を考える必要があるでしょう。
日本では1946年の当用漢字表告示を機として文字通り“一掃”された「障碍」は繁体字表記を「障礙」と書くことからもわかるように、元来は「道をふさぐように置かれている石を疑う」と言う意味を持つ漢字です。
現在も中国では「障碍」、また香港や台湾では「障礙」表記が、漢字が日常的に用いられなくなった韓国でも「障碍」を由来とする??(チャンエ)が使用されていますが、対する「障害」は日本で明治初期に disorder の訳語として考案された医学用語が起源とみられるものの中国や香港、台湾では使用されていません。
韓国では日本統治時代に入って来た「障害」が??(チャンへ)として医学用語の分野では現在も使われていますが、この語が日本の「障害」のような disability の意味で使われることはまずありません。
過去にも「痴呆症」が「認知症」、また「精神分裂病」が「統合失調症」と改名されて来た経緯があるように当初の名称が症例を表す際に不適切なものであったり、主として完治の見込みが無いと言う不可逆的なものであると言う誤解を生じさせる場合の用語の見直しは常に行われて来ました。
日本精神神経学会が公表した今回のガイドラインに対しても、短絡的に「言葉狩り」と決め付けるのではなく、これまで余りにも多くのニュアンスが異なる英単語を「障害」で一くくりにして来たことが本当に訳として適切であったのかを、多くの要望がありながらも文化庁が今なお拒絶し続けている「碍」の常用漢字追加を含めて考え直す契機とする必要があるでしょう。
DSM-5 病名・用語翻訳ガイドライン(日本精神神経学会) http://www.jspn.or.jp/activity/opinion/dsm-5/ CP:http://zhp.jp/HJhO
(84oca ウェブライター)
↑ 2014/06/02-17:00 ガジェット通信 http://getnews.jp/archives/588857 CP:http://zhp.jp/XKEi
“「まるで魔法!」注目の認知症ケア技法「ユマニチュード」の秘密”
「ユマニチュード」をご存知だろうか。
なんとなく哲学的な響きをもつ言葉だが、これはフランスで生まれた認知症ケアの技法。
最近、看護や介護などの現場で劇的な効果をあげ、「魔法のようだ」と注目を集めている。
たとえば、保清・清拭は、ケア業務の半分を占めると言われるものだが、ある介護施設では、ユマニチュードによるケアの導入で、ベットで行う清拭が60%から0%になったという。
また、どんなにベテランで有能な看護師が対処しても手に負えない、いわゆる「困った患者」が、ユマニチュードを学んだ看護師のケアでは、まったく別人のように穏やかにケアを受け、笑顔で「ありがとう」とお礼まで言ってくれた。
さらに、ユマニチュードを導入した別の施設では、認知症患者の攻撃的で破壊的な行動を83%減らせたとの報告もある。
そして、今年の2月には、NHKの番組『クローズアップ現代』でユマニチュードの創始者のひとり、 イヴ ジネストらのケアによって、歩行が困難とされていた患者が短期間で立てるようになる様子が紹介され、大きな反響を呼んだ。
〔中略:warmart〕
技術の説明は具体的だ。
例えば、「見る技術」。
同じ目の高さから、顔を近づけて(0.4秒以上)見つめる。
ただ見るのではなく、こちらから視線をつかみにいく。
ベッドで壁の方に横向きになったままの患者さんなら、ベッドを動かし、壁との間に入ってでも、視線を合わせにいく。
ちょっとやり過ぎなのでは? と思うけれど、視線をとらえられないまま話しかけてもなかなか通じないのだという。
そして、視線があったら2秒以内に話かける。
その事でこちらに攻撃的な意図はない事を伝えられる。
また「話す技術」では、反応のない患者さんに言葉をかけ続けるための、「オートフィードバック」という方法を教授してくれる。
「これから腕を洗いますね」と予告し、そして腕を上げながら「腕を上げます。
左腕です。とてもよく伸びていますね」と実況中継することで、相手に反応がなくてもコミュニケーションを持続させるエネルギーを作り出すのだという。
「触れる技術」も丁寧でわかりやすい。
触れる時は飛行機が着陸するイメージで、離す時は飛行機が離陸するイメージで行う。
そして、「立たせる技術」では、「40秒間立つことができたら寝たきりは防げる」と、立つことの重要性を説いたうえで、まず握手することから始まる介助のテクニックを事細かに説明してくれる。
ユマニチュードは、全部で150をこえるこういった実践技術に基づいて成り立っており、だからこそ誰にでも実行でき、魔法のような効果をあげているのだ。
〔中略:warmart〕
《ユマニチュードの理念は絆です。
人間は相手がいなければ存在できません。
あなたがわたしに対して人として尊重した態度をとり、人として尊重して話しかけてくれることによって、わたしは人間となるのです。
わたしがここにいるのは、あなたがここにいてくれるからです、逆にあなたがここにいるのも、わたしがここにいるからです。
わたしが誰かをケアするとき、その中心にあるのは「その人」ではありません。
ましてや、その人の「病気」ではありません。
中心にあるのは、わたしとその人との「絆」です。》(同書)
そう、まさに、ユマニチュードは哲学なのだ。
しかし、誤解してはならないのは、これはあくまでも、哲学に基づく〈技術〉であって精神論とは異なるということ。
だから、適性や優しさの問題にすり替えてはいけない。
極端にいえば、愛情を持てない相手にでも、この技術を使って人間としてきちんと向き合えば、相手を怖がらせる事もなく、威圧する事もなく、絆を築けるのだ。
優しくなくても優しくなれる。
ケアする側も育てられる技術ともいえる。
この技術をうまく習得すれば、認知症ケアだけでなく、あらゆる局面のコミュニケーションに応用することができるかもしれない。
しかし、何度も言うようだが、〈正面から目をみてやさしく話しかけるだけで〉〈力を入れずにそっと支えるだけで〉、認識能力が落ち、心閉ざした人がみるみる変わっていくなんて驚きではないか。
同書はいう。
「この本には常識しか書かれていません。
しかし、常識を徹底させると革命になります。」
そう。私たちはしょっちゅう「常識」という言葉を口にしながら、実はその常識を本気で実践しようとしてこなかったのかもしれない。
介護技術の入門書ながら、いつのまにかそんなことまで考えさせられていた。
「ユマニチュード」はやっぱり哲学だ。
(森野立)
2014/09/16 LITERA http://lite-ra.com/2014/09/post-466.html CP:http://zhp.jp/oQKl
“超高齢者の幸せのかたち 「老年的超越」に共通する価値観は”
著者は高齢者心理学が専門で、東京都老人総合研究所の研究員として活動中。
これまで高齢者、特に「超高齢者」のインタビューをたくさん積み重ねてきており、その経験からたとえばこんな話をする。
<九十歳、百歳の高齢の方は、「明日目が覚めないかもしれない」「明日はもう死んでいるかもしれない」ということを自然におっしゃいます。
私だったら、そんなことを本気で考え始めたら、ものすごく怖くなります。
でも、超高齢の方は、怖さというものを感じているようには見えません。
死に対する覚悟という雰囲気もありません。
それならば、死の恐怖を乗り越えたのかというと、そういう感じもありません。
ただあるがままに受け入れている様子です。>
ある種の悟りのような心境だろうか。
いや、ニュアンスとしてはそれとも違っていて、もっとチャーミングな感じの超高齢者が多いようだ。
<九十歳くらいの高齢の方と話していていつも驚くのは、ちょっとしたことに対しても楽しみを感じている方が多いということです。
食事に関して「ごはんがおいしい」「何を食べてもおいしい」とおっしゃる方はたくさんいます。
その他にも、「テレビを見ているのが本当に楽しい」、「お酒を飲んでいるのが楽しい」、「寝るのが大好きだ」、「お友達が来て話をするのが楽しみ」など何でも楽しみと感じるようです。>
著者によれば、70歳ぐらいでは昔できたことができなくなったせいで、自信を失い、うつ的になる場合もあるという。
だが、その段階を超えて、90歳以上になると、何か1つでも自分ができることを見つけ、「まだ、これができる」と喜べる境地になるらしい。
だけどそれって、子供や孫やひ孫など、まわりの手助けのおかげで成り立っている恵まれたケースの喜びでは?
そうも思ったのだが、違うようだ。
「子供なんて全然来ないし、孫にもずっと会っていない」という場合も少なくなく、老人たちのたいていは孤独感を抱いている。
しかし、「嫌な気分はほとんどない。
気持ちは落ち着いている。
いいことがあるわけではないけれど、とても幸せだよ」というふうに語ることが一般的なのだという。
こうした気持ちのあり方を、トルンスタムという社会学者は「老年的超越」と名づけたそうである。
従来の喜ばしき高齢者のあり方は「生涯現役」だったが、それとは正反対に思えるようなあり方も、超高齢者の幸せのかたちとして存在しているという発見だ。
その「老年的超越」には、次のような価値観が共通している。
・身体的な健康を重視しない
・外に向けた活動を重視しない
・社会的役割を重視しない
・社会的ネットワークの縮小にこだわらない
これらの項目だけを見たら、まるで重度のひきこもりのようだが、「老年的超越」は、何かから逃げているわけではない。
身体能力や社会的能力は明らかに衰えていく一方でも、「あれこれ考えない」ことによって、それを否定的に捉えず、現状をあるがままに受け入れ、今を楽しんでいる。
メカニズムはまだ解明されていないけれど、そういう境地に達しているとしか思えない超高齢者が、全体の二割くらいはいるのだそうだ。
もちろん、「老年的超越」の度合いの高い老人だって、誰かに下の世話をやってもらう必要が出てくる。
決してキレイ事だけで片付かない現実もある。
でも、そうして幸せに老いていく人生の大先輩の姿は、問題山積の超高齢化社会にあって、ひとつの救いだ。
「長生き万歳!」と言えそうに思えるのだ。
↑ 2014/09/06-16:00 NEWSポストセブン http://getnews.jp/archives/661788 CP:http://zhp.jp/fUIX
多幸感(たこうかん、英:Euphoria)とは、非常に強い幸福感や超越的満足感のことである。
脳内で、快楽などを司るA10神経のシナプス間に、幸福感を司る神経伝達物質であるセロトニンが、大量に放出されている状態とされる。
愛情による至福感や、競技で勝利したときの陶酔感、オーガズムは、多幸感の例である。
また、多幸感は宗教的儀式や瞑想によっても生じうる。
特定の薬物の副作用として生じる場合もあり、また、精神や神経の疾患によって生じる場合もある。
高齢者が自然と感じるようになる幸福感も多幸感の一種とされる(老年的超越)。
↑ Wikipedia "多幸感" http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E5%B9%B8%E6%84%9F CP:http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E5%B9%B8%E6%84%9F
統合失調症、新薬の手掛かり=患者iPSで異常発見−理研など
2016年11月12日04時29分
統合失調症患者の人工多能性幹細胞(iPS細胞)を作り、脳の神経系統の細胞に変える実験を行ったところ、神経細胞の割合が健康な人より少なく、神経細胞を助ける細胞の一種「アストロサイト」の割合が多かったと、理化学研究所などの国際研究チームが12日までに発表した。
死亡した患者の脳でも、同様の異常が確認された。胎児から誕生後の脳が発達する時期に障害が起きているとみられ、新薬を開発する手掛かりになる。論文は英医学誌トランスレーショナル・サイカイアトリー電子版に掲載された。
iPS細胞を作ったのは、22番染色体の一部に異常があるタイプの患者。神経細胞とアストロサイトの割合が決まる過程には「p38α」と呼ばれるたんぱく質が関与していることが分かった。脳神経の発達障害を改善する薬を開発できる可能性があるという。
http://www.jiji.com/sp/article?k=2016111200026
2016年11月12日04時29分
統合失調症患者の人工多能性幹細胞(iPS細胞)を作り、脳の神経系統の細胞に変える実験を行ったところ、神経細胞の割合が健康な人より少なく、神経細胞を助ける細胞の一種「アストロサイト」の割合が多かったと、理化学研究所などの国際研究チームが12日までに発表した。
死亡した患者の脳でも、同様の異常が確認された。胎児から誕生後の脳が発達する時期に障害が起きているとみられ、新薬を開発する手掛かりになる。論文は英医学誌トランスレーショナル・サイカイアトリー電子版に掲載された。
iPS細胞を作ったのは、22番染色体の一部に異常があるタイプの患者。神経細胞とアストロサイトの割合が決まる過程には「p38α」と呼ばれるたんぱく質が関与していることが分かった。脳神経の発達障害を改善する薬を開発できる可能性があるという。
http://www.jiji.com/sp/article?k=2016111200026
鈴哀さん、コメント ありがとうございます。
介護療養型医療施設・療養病床は今、特に認知症の高齢者を受け入れてもらう施設として注目されているんですね。
いわゆる精神病院や知的障害者の介護施設と大別としては近くても、人口の高齢化でその需要が年々増してきている。
以下は想像ですが。
それに合わせて、ピンからキリまでの質の施設が増えている。
もちろん充実した内容の施設はあるが、当然に高所得者向けの、つまり1割に満たない人々むけのもの。
問題は、必要に迫られてるがお金も限られている世帯。
ネットに集まるコメントは、傾向が偏るということがありながらも、療養病床のクレームは質・量ともに一定量 ある印象がありました。
もし需要と供給のバランスから安価で低質な療養病床が増加しているなら、法整備で質の向上を敷く必要があるが、それで利益が見込めず施設数が増えないと困る、という政権の意向があるのでしょうか。
. . . ?
介護療養型医療施設・療養病床は今、特に認知症の高齢者を受け入れてもらう施設として注目されているんですね。
いわゆる精神病院や知的障害者の介護施設と大別としては近くても、人口の高齢化でその需要が年々増してきている。
以下は想像ですが。
それに合わせて、ピンからキリまでの質の施設が増えている。
もちろん充実した内容の施設はあるが、当然に高所得者向けの、つまり1割に満たない人々むけのもの。
問題は、必要に迫られてるがお金も限られている世帯。
ネットに集まるコメントは、傾向が偏るということがありながらも、療養病床のクレームは質・量ともに一定量 ある印象がありました。
もし需要と供給のバランスから安価で低質な療養病床が増加しているなら、法整備で質の向上を敷く必要があるが、それで利益が見込めず施設数が増えないと困る、という政権の意向があるのでしょうか。
. . . ?
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
spɐɯou ʇsol 考える旅人 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
spɐɯou ʇsol 考える旅人 のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75504人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208298人
- 3位
- 音楽が無いと生きていけない
- 196031人
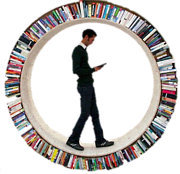

![[dir] 献血](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/19/76/3011976_247s.gif)





















