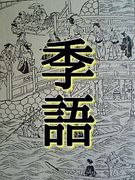画像1:「からくり御伽傀儡師」(画:文調)明和五年(1768)上演
画像2:「このころぐさ」部分(画:菱川師宣)江戸 元禄期
画像3:人倫訓蒙図彙(じんりんきんもうずい / 元禄期の職業図鑑)より
***************
「傀儡師」(かいらいし)は正月の季語。三河万歳のように正月の祝福芸として家々を回ったのだとか。
「傀儡師」が俳句の季語リストにあったので、びっくりしました。
「かいらいし」とルビをふらなければ、ふつうは読むことさえできないと思います。
傀儡師は胸に箱をかけ、その中から木偶人形を取り出して舞わせた大道芸人のことで、人形浄瑠璃や文楽のルーツとなったものです。
日本では、古くから神社などで神の仮りの姿として、主に木で作った人の形「ひとかた」、つまり人形を作って巫女がそれを舞わして、神霊を慰め、厄を払っていました。これが人形の始まりで、人形を舞わす人を「人形まわし」といいました。
奈良時代に中国から「散楽」(さんがく)という芸能が入ってきました。「散楽」は、曲伎(曲芸的演技・軽業)や幻戯(奇術・手品)、滑稽物真似など雑多な芸を、音楽に乗って演じる大衆芸能で、平安時代には転訛して 「さるがく」 と呼ばれる。これが、中世に花開く「能狂言」の源流です。
当時の大衆芸人の中に、漢字で「傀儡子」」と書く一群がいたそうです。難しい漢字だけど、「かいらいし」 または「く ぐつし」 と読む。
「かいらい」、「く ぐつ」 とも語源はわからない。歌に合わせて手遣いで人形を舞わせ、操るものでした。これが源流となって 「人形浄瑠璃」 ができました。三味線伴奏で語る義太夫節などの浄瑠璃に合わせて人形を遣う人形劇です。
ボクが傀儡師のことを知ったのは、忠臣蔵の関係で近松門左衛門の 「曽根崎心中」 や彼の弟子にあたる竹田出雲(二世)らによる 「仮名手本忠臣蔵」 を調べていたときでした。いずれも、はじめは人形浄瑠璃として上演されたものです。
調べればいろいろ出てくるものです。
吉良邸討入事件の 30年前、寛文十二年(1672)二月二日に、市谷の「浄瑠璃坂」を上ったところで、敵味方合わせて100人超の大規模な夜討事件がありました。この事件について江戸学の始祖、三田村鳶魚は、「吉良邸討入のお手本」 とまで書いていますが、それはさておいて、浄瑠璃坂は今でもあって、外堀通りからルーテル教会を左に見て上がる坂道。事件が起きるよりももっと昔に、坂の上には人形浄瑠璃を上演する小屋があったそうです。
そんなこともあって人形浄瑠璃の背景を探ったところ、当時も傀儡師がいたことがわかってきました。
ところで、明治に成立した俳句のなかに「傀儡師」を季語として用いたものがあるのか。先例を探すと、
傀儡師日暮れて帰る羅生門 藤野古白
という句がありました。作者の藤野古白(1871-1895)は正岡子規の従兄弟で、子規より四歳年上でした。
あ、そうだ。芥川竜之介(1892-1927)の短編集に『傀儡師』があった。ネットの青空文庫に収録されている。黒澤明監督の映画「羅生門」の脚本は竜之介の『薮の中』をもとに書かれ、同じく芥川竜之介の『羅生門』を加えて完成されたものでした。
芥川竜之介は、藤野古白よりも少し後の時代の人です。
竜之介が古白の句をヒントにしたのでなければ、明治に生きた彼らにとっては、「傀儡師」はとりたてて難しく思うようなものではなかったのかもしれません。
傀儡師は、西宮神社(えべっさん)に奉仕していた散所(現在の産所町)の民がその発祥であるとされています。
人形浄瑠璃は全国に伝わり繁栄したのですが、西宮の傀儡師は天保のころには数件にまで減り、明治の中ごろに最後の傀儡師、吉田小六が廃業してからは完全に消えてしまった、といいます。
画像2:「このころぐさ」部分(画:菱川師宣)江戸 元禄期
画像3:人倫訓蒙図彙(じんりんきんもうずい / 元禄期の職業図鑑)より
***************
「傀儡師」(かいらいし)は正月の季語。三河万歳のように正月の祝福芸として家々を回ったのだとか。
「傀儡師」が俳句の季語リストにあったので、びっくりしました。
「かいらいし」とルビをふらなければ、ふつうは読むことさえできないと思います。
傀儡師は胸に箱をかけ、その中から木偶人形を取り出して舞わせた大道芸人のことで、人形浄瑠璃や文楽のルーツとなったものです。
日本では、古くから神社などで神の仮りの姿として、主に木で作った人の形「ひとかた」、つまり人形を作って巫女がそれを舞わして、神霊を慰め、厄を払っていました。これが人形の始まりで、人形を舞わす人を「人形まわし」といいました。
奈良時代に中国から「散楽」(さんがく)という芸能が入ってきました。「散楽」は、曲伎(曲芸的演技・軽業)や幻戯(奇術・手品)、滑稽物真似など雑多な芸を、音楽に乗って演じる大衆芸能で、平安時代には転訛して 「さるがく」 と呼ばれる。これが、中世に花開く「能狂言」の源流です。
当時の大衆芸人の中に、漢字で「傀儡子」」と書く一群がいたそうです。難しい漢字だけど、「かいらいし」 または「く ぐつし」 と読む。
「かいらい」、「く ぐつ」 とも語源はわからない。歌に合わせて手遣いで人形を舞わせ、操るものでした。これが源流となって 「人形浄瑠璃」 ができました。三味線伴奏で語る義太夫節などの浄瑠璃に合わせて人形を遣う人形劇です。
ボクが傀儡師のことを知ったのは、忠臣蔵の関係で近松門左衛門の 「曽根崎心中」 や彼の弟子にあたる竹田出雲(二世)らによる 「仮名手本忠臣蔵」 を調べていたときでした。いずれも、はじめは人形浄瑠璃として上演されたものです。
調べればいろいろ出てくるものです。
吉良邸討入事件の 30年前、寛文十二年(1672)二月二日に、市谷の「浄瑠璃坂」を上ったところで、敵味方合わせて100人超の大規模な夜討事件がありました。この事件について江戸学の始祖、三田村鳶魚は、「吉良邸討入のお手本」 とまで書いていますが、それはさておいて、浄瑠璃坂は今でもあって、外堀通りからルーテル教会を左に見て上がる坂道。事件が起きるよりももっと昔に、坂の上には人形浄瑠璃を上演する小屋があったそうです。
そんなこともあって人形浄瑠璃の背景を探ったところ、当時も傀儡師がいたことがわかってきました。
ところで、明治に成立した俳句のなかに「傀儡師」を季語として用いたものがあるのか。先例を探すと、
傀儡師日暮れて帰る羅生門 藤野古白
という句がありました。作者の藤野古白(1871-1895)は正岡子規の従兄弟で、子規より四歳年上でした。
あ、そうだ。芥川竜之介(1892-1927)の短編集に『傀儡師』があった。ネットの青空文庫に収録されている。黒澤明監督の映画「羅生門」の脚本は竜之介の『薮の中』をもとに書かれ、同じく芥川竜之介の『羅生門』を加えて完成されたものでした。
芥川竜之介は、藤野古白よりも少し後の時代の人です。
竜之介が古白の句をヒントにしたのでなければ、明治に生きた彼らにとっては、「傀儡師」はとりたてて難しく思うようなものではなかったのかもしれません。
傀儡師は、西宮神社(えべっさん)に奉仕していた散所(現在の産所町)の民がその発祥であるとされています。
人形浄瑠璃は全国に伝わり繁栄したのですが、西宮の傀儡師は天保のころには数件にまで減り、明治の中ごろに最後の傀儡師、吉田小六が廃業してからは完全に消えてしまった、といいます。
|
|
|
|
|
|
|
|
季語 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
季語のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 十二国記
- 23165人
- 2位
- 楽天イーグルス
- 31952人
- 3位
- 北海道日本ハムファイターズ
- 28124人