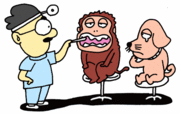形成外科医です。
外傷など原因とする軟部組織や骨組織の再建をやってます。
顔面骨の修正、唇口蓋裂の手術などの口腔内外の手術も行なってます。
歯牙の移動、歯槽骨への骨移植による再建なども含まれます。
私からすると、歯牙ってのは人体の骨組織の中で唯一骨膜がないというへんてこりんな組織です。皮膚や粘膜で覆われておらず、常に露出しています。普通の骨であれば、骨膜がなければ血液が循環せずにすぐに腐ります。露出すればあっという間に感染し、骨髄炎になり、四肢などであれば切断にいたることも多いです。至らなくても長期の治療が必要となります。
歯牙は細菌だらけの口腔内に露出したまま平気な顔をしています。
本来感染に弱いはずの骨組織でありながら、歯牙のエナメル質を浸食できるのはmutansなどのごく一部の細菌種だけです。
じゃあ歯牙への感染なんて起こらないのかと思いきや、う歯という形で多くの方が苦しまれております。
その反面、全く歯垢や歯石のケアしていないのに虫歯がない方も数多いです。
う歯ってのは、いったい何なんでしょう?
感染症というには、個人の感受性に差が大きいです。
生活習慣病というには、ケアをしているのに虫歯の多い人、ケアをしていないのに虫歯のない人の差が激しいです。
う歯の予防は結局はブラッシングという歯医者さんが多いのですが、どうにもブラッシングの精度と頻度と、予防効果が相関していないように感じます。
生後数年の口腔内の細菌叢のバランスによる、という説は一見説得力があります。生後数年以内にう蝕の原因菌が口腔内に常在しなければ、その後は他の菌によって細菌叢が形成され、原因菌が感染できなくなるという説です。
しかしながら、小児期にケアがないのに全くう歯がなく、う歯の感受性がないのかと思いきや、成人後に急にう歯が発生、進展するという方も少なくありません。
あるいは、何年も進展していなかったう歯が急激に進んだりする事もあります。
う歯症例に日常的に接している歯科医の先生方は、う歯に対してどのような疾患イメージを持っているのでしょうか?お聞かせ願えれば幸いです。
外傷など原因とする軟部組織や骨組織の再建をやってます。
顔面骨の修正、唇口蓋裂の手術などの口腔内外の手術も行なってます。
歯牙の移動、歯槽骨への骨移植による再建なども含まれます。
私からすると、歯牙ってのは人体の骨組織の中で唯一骨膜がないというへんてこりんな組織です。皮膚や粘膜で覆われておらず、常に露出しています。普通の骨であれば、骨膜がなければ血液が循環せずにすぐに腐ります。露出すればあっという間に感染し、骨髄炎になり、四肢などであれば切断にいたることも多いです。至らなくても長期の治療が必要となります。
歯牙は細菌だらけの口腔内に露出したまま平気な顔をしています。
本来感染に弱いはずの骨組織でありながら、歯牙のエナメル質を浸食できるのはmutansなどのごく一部の細菌種だけです。
じゃあ歯牙への感染なんて起こらないのかと思いきや、う歯という形で多くの方が苦しまれております。
その反面、全く歯垢や歯石のケアしていないのに虫歯がない方も数多いです。
う歯ってのは、いったい何なんでしょう?
感染症というには、個人の感受性に差が大きいです。
生活習慣病というには、ケアをしているのに虫歯の多い人、ケアをしていないのに虫歯のない人の差が激しいです。
う歯の予防は結局はブラッシングという歯医者さんが多いのですが、どうにもブラッシングの精度と頻度と、予防効果が相関していないように感じます。
生後数年の口腔内の細菌叢のバランスによる、という説は一見説得力があります。生後数年以内にう蝕の原因菌が口腔内に常在しなければ、その後は他の菌によって細菌叢が形成され、原因菌が感染できなくなるという説です。
しかしながら、小児期にケアがないのに全くう歯がなく、う歯の感受性がないのかと思いきや、成人後に急にう歯が発生、進展するという方も少なくありません。
あるいは、何年も進展していなかったう歯が急激に進んだりする事もあります。
う歯症例に日常的に接している歯科医の先生方は、う歯に対してどのような疾患イメージを持っているのでしょうか?お聞かせ願えれば幸いです。
|
|
|
|
コメント(41)
》 歯牙ってのは人体の骨組織の中で唯一骨膜がないというへんてこりんな組織です
上図の通り、歯は三層構造を為しており、骨とは歯根膜と称される骨膜様靭帯組織で結合しています。
口腔内に露出する部分はエナメル質渡渉する完結組織で、恐らく人体中でもっとも硬度の高い組織となりますが再生機能(新陳代謝)は有りません
》 う歯に対してどのような疾患イメージを持っているのでしょうか?お聞かせ願えれば幸いです。
齲蝕・歯周疾患は生活習慣病の典型例と捉えています
勿論、罹患傾向には個人差が大きいことはご指摘の通りであり、それ故各個人ごとに異なった最適治療を目指すのが歯科医の本領を発揮すべき部分と考えます
》 顔面骨の修正、唇口蓋裂の手術などの口腔内外の手術も行なってます。 歯牙の移動、歯槽骨への骨移植による再建なども含まれます
この辺り、開業歯科医では手も足も出ない部分が多く、外科・形成外科に任せるより他無いのですが・・
私は救急病院の傍で開業しているせいもあり、事故外傷による顎骨骨折等の外科処置後のフォローを依頼される機会を比較的多く持っています
その際、骨折修復後の状況を見ますと、上顎または下顎の再建にしか注意がいっておらず上下顎の咬合(上下顎の噛み合わせ)がまったく考慮されていないケースを頻繁に目にします。
増してや、咬頭傾斜度と上下歯牙の勘合などは全く意識の外にあるとしか思えないケースが殆どを占めており、結果として当初の創傷は治癒しているものの咬合不調和のため正常な咀嚼機能を初めとする口腔機能が発揮できないもの、顎関節症の併発等の二次疾患が生じていることもあります。
歯科と云う一診療科全対を把握するのは無理としても、咬合、歯列、咬頭傾斜などをキーワードにいま少し「噛み合わせ」と云うものに興味を抱いて頂ければ、事後のトラブルを減少させられるのではと考えております。
上図の通り、歯は三層構造を為しており、骨とは歯根膜と称される骨膜様靭帯組織で結合しています。
口腔内に露出する部分はエナメル質渡渉する完結組織で、恐らく人体中でもっとも硬度の高い組織となりますが再生機能(新陳代謝)は有りません
》 う歯に対してどのような疾患イメージを持っているのでしょうか?お聞かせ願えれば幸いです。
齲蝕・歯周疾患は生活習慣病の典型例と捉えています
勿論、罹患傾向には個人差が大きいことはご指摘の通りであり、それ故各個人ごとに異なった最適治療を目指すのが歯科医の本領を発揮すべき部分と考えます
》 顔面骨の修正、唇口蓋裂の手術などの口腔内外の手術も行なってます。 歯牙の移動、歯槽骨への骨移植による再建なども含まれます
この辺り、開業歯科医では手も足も出ない部分が多く、外科・形成外科に任せるより他無いのですが・・
私は救急病院の傍で開業しているせいもあり、事故外傷による顎骨骨折等の外科処置後のフォローを依頼される機会を比較的多く持っています
その際、骨折修復後の状況を見ますと、上顎または下顎の再建にしか注意がいっておらず上下顎の咬合(上下顎の噛み合わせ)がまったく考慮されていないケースを頻繁に目にします。
増してや、咬頭傾斜度と上下歯牙の勘合などは全く意識の外にあるとしか思えないケースが殆どを占めており、結果として当初の創傷は治癒しているものの咬合不調和のため正常な咀嚼機能を初めとする口腔機能が発揮できないもの、顎関節症の併発等の二次疾患が生じていることもあります。
歯科と云う一診療科全対を把握するのは無理としても、咬合、歯列、咬頭傾斜などをキーワードにいま少し「噛み合わせ」と云うものに興味を抱いて頂ければ、事後のトラブルを減少させられるのではと考えております。
先日顎骨骨折の方で包帯固定だけで済まされている方を見かけました。
残念ながらそのままで顎位固定されてしまっていたので咬合が一点のみでさせるという厳しい状態になってしまってました。
咬合が果たす役割は若干歯科業界では大きく語られ気味ですが、もう少し医科の方々に認知されてもいいジャンルであると考えます。
>骨膜と骨と歯
骨膜ですか・・。骨膜はとても有用ですね。たとえ骨の欠損が出来ても骨膜がそんざいしておれば骨の回復ができるのですから・・。
ただ・・歯と骨は同じ硬組織にありながらも、発生学的には由来となる間葉系もことなるので基本は別物とお考え頂いたほうが良いかと思います。
>う蝕
実は他の感染症とあまり大差はないのではないでしょうか。
糖尿病疾患に起きる手足の感染症なんかとメカニズムは近いのではないでしょうかね・・。もちろん起きる組織が異なるので対処法が違うのですが。
糖分が存在する培地に菌が繁殖する・・しごく普通のできごとのようにも思います。
培地を機械的清掃しても繁殖が止まらないのと同じで・・。
月並みな話ですが・・、防御因子(身体の抵抗力、機械的清掃、歯面の強化などなど)と攻撃因子(細菌活動性、糖の存在、基礎疾患などなど)の戦いではないかと・・。
やはりステロイド飲み始めたり、入院して環境が激変したり、部活はじめてスポーツドリンク飲みはじめたり、攻撃因子側を加速させるものはイロイロありますよ・・。
>口腔ケアなしでう蝕ない
これは生活習慣がしっかりしてて抵抗力も強ければありうる話です。ただ・・誰もが手に入れられるわけではない状態です・・。人間ドックうけなくても健康な方がいるのと同じではないでしょうか。
>治療
で・・いつも思うのですが。こういう発生を起きるう蝕に人工物を入れる治療が適切なのかという話なのですが。
そもそも細菌学的にのみ考えれば感染部分のみを除去してしまうのが適切なのでしょうが、実際の機能回復の面からみれば何かしらそこを補填しなくてはいけません。また、除去した部分を密閉しないと(細菌学的にかなり厳しいことはわかっていますが・・)再感染を起こしてしまいます。ですのでやむを得ず人工物を充填しているのです。
ですので自ら進んで人工物を入れたり、ましてや喜ぶなどということはありえないなと感じています・・。進んで入れる人の感覚はピアスのような発想なのでしょうか・・。
以上が私見ではありますが・・。
残念ながらそのままで顎位固定されてしまっていたので咬合が一点のみでさせるという厳しい状態になってしまってました。
咬合が果たす役割は若干歯科業界では大きく語られ気味ですが、もう少し医科の方々に認知されてもいいジャンルであると考えます。
>骨膜と骨と歯
骨膜ですか・・。骨膜はとても有用ですね。たとえ骨の欠損が出来ても骨膜がそんざいしておれば骨の回復ができるのですから・・。
ただ・・歯と骨は同じ硬組織にありながらも、発生学的には由来となる間葉系もことなるので基本は別物とお考え頂いたほうが良いかと思います。
>う蝕
実は他の感染症とあまり大差はないのではないでしょうか。
糖尿病疾患に起きる手足の感染症なんかとメカニズムは近いのではないでしょうかね・・。もちろん起きる組織が異なるので対処法が違うのですが。
糖分が存在する培地に菌が繁殖する・・しごく普通のできごとのようにも思います。
培地を機械的清掃しても繁殖が止まらないのと同じで・・。
月並みな話ですが・・、防御因子(身体の抵抗力、機械的清掃、歯面の強化などなど)と攻撃因子(細菌活動性、糖の存在、基礎疾患などなど)の戦いではないかと・・。
やはりステロイド飲み始めたり、入院して環境が激変したり、部活はじめてスポーツドリンク飲みはじめたり、攻撃因子側を加速させるものはイロイロありますよ・・。
>口腔ケアなしでう蝕ない
これは生活習慣がしっかりしてて抵抗力も強ければありうる話です。ただ・・誰もが手に入れられるわけではない状態です・・。人間ドックうけなくても健康な方がいるのと同じではないでしょうか。
>治療
で・・いつも思うのですが。こういう発生を起きるう蝕に人工物を入れる治療が適切なのかという話なのですが。
そもそも細菌学的にのみ考えれば感染部分のみを除去してしまうのが適切なのでしょうが、実際の機能回復の面からみれば何かしらそこを補填しなくてはいけません。また、除去した部分を密閉しないと(細菌学的にかなり厳しいことはわかっていますが・・)再感染を起こしてしまいます。ですのでやむを得ず人工物を充填しているのです。
ですので自ら進んで人工物を入れたり、ましてや喜ぶなどということはありえないなと感じています・・。進んで入れる人の感覚はピアスのような発想なのでしょうか・・。
以上が私見ではありますが・・。
咬合に関してもアドバイスありがとうございます。
私が咬合に影響のある手術をする場合は基本的に咬合状態で顎間固定を行ないますので悪影響はないですね。
ただし先天奇形の場合は歯列が大きく変わるので、信頼できる矯正歯科医と事前連携の上手術計画を行ないます。
咬合に影響を与える骨折で包帯固定しかしないというのは、単なる勉強不足としかいいようがないですね。頭頚部外相や疾患を専門とする医師はごく少数ですが、専門外なら専門外で適時に紹介を行なえばいいだけの事で。紹介ができない者は臨床をすべきでないですね。これは強く思います。
まあ、咬合に関してこのトピックの意図するところではないので、ここらへんで。
生活習慣病であるのなら、
1.原因となる生活習慣を特定できる事。
2.その生活習慣を行なうと罹患する事。
3.その生活習慣をやめると治癒する事。
の三つを同時に満たす必要がありますが、う歯の場合1.に関しては多くの原因が上げられていますが、2.と3.に関して、特に3.に関しては例外的、というか実例が大変少ないと思いますがいかがでしょうか?
飴をなめるから虫歯になった、じゃあやめたら虫歯にならなくなった、という話はあまり聞きません。
もちろん一度う蝕が発生すれば口腔内にmutans等の頑強な感染巣が形成され、他の易感染部位に絶えず菌体が供給されて新規う蝕リスクが上がる、というのはわかりますが、少なくとも肉眼レベルの感染歯質を全て削除され、象牙質などの易感染部位の露出を完全に被覆したあとでもやはり再発する患者さんが多い(というかほとんど?)と感じています。
いくらカリエスになっても雁としてケアを強化しない、全く生活習慣を変えないという方は、今の日本人ではむしろ少数派ではないでしょうか?
ある程度の進行したカリエスを経験した時点で新規カリエスの予防に強い動機を持つ方がほとんどで、ブラッシングはもとより各種化学的予防法(フッ素やキシリトール)、フロスの使用や定期的歯科受診PMTCなど予防に熱心な方は近年急激に増えましたし、今や少数派とはいえないでしょう。
ただそのような方でも少なくない割合で新規カリエスを経験する事になっています。
数多くの進行因子と抑止因子が複雑に絡み合って結果につながるとはおそらく医学的に一番正しい認識なのでしょうが、実際のところ臨床において実際に患者さんの利益となるには、ちょっと曖昧すぎるイメージのように感じています。
一旦予防動機の上がった方でも、数年経てば起きる再発にあきらめてしまい、定期受診はおろか既に発生したカリエスの治療にすら来なくなってしまう方も多いです。
結局のところ「何が悪かったのか、これからどうすればいいのか」がはっきりしないまま再発を経験すると、せっかく上がった予防、治療意識が下がってしまい、やがて自然経過に任せてしまうというとても良くない流れに陥ってしまいます。
通常の外科的感染症であれば感染巣の除去と物理的に洗浄によってほぼ後遺症なく治癒します。骨髄炎に至れば治療期間は遷延しますが、適切な投薬と栄養でまず治ります。感染巣の除去が多少不十分でも、十分小さくなれば免疫系の働きで顕微鏡レベルで感染巣は排除されます。
それに対してう歯は感染巣の除去後に除去部がほとんど再生してないため、仰るように補綴が必要となり、それ自体が次回感染のリスクとなるというジレンマがあります。
そこら辺も患者さんが適切な治療動機を保ちにくい点だと思うのですよ。
理想的な「う歯の発生しない体質と生活スタイル」を設定し、それと患者の実態の違いを探し出し、その中で重要度の高い者から生活指導していく、というのがあるべきう歯予防の姿だと思うのですが、実際のところそうした生活スタイルを思い描きにくい、あるいはそうしたスタイルに近い生活をしており、特段の基礎疾患もないのに次々と再発する例などがあって。
何事にも例外があるとは言え、一念発起して生活スタイルを変えてう歯のない生活を目指した方が、結局は再発して動機を失う例が少なくないと感じています。
はっきりとしたリスク因子のない方でもそうなので、何か今まで余り語られる事のないリスク因子があるのではないかという風にも考えておる訳です。
唾液の量もその一つなのかと思うのですが、私自身唾液の量はかなり多い方なのですが、う蝕が進行する傾向にあります。もちろん世に知られている程度のケアはしております。
そういえば、こういう人は進行しやすいな、こういう人は進行しないな、の様な漠然とした者でもいいので臨床家の先生方の印象を伺えたらいいなあと思いましてトピを立てました。
「結局何しても時間が経てば虫歯になっちゃうじゃん」というあきらめに対して、少しでも福音があればと思うのですよ。
私が咬合に影響のある手術をする場合は基本的に咬合状態で顎間固定を行ないますので悪影響はないですね。
ただし先天奇形の場合は歯列が大きく変わるので、信頼できる矯正歯科医と事前連携の上手術計画を行ないます。
咬合に影響を与える骨折で包帯固定しかしないというのは、単なる勉強不足としかいいようがないですね。頭頚部外相や疾患を専門とする医師はごく少数ですが、専門外なら専門外で適時に紹介を行なえばいいだけの事で。紹介ができない者は臨床をすべきでないですね。これは強く思います。
まあ、咬合に関してこのトピックの意図するところではないので、ここらへんで。
生活習慣病であるのなら、
1.原因となる生活習慣を特定できる事。
2.その生活習慣を行なうと罹患する事。
3.その生活習慣をやめると治癒する事。
の三つを同時に満たす必要がありますが、う歯の場合1.に関しては多くの原因が上げられていますが、2.と3.に関して、特に3.に関しては例外的、というか実例が大変少ないと思いますがいかがでしょうか?
飴をなめるから虫歯になった、じゃあやめたら虫歯にならなくなった、という話はあまり聞きません。
もちろん一度う蝕が発生すれば口腔内にmutans等の頑強な感染巣が形成され、他の易感染部位に絶えず菌体が供給されて新規う蝕リスクが上がる、というのはわかりますが、少なくとも肉眼レベルの感染歯質を全て削除され、象牙質などの易感染部位の露出を完全に被覆したあとでもやはり再発する患者さんが多い(というかほとんど?)と感じています。
いくらカリエスになっても雁としてケアを強化しない、全く生活習慣を変えないという方は、今の日本人ではむしろ少数派ではないでしょうか?
ある程度の進行したカリエスを経験した時点で新規カリエスの予防に強い動機を持つ方がほとんどで、ブラッシングはもとより各種化学的予防法(フッ素やキシリトール)、フロスの使用や定期的歯科受診PMTCなど予防に熱心な方は近年急激に増えましたし、今や少数派とはいえないでしょう。
ただそのような方でも少なくない割合で新規カリエスを経験する事になっています。
数多くの進行因子と抑止因子が複雑に絡み合って結果につながるとはおそらく医学的に一番正しい認識なのでしょうが、実際のところ臨床において実際に患者さんの利益となるには、ちょっと曖昧すぎるイメージのように感じています。
一旦予防動機の上がった方でも、数年経てば起きる再発にあきらめてしまい、定期受診はおろか既に発生したカリエスの治療にすら来なくなってしまう方も多いです。
結局のところ「何が悪かったのか、これからどうすればいいのか」がはっきりしないまま再発を経験すると、せっかく上がった予防、治療意識が下がってしまい、やがて自然経過に任せてしまうというとても良くない流れに陥ってしまいます。
通常の外科的感染症であれば感染巣の除去と物理的に洗浄によってほぼ後遺症なく治癒します。骨髄炎に至れば治療期間は遷延しますが、適切な投薬と栄養でまず治ります。感染巣の除去が多少不十分でも、十分小さくなれば免疫系の働きで顕微鏡レベルで感染巣は排除されます。
それに対してう歯は感染巣の除去後に除去部がほとんど再生してないため、仰るように補綴が必要となり、それ自体が次回感染のリスクとなるというジレンマがあります。
そこら辺も患者さんが適切な治療動機を保ちにくい点だと思うのですよ。
理想的な「う歯の発生しない体質と生活スタイル」を設定し、それと患者の実態の違いを探し出し、その中で重要度の高い者から生活指導していく、というのがあるべきう歯予防の姿だと思うのですが、実際のところそうした生活スタイルを思い描きにくい、あるいはそうしたスタイルに近い生活をしており、特段の基礎疾患もないのに次々と再発する例などがあって。
何事にも例外があるとは言え、一念発起して生活スタイルを変えてう歯のない生活を目指した方が、結局は再発して動機を失う例が少なくないと感じています。
はっきりとしたリスク因子のない方でもそうなので、何か今まで余り語られる事のないリスク因子があるのではないかという風にも考えておる訳です。
唾液の量もその一つなのかと思うのですが、私自身唾液の量はかなり多い方なのですが、う蝕が進行する傾向にあります。もちろん世に知られている程度のケアはしております。
そういえば、こういう人は進行しやすいな、こういう人は進行しないな、の様な漠然とした者でもいいので臨床家の先生方の印象を伺えたらいいなあと思いましてトピを立てました。
「結局何しても時間が経てば虫歯になっちゃうじゃん」というあきらめに対して、少しでも福音があればと思うのですよ。
》1.原因となる生活習慣を特定できる事。
これは口腔ケア(食生活・歯磨き習慣等)が挙げられます。
》2.その生活習慣を行なうと罹患する事。
歯牙疾患を含む口腔疾患は、その口腔ケアを適切に行なうことで激減するのは日常臨床でも日々経験することであり、不足すると罹患率は高くなります。
》3.その生活習慣をやめると治癒する事。
口腔ケアを適切に行なわない、悪影響を及ぼすと言われている食生活(習慣・嗜好)を改善しないことが日常の生活習慣となり、口腔疾患の原因となっていると考えられる症例が数多存在します。
ですから「止める」のではなく良好な日常生活習慣を「する」事が口腔疾患罹患傾向の改善に寄与します。
》飴をなめるから虫歯になった、じゃあやめたら虫歯にならなくなった、という話はあまり聞きません
一診療所のデータでは母数不足で傾向を語るまでにはいきませんが・・・・
物資不足の戦中・戦後(昭和初期から25年くらい)に成長期を過ごした世代には齲蝕が少ないというデータはあります。
但し、この世代は歯牙清掃目的の歯磨を行なうという意識が極めて希薄ですので重度の歯周疾患を起こしている方は多いようです。
また、高度成長期を所謂「かぎっ子」として過ごした世代に齲蝕が多い事は定説となっています。
》各種化学的予防法(フッ素やキシリトール)、フロスの使用や定期的歯科受診PMTCなど予防に熱心な方は近年急激に増えましたし、今や少数派とはいえないでしょう
予防意識は確かに高くなっていますが、効果有る予防知識を備えているかどうかに付いては極めて疑問。
挙げておられる予防法を指導し、実践している方も多いのですが正しく実践しているか方の比率はどれほどのものなのでしょうね。
薬剤・器具に頼って一時的な改善を見るもののなし崩しに元の習慣に戻り、長期的に持続させる方は多く無いような気もします。
》今や少数派とはいえないでしょう
薬剤・器具は正しく使うのであれば確かに使った方が良いのですが、こういった啓蒙活動は来患数の減少という歯科経営経済上の要素も大きく影響しています。
これは口腔ケア(食生活・歯磨き習慣等)が挙げられます。
》2.その生活習慣を行なうと罹患する事。
歯牙疾患を含む口腔疾患は、その口腔ケアを適切に行なうことで激減するのは日常臨床でも日々経験することであり、不足すると罹患率は高くなります。
》3.その生活習慣をやめると治癒する事。
口腔ケアを適切に行なわない、悪影響を及ぼすと言われている食生活(習慣・嗜好)を改善しないことが日常の生活習慣となり、口腔疾患の原因となっていると考えられる症例が数多存在します。
ですから「止める」のではなく良好な日常生活習慣を「する」事が口腔疾患罹患傾向の改善に寄与します。
》飴をなめるから虫歯になった、じゃあやめたら虫歯にならなくなった、という話はあまり聞きません
一診療所のデータでは母数不足で傾向を語るまでにはいきませんが・・・・
物資不足の戦中・戦後(昭和初期から25年くらい)に成長期を過ごした世代には齲蝕が少ないというデータはあります。
但し、この世代は歯牙清掃目的の歯磨を行なうという意識が極めて希薄ですので重度の歯周疾患を起こしている方は多いようです。
また、高度成長期を所謂「かぎっ子」として過ごした世代に齲蝕が多い事は定説となっています。
》各種化学的予防法(フッ素やキシリトール)、フロスの使用や定期的歯科受診PMTCなど予防に熱心な方は近年急激に増えましたし、今や少数派とはいえないでしょう
予防意識は確かに高くなっていますが、効果有る予防知識を備えているかどうかに付いては極めて疑問。
挙げておられる予防法を指導し、実践している方も多いのですが正しく実践しているか方の比率はどれほどのものなのでしょうね。
薬剤・器具に頼って一時的な改善を見るもののなし崩しに元の習慣に戻り、長期的に持続させる方は多く無いような気もします。
》今や少数派とはいえないでしょう
薬剤・器具は正しく使うのであれば確かに使った方が良いのですが、こういった啓蒙活動は来患数の減少という歯科経営経済上の要素も大きく影響しています。
エナメル質(外肺葉)⇔ 上皮組織
象牙質(中胚葉) ⇔ 骨組織
歯根膜(外肺葉性間葉 と記憶してます・・・) ⇔ 骨膜
歯髄(中胚葉) ⇔ 神経・血管組織
のイメージです。
上皮なら傷を負っても再生しますが、エナメル質は高度に石灰化しており、有機質は1%程度しか残存していませんし、残っている有機質は仕事をおえて残存したものですので、再生能力は残されていないと思います。
象牙質は歯髄が生きていればある程度の再生能力はあります。
これらのサイトにわかりやすく説明されていますね。
http://milk.asm.ne.jp/jimu/ca/12_1.htm
http://www.ne.jp/asahi/fumi/dental/perio2/anatomy/anatomy2.html
http://jp.encarta.msn.com/text_761561931___2/content.html
う蝕は口腔内の常在菌が糖類などを取り込み、代謝産物の酸を排出することで生じます。
通常、食事をすると口腔内のpHは4〜5程度まで下がります。
口腔内のpHがエナメル質の脱灰が生じる臨界PH(5.5)より下がることで、歯質中のCaやPなどが溶出し脱灰現象が生じます。
食事により下がったpHは唾液の緩衝能により徐々に戻り、溶出したCaやPなどのミネラルが歯に戻ってきます(再石灰化)。
つまり、歯は食事をするたびに溶け、その後治っていると考えられます。
唾液の量が少ない方や緩衝能が少ない方はう蝕になりやすい考えられます。
また、口腔内のpHが中性に戻る前に間食をしたりすると、pHが低下し脱灰が再度始まってしまいます。
これを繰り返し、穴が開いてしまったのがう蝕です。
しっかりと歯磨きをしているのにう蝕が多い方は間食(ジュースや缶コーヒなど糖分を含む飲み物を含む)している方が多いように感じます。
また、修復物があると歯質と修復物の間にすき間ができるので細菌の温床となり、2次う蝕になりやすいと思います。
患者さんの中には修復物を入れるとむし歯にならないと思っている方もまだまだおられますが、かえって逆なんですよね〜。
乱筆乱文で申し訳ありません。
象牙質(中胚葉) ⇔ 骨組織
歯根膜(外肺葉性間葉 と記憶してます・・・) ⇔ 骨膜
歯髄(中胚葉) ⇔ 神経・血管組織
のイメージです。
上皮なら傷を負っても再生しますが、エナメル質は高度に石灰化しており、有機質は1%程度しか残存していませんし、残っている有機質は仕事をおえて残存したものですので、再生能力は残されていないと思います。
象牙質は歯髄が生きていればある程度の再生能力はあります。
これらのサイトにわかりやすく説明されていますね。
http://milk.asm.ne.jp/jimu/ca/12_1.htm
http://www.ne.jp/asahi/fumi/dental/perio2/anatomy/anatomy2.html
http://jp.encarta.msn.com/text_761561931___2/content.html
う蝕は口腔内の常在菌が糖類などを取り込み、代謝産物の酸を排出することで生じます。
通常、食事をすると口腔内のpHは4〜5程度まで下がります。
口腔内のpHがエナメル質の脱灰が生じる臨界PH(5.5)より下がることで、歯質中のCaやPなどが溶出し脱灰現象が生じます。
食事により下がったpHは唾液の緩衝能により徐々に戻り、溶出したCaやPなどのミネラルが歯に戻ってきます(再石灰化)。
つまり、歯は食事をするたびに溶け、その後治っていると考えられます。
唾液の量が少ない方や緩衝能が少ない方はう蝕になりやすい考えられます。
また、口腔内のpHが中性に戻る前に間食をしたりすると、pHが低下し脱灰が再度始まってしまいます。
これを繰り返し、穴が開いてしまったのがう蝕です。
しっかりと歯磨きをしているのにう蝕が多い方は間食(ジュースや缶コーヒなど糖分を含む飲み物を含む)している方が多いように感じます。
また、修復物があると歯質と修復物の間にすき間ができるので細菌の温床となり、2次う蝕になりやすいと思います。
患者さんの中には修復物を入れるとむし歯にならないと思っている方もまだまだおられますが、かえって逆なんですよね〜。
乱筆乱文で申し訳ありません。
連続で失礼します。
なるほど御自分の体験を通じてそう思われたわけですね。
職業的なことからかなりセルフコントロールは難しいのではないでしょうか。
これはご本人の責任という意味ではなく、職務上かなり不規則な生活習慣のため困難であるという意味です。
自分も形成外科の先生とお仕事を一緒にさせていただいたことがありますが。
そのご苦労には頭が下がる気持ちです。
個人的にはある程度管理下にある天然歯(まったくいじっていない歯)は疾患にほぼ侵されずに済みますし、残念ながら人工物装着または充填歯は管理下においても非常に疾患に侵されやすいイメージですね・・・。答えになっていないですが・・。
予防はだいぶん啓蒙していますがまだまだ未熟です。甘い・・甘いですね認識が皆様の。
自分の体験談ではいろいろ改善の結果、歯科医師になる前の10台後半の口腔内は無茶苦茶(はずかしい・・)ですが、20台は改心し(?)口腔内はほとんど手をいれず、30台もそのまま推移してます。
なるほど御自分の体験を通じてそう思われたわけですね。
職業的なことからかなりセルフコントロールは難しいのではないでしょうか。
これはご本人の責任という意味ではなく、職務上かなり不規則な生活習慣のため困難であるという意味です。
自分も形成外科の先生とお仕事を一緒にさせていただいたことがありますが。
そのご苦労には頭が下がる気持ちです。
個人的にはある程度管理下にある天然歯(まったくいじっていない歯)は疾患にほぼ侵されずに済みますし、残念ながら人工物装着または充填歯は管理下においても非常に疾患に侵されやすいイメージですね・・・。答えになっていないですが・・。
予防はだいぶん啓蒙していますがまだまだ未熟です。甘い・・甘いですね認識が皆様の。
自分の体験談ではいろいろ改善の結果、歯科医師になる前の10台後半の口腔内は無茶苦茶(はずかしい・・)ですが、20台は改心し(?)口腔内はほとんど手をいれず、30台もそのまま推移してます。
えとですね、上記の生活習慣病の条件は、定義そのものです。別に僕が思いついたもんじゃありません。
脳卒中といういい方はもはや医療関係者はまずしないのですが、それも含めて高血圧や糖尿病は、生活習慣病の代表のようにいわれますが、実のところ生活習慣と関係ない部分もある訳です。遺伝とか、その他の疾患の二次的なものとか。
う歯のようにまさに患者さん本人の感受性(遺伝的背景など)に依存する部分が大きい。だから、患者さんによって生活習慣改善による効果はばらつきがあり、治療効果の評価方法に問題が出てきた訳です。
そこで出てきたのが「メタボ」なんですよ。
血管疾患(脳梗塞や脳出血、冠疾患、動脈硬化)や糖尿病、高脂血症の中で純粋に生活習慣によって起こる部分をまとめて抽出したところ、要するに「デブ」だったと、そういうわけです。(ホントはデブとはちょっと違うんですけどね)
要するに今まで生活習慣病といわれたものの中で、本人の努力によって改善する部分は肥満だから、それだけを集中してパックアップしようというのがメタボ対数な訳です。
で、う歯に関しても、本人の努力による改善可能な部分で、大きい要素は何かなと思う訳です。
んー、虫歯になるのは結局ブラッシングが悪いからと言う事でしょうか?
では、虫歯の再発を繰り返していた方が、熱心な指導の末、新規う蝕が発生しなくなった、という経験はありますでしょうか?
脳卒中といういい方はもはや医療関係者はまずしないのですが、それも含めて高血圧や糖尿病は、生活習慣病の代表のようにいわれますが、実のところ生活習慣と関係ない部分もある訳です。遺伝とか、その他の疾患の二次的なものとか。
う歯のようにまさに患者さん本人の感受性(遺伝的背景など)に依存する部分が大きい。だから、患者さんによって生活習慣改善による効果はばらつきがあり、治療効果の評価方法に問題が出てきた訳です。
そこで出てきたのが「メタボ」なんですよ。
血管疾患(脳梗塞や脳出血、冠疾患、動脈硬化)や糖尿病、高脂血症の中で純粋に生活習慣によって起こる部分をまとめて抽出したところ、要するに「デブ」だったと、そういうわけです。(ホントはデブとはちょっと違うんですけどね)
要するに今まで生活習慣病といわれたものの中で、本人の努力によって改善する部分は肥満だから、それだけを集中してパックアップしようというのがメタボ対数な訳です。
で、う歯に関しても、本人の努力による改善可能な部分で、大きい要素は何かなと思う訳です。
んー、虫歯になるのは結局ブラッシングが悪いからと言う事でしょうか?
では、虫歯の再発を繰り返していた方が、熱心な指導の末、新規う蝕が発生しなくなった、という経験はありますでしょうか?
食生活とブラッシング、要するに生活習慣ですが、やはり大きな要因になってるわけです。例えば、受験生、特に不規則な食物摂取、例えば炭酸飲料やスナック菓子を四六時中食べている学生なんかは、ブラッシングがさほど悪くなくても歯はボロボロです。ブラッシングが不良な場合だと、口腔内は本当に酷いもんです。思えば、自分自身もう蝕多発時期はその頃だった気がします。
また、しつけのされていない乳幼児。要するに母親がだらしない場合も同様に酷い口腔内をしています。ただこの場合、母親の意識付けで明らかにう蝕の出来具合は改善されてきます。おやつの与え方とブラッシング指導、それとよく咬める食事指導です。
乳幼児の場合は母親の意識次第で比較的改善しやすいですが、学生の場合や、意識が低い患者だと、どれだけ言っても効果の低いことが多いですね・。
また、しつけのされていない乳幼児。要するに母親がだらしない場合も同様に酷い口腔内をしています。ただこの場合、母親の意識付けで明らかにう蝕の出来具合は改善されてきます。おやつの与え方とブラッシング指導、それとよく咬める食事指導です。
乳幼児の場合は母親の意識次第で比較的改善しやすいですが、学生の場合や、意識が低い患者だと、どれだけ言っても効果の低いことが多いですね・。
はい。
そういうイメージでよろしいかと。
例えば飴ばかり舐めている方は歯頚部に小さい虫歯が見られます。全体的に。
いくら、定期検診受けても歯ブラシをしっかりしていてもなってしまいます。
また、三食と間食。きっちり食生活が出来ている子供は極端な話、歯磨きを一所懸命していなくても虫歯は少ないです。
但し、子供の時に感受性が高くなっている方は大人になって改善しても、やっぱりなりやすいようです。
それは口腔内の環境、唾液、細菌、歯、等の質や緩衝能力が既に衰えているかのような状況でしょうか?
口腔内のpHの関係は非常に大きいと思います。プラークコントロール(ブラッシングテクニック)よりもね。
そういうイメージでよろしいかと。
例えば飴ばかり舐めている方は歯頚部に小さい虫歯が見られます。全体的に。
いくら、定期検診受けても歯ブラシをしっかりしていてもなってしまいます。
また、三食と間食。きっちり食生活が出来ている子供は極端な話、歯磨きを一所懸命していなくても虫歯は少ないです。
但し、子供の時に感受性が高くなっている方は大人になって改善しても、やっぱりなりやすいようです。
それは口腔内の環境、唾液、細菌、歯、等の質や緩衝能力が既に衰えているかのような状況でしょうか?
口腔内のpHの関係は非常に大きいと思います。プラークコントロール(ブラッシングテクニック)よりもね。
すでに既出の意見なんですが、そのことについてあまり深く
認識されていないようなので、意見を出したいと思います。
お医者さんは通常体内を治療するのが一般的です。
(一般的という言い方はちょっと変なんですが)
体外のケアが不足して、たとえば耳垢がたまりすぎて
耳が聞こえなくなった、頭を洗わずにしらみがわいた、、など
そういったことにじゃあくすりで治しましょう、、とは
普通できないですよね。(まあしらみは薬で死ぬかもしれませんけど)
こういった体の外に対するケアということをするのが
介護の仕事、ケアで、体内を治療するのがキュアだと
大まかな区別をするとしましょう。(細かくは突っ込まないで下さいね。)
そして齲蝕の発生する歯というものはその体内と体外を貫いている
という臓器で、通常の体内での免疫力が及ばない口腔内で
発生しているという点が通常の疾患との決定的な違いだと思います。
その点を考えずに疾患として捉えて、治療というものを
考えると、医者からするととても不思議な
点なんだと思います。
口腔内にも確かに唾液などの免疫は存在しますが、
決して無菌状態ではないし、ありとあらゆる食べ物が入ってくる
(しかも毎日)インキュベーターのような環境です。
体内に直接ジュースを入れたらえらいことになります。
細かな脱灰などの話も出てきていますが、それはあくまで体外の話です。
口腔内は外界とつながっている体外です。
脱灰するのを再石灰化させているのは体外に出た唾液です。
毎日脱灰再石灰化を繰り返しています。
この視点のほうももう少し考えていただければと。
認識されていないようなので、意見を出したいと思います。
お医者さんは通常体内を治療するのが一般的です。
(一般的という言い方はちょっと変なんですが)
体外のケアが不足して、たとえば耳垢がたまりすぎて
耳が聞こえなくなった、頭を洗わずにしらみがわいた、、など
そういったことにじゃあくすりで治しましょう、、とは
普通できないですよね。(まあしらみは薬で死ぬかもしれませんけど)
こういった体の外に対するケアということをするのが
介護の仕事、ケアで、体内を治療するのがキュアだと
大まかな区別をするとしましょう。(細かくは突っ込まないで下さいね。)
そして齲蝕の発生する歯というものはその体内と体外を貫いている
という臓器で、通常の体内での免疫力が及ばない口腔内で
発生しているという点が通常の疾患との決定的な違いだと思います。
その点を考えずに疾患として捉えて、治療というものを
考えると、医者からするととても不思議な
点なんだと思います。
口腔内にも確かに唾液などの免疫は存在しますが、
決して無菌状態ではないし、ありとあらゆる食べ物が入ってくる
(しかも毎日)インキュベーターのような環境です。
体内に直接ジュースを入れたらえらいことになります。
細かな脱灰などの話も出てきていますが、それはあくまで体外の話です。
口腔内は外界とつながっている体外です。
脱灰するのを再石灰化させているのは体外に出た唾液です。
毎日脱灰再石灰化を繰り返しています。
この視点のほうももう少し考えていただければと。
私は外科医なんでどちらかというと身体の外側を扱っております。
特に形成外科医は体表疾患を扱うことが大半です。
このトピやこれまでお会いした歯科医の方々(一部の歯科医の先生はご存じかと思いますが、形成外科はおそらく医者の中でもっとも歯科医の先生に接する機会の多い科です。また個人的に歯科麻酔の先生方と仕事をしてきたという経緯もあります)に感じた印象としては、歯科及び口腔医学の特殊性を十分理解して臨床に当たられています。
しかし特殊性を意識するあまり口腔が人体の一部であると言うことを忘れているような印象です。
例えば、口腔が消化管の一部であるとか、歯牙も食物を破砕して食物吸収に資しているという点で消化器も一部である、という意識が薄いように感じております。
「人体一般ではこうである、しかし口腔ではこうである」
という議論じゃなくて、いきなり
「口腔は特殊だから〜である」という話ばかりで、人体一般のどういう点と比べて特殊なのかという認識が不足している印象です。
例えば>>27で仰る「体内と体外を貫いてる臓器だから〜通常の疾患との決定的な違い」とのご認識ですが、全身の上皮由来の組織の大半が「体内と体外を貫いている臓器」です。
もっとも巨大な臓器と言われる皮膚組織を筆頭に、その他に消化管粘膜(わかりずらいかもしれませんが、食道や胃、小腸、大腸などの消化管の内腔は「体外」であり、その表面を覆う粘膜は体外と体内の境目になります)などであり、これらは通常の医療の例外ではなくむしろ主な治療対象です。
免疫の点からしても、むしろ強力な免疫反応の起こりやすいことは、各種アレルギーやアトピーなどによる難治性の皮膚炎が数多く存在することからもわかると思います。
歯牙は別として口腔内環境を形成する口腔粘膜、唾液腺、咽頭などはむしろ私の専門分野ですが、口腔内を消化管の一部と考えた場合、特段に特殊な構造があるわけではありません。粘膜があり、腔内を循環する分泌物(唾液)がある。
胃液の洗浄を受けないため胃などにはほとんど存在しない最近が大量に存在しているのが特徴ですが、これは口と同じように消化管の反対の端である肛門とよく似ている特徴であることは興味深いことです。
食物が入るところと出るところである点で口腔と肛門は全く逆なわけですが、実はよく似ているところがたくさんあります。
非常に多くの最近が常在していること、そして結構の豊富な静脈相が粘膜下(口腔で言うと舌のすぐ下)が存在し、消化器系を経由せずに直接薬の投与が可能な点です。口で言うと舌下投与、肛門で言うといわゆる座薬です。
もちろん肛門には歯牙がありませんし、分泌液も少ないですからその点は大きく違いますが。
口腔内、歯牙、そして歯周組織は確かに人体の他の部分と違う特徴を持っています。しかしだからといって口腔とはの全てが他の部分と違っているわけではありません。
人体のトラブルの多くは異物と人体の接する、まさに体内外の境目である「上皮」において発生するわけでして、(例えば胃潰瘍や大腸癌などの消化器ガンの大半)、その点は、う歯を含めた口腔内トラブルと同じです。
悪性腫瘍、感染症の大半は上皮近傍で発生します。
どこまでが人体一般と同様で、どこからが口腔内独特のことなのか、そこら辺を意識して頂けると既存の治療技術の応用拡大や、新しい治療法の導入が効率よく進むのではないかと思います。
同様の考えは、人体と他の生物を比較する際にも有用です。
最近では遺伝子を比較するのが盛んですが、
「人間のどういう点が他の生物と似ているのか、どういう点が人間だけの特徴なのか?」という視点で、人間や他の生物の特徴を整理して、人体の仕組みのイメージをより精度の高いものにしてくわけです。
私が「へんてこりんと」感じるう歯の疾患イメージも、他の生活習慣病や感染症などとどこが違うのか、どこが同じなのかを両方把握することによって初めて「へんてこりん」さを解消出来るのではないかと思うわけです。
特に形成外科医は体表疾患を扱うことが大半です。
このトピやこれまでお会いした歯科医の方々(一部の歯科医の先生はご存じかと思いますが、形成外科はおそらく医者の中でもっとも歯科医の先生に接する機会の多い科です。また個人的に歯科麻酔の先生方と仕事をしてきたという経緯もあります)に感じた印象としては、歯科及び口腔医学の特殊性を十分理解して臨床に当たられています。
しかし特殊性を意識するあまり口腔が人体の一部であると言うことを忘れているような印象です。
例えば、口腔が消化管の一部であるとか、歯牙も食物を破砕して食物吸収に資しているという点で消化器も一部である、という意識が薄いように感じております。
「人体一般ではこうである、しかし口腔ではこうである」
という議論じゃなくて、いきなり
「口腔は特殊だから〜である」という話ばかりで、人体一般のどういう点と比べて特殊なのかという認識が不足している印象です。
例えば>>27で仰る「体内と体外を貫いてる臓器だから〜通常の疾患との決定的な違い」とのご認識ですが、全身の上皮由来の組織の大半が「体内と体外を貫いている臓器」です。
もっとも巨大な臓器と言われる皮膚組織を筆頭に、その他に消化管粘膜(わかりずらいかもしれませんが、食道や胃、小腸、大腸などの消化管の内腔は「体外」であり、その表面を覆う粘膜は体外と体内の境目になります)などであり、これらは通常の医療の例外ではなくむしろ主な治療対象です。
免疫の点からしても、むしろ強力な免疫反応の起こりやすいことは、各種アレルギーやアトピーなどによる難治性の皮膚炎が数多く存在することからもわかると思います。
歯牙は別として口腔内環境を形成する口腔粘膜、唾液腺、咽頭などはむしろ私の専門分野ですが、口腔内を消化管の一部と考えた場合、特段に特殊な構造があるわけではありません。粘膜があり、腔内を循環する分泌物(唾液)がある。
胃液の洗浄を受けないため胃などにはほとんど存在しない最近が大量に存在しているのが特徴ですが、これは口と同じように消化管の反対の端である肛門とよく似ている特徴であることは興味深いことです。
食物が入るところと出るところである点で口腔と肛門は全く逆なわけですが、実はよく似ているところがたくさんあります。
非常に多くの最近が常在していること、そして結構の豊富な静脈相が粘膜下(口腔で言うと舌のすぐ下)が存在し、消化器系を経由せずに直接薬の投与が可能な点です。口で言うと舌下投与、肛門で言うといわゆる座薬です。
もちろん肛門には歯牙がありませんし、分泌液も少ないですからその点は大きく違いますが。
口腔内、歯牙、そして歯周組織は確かに人体の他の部分と違う特徴を持っています。しかしだからといって口腔とはの全てが他の部分と違っているわけではありません。
人体のトラブルの多くは異物と人体の接する、まさに体内外の境目である「上皮」において発生するわけでして、(例えば胃潰瘍や大腸癌などの消化器ガンの大半)、その点は、う歯を含めた口腔内トラブルと同じです。
悪性腫瘍、感染症の大半は上皮近傍で発生します。
どこまでが人体一般と同様で、どこからが口腔内独特のことなのか、そこら辺を意識して頂けると既存の治療技術の応用拡大や、新しい治療法の導入が効率よく進むのではないかと思います。
同様の考えは、人体と他の生物を比較する際にも有用です。
最近では遺伝子を比較するのが盛んですが、
「人間のどういう点が他の生物と似ているのか、どういう点が人間だけの特徴なのか?」という視点で、人間や他の生物の特徴を整理して、人体の仕組みのイメージをより精度の高いものにしてくわけです。
私が「へんてこりんと」感じるう歯の疾患イメージも、他の生活習慣病や感染症などとどこが違うのか、どこが同じなのかを両方把握することによって初めて「へんてこりん」さを解消出来るのではないかと思うわけです。
うーん・・・。立派な臨床家の方とおみうけしていますが・・。
確かに理屈としてはおっしゃられていることは十分解りますが。
もしよければ臨床例をあげて「こういう場合どうとらえますか?意見を聞かせてください」のほうが早いのではないのでしょうか・・。
何かしら歯科に対してメッセージを発せられたいのでしょうが、いまひとつどこにフォーカスをおけばよいのかわかりかねます。
これでは学者のようです・・・。
確かに理論は大事ですが理論と実戦の配分がとても大事なのは、自分などが説明せずとも十分ご存知のはずです。
できれば臨床症例でこういう対応はおかしいと具体例をお示しいただいたほうが早いのでは・・。
ま・・個人情報保護の点で難しいのですが。
確かに理屈としてはおっしゃられていることは十分解りますが。
もしよければ臨床例をあげて「こういう場合どうとらえますか?意見を聞かせてください」のほうが早いのではないのでしょうか・・。
何かしら歯科に対してメッセージを発せられたいのでしょうが、いまひとつどこにフォーカスをおけばよいのかわかりかねます。
これでは学者のようです・・・。
確かに理論は大事ですが理論と実戦の配分がとても大事なのは、自分などが説明せずとも十分ご存知のはずです。
できれば臨床症例でこういう対応はおかしいと具体例をお示しいただいたほうが早いのでは・・。
ま・・個人情報保護の点で難しいのですが。
体内と体外を貫く器官との認識を持たれた上での疑問だったんですね。
とても興味深く感じます。
僕はこの手の話題は結構楽しく読ませてもらっています。
お医者さんの考える齲蝕のイメージ、
体の一部としての疾患との捉え方、もっと深く考えられればいいと思っています。
>「口腔は特殊だから〜である」という話ばかりで、人体一般のどういう点と比>べて特殊なのかという認識が不足している印象です。
一番決定的な違いは、その器官を作った細胞が存在しない、
再生する事が無いというところでしょうか?
(もちろん象牙質は2次象牙質を作るとかは認識しているし、治療に利用することもあります。)
ほかの臓器で、体内と体外を貫くもので再生されていないものは
無いと思います。
この点が決定的にほかの臓器と違うところだと認識しています。
(神経も再生しないとかの突っ込みはやめてくださいね。)
とても興味深く感じます。
僕はこの手の話題は結構楽しく読ませてもらっています。
お医者さんの考える齲蝕のイメージ、
体の一部としての疾患との捉え方、もっと深く考えられればいいと思っています。
>「口腔は特殊だから〜である」という話ばかりで、人体一般のどういう点と比>べて特殊なのかという認識が不足している印象です。
一番決定的な違いは、その器官を作った細胞が存在しない、
再生する事が無いというところでしょうか?
(もちろん象牙質は2次象牙質を作るとかは認識しているし、治療に利用することもあります。)
ほかの臓器で、体内と体外を貫くもので再生されていないものは
無いと思います。
この点が決定的にほかの臓器と違うところだと認識しています。
(神経も再生しないとかの突っ込みはやめてくださいね。)
いえいえ、臨床に限らず基礎医学においても、そういう「ぱっと見の第一印象的な意見」が大事だと思います。
トピ題に書いたように、当初はエナメル質は骨の一種だと思っていたために、骨が露出しているなんて歯牙とは変わった組織だなと思っていました。
しかしながらその後のご指摘で、象牙質までが骨であり、エナメル質は上皮由来の成分で、象牙質を覆う「硬い皮膚(ものすごい固さですが(笑))」のようなもの、と認識を改めました。
まあ骨を直接皮膚が覆っているのというのは、やっぱり不思議なものではありますが。
「硬い皮膚と」と言えば、人体では他に指先の「爪甲(そうこう、爪の事)」が該当します。これは皮膚の角質という組織が固くなったものです。ただ人間だと歯牙と爪甲は余り似ていませんが、ネコ科やイヌ科ではよく似ています。用途も、獲物の捕食、殺傷に両方とも使われる点でも似ています。
これらの動物では歯牙も爪甲も「再生」します。
残念ながら人間では歯牙は一回しか生え変わりませんが、爪甲は少しずつ生え替わりますね。
その代り、人間は歯牙を研ぐ必要がありませんが、爪甲は定期的に削ったり切る必要があります。
多くの動物では歯も爪も生え続けるので定期的に削る必要があります。
どちらがいいんでしょうね。
で、歯牙でいう「う歯」は、爪甲ではあるのでしょうか?
生活習慣に依存した慢性的感染症…
あります。いわゆる爪水虫です。
水虫の中でも一番治りにくい水虫で、白癬菌という真菌(カビの事)が爪の裏まで入り込み、感染してしまった状態です。
う歯のように爪甲がとかされるという事はないですが、爪が汚く濁り、時にはあり得ない程に歪み、巻き爪などになって激しい痛みや二次感染を引き起します。
長期間放置すれば、白癬菌が血流に入り込んで重篤な敗血症を起こし、命の危険にさらされる事すらあります。
う歯が進行して歯髄炎になった場合と、似てないですか?
近年まで爪水虫の治療は困難で、今でも「治らない」という医者もおりますが、実はきちんとした治療を実施すれば100%治ります。
爪に入った白癬菌にはどんな薬も届かないから無理、というのが長い事通説だったんですが、爪に蓄積する抗真菌薬(カビ用の抗生剤みたいなものです)と爪にしみこむ薬の開発、そして外科的に感染した爪を切り取る手術によって、もはや治らない水虫はないと言っても過言ではありません。実際僕の患者さんで治らなかった人は一人もいません。
もちろん生活習慣(爪の清潔保持)の改善も必要ですが。
う歯も現状では、感染部位を削除して補綴を行なうだけ、う蝕の予防と進行の防止に努め、できるだけ抜歯に至る時期を遅くする事しかできない、そういう認識かと思います。削ってしまった歯質は決して元に戻らない、と。
しかし、う歯も雑多な細菌種に起こる訳ではなく、特定の数種類の原因菌によってのみ起こるという点でも、ほとんどが白癬菌で起こる水虫と似ています。
爪と違って再生しない点、代謝がものすごく遅い点などで水虫より不利ですが、治療法の確立した水虫との類似点が、何らかの新たなう歯治療のヒントになったりしないかなあと、思ったりする訳です。
トピ題に書いたように、当初はエナメル質は骨の一種だと思っていたために、骨が露出しているなんて歯牙とは変わった組織だなと思っていました。
しかしながらその後のご指摘で、象牙質までが骨であり、エナメル質は上皮由来の成分で、象牙質を覆う「硬い皮膚(ものすごい固さですが(笑))」のようなもの、と認識を改めました。
まあ骨を直接皮膚が覆っているのというのは、やっぱり不思議なものではありますが。
「硬い皮膚と」と言えば、人体では他に指先の「爪甲(そうこう、爪の事)」が該当します。これは皮膚の角質という組織が固くなったものです。ただ人間だと歯牙と爪甲は余り似ていませんが、ネコ科やイヌ科ではよく似ています。用途も、獲物の捕食、殺傷に両方とも使われる点でも似ています。
これらの動物では歯牙も爪甲も「再生」します。
残念ながら人間では歯牙は一回しか生え変わりませんが、爪甲は少しずつ生え替わりますね。
その代り、人間は歯牙を研ぐ必要がありませんが、爪甲は定期的に削ったり切る必要があります。
多くの動物では歯も爪も生え続けるので定期的に削る必要があります。
どちらがいいんでしょうね。
で、歯牙でいう「う歯」は、爪甲ではあるのでしょうか?
生活習慣に依存した慢性的感染症…
あります。いわゆる爪水虫です。
水虫の中でも一番治りにくい水虫で、白癬菌という真菌(カビの事)が爪の裏まで入り込み、感染してしまった状態です。
う歯のように爪甲がとかされるという事はないですが、爪が汚く濁り、時にはあり得ない程に歪み、巻き爪などになって激しい痛みや二次感染を引き起します。
長期間放置すれば、白癬菌が血流に入り込んで重篤な敗血症を起こし、命の危険にさらされる事すらあります。
う歯が進行して歯髄炎になった場合と、似てないですか?
近年まで爪水虫の治療は困難で、今でも「治らない」という医者もおりますが、実はきちんとした治療を実施すれば100%治ります。
爪に入った白癬菌にはどんな薬も届かないから無理、というのが長い事通説だったんですが、爪に蓄積する抗真菌薬(カビ用の抗生剤みたいなものです)と爪にしみこむ薬の開発、そして外科的に感染した爪を切り取る手術によって、もはや治らない水虫はないと言っても過言ではありません。実際僕の患者さんで治らなかった人は一人もいません。
もちろん生活習慣(爪の清潔保持)の改善も必要ですが。
う歯も現状では、感染部位を削除して補綴を行なうだけ、う蝕の予防と進行の防止に努め、できるだけ抜歯に至る時期を遅くする事しかできない、そういう認識かと思います。削ってしまった歯質は決して元に戻らない、と。
しかし、う歯も雑多な細菌種に起こる訳ではなく、特定の数種類の原因菌によってのみ起こるという点でも、ほとんどが白癬菌で起こる水虫と似ています。
爪と違って再生しない点、代謝がものすごく遅い点などで水虫より不利ですが、治療法の確立した水虫との類似点が、何らかの新たなう歯治療のヒントになったりしないかなあと、思ったりする訳です。
>爪と違って再生しない点、代謝がものすごく遅い点などで水虫より不利ですが
そこがむしろ一番の相違点であり、う歯の治療が困難である主原因でしょう。
爪の治療も原則として『感染質の除去→再生時に再感染の防止』で修復するのでしょうが、歯は再生がありませんので代替材料にて修復する以外にはないです。
感染質の除去の後で再生がありませんので、爪水虫よりも癌の治療に似ている気がします。放射線療法や化学療法など発達してきたにも関わらず部分切除(もしくは全摘)が未だに最良の方法であり、摘出後のリカバリーは代替えの人工材料以外にあまりない…
早期発見、早期治療が原則ですが絶対に再発がないとは言い切れず、再発を何度も繰り返したりする。
感染症の要素も勿論あると思います。う蝕の治療ではなく予防に関しては細菌叢のコントロールができれば可能かもしれないとは思いますが…
そこがむしろ一番の相違点であり、う歯の治療が困難である主原因でしょう。
爪の治療も原則として『感染質の除去→再生時に再感染の防止』で修復するのでしょうが、歯は再生がありませんので代替材料にて修復する以外にはないです。
感染質の除去の後で再生がありませんので、爪水虫よりも癌の治療に似ている気がします。放射線療法や化学療法など発達してきたにも関わらず部分切除(もしくは全摘)が未だに最良の方法であり、摘出後のリカバリーは代替えの人工材料以外にあまりない…
早期発見、早期治療が原則ですが絶対に再発がないとは言い切れず、再発を何度も繰り返したりする。
感染症の要素も勿論あると思います。う蝕の治療ではなく予防に関しては細菌叢のコントロールができれば可能かもしれないとは思いますが…
大変面白い話なので参加させていただきます。
なんかややこしい方向に話は行ってますが、
トピ主の先生の最初の議案は歯科においては
ロジックと臨床の差があるのか?
がご質問内容だと思います。
それにつきましてはウ蝕(う歯)は、mutans streptococci
プラス後天的な様々な環境因子から起こる酸蝕症であり、
感染症でも生活習慣病でもなく、それ以前に疾患ではないと
言う事は等の昔に結論付けられています。
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1074995?ordinalpos=333&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
臨床実感からしてもその通りだと思います。
よってテクニカルエラーもしくはディアグノシスエラー
しかありません。
それ以上も無いですし、それ以下も無いのでご勘弁いただければ
と思います。
また
>しかしながらその後のご指摘で、象牙質までが骨であり、エナメル質は上皮由来の成分で、象牙質を覆う「硬い皮膚(ものすごい固さですが(笑))」のようなもの、と認識を改めました。
まあ骨を直接皮膚が覆っているのというのは、やっぱり不思議なものではありますが。
これも象牙質は中胚葉由来の組織ですが、決して骨ではありません。
骨はあくまでも歯槽骨までです(笑)
よって爪と同じロジックが成り立つと思います。
再生能力に関しては置いといて・・・
なんかややこしい方向に話は行ってますが、
トピ主の先生の最初の議案は歯科においては
ロジックと臨床の差があるのか?
がご質問内容だと思います。
それにつきましてはウ蝕(う歯)は、mutans streptococci
プラス後天的な様々な環境因子から起こる酸蝕症であり、
感染症でも生活習慣病でもなく、それ以前に疾患ではないと
言う事は等の昔に結論付けられています。
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1074995?ordinalpos=333&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
臨床実感からしてもその通りだと思います。
よってテクニカルエラーもしくはディアグノシスエラー
しかありません。
それ以上も無いですし、それ以下も無いのでご勘弁いただければ
と思います。
また
>しかしながらその後のご指摘で、象牙質までが骨であり、エナメル質は上皮由来の成分で、象牙質を覆う「硬い皮膚(ものすごい固さですが(笑))」のようなもの、と認識を改めました。
まあ骨を直接皮膚が覆っているのというのは、やっぱり不思議なものではありますが。
これも象牙質は中胚葉由来の組織ですが、決して骨ではありません。
骨はあくまでも歯槽骨までです(笑)
よって爪と同じロジックが成り立つと思います。
再生能力に関しては置いといて・・・
こんばんは。
パラデン先生!!
ご指摘ありがとうございます!!
私はやっぱりヤブ歯医者でした(汗)
しっかりと疾患と定義されてました。
お騒がせしました・・
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%86%E8%9D%95
いやぁ〜実を言うと学生時代に読んだ論文の要点を
ノートしていたのを鵜呑みにしてコメントしてしまい
ました。
言い訳になってしまいますが、血流の無い硬組織である
エナメル質表面における脱灰現象は単に化学現象であり
宿主応答とか免疫や炎症反応と言った疾患レベルの話で
無いので、てっきり疾患のカテゴリーにはまらないと
勝手に思っておりましたし、WHOのトピックでもcariesは
あくまでもcariesの記述しかなくdiseaseにあらずと勝手に
思っておりました。
http://www.who.int/oral_health/objectives/en/index.html
ごめんなさい。
歯医者辞めますわ。
とりあえず今から私の肛門にもしも歯があったらを
考えて今後の人生を考えます・・
パラデン先生!!
ご指摘ありがとうございます!!
私はやっぱりヤブ歯医者でした(汗)
しっかりと疾患と定義されてました。
お騒がせしました・・
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%86%E8%9D%95
いやぁ〜実を言うと学生時代に読んだ論文の要点を
ノートしていたのを鵜呑みにしてコメントしてしまい
ました。
言い訳になってしまいますが、血流の無い硬組織である
エナメル質表面における脱灰現象は単に化学現象であり
宿主応答とか免疫や炎症反応と言った疾患レベルの話で
無いので、てっきり疾患のカテゴリーにはまらないと
勝手に思っておりましたし、WHOのトピックでもcariesは
あくまでもcariesの記述しかなくdiseaseにあらずと勝手に
思っておりました。
http://www.who.int/oral_health/objectives/en/index.html
ごめんなさい。
歯医者辞めますわ。
とりあえず今から私の肛門にもしも歯があったらを
考えて今後の人生を考えます・・
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
歯医者の本音 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート