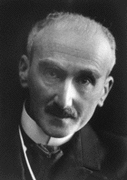第12回
さて、いよいよ本日で最後まで読みきります。最後まで付いてきてくださっている方、本当にありがとうございます。あと少しです。頑張りましょう。
(第24段落)この段落でいよいよカントが登場します。カントほどの偉大な思想家でも、ベルグソン哲学においては常に悪役です。これは実に不思議なことなのですが。
冒頭の「直観に行くのに感覚と意識との範囲の外に出る必要はないからです。」(Car il n'est pas nécessaire, pour aller à l'intuition, de se transporter hors du domaine des sens et de la conscience.)という意味ですが、これは要するに我々人間が直観によって真理を把握するのは知覚上においてであってそれ以外はあり得ないということです(第10回を参照)。次にくる「カントはそれを必要だと信じたことです」というのはそれをカントが出来るといったということではない。カントの超越論的観念論では、ベルグソンの言う直観の対象となる絶対的真理は、感性の直観形式及び悟性の向こう側、即ち物自体の世界なのであるから、我々の現象界を超越しており、人間がどう頑張ってみてもこれを触知することは出来ないというのがカントの立場だからです。カントの誤りは運動や時間の本性である持続を感性の直観形式としてしか捉えなかったことだとベルグソンは考えます。この立場にたてば、事象を運動として捉えることが可能であり、それこそまさにこれまでに述べられてきた直観的方法なわけです。
ところで、ベルグソンはこのようなカント批判を行うわけですが、しかしこのような批判の表現を目にすると、実は別の面ではカントの物自体の想定と主観性の二分法いう考え方を暗に認めていることになるのではないかというのが僕の考え方です。なるほど感性の直観形式の「時間」については、確かにベルグソンの指摘はまったく正しい。しかし、だからといって、空間の直観形式、純粋悟性概念のカテゴリー論を完全に廃棄できるのか?メルロ・ポンティのような現象学者によれば、このような超越論的形式を認めることは知覚に対する「古典的偏見」に他ならないというでしょうけど、ベルグソンは現象学の立場にはたちませんので、現象学的還元された状態から出発する必要はないわけです。その場合、カントの考え方をある程度復権できるのではないか?そしてそうだとするそのことはとベルグソンの『物質と記憶』のイマージュ論とどう関係するのか?これは慎重な比較研究を要する非常に大きな問題ですので、ここでは問題提起として指摘するだけに留めましょう。
(最終段落)この最後の段落は総括ですね。このような哲学的直観の立場に立つと日常生活がどのように変わるかを述べています。我々の日常の世界は、世界の影で死のように冷たい世界だという(Car le monde où nos sens et notre conscience nous introduisent habituellement n'est plus que l'ombre de lui-même ; et il est froid comme la mort.)。しかしこれが直観によって温められ、明るくされる。日常的知覚は「電撃を受けて、その中にこわばっていたものがほぐれ、眠っていたものが目覚め、死んだものはよみがえってきます。」(: aussitôt le raidi se détend, l'assoupi se réveille, le mort ressuscite dans notre perception galvanisée.)という。ここの記述はあたかもプラトンの『国家』(第7巻)にある有名な「洞窟の比喩」を思い起こします。通常の人間生活というのは、囚人達が洞窟の中で壁に映る影を見ているようなものだが、彼らを洞窟の外に引きづりだして太陽の光に照らされている世界(イデアの世界)を見せる必要がある。しかしベルグソンがここで言っているのはイデアではなくまったくその対立物である持続の世界だ。ベルグソンはプラトン的なイデアの世界=永遠で不動の世界を運動の世界=持続に転倒させたわけです。この哲学史的意義は革命的と評してもいいでしょう。その立場が「持続の相の下に」(sub specia duratonis)というスピノザの「永遠の相の下に」(sub specia aeternitatis)という『エチカ』の言をもじった言い方で表わされています。この持続の相のもとに立つと、空間的なものの見かたに立脚する真理の捉え方はみな相対的なものでしかなくなり、かくて、プラトンもアリストテレスもデカルトもスピノザもはたまたカントの批判哲学までもがすべてtabula rasa(白紙還元)されるのであります。その劇的な論旨は『創造的進化』第4章に見られるとおりです。
余談ですが、「永遠の相の下に」について、これは『エチカ』第二部定理44系2に登場することばです。岩波文庫版ではこの部分に詳細な注が付されているが、その意味が確認できたので余計なことですが、すこし寄り道しましょう。いま僕の手元に最近入手した『エチカ』の羅仏対訳版がある。最近はインターネットで何でも手に入りますよね。これの仏訳のほうは現在フランスでも流布しているGF-Flammarion版のスピノザ著作集版のどうやら元となっているらしいC.Appuhnの訳だ(Spinoza : Ethique, 1934, Librairie Garnier Freres)。これによって、これによってラテン語原文を拾ってみると、
De natura Rationis est, res sub quadam aeternitatis specie percipere.
となる。対するAppuhnの仏訳は、
Il est de la nature de la Raison de percevoir kes choses comme possédant une certaine sorte d’ éternié.
です。訳せば、「ある種の永遠を所有するが如く事物を知覚することは理性の本性に属する。」となっている。これは岩波文庫版の畠中さんの注釈で指摘されているように、行き過ぎに思われますので、GF-Flammarionの仏訳でエチカを読まれる方は要注意。単純にオーソドックスなラテン語文法に従って解析してみても、
Sub:奪格支配の前置詞、「〜のもと」
quadam:不定形容詞のquidamの女性形奪格、一般的な訳は「ある〜」
aeternitatis:女性名詞のaeternitasの属格、「永遠の」
specie:女性名詞のspeciesの奪格、「見ること、像」
ということで、「ある永遠の相のもとに」と訳すのが自然です。
それで、この「持続の相のもとに」世界を認識するとどんなことになるか?「それは私たち自身をも活気づけてくれます。こうして哲学は、実践においても思索においても科学を補うものとなります。生活の利便にのみ向けられた応用によって、科学は私たちに快適を、せいぜい快楽を約束してくれます。しかし哲学は、すでに歓喜を私たちに与えてくれていると思います。」(Les satisfactions que l'art ne fournira jamais qu'à des privilégiés de la nature et de la fortune, et de loin en loin seulement, la philosophie ainsi entendue nous les offrirait à tous, à tout moment, en réinsufflant la vie aux fantômes qui nous entourent et en nous revivifiant nous-mêmes. Par là elle deviendrait complémentaire de la science dans la pratique aussi bien que dans la spéculation. Avec ses applications qui ne visent que la commodité de l'existence, la science nous promet le bien-être, tout au plus le plaisir. Mais la philosophie pourrait déjà nous donner la joie.)これが、この「哲学的直観」の締めくくりです。科学を代表とされる空間的なものの見かたや常識によってもたらされるのは、「快楽」(le plaisir)だが、直観に基づく真の哲学によってもたらされるのは「歓喜」(la joie)だ。この快楽と歓喜の二分法は哲学を唯物論から峻別してささげられたこの場限りの祝辞的空言ではなく、ベルグソン哲学の根底を流れる考え方であることは、「意識と生命」や『道徳と宗教との二源泉』を読んだ方にはお分かりと思います。即ち快楽が物質的生活に基づいたものであり、文明の機械化はこれを追求していくのに対し、歓喜は開いた魂の創造的情動であり、生命の単純性への回帰を意味する。従って、この歓喜という感情の背後には哲学的直観だけではなく、開いた宗教があるわけです。即ち、哲学と開いた宗教とは切っても切れない関係にあるということです。
ところで、これは僕の師のある哲学者の先生から教えていただいて知ったのですが、この歓喜と快楽といった二分法はベルグソンに始まったものではなく、西洋哲学の根源に関わるもののようです。というのも、プラトンの『プロタゴラス』の23節で既に、ソクラテス的討論による知によってもたらされる感情について以下のように述べられています。「というのは、喜びとは、何かを学んで知恵を身につけるときに、純粋に精神だけによって感ずるものであるが、楽しみとは、ものを食うとか、あるいはその他何らかの快楽によって身に受けるときに、純粋に肉体だけによって感じるものなのであるから。」(岩波文庫版藤沢令夫訳)。ちなみに仏訳では、喜びにla joieを、楽しみにle plaisirを当てているのだそうです。即ち古代にあっても、哲学というものが、ベルグソンのいう開いた宗教と根源から結びついたものであることが分かるでしょう。
ところが、さらに言えば、この哲学に伴う「歓喜」(la joie)は別に西洋だけにある感情ではない。東洋の哲学の根源である『論語』の冒頭を開いてみてください。「子曰く、学びて時に之を習う、亦た説(よろこ)ばしからずや。朋有り遠方より来る、亦た楽しからずや。人知らずして恨みず、亦た君子ならずや。」と孔子も言っている。論語は天の意を会得する道を説いた書ですから、「説ばし」とか「楽し」といった感情は、断じてplaisirではなく、joieでしかありえない。この冒頭の意味は、「何度も何度も反復し学習していると、いままで分からなかったことでも、ある日突然その真意を悟入し、自分の力として働きを示すようになる。なんとも喜ばしいことではないか。」ということで、「時に」はsometimesではなく、timely即ちしかるべき時にという意味です。即ち、それは人や書物の出会いと同じように、物事の理解というのは「時が熟して」初めて理解できるもので、この場合の理解は、「腑に落ちること」。氷が春風に吹かれて氷解するようなこと。つまりは宗教的悟りにもつながるものです。それが学問というものなわけです。こうした作業は天への道ですから孤独なものですが、志を持った友人達が集まってお互いに練磨すればなんとも楽しいことではないか。しかも、こうした歓喜(la joie)は、富や名声、地位とは無関係だ。一度学問の本質を理解できれば、そんなものはどうでもよくなる。なんとも君子ではないか。というわけです。論語もある意味では、開いた宗教の一種ですから、ベルグソンのいう歓喜という感情がいかに人類有史の哲学が発生していらいの根源的感情であるかということが分かるでしょう。
さて、今日の我が日本の哲学は、このような感情をともなったものとして理解されているか?大方は否ですね。哲学は、とくに戦後の大学闘争以来、大学を中心としてアカデミズムの業績作りか、論壇ジャーナリズムの商品としてしか扱われてこなかったし、今でも事態は同じでしょう。それがために、こうした哲学の商売人たちは、哲学の担い手を育てることをしてこなかったため、まさしく哲学の扼殺(ジャンケレヴィッチ)に直面しているわけです。本当は哲学はベルグソンの言うとおり、日常的なものの見かたを暖め、光を与える、単純なものであり、そこから得られる歓喜は、地位や名声などとは無縁なものです。そのことを僕達が気づき、哲学を街中の、学校の、家庭の、職場の、社会の「どこにでもありどこにでもない」(Partout et nulle part)行いとして僕達の中に取り戻さなければ本当に扼殺されてしまい、人間のもっとも尊い「自由」を失ってしまうことでしょう。
これで最後ですね。最後まで読んでくださった方、本当にありがとうございます。でもまだ終わりませんよ。(笑)
【次回】
最終回(10月23日(日)〜):自由討論(「哲学的直観」総括)
「哲学的直観」を読んで、自由にご意見、ご感想をご記入ください。僕へのCommentaireへの批判、ご意見も大歓迎です。
さて、いよいよ本日で最後まで読みきります。最後まで付いてきてくださっている方、本当にありがとうございます。あと少しです。頑張りましょう。
(第24段落)この段落でいよいよカントが登場します。カントほどの偉大な思想家でも、ベルグソン哲学においては常に悪役です。これは実に不思議なことなのですが。
冒頭の「直観に行くのに感覚と意識との範囲の外に出る必要はないからです。」(Car il n'est pas nécessaire, pour aller à l'intuition, de se transporter hors du domaine des sens et de la conscience.)という意味ですが、これは要するに我々人間が直観によって真理を把握するのは知覚上においてであってそれ以外はあり得ないということです(第10回を参照)。次にくる「カントはそれを必要だと信じたことです」というのはそれをカントが出来るといったということではない。カントの超越論的観念論では、ベルグソンの言う直観の対象となる絶対的真理は、感性の直観形式及び悟性の向こう側、即ち物自体の世界なのであるから、我々の現象界を超越しており、人間がどう頑張ってみてもこれを触知することは出来ないというのがカントの立場だからです。カントの誤りは運動や時間の本性である持続を感性の直観形式としてしか捉えなかったことだとベルグソンは考えます。この立場にたてば、事象を運動として捉えることが可能であり、それこそまさにこれまでに述べられてきた直観的方法なわけです。
ところで、ベルグソンはこのようなカント批判を行うわけですが、しかしこのような批判の表現を目にすると、実は別の面ではカントの物自体の想定と主観性の二分法いう考え方を暗に認めていることになるのではないかというのが僕の考え方です。なるほど感性の直観形式の「時間」については、確かにベルグソンの指摘はまったく正しい。しかし、だからといって、空間の直観形式、純粋悟性概念のカテゴリー論を完全に廃棄できるのか?メルロ・ポンティのような現象学者によれば、このような超越論的形式を認めることは知覚に対する「古典的偏見」に他ならないというでしょうけど、ベルグソンは現象学の立場にはたちませんので、現象学的還元された状態から出発する必要はないわけです。その場合、カントの考え方をある程度復権できるのではないか?そしてそうだとするそのことはとベルグソンの『物質と記憶』のイマージュ論とどう関係するのか?これは慎重な比較研究を要する非常に大きな問題ですので、ここでは問題提起として指摘するだけに留めましょう。
(最終段落)この最後の段落は総括ですね。このような哲学的直観の立場に立つと日常生活がどのように変わるかを述べています。我々の日常の世界は、世界の影で死のように冷たい世界だという(Car le monde où nos sens et notre conscience nous introduisent habituellement n'est plus que l'ombre de lui-même ; et il est froid comme la mort.)。しかしこれが直観によって温められ、明るくされる。日常的知覚は「電撃を受けて、その中にこわばっていたものがほぐれ、眠っていたものが目覚め、死んだものはよみがえってきます。」(: aussitôt le raidi se détend, l'assoupi se réveille, le mort ressuscite dans notre perception galvanisée.)という。ここの記述はあたかもプラトンの『国家』(第7巻)にある有名な「洞窟の比喩」を思い起こします。通常の人間生活というのは、囚人達が洞窟の中で壁に映る影を見ているようなものだが、彼らを洞窟の外に引きづりだして太陽の光に照らされている世界(イデアの世界)を見せる必要がある。しかしベルグソンがここで言っているのはイデアではなくまったくその対立物である持続の世界だ。ベルグソンはプラトン的なイデアの世界=永遠で不動の世界を運動の世界=持続に転倒させたわけです。この哲学史的意義は革命的と評してもいいでしょう。その立場が「持続の相の下に」(sub specia duratonis)というスピノザの「永遠の相の下に」(sub specia aeternitatis)という『エチカ』の言をもじった言い方で表わされています。この持続の相のもとに立つと、空間的なものの見かたに立脚する真理の捉え方はみな相対的なものでしかなくなり、かくて、プラトンもアリストテレスもデカルトもスピノザもはたまたカントの批判哲学までもがすべてtabula rasa(白紙還元)されるのであります。その劇的な論旨は『創造的進化』第4章に見られるとおりです。
余談ですが、「永遠の相の下に」について、これは『エチカ』第二部定理44系2に登場することばです。岩波文庫版ではこの部分に詳細な注が付されているが、その意味が確認できたので余計なことですが、すこし寄り道しましょう。いま僕の手元に最近入手した『エチカ』の羅仏対訳版がある。最近はインターネットで何でも手に入りますよね。これの仏訳のほうは現在フランスでも流布しているGF-Flammarion版のスピノザ著作集版のどうやら元となっているらしいC.Appuhnの訳だ(Spinoza : Ethique, 1934, Librairie Garnier Freres)。これによって、これによってラテン語原文を拾ってみると、
De natura Rationis est, res sub quadam aeternitatis specie percipere.
となる。対するAppuhnの仏訳は、
Il est de la nature de la Raison de percevoir kes choses comme possédant une certaine sorte d’ éternié.
です。訳せば、「ある種の永遠を所有するが如く事物を知覚することは理性の本性に属する。」となっている。これは岩波文庫版の畠中さんの注釈で指摘されているように、行き過ぎに思われますので、GF-Flammarionの仏訳でエチカを読まれる方は要注意。単純にオーソドックスなラテン語文法に従って解析してみても、
Sub:奪格支配の前置詞、「〜のもと」
quadam:不定形容詞のquidamの女性形奪格、一般的な訳は「ある〜」
aeternitatis:女性名詞のaeternitasの属格、「永遠の」
specie:女性名詞のspeciesの奪格、「見ること、像」
ということで、「ある永遠の相のもとに」と訳すのが自然です。
それで、この「持続の相のもとに」世界を認識するとどんなことになるか?「それは私たち自身をも活気づけてくれます。こうして哲学は、実践においても思索においても科学を補うものとなります。生活の利便にのみ向けられた応用によって、科学は私たちに快適を、せいぜい快楽を約束してくれます。しかし哲学は、すでに歓喜を私たちに与えてくれていると思います。」(Les satisfactions que l'art ne fournira jamais qu'à des privilégiés de la nature et de la fortune, et de loin en loin seulement, la philosophie ainsi entendue nous les offrirait à tous, à tout moment, en réinsufflant la vie aux fantômes qui nous entourent et en nous revivifiant nous-mêmes. Par là elle deviendrait complémentaire de la science dans la pratique aussi bien que dans la spéculation. Avec ses applications qui ne visent que la commodité de l'existence, la science nous promet le bien-être, tout au plus le plaisir. Mais la philosophie pourrait déjà nous donner la joie.)これが、この「哲学的直観」の締めくくりです。科学を代表とされる空間的なものの見かたや常識によってもたらされるのは、「快楽」(le plaisir)だが、直観に基づく真の哲学によってもたらされるのは「歓喜」(la joie)だ。この快楽と歓喜の二分法は哲学を唯物論から峻別してささげられたこの場限りの祝辞的空言ではなく、ベルグソン哲学の根底を流れる考え方であることは、「意識と生命」や『道徳と宗教との二源泉』を読んだ方にはお分かりと思います。即ち快楽が物質的生活に基づいたものであり、文明の機械化はこれを追求していくのに対し、歓喜は開いた魂の創造的情動であり、生命の単純性への回帰を意味する。従って、この歓喜という感情の背後には哲学的直観だけではなく、開いた宗教があるわけです。即ち、哲学と開いた宗教とは切っても切れない関係にあるということです。
ところで、これは僕の師のある哲学者の先生から教えていただいて知ったのですが、この歓喜と快楽といった二分法はベルグソンに始まったものではなく、西洋哲学の根源に関わるもののようです。というのも、プラトンの『プロタゴラス』の23節で既に、ソクラテス的討論による知によってもたらされる感情について以下のように述べられています。「というのは、喜びとは、何かを学んで知恵を身につけるときに、純粋に精神だけによって感ずるものであるが、楽しみとは、ものを食うとか、あるいはその他何らかの快楽によって身に受けるときに、純粋に肉体だけによって感じるものなのであるから。」(岩波文庫版藤沢令夫訳)。ちなみに仏訳では、喜びにla joieを、楽しみにle plaisirを当てているのだそうです。即ち古代にあっても、哲学というものが、ベルグソンのいう開いた宗教と根源から結びついたものであることが分かるでしょう。
ところが、さらに言えば、この哲学に伴う「歓喜」(la joie)は別に西洋だけにある感情ではない。東洋の哲学の根源である『論語』の冒頭を開いてみてください。「子曰く、学びて時に之を習う、亦た説(よろこ)ばしからずや。朋有り遠方より来る、亦た楽しからずや。人知らずして恨みず、亦た君子ならずや。」と孔子も言っている。論語は天の意を会得する道を説いた書ですから、「説ばし」とか「楽し」といった感情は、断じてplaisirではなく、joieでしかありえない。この冒頭の意味は、「何度も何度も反復し学習していると、いままで分からなかったことでも、ある日突然その真意を悟入し、自分の力として働きを示すようになる。なんとも喜ばしいことではないか。」ということで、「時に」はsometimesではなく、timely即ちしかるべき時にという意味です。即ち、それは人や書物の出会いと同じように、物事の理解というのは「時が熟して」初めて理解できるもので、この場合の理解は、「腑に落ちること」。氷が春風に吹かれて氷解するようなこと。つまりは宗教的悟りにもつながるものです。それが学問というものなわけです。こうした作業は天への道ですから孤独なものですが、志を持った友人達が集まってお互いに練磨すればなんとも楽しいことではないか。しかも、こうした歓喜(la joie)は、富や名声、地位とは無関係だ。一度学問の本質を理解できれば、そんなものはどうでもよくなる。なんとも君子ではないか。というわけです。論語もある意味では、開いた宗教の一種ですから、ベルグソンのいう歓喜という感情がいかに人類有史の哲学が発生していらいの根源的感情であるかということが分かるでしょう。
さて、今日の我が日本の哲学は、このような感情をともなったものとして理解されているか?大方は否ですね。哲学は、とくに戦後の大学闘争以来、大学を中心としてアカデミズムの業績作りか、論壇ジャーナリズムの商品としてしか扱われてこなかったし、今でも事態は同じでしょう。それがために、こうした哲学の商売人たちは、哲学の担い手を育てることをしてこなかったため、まさしく哲学の扼殺(ジャンケレヴィッチ)に直面しているわけです。本当は哲学はベルグソンの言うとおり、日常的なものの見かたを暖め、光を与える、単純なものであり、そこから得られる歓喜は、地位や名声などとは無縁なものです。そのことを僕達が気づき、哲学を街中の、学校の、家庭の、職場の、社会の「どこにでもありどこにでもない」(Partout et nulle part)行いとして僕達の中に取り戻さなければ本当に扼殺されてしまい、人間のもっとも尊い「自由」を失ってしまうことでしょう。
これで最後ですね。最後まで読んでくださった方、本当にありがとうございます。でもまだ終わりませんよ。(笑)
【次回】
最終回(10月23日(日)〜):自由討論(「哲学的直観」総括)
「哲学的直観」を読んで、自由にご意見、ご感想をご記入ください。僕へのCommentaireへの批判、ご意見も大歓迎です。
|
|
|
|
|
|
|
|
アンリ・ベルクソン 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-