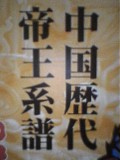或說聽計當而身疏。或言不用計不行而益親。何以明之。
三國伐齊,圍平陸。括子以報于牛子曰、三國之地,不接於我。逾鄰國而圍平陸,利不足貪也。然則求名於我也。請以齊侯往。牛子以為善。括子出,無害子入。牛子以括子言告無害子。無害子曰、異乎臣之所聞。牛子曰、國危而不安,患結而不解。何謂貴智。無害子曰、臣聞裂壤土以安社稷者,聞殺身破家以存其國者,不聞出其君以為封疆者。牛子不聽無害子之言,而用括子之計,三國之兵罷,而平陸之地存。自此之後,括子日以疏,無害子日以進。故謀患而患解,圖國而國存,括子之智得矣。無害子之慮無中於策,謀無益于國,然而心調於君,有義行也。今人待冠而飾首,待履而行地。冠履之於人也,寒不能暖,風不能障,暴不能蔽也。然而冠冠履履者,其所自托者然也。夫咎犯戰勝城濮,而雍季無尺寸之功,然而雍季先賞而咎犯後存者,其言有貴者也。故義者,天下之所賞也。百言百當,不如擇趨而審行也。
說聽かれ計當りて身疏んぜれるること或り。言用いられず計行われずして親を益すこと或り。何を以て之を明らかにせん。
三國、斉を伐ちて,平陸を圍む。括子(人名、斉の臣)、以て牛子(人名、斉の臣)に報じて曰く、「三國の地は、我に接せず。鄰國を逾(こえる)えて平陸を圍む,利は貪るに足らざらん。然れば則ち名を我に求むればなり。請う、齊侯を以て往かんことを。」牛子、以て善しと為す。括子出でて,無害子(人名、斉の臣)入る。牛子、括子の言を以て無害子に告ぐ。無害子曰く、「臣の聞く所に異なれり。」牛子曰く、「國危うくして安んぜず,患え結ばれて解かれず。何をか謂わん、智を貴し、と。」無害子曰く、「臣、壤土を裂き以て社稷を安んずる者を聞き,身を殺し家を破り以て其の國を存する者を聞くも、其の君を出だし以て封疆の為にする者を聞かず。」牛子、無害子の言を聽かずして、括子の計を用う。三國の兵罷みて、平陸の地存す。此れ自りの後,括子は日に以て疏ぜられ,無害子は日に以て進む。故に患えを謀りて患え解き,國を圖りて國存するに,括子の智は得たり。無害子の慮は策に中(あたる)る無く,謀は國に益する無し,然れども心の君に調(周に通じ、かなう)うは,義行有ればなり。今、人、冠を待ちて首を飾り,履を待ちて地を行く。冠履の人に於けるや,寒に暖むる能わず,風に障ぎる能わず,暴に蔽う能わざるなり。然れども冠を冠り履を履くは,其れ自ら托す所の者然ればなり。夫れ咎犯は戰いて城濮に勝ち,而して雍季は尺寸の功無し,然れども雍季、先に賞せられて、咎犯、後に存するは,其の言に貴き者有ればなり。故に義は,天下の賞する所なり。百言百當なるも,趨を擇びて行を審かにするに如かざるなり。
<語釈>
三国 ― 趙・韓・魏
封疆 ― 国境
待冠 ― “待”は“まつ”と読んでいるが、備える、或いは持っている、と言う意味である。
戦勝城濮 ― これは春秋時代の最も重要な戦いの一つである城濮の戦いのことである。
<通釈>
意見を聞かれたので、考えを述べたところ、それが当ったにもかかわらず、自身は疎外されることがある、反対に意見は用いられず、実行もされなかったのに、親愛を益すことがある。何によって之を明らかにしようか。
趙・韓・魏の三国は、斉を伐ち平陸の邑を囲んだ。括子(人名)は牛子(人名)に、三國の地は、斉に接していないので、隣の國を逾えて、我が平陸を圍んでいますが、利益を貪るに足るほどの土地ではありません。ですから此れは大国の斉を伐ったという名声を求めてのことでありましょう。ですので、どうか齊侯に平陸へ往かれますように、と報告した。牛子は善く分かった、と答えた。括子が退出すると、代わって無害子(人名)が入ってきた。牛子は括子が述べたことを無害子に告げると、無害子は、臣が聞いた事とは異なっています、答えた。牛子は、今國は危機に直面して安まらず,患いが解決できないのに、口先だけの知識など、何の意味があろうか、と述べると、無害子は、臣は国土を裂いて侵略者に差し出して、国を保った者は聞いたことがある。自分を犠牲にし家をつぶしても国を存続させた者は聞いたことがある。しかし、自分の主君を連れ出すことによって、国境を守ろうとするものは聞いた事がない、と答えた。牛子は無害子の言を聽かずに、括子の意見をを採用した。やがて三國の兵は戻って行き、平陸の地は無事に存続した。しかしながら、此れ自り後,括子は次第に疏じられ,無害子は日増しに昇進していった。つまり患いを取り除くことを謀って之を解決し,國の事を考えて存続させるには,括子の智は的を得ていた。無害子の考えは策に合致せず,国のためには無益であった。けれども、その心が主君の意に適ったのは、君臣の義に適った行いであったからである。たとえば、人は冠を待っているから首を飾り,履を待っているから地を行くが、冠や履は人々にとって,寒さを暖めることも無く,風を障ぎることも無く,日差しを蔽うことも無い。けれども冠を被り、履物をを履くのは,それぞれに其の使用目的があるからである。あの城濮の戦いでは咎犯(人名)は勝ち,雍季(人名)は少しの功も無かった,けれども雍季のほうが先に賞められて、咎犯が後になったのは,雍季の意見に貴いものが有ったからである。このように義は,世の中挙げて賞賛する所のものである。百の意見を述べて全て的中しても,趨勢を善く見極めて行を明らかにするには及ばない。
<解説>
三国が斉の平陸を囲んだのは、何時か。史記六国表の斉の威王23年に、趙と平陸に会す、と記されている。威王23年は、周の顕王13年(前356年)である。これ以外に平陸での会合は見当たらない。しかし、括子・牛子・無害子の話は史記では見当たらないので定かではない。
城濮の戦いは、蔡・陳・鄭・宋・曹等の小国を侵して、中原を目指し北進してきた新興勢力の楚に対して、晋の文侯が中心になって、城濮で楚と戦い、之を破って、楚の北進を止めた戦いであった。此の戦いにより、晋の文侯は覇者としての階段を昇っていったのである。
咎犯と雍季の話は次章で詳しく出てくるのでここでは触れない。
此の章のテーマは、分かりやすく言えば、意見を述べるのも空気を読んで述べなさい、と言う事であろうか。正しいからと言って、そのときの状況を善く見極めずに述べるのは、独りよがりである。前章の“言葉の上では正しいことを言っているのに、実際には其れに対して害を及ぼすことがあって、用いることが出来ない。”と言うことと合わせて、正しいだけでは実際に適用せず、用いられないことがあることを、理解しておかなければいけない。本当に用いられて、現実に則した、本当の“正しさ”は、全体を把握した中でこそ、生かされるのである。分かっていても、私はこれが苦手で、正しい事を言って、疎んぜらるタイプである。
三國伐齊,圍平陸。括子以報于牛子曰、三國之地,不接於我。逾鄰國而圍平陸,利不足貪也。然則求名於我也。請以齊侯往。牛子以為善。括子出,無害子入。牛子以括子言告無害子。無害子曰、異乎臣之所聞。牛子曰、國危而不安,患結而不解。何謂貴智。無害子曰、臣聞裂壤土以安社稷者,聞殺身破家以存其國者,不聞出其君以為封疆者。牛子不聽無害子之言,而用括子之計,三國之兵罷,而平陸之地存。自此之後,括子日以疏,無害子日以進。故謀患而患解,圖國而國存,括子之智得矣。無害子之慮無中於策,謀無益于國,然而心調於君,有義行也。今人待冠而飾首,待履而行地。冠履之於人也,寒不能暖,風不能障,暴不能蔽也。然而冠冠履履者,其所自托者然也。夫咎犯戰勝城濮,而雍季無尺寸之功,然而雍季先賞而咎犯後存者,其言有貴者也。故義者,天下之所賞也。百言百當,不如擇趨而審行也。
說聽かれ計當りて身疏んぜれるること或り。言用いられず計行われずして親を益すこと或り。何を以て之を明らかにせん。
三國、斉を伐ちて,平陸を圍む。括子(人名、斉の臣)、以て牛子(人名、斉の臣)に報じて曰く、「三國の地は、我に接せず。鄰國を逾(こえる)えて平陸を圍む,利は貪るに足らざらん。然れば則ち名を我に求むればなり。請う、齊侯を以て往かんことを。」牛子、以て善しと為す。括子出でて,無害子(人名、斉の臣)入る。牛子、括子の言を以て無害子に告ぐ。無害子曰く、「臣の聞く所に異なれり。」牛子曰く、「國危うくして安んぜず,患え結ばれて解かれず。何をか謂わん、智を貴し、と。」無害子曰く、「臣、壤土を裂き以て社稷を安んずる者を聞き,身を殺し家を破り以て其の國を存する者を聞くも、其の君を出だし以て封疆の為にする者を聞かず。」牛子、無害子の言を聽かずして、括子の計を用う。三國の兵罷みて、平陸の地存す。此れ自りの後,括子は日に以て疏ぜられ,無害子は日に以て進む。故に患えを謀りて患え解き,國を圖りて國存するに,括子の智は得たり。無害子の慮は策に中(あたる)る無く,謀は國に益する無し,然れども心の君に調(周に通じ、かなう)うは,義行有ればなり。今、人、冠を待ちて首を飾り,履を待ちて地を行く。冠履の人に於けるや,寒に暖むる能わず,風に障ぎる能わず,暴に蔽う能わざるなり。然れども冠を冠り履を履くは,其れ自ら托す所の者然ればなり。夫れ咎犯は戰いて城濮に勝ち,而して雍季は尺寸の功無し,然れども雍季、先に賞せられて、咎犯、後に存するは,其の言に貴き者有ればなり。故に義は,天下の賞する所なり。百言百當なるも,趨を擇びて行を審かにするに如かざるなり。
<語釈>
三国 ― 趙・韓・魏
封疆 ― 国境
待冠 ― “待”は“まつ”と読んでいるが、備える、或いは持っている、と言う意味である。
戦勝城濮 ― これは春秋時代の最も重要な戦いの一つである城濮の戦いのことである。
<通釈>
意見を聞かれたので、考えを述べたところ、それが当ったにもかかわらず、自身は疎外されることがある、反対に意見は用いられず、実行もされなかったのに、親愛を益すことがある。何によって之を明らかにしようか。
趙・韓・魏の三国は、斉を伐ち平陸の邑を囲んだ。括子(人名)は牛子(人名)に、三國の地は、斉に接していないので、隣の國を逾えて、我が平陸を圍んでいますが、利益を貪るに足るほどの土地ではありません。ですから此れは大国の斉を伐ったという名声を求めてのことでありましょう。ですので、どうか齊侯に平陸へ往かれますように、と報告した。牛子は善く分かった、と答えた。括子が退出すると、代わって無害子(人名)が入ってきた。牛子は括子が述べたことを無害子に告げると、無害子は、臣が聞いた事とは異なっています、答えた。牛子は、今國は危機に直面して安まらず,患いが解決できないのに、口先だけの知識など、何の意味があろうか、と述べると、無害子は、臣は国土を裂いて侵略者に差し出して、国を保った者は聞いたことがある。自分を犠牲にし家をつぶしても国を存続させた者は聞いたことがある。しかし、自分の主君を連れ出すことによって、国境を守ろうとするものは聞いた事がない、と答えた。牛子は無害子の言を聽かずに、括子の意見をを採用した。やがて三國の兵は戻って行き、平陸の地は無事に存続した。しかしながら、此れ自り後,括子は次第に疏じられ,無害子は日増しに昇進していった。つまり患いを取り除くことを謀って之を解決し,國の事を考えて存続させるには,括子の智は的を得ていた。無害子の考えは策に合致せず,国のためには無益であった。けれども、その心が主君の意に適ったのは、君臣の義に適った行いであったからである。たとえば、人は冠を待っているから首を飾り,履を待っているから地を行くが、冠や履は人々にとって,寒さを暖めることも無く,風を障ぎることも無く,日差しを蔽うことも無い。けれども冠を被り、履物をを履くのは,それぞれに其の使用目的があるからである。あの城濮の戦いでは咎犯(人名)は勝ち,雍季(人名)は少しの功も無かった,けれども雍季のほうが先に賞められて、咎犯が後になったのは,雍季の意見に貴いものが有ったからである。このように義は,世の中挙げて賞賛する所のものである。百の意見を述べて全て的中しても,趨勢を善く見極めて行を明らかにするには及ばない。
<解説>
三国が斉の平陸を囲んだのは、何時か。史記六国表の斉の威王23年に、趙と平陸に会す、と記されている。威王23年は、周の顕王13年(前356年)である。これ以外に平陸での会合は見当たらない。しかし、括子・牛子・無害子の話は史記では見当たらないので定かではない。
城濮の戦いは、蔡・陳・鄭・宋・曹等の小国を侵して、中原を目指し北進してきた新興勢力の楚に対して、晋の文侯が中心になって、城濮で楚と戦い、之を破って、楚の北進を止めた戦いであった。此の戦いにより、晋の文侯は覇者としての階段を昇っていったのである。
咎犯と雍季の話は次章で詳しく出てくるのでここでは触れない。
此の章のテーマは、分かりやすく言えば、意見を述べるのも空気を読んで述べなさい、と言う事であろうか。正しいからと言って、そのときの状況を善く見極めずに述べるのは、独りよがりである。前章の“言葉の上では正しいことを言っているのに、実際には其れに対して害を及ぼすことがあって、用いることが出来ない。”と言うことと合わせて、正しいだけでは実際に適用せず、用いられないことがあることを、理解しておかなければいけない。本当に用いられて、現実に則した、本当の“正しさ”は、全体を把握した中でこそ、生かされるのである。分かっていても、私はこれが苦手で、正しい事を言って、疎んぜらるタイプである。
|
|
|
|
|
|
|
|
中国史 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
中国史のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55348人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90003人
- 3位
- 酒好き
- 170654人