道無き道を果敢に進んでゆく
眩しいばかりの開拓精神溢れた青年医師でした。
以前に、あるパーティで国境無き医師団の山本敏晴先生とお話出来る機会に恵まれました。
当時まだ30代前半の、山本先生は、道無き道を果敢に進んでゆく
眩しいばかりの開拓精神溢れた青年医師でした。
山本敏晴先生プロフィール
医師・医学博士・写真家・国際協力師・NPO法人「宇宙船地球号」事務局長の日記。
70カ国以上を訪れ、40カ国以上でプロジェクトを実施。
「本当に意味のある国際協力」を求めて活動中。
最近は後輩の育成のために尽力し、「国際協力師」という新しい職業を提唱。
一方、「持続可能な社会・持続可能な世界」の実現のために、日本でできる国際協力の形も提案しており、企業のCSR(企業の社会的責任)や消費者による買い物方法の改善、などの啓発も行う。 http://
http://
徹子の部屋にも出演されていらしたので少しはどのような方かを知っていましたが,山本敏晴先生の講演、ブログを通して数々のお言葉に感動しました。
そのお人柄、なさっていらっしゃる事の素晴らしさに魅き付けられてしまいました。その山本敏晴先生の講演の中で印象に残っているお言葉
≪愛情の反対は憎しみではなく無関心≫
という言葉について、以下のようにブログに掲載されていたので掲載させていただきます。山本敏晴先生はマイミクさんです。
マザーテレサ。
本名: アグネス・ゴンジャ・ボヤジュ。1910年生、1997年没。
オスマン帝国領のコソボ州(現マケドニア)生まれ。カトリック教会の修道女。
1931年、インドにわたり、カルカッタ(コルカタ)などで、地理を教えた。
1948年以降、「最も貧しい人の中で働きなさい」
という(神からの)啓示を受け、「死を待つ人の家」、「らい病患者の家」、「孤児院」などを作り、貧しい人々を救おうとした。
1979年、ノーベル平和賞を受賞。彼女の言葉に、以下のものがある。
・・・
「私は、今の世界の「最大の病気」は、らい病でも結核でもなく、(一人の人が)自分はいてもいなくてもいいんだ、だれもかまってくれないんだ、社会から見捨てられているんだ、と感じてしまうことだと思います。
「最大の病気」は、
すぐ近くに住んでいる近所の人が(経済的な)搾取や、国家権力による抑圧や、極度の貧困や、病気におびやかされていても(あなたが)無関心でいること、だと思います。」
・・・
彼女は、少なくとも3回、来日している。
1981年4月、1982年4月、1984年11月。
その時、こんなことを話している。
・・・
「私は、日本に来て、その繁栄の程度に驚きました。
日本人は物質的に本当に豊かになりました。
しかし、道を歩いていて気がついたのは、日本の多くの人は、
社会的な弱者や、貧しい人に、無関心だと思います。
私は、他の世界の人たちを知っています。その人たちは、
物質的には貧しいのですが、他の貧しい人を助けようとします。
その人たちは、精神的にはとっても豊かな人たちなのです。
(日本人をはじめとする)物質的に豊かな多くの人は、他人に対して無関心になってしまうようです。(あなたたちは)精神的に貧しい人たちだと、私は思います。愛の反対は憎しみとおもうかもしれませんが、実は無関心なのです。」
・・・
以上の話があるのだが、この中で、核心となっているフレーズ
「愛情の反対は憎しみではなく無関心」
という部分を私は、自分の講演の中で、頻繁に使っている。
わたしなりの、解釈を加えた上で。
(私の講演の中では、世界は、これこれこのように大変な問題があり、
それは、私たちが、日本で、のうのうと豊かな生活を送っていることと、間接的につながっている。
あなたは、それを、今、知ってしまった。
それに対して、これから、あなたは、何もしないのか?
というような流れで、このフレーズを引用している。)
それはともかく、いろいろ調べたのだが、この
「愛情の反対は憎しみではなく無関心」
というフレーズはもともとは、マザー・テレサが言ったものではないものらしい。いくつかの文献にそれを示唆するものがあった。
で、一応、今回、その、もともとの出典を調べてみようと思う。
・・・
まず、時代を一気に遡(さかのぼ)ろう。
キリスト教の聖典、新約聖書の最後に、
<span class="large"><span style="color:#00ccff">「ヨハネ黙示録」</span></span>というものがある。その中に、次の一節がある。
・・・
ヨハネ黙示録 3、7−19
ラオディキアにある教会にあてた手紙
「私は、あなたの行いを知っている。あなたは、冷たくもなく、熱くもない。むしろ、冷たいか熱いか、どちらかであって欲しい。
熱くも、冷たくもなく、なまぬるいので、わたしは、あなたを、口から吐き出そうとしてる。
あなたは、自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分がみじめで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸の者であることを知らない。わたしはあなたに忠告をしよう。」
・・・
ラオディキアとは、「人間が支配する世界(または時代)」という意味らしい。西暦1900年以降から現代にいたるまでの時代を「予言」して、上記の一節が書かれた・・とのこと。
この、冷たいか、熱いか、それとも、なまぬるいか、
という一節は、いろいろな解釈をすることができるため議論を呼ぶ。
ただ、ふつうに考えると(キリスト教に対する)信仰の姿勢を
批判したものであると考えるのが妥当であろう。
(ようするに、もっと真摯(しんし)になって信仰せよ、ということ。
キリスト教信仰の、倦怠期に入った人々に対して。)
しかし、一節には(解釈によっては)これこそが、「愛情の反対は憎しみではなく無関心」だ、という人もいる。(マザー・テレサもキリスト教徒なわけだから、これに影響された可能性が、最も高い、と言う。)
うーん。熱いのが「愛」で冷たいのが「憎しみ」でなまぬるいのが、「無関心」??
ほんとかな。
・・・
さらに、時代をさかのぼろう。
<span class="large"><span style="color:#00ff00">孟子(もうし)</span></span>という人がいた。
紀元前372年生、 紀元前289年没。中国の戦国時代の儒(じゅ)学者だ。(人間の)性善説を説いたことで有名。
人は誰でも「人に忍びざるの心」があると説いた。
わかりやすく言うと、誰にでも「他者の苦しみに無関心ではいられない心」が、あるのだと説いたのだ。
孟子は、(師である)孔子の「仁」(じん)を、自分なりに解釈し、
(国家の)君主の役割は、「人に忍びざるの心」を持ち、
国民に安定した生業(なりわい)を保障し、
安心できる社会環境を整えることだ、と説いた。
(この頃の、哲学者(儒学者)の役割は、当時の中国で乱立していた、どこかの小国に雇われ、国の方針をうちだすことであった・・
という社会背景があったから、上記のようなことを言っていたのである。)
ともかく、このような心の持ちようを、「惻隠(そくいん)の心」という。繰り返すが、それは「人の不幸を見過ごすことができない心」
であり、「人に忍びざるの心」とも表記される。
孟子、曰く(いわく)
人は、生まれながら、その心をもっており、それを失ってしまった人に
それを取り戻させることこそが、正しい道である、と主張した。
・・・
同じ頃、古代ギリシャにて。
ソクラテス
紀元前469年生、紀元前399年没。
「自分を知り、他人の状況をよく調べ、
知を愛し、それを求めながら生きるのでなければならない」
・・・・・・・・・・・・・
うーーん。
このあたりが、「愛情の反対は憎しみではなく無関心」の原点かな?
・・・
もう一つ、
<span class="large"><span style="color:#006600">孔子の言う、「仁」(じん)</span></span>を紹介しよう。
孔子。紀元前551年生、紀元前479年没。儒家の始祖。仁(じん)とは何か?実は、孔子は、それを明確にしていない。彼の残した、多数の(異なる)回答が残っておりどれが本当なのか、よくわからない。しかし、一般には、「仁」とは「他人に対する優しさ、もしくは情(じょう)、あるいは情け(なさけ)」を意味するものだと解されている。
これ以上の深い意味は、上述の、孟子が解釈した「惻隠の心」あたりで、理解していただきたい。(現代風に、解釈するならば、ほおっておけない気持ち、ということになるかと思う。)
ともかく、この「仁」という考え方は少なくとも、中国人のもっとも根本的な人間性の構築に大きく影響していくことになる。そして、それは、我が国にもおよんだ。
・・・
古事記や日本書紀の時代に、一人の天皇がいた。仁徳天皇(にんとくてんのう)という人だ。西暦313年生、399年没。(実在性を疑問視する学者も多い。)ともかく、「聖帝」とまで呼ばれるこの人の名前に
「仁」という文字が、入れられることになる。
・・・
その後、「仁」という文字は、歴代の天皇家の中で、非常に重要な(名前をつけるときの)漢字となり、多数の天皇にその文字が入った名前がつけられた。
(上述の、孟子が、国家の君主たちにいった逸話(いつわ)を思い出して頂けるだろうか?)
・・・
(国家の)君主の役割は、「人に忍びざるの心」を持ち、国民に安定した生業(なりわい)を保障し、安心できる社会環境を整えることである。
・・・
例えば、昭和天皇のの、諱(いみな、本名のこと)は裕仁(ひろひと)。
現在の天皇(平成天皇)は、明仁(あきひと)。ことごとく、この「仁」という文字が付いている。そしてそれを、「ひと」と読ませている。
・・・
現在、日本の天皇は、国の象徴という形で存在しているようだが、その、「仁」が名前につく人(家系?)を象徴だと仰いでいる私たち日本人も、やっぱり、一応、「惻隠の心」あたりを、ひそかにもっておいても
いいんじゃないだろうか?
「知ってしまった以上、ほおってはおけない」という心(姿勢)を。
最後に、世界の三聖、孔子の言葉を引用しておく。
「義をみてせざるは、勇なきなり!」
眩しいばかりの開拓精神溢れた青年医師でした。
以前に、あるパーティで国境無き医師団の山本敏晴先生とお話出来る機会に恵まれました。
当時まだ30代前半の、山本先生は、道無き道を果敢に進んでゆく
眩しいばかりの開拓精神溢れた青年医師でした。
山本敏晴先生プロフィール
医師・医学博士・写真家・国際協力師・NPO法人「宇宙船地球号」事務局長の日記。
70カ国以上を訪れ、40カ国以上でプロジェクトを実施。
「本当に意味のある国際協力」を求めて活動中。
最近は後輩の育成のために尽力し、「国際協力師」という新しい職業を提唱。
一方、「持続可能な社会・持続可能な世界」の実現のために、日本でできる国際協力の形も提案しており、企業のCSR(企業の社会的責任)や消費者による買い物方法の改善、などの啓発も行う。 http://
http://
徹子の部屋にも出演されていらしたので少しはどのような方かを知っていましたが,山本敏晴先生の講演、ブログを通して数々のお言葉に感動しました。
そのお人柄、なさっていらっしゃる事の素晴らしさに魅き付けられてしまいました。その山本敏晴先生の講演の中で印象に残っているお言葉
≪愛情の反対は憎しみではなく無関心≫
という言葉について、以下のようにブログに掲載されていたので掲載させていただきます。山本敏晴先生はマイミクさんです。
マザーテレサ。
本名: アグネス・ゴンジャ・ボヤジュ。1910年生、1997年没。
オスマン帝国領のコソボ州(現マケドニア)生まれ。カトリック教会の修道女。
1931年、インドにわたり、カルカッタ(コルカタ)などで、地理を教えた。
1948年以降、「最も貧しい人の中で働きなさい」
という(神からの)啓示を受け、「死を待つ人の家」、「らい病患者の家」、「孤児院」などを作り、貧しい人々を救おうとした。
1979年、ノーベル平和賞を受賞。彼女の言葉に、以下のものがある。
・・・
「私は、今の世界の「最大の病気」は、らい病でも結核でもなく、(一人の人が)自分はいてもいなくてもいいんだ、だれもかまってくれないんだ、社会から見捨てられているんだ、と感じてしまうことだと思います。
「最大の病気」は、
すぐ近くに住んでいる近所の人が(経済的な)搾取や、国家権力による抑圧や、極度の貧困や、病気におびやかされていても(あなたが)無関心でいること、だと思います。」
・・・
彼女は、少なくとも3回、来日している。
1981年4月、1982年4月、1984年11月。
その時、こんなことを話している。
・・・
「私は、日本に来て、その繁栄の程度に驚きました。
日本人は物質的に本当に豊かになりました。
しかし、道を歩いていて気がついたのは、日本の多くの人は、
社会的な弱者や、貧しい人に、無関心だと思います。
私は、他の世界の人たちを知っています。その人たちは、
物質的には貧しいのですが、他の貧しい人を助けようとします。
その人たちは、精神的にはとっても豊かな人たちなのです。
(日本人をはじめとする)物質的に豊かな多くの人は、他人に対して無関心になってしまうようです。(あなたたちは)精神的に貧しい人たちだと、私は思います。愛の反対は憎しみとおもうかもしれませんが、実は無関心なのです。」
・・・
以上の話があるのだが、この中で、核心となっているフレーズ
「愛情の反対は憎しみではなく無関心」
という部分を私は、自分の講演の中で、頻繁に使っている。
わたしなりの、解釈を加えた上で。
(私の講演の中では、世界は、これこれこのように大変な問題があり、
それは、私たちが、日本で、のうのうと豊かな生活を送っていることと、間接的につながっている。
あなたは、それを、今、知ってしまった。
それに対して、これから、あなたは、何もしないのか?
というような流れで、このフレーズを引用している。)
それはともかく、いろいろ調べたのだが、この
「愛情の反対は憎しみではなく無関心」
というフレーズはもともとは、マザー・テレサが言ったものではないものらしい。いくつかの文献にそれを示唆するものがあった。
で、一応、今回、その、もともとの出典を調べてみようと思う。
・・・
まず、時代を一気に遡(さかのぼ)ろう。
キリスト教の聖典、新約聖書の最後に、
<span class="large"><span style="color:#00ccff">「ヨハネ黙示録」</span></span>というものがある。その中に、次の一節がある。
・・・
ヨハネ黙示録 3、7−19
ラオディキアにある教会にあてた手紙
「私は、あなたの行いを知っている。あなたは、冷たくもなく、熱くもない。むしろ、冷たいか熱いか、どちらかであって欲しい。
熱くも、冷たくもなく、なまぬるいので、わたしは、あなたを、口から吐き出そうとしてる。
あなたは、自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分がみじめで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸の者であることを知らない。わたしはあなたに忠告をしよう。」
・・・
ラオディキアとは、「人間が支配する世界(または時代)」という意味らしい。西暦1900年以降から現代にいたるまでの時代を「予言」して、上記の一節が書かれた・・とのこと。
この、冷たいか、熱いか、それとも、なまぬるいか、
という一節は、いろいろな解釈をすることができるため議論を呼ぶ。
ただ、ふつうに考えると(キリスト教に対する)信仰の姿勢を
批判したものであると考えるのが妥当であろう。
(ようするに、もっと真摯(しんし)になって信仰せよ、ということ。
キリスト教信仰の、倦怠期に入った人々に対して。)
しかし、一節には(解釈によっては)これこそが、「愛情の反対は憎しみではなく無関心」だ、という人もいる。(マザー・テレサもキリスト教徒なわけだから、これに影響された可能性が、最も高い、と言う。)
うーん。熱いのが「愛」で冷たいのが「憎しみ」でなまぬるいのが、「無関心」??
ほんとかな。
・・・
さらに、時代をさかのぼろう。
<span class="large"><span style="color:#00ff00">孟子(もうし)</span></span>という人がいた。
紀元前372年生、 紀元前289年没。中国の戦国時代の儒(じゅ)学者だ。(人間の)性善説を説いたことで有名。
人は誰でも「人に忍びざるの心」があると説いた。
わかりやすく言うと、誰にでも「他者の苦しみに無関心ではいられない心」が、あるのだと説いたのだ。
孟子は、(師である)孔子の「仁」(じん)を、自分なりに解釈し、
(国家の)君主の役割は、「人に忍びざるの心」を持ち、
国民に安定した生業(なりわい)を保障し、
安心できる社会環境を整えることだ、と説いた。
(この頃の、哲学者(儒学者)の役割は、当時の中国で乱立していた、どこかの小国に雇われ、国の方針をうちだすことであった・・
という社会背景があったから、上記のようなことを言っていたのである。)
ともかく、このような心の持ちようを、「惻隠(そくいん)の心」という。繰り返すが、それは「人の不幸を見過ごすことができない心」
であり、「人に忍びざるの心」とも表記される。
孟子、曰く(いわく)
人は、生まれながら、その心をもっており、それを失ってしまった人に
それを取り戻させることこそが、正しい道である、と主張した。
・・・
同じ頃、古代ギリシャにて。
ソクラテス
紀元前469年生、紀元前399年没。
「自分を知り、他人の状況をよく調べ、
知を愛し、それを求めながら生きるのでなければならない」
・・・・・・・・・・・・・
うーーん。
このあたりが、「愛情の反対は憎しみではなく無関心」の原点かな?
・・・
もう一つ、
<span class="large"><span style="color:#006600">孔子の言う、「仁」(じん)</span></span>を紹介しよう。
孔子。紀元前551年生、紀元前479年没。儒家の始祖。仁(じん)とは何か?実は、孔子は、それを明確にしていない。彼の残した、多数の(異なる)回答が残っておりどれが本当なのか、よくわからない。しかし、一般には、「仁」とは「他人に対する優しさ、もしくは情(じょう)、あるいは情け(なさけ)」を意味するものだと解されている。
これ以上の深い意味は、上述の、孟子が解釈した「惻隠の心」あたりで、理解していただきたい。(現代風に、解釈するならば、ほおっておけない気持ち、ということになるかと思う。)
ともかく、この「仁」という考え方は少なくとも、中国人のもっとも根本的な人間性の構築に大きく影響していくことになる。そして、それは、我が国にもおよんだ。
・・・
古事記や日本書紀の時代に、一人の天皇がいた。仁徳天皇(にんとくてんのう)という人だ。西暦313年生、399年没。(実在性を疑問視する学者も多い。)ともかく、「聖帝」とまで呼ばれるこの人の名前に
「仁」という文字が、入れられることになる。
・・・
その後、「仁」という文字は、歴代の天皇家の中で、非常に重要な(名前をつけるときの)漢字となり、多数の天皇にその文字が入った名前がつけられた。
(上述の、孟子が、国家の君主たちにいった逸話(いつわ)を思い出して頂けるだろうか?)
・・・
(国家の)君主の役割は、「人に忍びざるの心」を持ち、国民に安定した生業(なりわい)を保障し、安心できる社会環境を整えることである。
・・・
例えば、昭和天皇のの、諱(いみな、本名のこと)は裕仁(ひろひと)。
現在の天皇(平成天皇)は、明仁(あきひと)。ことごとく、この「仁」という文字が付いている。そしてそれを、「ひと」と読ませている。
・・・
現在、日本の天皇は、国の象徴という形で存在しているようだが、その、「仁」が名前につく人(家系?)を象徴だと仰いでいる私たち日本人も、やっぱり、一応、「惻隠の心」あたりを、ひそかにもっておいても
いいんじゃないだろうか?
「知ってしまった以上、ほおってはおけない」という心(姿勢)を。
最後に、世界の三聖、孔子の言葉を引用しておく。
「義をみてせざるは、勇なきなり!」
|
|
|
|
|
|
|
|
長谷川泰子さんを応援する会。 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
長谷川泰子さんを応援する会。のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75487人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6448人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208289人
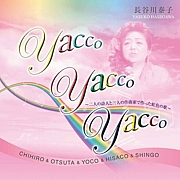







![Grande Messe[ミサ曲コミュ]](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/86/11/308611_96s.jpg)















