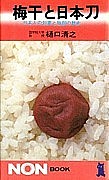欧米在住日本人は「なぜ欧米人はすぐ謝らないのか」と言うが、私はむしろ「なぜ日本人はすぐ謝るのか」の方が興味がある。交通事故を起こしたときなどに謝ると、後日法廷で「相手は謝罪したから、自己の過失を認めた」と証言されて不利になるので、謝罪しないのだという。だが謝罪の意を表明しないことから、関係がかえって険悪になることもあり、「謝罪しても責任を認めたことにならない法律」が作られている。
(1) 成果より忠誠心
戦国時代は戦が常態化し、兵力はいくらでも要るから、万年人手不足となり、就職は「売り手市場」となる。藤堂高虎は「武士たるもの七度主君を変えねば武士とは言えぬ」と言い、自分を買ってくれる主君を探して何度も仕官した。また朝倉宗滴は「武者は犬ともいへ、畜生ともいへ、勝つことが本にて候」と言い、戦国時代において勝ち残ることの重要性を訴えた。
これが江戸時代になると、戦がないため兵力は不要で、家臣を増やせば人件費がかかるだけだから、一度浪人となると再就職は困難だった。またこのような時代に求められたのは武芸の能力ではなく、忠誠心だっただろう。
主君に供をする者が数人の賊に襲われたら、主君を守るため最後まで戦わなければならない。職業は世襲制だから、たとえ戦死するようなことがあっても「よくぞ命がけで戦ってくれた」と誉められ、その子が再び召し抱えられることになる。しかし逃げればお家は取り潰しとなり、子々孫々まで浪人となるだろう。この時代は、個人の人命より家名が大切なのであって、実際に主君を守れたかどうか、武芸の腕は立つのかといった成果は、あまり重視されなかったようだ。
(2) 日本人の英雄は義に殉じる
北米では、歴史的勝者が英雄とされる。ところが日本人には判官びいきの民族性があり、源義経・楠正成のような敗者をしばしば英雄として讃美する。この違いは、どこから来るのだろうか。
楠正成は足利尊氏との決戦において、兵力に劣るため、敵を京都の街におびき寄せ、街に火を放てば、敵は大軍だから狭い京都の街路を迅速に動けず、炎に包まれるだろうというゲリラ戦を主張した。だが後醍醐天皇は、政治家として民を苦しめるわけにはいかぬから、敵を京に入れず、もっと西で迎撃せよと命じる。両者とも、勝つことだけを求めているわけではない。楠正成は、負けるとわかっている戦いに、裏切ることもせず慫慂として従う。日本人は勝つことにではなく、義に殉じる無私の精神に、心打たれるのだ。
日本人が重視するのは、成果よりむしろ真面目さ・純粋さである。だから仕事でミスをしたとき、すぐに謝罪することで、迷惑をかけた非を認める純粋さが求められるのではないだろうか。
(3) 日本人の失笑を買ったアメリカ版「フランダースの犬」
イギリスの作家ウィーダの小説「フランダースの犬」は、イギリスでもベルギーでも全く評価されなかった。画家志望の少年ネロがみなしごとなり、わずかに残ったお金で食料ではなく絵の具を買い、展覧会入選を夢見て破れ、憧れのルーベンスの絵の前で凍死する物語である。ウィーダは彼女自身が売れない作家で、理想に殉じるネロの姿を通して、自身の高い理想を謳いあげたものと思われるが、そのようなストイシズムはヨーロッパ人には評価されなかったようだ。
これがアメリカ映画になると、「子供が何の助けもなく死んでいく物語には意味がない」として、凍死寸前のネロのもとに父親が迎えに来るというラストシーンを描き、多くの日本人観客をずっこけさせた。日本人ファンは、ネロが放火の疑いをかけられても誰も恨むことなく、運命を受け容れる姿に心打たれたのだから、それを全否定し、努力は報われなければならない、必ず成功しなければならないとして原作を歪曲した結末に、非常な違和感を抱いたのだ。
武蔵野大学の高橋晃教授は、アンデルセンの童話「人魚姫」と「マッチ売りの少女」が、アメリカのバージョンにおいてハッピー・エンドに改変されていたことを発見した。
(1) 成果より忠誠心
戦国時代は戦が常態化し、兵力はいくらでも要るから、万年人手不足となり、就職は「売り手市場」となる。藤堂高虎は「武士たるもの七度主君を変えねば武士とは言えぬ」と言い、自分を買ってくれる主君を探して何度も仕官した。また朝倉宗滴は「武者は犬ともいへ、畜生ともいへ、勝つことが本にて候」と言い、戦国時代において勝ち残ることの重要性を訴えた。
これが江戸時代になると、戦がないため兵力は不要で、家臣を増やせば人件費がかかるだけだから、一度浪人となると再就職は困難だった。またこのような時代に求められたのは武芸の能力ではなく、忠誠心だっただろう。
主君に供をする者が数人の賊に襲われたら、主君を守るため最後まで戦わなければならない。職業は世襲制だから、たとえ戦死するようなことがあっても「よくぞ命がけで戦ってくれた」と誉められ、その子が再び召し抱えられることになる。しかし逃げればお家は取り潰しとなり、子々孫々まで浪人となるだろう。この時代は、個人の人命より家名が大切なのであって、実際に主君を守れたかどうか、武芸の腕は立つのかといった成果は、あまり重視されなかったようだ。
(2) 日本人の英雄は義に殉じる
北米では、歴史的勝者が英雄とされる。ところが日本人には判官びいきの民族性があり、源義経・楠正成のような敗者をしばしば英雄として讃美する。この違いは、どこから来るのだろうか。
楠正成は足利尊氏との決戦において、兵力に劣るため、敵を京都の街におびき寄せ、街に火を放てば、敵は大軍だから狭い京都の街路を迅速に動けず、炎に包まれるだろうというゲリラ戦を主張した。だが後醍醐天皇は、政治家として民を苦しめるわけにはいかぬから、敵を京に入れず、もっと西で迎撃せよと命じる。両者とも、勝つことだけを求めているわけではない。楠正成は、負けるとわかっている戦いに、裏切ることもせず慫慂として従う。日本人は勝つことにではなく、義に殉じる無私の精神に、心打たれるのだ。
日本人が重視するのは、成果よりむしろ真面目さ・純粋さである。だから仕事でミスをしたとき、すぐに謝罪することで、迷惑をかけた非を認める純粋さが求められるのではないだろうか。
(3) 日本人の失笑を買ったアメリカ版「フランダースの犬」
イギリスの作家ウィーダの小説「フランダースの犬」は、イギリスでもベルギーでも全く評価されなかった。画家志望の少年ネロがみなしごとなり、わずかに残ったお金で食料ではなく絵の具を買い、展覧会入選を夢見て破れ、憧れのルーベンスの絵の前で凍死する物語である。ウィーダは彼女自身が売れない作家で、理想に殉じるネロの姿を通して、自身の高い理想を謳いあげたものと思われるが、そのようなストイシズムはヨーロッパ人には評価されなかったようだ。
これがアメリカ映画になると、「子供が何の助けもなく死んでいく物語には意味がない」として、凍死寸前のネロのもとに父親が迎えに来るというラストシーンを描き、多くの日本人観客をずっこけさせた。日本人ファンは、ネロが放火の疑いをかけられても誰も恨むことなく、運命を受け容れる姿に心打たれたのだから、それを全否定し、努力は報われなければならない、必ず成功しなければならないとして原作を歪曲した結末に、非常な違和感を抱いたのだ。
武蔵野大学の高橋晃教授は、アンデルセンの童話「人魚姫」と「マッチ売りの少女」が、アメリカのバージョンにおいてハッピー・エンドに改変されていたことを発見した。
|
|
|
|
コメント(4)
謝ることが、美徳だからです。
そうやって教えこまれてきたから。
アクシデントがあったとき、
明らかに「相手が悪い」と自覚していて、
「てめえ、どうしてくれんだよ!」ってときは謝ったりはしません。
ただ、事態を正確に把握できていない「不慮のアクシデント」の場合、
自分にも落ち度があったのではないか?
と考えるように、教えられています。
それは、
「謝ったほうが円滑に進む」
「謝ったほうが、相手も自分の罪を認めやすい」
という極めて日本的な感覚によるものです。
「まず一言、謝ってから」落ち着いて話そうと。
だから、状態が見えない時の「謝まる行為」は、
「お互い冷静に、ことを荒立てないでいきましょう」
という呼びかけです。
そしてそれができるのが、日本では大人なのです。
また、黒を白と言い募ったり、
自分の罪を認めないのは、恥です。
潔いとはいえません。
もちろん、今の、特に戦後の団塊の世代以降の日本人は、
打算的要素で「まず謝っちまえ」というのが多く、卑屈であることは否めませんが。
そうやって教えこまれてきたから。
アクシデントがあったとき、
明らかに「相手が悪い」と自覚していて、
「てめえ、どうしてくれんだよ!」ってときは謝ったりはしません。
ただ、事態を正確に把握できていない「不慮のアクシデント」の場合、
自分にも落ち度があったのではないか?
と考えるように、教えられています。
それは、
「謝ったほうが円滑に進む」
「謝ったほうが、相手も自分の罪を認めやすい」
という極めて日本的な感覚によるものです。
「まず一言、謝ってから」落ち着いて話そうと。
だから、状態が見えない時の「謝まる行為」は、
「お互い冷静に、ことを荒立てないでいきましょう」
という呼びかけです。
そしてそれができるのが、日本では大人なのです。
また、黒を白と言い募ったり、
自分の罪を認めないのは、恥です。
潔いとはいえません。
もちろん、今の、特に戦後の団塊の世代以降の日本人は、
打算的要素で「まず謝っちまえ」というのが多く、卑屈であることは否めませんが。
●なぜ日本人選手は謝るのか? 社会学者の論考『選手はもはや「個人」ではない』にみる責任と呪縛
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180215-00010004-victory-spo
熱戦が繰り広げられている平昌オリンピック。メダルの期待がかかる日本人選手が続々と登場してくるなか、気に掛かるのは、その期待通りの結果を出せなかったときだ。これまでオリンピックなどのビッグイベントではしばしば、日本人選手がテレビの向こうにいるファンに向けて、涙ながらに謝る姿を目にしてきた。なぜ日本人選手は“謝る”のだろうか? スポーツの勝敗は誰のものなのだろうか? 平昌オリンピックが開催中で、東京オリンピックを2年後に控えている今だからこそ、あらためて考えてみたい。
★期待通りの結果を残せなかったとき、ファンに対して謝るべきなのか?
日本の選手はお詫びの言葉をよく口にするような気がする。期待通りの結果を出せなかったとき、チームの足を引っ張るようなプレーをしてしまったときに「申し訳ない」と言う。
私がそんなことを感じたのは、2016年リオデジャネイロのオリンピック・パラリンピックの頃だった。米NBC局が映し出す米国選手は、負けたときでもあまり謝らず、サポートしてくれた周囲、応援してくれたファンに感謝の言葉を述べていた。それと比較すると、日本の選手はよく謝っていた。これは文化の違いから来るものだから、どちらが良くて、どちらが悪い、という種類のものではない。何かをしてはいけない理由を教えるとき、キリスト教文化圏では「神の命令だから」、日本文化圏では「他人に迷惑を掛けるから」とされることが多いことも影響しているだろう。
それでも、日本の選手が、記者会見で「申し訳ない」と絞り出すのを聞くと、私は心苦しい気持ちになる。スタッフやチームメイトら身近な人に謝りたいと思うのは、当たり前のことかもしれないが、テレビ画面の向こうにいる人たちにも謝らなければならないのか。不祥事の会見でもないのに。
結果を出せなかった選手がお詫びするのには、それぞれの事情があるだろうが、ここでは、私なりの考えを綴ってみたい。
★報酬系を活性化させるマスメディアの報道
選手たちは、期待に応えられなかったことを申し訳なく感じているようだ。各競技団体、指導者ら、選手を直接的にサポートしている人からの期待がある。オリンピック・パラリンピック級の大きなスポーツイベントになれば、世間からの期待も膨らむ。
世間からの期待に少なからぬ影響を及ぼしているのが、マスメディアだ。マスメディアは選手への期待を煽りがちだ。
人の脳には報酬系というドーパミン神経系がある。報酬系は「心地よい」という感覚を生むための装置だ。例えば、喉が渇いている人が水を飲むと、報酬系は活性化する。実際に水を飲んだときだけでなく、もうすぐ水を飲むことができると想像するだけでも活性化するそうだ。人間は報酬系がゴーザインを出した行動を選ぶようになっているという。
これをスポーツ報道に当てはめてみる。これから始まる大会で、日本の選手はメダルを獲得できるかもしれない、と期待を込めた文脈で報じる。視聴者、読者は、応援する選手の活躍を想像するだけで、報酬系が活性化されるのではないか。胸躍る瞬間を逃したくないと思い、中継や記事を求めるのではないだろうか。マスメディアは、できるだけ多くの人に試合中継を視聴してもらう、記事を読んでもらうことでビジネスが成り立っている。だから、無意識的であれ、意識的であれ、期待させるような報道になっている。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180215-00010004-victory-spo
熱戦が繰り広げられている平昌オリンピック。メダルの期待がかかる日本人選手が続々と登場してくるなか、気に掛かるのは、その期待通りの結果を出せなかったときだ。これまでオリンピックなどのビッグイベントではしばしば、日本人選手がテレビの向こうにいるファンに向けて、涙ながらに謝る姿を目にしてきた。なぜ日本人選手は“謝る”のだろうか? スポーツの勝敗は誰のものなのだろうか? 平昌オリンピックが開催中で、東京オリンピックを2年後に控えている今だからこそ、あらためて考えてみたい。
★期待通りの結果を残せなかったとき、ファンに対して謝るべきなのか?
日本の選手はお詫びの言葉をよく口にするような気がする。期待通りの結果を出せなかったとき、チームの足を引っ張るようなプレーをしてしまったときに「申し訳ない」と言う。
私がそんなことを感じたのは、2016年リオデジャネイロのオリンピック・パラリンピックの頃だった。米NBC局が映し出す米国選手は、負けたときでもあまり謝らず、サポートしてくれた周囲、応援してくれたファンに感謝の言葉を述べていた。それと比較すると、日本の選手はよく謝っていた。これは文化の違いから来るものだから、どちらが良くて、どちらが悪い、という種類のものではない。何かをしてはいけない理由を教えるとき、キリスト教文化圏では「神の命令だから」、日本文化圏では「他人に迷惑を掛けるから」とされることが多いことも影響しているだろう。
それでも、日本の選手が、記者会見で「申し訳ない」と絞り出すのを聞くと、私は心苦しい気持ちになる。スタッフやチームメイトら身近な人に謝りたいと思うのは、当たり前のことかもしれないが、テレビ画面の向こうにいる人たちにも謝らなければならないのか。不祥事の会見でもないのに。
結果を出せなかった選手がお詫びするのには、それぞれの事情があるだろうが、ここでは、私なりの考えを綴ってみたい。
★報酬系を活性化させるマスメディアの報道
選手たちは、期待に応えられなかったことを申し訳なく感じているようだ。各競技団体、指導者ら、選手を直接的にサポートしている人からの期待がある。オリンピック・パラリンピック級の大きなスポーツイベントになれば、世間からの期待も膨らむ。
世間からの期待に少なからぬ影響を及ぼしているのが、マスメディアだ。マスメディアは選手への期待を煽りがちだ。
人の脳には報酬系というドーパミン神経系がある。報酬系は「心地よい」という感覚を生むための装置だ。例えば、喉が渇いている人が水を飲むと、報酬系は活性化する。実際に水を飲んだときだけでなく、もうすぐ水を飲むことができると想像するだけでも活性化するそうだ。人間は報酬系がゴーザインを出した行動を選ぶようになっているという。
これをスポーツ報道に当てはめてみる。これから始まる大会で、日本の選手はメダルを獲得できるかもしれない、と期待を込めた文脈で報じる。視聴者、読者は、応援する選手の活躍を想像するだけで、報酬系が活性化されるのではないか。胸躍る瞬間を逃したくないと思い、中継や記事を求めるのではないだろうか。マスメディアは、できるだけ多くの人に試合中継を視聴してもらう、記事を読んでもらうことでビジネスが成り立っている。だから、無意識的であれ、意識的であれ、期待させるような報道になっている。
★敗戦の原因の追求から自らを守る
しかし、見ている人は、期待していた通りのことが起こらなかった場合には、期待していた分だけ、落胆や欲求不満を感じてしまう。期待外れのがっかりした気分から抜け出したいと思う。そのためには、納得できる敗戦の理由や文脈を必要とするようになる。
スポーツにかかわらず、何かうまくいかなかったときに、「なぜこうなったのか」と考える。たいていの人は、うまくいっているときには、「なぜうまくいったのか」を自問することは少ないだろう。
スポーツ報道でも似たようなところがある。選手が勝ったり記録を達成した瞬間には、その理由を報じるケースももちろんあるが、どちらかといえばそれがどれほど価値のあることなのかを強調する傾向が強いようにみえる。例えば、『〇〇種目では日本初の金メダル!』、『史上〇人目の記録達成!』などという表現だ。負けたときには、対戦相手や気候、審判などの外的要因、選手自身の内的要因を挙げ、説明を加えながらソフトランディングさせることが多いように感じる。
しかし、このようなメディアの手法は日本だけでなく、米国でも同じようなもの。スポーツ報道に力を入れている国や地域なら、どこも似たり寄ったりのスタイルだろう。
日本の選手は、負けた原因の追及から身を守ろうとして、他人に求められる前に、自分で自分を罰し、それを世間に知らせているのではないか。米国の選手は、感謝の言葉や対戦相手の強さを称えることで、原因の追究から自分のメンツを守ろうとしているのかもしれない。
★『勝敗は背後の集団の実力の程度を象徴する』社会学者の論考
日本の社会学者、作田啓一は1965年9月に『高校野球と精神主義』という論考を発表している。タイトルの通り、当時の高校野球について書かれたものだ。また文末には、前回の東京オリンピックを控えた1964年7月に書いたものだという但し書きがあるように、オリンピックを意識して執筆されたものでもある。
「球児が試合に負けた後、泣いていた。負けて泣くのは高校生選手が純真だからに違いないが、泣くほどに勝利を希求させる大人たちの圧力を思うと、その純真さに素直に同情する気持ちになれない」(出典:『高校野球と精神主義』(作田啓一))
と、作田は述べている。
そして、このように続く。
「日本の社会では、個人は集団を、集団はもっと大きい集団を代表する仕組みになっている。大はオリンピックから小は高校野球に至るまで、人は国家のために、母校は郷土の栄誉のために、どうしても勝たなければならない。私たちはいつも、家族や職場や組合の代表者としての責任を重く背負ってよろめいている」(出典:『高校野球と精神主義』(作田啓一))
オリンピックやパラリンピックに出場する選手たちは、代表の座を勝ち取った喜びよりも、選ばれた責任の重さに苦しんでいるのかもしれない。
さらに作田は、
「集団的なものは宗教的『聖』の範疇に属し、個人的なものは日常的『俗』の範疇に属するとすれば、私たち日本人が集団の代表として行動するとき、私たちはいわば宗教的な営みを行っているのである。郷土や母校や後援会の期待を担って甲子園に出場する選手たちはもはや『個人』ではない。彼らは集団の繁栄を儀礼的に演出する司祭である。チームの勝敗は背後の集団の実力の程度を象徴するから、絶対に負けてはならない」(出典:『高校野球と精神主義』(作田啓一))
としている。
50年以上前の日本に比べて、個人を縛る程度は弱まってきている。とはいえ、選手たちは今も、代表になれば「個人」ではなくなり、所属する集団や国家の象徴であるために、「負けてはいけない」という重圧を背負っているのだろう。司祭として任務を遂行できなかった自分を自分で罰し、詫びるのかもしれない。
人々が、オリンピックやパラリンピックで、代表選手を応援するのは、同じ国の選手という気持ちの結びつきがあるからだ。自分の国の選手に期待するのは、日本に限らず、どこの国でもそうだろう。ただ、周囲の期待と結果が一致しなかったからといって、自罰的になってほしくはない。選手の好パフォーマンスや好成績は、応援する者の喜びである。けれど、日本という国のすばらしさを象徴するために、どうしても勝たなければという重圧を背負ってほしくはない。責任や呪縛から心身を解放してパフォーマンスしてほしい。
負けた選手たちの「申し訳ない」という言葉を聞くとき、聞いているこちらも選手に対して申し訳ないような気持ちになってくる。私も日本人だからなのだろう。
(文=谷口輝世子)
しかし、見ている人は、期待していた通りのことが起こらなかった場合には、期待していた分だけ、落胆や欲求不満を感じてしまう。期待外れのがっかりした気分から抜け出したいと思う。そのためには、納得できる敗戦の理由や文脈を必要とするようになる。
スポーツにかかわらず、何かうまくいかなかったときに、「なぜこうなったのか」と考える。たいていの人は、うまくいっているときには、「なぜうまくいったのか」を自問することは少ないだろう。
スポーツ報道でも似たようなところがある。選手が勝ったり記録を達成した瞬間には、その理由を報じるケースももちろんあるが、どちらかといえばそれがどれほど価値のあることなのかを強調する傾向が強いようにみえる。例えば、『〇〇種目では日本初の金メダル!』、『史上〇人目の記録達成!』などという表現だ。負けたときには、対戦相手や気候、審判などの外的要因、選手自身の内的要因を挙げ、説明を加えながらソフトランディングさせることが多いように感じる。
しかし、このようなメディアの手法は日本だけでなく、米国でも同じようなもの。スポーツ報道に力を入れている国や地域なら、どこも似たり寄ったりのスタイルだろう。
日本の選手は、負けた原因の追及から身を守ろうとして、他人に求められる前に、自分で自分を罰し、それを世間に知らせているのではないか。米国の選手は、感謝の言葉や対戦相手の強さを称えることで、原因の追究から自分のメンツを守ろうとしているのかもしれない。
★『勝敗は背後の集団の実力の程度を象徴する』社会学者の論考
日本の社会学者、作田啓一は1965年9月に『高校野球と精神主義』という論考を発表している。タイトルの通り、当時の高校野球について書かれたものだ。また文末には、前回の東京オリンピックを控えた1964年7月に書いたものだという但し書きがあるように、オリンピックを意識して執筆されたものでもある。
「球児が試合に負けた後、泣いていた。負けて泣くのは高校生選手が純真だからに違いないが、泣くほどに勝利を希求させる大人たちの圧力を思うと、その純真さに素直に同情する気持ちになれない」(出典:『高校野球と精神主義』(作田啓一))
と、作田は述べている。
そして、このように続く。
「日本の社会では、個人は集団を、集団はもっと大きい集団を代表する仕組みになっている。大はオリンピックから小は高校野球に至るまで、人は国家のために、母校は郷土の栄誉のために、どうしても勝たなければならない。私たちはいつも、家族や職場や組合の代表者としての責任を重く背負ってよろめいている」(出典:『高校野球と精神主義』(作田啓一))
オリンピックやパラリンピックに出場する選手たちは、代表の座を勝ち取った喜びよりも、選ばれた責任の重さに苦しんでいるのかもしれない。
さらに作田は、
「集団的なものは宗教的『聖』の範疇に属し、個人的なものは日常的『俗』の範疇に属するとすれば、私たち日本人が集団の代表として行動するとき、私たちはいわば宗教的な営みを行っているのである。郷土や母校や後援会の期待を担って甲子園に出場する選手たちはもはや『個人』ではない。彼らは集団の繁栄を儀礼的に演出する司祭である。チームの勝敗は背後の集団の実力の程度を象徴するから、絶対に負けてはならない」(出典:『高校野球と精神主義』(作田啓一))
としている。
50年以上前の日本に比べて、個人を縛る程度は弱まってきている。とはいえ、選手たちは今も、代表になれば「個人」ではなくなり、所属する集団や国家の象徴であるために、「負けてはいけない」という重圧を背負っているのだろう。司祭として任務を遂行できなかった自分を自分で罰し、詫びるのかもしれない。
人々が、オリンピックやパラリンピックで、代表選手を応援するのは、同じ国の選手という気持ちの結びつきがあるからだ。自分の国の選手に期待するのは、日本に限らず、どこの国でもそうだろう。ただ、周囲の期待と結果が一致しなかったからといって、自罰的になってほしくはない。選手の好パフォーマンスや好成績は、応援する者の喜びである。けれど、日本という国のすばらしさを象徴するために、どうしても勝たなければという重圧を背負ってほしくはない。責任や呪縛から心身を解放してパフォーマンスしてほしい。
負けた選手たちの「申し訳ない」という言葉を聞くとき、聞いているこちらも選手に対して申し訳ないような気持ちになってくる。私も日本人だからなのだろう。
(文=谷口輝世子)
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ここが変だよ比較文化論 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-