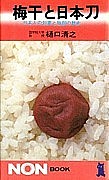(1) 梅棹の「生態史観」
梅棹忠夫著「文明の生態史観」を読んだ。中央アジアを旅した梅棹は、中央アジアは東洋とも西洋とも異なり、また「オリエント」と東洋も明らかに異なるもので、従来から言われてきた「東洋と西洋」の二分法はそぐわないと考えた。そこで彼は、ユーラシア大陸を外辺部と中央部に二分し、前者を「第一地域」後者を「第二地域」として、後者を東洋でも西洋でもない「中洋」と呼んだ。
梅棹によると、第二地域は乾燥地帯とその周辺である。乾燥地帯の民族は、食糧が不足するとその周辺地帯に侵入し略奪を周期的に繰り返した。王朝が建てられ、社会が成熟すると、異民族が侵入してこれを打倒し、また新しい王朝を建てる「繰り返しの歴史」だった。餓鬼が石を積むと鬼が来て崩し、また一から積み始めるという「賽の河原の歴史」である。
これに対し第一地域は、海に面しているため気候は穏やかで、農耕に適しているだけではなく、大陸の外辺部のため異民族の侵入をほとんど経験しなかった。王朝が建てられ、社会が成熟すると、封建社会が成立し、そこから武士道や騎士道のような公共精神が形成され、それがやがて資本主義・市民社会へとつながっていく「積み重ねの歴史」だった。
第一地域は、西欧と日本である。第二地域は、その位置と気候により?区・?区・?区・?区に分けられ、それぞれ中国、インド、ロシア、中東を表す。第二地域には強権的な中央集権国家が形成され、近世ではそれぞれが清帝国、ムガール帝国、ロシア帝国、オスマン帝国の四大帝国に該当したが、すべて20世紀にほろんだ。
梅棹は、第二地域は異民族侵入の歴史から、その文化は「アロジェニック・サクセッション(外からの影響による発展)」になるのに対し、第一地域の文化は「オートジェニック・サクセッション(自発的発展)」になると説明した。
このような梅棹の世界観は、従来から日本人論で言われてきた「日本人は農耕民族、欧米人は狩猟民族」「欧米人は契約精神、日本人は義理人情」「欧米人は大陸根性、日本人は島国根性」「ヨーロッパは他国に侵略されたことがあるが日本はない」「欧米の文化は自作の文化、日本の文化は欧米の模倣」などの、「日本対欧米」の二項対立論とは対照的に、両者の共通性を述べて同一地域に分類する極めて斬新なものである。このような独創的な論説が、1957年にすでに発表されていたことにも驚くが、彼の世界観はその後の日本人論に踏襲されていない。その理由はやはりハルミ・ベフが述べるように、日本人は欧米人からどう見られているかにしか興味がないため、あくまでも欧米との対比でしか論じようとしないからだろう。両者を同じ次元で比較すると優劣がついてしまうため、日本人論はそれを避けるべく、日本と欧米を異質で互いに理解不能なものと定義することが多い。
(2) 世界の封建制
確かに武士道と騎士道には、忠誠心と公共心を重んじるなどの共通点がある。だが騎士道が契約によって結ばれたドライな関係であるのに対し、武士道は地縁・血縁で結ばれた関係であることや、ヨーロッパの封建制は農民を奴隷同然に所有したが、日本の封建制は徴税権があるにすぎなかったなどの相違点もある。
梅棹は、封建制は日本と西欧にしか出現せず、したがって武士道・騎士道精神は日本と西欧特有のものだとしたが、現在の学術水準では疑問視されている。日本や西欧の封建制に類似した、土地を介した分権支配体制にはイスラムのイクター制、オスマン帝国のティマール制、ビザンツ帝国のプロノイア制などがある。そもそも西欧封建制と日本封建制の間にも相違点があり、何をもって「封建制」とするかは、分類の手法・言葉の定義の問題にすぎないとする見方が主流になりつつある。
また梅棹の世界観は、アフリカ・アメリカ・オセアニアについて説明していない。また第一地域では封建制が忠誠心と公共心を育み、それが勤勉の精神につながり産業革命の原動力になったとしているが、日本の産業革命は自発的発展ではなく、欧米技術を導入した結果である。梅棹の世界観は全体的に、日本一国を西欧全体と対比するなど、日本を過大に評価しているという批判がある。
梅棹の説は、独創的すぎて後継者が現れなかったが、歴史学に生態地理学の観点を導入する手法は、ジャレド・ダイヤモンドなどに引き継がれた。
(3) 歴史を地政学的に見る
封建制が成立するためには、いくつかの条件がある。(1)中央政権が強大でなく地方領主が自立していること、(2)文官ではなく武官が実力をもっていること、(3)遊牧生活ではなく定住し農民が農地に依存していること、(4)職業の世襲による固定、(5)貨幣経済が未発達であること、である。
(1)は、地方が無秩序となり、弱い領主は強い領主の庇護下に入らなければならない。こうして領主が階層を成し、最下層の農民から搾取する体制ができる。(2)は、文官ではなく武官が荘園を経営する軍事政権でなければならない。(3)は、土地本位制が成立するためには、農民が土地に縛られていなければならない。(4)は、領主が農民から搾取し続けるためには職業が固定化されていなければならない。(5)は、貨幣経済が発達すると金が金を生むようになり、資本主義となるので、土地本位制を維持するためには物々交換が行われ、納税も物納が望ましい。
中国では周の時代に封建制が成立したが、後に始皇帝に統一され、以後中央集権制が続いた。地方を治めていたのは中央から派遣された役人であり、文官による統治が定着した。中華平原には山地がないので、中国の為政者は広大な領域を統一して統治できたのだろう。
これがヨーロッパになると、ローマ帝国が分裂した後、ついに統一国家は現れなかった。ヨーロッパは狭い地域に、小さい国々がひしめき合っている。その理由は、ヨーロッパは中央にアルプス山脈があるほか、半島や島が多く、どうしても文化的にいくつかの地域に分かれてしまうのである。そして山や海や、半島が大陸と接する隘路は、絶好の防衛拠点となる。
日本の場合も、本州中央部には険しい山脈があり、全国的に山がちで広い平野に乏しい。街道を10キロ進むごとに、山地がせり出した隘路があり、それらにいちいち城がある。侵略者は10キロ進むごとにいちいち城を落とさねばならず、わずかの距離を進軍するにも時間がかかったことだろう。実際古戦場を見てみると、ヨーロッパでは開けた平原が多いが、日本はたいてい山や川に挟まれた隘路である。日本の武士団がヨーロッパのような密集隊形をとらなかった理由も、これで説明できる。
梅棹の言う第二地域では、中央集権国家が衰えて地方軍閥政権が分立しても、再度統一され中央政権国家が成立するというサイクルを繰り返した。中国や中東が近代化できなかったのは、政治権力が王侯貴族から民衆に移らなかったからである。近代化を実現するためには資本主義を経験していなければならず、資本主義を達成する前には十分な期間の地方分権制を経験する必要がある。資本主義には競争原理が必要だからである。明治維新の直前には、日本には多くの藩があり、互いに政治の主導権を巡って牽制し合い、また競って藩士を留学させた。ヨーロッパが近代の覇者となれたのは、競争があったからであり、中世の覇者である中国・中東が没落したのは、統一中央集権国家のため競争がなかったからというのが、筆者の見解である。
梅棹忠夫著「文明の生態史観」を読んだ。中央アジアを旅した梅棹は、中央アジアは東洋とも西洋とも異なり、また「オリエント」と東洋も明らかに異なるもので、従来から言われてきた「東洋と西洋」の二分法はそぐわないと考えた。そこで彼は、ユーラシア大陸を外辺部と中央部に二分し、前者を「第一地域」後者を「第二地域」として、後者を東洋でも西洋でもない「中洋」と呼んだ。
梅棹によると、第二地域は乾燥地帯とその周辺である。乾燥地帯の民族は、食糧が不足するとその周辺地帯に侵入し略奪を周期的に繰り返した。王朝が建てられ、社会が成熟すると、異民族が侵入してこれを打倒し、また新しい王朝を建てる「繰り返しの歴史」だった。餓鬼が石を積むと鬼が来て崩し、また一から積み始めるという「賽の河原の歴史」である。
これに対し第一地域は、海に面しているため気候は穏やかで、農耕に適しているだけではなく、大陸の外辺部のため異民族の侵入をほとんど経験しなかった。王朝が建てられ、社会が成熟すると、封建社会が成立し、そこから武士道や騎士道のような公共精神が形成され、それがやがて資本主義・市民社会へとつながっていく「積み重ねの歴史」だった。
第一地域は、西欧と日本である。第二地域は、その位置と気候により?区・?区・?区・?区に分けられ、それぞれ中国、インド、ロシア、中東を表す。第二地域には強権的な中央集権国家が形成され、近世ではそれぞれが清帝国、ムガール帝国、ロシア帝国、オスマン帝国の四大帝国に該当したが、すべて20世紀にほろんだ。
梅棹は、第二地域は異民族侵入の歴史から、その文化は「アロジェニック・サクセッション(外からの影響による発展)」になるのに対し、第一地域の文化は「オートジェニック・サクセッション(自発的発展)」になると説明した。
このような梅棹の世界観は、従来から日本人論で言われてきた「日本人は農耕民族、欧米人は狩猟民族」「欧米人は契約精神、日本人は義理人情」「欧米人は大陸根性、日本人は島国根性」「ヨーロッパは他国に侵略されたことがあるが日本はない」「欧米の文化は自作の文化、日本の文化は欧米の模倣」などの、「日本対欧米」の二項対立論とは対照的に、両者の共通性を述べて同一地域に分類する極めて斬新なものである。このような独創的な論説が、1957年にすでに発表されていたことにも驚くが、彼の世界観はその後の日本人論に踏襲されていない。その理由はやはりハルミ・ベフが述べるように、日本人は欧米人からどう見られているかにしか興味がないため、あくまでも欧米との対比でしか論じようとしないからだろう。両者を同じ次元で比較すると優劣がついてしまうため、日本人論はそれを避けるべく、日本と欧米を異質で互いに理解不能なものと定義することが多い。
(2) 世界の封建制
確かに武士道と騎士道には、忠誠心と公共心を重んじるなどの共通点がある。だが騎士道が契約によって結ばれたドライな関係であるのに対し、武士道は地縁・血縁で結ばれた関係であることや、ヨーロッパの封建制は農民を奴隷同然に所有したが、日本の封建制は徴税権があるにすぎなかったなどの相違点もある。
梅棹は、封建制は日本と西欧にしか出現せず、したがって武士道・騎士道精神は日本と西欧特有のものだとしたが、現在の学術水準では疑問視されている。日本や西欧の封建制に類似した、土地を介した分権支配体制にはイスラムのイクター制、オスマン帝国のティマール制、ビザンツ帝国のプロノイア制などがある。そもそも西欧封建制と日本封建制の間にも相違点があり、何をもって「封建制」とするかは、分類の手法・言葉の定義の問題にすぎないとする見方が主流になりつつある。
また梅棹の世界観は、アフリカ・アメリカ・オセアニアについて説明していない。また第一地域では封建制が忠誠心と公共心を育み、それが勤勉の精神につながり産業革命の原動力になったとしているが、日本の産業革命は自発的発展ではなく、欧米技術を導入した結果である。梅棹の世界観は全体的に、日本一国を西欧全体と対比するなど、日本を過大に評価しているという批判がある。
梅棹の説は、独創的すぎて後継者が現れなかったが、歴史学に生態地理学の観点を導入する手法は、ジャレド・ダイヤモンドなどに引き継がれた。
(3) 歴史を地政学的に見る
封建制が成立するためには、いくつかの条件がある。(1)中央政権が強大でなく地方領主が自立していること、(2)文官ではなく武官が実力をもっていること、(3)遊牧生活ではなく定住し農民が農地に依存していること、(4)職業の世襲による固定、(5)貨幣経済が未発達であること、である。
(1)は、地方が無秩序となり、弱い領主は強い領主の庇護下に入らなければならない。こうして領主が階層を成し、最下層の農民から搾取する体制ができる。(2)は、文官ではなく武官が荘園を経営する軍事政権でなければならない。(3)は、土地本位制が成立するためには、農民が土地に縛られていなければならない。(4)は、領主が農民から搾取し続けるためには職業が固定化されていなければならない。(5)は、貨幣経済が発達すると金が金を生むようになり、資本主義となるので、土地本位制を維持するためには物々交換が行われ、納税も物納が望ましい。
中国では周の時代に封建制が成立したが、後に始皇帝に統一され、以後中央集権制が続いた。地方を治めていたのは中央から派遣された役人であり、文官による統治が定着した。中華平原には山地がないので、中国の為政者は広大な領域を統一して統治できたのだろう。
これがヨーロッパになると、ローマ帝国が分裂した後、ついに統一国家は現れなかった。ヨーロッパは狭い地域に、小さい国々がひしめき合っている。その理由は、ヨーロッパは中央にアルプス山脈があるほか、半島や島が多く、どうしても文化的にいくつかの地域に分かれてしまうのである。そして山や海や、半島が大陸と接する隘路は、絶好の防衛拠点となる。
日本の場合も、本州中央部には険しい山脈があり、全国的に山がちで広い平野に乏しい。街道を10キロ進むごとに、山地がせり出した隘路があり、それらにいちいち城がある。侵略者は10キロ進むごとにいちいち城を落とさねばならず、わずかの距離を進軍するにも時間がかかったことだろう。実際古戦場を見てみると、ヨーロッパでは開けた平原が多いが、日本はたいてい山や川に挟まれた隘路である。日本の武士団がヨーロッパのような密集隊形をとらなかった理由も、これで説明できる。
梅棹の言う第二地域では、中央集権国家が衰えて地方軍閥政権が分立しても、再度統一され中央政権国家が成立するというサイクルを繰り返した。中国や中東が近代化できなかったのは、政治権力が王侯貴族から民衆に移らなかったからである。近代化を実現するためには資本主義を経験していなければならず、資本主義を達成する前には十分な期間の地方分権制を経験する必要がある。資本主義には競争原理が必要だからである。明治維新の直前には、日本には多くの藩があり、互いに政治の主導権を巡って牽制し合い、また競って藩士を留学させた。ヨーロッパが近代の覇者となれたのは、競争があったからであり、中世の覇者である中国・中東が没落したのは、統一中央集権国家のため競争がなかったからというのが、筆者の見解である。
|
|
|
|
|
|
|
|
ここが変だよ比較文化論 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
ここが変だよ比較文化論のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90027人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6407人
- 3位
- 独り言
- 9045人