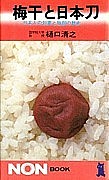過度の受験競争は、韓国などアジアで広く見られるもので、日本だけではない。これとは別に、学歴偏重主義ならフランスなどにもあるのだが、日本の受験偏重主義は、入学資格を手に入れるための競争は過激だが、いったん入ってしまえば出ることについては競争が極度にゆるいため、入学した大学生が勉強しないという問題がある。
大学は研究の場だが、入学する資質は一般教養のレベルで問われるため、日本人にとっての勉強とは事実関係を端的に問うものだと考えられており、学問に真に必要な資質である思考力、分析力、判断力、創造性はどの過程においても問われていない。
mixiなどの掲示板で議論していても、議論のルールも知らない人がいて、これでどうやって論文書いて学位を取ったのだろうと疑いたくなる人がいる。有体に申せば、日本の大学生はカナダの大学生に比べ、明らかに見劣りする。
「日本は学歴主義で北米は実力主義」だと思いこんでいる人がいるが、考えようではカナダの方が厳格な学歴主義だとも言える。「マクリーンズ」などが大学の格付けをしているが、それは学部・学科ごとに格付けをしているわけで、日本のように全ての学部・学科が東大を頂点としたヒエラルキーになっているわけではなく、学部・学科ごとにランキングが異なる。ある大学は経営学に秀で、ある大学は会計学に秀でているということなので、企業は人を募集するとき、学校名を指定するだけではなく学部・学科まで指定する。「ウチはA大学経済学部、B大学経営学部、C大学商学部以外採用しません」と言うのである。そこでいくら「私は名門トロント大学の文学部を出ているのだ」などと言っても通用しない。カナダの企業で必要なのはスキルであって、学歴ではないからだ。大学も出ていない人は論外である。もしも日本の留学エージェントが「英語が上達すればいい仕事にありつけますよ」と言っていたら、その人は詐欺師である。英語ができるだけでいい仕事にありつけるなら、どうして平日の昼間から多くの若者が物乞いをしているのだろうか。北米の大学を出ていなければ、いい仕事など絶対にない。
日本にも指定校制度はあるが、そこで指定されているのは大学名だけで、学部・学科までは指定されない。銀行に入社する場合でも、大学名は気にするが専門は経済学部でなくても、文学部でもいいのである。
日本では仕事は入社してから教えるので、スキルは問題にされない。真面目に働くことをアピールしさえすればよいのだ。ことによると、同業他社から来た人でも「うちで働くからには、よそのやり方は忘れて下さい」などと言われかねない。こうなるとむしろ、経験ない人の方が教えやすいのではないかとすら思える。
そうなると採用時に問題にされるのは学校名(学歴)であって、専攻科目や能力そのものではない。偏差値が日本でのみ重んじられるのは、日本人が一般教養主義でスペシャリスト志向でないからであり、カナダに比べある意味ぬるいとも言える。彼らが気にするのはスキルではなく人格や一般教養であり、そこでは同性愛者・左翼運動家・少数民族などは厳しく選別されることになる。日本人にとって学歴主義・偏差値主義の厳しさは、カナダとは違った次元にあるのである。
大学は研究の場だが、入学する資質は一般教養のレベルで問われるため、日本人にとっての勉強とは事実関係を端的に問うものだと考えられており、学問に真に必要な資質である思考力、分析力、判断力、創造性はどの過程においても問われていない。
mixiなどの掲示板で議論していても、議論のルールも知らない人がいて、これでどうやって論文書いて学位を取ったのだろうと疑いたくなる人がいる。有体に申せば、日本の大学生はカナダの大学生に比べ、明らかに見劣りする。
「日本は学歴主義で北米は実力主義」だと思いこんでいる人がいるが、考えようではカナダの方が厳格な学歴主義だとも言える。「マクリーンズ」などが大学の格付けをしているが、それは学部・学科ごとに格付けをしているわけで、日本のように全ての学部・学科が東大を頂点としたヒエラルキーになっているわけではなく、学部・学科ごとにランキングが異なる。ある大学は経営学に秀で、ある大学は会計学に秀でているということなので、企業は人を募集するとき、学校名を指定するだけではなく学部・学科まで指定する。「ウチはA大学経済学部、B大学経営学部、C大学商学部以外採用しません」と言うのである。そこでいくら「私は名門トロント大学の文学部を出ているのだ」などと言っても通用しない。カナダの企業で必要なのはスキルであって、学歴ではないからだ。大学も出ていない人は論外である。もしも日本の留学エージェントが「英語が上達すればいい仕事にありつけますよ」と言っていたら、その人は詐欺師である。英語ができるだけでいい仕事にありつけるなら、どうして平日の昼間から多くの若者が物乞いをしているのだろうか。北米の大学を出ていなければ、いい仕事など絶対にない。
日本にも指定校制度はあるが、そこで指定されているのは大学名だけで、学部・学科までは指定されない。銀行に入社する場合でも、大学名は気にするが専門は経済学部でなくても、文学部でもいいのである。
日本では仕事は入社してから教えるので、スキルは問題にされない。真面目に働くことをアピールしさえすればよいのだ。ことによると、同業他社から来た人でも「うちで働くからには、よそのやり方は忘れて下さい」などと言われかねない。こうなるとむしろ、経験ない人の方が教えやすいのではないかとすら思える。
そうなると採用時に問題にされるのは学校名(学歴)であって、専攻科目や能力そのものではない。偏差値が日本でのみ重んじられるのは、日本人が一般教養主義でスペシャリスト志向でないからであり、カナダに比べある意味ぬるいとも言える。彼らが気にするのはスキルではなく人格や一般教養であり、そこでは同性愛者・左翼運動家・少数民族などは厳しく選別されることになる。日本人にとって学歴主義・偏差値主義の厳しさは、カナダとは違った次元にあるのである。
|
|
|
|
コメント(19)
オーストラリアはコネ社会だそうです。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=263214&page=1&id=4686064
似たような意見は、カナダでも聞きます。
http://bbs.jpcanada.com/log/16/8458.html
http://bbs.jpcanada.com/log/12/260.html
http://bbs.jpcanada.com/log/9/3385.html
http://bbs.jpcanada.com/log/11/2495.html
http://bbs.jpcanada.com/log/5/1219.html
最後のリンクは、読んでいて辛くなります。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=263214&page=1&id=4686064
似たような意見は、カナダでも聞きます。
http://bbs.jpcanada.com/log/16/8458.html
http://bbs.jpcanada.com/log/12/260.html
http://bbs.jpcanada.com/log/9/3385.html
http://bbs.jpcanada.com/log/11/2495.html
http://bbs.jpcanada.com/log/5/1219.html
最後のリンクは、読んでいて辛くなります。
明察で的を射た考察だと感服しました。
真に「学歴社会」なら学歴の長さや実績が就職率に反映されるはずですが、
日本は学歴が一定数以上長くなると逆に企業から敬遠される傾向にあります。
(大卒はいいが文系大学院卒はあまり採用しないなど)
むしろ日本は「学閥社会」「大学名によるランキング選別採用」を用いている
社会といえるでしょう。
そこで質問ですが、
日本の大企業や官僚に多い、特定大学の先輩後輩(OB)による
企業や職場の「学閥」というのはカナダでは存在するのでしょうか?
>カナダの企業で必要なのはスキルであって、学歴ではないからだ。
欧州の企業も基本的に同じです。
日本の場合は中途採用試験がそれに当たるでしょうか。
それでもスキル面においてずいぶん緩やかな気がします。
あと公務員に関しても、
日本の官僚でさえゼネラルな広く浅い一般教養知識が問われるだけですが、
欧州本部や委員会など世界のエリートがしのぎを削る場では専門分野の
突っ込んだ知識やスキルが必要とされます。
学歴が長すぎると日本では「無用の長物」とされますし、学部で学んだ
専門性が就職してもほとんど活かされる機会はありません。
文系などすべてゼロベースで一から「初等研修」を受けるというありさまです。
高学歴エリート嫌悪主義、スキル無視主義ではないかとすら思えるほどです。
(今日本で「高学歴ワーキングプア」という言葉が流行しているように)
カナダで「高学歴ワーキングプア」はあるのでしょうか?
真に「学歴社会」なら学歴の長さや実績が就職率に反映されるはずですが、
日本は学歴が一定数以上長くなると逆に企業から敬遠される傾向にあります。
(大卒はいいが文系大学院卒はあまり採用しないなど)
むしろ日本は「学閥社会」「大学名によるランキング選別採用」を用いている
社会といえるでしょう。
そこで質問ですが、
日本の大企業や官僚に多い、特定大学の先輩後輩(OB)による
企業や職場の「学閥」というのはカナダでは存在するのでしょうか?
>カナダの企業で必要なのはスキルであって、学歴ではないからだ。
欧州の企業も基本的に同じです。
日本の場合は中途採用試験がそれに当たるでしょうか。
それでもスキル面においてずいぶん緩やかな気がします。
あと公務員に関しても、
日本の官僚でさえゼネラルな広く浅い一般教養知識が問われるだけですが、
欧州本部や委員会など世界のエリートがしのぎを削る場では専門分野の
突っ込んだ知識やスキルが必要とされます。
学歴が長すぎると日本では「無用の長物」とされますし、学部で学んだ
専門性が就職してもほとんど活かされる機会はありません。
文系などすべてゼロベースで一から「初等研修」を受けるというありさまです。
高学歴エリート嫌悪主義、スキル無視主義ではないかとすら思えるほどです。
(今日本で「高学歴ワーキングプア」という言葉が流行しているように)
カナダで「高学歴ワーキングプア」はあるのでしょうか?
「日本は学歴社会、北米は実力社会」は本当か、という問いに対する答え方はいろいろあると思います。以下は、上の議論とはつながりがあまりありませんがご了解のほど。
大学を卒業して普通の会社に普通に就職したと仮定して、日・米で考えます。
採用する側(会社)は、応募する側(大学卒業者)に対して何らかのフィルターをかけないといけません。
その際、就職時に“学歴”が重視されることは日米ともにですが、その“学歴”は大きく2つの特徴に分けられるのだと思います。すなわち“大学名”と“学科名”。その2つのうち、日本では“大学名”の方により重点が置かれる傾向があり、米国では“学科名”の方により重点が置かれる傾向があるように思います。もちろん“傾向がある”のであって、0・1の関係ではありません。
ところで、日本で“学歴”という場合には、何を勉強したかをあまりイメージしません。そうすると残るのは“大学名”。その見方の窓を通して米国の状況を見ると“学歴社会ではない”というように見えるのではないでしょうか。
次に就職した後。会社内で“実力”が重視されるのは日米ともにですが、その“実力”は大きく2つの特徴に分けられると思います。すなわち“協調する力”と“リードする力”。その2つのうち、日本では“協調する力”の方により重点が置かれる傾向があり、米国では“リードする力”の方により重点が置かれる傾向があるように思います。
ところで、日本で“実力”という場合には、協調する能力をあまりイメージしません。そうすると残るのは“リードする力”。その見方の窓を通して米国の状況を見ると“実力社会だ”というように見えるのではないでしょうか。
以上のことから、日本の典型的な視点を通じてみると「日本は学歴社会だが、北米はそうでもない」「北米は実力社会だが、日本はそうでもない」ということが言えるのでは。
これら2つの見方は、本来直接的に対比するべきものではないはずですが、これら2つの見方を無理やり足し算して「会社社会」全体を俯瞰した見方とするならば、「日本は学歴社会、北米は実力社会」ということになるのでは。
ということで、「日本は学歴社会、北米は実力社会」は本当だ、というのが私なりの答えです。
大学を卒業して普通の会社に普通に就職したと仮定して、日・米で考えます。
採用する側(会社)は、応募する側(大学卒業者)に対して何らかのフィルターをかけないといけません。
その際、就職時に“学歴”が重視されることは日米ともにですが、その“学歴”は大きく2つの特徴に分けられるのだと思います。すなわち“大学名”と“学科名”。その2つのうち、日本では“大学名”の方により重点が置かれる傾向があり、米国では“学科名”の方により重点が置かれる傾向があるように思います。もちろん“傾向がある”のであって、0・1の関係ではありません。
ところで、日本で“学歴”という場合には、何を勉強したかをあまりイメージしません。そうすると残るのは“大学名”。その見方の窓を通して米国の状況を見ると“学歴社会ではない”というように見えるのではないでしょうか。
次に就職した後。会社内で“実力”が重視されるのは日米ともにですが、その“実力”は大きく2つの特徴に分けられると思います。すなわち“協調する力”と“リードする力”。その2つのうち、日本では“協調する力”の方により重点が置かれる傾向があり、米国では“リードする力”の方により重点が置かれる傾向があるように思います。
ところで、日本で“実力”という場合には、協調する能力をあまりイメージしません。そうすると残るのは“リードする力”。その見方の窓を通して米国の状況を見ると“実力社会だ”というように見えるのではないでしょうか。
以上のことから、日本の典型的な視点を通じてみると「日本は学歴社会だが、北米はそうでもない」「北米は実力社会だが、日本はそうでもない」ということが言えるのでは。
これら2つの見方は、本来直接的に対比するべきものではないはずですが、これら2つの見方を無理やり足し算して「会社社会」全体を俯瞰した見方とするならば、「日本は学歴社会、北米は実力社会」ということになるのでは。
ということで、「日本は学歴社会、北米は実力社会」は本当だ、というのが私なりの答えです。
>2
>特定大学の先輩後輩(OB)による企業や職場の「学閥」というのはカナダでは存在するのでしょうか?
カナダはコネ社会ですが、学閥だけが唯一にして万能のコネということはないと思います。
>むしろ日本は「学閥社会」
昔は薩摩・長州が政治を恣にし、その前は譜代大名でないと政治に参与できず、外様は排除されていました。
数あるコネのうち、現代日本では学閥が重視されているというだけのことです。
明治維新によって階級をほぼ撤廃した日本は、貧乏人でも勉強すれば出世できる世界でも稀な平等競争社会を実現しました。明治末期には、旧幕府系の人材でも要職に登用されたのです。
学歴主義の真の問題点は、大学で得たスキルが問われず、一般教養を問う入試の成績だけが重視されることです。また学歴重視は結局のところ人格重視であり、スキル追求よりもマイナリティ排除に走りかねないという点は、今後問われていくべきでしょう。
>日本の官僚でさえゼネラルな広く浅い一般教養知識が問われるだけですが、欧州本部や委員会など世界のエリートがしのぎを削る場では専門分野の突っ込んだ知識やスキルが必要とされます
公務員試験には暗号解読問題が必ず出題されるのですが、「世界のエリートがしのぎを削る」どんな専門分野のスキルが必要とされているのでしょうか。
http://blogs.yahoo.co.jp/sutekitaro/folder/179126.html
>カナダで「高学歴ワーキングプア」はあるのでしょうか?
カナダでは大学を出ても仕事がないので、大卒の無職はいますが、ワーキングプアはどうでしょうか。
海外大卒の移民などは、日本やインドで医者・教師・エンジニアをやっていた人でも、カナダでタクシー運転手やピザ配達をやっていることがあります。似たような問題がいずれ日本でも増えることでしょう。
カナダで話題の「ナニーゲート事件」では、移民誘致は外国出身労働者に3K労働を強要しているだけではないかとして、移民システムそのものが問い直されています。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?page=1&comm_id=1611536&id=42896785
>特定大学の先輩後輩(OB)による企業や職場の「学閥」というのはカナダでは存在するのでしょうか?
カナダはコネ社会ですが、学閥だけが唯一にして万能のコネということはないと思います。
>むしろ日本は「学閥社会」
昔は薩摩・長州が政治を恣にし、その前は譜代大名でないと政治に参与できず、外様は排除されていました。
数あるコネのうち、現代日本では学閥が重視されているというだけのことです。
明治維新によって階級をほぼ撤廃した日本は、貧乏人でも勉強すれば出世できる世界でも稀な平等競争社会を実現しました。明治末期には、旧幕府系の人材でも要職に登用されたのです。
学歴主義の真の問題点は、大学で得たスキルが問われず、一般教養を問う入試の成績だけが重視されることです。また学歴重視は結局のところ人格重視であり、スキル追求よりもマイナリティ排除に走りかねないという点は、今後問われていくべきでしょう。
>日本の官僚でさえゼネラルな広く浅い一般教養知識が問われるだけですが、欧州本部や委員会など世界のエリートがしのぎを削る場では専門分野の突っ込んだ知識やスキルが必要とされます
公務員試験には暗号解読問題が必ず出題されるのですが、「世界のエリートがしのぎを削る」どんな専門分野のスキルが必要とされているのでしょうか。
http://blogs.yahoo.co.jp/sutekitaro/folder/179126.html
>カナダで「高学歴ワーキングプア」はあるのでしょうか?
カナダでは大学を出ても仕事がないので、大卒の無職はいますが、ワーキングプアはどうでしょうか。
海外大卒の移民などは、日本やインドで医者・教師・エンジニアをやっていた人でも、カナダでタクシー運転手やピザ配達をやっていることがあります。似たような問題がいずれ日本でも増えることでしょう。
カナダで話題の「ナニーゲート事件」では、移民誘致は外国出身労働者に3K労働を強要しているだけではないかとして、移民システムそのものが問い直されています。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?page=1&comm_id=1611536&id=42896785
>4
>公務員試験には暗号解読問題が必ず出題されるのですが
最近では公務員試験でも、暗号問題は国税専門官や地方試験の一部しか出題され
なくなりました。
代わりにパズル的な推理問題、図形やグラフを用いた問題が多用されています。
ただこれらも「頭の体操パズル」の類で、専門知識を求めるものでも、スキルを
求めるものでもない、一種の「単純作業能力検査」です。
>どんな専門分野のスキルが必要とされているのでしょうか。
それぞれのジャンルの政策能力に直結する、たとえば労働・福祉・環境・医療・
社会保障・移民・文化・消費者保護・エネルギー・農業・産業経済・外交と
いった多方面の政策立案能力を見る試験が課されています。
それ以外には、3か国語(英・独・仏語)と法律、経済等の専門分野に関する
知識を問う試験が課されます。EUに関する法や法令は必須です。
>公務員試験には暗号解読問題が必ず出題されるのですが
最近では公務員試験でも、暗号問題は国税専門官や地方試験の一部しか出題され
なくなりました。
代わりにパズル的な推理問題、図形やグラフを用いた問題が多用されています。
ただこれらも「頭の体操パズル」の類で、専門知識を求めるものでも、スキルを
求めるものでもない、一種の「単純作業能力検査」です。
>どんな専門分野のスキルが必要とされているのでしょうか。
それぞれのジャンルの政策能力に直結する、たとえば労働・福祉・環境・医療・
社会保障・移民・文化・消費者保護・エネルギー・農業・産業経済・外交と
いった多方面の政策立案能力を見る試験が課されています。
それ以外には、3か国語(英・独・仏語)と法律、経済等の専門分野に関する
知識を問う試験が課されます。EUに関する法や法令は必須です。
すげえハイレベルな掲示板を見つけました。当コミュなど足元にも及びません。
==================================
●英米より日本の方が機会平等で実力社会
http://agora-web.jp/archives/1447416.html
欧米人は日本人と違って何より家族を大切にする、と信じられているが、日本より欧米諸国のほうがはるかに離婚率が高い。また、アメリカは誰にもチャンスを与えられる実力社会だ、などといわれるが、所得階層間の世代を超えた移動は、実はアメリカやイギリスは、世界の中で最もむずかしいグループに入り、他の先進国よりもはるかに親の収入がものを言うのである。
上の図は、父親の所得が、息子の所得をどれぐらい決定するかを各国で調査した結果だ。この数値は簡単に説明すると、例えば、0.5だと、父親の所得が平均値よりも100%多ければ、つまり平均値の2倍なら、息子の所得はだいたい平均値よりも50%多い、ということを表している。0.0だと、父親の所得は息子の所得に全く影響を与えないことを意味する。ディテールを省略して簡単に数式で表すと、次のβのことだ。
息子の所得 = β × 父親の所得 + α
英米は0.5前後でかなり高い値を示している。つまり父親の所得が息子によく引き継がれている。一方で、カナダや北欧三国は0.2以下で、親子間の相関は非常に小さい。このグラフには入っていないが、実は日本は0.34で、英米よりも、親の所得と子の所得の関係性が低いのである。要するには、英米より日本の方が、はるかに機会平等で実力社会なのだ。
筆者はこれは教育制度に起因していると考えている。英米の学校は、私立が中心で、かなり自由化されている。つまり、いい教育には高い学費が必要なのだ。一方で、カナダや北欧三国は学費は大学まで含めて無料である。日本も、公立の場合、高校卒業程度まではほとんど無料といっていいほど低コストである。
また、英米の名門大学は、日本のようにペーパーテスト一発勝負ではなく、どういう高校時代を送ったのか、スポーツは何を頑張ったのか、ボランティアには積極的だったか、など総合的に資質を問われる。これも多くの人が勘違いしているのだが、こうやって総合的なテストが行われると、名門大学はどこもかしこも個性のない金太郎飴みたいな学生ばかりになる。アメリカの名門大学の学生は、ハキハキとしていて、リーダーシップに積極的で、ボランティアに熱心で、スポーツもやって、といかにもナイスガイという感じの、薄っぺらい人間ばかりで、新卒の採用面接などしていると本当にうんざりする。
その点、日本の名門大学の学生はペーパーテスト一発勝負なので、パチスロにハマっていたり、コミュニケーション障害だったり、リーダーシップどころか友だちがひとりもいないような人間がゴロゴロいて、実に個性的だ。だから、筆者のような人間も楽しく学生生活を送ることができた。
アメリカの大学がすごいのは、こうやって金持ちの親から授業料としてかき集めた金を使って、世界中から著名な学者や、優秀な大学院生をスカウトして来ているからであって、教育が優れているわけでは全くない。あくまで、学術研究の頂点の部分がすごいだけなのである。
貧しい階層から這い上がり、アメリカン・ドリームを掴む、というストーリーには事欠かないのだが、このような極一部の例外的な存在が、アメリカは機会平等で誰にでもチャンスを与える、という幻想を世界中に振りまいているのだ。しかし、実際の所、アメリカよりも日本の方がはるかに機会平等で、誰にでもチャンスがある、ということは知っておいた方がいいだろう。
==================================
●英米より日本の方が機会平等で実力社会
http://agora-web.jp/archives/1447416.html
欧米人は日本人と違って何より家族を大切にする、と信じられているが、日本より欧米諸国のほうがはるかに離婚率が高い。また、アメリカは誰にもチャンスを与えられる実力社会だ、などといわれるが、所得階層間の世代を超えた移動は、実はアメリカやイギリスは、世界の中で最もむずかしいグループに入り、他の先進国よりもはるかに親の収入がものを言うのである。
上の図は、父親の所得が、息子の所得をどれぐらい決定するかを各国で調査した結果だ。この数値は簡単に説明すると、例えば、0.5だと、父親の所得が平均値よりも100%多ければ、つまり平均値の2倍なら、息子の所得はだいたい平均値よりも50%多い、ということを表している。0.0だと、父親の所得は息子の所得に全く影響を与えないことを意味する。ディテールを省略して簡単に数式で表すと、次のβのことだ。
息子の所得 = β × 父親の所得 + α
英米は0.5前後でかなり高い値を示している。つまり父親の所得が息子によく引き継がれている。一方で、カナダや北欧三国は0.2以下で、親子間の相関は非常に小さい。このグラフには入っていないが、実は日本は0.34で、英米よりも、親の所得と子の所得の関係性が低いのである。要するには、英米より日本の方が、はるかに機会平等で実力社会なのだ。
筆者はこれは教育制度に起因していると考えている。英米の学校は、私立が中心で、かなり自由化されている。つまり、いい教育には高い学費が必要なのだ。一方で、カナダや北欧三国は学費は大学まで含めて無料である。日本も、公立の場合、高校卒業程度まではほとんど無料といっていいほど低コストである。
また、英米の名門大学は、日本のようにペーパーテスト一発勝負ではなく、どういう高校時代を送ったのか、スポーツは何を頑張ったのか、ボランティアには積極的だったか、など総合的に資質を問われる。これも多くの人が勘違いしているのだが、こうやって総合的なテストが行われると、名門大学はどこもかしこも個性のない金太郎飴みたいな学生ばかりになる。アメリカの名門大学の学生は、ハキハキとしていて、リーダーシップに積極的で、ボランティアに熱心で、スポーツもやって、といかにもナイスガイという感じの、薄っぺらい人間ばかりで、新卒の採用面接などしていると本当にうんざりする。
その点、日本の名門大学の学生はペーパーテスト一発勝負なので、パチスロにハマっていたり、コミュニケーション障害だったり、リーダーシップどころか友だちがひとりもいないような人間がゴロゴロいて、実に個性的だ。だから、筆者のような人間も楽しく学生生活を送ることができた。
アメリカの大学がすごいのは、こうやって金持ちの親から授業料としてかき集めた金を使って、世界中から著名な学者や、優秀な大学院生をスカウトして来ているからであって、教育が優れているわけでは全くない。あくまで、学術研究の頂点の部分がすごいだけなのである。
貧しい階層から這い上がり、アメリカン・ドリームを掴む、というストーリーには事欠かないのだが、このような極一部の例外的な存在が、アメリカは機会平等で誰にでもチャンスを与える、という幻想を世界中に振りまいているのだ。しかし、実際の所、アメリカよりも日本の方がはるかに機会平等で、誰にでもチャンスがある、ということは知っておいた方がいいだろう。
Ken Nakatani 甲南大学 Professor of linguistics
「所得階層間の世代を超えた移動」が英米の方が難しく日本の方が機会平等というのは事実ですが(ていうか、ほとんど常識)、「名門大学はどこもかしこも個性のない金太郎飴みたない学生ばかり」というのは極論でしょう。確かにそういう学生もたくさんいますが、それなら日本の旧帝大にもたくさんいる。さらに、アイビーリーグ・レベルは「総合力」だけでは突破できないし、「極端に一芸に秀でた人」もたくさん受け入れるので、変人もいっぱいいる。ザッカーバーグやビル・ゲイツのどこが無個性? MITのような理系大学の学生はもっと強烈。ようするに筆者が「いかにもナイスガイという感じの、薄っぺらい人間ばかりで、新卒の採用面接などしていると本当にうんざりする」というのは、そういう学生しか受けにこないというだけのことではないかと邪推してしまいます。
また、「アメリカの大学がすごいのは、こうやって金持ちの親から授業料としてかき集めた金を使って、世界中から著名な学者や、優秀な大学院生をスカウトして来ているから」というのはこれまた事実ですが、だからといって「教育が優れているわけでは全くない」と断定できるはずもない。…と、アゴラにマジレス
「所得階層間の世代を超えた移動」が英米の方が難しく日本の方が機会平等というのは事実ですが(ていうか、ほとんど常識)、「名門大学はどこもかしこも個性のない金太郎飴みたない学生ばかり」というのは極論でしょう。確かにそういう学生もたくさんいますが、それなら日本の旧帝大にもたくさんいる。さらに、アイビーリーグ・レベルは「総合力」だけでは突破できないし、「極端に一芸に秀でた人」もたくさん受け入れるので、変人もいっぱいいる。ザッカーバーグやビル・ゲイツのどこが無個性? MITのような理系大学の学生はもっと強烈。ようするに筆者が「いかにもナイスガイという感じの、薄っぺらい人間ばかりで、新卒の採用面接などしていると本当にうんざりする」というのは、そういう学生しか受けにこないというだけのことではないかと邪推してしまいます。
また、「アメリカの大学がすごいのは、こうやって金持ちの親から授業料としてかき集めた金を使って、世界中から著名な学者や、優秀な大学院生をスカウトして来ているから」というのはこれまた事実ですが、だからといって「教育が優れているわけでは全くない」と断定できるはずもない。…と、アゴラにマジレス
Yoshito J. Yamamoto
父親と息子の所得の相関性が低いことが機会平等で実力社会であるという裏付けになるというのは、論理が飛躍している。英米も日本も同じ実力主義の機会均等社会であっても、父親と息子の人間関係が希薄なために家庭教育の影響が小さければ、父親の実力と息子の実力の相関性が低くなり、従って所得の相関性も低くなる。日本で育ったアメリカ人である私からみれば、日本の父親と息子の人間関係は英米のそれと比較すれば皆無に等しいものであることを知らない、日本の家族関係が世界共通であるとしか考えていないものである。日本で所得の高い職業についている父親は仕事を休んで息子の草野球の試合を応援に行くなどとというのはほとんどあり得ないが、アメリカでは、所得の高い職業についている父親の方がスケジュールの融通性があり、部下が仕事をしていても職場を抜け出して応援に行くことが普通である。所得が高い父親の方が息子と一緒に過ごす時間を取れることが多く、従って実力があって所得の高い職業についている父親の方が息子に様々な教訓を教える機会が豊富で、従って息子も父親の教訓を糧に実力を身につけることが多く、従って息子と父親の実力の相関性が高くなり、所得と実力の相関性の高い機会均等の実力社会であれば息子と父親の所得の相関性も高くなる。この記事の著者は統計の読み方も誤っているし、英米の家族関係についての知識も有していない。
父親と息子の所得の相関性が低いことが機会平等で実力社会であるという裏付けになるというのは、論理が飛躍している。英米も日本も同じ実力主義の機会均等社会であっても、父親と息子の人間関係が希薄なために家庭教育の影響が小さければ、父親の実力と息子の実力の相関性が低くなり、従って所得の相関性も低くなる。日本で育ったアメリカ人である私からみれば、日本の父親と息子の人間関係は英米のそれと比較すれば皆無に等しいものであることを知らない、日本の家族関係が世界共通であるとしか考えていないものである。日本で所得の高い職業についている父親は仕事を休んで息子の草野球の試合を応援に行くなどとというのはほとんどあり得ないが、アメリカでは、所得の高い職業についている父親の方がスケジュールの融通性があり、部下が仕事をしていても職場を抜け出して応援に行くことが普通である。所得が高い父親の方が息子と一緒に過ごす時間を取れることが多く、従って実力があって所得の高い職業についている父親の方が息子に様々な教訓を教える機会が豊富で、従って息子も父親の教訓を糧に実力を身につけることが多く、従って息子と父親の実力の相関性が高くなり、所得と実力の相関性の高い機会均等の実力社会であれば息子と父親の所得の相関性も高くなる。この記事の著者は統計の読み方も誤っているし、英米の家族関係についての知識も有していない。
山本 匡人 大阪大学
親が高所得→子供にかける時間が長い→親から子へ実力が継承される→機会平等で実力社会であれば子供も高所得
という論理を主張されていらっしゃると思うのですが、私は、「子供の教育にかける時間が長く、親から子へ実力が継承される」という点について信ぴょう性に欠けると考えます。
根拠として、「ヤバい経済学」(英題:freakonmics)第5章の「完璧な子育て」の章に示されている研究を紹介します。
詳しい数字は失念してしまったのですが、アメリカの統計データを使って、親のどういった行動が子供の能力に影響するかということを調べた研究です。
その中では、「小さいころに本を読んであげた」「対話を大切にした」といった「子供に何か特別なことをした」という要素よりも、「高所得である」「離婚歴がない」などといった「親がどういう人間か」という要素のほうが子供の知性との相関が高かったそうです。(ちなみにその研究によると、親に離婚歴がなく、母親は初めての子供を30歳未満で産んでおり、父親の年収が〜万ドル以上である子供が最も知性が高くなる確率が高いそうです。)
以上の研究を根拠に、「子供の教育にかける時間が長く、親から子へ実力が継承される」という点が論理的につながりがないので、「アメリカは機会平等である」という主張を否定します。
むしろ、親が高所得な場合、子供が高額な私立学校に通うことができたりアルバイトなどをする必要がないなど、より多い機会、質のよい機会にめぐり合える機会があり、高所得を得る可能性が高くなるのではないかと考えます。
例えばスタンフォードのMBAは年間8万ドルもの学費や、西海岸の高い物価に耐えられる人間しか通うことができません。日本との対比で言えば、日本で3番目の大阪大学でさえ年間約50万円、ドルにして約6000ドルです。教育を得られる機会という点でもアメリカより日本のほうが機会平等に見えますが。
※学費については、奨学金や学費免除といった制度があり低所得者層でも質の高い教育を得る方法があるので、「逆転可能な社会」とは言えるとおもいます。ただ、逆転可能だからと言って機会が平等だとは言えません。日本も、機会が平等だからと言って逆転が可能かと言うとそうでもないですしね。
実力社会については、著者のデータからは読み取れないので賛成とも反対とも言い兼ねます。
親が高所得→子供にかける時間が長い→親から子へ実力が継承される→機会平等で実力社会であれば子供も高所得
という論理を主張されていらっしゃると思うのですが、私は、「子供の教育にかける時間が長く、親から子へ実力が継承される」という点について信ぴょう性に欠けると考えます。
根拠として、「ヤバい経済学」(英題:freakonmics)第5章の「完璧な子育て」の章に示されている研究を紹介します。
詳しい数字は失念してしまったのですが、アメリカの統計データを使って、親のどういった行動が子供の能力に影響するかということを調べた研究です。
その中では、「小さいころに本を読んであげた」「対話を大切にした」といった「子供に何か特別なことをした」という要素よりも、「高所得である」「離婚歴がない」などといった「親がどういう人間か」という要素のほうが子供の知性との相関が高かったそうです。(ちなみにその研究によると、親に離婚歴がなく、母親は初めての子供を30歳未満で産んでおり、父親の年収が〜万ドル以上である子供が最も知性が高くなる確率が高いそうです。)
以上の研究を根拠に、「子供の教育にかける時間が長く、親から子へ実力が継承される」という点が論理的につながりがないので、「アメリカは機会平等である」という主張を否定します。
むしろ、親が高所得な場合、子供が高額な私立学校に通うことができたりアルバイトなどをする必要がないなど、より多い機会、質のよい機会にめぐり合える機会があり、高所得を得る可能性が高くなるのではないかと考えます。
例えばスタンフォードのMBAは年間8万ドルもの学費や、西海岸の高い物価に耐えられる人間しか通うことができません。日本との対比で言えば、日本で3番目の大阪大学でさえ年間約50万円、ドルにして約6000ドルです。教育を得られる機会という点でもアメリカより日本のほうが機会平等に見えますが。
※学費については、奨学金や学費免除といった制度があり低所得者層でも質の高い教育を得る方法があるので、「逆転可能な社会」とは言えるとおもいます。ただ、逆転可能だからと言って機会が平等だとは言えません。日本も、機会が平等だからと言って逆転が可能かと言うとそうでもないですしね。
実力社会については、著者のデータからは読み取れないので賛成とも反対とも言い兼ねます。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ここが変だよ比較文化論 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-