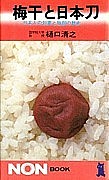mixiニュースより
http://
>2009年3月20日、南方網は「日本の混浴の歴史とその復興」を掲載した。観光振興に力を入れている日本は中国からの観光客誘致にも熱心だが、中国人が最も関心を持っているのは芸者と混浴だという。
>1879年、清末の新聞記者・王稲(ワン・ダオ)は日本を訪問、混浴に関する記述を残している。王稲からさかのぼること26年、米国のペリー提督も日本の公衆浴場が混浴であるとの記述を残しており、通俗文学の卑わいな挿絵とともに日本人がみだらであることの証左としている。ただしプロイセンの外交官であるフリードリヒ・アルブレヒト・オイレンブルク伯爵は「老若男女が一つの風呂に入っても何の問題も発生しない。いや、入浴している者はほかの人の性別に注意すらしていないようだ」とも書き残している。
(中略)
>こうした日本独特の混浴文化に中国人旅行客は強い関心を持っている。ツアー旅行に参加したある中国人男性はガイドに「ぜひ混浴温泉に行ってみたい」と訴えたという。ガイドはこれに「ではこのツアーの皆さんも男女一緒にお風呂に入ることになりますよ」と笑って答えたのだとか。
=========================================
(1) 西洋人の見た日本の浴場
幕末に日本を訪れた西洋人は、日本人の入浴文化について以下のように記録している。
「裸でも気にせずに男女混浴をしている公衆浴場を目のあたりにすると、アメリカ人には住民の道徳性について、さほど良い印象は持てないだろう。」 (「ペリー艦隊日本遠征記」)
「私が見聞した異教徒諸国の中では、この国が一番淫らかと思われた。体験したところから判断すると、慎みを知らないといっても過言ではない。婦人達は胸を隠そうとしないし、歩くたびに太股まで覗かせる。男は男で、前をほんの半端なぼろで隠しただけで出歩き、その着装具合を気にもとめていない。裸体の姿は男女共に街頭に見られ、世間体などはおかまいなしに、等しく混浴の銭湯に通っている。」 (サミュエル・ウィリアムズ著「ペリー日本遠征随行記」)
「湯治場は街路からあけすけに見えるところにあり、入浴者を日光からさえぎるための小屋の屋根があるだけだった。われわれが近づいたときに、中年過ぎのひとりの婦人が温泉のふちへ上がってきた。あとには、まだ五、六人の婦人が湯につかっていた。この婦人は、一切の自意識や当惑といったものをまったくもち合わせていなかったので、カンフスの『おお、神聖なる無知よ』という叫びを想い起こさないわけにはゆかなかった。」 (ラザフォード・オールコック著「大君の都」)
「真冬にも関わらず素っ裸で、カラダを茹でカニのように真っ赤にさせた銭湯帰りの子供が私たちの前を走っていった。見れば銭湯の二階には茶を飲む部屋があり、二階の欄干からふんどし姿の裸の男達が私たちを見ているのには驚いた」 (フリードリヒ=アルブレヒト・オイレンブルク著「日本遠征記」)
(2) 江戸期の公衆浴場
ガスも水道もない江戸初期、大量の水と薪を入手することは難しく、武家や豪商ですら自宅に風呂はなかった。都市では公衆浴場は必要不可欠であり、記録に残る最初の銭湯が登場するのは1591年のことである。
水と薪が十分供給できないため、全身浴ができるようになるのは江戸後期で、初期は小さな浴槽で半身浴していた。浴槽は一つしかなく、混浴である。熱を逃がさないため窓は少なく、内部は薄暗かった。そのため若い女性にいたずらをする男性はいたようで、当時の川柳に残っている。ただ薄暗い湯屋の中で、裸を恥ずかしがる観念があったとは考えにくい。銭湯の二階は庶民の社交場で、武士は刀を預けて囲碁・将棋に興じ、庶民は歌舞伎役者の品定めなどさまざまな話題に花を咲かせた。銭湯の2階からは、浴室が丸見えだった。
後の時代には、湯女が銭湯で垢すりや髪すきを行う湯女風呂が登場した。松平定信は1791年、江戸の銭湯での混浴禁止令を出したが、これは湯屋における売買の取り締まりを企図したものと考えられている。なお定信は浮世絵の多色刷りも禁止しているが、春画を取り締まるためだった。
男女別浴が成立すると、女は日中、男は仕事帰りに銭湯に通った。八丁堀の同心は女湯に入る特権があり、夜の町の事情に詳しい男が入る朝方を狙って女湯に入り、男湯の会話に聞き耳を立てていた。この時間に女が女湯に入れば、鉢合わせすることもあっただろう。
(3) 裸の禁止
江戸時代には軒先での行水は普通に行われ、肉体労働者は褌一丁で働いていた。だが西洋人からの批判は厳しく、脱亜入欧路線真っしぐらの明治政府は、1869年混浴禁止令、次いで1872年には人前で裸になることを禁止した。だが長年の慣行がお触れ一つで変わるはずもなく、男女別浴を命じられた銭湯は、一つの湯船の中心に板を通して光熱費の節減を図るなど、銭湯と政府の化かし合いは続き、混浴禁止令はその後幾度も出されることとなった。銭湯での混浴が完全に消滅するのは、1900年のことである。
1872年の裸禁止令に対し、「新聞雑誌」第50号は「裸や肌脱ぎがいけないというなら、いつも肌脱ぎしているお釈迦様はどうなんだ」と述べ、自国文化を擁護した。
(4) もう一つの視点
「日本人=混浴=猥褻」の固定観念は、浮世絵の春画が外国人の目に触れることによっていっそう増幅された。だがいっぽうでは、日本の風俗に理解を示す西洋人もいた。スイス全権大使として1863年に来日したエメ・アンベールは「幕末日本風俗図絵」の中で、
「このような風習がわれわれにとってどんなに奇異なものと思われても、ヨーロッパ人が到来する以前には、日本人は自分達の風習に非難されるべき一面があるなどとは、明らかに誰一人疑っていなかった。それどころか、それが家庭生活の慣例と完全に調和を保っており、その上、身体を清めるという宗教的・衛生的義務と関係ない、あらゆる偏見を排除し、道徳的見地からしても申し分のないものと思っていたに相違ない。一方、ヨーロッパ人は、日本人が自負している偏見のない現実と事象を抽象的に考える能力が日本人にあることを信じたくはなかったのである。」
と述べている。また1865年に来日したハインリッヒ・シュリーマンは「シュリーマン旅行記清国・日本」の中で、
「夜明けから日暮れまで、禁断の林檎を齧る前のわれわれの先祖と同じ姿になった老若男女が、いっしょに湯をつかっている。彼らはそれぞれの手桶で湯を汲み、ていねいに体を洗い、また着物を身に着けて出て行く。『なんと清らかな素朴さだろう!』初めて公衆浴場の前を通り三、四十人の全裸の男女を目にした時、私はこう叫んだものである。自国の習慣に従って生きているかぎり、間違った行為をしていると感じないものだからだ。そこでは淫らな意識が生まれようがない。父母、夫婦、兄妹、すべてのものが男女混浴を容認しており、幼いころからこうした浴場に通うことが習慣になっている人々にとって、男女混浴は恥ずかしいことでも、いけないことでもないのである。」
と述べた。
1860年代に入り、外国人の姿が珍しくなくなると、かつては人前で行水していた日本女性は、やがて公共の場での裸を憚るようになる。
1888年に来日し15年間日本に暮らしたイギリス人宣教師ウォルター・ウェストンは、「知られざる日本を旅して」の中で「日本人が伝統的な男女混浴をやめたのは、外国人の偏見による」と述べ、「日本では裸体は見てもよいが、見つめてはならない」と指摘した。また福井藩校や東京の大学南校に勤めたアメリカ人ウィリアム・グリフィスは「男たちは誰一人として女の裸をじろじろ見たりはせず、何の興味も示さなかった。それが普通で、女性の顔か手を見るぐらいの気持ちしか起こらぬものらしい。」と述べるとともに、「裸を恥ずかしがらぬ日本人に対してより、それを見ようとしげしげと銭湯の前に通い、好色な視線で眺めては『淫らだ!』と恥知らずに非難している外国人を非難すべきだ」と主張した。同時に「日本で女性を買う上得意は、キリスト教国から来た人たちだ」とも指摘している。
玉虫佐太夫は1860年に遣米使節団に加わり、異文化の中で自国文化を顧みる機会を得た。乗船したアメリカ軍艦ボウハタン号がパナマに差しかかり、暑さが厳しくなると、日本人たちが肌脱ぎになったり、着物のスソをまくったりしたが、佐太夫はアメリカ水兵に嘲笑されていることに気づいたのである。彼らは暑さ厳しいときでも決して肌をあらわさなかった。左太夫は「善俗ナリトイフベシ」と記録している。
(5) カナダの風俗
カナダの山岳地帯には温泉があるが、温度はぬるく、人々は水着を着用して入る。当然、混浴である。西洋では日本と異なり、温泉は温熱療法として使われている。日本人が「いい湯だな」と感じるのは43℃程度とされているが、西洋人は肌が薄いのか、猛烈に熱いと感じるようだ。カナダ在住日本人の大多数にはカナダの温泉は物足りず、銭湯が欲しいと思う人もいるようだが、そんなものを設置したらホモが喜ぶだけなので、日本人以外は誰もそのようなことを考えない。
北国は冬の日照時間が少ないせいか、日光浴の習慣がある。裏庭でトップレスで日光浴する人は、珍しくない。ヌーディストビーチはしげしげと凝視するところでもなければ、売春の交渉をするところでもなく、全裸または半裸で日光浴するところである。
日本人には日光浴の習慣がないので、ヌーディストビーチはやはり奇特な習慣として映る。日本人観光客の中には、これを物珍しげに眺めに行く人もいるようだ。それは混浴を淫らなものとして眺めていた幕末の西洋人と、同じ視点に立つものである。
日本人もかつては、軒下で行水した。人前で授乳する女性もいた。山下清のようにシャツ1枚で出歩く人もいた。今やほとんどの世帯には風呂があり、このような人々はいつから見かけなくなったのだろうか。
カナダでは今も、上半身裸でダウンタウンを出歩く人を見かける。「女性にも男性と同じ権利を認めるべきだ」とする裁判も起きた。異文化を理解することは難しく、何を恥とするかの価値観も文化によって異なるようだ。
【参考】 カナダのトップフリー運動
http://
図左:「ペリー艦隊日本遠征記」より「下田の公衆浴場」。
写真右:バンクーバーのヌーディストビーチ。
http://
>2009年3月20日、南方網は「日本の混浴の歴史とその復興」を掲載した。観光振興に力を入れている日本は中国からの観光客誘致にも熱心だが、中国人が最も関心を持っているのは芸者と混浴だという。
>1879年、清末の新聞記者・王稲(ワン・ダオ)は日本を訪問、混浴に関する記述を残している。王稲からさかのぼること26年、米国のペリー提督も日本の公衆浴場が混浴であるとの記述を残しており、通俗文学の卑わいな挿絵とともに日本人がみだらであることの証左としている。ただしプロイセンの外交官であるフリードリヒ・アルブレヒト・オイレンブルク伯爵は「老若男女が一つの風呂に入っても何の問題も発生しない。いや、入浴している者はほかの人の性別に注意すらしていないようだ」とも書き残している。
(中略)
>こうした日本独特の混浴文化に中国人旅行客は強い関心を持っている。ツアー旅行に参加したある中国人男性はガイドに「ぜひ混浴温泉に行ってみたい」と訴えたという。ガイドはこれに「ではこのツアーの皆さんも男女一緒にお風呂に入ることになりますよ」と笑って答えたのだとか。
=========================================
(1) 西洋人の見た日本の浴場
幕末に日本を訪れた西洋人は、日本人の入浴文化について以下のように記録している。
「裸でも気にせずに男女混浴をしている公衆浴場を目のあたりにすると、アメリカ人には住民の道徳性について、さほど良い印象は持てないだろう。」 (「ペリー艦隊日本遠征記」)
「私が見聞した異教徒諸国の中では、この国が一番淫らかと思われた。体験したところから判断すると、慎みを知らないといっても過言ではない。婦人達は胸を隠そうとしないし、歩くたびに太股まで覗かせる。男は男で、前をほんの半端なぼろで隠しただけで出歩き、その着装具合を気にもとめていない。裸体の姿は男女共に街頭に見られ、世間体などはおかまいなしに、等しく混浴の銭湯に通っている。」 (サミュエル・ウィリアムズ著「ペリー日本遠征随行記」)
「湯治場は街路からあけすけに見えるところにあり、入浴者を日光からさえぎるための小屋の屋根があるだけだった。われわれが近づいたときに、中年過ぎのひとりの婦人が温泉のふちへ上がってきた。あとには、まだ五、六人の婦人が湯につかっていた。この婦人は、一切の自意識や当惑といったものをまったくもち合わせていなかったので、カンフスの『おお、神聖なる無知よ』という叫びを想い起こさないわけにはゆかなかった。」 (ラザフォード・オールコック著「大君の都」)
「真冬にも関わらず素っ裸で、カラダを茹でカニのように真っ赤にさせた銭湯帰りの子供が私たちの前を走っていった。見れば銭湯の二階には茶を飲む部屋があり、二階の欄干からふんどし姿の裸の男達が私たちを見ているのには驚いた」 (フリードリヒ=アルブレヒト・オイレンブルク著「日本遠征記」)
(2) 江戸期の公衆浴場
ガスも水道もない江戸初期、大量の水と薪を入手することは難しく、武家や豪商ですら自宅に風呂はなかった。都市では公衆浴場は必要不可欠であり、記録に残る最初の銭湯が登場するのは1591年のことである。
水と薪が十分供給できないため、全身浴ができるようになるのは江戸後期で、初期は小さな浴槽で半身浴していた。浴槽は一つしかなく、混浴である。熱を逃がさないため窓は少なく、内部は薄暗かった。そのため若い女性にいたずらをする男性はいたようで、当時の川柳に残っている。ただ薄暗い湯屋の中で、裸を恥ずかしがる観念があったとは考えにくい。銭湯の二階は庶民の社交場で、武士は刀を預けて囲碁・将棋に興じ、庶民は歌舞伎役者の品定めなどさまざまな話題に花を咲かせた。銭湯の2階からは、浴室が丸見えだった。
後の時代には、湯女が銭湯で垢すりや髪すきを行う湯女風呂が登場した。松平定信は1791年、江戸の銭湯での混浴禁止令を出したが、これは湯屋における売買の取り締まりを企図したものと考えられている。なお定信は浮世絵の多色刷りも禁止しているが、春画を取り締まるためだった。
男女別浴が成立すると、女は日中、男は仕事帰りに銭湯に通った。八丁堀の同心は女湯に入る特権があり、夜の町の事情に詳しい男が入る朝方を狙って女湯に入り、男湯の会話に聞き耳を立てていた。この時間に女が女湯に入れば、鉢合わせすることもあっただろう。
(3) 裸の禁止
江戸時代には軒先での行水は普通に行われ、肉体労働者は褌一丁で働いていた。だが西洋人からの批判は厳しく、脱亜入欧路線真っしぐらの明治政府は、1869年混浴禁止令、次いで1872年には人前で裸になることを禁止した。だが長年の慣行がお触れ一つで変わるはずもなく、男女別浴を命じられた銭湯は、一つの湯船の中心に板を通して光熱費の節減を図るなど、銭湯と政府の化かし合いは続き、混浴禁止令はその後幾度も出されることとなった。銭湯での混浴が完全に消滅するのは、1900年のことである。
1872年の裸禁止令に対し、「新聞雑誌」第50号は「裸や肌脱ぎがいけないというなら、いつも肌脱ぎしているお釈迦様はどうなんだ」と述べ、自国文化を擁護した。
(4) もう一つの視点
「日本人=混浴=猥褻」の固定観念は、浮世絵の春画が外国人の目に触れることによっていっそう増幅された。だがいっぽうでは、日本の風俗に理解を示す西洋人もいた。スイス全権大使として1863年に来日したエメ・アンベールは「幕末日本風俗図絵」の中で、
「このような風習がわれわれにとってどんなに奇異なものと思われても、ヨーロッパ人が到来する以前には、日本人は自分達の風習に非難されるべき一面があるなどとは、明らかに誰一人疑っていなかった。それどころか、それが家庭生活の慣例と完全に調和を保っており、その上、身体を清めるという宗教的・衛生的義務と関係ない、あらゆる偏見を排除し、道徳的見地からしても申し分のないものと思っていたに相違ない。一方、ヨーロッパ人は、日本人が自負している偏見のない現実と事象を抽象的に考える能力が日本人にあることを信じたくはなかったのである。」
と述べている。また1865年に来日したハインリッヒ・シュリーマンは「シュリーマン旅行記清国・日本」の中で、
「夜明けから日暮れまで、禁断の林檎を齧る前のわれわれの先祖と同じ姿になった老若男女が、いっしょに湯をつかっている。彼らはそれぞれの手桶で湯を汲み、ていねいに体を洗い、また着物を身に着けて出て行く。『なんと清らかな素朴さだろう!』初めて公衆浴場の前を通り三、四十人の全裸の男女を目にした時、私はこう叫んだものである。自国の習慣に従って生きているかぎり、間違った行為をしていると感じないものだからだ。そこでは淫らな意識が生まれようがない。父母、夫婦、兄妹、すべてのものが男女混浴を容認しており、幼いころからこうした浴場に通うことが習慣になっている人々にとって、男女混浴は恥ずかしいことでも、いけないことでもないのである。」
と述べた。
1860年代に入り、外国人の姿が珍しくなくなると、かつては人前で行水していた日本女性は、やがて公共の場での裸を憚るようになる。
1888年に来日し15年間日本に暮らしたイギリス人宣教師ウォルター・ウェストンは、「知られざる日本を旅して」の中で「日本人が伝統的な男女混浴をやめたのは、外国人の偏見による」と述べ、「日本では裸体は見てもよいが、見つめてはならない」と指摘した。また福井藩校や東京の大学南校に勤めたアメリカ人ウィリアム・グリフィスは「男たちは誰一人として女の裸をじろじろ見たりはせず、何の興味も示さなかった。それが普通で、女性の顔か手を見るぐらいの気持ちしか起こらぬものらしい。」と述べるとともに、「裸を恥ずかしがらぬ日本人に対してより、それを見ようとしげしげと銭湯の前に通い、好色な視線で眺めては『淫らだ!』と恥知らずに非難している外国人を非難すべきだ」と主張した。同時に「日本で女性を買う上得意は、キリスト教国から来た人たちだ」とも指摘している。
玉虫佐太夫は1860年に遣米使節団に加わり、異文化の中で自国文化を顧みる機会を得た。乗船したアメリカ軍艦ボウハタン号がパナマに差しかかり、暑さが厳しくなると、日本人たちが肌脱ぎになったり、着物のスソをまくったりしたが、佐太夫はアメリカ水兵に嘲笑されていることに気づいたのである。彼らは暑さ厳しいときでも決して肌をあらわさなかった。左太夫は「善俗ナリトイフベシ」と記録している。
(5) カナダの風俗
カナダの山岳地帯には温泉があるが、温度はぬるく、人々は水着を着用して入る。当然、混浴である。西洋では日本と異なり、温泉は温熱療法として使われている。日本人が「いい湯だな」と感じるのは43℃程度とされているが、西洋人は肌が薄いのか、猛烈に熱いと感じるようだ。カナダ在住日本人の大多数にはカナダの温泉は物足りず、銭湯が欲しいと思う人もいるようだが、そんなものを設置したらホモが喜ぶだけなので、日本人以外は誰もそのようなことを考えない。
北国は冬の日照時間が少ないせいか、日光浴の習慣がある。裏庭でトップレスで日光浴する人は、珍しくない。ヌーディストビーチはしげしげと凝視するところでもなければ、売春の交渉をするところでもなく、全裸または半裸で日光浴するところである。
日本人には日光浴の習慣がないので、ヌーディストビーチはやはり奇特な習慣として映る。日本人観光客の中には、これを物珍しげに眺めに行く人もいるようだ。それは混浴を淫らなものとして眺めていた幕末の西洋人と、同じ視点に立つものである。
日本人もかつては、軒下で行水した。人前で授乳する女性もいた。山下清のようにシャツ1枚で出歩く人もいた。今やほとんどの世帯には風呂があり、このような人々はいつから見かけなくなったのだろうか。
カナダでは今も、上半身裸でダウンタウンを出歩く人を見かける。「女性にも男性と同じ権利を認めるべきだ」とする裁判も起きた。異文化を理解することは難しく、何を恥とするかの価値観も文化によって異なるようだ。
【参考】 カナダのトップフリー運動
http://
図左:「ペリー艦隊日本遠征記」より「下田の公衆浴場」。
写真右:バンクーバーのヌーディストビーチ。
|
|
|
|
コメント(2)
幕末にアメリカを訪問した幕府の全権委員村垣範正は、ハワイでカメハメハ四世・エマ夫妻に謁見したあと、ざれ歌を詠んでいる。
「ご亭主はたすき掛けなり おくさんは大肌脱ぎで珍客にあう」
国王の「たすき掛け」は大綬、王妃の「大肌脱ぎ」はデコルテのことだろう。裸で行水が珍しくもない当時の日本人にとっても、胸を大きく露出したデコルテは奇異に映ったようだ。たすき掛けは力仕事をする際にするもので、国王夫妻が正装していることなど当然承知してはいるが、大綬がたすき掛けに似ているのを茶化している。ハワイの民衆がどんな服装をしているかは見ていただろうから、丁髷を結って大小二本差している自分たちの方が珍奇に見えるという自覚はあったようで、それゆえ自分たちの方を「珍客」と言っている。つまりは、お互いが相手を珍客だと思っていたということだ。
「ご亭主はたすき掛けなり おくさんは大肌脱ぎで珍客にあう」
国王の「たすき掛け」は大綬、王妃の「大肌脱ぎ」はデコルテのことだろう。裸で行水が珍しくもない当時の日本人にとっても、胸を大きく露出したデコルテは奇異に映ったようだ。たすき掛けは力仕事をする際にするもので、国王夫妻が正装していることなど当然承知してはいるが、大綬がたすき掛けに似ているのを茶化している。ハワイの民衆がどんな服装をしているかは見ていただろうから、丁髷を結って大小二本差している自分たちの方が珍奇に見えるという自覚はあったようで、それゆえ自分たちの方を「珍客」と言っている。つまりは、お互いが相手を珍客だと思っていたということだ。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ここが変だよ比較文化論 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-