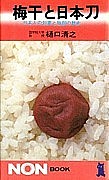読売新聞12月25日
ベルギー北部フランドル(英名フランダース)地方在住のベルギー人映画監督が、クリスマスにちなんだ悲運の物語として日本で知られる「フランダースの犬」を“検証”するドキュメンタリー映画を作成した。
物語の主人公ネロと忠犬パトラッシュが、クリスマスイブの夜に力尽きたアントワープの大聖堂で、27日に上映される。映画のタイトルは「パトラッシュ」で、監督はディディエ・ボルカールトさん(36)。制作のきっかけは、大聖堂でルーベンスの絵を見上げ、涙を流す日本人の姿を見たことだったという。
物語では、画家を夢見る少年ネロが、放火のぬれぎぬを着せられて、村を追われ、吹雪の中をさまよった揚げ句、一度見たかったこの絵を目にする。そして誰を恨むこともなく、忠犬とともに天に召される。原作は英国人作家ウィーダが1870年代に書いたが、欧州では、物語は「負け犬の死」(ボルカールトさん)としか映らず、評価されることはなかった。米国では過去に5回映画化されているが、いずれもハッピーエンドに書き換えられた。悲しい結末の原作が、なぜ日本でのみ共感を集めたのかは、長く謎とされてきた。ボルカールトさんらは、3年をかけて謎の解明を試みた。資料発掘や、世界6か国での計100人を超えるインタビューで、浮かび上がったのは、日本人の心に潜む「滅びの美学」だった。
プロデューサーのアン・バンディーンデレンさん(36)は「日本人は、信義や友情のために敗北や挫折を受け入れることに、ある種の崇高さを見いだす。ネロの死に方は、まさに日本人の価値観を体現するもの」と結論づけた。
YouTube - 「フランダースの犬」最終回
http://
「フランダースの犬」原作小説
http://
===============================
●原作のネロは15歳
絵が好きな彼は、仕事を怠けて絵を描くことがあった。この年齢ならば、画家で食っていけないなら観念して就職すればいいものを、自分の意志で就職もせず、食べ物を買うお金で絵の具を買った。悲劇を回避する方法はいくらでもあったのに、彼は自分の意志で教会に行き、ルーベンスの絵の前でのたれ死にする道を選んだのである。堅気の職業を拒否し、最後まで画家として、己の才能を認めない世をはかなんで憤死するのである。これはまさに「負け犬」そのものであり、これでは親たちがこの作品を嫌悪するのも無理はない。
ネロが放火の疑いをかけられたのも、彼が画家を志し15歳にもなって定職に就かず、それでいて金持ちの娘に言い寄ったからだろう。彼は原作では、コンクールで入賞したらアロアを嫁にしてみんなを見返してやろうと考えていた。純真・無欲ではなかったのだ。
ボルカールト監督は、原作と日本アニメの違いは把握していただろうか。
日本アニメではネロは10歳の設定で、定職につくことはできず、親に死なれ、村を追放されれば、のたれ死にするより道はない。子供ならば石にかじりついてでも生き抜くしたたかさよりも、純真さが求められるだろう。そのぶん悲劇性がいっそう際立つ効果を生んだが、親が死んだら孤児院に行くべき年齢に設定してしまったことで、ベルギー人に疑問を抱かせる作品になってしまった。10歳の子供にコンクールで認められる画才があるという設定は、さすがに無理があるだろう。
余談だがオランダの画家ゴッホは、37歳にもなって弟の仕送りで生活しており、存命中は絵が全く売れなかった。
●共同体の絶対化と諦念
ネロは濡れ衣を着せられても村人を恨んだりせず、従容として死を受け容れる。彼は共同体の平和を乱してしまったため、もはや共同体から排除されるしかないのだ(原作では、村の若者みんなが美しくて金持ちのアロアを狙っているので、色男のネロは存在そのものが罪である以上、弁明は無駄である)。彼がそれでも村人に怒れないのは、アロアの家族だからか、それとも「世間」という名の共同体が絶対だからか。
日本人は世間に居場所がなくなると、自殺してしまうようだ。義経しかり、渡辺崋山しかり。日本人は犯した罪より、反省の色がないことの方が罪悪視されてしまうから、相手を恨み復讐する行為は、視聴者の共感を呼ばないだろう。だが主人公のもう一方は動物なので、恨み言を言うことはない。
「パトラッシュ、疲れたろう、僕も疲れたんだ…」
ネロのこの言葉が、全てに対する無抵抗と諦念を示している。
「寒いことも悲しいこともお腹がすくこともない世界」が虚構であり、それが「寒いことも悲しいことも空腹もある」、そしてそれを見捨てる無情な現世への反語だとわかっているから、悲しいのである。昇天してゆくネロがとてもうれしそうに見えることが、この少年が現世において居場所がないことを表しているのだ。
理想ではなく、現実は理不尽なことが多いから、日本人はよりリアリティのある作品を嗜好すると思うのだが、どうだろうか。パーティは必ず夫婦同伴、パートナーには定期的に「愛してる」と言葉で言い、「真実の愛・永遠の愛・無限の愛」の実在を疑わず、キリスト教的理想・理念をふりかざす欧米人は、升添要一が言うところの「ええ格好しい・偽善者」なのだろうか?
図左:昇天するネロとパトラッシュ。
写真中:「フランダースの犬」の舞台とされるホーボーケン村のネロとパトラッシュ像。ネロも犬も日本アニメ版のイメージと激しく異なっているとして、新「がっかり名所」になりつつあるようだが、原作のイメージはこうだから仕方がない。
写真右:ノートルダム大聖堂に展示されているルーベンス画「キリストの昇架」(アントワープ)。
ベルギー北部フランドル(英名フランダース)地方在住のベルギー人映画監督が、クリスマスにちなんだ悲運の物語として日本で知られる「フランダースの犬」を“検証”するドキュメンタリー映画を作成した。
物語の主人公ネロと忠犬パトラッシュが、クリスマスイブの夜に力尽きたアントワープの大聖堂で、27日に上映される。映画のタイトルは「パトラッシュ」で、監督はディディエ・ボルカールトさん(36)。制作のきっかけは、大聖堂でルーベンスの絵を見上げ、涙を流す日本人の姿を見たことだったという。
物語では、画家を夢見る少年ネロが、放火のぬれぎぬを着せられて、村を追われ、吹雪の中をさまよった揚げ句、一度見たかったこの絵を目にする。そして誰を恨むこともなく、忠犬とともに天に召される。原作は英国人作家ウィーダが1870年代に書いたが、欧州では、物語は「負け犬の死」(ボルカールトさん)としか映らず、評価されることはなかった。米国では過去に5回映画化されているが、いずれもハッピーエンドに書き換えられた。悲しい結末の原作が、なぜ日本でのみ共感を集めたのかは、長く謎とされてきた。ボルカールトさんらは、3年をかけて謎の解明を試みた。資料発掘や、世界6か国での計100人を超えるインタビューで、浮かび上がったのは、日本人の心に潜む「滅びの美学」だった。
プロデューサーのアン・バンディーンデレンさん(36)は「日本人は、信義や友情のために敗北や挫折を受け入れることに、ある種の崇高さを見いだす。ネロの死に方は、まさに日本人の価値観を体現するもの」と結論づけた。
YouTube - 「フランダースの犬」最終回
http://
「フランダースの犬」原作小説
http://
===============================
●原作のネロは15歳
絵が好きな彼は、仕事を怠けて絵を描くことがあった。この年齢ならば、画家で食っていけないなら観念して就職すればいいものを、自分の意志で就職もせず、食べ物を買うお金で絵の具を買った。悲劇を回避する方法はいくらでもあったのに、彼は自分の意志で教会に行き、ルーベンスの絵の前でのたれ死にする道を選んだのである。堅気の職業を拒否し、最後まで画家として、己の才能を認めない世をはかなんで憤死するのである。これはまさに「負け犬」そのものであり、これでは親たちがこの作品を嫌悪するのも無理はない。
ネロが放火の疑いをかけられたのも、彼が画家を志し15歳にもなって定職に就かず、それでいて金持ちの娘に言い寄ったからだろう。彼は原作では、コンクールで入賞したらアロアを嫁にしてみんなを見返してやろうと考えていた。純真・無欲ではなかったのだ。
ボルカールト監督は、原作と日本アニメの違いは把握していただろうか。
日本アニメではネロは10歳の設定で、定職につくことはできず、親に死なれ、村を追放されれば、のたれ死にするより道はない。子供ならば石にかじりついてでも生き抜くしたたかさよりも、純真さが求められるだろう。そのぶん悲劇性がいっそう際立つ効果を生んだが、親が死んだら孤児院に行くべき年齢に設定してしまったことで、ベルギー人に疑問を抱かせる作品になってしまった。10歳の子供にコンクールで認められる画才があるという設定は、さすがに無理があるだろう。
余談だがオランダの画家ゴッホは、37歳にもなって弟の仕送りで生活しており、存命中は絵が全く売れなかった。
●共同体の絶対化と諦念
ネロは濡れ衣を着せられても村人を恨んだりせず、従容として死を受け容れる。彼は共同体の平和を乱してしまったため、もはや共同体から排除されるしかないのだ(原作では、村の若者みんなが美しくて金持ちのアロアを狙っているので、色男のネロは存在そのものが罪である以上、弁明は無駄である)。彼がそれでも村人に怒れないのは、アロアの家族だからか、それとも「世間」という名の共同体が絶対だからか。
日本人は世間に居場所がなくなると、自殺してしまうようだ。義経しかり、渡辺崋山しかり。日本人は犯した罪より、反省の色がないことの方が罪悪視されてしまうから、相手を恨み復讐する行為は、視聴者の共感を呼ばないだろう。だが主人公のもう一方は動物なので、恨み言を言うことはない。
「パトラッシュ、疲れたろう、僕も疲れたんだ…」
ネロのこの言葉が、全てに対する無抵抗と諦念を示している。
「寒いことも悲しいこともお腹がすくこともない世界」が虚構であり、それが「寒いことも悲しいことも空腹もある」、そしてそれを見捨てる無情な現世への反語だとわかっているから、悲しいのである。昇天してゆくネロがとてもうれしそうに見えることが、この少年が現世において居場所がないことを表しているのだ。
理想ではなく、現実は理不尽なことが多いから、日本人はよりリアリティのある作品を嗜好すると思うのだが、どうだろうか。パーティは必ず夫婦同伴、パートナーには定期的に「愛してる」と言葉で言い、「真実の愛・永遠の愛・無限の愛」の実在を疑わず、キリスト教的理想・理念をふりかざす欧米人は、升添要一が言うところの「ええ格好しい・偽善者」なのだろうか?
図左:昇天するネロとパトラッシュ。
写真中:「フランダースの犬」の舞台とされるホーボーケン村のネロとパトラッシュ像。ネロも犬も日本アニメ版のイメージと激しく異なっているとして、新「がっかり名所」になりつつあるようだが、原作のイメージはこうだから仕方がない。
写真右:ノートルダム大聖堂に展示されているルーベンス画「キリストの昇架」(アントワープ)。
|
|
|
|
コメント(18)
「フランダースの犬」最終回については、日記でいろいろな意見を読みました。
・滅びの美学は日本独自のものではない
・ネロの最期に涙するのは滅びの美学ではなく、ただの同情
・貧しい子供が濡れ衣を着せられて凍死するだけの話は駄作
・原作はイエスの生涯のオマージュ
・ラストシーンはキリスト教ではなく仏教
これらのテーマについて議論していきたいと思います。
興味深い意見を紹介します。
===============================
http://mixi.jp/view_diary.pl?owner_id=7449246&id=665138447
片親どころかおじいさんしか居ないし
あの年になっても自立できない怪しい小僧が、
町の名士の娘を好きになっちゃって
お父様が娘の将来を危惧して小僧を排除しようとする名作だろ?
立場を変えるだけでも
ちょっと物語の性質が変わる。
主人公にしか感情移入できなくなるというのは
海外からみると日本人の特性になるのかもしれない。
だからニュース報道でも
被害者とされる人間にしか目を向けない。
犯人=どんな事情があっても犯罪者なのだ
===============================
この日記、最高でした。
http://mixi.jp/view_diary.pl?owner_id=14379326&id=664897618
精神的な価値観を持つ、日本民族には、
その「正直に生き、だれにも知られずに、この世を去る」
一見負け犬物語の、「その先」にある
「誠実と信仰に生きた者の『勝利の歌』」が
聞こえているのでございましてよ。
『勝利の歌』でございますわ。
死んで、帰天して、
主の御前で「私は、これこれこのように、
正直に、誠実に、信仰心を持って、生きました」
そういう「信仰の姿」を主にご報告しているシーンを
日本人の「洗練された魂」は、見ているのでございます。
「気高さ」
と、言い換えてもよろしいのかもしれませんわねぇ。
日本人は、魂のランクが、違うのざます。
・滅びの美学は日本独自のものではない
・ネロの最期に涙するのは滅びの美学ではなく、ただの同情
・貧しい子供が濡れ衣を着せられて凍死するだけの話は駄作
・原作はイエスの生涯のオマージュ
・ラストシーンはキリスト教ではなく仏教
これらのテーマについて議論していきたいと思います。
興味深い意見を紹介します。
===============================
http://mixi.jp/view_diary.pl?owner_id=7449246&id=665138447
片親どころかおじいさんしか居ないし
あの年になっても自立できない怪しい小僧が、
町の名士の娘を好きになっちゃって
お父様が娘の将来を危惧して小僧を排除しようとする名作だろ?
立場を変えるだけでも
ちょっと物語の性質が変わる。
主人公にしか感情移入できなくなるというのは
海外からみると日本人の特性になるのかもしれない。
だからニュース報道でも
被害者とされる人間にしか目を向けない。
犯人=どんな事情があっても犯罪者なのだ
===============================
この日記、最高でした。
http://mixi.jp/view_diary.pl?owner_id=14379326&id=664897618
精神的な価値観を持つ、日本民族には、
その「正直に生き、だれにも知られずに、この世を去る」
一見負け犬物語の、「その先」にある
「誠実と信仰に生きた者の『勝利の歌』」が
聞こえているのでございましてよ。
『勝利の歌』でございますわ。
死んで、帰天して、
主の御前で「私は、これこれこのように、
正直に、誠実に、信仰心を持って、生きました」
そういう「信仰の姿」を主にご報告しているシーンを
日本人の「洗練された魂」は、見ているのでございます。
「気高さ」
と、言い換えてもよろしいのかもしれませんわねぇ。
日本人は、魂のランクが、違うのざます。
>なんかこの人、結論を決め打ちして後からつじつま合わせたんじゃないか
はじめに日本人の感性は独特だという結論があり、それから日本独自と思われる「滅びの美学」「敗者の矜持」を持ち出している感じがしますね。
先に日本アニメ版を見た人が、原作やアメリカ映画をおかしいというのはいかがなものでしょうか。「ラストサムライ」なんかは日本人から見てかなりおかしく、感情移入を妨げています。
「アルプスの少女ハイジ」は現地調査しているので、スイスの視聴者は日本のアニメだと気づかないほどでしたが、「フランダースの犬」は現地調査がなかったため、ラストシーンはフランダースというよりシベリア、服装もオランダ風です。
>欧州では、物語は「負け犬の死」(ボルカールトさん)としか映らず
主人公が犬だけに“die like a dog”(みじめな死)とどうしても言いたくて、それを「負け犬の死」と誤訳したのではないかという説が2ちゃんねるで流れています。
はじめに日本人の感性は独特だという結論があり、それから日本独自と思われる「滅びの美学」「敗者の矜持」を持ち出している感じがしますね。
先に日本アニメ版を見た人が、原作やアメリカ映画をおかしいというのはいかがなものでしょうか。「ラストサムライ」なんかは日本人から見てかなりおかしく、感情移入を妨げています。
「アルプスの少女ハイジ」は現地調査しているので、スイスの視聴者は日本のアニメだと気づかないほどでしたが、「フランダースの犬」は現地調査がなかったため、ラストシーンはフランダースというよりシベリア、服装もオランダ風です。
>欧州では、物語は「負け犬の死」(ボルカールトさん)としか映らず
主人公が犬だけに“die like a dog”(みじめな死)とどうしても言いたくて、それを「負け犬の死」と誤訳したのではないかという説が2ちゃんねるで流れています。
http://crossroads.journalismcentre.com/2006/a-dog-of-flanders-revisited/
「我々の西洋文化においては、人が死んだらそれは負けを意味する。しかしアジア人は死を失敗と見なさない。誠実な心をもってゴールを追い求めることに全人生を費やすことが、あなたを永遠のヒーローにするだろう。それこそまさにネロがしたことなのだ。」
「敗者の美学」はもう一つの重要な要因かもしれない。日本では敗者が勝者より多くの同情を得る物語が伝統的に存在する。日本人にはそれを表す用語さえある。悲劇のヒーローへの同情を意味する「判官ひいき」である。
なぜ日本人は子供たちに悲しい物語を語るのだろうか。
「それは、文化において子供たちを育てる方法に関係がある」と、発達心理学が専門の武蔵野大学教授高橋アキラ氏は説明する。
日本では、道徳教育と育児の基本原理は感情移入である。子供たちは最初に、他の人々が何を考えるかについて考えて、それからふるまいを決定することを教えられる。両親と教師たちは、こう言うだろう。
「あなたがこのように行動すれば、友だちはどう感じるか考えなさい」あるいは「それではおかあさんが悲しむだろう」。
「しかしアメリカや、おそらくその他の多くの国では、両親と教師たちは権威としてふるまい、単に何が正しく何が間違っているかについて子供たちに語る。道徳の原則は、人間関係の外側に存在する社会的ルールである。日本では、道徳は自分がしつけられたように自分自身をしつけるようなものだと考えられている。そして、人はどの方法が正しいとか好ましいとか断言することはできない。」
高橋は、子供は悲しい感情により深く感情移入する傾向があることを示唆する。それゆえ日本人は、サド・エンドは子供に他者を気づかう方法を教えるための手段の一つとして使えるという理由で、評価しているのだ。
彼は、アメリカの児童教育マニュアルを調査したが、推薦された本のリストには悲しい物語は一つも見つからなかった。
「子供の物語は、夢を与えることになっている。努力は、最終的に成果をあげなければならない。暴力的な映画と同様、悲しい物語はアメリカでは忌避されている。」
高橋は、アンデルセンの有名なサド・エンド・ストーリーである「人魚姫」と「マッチ売りの少女」がアメリカのバージョンにおいてハッピー・エンドに改変されていたことも発見した。
「我々の西洋文化においては、人が死んだらそれは負けを意味する。しかしアジア人は死を失敗と見なさない。誠実な心をもってゴールを追い求めることに全人生を費やすことが、あなたを永遠のヒーローにするだろう。それこそまさにネロがしたことなのだ。」
「敗者の美学」はもう一つの重要な要因かもしれない。日本では敗者が勝者より多くの同情を得る物語が伝統的に存在する。日本人にはそれを表す用語さえある。悲劇のヒーローへの同情を意味する「判官ひいき」である。
なぜ日本人は子供たちに悲しい物語を語るのだろうか。
「それは、文化において子供たちを育てる方法に関係がある」と、発達心理学が専門の武蔵野大学教授高橋アキラ氏は説明する。
日本では、道徳教育と育児の基本原理は感情移入である。子供たちは最初に、他の人々が何を考えるかについて考えて、それからふるまいを決定することを教えられる。両親と教師たちは、こう言うだろう。
「あなたがこのように行動すれば、友だちはどう感じるか考えなさい」あるいは「それではおかあさんが悲しむだろう」。
「しかしアメリカや、おそらくその他の多くの国では、両親と教師たちは権威としてふるまい、単に何が正しく何が間違っているかについて子供たちに語る。道徳の原則は、人間関係の外側に存在する社会的ルールである。日本では、道徳は自分がしつけられたように自分自身をしつけるようなものだと考えられている。そして、人はどの方法が正しいとか好ましいとか断言することはできない。」
高橋は、子供は悲しい感情により深く感情移入する傾向があることを示唆する。それゆえ日本人は、サド・エンドは子供に他者を気づかう方法を教えるための手段の一つとして使えるという理由で、評価しているのだ。
彼は、アメリカの児童教育マニュアルを調査したが、推薦された本のリストには悲しい物語は一つも見つからなかった。
「子供の物語は、夢を与えることになっている。努力は、最終的に成果をあげなければならない。暴力的な映画と同様、悲しい物語はアメリカでは忌避されている。」
高橋は、アンデルセンの有名なサド・エンド・ストーリーである「人魚姫」と「マッチ売りの少女」がアメリカのバージョンにおいてハッピー・エンドに改変されていたことも発見した。
>どうしてこれが負け犬なんでしょうか・・・
世に認められることなく死んで行くからです。原作では、自分の意志で自殺しています。
>彼は自分の考える理想・都合に合わない青年を、アロアから引き離すことに一生懸命だった
その通りです。どちらが言い寄ったかは問題でなく、アロアは娘だから、悪いのは一方的にネロです。
>アロアの父親の不安・心配を理解していたから
父コゼツの娘アロアへの愛は、当然とはいえ、たいへん利己的なものです。
>彼が自分の境遇を受け止め
>村人たちの状況も理解していたからだと思います
ネロはマゾです。また河合隼雄は「日本人の民族性はマゾ」と看過しています。
>どうしてコレが「純粋無垢ではない」と評価されるのかわかりません
純粋に絵を愛したわけでもなく、復讐心と功名心がありました。
15歳の男なら当然でしょう。10歳の子供がこうだったら可愛くないです。
>彼「が」共同体の平和を乱したのではないと思います
客観的にはそうです。しかしネロが村に戻ってきたら、村人たちはみな罪悪感を抱くことになり、耐えられないでしょうから、排除するしかないでしょう。村人たちにとっては、ネロはやっかい者なのです。
これはよくある話だと思います。こういうときに神父が出て来て、村人たちに和解を説いていたらネロは死なずに済んだでしょう。しかし実際には、礼拝堂に勝手に上がり込んでも、死んでも気がつかないような教会でした。
本作はイエスの生涯のオマージュだとする解釈があります。
イエスは親の石工の仕事を継がず、布教活動に執心し、故郷で布教していたら、家族が心配になって見に来たので「ご家族が心配して見に来ていますよ」と言ったら、「私の家族とは誰ですか。私の教えを聞いて守る者が私の家族です」と答えました。イエスの少年時代を知る人々はイエスを神として受け容れませんでしたが、イエスもまた、説教を聞きに来たのではなく(気がふれたと)心配になって来た家族を受け容れませんでした。
当時ユダヤ植民地と宗主国ローマは対立していましたが、イエスはその両者から睨まれ、ユダヤ教徒から「自分をユダヤの王と呼び、皇帝に税を納めることを禁じた」という無実の罪を着せられ、処刑されます。彼が三日目に復活しなかったら、本物の負け犬だったでしょう。
ネロは人を恨まず、仕事をせずに絵を描くことに専念しましたが、村人たちから理解されず、無実の罪を着せられ、拾ったお金で飢えをしのげばいいものを正直に返し、最後はのたれ死にします。彼が最後に見たものは「キリストの昇架」。それは今の世にキリストが登場しても受け容れられないだろう、そして教会で人が凍死しても教会は救えないという皮肉があるのではないでしょうか。
>与えられた枠からはみ出しながらも「思うように」生きたことに感動しました。
>死に直面するほどに疲れ切った飢えた体で、それを満たす物理的な要素の全く無い2枚の絵の前で、最高の幸せを感じた。
>心の豊かさ・自由を最後まで保ったネロの精神の強さに感動しました。
私は美大卒のいっちさんの言葉に、驚愕しています。
作者のウィーダは耽美主義に分類されていますが、彼女自身が理想主義的な作品を書き、そして長い間認められなかったことが、ネロの人格に投影されているのでしょう。
いっちさんのこの言葉こそ、ウィーダがいちばん言いたかったことなのかも知れません。
「思うように生きた」ということであれば、私ほど「思うように生きた」人はほかにいないだろうという自負があります。新潟市で一番大きな○○会社を辞め、単身カナダに渡り、好きな文学をやって過ごす。「負け犬が書く作品」などと言われていますが、いくらはみ出し者の私でも、食っていけなくなるほどのめり込んだりはしません。文学はしょせん、人生を楽しくしてくれるための趣味に過ぎないのですから。
世に認められることなく死んで行くからです。原作では、自分の意志で自殺しています。
>彼は自分の考える理想・都合に合わない青年を、アロアから引き離すことに一生懸命だった
その通りです。どちらが言い寄ったかは問題でなく、アロアは娘だから、悪いのは一方的にネロです。
>アロアの父親の不安・心配を理解していたから
父コゼツの娘アロアへの愛は、当然とはいえ、たいへん利己的なものです。
>彼が自分の境遇を受け止め
>村人たちの状況も理解していたからだと思います
ネロはマゾです。また河合隼雄は「日本人の民族性はマゾ」と看過しています。
>どうしてコレが「純粋無垢ではない」と評価されるのかわかりません
純粋に絵を愛したわけでもなく、復讐心と功名心がありました。
15歳の男なら当然でしょう。10歳の子供がこうだったら可愛くないです。
>彼「が」共同体の平和を乱したのではないと思います
客観的にはそうです。しかしネロが村に戻ってきたら、村人たちはみな罪悪感を抱くことになり、耐えられないでしょうから、排除するしかないでしょう。村人たちにとっては、ネロはやっかい者なのです。
これはよくある話だと思います。こういうときに神父が出て来て、村人たちに和解を説いていたらネロは死なずに済んだでしょう。しかし実際には、礼拝堂に勝手に上がり込んでも、死んでも気がつかないような教会でした。
本作はイエスの生涯のオマージュだとする解釈があります。
イエスは親の石工の仕事を継がず、布教活動に執心し、故郷で布教していたら、家族が心配になって見に来たので「ご家族が心配して見に来ていますよ」と言ったら、「私の家族とは誰ですか。私の教えを聞いて守る者が私の家族です」と答えました。イエスの少年時代を知る人々はイエスを神として受け容れませんでしたが、イエスもまた、説教を聞きに来たのではなく(気がふれたと)心配になって来た家族を受け容れませんでした。
当時ユダヤ植民地と宗主国ローマは対立していましたが、イエスはその両者から睨まれ、ユダヤ教徒から「自分をユダヤの王と呼び、皇帝に税を納めることを禁じた」という無実の罪を着せられ、処刑されます。彼が三日目に復活しなかったら、本物の負け犬だったでしょう。
ネロは人を恨まず、仕事をせずに絵を描くことに専念しましたが、村人たちから理解されず、無実の罪を着せられ、拾ったお金で飢えをしのげばいいものを正直に返し、最後はのたれ死にします。彼が最後に見たものは「キリストの昇架」。それは今の世にキリストが登場しても受け容れられないだろう、そして教会で人が凍死しても教会は救えないという皮肉があるのではないでしょうか。
>与えられた枠からはみ出しながらも「思うように」生きたことに感動しました。
>死に直面するほどに疲れ切った飢えた体で、それを満たす物理的な要素の全く無い2枚の絵の前で、最高の幸せを感じた。
>心の豊かさ・自由を最後まで保ったネロの精神の強さに感動しました。
私は美大卒のいっちさんの言葉に、驚愕しています。
作者のウィーダは耽美主義に分類されていますが、彼女自身が理想主義的な作品を書き、そして長い間認められなかったことが、ネロの人格に投影されているのでしょう。
いっちさんのこの言葉こそ、ウィーダがいちばん言いたかったことなのかも知れません。
「思うように生きた」ということであれば、私ほど「思うように生きた」人はほかにいないだろうという自負があります。新潟市で一番大きな○○会社を辞め、単身カナダに渡り、好きな文学をやって過ごす。「負け犬が書く作品」などと言われていますが、いくらはみ出し者の私でも、食っていけなくなるほどのめり込んだりはしません。文学はしょせん、人生を楽しくしてくれるための趣味に過ぎないのですから。
お初に書き込み失礼します。
『フランダースの犬』に限らず、世界名作劇場では原作をかなり改変してるんですよね。
『アルプスの少女ハイジ』なども、本来はもっと信仰色の強い作品ですし。
『母を訪ねて三千里』に至っては、トリビアでもお馴染み原作は…(笑)
つまり、日本人が日本人向けに(日本人の共感を呼ぶように)アレンジしているのです。そして、そのアレンジは当時(1970年代)の視聴率的に見れば大成功だったわけです。当時だけに限定せず、未だに根強い人気があるのはご存知の通り。
原作とアニメ。
あくまで世界名作劇場全盛期・1970年代の話ではありますが、現在でも原作に対して違和感持つ人が多いわけですから、考え方・感じ方に日本と欧米で大きな相違があるのは事実でしょう。どこを改変したか調べることで、比較文化の有効な一助になるとは思います。
個人的には、アチラから「滅びの美学」と見られるのは分からなくもないです。それが正しいかどうかは別にして。
『フランダースの犬』に限らず、世界名作劇場では原作をかなり改変してるんですよね。
『アルプスの少女ハイジ』なども、本来はもっと信仰色の強い作品ですし。
『母を訪ねて三千里』に至っては、トリビアでもお馴染み原作は…(笑)
つまり、日本人が日本人向けに(日本人の共感を呼ぶように)アレンジしているのです。そして、そのアレンジは当時(1970年代)の視聴率的に見れば大成功だったわけです。当時だけに限定せず、未だに根強い人気があるのはご存知の通り。
原作とアニメ。
あくまで世界名作劇場全盛期・1970年代の話ではありますが、現在でも原作に対して違和感持つ人が多いわけですから、考え方・感じ方に日本と欧米で大きな相違があるのは事実でしょう。どこを改変したか調べることで、比較文化の有効な一助になるとは思います。
個人的には、アチラから「滅びの美学」と見られるのは分からなくもないです。それが正しいかどうかは別にして。
https://serai.jp/hobby/342092
フランダースの犬といえばパトラッシュと少年ネロ。テレビアニメの最後のシーンは、クリスマスの深夜、大聖堂の中でした。力尽きたネロはパトラッシュの背中に手を乗せて言います。「パトラッシュ……疲れたろう。僕も疲れたんだ。なんだかとっても眠いんだ……」。パトラッシュとネロはずっと見たかった絵の前で、眠るように亡くなります。
天使が舞い降り、ふたりを天へと誘う、最後の昇天シーンは、多くの人の心を捉え、「フランダースの犬」は今でも人気の高い作品です。CMを提供したカルピスの会長は敬虔なクリスチャンで、この昇天シーンに流れる曲をアベ・マリアにするようにと、黒田昌太郎監督へ指示を出しました。
司馬遼太郎をして「桃太郎か浦島太郎ほどの知名度がある」(街道をゆく・オランダ紀行)と言わしめたほど、フランダースの犬は日本で特に有名な作品です。しかし、原作の舞台となったベルギーやイギリスなどヨーロッパでは忘れられた存在であることを知って驚いた司馬遼太郎は、「フランダースの犬の謎」という文章を残しました。
■ネロの心情に寄り添えない欧米人の感覚
日本人の心を捉えたこの名作ですが、パトラッシュもネロも死なない、ハッピーエンドの「フランダースの犬」が発刊されていました。1931(昭和6)年、大日本雄弁会講談社発刊「花の首輪」(宇野浩二著)と、1936(昭和11)年、同社刊「フランダースの犬」(池田宣政著)では、大聖堂で横たわっていたネロとパトラッシュは眠りから覚め、立派な馬車に乗って故郷へ帰ります。少年少女向けの物語にする際、なるべく受け入れやすいように変えたのでしょう。ハッピーエンド版を書いた宇野浩二は、「結末は雑誌社の方から頼まれて、直しましたが、これは直した方がよいと思って直しました」と書き残しています。
原作とは異なり、死なないパトラッシュとネロは、日本以外にもたくさん存在しました。アメリカ、イギリスでは映画にもなっています。子供であっても自主独立を目指すべきという考え方が行き渡っているヨーロッパでは、ネロが15歳になってもきちんと自立していない点が理解されず、「ダメな子がダメなまま死ぬ」という物語は、心情的に受け入れ難く、ハッピーエンドに変えたのでしょう。
画家を目指す主人公・ネロはミルク運びの仕事をしていましたが、新しく参入した会社により、職を失います。欧米人の感覚では、これもただ仕事を追われるだけの無能者という印象が強く、前向きに戦ったり、再雇用を請求するような強い意志をもたないネロに共感できません。結局、ハッピーエンドにしなければ、理解しがたい内容でもあり、「フランダースの犬」は時代とともに忘れられた作品となりました。
フランダースの犬といえばパトラッシュと少年ネロ。テレビアニメの最後のシーンは、クリスマスの深夜、大聖堂の中でした。力尽きたネロはパトラッシュの背中に手を乗せて言います。「パトラッシュ……疲れたろう。僕も疲れたんだ。なんだかとっても眠いんだ……」。パトラッシュとネロはずっと見たかった絵の前で、眠るように亡くなります。
天使が舞い降り、ふたりを天へと誘う、最後の昇天シーンは、多くの人の心を捉え、「フランダースの犬」は今でも人気の高い作品です。CMを提供したカルピスの会長は敬虔なクリスチャンで、この昇天シーンに流れる曲をアベ・マリアにするようにと、黒田昌太郎監督へ指示を出しました。
司馬遼太郎をして「桃太郎か浦島太郎ほどの知名度がある」(街道をゆく・オランダ紀行)と言わしめたほど、フランダースの犬は日本で特に有名な作品です。しかし、原作の舞台となったベルギーやイギリスなどヨーロッパでは忘れられた存在であることを知って驚いた司馬遼太郎は、「フランダースの犬の謎」という文章を残しました。
■ネロの心情に寄り添えない欧米人の感覚
日本人の心を捉えたこの名作ですが、パトラッシュもネロも死なない、ハッピーエンドの「フランダースの犬」が発刊されていました。1931(昭和6)年、大日本雄弁会講談社発刊「花の首輪」(宇野浩二著)と、1936(昭和11)年、同社刊「フランダースの犬」(池田宣政著)では、大聖堂で横たわっていたネロとパトラッシュは眠りから覚め、立派な馬車に乗って故郷へ帰ります。少年少女向けの物語にする際、なるべく受け入れやすいように変えたのでしょう。ハッピーエンド版を書いた宇野浩二は、「結末は雑誌社の方から頼まれて、直しましたが、これは直した方がよいと思って直しました」と書き残しています。
原作とは異なり、死なないパトラッシュとネロは、日本以外にもたくさん存在しました。アメリカ、イギリスでは映画にもなっています。子供であっても自主独立を目指すべきという考え方が行き渡っているヨーロッパでは、ネロが15歳になってもきちんと自立していない点が理解されず、「ダメな子がダメなまま死ぬ」という物語は、心情的に受け入れ難く、ハッピーエンドに変えたのでしょう。
画家を目指す主人公・ネロはミルク運びの仕事をしていましたが、新しく参入した会社により、職を失います。欧米人の感覚では、これもただ仕事を追われるだけの無能者という印象が強く、前向きに戦ったり、再雇用を請求するような強い意志をもたないネロに共感できません。結局、ハッピーエンドにしなければ、理解しがたい内容でもあり、「フランダースの犬」は時代とともに忘れられた作品となりました。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ここが変だよ比較文化論 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
ここが変だよ比較文化論のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90036人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6416人
- 3位
- 独り言
- 9044人