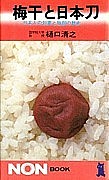カナダ在住日本人はよく「アメリカ・カナダは新興国で伝統がないが、日本は長い伝統のある国だ」と言う。そこでは古いものの良さばかりが強調されているきらいがあるように思うのだが、世界の独立国についてその建国記念日を列挙し、その契機となる事件が起こった年を見てみよう。
★独立を記念するもの(「独立記念日」以外の名称は〔 〕に示した)
・オランダ:1581年7月25日 スペインからの独立を宣言した日。
・アメリカ:1776年7月4日 イギリスからの独立を宣言した日。
・コロンビア:1810年7月20日 スペインから独立した日。
・ベネズエラ〔独立調印記念日〕:1811年7月5日 スペインから独立した日。
・アルゼンチン〔独立宣言の日〕:1816年7月9日 ラプラタ連合がスペインからの独立を宣言した日。革命による自治政府樹立は1810年5月25日。
・ギリシャ:1821年3月25日 ギリシャのゲルマノス総主教がトルコに対し独立を宣言した日。
・ペルー:1821年7月28日 スペインから独立した日。
・グアテマラ:1821年9月12日 スペインから独立した日。
・コスタリカ:1821年9月12日 スペインから独立した日。
・ニカラグア:1821年9月15日 スペインから独立した日。
・ホンジュラス:1821年9月15日 スペインから独立した日。
・エクアドル:1822年8月10日 スペインから独立した日。
・ボリビア:1825年8月6日 スペインから独立した日。
・ベルギー:1831年7月21日 レオポルト1世が初代国王に即位した日。
・南アフリカ:1910年5月31日 大英帝国内の主権国家として独立した日。
・アイスランド:1944年6月17日 自治権運動の指導者ヨン・シグルドソンの誕生日に独立宣言。1874年に自治権獲得し、1918年に事実上独立。
・イスラエル:1948年5月14日 独立を宣言した日。
・セネガル:1960年4月4日 マリ連邦としてフランスから独立した日。
・マリ:1960年9月22日 マリ連邦からセネガルが分離した日。
・アラブ首長国連邦〔連邦結成記念日〕:1971年12月2日 イギリスから独立し首長国連邦を結成した日。
・ロシア〔主権宣言記念日〕:1991年6月12日 ソ連からの独立を宣言した日。
・ウクライナ:1991年8月24日 ソ連からの独立を宣言した日。
★革命を記念するもの(「革命記念日」以外の名称は〔 〕に示した)
・フランス〔国祭日〕:1789年7月14日 パリ市民がバスチーユ牢獄を襲撃して政治犯を解放し、フランス革命が始まった日。日本語での名称は「パリ祭」。
・メキシコ〔独立記念日〕:1810年9月16日 ドロレスの教会からメキシコ独立革命が始まった日。独立は1821年8月24日コルドバ条約が締結された日。
・中華民国〔双十国慶節〕:1911年10月10日 孫文の中国革命同盟会が湖北省武昌で蜂起し辛亥革命が始まった日。
・ハンガリー〔1848年の革命と自由戦争記念日〕:1848年3月15日 ハプスブルグ家支配に対し三月革命を起こした日。オーストリア・ハンガリー帝国からの独立は1918年10月31日。
・エジプト:1952年7月23日 ナセル率いる自由将校団がクーデターで王政を打倒した日(エジプト革命)。独立は1922年2月28日。
・ハンガリー〔1956年革命および共和国宣言の記念日〕:1956年10月23日 共産党の圧政に対し国民が蜂起した「ハンガリー動乱」が勃発した日。
・キューバ〔解放記念日〕:1959年1月1日 キューバ革命を達成した日。
・リビア:1969年9月1日 カダフィ大尉らが無血クーデターで王制を打倒した日。
・ラオス〔建国記念日〕:1975年12月2日 王政を廃止し人民民主共和国を宣言した日。独立は1949年7月19日。
★伝説に基づくもの
・大韓民国〔開天節〕:BC2333年10月3日 檀君が最初の朝鮮人国家を平壌で建国したとされる日。
・日本〔建国記念の日〕:BC660年2月11日(旧暦1月1日) 初代神武天皇が即位したとされる日。
・ハンガリー〔建国記念日(聖イシュトバーンの日)〕:8月20日 初代国王の名がイシュトバーンであることから、聖イシュトバーンの日である8月20日を建国を祝う日とした。
★その他
・アイルランド〔聖パトリックの日〕:461年3月17日 アイルランドの守護聖人聖パトリックの命日。
・スイス〔建国記念日〕:1291年8月1日 スイス誓約同盟が結ばれた日。
・カナダ〔カナダ・デー〕:1867年7月1日 最初の憲法が施行され自治政府が発祥した日。
・オーストラリア〔オーストラリア・デー〕:1888年1月26日 最初の移民団がシドニー湾から上陸した日。
・ポルトガル〔共和国記念日〕:1910年10月5日 クーデターで王政を廃止し、共和制に移行した日。レオンからの独立宣言は1128年、カスティーリャからの独立は1385年。
・ギリシャ〔国家記念日(オーヒデー)〕:1940年10月28日 ギリシャ領の自由な通過を求めたイタリアのムッソリーニに対し、政府が「オーヒ(No)」を宣言した日。
・トルコ〔共和国宣言記念日〕:1923年10月29日 共和国となった日。
・イタリア〔共和国記念日〕:1942年6月2日 国民投票により王制を廃止し共和制に移行することを決定した日。統一国家成立は1861年3月17日。
・アルバニア〔解放記念日〕:1944年11月29日 イタリア軍からの解放を宣言した日。独立は1912年11月28日。
・ベラルーシ〔独立記念日〕:1945年7月3日 首都ミンスクがドイツ軍から解放された日。
・大韓民国〔光復節〕:1945年8月15日 日本国天皇が国民に終戦を告げるラジオ放送を行った日。実際に大韓民国が樹立されたのは、アメリカの軍政が終了し建国の宣布式が挙行された1948年8月13日。
・北朝鮮〔国慶節記念日〕:1948年9月9日 朝鮮民主主義人民共和国建国が宣布された日。
・中華人民共和国〔国慶節〕:1949年10月1日 毛沢東が天安門で建国宣言をした日。
・オーストリア〔建国記念日〕:1955年10月26日 1955年永世中立国を宣言した日。
・タンザニア〔連合記念日〕:1964年4月26日 ザンジバルとタンガニーカが合併しタンザニアを建国した日。
・イラク:1968年7月17日 無血クーデターによってバース党が政権を掌握した日。独立は1932年10月3日。
・ドイツ連邦〔ドイツ統一の日〕:1990年10月3日 東西ドイツが再統一された日。最初のドイツ建国は1871年。
※ハンガリーには3つの建国記念日と2つの国歌がある。
※カナダの独立時期については以下を参照。
http://
★独立を記念するもの(「独立記念日」以外の名称は〔 〕に示した)
・オランダ:1581年7月25日 スペインからの独立を宣言した日。
・アメリカ:1776年7月4日 イギリスからの独立を宣言した日。
・コロンビア:1810年7月20日 スペインから独立した日。
・ベネズエラ〔独立調印記念日〕:1811年7月5日 スペインから独立した日。
・アルゼンチン〔独立宣言の日〕:1816年7月9日 ラプラタ連合がスペインからの独立を宣言した日。革命による自治政府樹立は1810年5月25日。
・ギリシャ:1821年3月25日 ギリシャのゲルマノス総主教がトルコに対し独立を宣言した日。
・ペルー:1821年7月28日 スペインから独立した日。
・グアテマラ:1821年9月12日 スペインから独立した日。
・コスタリカ:1821年9月12日 スペインから独立した日。
・ニカラグア:1821年9月15日 スペインから独立した日。
・ホンジュラス:1821年9月15日 スペインから独立した日。
・エクアドル:1822年8月10日 スペインから独立した日。
・ボリビア:1825年8月6日 スペインから独立した日。
・ベルギー:1831年7月21日 レオポルト1世が初代国王に即位した日。
・南アフリカ:1910年5月31日 大英帝国内の主権国家として独立した日。
・アイスランド:1944年6月17日 自治権運動の指導者ヨン・シグルドソンの誕生日に独立宣言。1874年に自治権獲得し、1918年に事実上独立。
・イスラエル:1948年5月14日 独立を宣言した日。
・セネガル:1960年4月4日 マリ連邦としてフランスから独立した日。
・マリ:1960年9月22日 マリ連邦からセネガルが分離した日。
・アラブ首長国連邦〔連邦結成記念日〕:1971年12月2日 イギリスから独立し首長国連邦を結成した日。
・ロシア〔主権宣言記念日〕:1991年6月12日 ソ連からの独立を宣言した日。
・ウクライナ:1991年8月24日 ソ連からの独立を宣言した日。
★革命を記念するもの(「革命記念日」以外の名称は〔 〕に示した)
・フランス〔国祭日〕:1789年7月14日 パリ市民がバスチーユ牢獄を襲撃して政治犯を解放し、フランス革命が始まった日。日本語での名称は「パリ祭」。
・メキシコ〔独立記念日〕:1810年9月16日 ドロレスの教会からメキシコ独立革命が始まった日。独立は1821年8月24日コルドバ条約が締結された日。
・中華民国〔双十国慶節〕:1911年10月10日 孫文の中国革命同盟会が湖北省武昌で蜂起し辛亥革命が始まった日。
・ハンガリー〔1848年の革命と自由戦争記念日〕:1848年3月15日 ハプスブルグ家支配に対し三月革命を起こした日。オーストリア・ハンガリー帝国からの独立は1918年10月31日。
・エジプト:1952年7月23日 ナセル率いる自由将校団がクーデターで王政を打倒した日(エジプト革命)。独立は1922年2月28日。
・ハンガリー〔1956年革命および共和国宣言の記念日〕:1956年10月23日 共産党の圧政に対し国民が蜂起した「ハンガリー動乱」が勃発した日。
・キューバ〔解放記念日〕:1959年1月1日 キューバ革命を達成した日。
・リビア:1969年9月1日 カダフィ大尉らが無血クーデターで王制を打倒した日。
・ラオス〔建国記念日〕:1975年12月2日 王政を廃止し人民民主共和国を宣言した日。独立は1949年7月19日。
★伝説に基づくもの
・大韓民国〔開天節〕:BC2333年10月3日 檀君が最初の朝鮮人国家を平壌で建国したとされる日。
・日本〔建国記念の日〕:BC660年2月11日(旧暦1月1日) 初代神武天皇が即位したとされる日。
・ハンガリー〔建国記念日(聖イシュトバーンの日)〕:8月20日 初代国王の名がイシュトバーンであることから、聖イシュトバーンの日である8月20日を建国を祝う日とした。
★その他
・アイルランド〔聖パトリックの日〕:461年3月17日 アイルランドの守護聖人聖パトリックの命日。
・スイス〔建国記念日〕:1291年8月1日 スイス誓約同盟が結ばれた日。
・カナダ〔カナダ・デー〕:1867年7月1日 最初の憲法が施行され自治政府が発祥した日。
・オーストラリア〔オーストラリア・デー〕:1888年1月26日 最初の移民団がシドニー湾から上陸した日。
・ポルトガル〔共和国記念日〕:1910年10月5日 クーデターで王政を廃止し、共和制に移行した日。レオンからの独立宣言は1128年、カスティーリャからの独立は1385年。
・ギリシャ〔国家記念日(オーヒデー)〕:1940年10月28日 ギリシャ領の自由な通過を求めたイタリアのムッソリーニに対し、政府が「オーヒ(No)」を宣言した日。
・トルコ〔共和国宣言記念日〕:1923年10月29日 共和国となった日。
・イタリア〔共和国記念日〕:1942年6月2日 国民投票により王制を廃止し共和制に移行することを決定した日。統一国家成立は1861年3月17日。
・アルバニア〔解放記念日〕:1944年11月29日 イタリア軍からの解放を宣言した日。独立は1912年11月28日。
・ベラルーシ〔独立記念日〕:1945年7月3日 首都ミンスクがドイツ軍から解放された日。
・大韓民国〔光復節〕:1945年8月15日 日本国天皇が国民に終戦を告げるラジオ放送を行った日。実際に大韓民国が樹立されたのは、アメリカの軍政が終了し建国の宣布式が挙行された1948年8月13日。
・北朝鮮〔国慶節記念日〕:1948年9月9日 朝鮮民主主義人民共和国建国が宣布された日。
・中華人民共和国〔国慶節〕:1949年10月1日 毛沢東が天安門で建国宣言をした日。
・オーストリア〔建国記念日〕:1955年10月26日 1955年永世中立国を宣言した日。
・タンザニア〔連合記念日〕:1964年4月26日 ザンジバルとタンガニーカが合併しタンザニアを建国した日。
・イラク:1968年7月17日 無血クーデターによってバース党が政権を掌握した日。独立は1932年10月3日。
・ドイツ連邦〔ドイツ統一の日〕:1990年10月3日 東西ドイツが再統一された日。最初のドイツ建国は1871年。
※ハンガリーには3つの建国記念日と2つの国歌がある。
※カナダの独立時期については以下を参照。
http://
|
|
|
|
コメント(18)
伝説に基づくものを除いて、建国記念日が最も古いのはスイスの1291年であり、それより古い国は現存していないか、あるいは現存していても「建国」や「独立」の概念がなかったものと思われる。こうして見ると、建国を紀元前にまで遡った韓国と日本の異常な古さが際立っているのがわかるだろう。
日本の建国がBC660年2月11日といっても、翌年のこの日から毎年祝っているわけではない。日本で最初に建国記念日が祝われたのは1874年のことであり、これ以前に建国を祝うという発想はなかった。そもそも日本の統一国家成立が明治初年と考えられ、国旗・国歌の制定、議会開設、憲法発布、いずれも明治以降のことであり、日本人に国家意識が形成されるのも明治以降と断言してよい。こう考えてみると、記録に残る歴史の長さや、建国記念日の古さに関係なく、日本における統一国家成立は欧米より遅いということが浮き彫りになってくるのである。
保守派の中には日本の長い歴史と伝統をやけに強調する者がいて、「日本の統一国家成立は欧米より後」などと言うと地団駄踏んでくやしがるのではないかと想像するが、私の意見はむしろ逆である。
日本の建国がBC660年2月11日といっても、翌年のこの日から毎年祝っているわけではない。日本で最初に建国記念日が祝われたのは1874年のことであり、これ以前に建国を祝うという発想はなかった。そもそも日本の統一国家成立が明治初年と考えられ、国旗・国歌の制定、議会開設、憲法発布、いずれも明治以降のことであり、日本人に国家意識が形成されるのも明治以降と断言してよい。こう考えてみると、記録に残る歴史の長さや、建国記念日の古さに関係なく、日本における統一国家成立は欧米より遅いということが浮き彫りになってくるのである。
保守派の中には日本の長い歴史と伝統をやけに強調する者がいて、「日本の統一国家成立は欧米より後」などと言うと地団駄踏んでくやしがるのではないかと想像するが、私の意見はむしろ逆である。
新しくできたものの方が、古いものより精巧にできているはずだというのが私の考えである。1870年代の明治維新と1940年代のGHQによる昭和改革、80年を隔てた二度の大改革が、近代日本を古き因習から完全に解き放ち、戦後世界の勝利者の地位にのし上げたのである。日本は決して、古臭い国ではない。
明治維新において、国民皆兵の妨げになるという理由で武士は廃止された。アメリカでは今日も実現していない国民の武装解除がこのとき行われ、ちょんまげ・俸禄が廃止されたばかりか、藩も藩主も廃止され、武士以上の特権だった苗字も全ての市民に認められた。こうして形式だけになった士族と華族は、次の昭和改革によって完全に消滅し、世界でも稀な平等国家が実現したのである。
昭和改革では財閥解体が行われた。旧財閥は金融資本と産業資本が結びつき、そのうえ政党と癒着していたのである。財閥解体によって松下・ソニー・オムロン・富士通・沖電気など、優秀な技術と国際競争力を持った新しい企業家の台頭が促された。財閥が存続していたら、彼ら新興企業家はつぶされていた可能性があるのだ。
戦後日本は敗戦により植民地を喪失したが、教育と産業において成功を収め、経済・文化大国となった。植民地はそれを維持する海軍費が莫大なものになるが、全て放棄したことにより植民地防衛の負担がなくなり、内地への投資が促されたという点も見逃せない(1950年代に中東で大規模な油田が発見され、安価で安定した供給が保障されたことも植民地のない日本には福音だった)。戦後日本は、教育においても産業においても広く人材を募り、努力すればのし上がれる競争原理を重んじた社会となったのである。身分制度はもはや邪魔なだけであろう。
明治維新は外国の侵略の恐怖から行われた政策であり、昭和改革も占領軍ゆえにできた政策だろう。だが世界には未だ貴族制や貴族院のある国、成文憲法のない国、採算が取れないのに意地で植民地を手放せない国、国民が銃で武装している国、スラム街に生まれたら教育も受けられず一生浮かばれない国が存在する。戦争に負けたことのない国、侵略の恐怖に晒されたことのない国は、自らを改革することができずにいるのだ。
昭和改革は残念ながら日本人自身の手によるものではなく、外国勢力によるものだった。保守派の中にはそれを針小棒大にとりあげ、「昭和改革は日本の伝統を破壊し、日本人の魂を抜き去って外国文化を植え付けようとした陰謀だ」などと観念論的批判をする者がいる。だがそのような人は、「国産のものは何でも良く、外来のものは何でも悪い」、「古いものは何でも良く、新しいものは何でも悪い」という信念に、理由なく取りつかれているのだ。
アメリカ・カナダを新興国と侮り、彼らにない日本の古さにばかりこだわるのはやめて、日本の新しさに目を向けるとともに、明治・昭和の近代二大改革を改めて評価したい。
明治維新において、国民皆兵の妨げになるという理由で武士は廃止された。アメリカでは今日も実現していない国民の武装解除がこのとき行われ、ちょんまげ・俸禄が廃止されたばかりか、藩も藩主も廃止され、武士以上の特権だった苗字も全ての市民に認められた。こうして形式だけになった士族と華族は、次の昭和改革によって完全に消滅し、世界でも稀な平等国家が実現したのである。
昭和改革では財閥解体が行われた。旧財閥は金融資本と産業資本が結びつき、そのうえ政党と癒着していたのである。財閥解体によって松下・ソニー・オムロン・富士通・沖電気など、優秀な技術と国際競争力を持った新しい企業家の台頭が促された。財閥が存続していたら、彼ら新興企業家はつぶされていた可能性があるのだ。
戦後日本は敗戦により植民地を喪失したが、教育と産業において成功を収め、経済・文化大国となった。植民地はそれを維持する海軍費が莫大なものになるが、全て放棄したことにより植民地防衛の負担がなくなり、内地への投資が促されたという点も見逃せない(1950年代に中東で大規模な油田が発見され、安価で安定した供給が保障されたことも植民地のない日本には福音だった)。戦後日本は、教育においても産業においても広く人材を募り、努力すればのし上がれる競争原理を重んじた社会となったのである。身分制度はもはや邪魔なだけであろう。
明治維新は外国の侵略の恐怖から行われた政策であり、昭和改革も占領軍ゆえにできた政策だろう。だが世界には未だ貴族制や貴族院のある国、成文憲法のない国、採算が取れないのに意地で植民地を手放せない国、国民が銃で武装している国、スラム街に生まれたら教育も受けられず一生浮かばれない国が存在する。戦争に負けたことのない国、侵略の恐怖に晒されたことのない国は、自らを改革することができずにいるのだ。
昭和改革は残念ながら日本人自身の手によるものではなく、外国勢力によるものだった。保守派の中にはそれを針小棒大にとりあげ、「昭和改革は日本の伝統を破壊し、日本人の魂を抜き去って外国文化を植え付けようとした陰謀だ」などと観念論的批判をする者がいる。だがそのような人は、「国産のものは何でも良く、外来のものは何でも悪い」、「古いものは何でも良く、新しいものは何でも悪い」という信念に、理由なく取りつかれているのだ。
アメリカ・カナダを新興国と侮り、彼らにない日本の古さにばかりこだわるのはやめて、日本の新しさに目を向けるとともに、明治・昭和の近代二大改革を改めて評価したい。
●日本国憲法は斬新か
世界の独立国の憲法について、制定した年と改正状況について見てみよう。
順位 制定年 国 名 改正状況
1 1787 アメリカ 1992年までに18回、27ヶ条の追補
2 1814 ノルウェー 1995年までに139回、256ヶ条の改正
3 1831 ベルギー 大きく5次の改正、1993年に大改正
4 1868 ルクセンブルグ 1983年までに9回改正
5 1874 スイス 1997年までに132回改正
〜〜〜
15 1946 日 本 改正なし
〜〜〜
17 1947 イタリア 1993年までに6回改正
18 1949 ドイツ 1998年までに46回改正
伝統のない国と思われているアメリカが、立憲政治と大統領制については世界のパイオニアである。戦後成立の新興国でない日・独・伊三国の憲法がなぜ新しいかについては、説明の必要はないだろう。
こう並べてみると、日本国憲法は新しいように見える。だが最後に改正された日をもって憲法成立の日とした場合、どうなるだろうか。制定されてから一度も改正されていない日本国憲法が、一番古くなるのである。
1940年代に制定され、一度も改正されていない日本国憲法には、アクセス権やプライバシー権は想定されていない。一例を挙げると「石に泳ぐ魚」訴訟では、作家の表現の自由と小説のモデルになった人物のプライバシー権が争われ、作家の敗訴となった。法律論では、明記されてないからといって保障されないわけではなく、憲法第13条「幸福追求権」の拡大解釈で問題ないのだが、ディベートの立場からすれば、一方の主張は明記されていて、もう一方の主張は明記されていないとなれば、どちらが勝利するかは明白であろう。日本国憲法はほかにも外国人の権利、高齢者・身体障害者の保護、公用語、議会解散権などの規定を欠いている。
日本国憲法は、ある人々が思うほど新しくもなければ斬新でもないだろう。だがそれより、自国の憲法を「外来の新参者」の如く扱い、内容に関係なく批判する者がいるのは困ったものである。
世界の独立国の憲法について、制定した年と改正状況について見てみよう。
順位 制定年 国 名 改正状況
1 1787 アメリカ 1992年までに18回、27ヶ条の追補
2 1814 ノルウェー 1995年までに139回、256ヶ条の改正
3 1831 ベルギー 大きく5次の改正、1993年に大改正
4 1868 ルクセンブルグ 1983年までに9回改正
5 1874 スイス 1997年までに132回改正
〜〜〜
15 1946 日 本 改正なし
〜〜〜
17 1947 イタリア 1993年までに6回改正
18 1949 ドイツ 1998年までに46回改正
伝統のない国と思われているアメリカが、立憲政治と大統領制については世界のパイオニアである。戦後成立の新興国でない日・独・伊三国の憲法がなぜ新しいかについては、説明の必要はないだろう。
こう並べてみると、日本国憲法は新しいように見える。だが最後に改正された日をもって憲法成立の日とした場合、どうなるだろうか。制定されてから一度も改正されていない日本国憲法が、一番古くなるのである。
1940年代に制定され、一度も改正されていない日本国憲法には、アクセス権やプライバシー権は想定されていない。一例を挙げると「石に泳ぐ魚」訴訟では、作家の表現の自由と小説のモデルになった人物のプライバシー権が争われ、作家の敗訴となった。法律論では、明記されてないからといって保障されないわけではなく、憲法第13条「幸福追求権」の拡大解釈で問題ないのだが、ディベートの立場からすれば、一方の主張は明記されていて、もう一方の主張は明記されていないとなれば、どちらが勝利するかは明白であろう。日本国憲法はほかにも外国人の権利、高齢者・身体障害者の保護、公用語、議会解散権などの規定を欠いている。
日本国憲法は、ある人々が思うほど新しくもなければ斬新でもないだろう。だがそれより、自国の憲法を「外来の新参者」の如く扱い、内容に関係なく批判する者がいるのは困ったものである。
何を以て古い国とするかというところから始まっちゃうと思うのですが、
・家系に基づく国家元首を戴く
・小国が合併し統一国家を形成
・もともと海によって隔てられ、国境を意識する必要が比較的少ない
あたりからイギリスに近い気もします。
イギリスは建国記念日がないそうですが、彼の国の伝統はどうでしょう。
また中国地域は秦が統一したとされています。
その後は北方・中原・南方の民族がかわりばんこに征服し統一国家を形成してきたので、中華人民共和国の「建国時期」と「伝統国であるか」という判定は一致しない気がします。
日本もむしろ「2000年の歴史の中で、ここ140年ほど空白ができた」程度なのかも知れません。
さらに米国は建国当初は東部の13州のみであり、その後先住民族を平らげて範囲を広げたという経緯は、大和朝廷とあまり変わらない気がします。
2000年後には「初代ワシントホホノミコト」なんて伝説になってるかも。(笑)
・家系に基づく国家元首を戴く
・小国が合併し統一国家を形成
・もともと海によって隔てられ、国境を意識する必要が比較的少ない
あたりからイギリスに近い気もします。
イギリスは建国記念日がないそうですが、彼の国の伝統はどうでしょう。
また中国地域は秦が統一したとされています。
その後は北方・中原・南方の民族がかわりばんこに征服し統一国家を形成してきたので、中華人民共和国の「建国時期」と「伝統国であるか」という判定は一致しない気がします。
日本もむしろ「2000年の歴史の中で、ここ140年ほど空白ができた」程度なのかも知れません。
さらに米国は建国当初は東部の13州のみであり、その後先住民族を平らげて範囲を広げたという経緯は、大和朝廷とあまり変わらない気がします。
2000年後には「初代ワシントホホノミコト」なんて伝説になってるかも。(笑)
>1
>そもそも日本の統一国家成立が明治初年と考えられ
統一国家の基準が曖昧ではないでしょうか?
国司のように中央から地方の行政官を派遣したのが、
7世紀末ですので、
すでに統一国家と言ってもいいと思いますが。
>2
>新しくできたものの方が、古いものより精巧にできているはずだというのが私の考えである。
社会主義は、資本主義よりも新しく採用された国家体制ですが
うまくいかなかったことは、歴史が示していますよね。
改良を常に考えることが、重要なファクターではないかと。
>3
>だがそれより、自国の憲法を「外来の新参者」の如く扱い、内容に関係なく批判する者がいるのは困ったものである。
確かにいるのでしょうが、
あまり、こういう人は聞いたことがないですし、
いたとしても、改憲論者の中でも、相手にされないのでは?
多くの改憲賛成派の論点は、ほぼ9条の内容についてだと思います。
>そもそも日本の統一国家成立が明治初年と考えられ
統一国家の基準が曖昧ではないでしょうか?
国司のように中央から地方の行政官を派遣したのが、
7世紀末ですので、
すでに統一国家と言ってもいいと思いますが。
>2
>新しくできたものの方が、古いものより精巧にできているはずだというのが私の考えである。
社会主義は、資本主義よりも新しく採用された国家体制ですが
うまくいかなかったことは、歴史が示していますよね。
改良を常に考えることが、重要なファクターではないかと。
>3
>だがそれより、自国の憲法を「外来の新参者」の如く扱い、内容に関係なく批判する者がいるのは困ったものである。
確かにいるのでしょうが、
あまり、こういう人は聞いたことがないですし、
いたとしても、改憲論者の中でも、相手にされないのでは?
多くの改憲賛成派の論点は、ほぼ9条の内容についてだと思います。
●街並み・景観の保護について
http://mixi.jp/view_bbs.pl?page=1&comm_id=87326&id=41411784
14 May
日本の景観に関して補足ですが、敗戦が日本の多くの人に与えた心理的な影響も関係が深いのではないかな、と最近考えています。今の若い人は、戦争で嫌な思いをしていないから、素直に日本の昔の景観や昔の物に向き合えるのだと思います。私の周囲で日本の昔のものや昔の風景がすきなのは、30代とか20代の若い子や、海外生活した人ばかりです。親の世代や親戚達は、食べ物は別として、日本の建物とか神社仏閣(葬式のときは別として)にはあんまり興味がないです。
私の親や親戚は、なんでも西洋のもの、特にアメリカのものが好きです。旅行に行く時も、老舗旅館や昔ながらの観光地など物凄く嫌がります。都会のでかいビルや、西洋風のレストランが好みです。海外旅行するときも西洋に行きたがります。
私はアメリカとイギリスとイタリアに住みましたが、戦勝国のアメリカもイギリスも、戦前の建物や分野に対する抵抗がまったくありません。戦前と戦後がつながっています。戦争自体を肯定する雰囲気だってあります。様々な戦争博物館に行っても「戦争は悪い」と書いてある展示は殆どないです。「わが国は一生懸命戦いました。昔の人は偉い。英雄をたたえましょう」みたいな展示しかないです。そして「悪いのは全部ナチと敵国日本です」と展示されています。
私が住んでいるイギリスのヨークと言う町では、夏に開催される地元のミリタリーフェスティバルには一般市民も参加して町中に戦争中の兵士が練り歩き、空には第二次世界大戦中のクラッシク飛行機(個人コレクター所有)が飛び交うほどです。戦争中の蛮行や価値観、建物を否定する動きは一切ありません。日本でこんな祭りをやったら、国を挙げての大騒動になるでしょう。
でもイタリアでは、ファシスト時代の考え方や建造物を肯定する人は誰もいません。私が住んでいたローマにはムッソリーニが建築した建物が沢山建っています。ある意味歴史的建造物ですけども、「とっとと爆破してしまえ」と言う人が多い程です。建物ひとつは誰も使う人がいないから、国連に無償で寄贈されました。誰もあの時代には良い思い出がないから、一国も早く消し去りたいと思ってる人が多いです。
日本は戦後、戦争前の価値観や社会、戦争に向かっていた社会を否定する考え方の人が大半だったそうです。特に戦後すぐはすごかった。ジョン・ダワーというアメリカ人の歴史学者の本を読むと、当時の日本人の多くは、日本語などやめて英語を国語にしてしまえとか、古いものは全部壊したほうが良いといっている人が本当に多かったらしくびっくりします。一般庶民がみんなそんな感じだったそうです。みんな戦争中に相当嫌な思いをしたからなのでしょう。マッカーサーには「日本を変えてくれ」と直訴する手紙が数万通単位で届いたそうです。
軍人だったうちのお爺さん、戦争でおじいさんが死んだ母方の御婆さん、軍国教育で嫌な思いをした叔父や叔母達は、日本食は好きだけど、西洋から来たもの、新しいもの、新しい建物が好きです。日本風な風景には懐かしい思い出はあるけども、昔を思い出したくない、という考え方が強かったみたいです。おじいさんもおばあさんも戦争中のもの、戦前のものは、着物などは残して、みんな捨てちゃいました。見ると昔を思い出すので嫌だそうです。
日本で戦後、古い建物があっけなく壊されたり、町がドンドン新しくなっていたのには、都市計画や建築、社会インフラの整備に関わっていた人達が「古いものは嫌だ」「西洋風のものが良い」「日本式は間違っていた」という考え方があったからではないかなと思っています。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?page=1&comm_id=87326&id=41411784
14 May
日本の景観に関して補足ですが、敗戦が日本の多くの人に与えた心理的な影響も関係が深いのではないかな、と最近考えています。今の若い人は、戦争で嫌な思いをしていないから、素直に日本の昔の景観や昔の物に向き合えるのだと思います。私の周囲で日本の昔のものや昔の風景がすきなのは、30代とか20代の若い子や、海外生活した人ばかりです。親の世代や親戚達は、食べ物は別として、日本の建物とか神社仏閣(葬式のときは別として)にはあんまり興味がないです。
私の親や親戚は、なんでも西洋のもの、特にアメリカのものが好きです。旅行に行く時も、老舗旅館や昔ながらの観光地など物凄く嫌がります。都会のでかいビルや、西洋風のレストランが好みです。海外旅行するときも西洋に行きたがります。
私はアメリカとイギリスとイタリアに住みましたが、戦勝国のアメリカもイギリスも、戦前の建物や分野に対する抵抗がまったくありません。戦前と戦後がつながっています。戦争自体を肯定する雰囲気だってあります。様々な戦争博物館に行っても「戦争は悪い」と書いてある展示は殆どないです。「わが国は一生懸命戦いました。昔の人は偉い。英雄をたたえましょう」みたいな展示しかないです。そして「悪いのは全部ナチと敵国日本です」と展示されています。
私が住んでいるイギリスのヨークと言う町では、夏に開催される地元のミリタリーフェスティバルには一般市民も参加して町中に戦争中の兵士が練り歩き、空には第二次世界大戦中のクラッシク飛行機(個人コレクター所有)が飛び交うほどです。戦争中の蛮行や価値観、建物を否定する動きは一切ありません。日本でこんな祭りをやったら、国を挙げての大騒動になるでしょう。
でもイタリアでは、ファシスト時代の考え方や建造物を肯定する人は誰もいません。私が住んでいたローマにはムッソリーニが建築した建物が沢山建っています。ある意味歴史的建造物ですけども、「とっとと爆破してしまえ」と言う人が多い程です。建物ひとつは誰も使う人がいないから、国連に無償で寄贈されました。誰もあの時代には良い思い出がないから、一国も早く消し去りたいと思ってる人が多いです。
日本は戦後、戦争前の価値観や社会、戦争に向かっていた社会を否定する考え方の人が大半だったそうです。特に戦後すぐはすごかった。ジョン・ダワーというアメリカ人の歴史学者の本を読むと、当時の日本人の多くは、日本語などやめて英語を国語にしてしまえとか、古いものは全部壊したほうが良いといっている人が本当に多かったらしくびっくりします。一般庶民がみんなそんな感じだったそうです。みんな戦争中に相当嫌な思いをしたからなのでしょう。マッカーサーには「日本を変えてくれ」と直訴する手紙が数万通単位で届いたそうです。
軍人だったうちのお爺さん、戦争でおじいさんが死んだ母方の御婆さん、軍国教育で嫌な思いをした叔父や叔母達は、日本食は好きだけど、西洋から来たもの、新しいもの、新しい建物が好きです。日本風な風景には懐かしい思い出はあるけども、昔を思い出したくない、という考え方が強かったみたいです。おじいさんもおばあさんも戦争中のもの、戦前のものは、着物などは残して、みんな捨てちゃいました。見ると昔を思い出すので嫌だそうです。
日本で戦後、古い建物があっけなく壊されたり、町がドンドン新しくなっていたのには、都市計画や建築、社会インフラの整備に関わっていた人達が「古いものは嫌だ」「西洋風のものが良い」「日本式は間違っていた」という考え方があったからではないかなと思っています。
>2
>日本は決して、古臭い国ではない。
制度としての日本国は古臭くないのですが、そこに住む日本人が古臭い。
あまりよい比喩ではないのですが、日本国が人の体だとすると、日本人は癌細胞のようなものなのでは。日本人が目指したいものは、日本国が目指したいものとは方向が違っているというか。
また、あまりよい比喩ではありませんが、日本国が人の体だとすると、日本人は寄生虫のようなものなのでは。日本人は、日本国内に住んでいるのだが十分に日本国の一部になっていない。
近代二大改革によって日本国側がサイボーグみたいになっていて、とても“新しい”ので、生身の日本人がついていけないということなのかもしれません。
さてこれから先の日本では、“日本国”側が勝つのか“日本人”側が勝つのか?
個人的には“日本国”側に加担したいですが、日本国を古臭い国に戻したいと考える日本人はたくさんおられますね。世界に向かって古さを誇示できれば幸せを感じられるということなんでしょうね。
>日本は決して、古臭い国ではない。
制度としての日本国は古臭くないのですが、そこに住む日本人が古臭い。
あまりよい比喩ではないのですが、日本国が人の体だとすると、日本人は癌細胞のようなものなのでは。日本人が目指したいものは、日本国が目指したいものとは方向が違っているというか。
また、あまりよい比喩ではありませんが、日本国が人の体だとすると、日本人は寄生虫のようなものなのでは。日本人は、日本国内に住んでいるのだが十分に日本国の一部になっていない。
近代二大改革によって日本国側がサイボーグみたいになっていて、とても“新しい”ので、生身の日本人がついていけないということなのかもしれません。
さてこれから先の日本では、“日本国”側が勝つのか“日本人”側が勝つのか?
個人的には“日本国”側に加担したいですが、日本国を古臭い国に戻したいと考える日本人はたくさんおられますね。世界に向かって古さを誇示できれば幸せを感じられるということなんでしょうね。
●産経ニュースより引用
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130503/plc13050321080015-n1.htm
日本国憲法は改正が極めて困難な憲法といわれるが、世界の憲法改正動向を見ると、諸外国は状況に応じて柔軟に憲法改正を図っている。一度も改正が図られていない日本国憲法は内外の諸困難に対応できないまま未改正の成文憲法では世界最古の法典となっており、今や世界から取り残されつつある。
諸外国の憲法改正状況を見てみよう。西修駒沢大学名誉教授の昨年11月末時点でのまとめでは、1787年に制定された米国合衆国憲法は1992年5月までに18回改正し、この間27カ条を追補した。ベルギーも1996年3月から2008年12月までに24回改正。ルクセンブルクは09年3月までに34回、ドイツは09年7月までに57回、フランスも08年7月までに24回といった具合だ。
西教授は「世界の趨勢(すうせい)は、憲法を状況に応じて柔軟かつ頻繁に改正を図っている」と指摘する。日本国憲法は世界の成文憲法を保有する188カ国で古い方から14番目で、改正されていない成文憲法のなかでは「世界最古の法典」となっている。
改正を阻む最大の理由は、現行憲法96条に衆参両院で総議員の3分の2以上の賛成がなければ改正の発議すらできないことだ。世論調査では憲法改正を支持する国民は半数を超えている。ところが、国会の一院でわずか3分の1を超える反対があれば頓挫し、“門前払い”となってしまう。
憲法改正の際には国民投票が必要であると憲法条文にうたわれているにもかかわらず、具体的な国民投票について定めた法律ができたのは平成19年になってからだ。
「憲法が主権者である国民のものになっていないのです。そもそも、この条項は日本の無力化を企図したGHQ(連合国軍総司令部)が改正をより困難にしようという意図でわざわざ厳し過ぎる条件を課した。このことを国民は主権者として深刻に考える必要がある」と話すのは、日本大学の百地章教授だ。
「憲法とは状況に応じ、改正を重ねながら国民と国家を守る統治のルールなのだから、不都合があれば当たり前に変えるべきで、少なくとも世界はそう考えている」と語る。さらに「中国や北朝鮮の脅威が増し、東日本大震災など国家の危機に現行憲法が対処できないことが明白なのに、現行憲法を不可侵の不磨の大典として指一本触れてはいけないかのようになっているのはおかしなことだ」と訴える。
===========================
表に「日本国憲法は世界の成文憲法保有188カ国中、古い方から14番目」とあるのは、「現存する憲法」のことであり、大日本帝国憲法など現存しないものは数えていない。
カナダの1867年憲法が抜けているのは、1982年の新憲法が制定されたことで無効になったと誤解されているのだろう。1867年憲法第37条には議会の議席配分が規定されており、しかも第51条第1項で10年ごとの人口調査で定数是正を義務づけていることから、頻繁に改正されており、最近の改正は2011年である。
(http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=1611536&page=3&id=65191202 参照)
カナダ憲法改正は、(1)連邦議会の上院・下院の過半数の同意と、(2)3分の2以上の州議会の同意を必要とし、かつそれらの州の人口が全州人口の50%以上でなければならない。州は10 あるから、3分の2以上とは7州以上のことであるが、オンタリオ州(人口比38%)とケベック州(人口比23%)の中部2州の人口が突出して多いことから、実質的に改正には「中部1州とその他6州」の同意を必要とする。ケベック州は以前から、憲法改正に関する「ケベックの拒否権」を要求しているが、現実は中部州には2分の1の拒否権があるに等しい。
これに加えて、(3)カナダ全州ではなく特定の州のみに関する条項の改正には、その州の議会の同意を必要とする。なおカナダ憲法改正には、国民投票が課せられないことに注意されたい。1992年には憲法改正の是非を問う国民投票が実施されたが、圧倒的多数で否決された。
(http://mixi.jp/view_bbs.pl?page=1&comm_id=1611536&id=30263863 の9〜12参照)
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130503/plc13050321080015-n1.htm
日本国憲法は改正が極めて困難な憲法といわれるが、世界の憲法改正動向を見ると、諸外国は状況に応じて柔軟に憲法改正を図っている。一度も改正が図られていない日本国憲法は内外の諸困難に対応できないまま未改正の成文憲法では世界最古の法典となっており、今や世界から取り残されつつある。
諸外国の憲法改正状況を見てみよう。西修駒沢大学名誉教授の昨年11月末時点でのまとめでは、1787年に制定された米国合衆国憲法は1992年5月までに18回改正し、この間27カ条を追補した。ベルギーも1996年3月から2008年12月までに24回改正。ルクセンブルクは09年3月までに34回、ドイツは09年7月までに57回、フランスも08年7月までに24回といった具合だ。
西教授は「世界の趨勢(すうせい)は、憲法を状況に応じて柔軟かつ頻繁に改正を図っている」と指摘する。日本国憲法は世界の成文憲法を保有する188カ国で古い方から14番目で、改正されていない成文憲法のなかでは「世界最古の法典」となっている。
改正を阻む最大の理由は、現行憲法96条に衆参両院で総議員の3分の2以上の賛成がなければ改正の発議すらできないことだ。世論調査では憲法改正を支持する国民は半数を超えている。ところが、国会の一院でわずか3分の1を超える反対があれば頓挫し、“門前払い”となってしまう。
憲法改正の際には国民投票が必要であると憲法条文にうたわれているにもかかわらず、具体的な国民投票について定めた法律ができたのは平成19年になってからだ。
「憲法が主権者である国民のものになっていないのです。そもそも、この条項は日本の無力化を企図したGHQ(連合国軍総司令部)が改正をより困難にしようという意図でわざわざ厳し過ぎる条件を課した。このことを国民は主権者として深刻に考える必要がある」と話すのは、日本大学の百地章教授だ。
「憲法とは状況に応じ、改正を重ねながら国民と国家を守る統治のルールなのだから、不都合があれば当たり前に変えるべきで、少なくとも世界はそう考えている」と語る。さらに「中国や北朝鮮の脅威が増し、東日本大震災など国家の危機に現行憲法が対処できないことが明白なのに、現行憲法を不可侵の不磨の大典として指一本触れてはいけないかのようになっているのはおかしなことだ」と訴える。
===========================
表に「日本国憲法は世界の成文憲法保有188カ国中、古い方から14番目」とあるのは、「現存する憲法」のことであり、大日本帝国憲法など現存しないものは数えていない。
カナダの1867年憲法が抜けているのは、1982年の新憲法が制定されたことで無効になったと誤解されているのだろう。1867年憲法第37条には議会の議席配分が規定されており、しかも第51条第1項で10年ごとの人口調査で定数是正を義務づけていることから、頻繁に改正されており、最近の改正は2011年である。
(http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=1611536&page=3&id=65191202 参照)
カナダ憲法改正は、(1)連邦議会の上院・下院の過半数の同意と、(2)3分の2以上の州議会の同意を必要とし、かつそれらの州の人口が全州人口の50%以上でなければならない。州は10 あるから、3分の2以上とは7州以上のことであるが、オンタリオ州(人口比38%)とケベック州(人口比23%)の中部2州の人口が突出して多いことから、実質的に改正には「中部1州とその他6州」の同意を必要とする。ケベック州は以前から、憲法改正に関する「ケベックの拒否権」を要求しているが、現実は中部州には2分の1の拒否権があるに等しい。
これに加えて、(3)カナダ全州ではなく特定の州のみに関する条項の改正には、その州の議会の同意を必要とする。なおカナダ憲法改正には、国民投票が課せられないことに注意されたい。1992年には憲法改正の是非を問う国民投票が実施されたが、圧倒的多数で否決された。
(http://mixi.jp/view_bbs.pl?page=1&comm_id=1611536&id=30263863 の9〜12参照)
憲法も法律である以上、議会の過半数のみで改正できる国もあるが、国民投票を課すことで「二重の鍵」を設定することが特別おかしなことだとは思わない。ただし、「両議院の3分の2」条件は不必要なほど高いと感じる。憲法改正の賛成論も反対論も意見として等しい価値があるべきであり、反対派は3分の1でいいが賛成派は3分の2なければならないというのは、反対派の1票の価値が賛成派の2倍あることになるから、「法の下に平等」の観点からは異議がある。
私は日本国憲法は、世界の憲法の中では改正困難な方に属していると評価するが、世界一困難というほどではない。よって上掲サンケイ記事中にある「改正を阻む最大の理由は、現行憲法96条に衆参両院で総議員の3分の2以上の賛成がなければ改正の発議すらできないことだ」という指摘には、同意できない。
そもそも、憲法が一度も改正されていないという理由で、日本が「世界から取り残されつつある」という事実はない。たとえ「二重の鍵」があっても、国民が改正を望むならすでに改正されているはずであり、憲法改正を争点とした選挙は一度も行われたことがない以上、国民の多くは憲法改正に関心がなかったから改正されなかったのだとしか言いようがない。憲法改正を問う国会の決議も、憲法施行以来一度もないのだから、96条の「両議院の3分の2以上の同意」規定が憲法改正を阻止した事実も存在しない。よって上掲サンケイ記事は、安倍政権の主張する96条改正を単に正当化する意図があるとしか考えられない。
私は日本国憲法は、世界の憲法の中では改正困難な方に属していると評価するが、世界一困難というほどではない。よって上掲サンケイ記事中にある「改正を阻む最大の理由は、現行憲法96条に衆参両院で総議員の3分の2以上の賛成がなければ改正の発議すらできないことだ」という指摘には、同意できない。
そもそも、憲法が一度も改正されていないという理由で、日本が「世界から取り残されつつある」という事実はない。たとえ「二重の鍵」があっても、国民が改正を望むならすでに改正されているはずであり、憲法改正を争点とした選挙は一度も行われたことがない以上、国民の多くは憲法改正に関心がなかったから改正されなかったのだとしか言いようがない。憲法改正を問う国会の決議も、憲法施行以来一度もないのだから、96条の「両議院の3分の2以上の同意」規定が憲法改正を阻止した事実も存在しない。よって上掲サンケイ記事は、安倍政権の主張する96条改正を単に正当化する意図があるとしか考えられない。
●憲法改正要件
日本
両院で2/3以上、国民の1/2以上
イタリア
議会の3分の2を2回、もし二回目に3分の2なければ国民投票
フィリピン
議会の4分の3と国民投票
韓国
国会(一院制)の2/3以上、国民の1/2以上
アメリカ
両院で2/3以上、州議会の3/4以上
ドイツ
両院の2/3以上
ベルギー
両院の2/3以上
ロシア
上院の3/4以上、下院の2/3以上、連邦構成会議体の2/3以上
カナダ
両院の1/2以上、州議会の2/3以上(ただし議決した州人口が全体の過半数であること)
スイス
両院の1/2以上 ただしいずれかが反対した場合は国民の1/2以上の賛成で両院を再選挙
フランス
両院の1/2以上、国民の1/2以上
スウェーデン
国会(一院制)の1/2以上 + 再選挙後にもう一度1/2以上
フィンランド
国会(一院制)の1/2以上 + 再選挙後に2/3以上
オランダ
下院の1/2以上 + 再選挙後に両院で2/3以上
日本
両院で2/3以上、国民の1/2以上
イタリア
議会の3分の2を2回、もし二回目に3分の2なければ国民投票
フィリピン
議会の4分の3と国民投票
韓国
国会(一院制)の2/3以上、国民の1/2以上
アメリカ
両院で2/3以上、州議会の3/4以上
ドイツ
両院の2/3以上
ベルギー
両院の2/3以上
ロシア
上院の3/4以上、下院の2/3以上、連邦構成会議体の2/3以上
カナダ
両院の1/2以上、州議会の2/3以上(ただし議決した州人口が全体の過半数であること)
スイス
両院の1/2以上 ただしいずれかが反対した場合は国民の1/2以上の賛成で両院を再選挙
フランス
両院の1/2以上、国民の1/2以上
スウェーデン
国会(一院制)の1/2以上 + 再選挙後にもう一度1/2以上
フィンランド
国会(一院制)の1/2以上 + 再選挙後に2/3以上
オランダ
下院の1/2以上 + 再選挙後に両院で2/3以上
http://www.asahi.com/articles/ASK515SJQK51UEHF007.html
米シカゴ大学が中心となった「比較憲法典プロジェクト」のデータを使って、東京大学のケネス・盛・マッケルウェイン准教授が、日本の憲法を分析した。
プロジェクトは、米国憲法が施行された1789年以降に存在した約900の成文憲法を英語に翻訳、760を超える項目についてデータ化した。日本からは、1946(昭和21)年に制定された日本国憲法と、1889(明治22)年に公布された大日本帝国憲法(明治憲法)の二つの憲法として扱われている。
■制定70年、世界一の「長寿」
改正されたことがない現行憲法では、制定から70年たった日本国憲法は世界一の「長寿」となっている。2位のデンマークは63年、3位のナウルは48年だ。
■歴代1位は80年
現在、残っていないが、過去に存在した憲法も含めて、改正していない期間を比べると、1861年にできた旧イタリア王国の憲法が80年を超えて歴代1位の「長寿」、日本国憲法は2位となっている。日本の明治憲法も、58年間改正されておらず7番目だ。
■「短い」ことも特徴
プロジェクトで英語に翻訳した現行憲法のうち、単語数が最も多いインドは14万6385。平均は、2万1千で、日本は4998。日本国憲法は、「短い」ことも大きな特徴だ。
■政治制度は少ない
世界各国の憲法に記されている選挙制度や裁判所の編成、地方自治に関する規定など政治制度について30の項目で分析すると、日本国憲法は少ない。
マッケルウェイン准教授は、「日本国憲法は、国会議員の定数や選挙制度など、『別に法律で定める』としている項目が多いため、変えるときも憲法の改正せずに法律の改正で済んできた。これも日本の憲法が『長寿』の原因のひとつだろう」と分析する。
■権利の多さも長寿の要因
世界各国の憲法に記されている思想や言論、信教の自由、教育の保障など国民の権利について、52の項目で分析すると、日本国憲法は多い。
マッケルウェイン准教授は、「日本国憲法は、制定当時としては先進的で、権利についての規定が多く盛り込まれた。このため、新たに権利を憲法に追加する必要性が少なく、これも『長寿』の原因のひとつだろう」と分析する。
米シカゴ大学が中心となった「比較憲法典プロジェクト」のデータを使って、東京大学のケネス・盛・マッケルウェイン准教授が、日本の憲法を分析した。
プロジェクトは、米国憲法が施行された1789年以降に存在した約900の成文憲法を英語に翻訳、760を超える項目についてデータ化した。日本からは、1946(昭和21)年に制定された日本国憲法と、1889(明治22)年に公布された大日本帝国憲法(明治憲法)の二つの憲法として扱われている。
■制定70年、世界一の「長寿」
改正されたことがない現行憲法では、制定から70年たった日本国憲法は世界一の「長寿」となっている。2位のデンマークは63年、3位のナウルは48年だ。
■歴代1位は80年
現在、残っていないが、過去に存在した憲法も含めて、改正していない期間を比べると、1861年にできた旧イタリア王国の憲法が80年を超えて歴代1位の「長寿」、日本国憲法は2位となっている。日本の明治憲法も、58年間改正されておらず7番目だ。
■「短い」ことも特徴
プロジェクトで英語に翻訳した現行憲法のうち、単語数が最も多いインドは14万6385。平均は、2万1千で、日本は4998。日本国憲法は、「短い」ことも大きな特徴だ。
■政治制度は少ない
世界各国の憲法に記されている選挙制度や裁判所の編成、地方自治に関する規定など政治制度について30の項目で分析すると、日本国憲法は少ない。
マッケルウェイン准教授は、「日本国憲法は、国会議員の定数や選挙制度など、『別に法律で定める』としている項目が多いため、変えるときも憲法の改正せずに法律の改正で済んできた。これも日本の憲法が『長寿』の原因のひとつだろう」と分析する。
■権利の多さも長寿の要因
世界各国の憲法に記されている思想や言論、信教の自由、教育の保障など国民の権利について、52の項目で分析すると、日本国憲法は多い。
マッケルウェイン准教授は、「日本国憲法は、制定当時としては先進的で、権利についての規定が多く盛り込まれた。このため、新たに権利を憲法に追加する必要性が少なく、これも『長寿』の原因のひとつだろう」と分析する。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ここが変だよ比較文化論 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-