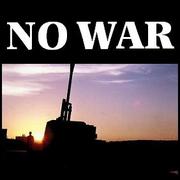http://
●731部隊
『生物戦部隊731』(アメリカが免罪した日本軍の戦争犯罪)
西里扶甬子著:草の根出版:2002年発行
第三章 新しい証言者と新資料の出現
昭和天皇死去・「731部隊展」以降
敗戦間際の細菌戦決死隊「夜桜特攻隊」
本人たちには知らされなかった「具体的出撃方法」とは、服部卓四郎参謀本部作戦課長が、1944年4月の段階で提案している、「潜水艦にPx(ペスト菌かペストノミ)を積んでオーストラリア、ハワイ、ミッドウェイに特攻攻撃する」ということだったかもしれない。
この時ペスト班で教育を受けていた別の下士官は、班長の机の上にあった「別の対米特攻計画」の書類を目にした。これには第一次出撃隊20人の名簿と、具体的計画が書かれていた。出発は昭和20年9月22日、目的地はアメリカ西海岸のサンディエゴ軍港で、4000トン級の潜水艦に特攻隊員を乗せて、軍港の沖500キロのサンゴ礁に接近し、片道燃料の艦載機で軍港の後背地に強行着陸、ペスト菌やペストノミを自ら散布して玉砕するという計画だった。
※陸軍はアメリカに対して細菌戦を強行しようとしていたことがよく分かる。私は全く軍事関係には素人だが、その当時の潜水艦に艦載機を搭載して飛び立たせることが果たしてできたのか?疑問だ!!
もし、この計画がうまくいったとしても、ペスト菌を人力で散布して、どのくらいの威力が出たのだろうか?広いアメリカ、余り効果は望めなかったのでは?
そして撒いた隊員は、その後自決するというシナリオは日本軍がいかに人命をおろそかにした軍隊であったかを物語る。
資料●
731細菌戦部隊の恐るべき全貌
http://
●731部隊
『生物戦部隊731』(アメリカが免罪した日本軍の戦争犯罪)
西里扶甬子著:草の根出版:2002年発行
第三章 新しい証言者と新資料の出現
昭和天皇死去・「731部隊展」以降
敗戦間際の細菌戦決死隊「夜桜特攻隊」
本人たちには知らされなかった「具体的出撃方法」とは、服部卓四郎参謀本部作戦課長が、1944年4月の段階で提案している、「潜水艦にPx(ペスト菌かペストノミ)を積んでオーストラリア、ハワイ、ミッドウェイに特攻攻撃する」ということだったかもしれない。
この時ペスト班で教育を受けていた別の下士官は、班長の机の上にあった「別の対米特攻計画」の書類を目にした。これには第一次出撃隊20人の名簿と、具体的計画が書かれていた。出発は昭和20年9月22日、目的地はアメリカ西海岸のサンディエゴ軍港で、4000トン級の潜水艦に特攻隊員を乗せて、軍港の沖500キロのサンゴ礁に接近し、片道燃料の艦載機で軍港の後背地に強行着陸、ペスト菌やペストノミを自ら散布して玉砕するという計画だった。
※陸軍はアメリカに対して細菌戦を強行しようとしていたことがよく分かる。私は全く軍事関係には素人だが、その当時の潜水艦に艦載機を搭載して飛び立たせることが果たしてできたのか?疑問だ!!
もし、この計画がうまくいったとしても、ペスト菌を人力で散布して、どのくらいの威力が出たのだろうか?広いアメリカ、余り効果は望めなかったのでは?
そして撒いた隊員は、その後自決するというシナリオは日本軍がいかに人命をおろそかにした軍隊であったかを物語る。
資料●
731細菌戦部隊の恐るべき全貌
http://
|
|
|
|
|
|
|
|
戦争反対! 更新情報
戦争反対!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 十二国記
- 23167人
- 2位
- 楽天イーグルス
- 31952人
- 3位
- 北海道日本ハムファイターズ
- 28124人