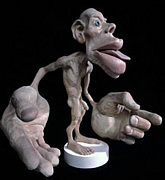久しぶりの投稿ですが 昨日9月27日の毎日新聞(下記Webより抜粋にて)に掲載されたようですが、詳しい情報もっている方あれば教えてください。
http://
脳卒中の後遺症で長期間まひした手の機能を改善させる手法を、慶応大の里宇明元(りう・めいげん)教授と牛場潤一講師らのチームが開発した。スポーツのイメージトレーニングのように手を動かすことを想像し、脳に刺激を与える訓練を繰り返すことで、筋肉の働きを誘発させた。チームは、新しいリハビリ法になるとみて、実用化を目指した臨床試験に着手した。
・・・・・チームは、手を動かす際に出る脳波が現れると、手首に装着した電動装具が動くシステムを構築した。
まひした患者の場合、最初は動かすことのできる人と異なる波形になる。そこで、コンピューター画面を通して違いを確認しながら、手を動かすイメージを繰り返し、正しい脳波が現れると、電動装具が手を強制的に動かす。
システムを使い、5年間も左手がまひしていた女性が1日1時間の訓練を週5回続けたところ、2週間後には積み木のような器具をつかんで持ち上げられるようになった。・・・・・
イメージを用いた方法がいよいよ本格かする兆しかな・・・今試みている方法ももっとイメージや意識を用いたものにすべきか検討すべきかもしれません。
http://
脳卒中の後遺症で長期間まひした手の機能を改善させる手法を、慶応大の里宇明元(りう・めいげん)教授と牛場潤一講師らのチームが開発した。スポーツのイメージトレーニングのように手を動かすことを想像し、脳に刺激を与える訓練を繰り返すことで、筋肉の働きを誘発させた。チームは、新しいリハビリ法になるとみて、実用化を目指した臨床試験に着手した。
・・・・・チームは、手を動かす際に出る脳波が現れると、手首に装着した電動装具が動くシステムを構築した。
まひした患者の場合、最初は動かすことのできる人と異なる波形になる。そこで、コンピューター画面を通して違いを確認しながら、手を動かすイメージを繰り返し、正しい脳波が現れると、電動装具が手を強制的に動かす。
システムを使い、5年間も左手がまひしていた女性が1日1時間の訓練を週5回続けたところ、2週間後には積み木のような器具をつかんで持ち上げられるようになった。・・・・・
イメージを用いた方法がいよいよ本格かする兆しかな・・・今試みている方法ももっとイメージや意識を用いたものにすべきか検討すべきかもしれません。
|
|
|
|
コメント(10)
マナさん
慶応大学医学部
http://www.keio-reha.com/gyoseki/hands_therapy.htm
にHANDS療法の概念説明がありました。それを要約すると
麻痺手指を随意的に生じる微細な筋活動を表面電極により捉え、
その筋活動量に応じて電気刺激を与える。
というのがHANDS療法ということで、作用させる筋の運動を捉えて足りないパワーを電流で与える方法のようです。おそらくこの方法では筋の収縮がみられないとだめなのではないでしょうか。BMI療法の場合、筋の収縮の前の脳波を測定してということなので、おそらくHANDS療法の弱点からさらに突っ込んだ方法だと思います。
尚、これは私の解釈ですが
慶応大学医学部
http://www.keio-reha.com/gyoseki/hands_therapy.htm
にHANDS療法の概念説明がありました。それを要約すると
麻痺手指を随意的に生じる微細な筋活動を表面電極により捉え、
その筋活動量に応じて電気刺激を与える。
というのがHANDS療法ということで、作用させる筋の運動を捉えて足りないパワーを電流で与える方法のようです。おそらくこの方法では筋の収縮がみられないとだめなのではないでしょうか。BMI療法の場合、筋の収縮の前の脳波を測定してということなので、おそらくHANDS療法の弱点からさらに突っ込んだ方法だと思います。
尚、これは私の解釈ですが
クーさんお久ぶりです
マヒ性の痛みや違和感は本当につらいようですね。意識を他に向けるなどその改善策はすでに言い尽くされていますし、クーさんは、実生活でその点は十分に行ってきているように思いますが・・それでもなかなかというのが現実でしょうか・・・・。
ただ、BMI療法の記事を見たとき、実際にやっていることは精密な脳波の測定機器を使うという点でさすが大学だとおもいましたが、私のリハビリ指導でもイメージや感覚についてその大切さは感じています。ただ、2週間集中的に1時間行った場合の臨床例で数年目の方の改善という報告を思うとき、改めて徹底的な集中、イメージの利用を促す必要性を感じました。
私としては目新しいというより、再認識してもっと丁寧に、徹底してイメージや感覚を使う、それらを当事者さん方にもより判りやすい方法が必要ではないかと思いました。
痛みや違和感についても、快を伴う感情や生活の充実、イメージ療法的に考えれば、損傷している部位、神経に対して癒し、許し、時に対決や決断、細胞や機能の改善イメージなど徹底した取り組みがこれまでとは違う反応を招く可能性はあると思います。
それを具体的にどのように実践し継続する手段の開発や発見が必要だと思います。
BMI療法もそのベースは、他の予想以上の改善を示した例などからメンタルや感覚の重要性、イメージの有効性などは判っていたことで、ただその目に見えない過程を、一般の方がわかるように、体験しやすい方法としてのアイデアだと思うんです。
マヒ性の痛みや違和感は本当につらいようですね。意識を他に向けるなどその改善策はすでに言い尽くされていますし、クーさんは、実生活でその点は十分に行ってきているように思いますが・・それでもなかなかというのが現実でしょうか・・・・。
ただ、BMI療法の記事を見たとき、実際にやっていることは精密な脳波の測定機器を使うという点でさすが大学だとおもいましたが、私のリハビリ指導でもイメージや感覚についてその大切さは感じています。ただ、2週間集中的に1時間行った場合の臨床例で数年目の方の改善という報告を思うとき、改めて徹底的な集中、イメージの利用を促す必要性を感じました。
私としては目新しいというより、再認識してもっと丁寧に、徹底してイメージや感覚を使う、それらを当事者さん方にもより判りやすい方法が必要ではないかと思いました。
痛みや違和感についても、快を伴う感情や生活の充実、イメージ療法的に考えれば、損傷している部位、神経に対して癒し、許し、時に対決や決断、細胞や機能の改善イメージなど徹底した取り組みがこれまでとは違う反応を招く可能性はあると思います。
それを具体的にどのように実践し継続する手段の開発や発見が必要だと思います。
BMI療法もそのベースは、他の予想以上の改善を示した例などからメンタルや感覚の重要性、イメージの有効性などは判っていたことで、ただその目に見えない過程を、一般の方がわかるように、体験しやすい方法としてのアイデアだと思うんです。
ぎゃーろさん
私は退院して、ネットや書籍等で自分なりに情報収集しましたが
動かない麻痺手を動かす手段(他の力を借りて)はBMI、HANDS、その他磁気療法があると知りました。
しかし、どの施設も医療保険が10割負担であったり、ある程度指の稼動領域が見られないと対象にならないものばかりでした。
臨床検査の被験者に応募もしましたがグーができてもパーができないとダメだと断られたり、動かない患者は裕福でないと希望を絶たれるのだと落胆しました。
話がそれますが
私は時間さえあれば健手で麻痺手を動かすようにしています。
7月に訪問マッサージを始めた所、2年間1mmも動かなかった手が自分の意志で
グーだけ出来るようになりました。また、足首がしっかりして装具が外れました(これは時期的なタイミングと合ったのかもしれませんが…)肩の可動範囲も飛躍的に広がりました。
その結果、徒手医療というものに非常に興味を持ちました。
自分なりの結論は、PT、OTにマッサージも入れるべきだと思っています。
クーさん
私はずっと視床痛というものに苦しんでいました。
自宅の気温が0.5〜1度下がるだけで足の痺れと痛み、浮腫みがひどくなります。
冬は弾性ハイソックスを手放せません。
マッサージの先生が今年は楽になりますよと言ってくれて、秋が怖かったのですが不思議と痺れが楽です。マッサージお薦めです。
クーさんも良いマッサージの先生に巡り会えますように。
長くなりました。
私は退院して、ネットや書籍等で自分なりに情報収集しましたが
動かない麻痺手を動かす手段(他の力を借りて)はBMI、HANDS、その他磁気療法があると知りました。
しかし、どの施設も医療保険が10割負担であったり、ある程度指の稼動領域が見られないと対象にならないものばかりでした。
臨床検査の被験者に応募もしましたがグーができてもパーができないとダメだと断られたり、動かない患者は裕福でないと希望を絶たれるのだと落胆しました。
話がそれますが
私は時間さえあれば健手で麻痺手を動かすようにしています。
7月に訪問マッサージを始めた所、2年間1mmも動かなかった手が自分の意志で
グーだけ出来るようになりました。また、足首がしっかりして装具が外れました(これは時期的なタイミングと合ったのかもしれませんが…)肩の可動範囲も飛躍的に広がりました。
その結果、徒手医療というものに非常に興味を持ちました。
自分なりの結論は、PT、OTにマッサージも入れるべきだと思っています。
クーさん
私はずっと視床痛というものに苦しんでいました。
自宅の気温が0.5〜1度下がるだけで足の痺れと痛み、浮腫みがひどくなります。
冬は弾性ハイソックスを手放せません。
マッサージの先生が今年は楽になりますよと言ってくれて、秋が怖かったのですが不思議と痺れが楽です。マッサージお薦めです。
クーさんも良いマッサージの先生に巡り会えますように。
長くなりました。
マナさん
良い体験談ありがとうございます。
・・ある程度指の稼動領域が見られないと対象にならないものばかりでした。・・・とのことですが
僕は本来患者さんが求めれば、可能性をあきらめない強い意志を示せばまずは試みるべきだと思っています。ただし、挑戦的に行っているのが一部の研究機関に限られるための現状で、もっと広く臨床家たちが患者さんの側に立った活動を行えばと私も思いますよ。
マナさん東京板橋ですね。 11月7日に東京のリハビリの講演会に行く予定しています。マナさんを勇気付けたマッサージ師さんやマナさんにお会いしてみたいと思いました。断られても諦めなかった手の動き状態など是非見せていただきたいと思っています。
良い体験談ありがとうございます。
・・ある程度指の稼動領域が見られないと対象にならないものばかりでした。・・・とのことですが
僕は本来患者さんが求めれば、可能性をあきらめない強い意志を示せばまずは試みるべきだと思っています。ただし、挑戦的に行っているのが一部の研究機関に限られるための現状で、もっと広く臨床家たちが患者さんの側に立った活動を行えばと私も思いますよ。
マナさん東京板橋ですね。 11月7日に東京のリハビリの講演会に行く予定しています。マナさんを勇気付けたマッサージ師さんやマナさんにお会いしてみたいと思いました。断られても諦めなかった手の動き状態など是非見せていただきたいと思っています。
脳はその支配域が固定で決まっているという80年前の理論で言えば、一度損傷すると改善しないということになりますが、それは古典の概念です。
また、日本のリハビリは高度成長時代(この言葉すらずいぶん過去、しらない世代、平成生まれが成人というのに)に、拡がりました。それはちょうど労働災害や交通事故による、部位の喪失にたいするリハビリだったわけで、その後の高齢化に対しての医療やリハビリは失敗、そのため他の先進国にはなかった『寝たきり老人』という言葉が生まれています。
喪失したものに対するリハビリであれば、残存機能利用して生活を、いつまでも失ったものにこだわってもという理屈は成り立ちますが、高齢化の中で出てきたのは脳の出血や梗塞による神経細胞の欠損。これは四肢の部位の消失とは違った概念や方法が必要であったが、急激な高齢化の中、とにかく寝たきりを作らないということが命題となり、特に手の麻痺の改善ははじめから否定する関係者が多いのがこれまでの流れのようです。
欧米では、神経的な疾患に対するリハビリは障がい児分野で発展をして、それが脳血管障害の大人にも普及してきていますが、日本では障がい児でも普及がすすまない現状があったようです。
実際に180日で個別な医療的なリハビリが終了となった背景には、あまり専門家方も語りませんが、リハビリの業界自体が、概ね半年以降の改善はないといってきたことがあり、それを受けて国が制度設計したわけで、私は国の責任より、現場の専門家の責任が大きいと思っています。
数年前に障がい者の方々の支援に対して、制度が大きく変更されました。そのとき障がい者畑の方々は、実態に合わない制度だと厚生労働省前に座り込みの運動を広げました。(ここでいう障がい者とは主に、若いく、先天性の小児麻痺や知的障害を持った方々)
しかし、180日のリハビリの制限が出たとき、どれだけリハビリや関わる医療の業界の方々が動いたのか?患者サイドに立つ業界の方々の意識の問題が大きくあり、そういう現場で、『6ヶ月以上は改善しない』という意識化で行われたリハビリによるデータを証に改善しないというのは、それこそ医学的、科学的ともいえない御都合データだと思っています。
では、すべてが改善するというほど簡単なことを申はしません。とても改善が難しく、日々私の臨床でも、目の前に大きな壁を感じていることも事実です。
しかし、当事者の方があきらめないというとき、それでは何ができるか、専門家として最大限に取り組み考えて見ましょう。とい職人がいてほしいですよね。
また、日本のリハビリは高度成長時代(この言葉すらずいぶん過去、しらない世代、平成生まれが成人というのに)に、拡がりました。それはちょうど労働災害や交通事故による、部位の喪失にたいするリハビリだったわけで、その後の高齢化に対しての医療やリハビリは失敗、そのため他の先進国にはなかった『寝たきり老人』という言葉が生まれています。
喪失したものに対するリハビリであれば、残存機能利用して生活を、いつまでも失ったものにこだわってもという理屈は成り立ちますが、高齢化の中で出てきたのは脳の出血や梗塞による神経細胞の欠損。これは四肢の部位の消失とは違った概念や方法が必要であったが、急激な高齢化の中、とにかく寝たきりを作らないということが命題となり、特に手の麻痺の改善ははじめから否定する関係者が多いのがこれまでの流れのようです。
欧米では、神経的な疾患に対するリハビリは障がい児分野で発展をして、それが脳血管障害の大人にも普及してきていますが、日本では障がい児でも普及がすすまない現状があったようです。
実際に180日で個別な医療的なリハビリが終了となった背景には、あまり専門家方も語りませんが、リハビリの業界自体が、概ね半年以降の改善はないといってきたことがあり、それを受けて国が制度設計したわけで、私は国の責任より、現場の専門家の責任が大きいと思っています。
数年前に障がい者の方々の支援に対して、制度が大きく変更されました。そのとき障がい者畑の方々は、実態に合わない制度だと厚生労働省前に座り込みの運動を広げました。(ここでいう障がい者とは主に、若いく、先天性の小児麻痺や知的障害を持った方々)
しかし、180日のリハビリの制限が出たとき、どれだけリハビリや関わる医療の業界の方々が動いたのか?患者サイドに立つ業界の方々の意識の問題が大きくあり、そういう現場で、『6ヶ月以上は改善しない』という意識化で行われたリハビリによるデータを証に改善しないというのは、それこそ医学的、科学的ともいえない御都合データだと思っています。
では、すべてが改善するというほど簡単なことを申はしません。とても改善が難しく、日々私の臨床でも、目の前に大きな壁を感じていることも事実です。
しかし、当事者の方があきらめないというとき、それでは何ができるか、専門家として最大限に取り組み考えて見ましょう。とい職人がいてほしいですよね。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
メンタル&リハビリ 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-