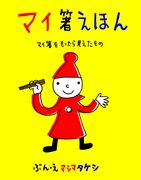―森が燃えていました。
森の生き物たちはわれ先にと逃げていきました。
でも、クリキンディという名のハチドリだけはいったりきたり、くちばしで水のしずくを一滴ずつ運んでは火の上に落していきます。
動物たちがそれを見て「そんなことをしていったい何になるんだ」といって笑います。
クリキンディはこう答えました。
「私は、私にできることをしているだけ」―
この物語は南アメリカの先住民に伝わるお話です(『ハチドリのひとしずく―いま、私にできること』監修者:辻信一。光文社より)。
昨年の4月に、『おいしいコーヒーの真実』という映画の上映会を催しました。
コーヒーは世界で最も日常的な飲物。全世界での1日あたりの消費量は約20億杯にもなる。コーヒーは大手企業が市場を支配し、石油に次ぐ取引規模を誇る国際商品になっている。オレたちは何気なく毎日おいしいコーヒーにお金を払い、それを愛しているが、コーヒー農家に支払われる代価は低く、多くの農家が困窮し、農園を手放さなくてはならないという現実が海の向こうで起きている。
このパラドックスが最もよく現われているコーヒー原産国のエチオピア。『おいしいコーヒーの真実』では、その原因となっている国際コーヒー協定の破綻による価格の大幅な落ち込みや、貿易の不公正なシステムを暴いている。 農民たちは教育を受けることも、食べることもままならず、貧困にあえいでいる。エチオピアでは毎年700万人が緊急食糧援助を受けており、緊急支援に依存せざるを得ない状況にある。しかし、アフリカの輸出シェアが1パーセント増えれば、年間で700億ドルを創出することができる。この金額はアフリカ全体が現在受け取っている援助額の5倍に相当する。必要なのは援助ではなく、自立を支援するためのプログラムなのだ。
オレはこの映画に出会うまで、こうしたエチオピアの実態をまったく知らなかった。アフリカが貧困にあえいでいることは知っていても、どこかの誰かがその救済をしてくれるものとばかり信じていた。でも、実際は全く違った。先進国は後進国からの搾取を続けながらその貧困を増大させ、その半面で国際支援などといって形だけの救済を行っている。だとしたら、なぜ自分たちの利益の一部を原産国に分けてあげることから始めないのだろう。大事なのは救済ではなく自立であることは明白なのにそうしないのは、おそらく彼らを自立させると不都合が生じる人たちがいるからだとしか考えられない。
島国の日本は食材だけに限らず建材や電化製品など生活にかかわるあらゆるものを輸入に頼っている国だ。食べたものが摂れたところから、実際に食べるところまで運ばれる距離をあらわすものさしを『フードマイレージ』というが、自給率が低く、食糧を輸入に頼っている日本のフードマイレージは世界一だという。当然、海外から食料を運ぶので、その運搬にかかるCO2の排出も膨大だ。でも、我々はフケーキとかなんとかとまやかしに翻弄されて、自分たちが何を選らばなければならないのかを見失っている。
先日、コーヒーを買おうと思って○ントムーンというショッピングモールの中にある『○ュピター』という輸入食材の店に行った。食材は国産品を選ぶことを心がけているが、さすがにコーヒーばかりは海外のものを選ぶしかない。スーパーマーケットにもコンビニにもコーヒーは売っているが、できることならフェアトレードの商品を買いたいと思い、海外からの輸入食材を専門に扱うこの店に来た。
その店にはたくさんの種類のコーヒー豆が売られていた。アフリカ産や南米産だけでなく、ハワイのコーヒー豆も置いてあるくらいに充実していた。でも、30種類以上はあると思われたコーヒー豆の中に、フェアトレードと表記したものがなかったので、店員に尋ねてみた。
「フェアトレードのコーヒー豆はどれ?表記がないということは、すべてフェアトレードだと考えていいのかな?」
すると、店員からは意外な返答が返ってきた。
「フェアトレードって、なんでしょう?」
20代半ばくらいの女性店員は、それがモカやコロンビアなどのコーヒーの銘柄の一種だとでも勘違いしたのか、初めて耳にする言葉に戸惑う表情を見せていた。
「『公平貿易』とか『公正貿易』とか言われるんだけど、んー、つまり、原産国の生産者に然るべき代価がきちんと手渡るようにフェアトレードレーベル機構に承認された…」
「あの・・・、ちょっと、あ、お待ちください」
女性店員はオレの発する言葉をまるで未知の惑星で交わされている宇宙語かのようにきょとんと聞きながら、結局、別の店員にバトンを渡すことにしたようだった。
しばらくすると、恰幅のいい女性店員がやってきた。
「どのようなものをお探しでしょう?」
そこから再びオレはフェアトレードについての説明を始めることになり、やはり店長らしきその恰幅のいい女性店員もオレの宇宙語を理解できないまま、「そういったものはお取り扱いしておりません」とわがままな顧客のリクエストを一蹴した。
悲しかったのは、フェアトレードという言葉が伝わらなかったことではなく、世界各国から輸入食材を仕入れて販売している店ですら、公平な貿易に無関心だという事実を目の当たりにしたことだった。食べるものに限らず、衣料品や電化製品を選ぶということは、自分のライフスタイルを選ぶことであり、自分や子供たちの未来を選ぶことでもあるというのに。
朝起きて、パンを焼き、コーヒーを飲む。その時、果たしてその小麦やコーヒーを生産した人たちがしかるべき代価を受け取っているのか考える。車で出勤する。その時、果たしてそのガソリンがあと何年採掘でき、どれだけの二酸化炭素を排出しているのか考える。電車で通勤する人も、その電力が自然エネルギーに切り替わったらどれだけ地球温暖化に貢献できるのか考える。家を建てるときに輸入木材とつぎはぎの金具ばかりで造られた家がいいのか、多少高くても国産木材で釘や金具を使わない古来の工法で建てた方がいいのか考える。衣類はどうだ。電化製品はどうだ。海の向こうの世界のことを考えるのが難しいのなら、自分の街に置き換えてみてもいい。スーパーマーケットで安い南米産の冷凍紅鮭を選ぶのか、地元の港に上がった新鮮な鮭を選ぶのか考える。はじめは面倒かもしれないけれど、習慣になってしまえば、次第に自分が今までどれだけの輸入品に囲まれて暮らしていたのかが浮き彫りになり、どれだけ自分の首を自分で絞めていたのかを知ることになる。
もう一度言わせてもらうが、食べるものに限らず、衣料品や電化製品を選ぶということは、自分のライフスタイルを選ぶことであり、同時に自分や子供たちの未来を選ぶことでもある。逆に行ってしまえば、今を楽に過ごそうと手を抜くことは、子供たちの未来を無思慮に踏みにじることにもなるということだ。
日本の国土の三分の二は森林。それに比べて中国は14.3%で、オーストラリアはわずか5.4%。それなのに、日本の人工林はほとんど利用されず、荒れ放題になっている。その反面、日本は木材消費の8割以上を100カ国以上の国からの輸入材で賄っている。日本人が一年間で一人当たりが使う紙や紙製品の量は250キログラム。ケニア人は4.37キログラム。これも海外から輸入する木材チップが原料になっている。タスマニアでは一年間にサッカー場2,500個分の森が伐採され、ウッドチップに加工されている。日本人はその9割を使っている。それなのに、日本人は一日に一人あたりで約一キログラムのゴミを出す。ネパール人はその四分の一しか排出しない。
こんな現状の中で地球の温暖化は深刻に進んでいる。専門家が分析したところによれば、人間の力でこの温暖化を食い止めることができるのはあと10年以内だという。それを過ぎてしまったら、どんなにフェアトレード商品を選ぼうと、ハイブリッド車を選ぼうと、マイバックやマイ箸を選ぼうと、オレたちは地球の破滅を食い止めることができなくなるそうだ。そんなのまやかしだと思う方は、あと10年間、自由気ままに暮らしてみたらいい。暴飲暴食を続けてにっちもさっちもいかなくなった人が医者に泣きついたところで、ただ自業自得ですねと見放されるのが落ちでしょう。
押しつけがましいことを言うつもりはまったくない。ただのひとりごとだと思っていただければいい。ただ、オレは冒頭の物語のハチドリがそうしたように、オレにできることを淡々とやっていくだけです。同じ破滅を迎えるにしても、何も行動を起こさずに破滅に加担するより、自分なりにできる限りのことはやったという信念を胸に静かに破滅していければましだと思うだけです。
森の生き物たちはわれ先にと逃げていきました。
でも、クリキンディという名のハチドリだけはいったりきたり、くちばしで水のしずくを一滴ずつ運んでは火の上に落していきます。
動物たちがそれを見て「そんなことをしていったい何になるんだ」といって笑います。
クリキンディはこう答えました。
「私は、私にできることをしているだけ」―
この物語は南アメリカの先住民に伝わるお話です(『ハチドリのひとしずく―いま、私にできること』監修者:辻信一。光文社より)。
昨年の4月に、『おいしいコーヒーの真実』という映画の上映会を催しました。
コーヒーは世界で最も日常的な飲物。全世界での1日あたりの消費量は約20億杯にもなる。コーヒーは大手企業が市場を支配し、石油に次ぐ取引規模を誇る国際商品になっている。オレたちは何気なく毎日おいしいコーヒーにお金を払い、それを愛しているが、コーヒー農家に支払われる代価は低く、多くの農家が困窮し、農園を手放さなくてはならないという現実が海の向こうで起きている。
このパラドックスが最もよく現われているコーヒー原産国のエチオピア。『おいしいコーヒーの真実』では、その原因となっている国際コーヒー協定の破綻による価格の大幅な落ち込みや、貿易の不公正なシステムを暴いている。 農民たちは教育を受けることも、食べることもままならず、貧困にあえいでいる。エチオピアでは毎年700万人が緊急食糧援助を受けており、緊急支援に依存せざるを得ない状況にある。しかし、アフリカの輸出シェアが1パーセント増えれば、年間で700億ドルを創出することができる。この金額はアフリカ全体が現在受け取っている援助額の5倍に相当する。必要なのは援助ではなく、自立を支援するためのプログラムなのだ。
オレはこの映画に出会うまで、こうしたエチオピアの実態をまったく知らなかった。アフリカが貧困にあえいでいることは知っていても、どこかの誰かがその救済をしてくれるものとばかり信じていた。でも、実際は全く違った。先進国は後進国からの搾取を続けながらその貧困を増大させ、その半面で国際支援などといって形だけの救済を行っている。だとしたら、なぜ自分たちの利益の一部を原産国に分けてあげることから始めないのだろう。大事なのは救済ではなく自立であることは明白なのにそうしないのは、おそらく彼らを自立させると不都合が生じる人たちがいるからだとしか考えられない。
島国の日本は食材だけに限らず建材や電化製品など生活にかかわるあらゆるものを輸入に頼っている国だ。食べたものが摂れたところから、実際に食べるところまで運ばれる距離をあらわすものさしを『フードマイレージ』というが、自給率が低く、食糧を輸入に頼っている日本のフードマイレージは世界一だという。当然、海外から食料を運ぶので、その運搬にかかるCO2の排出も膨大だ。でも、我々はフケーキとかなんとかとまやかしに翻弄されて、自分たちが何を選らばなければならないのかを見失っている。
先日、コーヒーを買おうと思って○ントムーンというショッピングモールの中にある『○ュピター』という輸入食材の店に行った。食材は国産品を選ぶことを心がけているが、さすがにコーヒーばかりは海外のものを選ぶしかない。スーパーマーケットにもコンビニにもコーヒーは売っているが、できることならフェアトレードの商品を買いたいと思い、海外からの輸入食材を専門に扱うこの店に来た。
その店にはたくさんの種類のコーヒー豆が売られていた。アフリカ産や南米産だけでなく、ハワイのコーヒー豆も置いてあるくらいに充実していた。でも、30種類以上はあると思われたコーヒー豆の中に、フェアトレードと表記したものがなかったので、店員に尋ねてみた。
「フェアトレードのコーヒー豆はどれ?表記がないということは、すべてフェアトレードだと考えていいのかな?」
すると、店員からは意外な返答が返ってきた。
「フェアトレードって、なんでしょう?」
20代半ばくらいの女性店員は、それがモカやコロンビアなどのコーヒーの銘柄の一種だとでも勘違いしたのか、初めて耳にする言葉に戸惑う表情を見せていた。
「『公平貿易』とか『公正貿易』とか言われるんだけど、んー、つまり、原産国の生産者に然るべき代価がきちんと手渡るようにフェアトレードレーベル機構に承認された…」
「あの・・・、ちょっと、あ、お待ちください」
女性店員はオレの発する言葉をまるで未知の惑星で交わされている宇宙語かのようにきょとんと聞きながら、結局、別の店員にバトンを渡すことにしたようだった。
しばらくすると、恰幅のいい女性店員がやってきた。
「どのようなものをお探しでしょう?」
そこから再びオレはフェアトレードについての説明を始めることになり、やはり店長らしきその恰幅のいい女性店員もオレの宇宙語を理解できないまま、「そういったものはお取り扱いしておりません」とわがままな顧客のリクエストを一蹴した。
悲しかったのは、フェアトレードという言葉が伝わらなかったことではなく、世界各国から輸入食材を仕入れて販売している店ですら、公平な貿易に無関心だという事実を目の当たりにしたことだった。食べるものに限らず、衣料品や電化製品を選ぶということは、自分のライフスタイルを選ぶことであり、自分や子供たちの未来を選ぶことでもあるというのに。
朝起きて、パンを焼き、コーヒーを飲む。その時、果たしてその小麦やコーヒーを生産した人たちがしかるべき代価を受け取っているのか考える。車で出勤する。その時、果たしてそのガソリンがあと何年採掘でき、どれだけの二酸化炭素を排出しているのか考える。電車で通勤する人も、その電力が自然エネルギーに切り替わったらどれだけ地球温暖化に貢献できるのか考える。家を建てるときに輸入木材とつぎはぎの金具ばかりで造られた家がいいのか、多少高くても国産木材で釘や金具を使わない古来の工法で建てた方がいいのか考える。衣類はどうだ。電化製品はどうだ。海の向こうの世界のことを考えるのが難しいのなら、自分の街に置き換えてみてもいい。スーパーマーケットで安い南米産の冷凍紅鮭を選ぶのか、地元の港に上がった新鮮な鮭を選ぶのか考える。はじめは面倒かもしれないけれど、習慣になってしまえば、次第に自分が今までどれだけの輸入品に囲まれて暮らしていたのかが浮き彫りになり、どれだけ自分の首を自分で絞めていたのかを知ることになる。
もう一度言わせてもらうが、食べるものに限らず、衣料品や電化製品を選ぶということは、自分のライフスタイルを選ぶことであり、同時に自分や子供たちの未来を選ぶことでもある。逆に行ってしまえば、今を楽に過ごそうと手を抜くことは、子供たちの未来を無思慮に踏みにじることにもなるということだ。
日本の国土の三分の二は森林。それに比べて中国は14.3%で、オーストラリアはわずか5.4%。それなのに、日本の人工林はほとんど利用されず、荒れ放題になっている。その反面、日本は木材消費の8割以上を100カ国以上の国からの輸入材で賄っている。日本人が一年間で一人当たりが使う紙や紙製品の量は250キログラム。ケニア人は4.37キログラム。これも海外から輸入する木材チップが原料になっている。タスマニアでは一年間にサッカー場2,500個分の森が伐採され、ウッドチップに加工されている。日本人はその9割を使っている。それなのに、日本人は一日に一人あたりで約一キログラムのゴミを出す。ネパール人はその四分の一しか排出しない。
こんな現状の中で地球の温暖化は深刻に進んでいる。専門家が分析したところによれば、人間の力でこの温暖化を食い止めることができるのはあと10年以内だという。それを過ぎてしまったら、どんなにフェアトレード商品を選ぼうと、ハイブリッド車を選ぼうと、マイバックやマイ箸を選ぼうと、オレたちは地球の破滅を食い止めることができなくなるそうだ。そんなのまやかしだと思う方は、あと10年間、自由気ままに暮らしてみたらいい。暴飲暴食を続けてにっちもさっちもいかなくなった人が医者に泣きついたところで、ただ自業自得ですねと見放されるのが落ちでしょう。
押しつけがましいことを言うつもりはまったくない。ただのひとりごとだと思っていただければいい。ただ、オレは冒頭の物語のハチドリがそうしたように、オレにできることを淡々とやっていくだけです。同じ破滅を迎えるにしても、何も行動を起こさずに破滅に加担するより、自分なりにできる限りのことはやったという信念を胸に静かに破滅していければましだと思うだけです。
|
|
|
|
|
|
|
|
マイ箸えほん 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
マイ箸えほん のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75496人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208293人
- 3位
- 音楽が無いと生きていけない
- 196030人