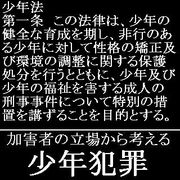日刊サイゾーの記事より
故・三浦和義、田代まさし、三田佳子の次男など、ワイドショーで騒がれた"ヒール"から、宮崎勤、林眞須美、小林薫といった"凶悪犯"など、マスコミが無視する彼らの「生の声」を雑誌「創」に掲載してきた同誌編集長・篠田博之氏。数多くの犯罪者と接してきた同氏が、自著を通して世に投げかけた問いが「罪を償うとは何なのか? 現行の死刑に、どのような効果があるのか?」といった難解なもの。裁判員として「人を裁く」立場になる可能性がある中で、そうした課題に思考をめぐらす義務が国民に求められている。
1988年から89年にかけて、東京・埼玉に住む幼女4人を次々に誘拐、殺害し、遺体を食べるなどの凶行に及んだ宮崎勤。04年、奈良県に住む女児を誘拐、殺害した後、遺体の写真をメールに添付して、母親の携帯電話に送りつけた小林薫。01年、授業中の大阪教育大学附属池田小学校に侵入し、手にした刃物で児童、教師を次々に刺し、8人を殺害した宅間守。
いずれも、耳を塞ぎたくなるような凶悪事件の犯人たちだ。3人には死刑判決が下され、宅間は04年9月、宮崎は今年6月に執行されている。月刊「創」編集長の篠田博之氏は、宮崎、小林に関しては本人との文通や面会など、宅間に関しては、獄中結婚した女性らを通じて、3人とかかわってきた。
「3人の死刑囚とのかかわりを通して、今の司法システムや死刑という極刑は本当に、人を裁き、凶悪犯罪を抑止するために有効に機能しているのか、という疑問を抱き続けてきました」
今年8月に刊行された『ドキュメント死刑囚』(ちくま新書)は、篠田氏のそうした思いをまとめたものだという。
「宮崎、小林、宅間の3人についてまとめようという気持ちは以前からありました。なぜこの3人かというと、家庭、特に父親との関係が複雑であるとか、社会的に弱い存在である子どもを狙った犯罪であるとか、すごく共通性があるからです」
両親をニセモノと呼んで忌避し、父親の自殺に「胸がスーッとした」と語った宮崎。最愛の母の死後、父親に突き放され続けた小林。権威主義的な父親に激しい体罰を加えられ、幼い頃から反発していた宅間。3人とも、精神鑑定で「反社会性人格障害」と診断されている。つまりは社会との関係をうまく保てないということだが、そんな彼らにとって、家庭とはどのような場所だったのか。篠田氏は、社会のどこかが壊れ始め、家族が崩壊し始めている現実を3人が体現していたのではないか、と分析する。もちろん、不遇な家庭環境や、不幸な生い立ちをもって凶悪な犯罪が許されるわけではないことは承知の上だ。
「どの事件も、その時代の社会を反映しています。動機や背景など、事件の根本的な原因を解明していかなければ、同種の犯罪はこれからも起こり続けるでしょう。ところが、今の司法のシステムというのは、処分を下すことにばかり力が注がれていて、真相解明という面がおろそかにされている。厳罰化による恐怖で犯罪を抑止する、という対症療法のみでは対処しきれていないのが現実です」
死刑になることを望み、裁判でも事実関係を一切争わなかった小林薫や、死を覚悟して事件を起こし、死の瞬間まで社会を憎み、反省や謝罪をすることを拒み続けた宅間守を「裁く」とは、どういうことなのか?
「もっとも、裁判は被告にどういう処分を下すかというのが一番の目的なので、裁判所だけに真相解明の役割まで求めるというのも酷な話です。もう少し広い枠で考えて、ジャーナリズムや精神医学といった、いろいろな分野の人が真相解明にかかわれるようなシステムをつくっていかなければならないでしょう」
そのジャーナリズムだが、事件を追いきれていないのが現状だ。
「今の報道のシステムって分厚いように見えて、実は穴がいっぱいあるんですよ。事件が発生してから最初の3カ月ぐらいは、集中的に取材して報道するけども、その後はパタッと終わってしまう。それから半年か1年もすると、担当者も代わってしまうというようなレベル。事件を長く追う、ということをしていないんですね」
長期間継続してアプローチすることで信頼関係を築いていかなければ、対象の内面を探ることはできない。しかし、数年毎に異動のある大手マスコミでは、ひとりの記者がひとつの事件を長年追い続けるということができないのだ。
「それでも、昔はコツコツ追いかけるフリーのノンフィクションライターが結構いたんです。でも、今ではそういう人もいなくなってしまった。そんなことをしていると、食べていけないから。たとえば宅間の場合、継続して追いかけている人ってほとんどいませんでしたよ。結構注目を浴びた事件が、手つかずになっているというケースが意外と多いんです。これでは、たとえば10年後、その事件について誰か知りたいと思った時に、まとまった文献が何も残っていないという状況になりかねない。これでいいのかな、という気がしますよね。考えると恐ろしいことだと思います」
●マスコミに課せられた多角的・継続的な報道
精神医学的なアプローチについても、真相解明のために効果的に用いられているとはいえない。今の裁判でも精神鑑定は行われている。しかし、責任能力があるかないかを決めるだけの道具に貶められている、というのが現状だ。
「精神鑑定で、たとえば統合失調症と認められると、死刑にできなくなってしまう。だから裁判所は、そういう結論の精神鑑定は採用しないんです。また、検察側が提示する犯行の動機というのは『性的関心で』とか『わいせつ目的で』とか、非常にわかりやすいんですよ。理解し難いロジック、必要のない精神医学的な関心は、全部切り捨ててしまうんです。おじいちゃんっ子だった宮崎にとって、祖父の死というのは明らかに大きな意味を持っているんですが、判決のロジックだと、ほとんど意味を持たなくなってしまう。やはり責任能力の有無を判断するためだけの精神鑑定ではなく、真相解明を目的とした精神鑑定も継続して行う必要があるでしょう」
こうした、現在の司法を取り巻くシステムを変えるには、どうすればいいのだろうか?
「マスコミ報道にしても、事件を長く追うような報道体制にしようと思えばできるはずなんです。また、死刑囚の接見交通権を制限していることの弊害は大きいでしょう。宮崎の事件は特にそうでしたが、凶悪犯に興味を持つ学者はたくさんいます。だから、ある程度接見ができるようにしておけば、おそらく精神科医で関心のある人がアプローチをすると思います」
加害者の声を発信することにより、被害者遺族の反発を招くこともある。
「今、死刑制度の存廃論議をすると、極端になりがちでしょう。廃止論者だと、被害者のことはまったく無視する、というような。被害者に対する関心というのは必要なことだと思います。光市母子殺人事件の被害者遺族である本村洋さんのように、当事者が語ることの意義についても評価しています。被害者の話を聞いて涙を流すというのは、我々が事件について考えるときの原点ですからね。ただ、議論する以上、どっちも主張できたほうがいいんですよ。だから、加害者側の情報も社会に提示していく、というのがマスコミの役割だと思うんですね」
そうしたことに対する、大手マスコミなりの難しさもある。
「テレビのような不特定多数の人が観るメディアで、宮崎の手紙をそのまま紹介する、というようなことをやると、当然抗議が殺到するんですよ。そういう意味では、大手マスコミの限界というのはありますよ。テレビで宮崎の内面に入って、それをフォローしていく、というのは至難の業だと思います。でも、『創』のような雑誌媒体だと、ある程度スタンスをわかっている人が買って読むので可能なんです。役割分担として、大手マスコミでは扱えない部分を『創』がやっている、という意識はありますね」
まもなく裁判員制度がスタートし、国民は当事者として事件にかかわることになる。司法制度・死刑制度への関心が高まる中、篠田氏が社会に投げかける問いの意味は大きい。
(文・逸見信介/「サイゾー」12月号より)
●篠田博之(しのだ・ひろゆき)
1951年生まれ。一橋大学卒業後、「月刊日本」編集部を経て、80年に綜合評論社の月刊「創」編集部に転職。81年に同誌編集長。82年に創出版を設立し、同誌の刊行を引き継ぐ。同社が発行する「マスコミ就職読本」編集長、日本ペンクラブ言論表現委員会副委員長なども兼任。
http://
故・三浦和義、田代まさし、三田佳子の次男など、ワイドショーで騒がれた"ヒール"から、宮崎勤、林眞須美、小林薫といった"凶悪犯"など、マスコミが無視する彼らの「生の声」を雑誌「創」に掲載してきた同誌編集長・篠田博之氏。数多くの犯罪者と接してきた同氏が、自著を通して世に投げかけた問いが「罪を償うとは何なのか? 現行の死刑に、どのような効果があるのか?」といった難解なもの。裁判員として「人を裁く」立場になる可能性がある中で、そうした課題に思考をめぐらす義務が国民に求められている。
1988年から89年にかけて、東京・埼玉に住む幼女4人を次々に誘拐、殺害し、遺体を食べるなどの凶行に及んだ宮崎勤。04年、奈良県に住む女児を誘拐、殺害した後、遺体の写真をメールに添付して、母親の携帯電話に送りつけた小林薫。01年、授業中の大阪教育大学附属池田小学校に侵入し、手にした刃物で児童、教師を次々に刺し、8人を殺害した宅間守。
いずれも、耳を塞ぎたくなるような凶悪事件の犯人たちだ。3人には死刑判決が下され、宅間は04年9月、宮崎は今年6月に執行されている。月刊「創」編集長の篠田博之氏は、宮崎、小林に関しては本人との文通や面会など、宅間に関しては、獄中結婚した女性らを通じて、3人とかかわってきた。
「3人の死刑囚とのかかわりを通して、今の司法システムや死刑という極刑は本当に、人を裁き、凶悪犯罪を抑止するために有効に機能しているのか、という疑問を抱き続けてきました」
今年8月に刊行された『ドキュメント死刑囚』(ちくま新書)は、篠田氏のそうした思いをまとめたものだという。
「宮崎、小林、宅間の3人についてまとめようという気持ちは以前からありました。なぜこの3人かというと、家庭、特に父親との関係が複雑であるとか、社会的に弱い存在である子どもを狙った犯罪であるとか、すごく共通性があるからです」
両親をニセモノと呼んで忌避し、父親の自殺に「胸がスーッとした」と語った宮崎。最愛の母の死後、父親に突き放され続けた小林。権威主義的な父親に激しい体罰を加えられ、幼い頃から反発していた宅間。3人とも、精神鑑定で「反社会性人格障害」と診断されている。つまりは社会との関係をうまく保てないということだが、そんな彼らにとって、家庭とはどのような場所だったのか。篠田氏は、社会のどこかが壊れ始め、家族が崩壊し始めている現実を3人が体現していたのではないか、と分析する。もちろん、不遇な家庭環境や、不幸な生い立ちをもって凶悪な犯罪が許されるわけではないことは承知の上だ。
「どの事件も、その時代の社会を反映しています。動機や背景など、事件の根本的な原因を解明していかなければ、同種の犯罪はこれからも起こり続けるでしょう。ところが、今の司法のシステムというのは、処分を下すことにばかり力が注がれていて、真相解明という面がおろそかにされている。厳罰化による恐怖で犯罪を抑止する、という対症療法のみでは対処しきれていないのが現実です」
死刑になることを望み、裁判でも事実関係を一切争わなかった小林薫や、死を覚悟して事件を起こし、死の瞬間まで社会を憎み、反省や謝罪をすることを拒み続けた宅間守を「裁く」とは、どういうことなのか?
「もっとも、裁判は被告にどういう処分を下すかというのが一番の目的なので、裁判所だけに真相解明の役割まで求めるというのも酷な話です。もう少し広い枠で考えて、ジャーナリズムや精神医学といった、いろいろな分野の人が真相解明にかかわれるようなシステムをつくっていかなければならないでしょう」
そのジャーナリズムだが、事件を追いきれていないのが現状だ。
「今の報道のシステムって分厚いように見えて、実は穴がいっぱいあるんですよ。事件が発生してから最初の3カ月ぐらいは、集中的に取材して報道するけども、その後はパタッと終わってしまう。それから半年か1年もすると、担当者も代わってしまうというようなレベル。事件を長く追う、ということをしていないんですね」
長期間継続してアプローチすることで信頼関係を築いていかなければ、対象の内面を探ることはできない。しかし、数年毎に異動のある大手マスコミでは、ひとりの記者がひとつの事件を長年追い続けるということができないのだ。
「それでも、昔はコツコツ追いかけるフリーのノンフィクションライターが結構いたんです。でも、今ではそういう人もいなくなってしまった。そんなことをしていると、食べていけないから。たとえば宅間の場合、継続して追いかけている人ってほとんどいませんでしたよ。結構注目を浴びた事件が、手つかずになっているというケースが意外と多いんです。これでは、たとえば10年後、その事件について誰か知りたいと思った時に、まとまった文献が何も残っていないという状況になりかねない。これでいいのかな、という気がしますよね。考えると恐ろしいことだと思います」
●マスコミに課せられた多角的・継続的な報道
精神医学的なアプローチについても、真相解明のために効果的に用いられているとはいえない。今の裁判でも精神鑑定は行われている。しかし、責任能力があるかないかを決めるだけの道具に貶められている、というのが現状だ。
「精神鑑定で、たとえば統合失調症と認められると、死刑にできなくなってしまう。だから裁判所は、そういう結論の精神鑑定は採用しないんです。また、検察側が提示する犯行の動機というのは『性的関心で』とか『わいせつ目的で』とか、非常にわかりやすいんですよ。理解し難いロジック、必要のない精神医学的な関心は、全部切り捨ててしまうんです。おじいちゃんっ子だった宮崎にとって、祖父の死というのは明らかに大きな意味を持っているんですが、判決のロジックだと、ほとんど意味を持たなくなってしまう。やはり責任能力の有無を判断するためだけの精神鑑定ではなく、真相解明を目的とした精神鑑定も継続して行う必要があるでしょう」
こうした、現在の司法を取り巻くシステムを変えるには、どうすればいいのだろうか?
「マスコミ報道にしても、事件を長く追うような報道体制にしようと思えばできるはずなんです。また、死刑囚の接見交通権を制限していることの弊害は大きいでしょう。宮崎の事件は特にそうでしたが、凶悪犯に興味を持つ学者はたくさんいます。だから、ある程度接見ができるようにしておけば、おそらく精神科医で関心のある人がアプローチをすると思います」
加害者の声を発信することにより、被害者遺族の反発を招くこともある。
「今、死刑制度の存廃論議をすると、極端になりがちでしょう。廃止論者だと、被害者のことはまったく無視する、というような。被害者に対する関心というのは必要なことだと思います。光市母子殺人事件の被害者遺族である本村洋さんのように、当事者が語ることの意義についても評価しています。被害者の話を聞いて涙を流すというのは、我々が事件について考えるときの原点ですからね。ただ、議論する以上、どっちも主張できたほうがいいんですよ。だから、加害者側の情報も社会に提示していく、というのがマスコミの役割だと思うんですね」
そうしたことに対する、大手マスコミなりの難しさもある。
「テレビのような不特定多数の人が観るメディアで、宮崎の手紙をそのまま紹介する、というようなことをやると、当然抗議が殺到するんですよ。そういう意味では、大手マスコミの限界というのはありますよ。テレビで宮崎の内面に入って、それをフォローしていく、というのは至難の業だと思います。でも、『創』のような雑誌媒体だと、ある程度スタンスをわかっている人が買って読むので可能なんです。役割分担として、大手マスコミでは扱えない部分を『創』がやっている、という意識はありますね」
まもなく裁判員制度がスタートし、国民は当事者として事件にかかわることになる。司法制度・死刑制度への関心が高まる中、篠田氏が社会に投げかける問いの意味は大きい。
(文・逸見信介/「サイゾー」12月号より)
●篠田博之(しのだ・ひろゆき)
1951年生まれ。一橋大学卒業後、「月刊日本」編集部を経て、80年に綜合評論社の月刊「創」編集部に転職。81年に同誌編集長。82年に創出版を設立し、同誌の刊行を引き継ぐ。同社が発行する「マスコミ就職読本」編集長、日本ペンクラブ言論表現委員会副委員長なども兼任。
http://
|
|
|
|
|
|
|
|
加害者の立場から考える少年犯罪 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
加害者の立場から考える少年犯罪のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90024人
- 2位
- 酒好き
- 170668人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37149人