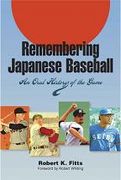静かになったところで一つ疑問を。
試合の「流れ」というのは本当に存在するのでしょうか?
試合が終わった後に
「ここで流れを一気に引き寄せたから勝てたんだ!」
という言い方は、結構することがあると思います。
野球の解説者とかもよくそういう言い方をしますよね。
(特に○川さんとか)
でも例えば実際の試合、4回表ノーアウト満塁を無得点に抑えて、
『よし、これで流れを引き寄せた』と思っても、
実際にその裏に三者凡退すると、
『まだ流れはどっちか分からない』と言いなおします。
そして勝敗が決まった後に、結果論として
『7回表の連続エラーで流れが変わった』
と、前に指摘した4回表のところと全く違った所を言ったりします。
結果論を語るだけのこの論法ならば、
どんな試合も必ず『流れを作り出せる』ことができ、それに対して雄弁に語ることも出来ます。勝敗の分かれ目を『流れ』という言葉を使って言い換えているだけにすぎません。
だから結果が出た後で『流れ』という言葉を使って、試合を論じるのは、
ここではいささか意味が無い気がします。
ここで上の様ではなく、『流れ』を、
点の入る確率(あるいは無失点で切り抜ける確率)は、
全く拮抗している状態のそれより上下するかどうか、
と決めたいと思います。
(あくまで、このトピックの中だけの定義です)
例えばあるゲームについて、
(1)1回表の攻撃で点が入る確率
(2)0−0のシーソーゲームで。
4回裏にノーアウト満塁のピンチを無失点で切り抜け、
5回表に一番打者から攻撃が始まるとして、点が入る確率
(1)'1回の表に先制された後の後の裏の攻撃で点が入る確率
(2)'1回の表を三者凡退に抑えた後の裏の攻撃で点が入る確率
この(1)(2)や(1)'(2)'では本当に(2)、(2)'のほうが確率が高いか?
と言うことです。
思うことがある方、意見をお願いします。
そんな都合のいい状況ありえない、
と確率を毛嫌いされる方もいると思いますが、
ひとつ以下を考えてみてください。
「打率」は、色々な対戦投手、違う状況(得点圏にランナーの有無)や、
そういう多数の異なる状況を含めて打者の実力として「妥当だ」と思ってますよね。
相川(Yb)は黒田(C)との対戦成績が12−6で得意にしてるから、
次の試合は3番バッターにしよう、とかは普通はしませんよね。
(このデータは例示のために適当なものですが)
そういう意味で様々な状況をひとくくりにした「打率」と同様に、
あるイニングの「得点率」を考えても良いとは思いませんか?
P.S.
最初に話したものを『流れ』と言うんだと言う人は、
その方がそう思われているならば別に構わないと思います。
否定しているわけではないので。
あくまで、議論をするならば一つの定義に従って話をすすめないと、
発散してしまうので。
試合の「流れ」というのは本当に存在するのでしょうか?
試合が終わった後に
「ここで流れを一気に引き寄せたから勝てたんだ!」
という言い方は、結構することがあると思います。
野球の解説者とかもよくそういう言い方をしますよね。
(特に○川さんとか)
でも例えば実際の試合、4回表ノーアウト満塁を無得点に抑えて、
『よし、これで流れを引き寄せた』と思っても、
実際にその裏に三者凡退すると、
『まだ流れはどっちか分からない』と言いなおします。
そして勝敗が決まった後に、結果論として
『7回表の連続エラーで流れが変わった』
と、前に指摘した4回表のところと全く違った所を言ったりします。
結果論を語るだけのこの論法ならば、
どんな試合も必ず『流れを作り出せる』ことができ、それに対して雄弁に語ることも出来ます。勝敗の分かれ目を『流れ』という言葉を使って言い換えているだけにすぎません。
だから結果が出た後で『流れ』という言葉を使って、試合を論じるのは、
ここではいささか意味が無い気がします。
ここで上の様ではなく、『流れ』を、
点の入る確率(あるいは無失点で切り抜ける確率)は、
全く拮抗している状態のそれより上下するかどうか、
と決めたいと思います。
(あくまで、このトピックの中だけの定義です)
例えばあるゲームについて、
(1)1回表の攻撃で点が入る確率
(2)0−0のシーソーゲームで。
4回裏にノーアウト満塁のピンチを無失点で切り抜け、
5回表に一番打者から攻撃が始まるとして、点が入る確率
(1)'1回の表に先制された後の後の裏の攻撃で点が入る確率
(2)'1回の表を三者凡退に抑えた後の裏の攻撃で点が入る確率
この(1)(2)や(1)'(2)'では本当に(2)、(2)'のほうが確率が高いか?
と言うことです。
思うことがある方、意見をお願いします。
そんな都合のいい状況ありえない、
と確率を毛嫌いされる方もいると思いますが、
ひとつ以下を考えてみてください。
「打率」は、色々な対戦投手、違う状況(得点圏にランナーの有無)や、
そういう多数の異なる状況を含めて打者の実力として「妥当だ」と思ってますよね。
相川(Yb)は黒田(C)との対戦成績が12−6で得意にしてるから、
次の試合は3番バッターにしよう、とかは普通はしませんよね。
(このデータは例示のために適当なものですが)
そういう意味で様々な状況をひとくくりにした「打率」と同様に、
あるイニングの「得点率」を考えても良いとは思いませんか?
P.S.
最初に話したものを『流れ』と言うんだと言う人は、
その方がそう思われているならば別に構わないと思います。
否定しているわけではないので。
あくまで、議論をするならば一つの定義に従って話をすすめないと、
発散してしまうので。
|
|
|
|
コメント(51)
>箕河さん
全く持ってトピ説明の書き込みを理解されてないようですが、
>>12で書かれているように、漠然と「流れ」と言っても、
いったいそれが何を指すのか分らないですよね?
だからトピ説明に「流れの定義」について書いたのですが。
2−0でリードしている状態。
防御率3.00レベルの先発ピッチャーが7回裏、1outとってから、
三連打と押し出し四球で依然満塁のピンチ。
ここで、防御率6.00レベルのリリーフに交代するのと、
続投させるのでは、どっちが正しい判断なのでしょうか?
続投させて逆転される→流れが完全に変わりましたね。
続投させて抑える→粘りのピッチングで流れを断ち切りましたね。
交代させて逆転される→流れを変えられませんでした。
交代させて抑える→継投で流れを断ち切りましたね。
いったいこの人の言っている「流れ」ってなんですかね。
「流れ」が非科学的だとか言っているんじゃなくて、
自分の中で「流れ」とは何かをハッキリしていないのに、
『「流れ」は存在するんだ』といわれても、何も議論ができないですよ。
だから僕は最初に書いたように、
得点確率の上下を「流れの良し悪し」としよう、と提案したのですが・・・
だから、この継投がもしも本当に得点される確率を低くするのならば、
継投で流れが相対的に良くなると『断言』できます。
だから僕の定義による「流れ」なら、
流れが絶対的に良くても、打たれることもありますし。
打たれたら流れが悪くて、抑えたら流れが良い、
という風に結果論を「流れ」という言葉を使って言い換えるだけならば、
「流れ」は必ず存在しますが、それを議論する意味は無いですよね。
全く持ってトピ説明の書き込みを理解されてないようですが、
>>12で書かれているように、漠然と「流れ」と言っても、
いったいそれが何を指すのか分らないですよね?
だからトピ説明に「流れの定義」について書いたのですが。
2−0でリードしている状態。
防御率3.00レベルの先発ピッチャーが7回裏、1outとってから、
三連打と押し出し四球で依然満塁のピンチ。
ここで、防御率6.00レベルのリリーフに交代するのと、
続投させるのでは、どっちが正しい判断なのでしょうか?
続投させて逆転される→流れが完全に変わりましたね。
続投させて抑える→粘りのピッチングで流れを断ち切りましたね。
交代させて逆転される→流れを変えられませんでした。
交代させて抑える→継投で流れを断ち切りましたね。
いったいこの人の言っている「流れ」ってなんですかね。
「流れ」が非科学的だとか言っているんじゃなくて、
自分の中で「流れ」とは何かをハッキリしていないのに、
『「流れ」は存在するんだ』といわれても、何も議論ができないですよ。
だから僕は最初に書いたように、
得点確率の上下を「流れの良し悪し」としよう、と提案したのですが・・・
だから、この継投がもしも本当に得点される確率を低くするのならば、
継投で流れが相対的に良くなると『断言』できます。
だから僕の定義による「流れ」なら、
流れが絶対的に良くても、打たれることもありますし。
打たれたら流れが悪くて、抑えたら流れが良い、
という風に結果論を「流れ」という言葉を使って言い換えるだけならば、
「流れ」は必ず存在しますが、それを議論する意味は無いですよね。
僕の大好きな野球漫画【ラストイニング】の台詞にこんなのがあります。
「勢いと流れはちがうんだよ」と
ピンチを切り抜けた後のイニングで点を入れた時こっちに流れがきてると誰もが思うでしょう。
例えば先頭打者が出て送りバント→右方向へ進塁打→タイムリーヒットと理想的な点の取り方をしたとします。
自分はここまではまだ勢いの段階なのではないかと思うんです。
理想的に点を取ったとしても1点だけ。こういう場合次の打者はなんとなくアウトになるケースが多くありませんか?多分点を取って緊張の糸が切れたからだと思います。
流れってそう簡単に途切れるものじゃないと思います。こと野球に関して言ったら次打者もヒットで続いてどんどん塁を埋めていって始めて勢いから流れに変わっていくんだと思います。
そして流れは次の守備にも影響を与えると思います。何をやっても上手くいく時間帯こそが流れだと思います。
まあ流れとは定義こそ曖昧なものですが、見てる人からでも明らかにこれは流れでしょうと分かりやすいものだと思います。
例えば0−0で7回1アウトランナー3塁なんて場面で点が入りそうなのに結局入らなかったなんて光景よくみかけますよね?
ここで1アウトランナー3塁までの時点では攻撃チームは流れがウチにきてるってやっぱり思ってしまいますよね?でも次打者がアウトになって2アウトになったら守備側は0点で切り抜けられるかもと期待が生まれてしまいます。これでは流れとはいえないでしょう。
分かり易いのが流れなんだったらスムーズに点を取らなきゃ。なので9回裏にサヨナラの0−1のピリピリした試合なんかは流れは1回も現れなかったということになります。勢いが途切れることを繰り返し最後につながった試合でしたということでしょうね。
もちろん打撃戦はその逆で。流れは1試合に必ず現れるものとは限りません。・・・と思う。
「勢いと流れはちがうんだよ」と
ピンチを切り抜けた後のイニングで点を入れた時こっちに流れがきてると誰もが思うでしょう。
例えば先頭打者が出て送りバント→右方向へ進塁打→タイムリーヒットと理想的な点の取り方をしたとします。
自分はここまではまだ勢いの段階なのではないかと思うんです。
理想的に点を取ったとしても1点だけ。こういう場合次の打者はなんとなくアウトになるケースが多くありませんか?多分点を取って緊張の糸が切れたからだと思います。
流れってそう簡単に途切れるものじゃないと思います。こと野球に関して言ったら次打者もヒットで続いてどんどん塁を埋めていって始めて勢いから流れに変わっていくんだと思います。
そして流れは次の守備にも影響を与えると思います。何をやっても上手くいく時間帯こそが流れだと思います。
まあ流れとは定義こそ曖昧なものですが、見てる人からでも明らかにこれは流れでしょうと分かりやすいものだと思います。
例えば0−0で7回1アウトランナー3塁なんて場面で点が入りそうなのに結局入らなかったなんて光景よくみかけますよね?
ここで1アウトランナー3塁までの時点では攻撃チームは流れがウチにきてるってやっぱり思ってしまいますよね?でも次打者がアウトになって2アウトになったら守備側は0点で切り抜けられるかもと期待が生まれてしまいます。これでは流れとはいえないでしょう。
分かり易いのが流れなんだったらスムーズに点を取らなきゃ。なので9回裏にサヨナラの0−1のピリピリした試合なんかは流れは1回も現れなかったということになります。勢いが途切れることを繰り返し最後につながった試合でしたということでしょうね。
もちろん打撃戦はその逆で。流れは1試合に必ず現れるものとは限りません。・・・と思う。
>流れってそう簡単に途切れるものじゃないと思います。こと野球に関して言ったら次打者もヒットで続いてどんどん塁を埋めていって始めて勢いから流れに変わっていくんだと思います。 そして流れは次の守備にも影響を与えると思います。何をやっても上手くいく時間帯こそが流れだと思います。
ではどんどん塁を埋めていって猛打爆発のイニングがあったならば、流れはウチに来ているのでしょうか?その試合は勝ち試合なのでしょうか?
■こっちが8回裏に打ちまくって勝った試合
■こっちが8回裏に打ちまくって9回表に滅多打ちされてギリギリ逃げ切った試合
前者の試合であれば、きっと「8回についにウチに流れが来たな」っていう人が多いのでは?
では後者の試合はどうでしょう。8回裏はみんなが「流れはウチにある」って思うんじゃないでしょうかね。でも9回表に滅多打ちされて僅差で勝利。これで「8回の流はウチにあった」って言えるんでしょうか?試合後に「流は最後まで分からなかった」っていう人が多いのでは?(後者でも8回に流がウチにあった、という人はいると思いますが、だとしたら何でその流のまま9回の攻撃をサクッと終わらせられなかったのか疑問です。)
前者の試合では「8回に流がウチに来た」。
後者の試合では「最後までたゆってた」。
同じ8回に得点を入れたのに、前者では「8回に流があった」と断定し、後者では「最後まで分からなかった」と言うことになります。これってただの言葉遊びで、試合が決まったターニングポイントがあればそこを『後から』流れと読んでるだけではないですかね?
こういう『流れ』とは、『試合中』に選手・監督として有益なことを何も言ってない気がするのですが。プラシーボ効果としてなら有益と言えますが・・・。
ではどんどん塁を埋めていって猛打爆発のイニングがあったならば、流れはウチに来ているのでしょうか?その試合は勝ち試合なのでしょうか?
■こっちが8回裏に打ちまくって勝った試合
■こっちが8回裏に打ちまくって9回表に滅多打ちされてギリギリ逃げ切った試合
前者の試合であれば、きっと「8回についにウチに流れが来たな」っていう人が多いのでは?
では後者の試合はどうでしょう。8回裏はみんなが「流れはウチにある」って思うんじゃないでしょうかね。でも9回表に滅多打ちされて僅差で勝利。これで「8回の流はウチにあった」って言えるんでしょうか?試合後に「流は最後まで分からなかった」っていう人が多いのでは?(後者でも8回に流がウチにあった、という人はいると思いますが、だとしたら何でその流のまま9回の攻撃をサクッと終わらせられなかったのか疑問です。)
前者の試合では「8回に流がウチに来た」。
後者の試合では「最後までたゆってた」。
同じ8回に得点を入れたのに、前者では「8回に流があった」と断定し、後者では「最後まで分からなかった」と言うことになります。これってただの言葉遊びで、試合が決まったターニングポイントがあればそこを『後から』流れと読んでるだけではないですかね?
こういう『流れ』とは、『試合中』に選手・監督として有益なことを何も言ってない気がするのですが。プラシーボ効果としてなら有益と言えますが・・・。
>例えば、相手の投手が簡単に打ち取れそうな先頭バッターに不用意な四球や死球を与えたり、打ち取った打球を野手がエラーしたり・・・。
後者について9回表をサクッと終わらせなかったのも、8回の攻撃がダブルプレーで終わったとか、内野フライの連続で終了したとか、同じように9回表に四球やエラーが続いたりと・・・。
解釈が都合よすぎでは無いですか?
統計を取って考えてみたんでしょうか?例えばゲッツーで終わった次の回は、そうじゃないときに比べて得点が取られやすいのでしょうか?ノーアウトのランナーがエラーで出されたとしたら、ヒットでノーアウトのランナーが出たときより得点されやすいのでしょうか?
そういうことを数字で考えずに、野球には流れなるものが存在すると思い込んでいるから、それを解釈するのに都合のいい場面だけがフラッシュバックされるのではないでしょうか?
心理学用語ではこのことを『確証バイアス』と言ったりします。
参考 http://www.genpaku.org/skepticj/confirmbias.html
http://www41.atwiki.jp/nagaselabs/pages/79.html
上記を見れば、『流れがある』と思い込んでる人が『経験的に・・・』と説明することはなんの説得力も持たないことが分かります。
トピ本文で定義したような『流れ』があるのか無いは私にもわかりませんし、それを信じる信じないは人それぞれです。しかし『ある』と断定する人がいるなら、その統計学的根拠を示して欲しいというのがトピの主旨のつもりだったのですが・・・
結果論的な話をするときならいくらでも「流れ」を存在させることができますが、例えばダイさんの様に「流れ」を結果論ではないとおっしゃるのならば、統計的に説明して欲しい物です。
「流れ」信じたい気持ちも分ります。
だって今まで、「流れ流れ」と言われて指導され続けてきたのですから。
確証バイアスにより、本当に結果論では無い「流れ」があるような印象が残るのです。
それを一度でいいから疑ってみませんか?
『経験・印象』ではなく『数字に残るデータ』で説明できなければ、
それはいつまでたっても『盲目的に信じている』の域を出ませんし、
『流れがある』と他人を説得することもできません。
後者について9回表をサクッと終わらせなかったのも、8回の攻撃がダブルプレーで終わったとか、内野フライの連続で終了したとか、同じように9回表に四球やエラーが続いたりと・・・。
解釈が都合よすぎでは無いですか?
統計を取って考えてみたんでしょうか?例えばゲッツーで終わった次の回は、そうじゃないときに比べて得点が取られやすいのでしょうか?ノーアウトのランナーがエラーで出されたとしたら、ヒットでノーアウトのランナーが出たときより得点されやすいのでしょうか?
そういうことを数字で考えずに、野球には流れなるものが存在すると思い込んでいるから、それを解釈するのに都合のいい場面だけがフラッシュバックされるのではないでしょうか?
心理学用語ではこのことを『確証バイアス』と言ったりします。
参考 http://www.genpaku.org/skepticj/confirmbias.html
http://www41.atwiki.jp/nagaselabs/pages/79.html
上記を見れば、『流れがある』と思い込んでる人が『経験的に・・・』と説明することはなんの説得力も持たないことが分かります。
トピ本文で定義したような『流れ』があるのか無いは私にもわかりませんし、それを信じる信じないは人それぞれです。しかし『ある』と断定する人がいるなら、その統計学的根拠を示して欲しいというのがトピの主旨のつもりだったのですが・・・
結果論的な話をするときならいくらでも「流れ」を存在させることができますが、例えばダイさんの様に「流れ」を結果論ではないとおっしゃるのならば、統計的に説明して欲しい物です。
「流れ」信じたい気持ちも分ります。
だって今まで、「流れ流れ」と言われて指導され続けてきたのですから。
確証バイアスにより、本当に結果論では無い「流れ」があるような印象が残るのです。
それを一度でいいから疑ってみませんか?
『経験・印象』ではなく『数字に残るデータ』で説明できなければ、
それはいつまでたっても『盲目的に信じている』の域を出ませんし、
『流れがある』と他人を説得することもできません。
■補足
もしかすると,『私が流れを敵視してる』と捉えられる方もいるかもしれないので一つ付け加えさせてください。トピ主文で定義される流れについて、それがあるかどうか、私の立場は完全にニュートラルです。どちらの主張もしていません。むしろ、逆に流れはあっても良いと思ってます。
ただ、このトピックで『結果論ではない流れが存在する』と主張される人のほとんど全てが、
「経験的に〜」「実際に試合をしてると〜」
という、理論的(=科学的・統計的)ではない説明に終始しています。
私は、
そんな説明では客観性を全く欠いているし、他人を説得できないし、
結局本当に正しいかどうか分からない。
信じている人同士で同意しあう、馴れ合い的な自己満足で終わってしまう。
ということが言いたいのです。
『理論野球』コミュニティ
というのを皆さんがどう捉えてるかは分らないのですが、
少なくとも客観的でない論拠に基づいて『正しい』と主張するのは、
理論ではなくオカルトの様な気がします。
だからこそ、流れの存在を主張する人たちに対して、
もっと理論的に考えて方って欲しいと思ってるので・・・。
P.S.
例えば連打が出れば、投手は焦り制球を欠き、野手はアウトを欲張りミスをして、打者もプラシーボ効果で普段以上の力を発揮することもあるでしょう。この様な理由により、連打のあとの次のバッターの出塁率は、普段のそれより上がるかもしれません。でも、こんな説明は全く持って客観的ではありません。だからこそ私はそれを「正しい」と言えません。統計的に示せていないからです。
もしかすると,『私が流れを敵視してる』と捉えられる方もいるかもしれないので一つ付け加えさせてください。トピ主文で定義される流れについて、それがあるかどうか、私の立場は完全にニュートラルです。どちらの主張もしていません。むしろ、逆に流れはあっても良いと思ってます。
ただ、このトピックで『結果論ではない流れが存在する』と主張される人のほとんど全てが、
「経験的に〜」「実際に試合をしてると〜」
という、理論的(=科学的・統計的)ではない説明に終始しています。
私は、
そんな説明では客観性を全く欠いているし、他人を説得できないし、
結局本当に正しいかどうか分からない。
信じている人同士で同意しあう、馴れ合い的な自己満足で終わってしまう。
ということが言いたいのです。
『理論野球』コミュニティ
というのを皆さんがどう捉えてるかは分らないのですが、
少なくとも客観的でない論拠に基づいて『正しい』と主張するのは、
理論ではなくオカルトの様な気がします。
だからこそ、流れの存在を主張する人たちに対して、
もっと理論的に考えて方って欲しいと思ってるので・・・。
P.S.
例えば連打が出れば、投手は焦り制球を欠き、野手はアウトを欲張りミスをして、打者もプラシーボ効果で普段以上の力を発揮することもあるでしょう。この様な理由により、連打のあとの次のバッターの出塁率は、普段のそれより上がるかもしれません。でも、こんな説明は全く持って客観的ではありません。だからこそ私はそれを「正しい」と言えません。統計的に示せていないからです。
>正の流れの時はバットを振ればヒットになるタイミングも感じています。
>なぜかその時に限って失投が来るんですよ。
確証バイアスのくだり、読まれましたか?
ご自身の中で確証バイアスが働いてるからこそ、
チャンスにヒットを打てた = 相手の失投だった
と都合の良い様に事実を解釈してる可能性を、
自分の中で吟味してみましたか?
自分を疑わない限り、真実は永遠に分かりませんが・・・。
少なくとも、理論的に考えてないのに主張しているのは、
馴れ合ってる様にしか見えないんですけどね・・・。
(流れが存在する派の人で、
流について「理論的」に話している人は誰も居ません。
私には幽霊が存在する派の人が、
その存在について「理論的」に語れないのと同じに見えるのですが。)
何度も言いますが、『理論的』に存在するのか知りたいからこそ、
理論的に話してくれる人を求めてるんですけど、やはり、
感情論が先に来てしまうようですね。 とても残念です。
>なぜかその時に限って失投が来るんですよ。
確証バイアスのくだり、読まれましたか?
ご自身の中で確証バイアスが働いてるからこそ、
チャンスにヒットを打てた = 相手の失投だった
と都合の良い様に事実を解釈してる可能性を、
自分の中で吟味してみましたか?
自分を疑わない限り、真実は永遠に分かりませんが・・・。
少なくとも、理論的に考えてないのに主張しているのは、
馴れ合ってる様にしか見えないんですけどね・・・。
(流れが存在する派の人で、
流について「理論的」に話している人は誰も居ません。
私には幽霊が存在する派の人が、
その存在について「理論的」に語れないのと同じに見えるのですが。)
何度も言いますが、『理論的』に存在するのか知りたいからこそ、
理論的に話してくれる人を求めてるんですけど、やはり、
感情論が先に来てしまうようですね。 とても残念です。
私も、幽霊の話もみなさんの流れの話も納得しています。
トピ主さんは、もしプロのスコアラーレベルの議論を望むのであれば、その上から目線もしょうがないかなとも思います。
けれど、ココではそれは難しいのでは!
プロのスコアラーやそれ同等の方達は、ココでは傍観しているだけで絶対に発言しないでしょう。
感情や気合いが自分の技術を120%にする野球が楽しいのですよ。オイラ達は。
もちろん、ある結果に対し、根拠を探して理論的に分析しヤーヤー言い合うのは楽しいですよ。
でもそれは、一緒にプレーした仲間とのリアルな場合だな。
だって、「流れ」はその場にいて感じるものだから。
すいません、そんなレベルで。
トピ主さんは、もしプロのスコアラーレベルの議論を望むのであれば、その上から目線もしょうがないかなとも思います。
けれど、ココではそれは難しいのでは!
プロのスコアラーやそれ同等の方達は、ココでは傍観しているだけで絶対に発言しないでしょう。
感情や気合いが自分の技術を120%にする野球が楽しいのですよ。オイラ達は。
もちろん、ある結果に対し、根拠を探して理論的に分析しヤーヤー言い合うのは楽しいですよ。
でもそれは、一緒にプレーした仲間とのリアルな場合だな。
だって、「流れ」はその場にいて感じるものだから。
すいません、そんなレベルで。
上から目線についてですが、
少なくとも『このトピ内では』理論的に語り合いたいと思いトピを立てました。
トピ主文にも詳しく説明書いたのにも関わらず、新たな書き込みのたびに、
なんら理論的ではない断定的な書き込みです。
こちらも「やってらんないよ」的な気持ちになってしまいます。
少なくとも、ここは『野球理論』というコミュニティであるからこそ、
私はこのコミュニティに参加して理論的に考えようとしているのですが・・・。
ただ単に流れは存在するということを主張したいだけであれば、
『流れを感じたとき』というトピックでも作っては如何でしょうか。
>てぬぐいさん
本当に存在するかどうか客観的に分らないものを存在すると思い込み、
信じている人同士で同意し合う行為こそ自己満足に他ならないと思いますが…
存在してると疑わず最初から信じているから、
都合の良い場面がフラッシュバックされるだけでは?
>風の音さん
何も、全てが全てスコアブックということでは無いかと。
例えば、1〜4回に5点取られ5〜8回に4点取り返した9回裏の攻撃で逆転する可能性は、
1〜8回まで0-0で9回表に1点取られた後の9回裏の攻撃で逆転する可能性は、
統計的に前者のほうが高いといえるかどうか?
(前者のほうが徐々に追いついてきて、流れはこちらにあるのか?)
これならスコアブックなんか無くても
プロ野球や高校野球の全試合のスコアをパーっと見てみれば、分りますよね。
この前提が不十分だという人は、例えば、
9回表の攻撃をゲッツーで終わらせられた後の1点差の9回裏に逆転する可能性と、
9回表の攻撃で逆転された後の1点差の9回裏に再逆転する可能性ではどうでしょう?
こうやって自分の納得するところまで前提を細かくして調べては如何でしょうか。
それを『一試合一試合違うんだから、そんなもの分らない』というのであれば、
ただ、自分の信じているものが壊れるのが怖くて、
それこそ何も分析する気が無いのだと私は感じてしまいます。
確かに試合をやっているときは『流れ』が存在するかのように考えたほうが面白いのは事実です。それは私も認めます。私だって楽しむときは『流れが良い』とか言っちゃってます。
しかし、楽しむ事と上達すること・勝つことは少し違うものですし、
『野球理論』とは後者に重きを置いている言葉ではないでしょうか?
(楽しむ事が上達に繋がることもありますが、楽しむことと上達することが別なこともあるのは分っていただけると思います。)
それに流れの有無に関わらず、
私はボールを投げたり打ったり、みんなでゲームをするだけで
十分におもしろいと思うのですが。
流れの存在を疑ったり否定したりすることは、
野球の楽しさを否定することになんらならないと思いますが。
以上、相変わらずの長文失礼しました。
少なくとも『このトピ内では』理論的に語り合いたいと思いトピを立てました。
トピ主文にも詳しく説明書いたのにも関わらず、新たな書き込みのたびに、
なんら理論的ではない断定的な書き込みです。
こちらも「やってらんないよ」的な気持ちになってしまいます。
少なくとも、ここは『野球理論』というコミュニティであるからこそ、
私はこのコミュニティに参加して理論的に考えようとしているのですが・・・。
ただ単に流れは存在するということを主張したいだけであれば、
『流れを感じたとき』というトピックでも作っては如何でしょうか。
>てぬぐいさん
本当に存在するかどうか客観的に分らないものを存在すると思い込み、
信じている人同士で同意し合う行為こそ自己満足に他ならないと思いますが…
存在してると疑わず最初から信じているから、
都合の良い場面がフラッシュバックされるだけでは?
>風の音さん
何も、全てが全てスコアブックということでは無いかと。
例えば、1〜4回に5点取られ5〜8回に4点取り返した9回裏の攻撃で逆転する可能性は、
1〜8回まで0-0で9回表に1点取られた後の9回裏の攻撃で逆転する可能性は、
統計的に前者のほうが高いといえるかどうか?
(前者のほうが徐々に追いついてきて、流れはこちらにあるのか?)
これならスコアブックなんか無くても
プロ野球や高校野球の全試合のスコアをパーっと見てみれば、分りますよね。
この前提が不十分だという人は、例えば、
9回表の攻撃をゲッツーで終わらせられた後の1点差の9回裏に逆転する可能性と、
9回表の攻撃で逆転された後の1点差の9回裏に再逆転する可能性ではどうでしょう?
こうやって自分の納得するところまで前提を細かくして調べては如何でしょうか。
それを『一試合一試合違うんだから、そんなもの分らない』というのであれば、
ただ、自分の信じているものが壊れるのが怖くて、
それこそ何も分析する気が無いのだと私は感じてしまいます。
確かに試合をやっているときは『流れ』が存在するかのように考えたほうが面白いのは事実です。それは私も認めます。私だって楽しむときは『流れが良い』とか言っちゃってます。
しかし、楽しむ事と上達すること・勝つことは少し違うものですし、
『野球理論』とは後者に重きを置いている言葉ではないでしょうか?
(楽しむ事が上達に繋がることもありますが、楽しむことと上達することが別なこともあるのは分っていただけると思います。)
それに流れの有無に関わらず、
私はボールを投げたり打ったり、みんなでゲームをするだけで
十分におもしろいと思うのですが。
流れの存在を疑ったり否定したりすることは、
野球の楽しさを否定することになんらならないと思いますが。
以上、相変わらずの長文失礼しました。
>とむニコさん
なるほど、そういう事ですか(9回裏に逆転する可能性の話について)。
私は、草野球ですが監督もやってますんで、そのような思考は常にやっております。
でないと、投手の替え時、勝負どころでのサインの選択を誤りますから。
けれど、とむニコさんのコメントを読んでいると、「統計学の専門知識が無いと語れない」という高い敷居を感じ畏縮してしまいます。
また、「プラシーボ効果」や「確証バイアス」などの心理学も持ち出されては、何をのたまってもアナタ様の「アー言えばコー言う攻撃」をかわす術が見つかりません。
そこで、とむニコさんにお願いです。
具体的な事例に基づいたとむニコさんの理論を示していただきたく思います。
その「模範回答」を我々が参考にして論じ方を真似することが出来ればいいなと思います。
とくに、選手の心理状態や、風向きなどの偶発的要素を、どのように数値化して確率論に展開するのか、すごく興味があります。
なるほど、そういう事ですか(9回裏に逆転する可能性の話について)。
私は、草野球ですが監督もやってますんで、そのような思考は常にやっております。
でないと、投手の替え時、勝負どころでのサインの選択を誤りますから。
けれど、とむニコさんのコメントを読んでいると、「統計学の専門知識が無いと語れない」という高い敷居を感じ畏縮してしまいます。
また、「プラシーボ効果」や「確証バイアス」などの心理学も持ち出されては、何をのたまってもアナタ様の「アー言えばコー言う攻撃」をかわす術が見つかりません。
そこで、とむニコさんにお願いです。
具体的な事例に基づいたとむニコさんの理論を示していただきたく思います。
その「模範回答」を我々が参考にして論じ方を真似することが出来ればいいなと思います。
とくに、選手の心理状態や、風向きなどの偶発的要素を、どのように数値化して確率論に展開するのか、すごく興味があります。
>風の音さん
きちんと分析して理論的な語ろうとするのであれば、
敷居がおのずと高くなるのは当然ではないでしょうか?
>草野球ですが監督もやってますんで、そのような思考は常にやっております。
>でないと、投手の替え時、勝負どころでのサインの選択を誤りますから。
例えばこれについてなのですが、確率的・統計的な計算をしていないのならば、
そもそも采配が誤りかどうかも検討できないのではないでしょうか?
例えば私が>>13で書いた、防御率3.00と6.00の投手交代の話です。
このケースで、統計的には投手続投が正しい判断だったとします
(↑この前提はあくまで仮の話です)。
ここで風の音さんが監督として同じような場面に出くわして
(もちろん風の音さんは、どちらが統計的に正しいのかは知らないとします)、
仮に投手交代を選択して後続を断ち切ったとしたら、
それは『正しい』判断なのでしょうか?
結果として『成功した』だけであって、
もしかしたらこれから先、統計的に間違っているのにもかかわらず、
同じ判断(すなわち投手交代)をし続けるのではないでしょうか?
単純な話、
9回裏の逆転チャンスにピッチャー豊田の打席で代打清水とするのは、
おそらく誰が考えても「正しい」采配ですよね?
仮に清水が凡打に終わり負けたとしても、
それは結果「失敗」なだけであり、
采配自体は正しいことをしたと言えます。
これは采配自体の正誤がはじめから明らかなので(清水>ピッチャー)、
仮に「結果失敗」でも誰も気にしませんが、
先の防御率の例については、
正誤が分らない微妙な問題を、ただひとつの『結果』から、
今後の采配の正誤を決めてしまう可能性があるということです。
普段から数字を意識していないのであれば。
ですから、本当に理論的に語る気持ちがあるのならば、
面倒くさがらずに数学(確率・統計)の勉強をして、
エクセルシートを開きながらデータ分析する必要があるのではないでしょうか?
もちろん、全ての状況について正しい采配を出来るわけがありません。
しかし、その采配を何らかの理由(ありがちなのが『流れ・勢い』)をつけて、
わかった風に語るのは、いささか自信過剰なような気がします。
わからないものをわからないと認める勇気が大事だと私は思います。
このトピックの前の方にも書いたと思いますが、トピ立て理由は
1.
野球に関するイロイロ(例えば流れ)についてデータをもってして語れる人がいたら、是非このトピックで話を聞きたかったからです。
2.
自分の経験で語る人(数値を出して語るのではなく印象で語る人)に対しては、
まずは自分が正しいと信じて疑わないコト(例えば『流れ』)とかを、
それを一旦は疑う勇気を持って欲しいと思っているからです。
何故なら信じているものがあるなら、
自分の信じていることが正しいように、
起こっていることを解釈して自分の中に印象付けられてしまうからです。
結果、より自分の信念は強固なものになってしまいます。
客観的な理由は何一つ無いのにもかかわらず・・・。
私の書き込みにイラっと来る人も多々いるかと思いますが、
一つの閉じたコミュニティだけの意見でなく、
私の様な考えもあるんだと思っていただければ幸です。
私に具体的な例示を示して欲しいというのは、また明日あたりに追記します。
きちんと分析して理論的な語ろうとするのであれば、
敷居がおのずと高くなるのは当然ではないでしょうか?
>草野球ですが監督もやってますんで、そのような思考は常にやっております。
>でないと、投手の替え時、勝負どころでのサインの選択を誤りますから。
例えばこれについてなのですが、確率的・統計的な計算をしていないのならば、
そもそも采配が誤りかどうかも検討できないのではないでしょうか?
例えば私が>>13で書いた、防御率3.00と6.00の投手交代の話です。
このケースで、統計的には投手続投が正しい判断だったとします
(↑この前提はあくまで仮の話です)。
ここで風の音さんが監督として同じような場面に出くわして
(もちろん風の音さんは、どちらが統計的に正しいのかは知らないとします)、
仮に投手交代を選択して後続を断ち切ったとしたら、
それは『正しい』判断なのでしょうか?
結果として『成功した』だけであって、
もしかしたらこれから先、統計的に間違っているのにもかかわらず、
同じ判断(すなわち投手交代)をし続けるのではないでしょうか?
単純な話、
9回裏の逆転チャンスにピッチャー豊田の打席で代打清水とするのは、
おそらく誰が考えても「正しい」采配ですよね?
仮に清水が凡打に終わり負けたとしても、
それは結果「失敗」なだけであり、
采配自体は正しいことをしたと言えます。
これは采配自体の正誤がはじめから明らかなので(清水>ピッチャー)、
仮に「結果失敗」でも誰も気にしませんが、
先の防御率の例については、
正誤が分らない微妙な問題を、ただひとつの『結果』から、
今後の采配の正誤を決めてしまう可能性があるということです。
普段から数字を意識していないのであれば。
ですから、本当に理論的に語る気持ちがあるのならば、
面倒くさがらずに数学(確率・統計)の勉強をして、
エクセルシートを開きながらデータ分析する必要があるのではないでしょうか?
もちろん、全ての状況について正しい采配を出来るわけがありません。
しかし、その采配を何らかの理由(ありがちなのが『流れ・勢い』)をつけて、
わかった風に語るのは、いささか自信過剰なような気がします。
わからないものをわからないと認める勇気が大事だと私は思います。
このトピックの前の方にも書いたと思いますが、トピ立て理由は
1.
野球に関するイロイロ(例えば流れ)についてデータをもってして語れる人がいたら、是非このトピックで話を聞きたかったからです。
2.
自分の経験で語る人(数値を出して語るのではなく印象で語る人)に対しては、
まずは自分が正しいと信じて疑わないコト(例えば『流れ』)とかを、
それを一旦は疑う勇気を持って欲しいと思っているからです。
何故なら信じているものがあるなら、
自分の信じていることが正しいように、
起こっていることを解釈して自分の中に印象付けられてしまうからです。
結果、より自分の信念は強固なものになってしまいます。
客観的な理由は何一つ無いのにもかかわらず・・・。
私の書き込みにイラっと来る人も多々いるかと思いますが、
一つの閉じたコミュニティだけの意見でなく、
私の様な考えもあるんだと思っていただければ幸です。
私に具体的な例示を示して欲しいというのは、また明日あたりに追記します。
>伯爵さん
『どう思うか』と漠然と聞かれること程、返答に困る質問は無いのですが・・・。
そもそもプロ野球に関わってる人間で無ければきちんと分析しませんよね?
なので、きちんと分析してない私が論理的に語れません。
単純にデータをザックリと解釈するならば、
攻撃という点に関しては、打率だけが関わるものではありません。
塁打数、盗塁数、相手のエラー数、被四死球数、打率はそういうものの一つの要素に過ぎませんよね?だから打率が低いからといって、例えば『打率が低いのに優勝したのは監督が素晴らしかったからだ』というのは結論付けられません。本塁打こそ少ないですが、一方で盗塁数についてはM・SHを大きく引き離して100以上であります。また、打率が低いといってもFは.259、トップであるSHの打率は.267,これが果たして大きいものでしょうか?それは過去のデータにさかのぼって検討して無いから、やはり『わかりません』。ちなみにFが4750打数で.259だとすると、統計的には真の打率(無限打数だったと仮定したときの打率)は90%の確率で.248-.269 の範囲に収まります。統計の標準的な考えで言えば90%というのは偶然として十分起こりえる範囲内の出来事と認識されるのが標準です(普通はもっと厳しく95%の確率まで考えますが、それだと範囲はさらに広がります)。つまり真の打率はもう少し高いかもしれないが、この4750打数についてはたまたま安打が少し少なかっただけとも言えるのです(サイコロを6000回振って970回しか1が出なかった、みたいなものです。)。
一方守りについては、防御率は3.22とこちらはリーグ二番目の低さですよね?だったらこれはFが優勝するのを裏付ける要因にはなりませんか?こちらについては、上の様に計算は何もして無いのでこれ以上の言及は控えます。またエラー数も関連するでしょうが、これも見ていません。
さて、私が思うのは伯爵さんが何故この様な質問をしたのか、ということです。
私は次のようなことを伯爵さんが考えたからなのでは?と思っています。
野球はすべからく、流れ・勢い・監督の采配、そういうものが重要になる。
Fだって打率が低いのに優勝したのは、それらに上手く乗っかれたからだ。
どうだ、打率が低いのに優勝した理由を説明してみろ!!
これが邪推であれば、大変申し訳ありません。
しかしながら、伯爵さんがそう思ってないにしろ、
他の方で上記の様に考えていらっしゃる方も居ると思います。
それが確証バイアスなのです。
現に、伯爵さんはFが防御率が低い、ということに全く触れずに、
打率のみについて私に尋ねてきました。
これは、防御率が低いという、
優勝するには理論的に必要であろうという数値に目をつむり、
理論的に一見してはおかしな点(打率が低いという事実)だけを上げました。
これが、まったく物事を客観的に見ておらず、
自分の信じたい事実を信じるように物事を捉えることになる、と言いたいのです。
(おそらく伯爵さんは防御率のことも分かっていて、
あえて私の反応を見るために打率だけの例を挙げたのかもしれませんが、
防御率のことを知らない人が、
『Fは打率低いのに優勝したんだよ。やっぱ数字だけじゃないよな』
とか言われると、なるほど、そのような気がしてきてしまうから不思議です。
特に自分が数字に強く無い人であればあるほど。
それに如何でしょうか?
阪神は打率・HRがセリーグで最下位にも関わらず三位です。
中日は打率・HRがセリーグでブービーにも関わらず二位です。
けれども防御率は2位、3位です。
この事実を考えれば、(当然過去の事例を多く参照する必要がありますが)、
実は打率が低いと言うことはペナントレースの結果にそれほど大きな影響は無いという仮定が成り立ちますよね?と言うよりも、上記で記述したように、高々4500打数程度であれば打率は±0.010程度ずれることは当然起こりえることで、その範囲でのズレ無いにある打率はみんな一緒と考えていい、ということにもなります。
この様にトコトンまで理論的に考えること無しに、
打率では測れないんだ、やっぱり流れとか勢いがあるんだ!
という結論に至ることは(もしそういう風に考えてる人がいるなら)、
それは思考することの怠慢ではないでしょうか。
確かに、『目に見えない力が作用している』と考えることは楽です。
しかし、目に見えるものから考えることを放棄してしまうと、
新しい発見は何も無いのではないでしょうか?
風の音さんの言っている、具体例については、また後日追記したいと思います。
この書き込みも、その例の一つだと思ってください。
何かご意見あれば是非よろしくお願いします。
『どう思うか』と漠然と聞かれること程、返答に困る質問は無いのですが・・・。
そもそもプロ野球に関わってる人間で無ければきちんと分析しませんよね?
なので、きちんと分析してない私が論理的に語れません。
単純にデータをザックリと解釈するならば、
攻撃という点に関しては、打率だけが関わるものではありません。
塁打数、盗塁数、相手のエラー数、被四死球数、打率はそういうものの一つの要素に過ぎませんよね?だから打率が低いからといって、例えば『打率が低いのに優勝したのは監督が素晴らしかったからだ』というのは結論付けられません。本塁打こそ少ないですが、一方で盗塁数についてはM・SHを大きく引き離して100以上であります。また、打率が低いといってもFは.259、トップであるSHの打率は.267,これが果たして大きいものでしょうか?それは過去のデータにさかのぼって検討して無いから、やはり『わかりません』。ちなみにFが4750打数で.259だとすると、統計的には真の打率(無限打数だったと仮定したときの打率)は90%の確率で.248-.269 の範囲に収まります。統計の標準的な考えで言えば90%というのは偶然として十分起こりえる範囲内の出来事と認識されるのが標準です(普通はもっと厳しく95%の確率まで考えますが、それだと範囲はさらに広がります)。つまり真の打率はもう少し高いかもしれないが、この4750打数についてはたまたま安打が少し少なかっただけとも言えるのです(サイコロを6000回振って970回しか1が出なかった、みたいなものです。)。
一方守りについては、防御率は3.22とこちらはリーグ二番目の低さですよね?だったらこれはFが優勝するのを裏付ける要因にはなりませんか?こちらについては、上の様に計算は何もして無いのでこれ以上の言及は控えます。またエラー数も関連するでしょうが、これも見ていません。
さて、私が思うのは伯爵さんが何故この様な質問をしたのか、ということです。
私は次のようなことを伯爵さんが考えたからなのでは?と思っています。
野球はすべからく、流れ・勢い・監督の采配、そういうものが重要になる。
Fだって打率が低いのに優勝したのは、それらに上手く乗っかれたからだ。
どうだ、打率が低いのに優勝した理由を説明してみろ!!
これが邪推であれば、大変申し訳ありません。
しかしながら、伯爵さんがそう思ってないにしろ、
他の方で上記の様に考えていらっしゃる方も居ると思います。
それが確証バイアスなのです。
現に、伯爵さんはFが防御率が低い、ということに全く触れずに、
打率のみについて私に尋ねてきました。
これは、防御率が低いという、
優勝するには理論的に必要であろうという数値に目をつむり、
理論的に一見してはおかしな点(打率が低いという事実)だけを上げました。
これが、まったく物事を客観的に見ておらず、
自分の信じたい事実を信じるように物事を捉えることになる、と言いたいのです。
(おそらく伯爵さんは防御率のことも分かっていて、
あえて私の反応を見るために打率だけの例を挙げたのかもしれませんが、
防御率のことを知らない人が、
『Fは打率低いのに優勝したんだよ。やっぱ数字だけじゃないよな』
とか言われると、なるほど、そのような気がしてきてしまうから不思議です。
特に自分が数字に強く無い人であればあるほど。
それに如何でしょうか?
阪神は打率・HRがセリーグで最下位にも関わらず三位です。
中日は打率・HRがセリーグでブービーにも関わらず二位です。
けれども防御率は2位、3位です。
この事実を考えれば、(当然過去の事例を多く参照する必要がありますが)、
実は打率が低いと言うことはペナントレースの結果にそれほど大きな影響は無いという仮定が成り立ちますよね?と言うよりも、上記で記述したように、高々4500打数程度であれば打率は±0.010程度ずれることは当然起こりえることで、その範囲でのズレ無いにある打率はみんな一緒と考えていい、ということにもなります。
この様にトコトンまで理論的に考えること無しに、
打率では測れないんだ、やっぱり流れとか勢いがあるんだ!
という結論に至ることは(もしそういう風に考えてる人がいるなら)、
それは思考することの怠慢ではないでしょうか。
確かに、『目に見えない力が作用している』と考えることは楽です。
しかし、目に見えるものから考えることを放棄してしまうと、
新しい発見は何も無いのではないでしょうか?
風の音さんの言っている、具体例については、また後日追記したいと思います。
この書き込みも、その例の一つだと思ってください。
何かご意見あれば是非よろしくお願いします。
伯爵さん
まずは、>>33の邪推の件、失礼しました。
私は必ずしも野球の専門家ではありませんが、
科学的方法論については心得があると自負しています。
普段接している人々とは異なる考え方に触れることで、
少しでも得ることがあったのならば、私も長文を書いた甲斐があったと思います。
ただ申し訳ないのですが、
伯爵さんがどういう意味で『確率』という言葉を使っているか、
少々不明なことがありました。
>相手が次に何を考えてくるかという仮定を元に試合を進めると、
>これこそ確率の話になります。
>数少ないチャンス(確率)
『確率』とはある事象がどのくらい起こりやすいかを表す数字なので、
上記二点がどういう確率なのかよく分かりませんでした。スイマセン。
それと、以下の節について加筆させて欲しいと思います。
>連打やミスで相手バッテリーがテンパって失投する確率が高いうちにに
これについては、
本当にそうなのか数字を調べてみないとわからない、
というのが私の主張です。
もしかしたら逆に、連打やミスでそれまで平然としていた相手バッテリーが集中を高めて
結果的に失投する確率が低くなるかもしれませんよね?
テンパって〜 というのは最初から連打やミスだと失投が多くなると信じている人の理屈です。
集中して〜 というのは最初から連打やミスだと失投が少なくなると信じている人の理屈です。
実際はどちらが正しいかわからないので、
先ずは数字を調べてみないといけない、と私は思うのです。
それをきちんと調べずに、前者が正しいと信じていることは、
確証バイアスを生みだし、思考の怠慢を作ってしまうと思います。
それに『流れ』の存在を信じる要素にもなりえます。
たしかに、私も前者が正しい気はしますが、数字を調べていないので断言できません。
そして常に逆の可能性も頭に入れて客観的に見ることが、思考し続けることではないでしょうか。
(私が野球商売をしていればどちらが正しいかきちんと調べますが、
そうでは無いので調べてません。ご了承を。)
>故に、試合の中の一球一球の仮定(確率)を元に行動することが
>『流れ』に値すると言うことに結びつきました。
スイマセン、これも「故に」が前の文章とどういう風に結びついているのかわかりませんでした。
なので、これについて私の解釈が以下です。
確率ということについて思うのですが、
試合の中の一球一球の仮定(確率)を元に行動することは理に叶っていると思います。
『このキャッチャーなら0-0はストレートの確率が高く,1-0は変化球を投げてくる確率が高い』
『3球連続で直球を投げる確率は非常に低い』
などのデータがあれば、変化球の確率が高い状況で盗塁を指示したり、ですよね。
こういう一球一球については配球の確率を調べる人がいます。
何故なら一球一球の配球を知っていれば有利になるからです。
打者も球種が分れば圧倒的に有利になります。
こういうのを伯爵さんは『流れ』と解釈したのでしょうか。
ちなみに私は、多くの人が使う『流れ』という言葉は、
これとは少々異なるのではないか、と思っています。
例えば私が上のほうで書いた連打とエラーの話については、
実際に確率を調べることなく、『こうだ!』と信じている人が殆どだと思います。
それを調べずに、信じたいことが実際に起きることがあるということが、
そして、そのことがしょっちゅう起こっているように見えることが、
多くの人の言う『流れ』なのかな、と思っています。。
(主文に書いてますが『流れ』という言葉をどう使うかは人によりけりなので、
伯爵さんの使い方が間違っていると言っているわけでは無いので、悪しからず)
ということで。
別に1on1ではないので他の方も何かご意見あればどうぞ。
まずは、>>33の邪推の件、失礼しました。
私は必ずしも野球の専門家ではありませんが、
科学的方法論については心得があると自負しています。
普段接している人々とは異なる考え方に触れることで、
少しでも得ることがあったのならば、私も長文を書いた甲斐があったと思います。
ただ申し訳ないのですが、
伯爵さんがどういう意味で『確率』という言葉を使っているか、
少々不明なことがありました。
>相手が次に何を考えてくるかという仮定を元に試合を進めると、
>これこそ確率の話になります。
>数少ないチャンス(確率)
『確率』とはある事象がどのくらい起こりやすいかを表す数字なので、
上記二点がどういう確率なのかよく分かりませんでした。スイマセン。
それと、以下の節について加筆させて欲しいと思います。
>連打やミスで相手バッテリーがテンパって失投する確率が高いうちにに
これについては、
本当にそうなのか数字を調べてみないとわからない、
というのが私の主張です。
もしかしたら逆に、連打やミスでそれまで平然としていた相手バッテリーが集中を高めて
結果的に失投する確率が低くなるかもしれませんよね?
テンパって〜 というのは最初から連打やミスだと失投が多くなると信じている人の理屈です。
集中して〜 というのは最初から連打やミスだと失投が少なくなると信じている人の理屈です。
実際はどちらが正しいかわからないので、
先ずは数字を調べてみないといけない、と私は思うのです。
それをきちんと調べずに、前者が正しいと信じていることは、
確証バイアスを生みだし、思考の怠慢を作ってしまうと思います。
それに『流れ』の存在を信じる要素にもなりえます。
たしかに、私も前者が正しい気はしますが、数字を調べていないので断言できません。
そして常に逆の可能性も頭に入れて客観的に見ることが、思考し続けることではないでしょうか。
(私が野球商売をしていればどちらが正しいかきちんと調べますが、
そうでは無いので調べてません。ご了承を。)
>故に、試合の中の一球一球の仮定(確率)を元に行動することが
>『流れ』に値すると言うことに結びつきました。
スイマセン、これも「故に」が前の文章とどういう風に結びついているのかわかりませんでした。
なので、これについて私の解釈が以下です。
確率ということについて思うのですが、
試合の中の一球一球の仮定(確率)を元に行動することは理に叶っていると思います。
『このキャッチャーなら0-0はストレートの確率が高く,1-0は変化球を投げてくる確率が高い』
『3球連続で直球を投げる確率は非常に低い』
などのデータがあれば、変化球の確率が高い状況で盗塁を指示したり、ですよね。
こういう一球一球については配球の確率を調べる人がいます。
何故なら一球一球の配球を知っていれば有利になるからです。
打者も球種が分れば圧倒的に有利になります。
こういうのを伯爵さんは『流れ』と解釈したのでしょうか。
ちなみに私は、多くの人が使う『流れ』という言葉は、
これとは少々異なるのではないか、と思っています。
例えば私が上のほうで書いた連打とエラーの話については、
実際に確率を調べることなく、『こうだ!』と信じている人が殆どだと思います。
それを調べずに、信じたいことが実際に起きることがあるということが、
そして、そのことがしょっちゅう起こっているように見えることが、
多くの人の言う『流れ』なのかな、と思っています。。
(主文に書いてますが『流れ』という言葉をどう使うかは人によりけりなので、
伯爵さんの使い方が間違っていると言っているわけでは無いので、悪しからず)
ということで。
別に1on1ではないので他の方も何かご意見あればどうぞ。
流れって試合にでてると感じるものですよね〜
でも、そのときに感じる流れ≠試合の流れであるのは確かだと思います。
流れにも大きさみたいなものがあり(自チームと相手チームそれぞれ持っている)、それが大きくなる事を流れが来るというのではないでしょうか?
(相手の流れが小さくなることも自チームに流れがくると表現する場合もあると考えれば)
流れがきていても(自チームの流れが大きくなっている)相手のチームの流れが
それより大きければ流れは移らないしということで。
部分的に流れが来る事もあります。ただ、試合全体で見たらそこの流れは結果に影響していない場合があり、解説者はそこについて触れないというとこでしょうかね。
聞いている人が野球経験者ばかりとは限らないので(ただでさえルールなど分かりにくいものですし)。
ただ個人の成績になると、その人の調子などによる影響が大きいのではないかと考えられると思います。塁が埋まってる状態で調子のいい人に回るとか、4番に回る(打てる確率の高い人)ときが流れがいいと感じやすいのですかね。
そこで打てなければ・・・となりますが。
でも、そのときに感じる流れ≠試合の流れであるのは確かだと思います。
流れにも大きさみたいなものがあり(自チームと相手チームそれぞれ持っている)、それが大きくなる事を流れが来るというのではないでしょうか?
(相手の流れが小さくなることも自チームに流れがくると表現する場合もあると考えれば)
流れがきていても(自チームの流れが大きくなっている)相手のチームの流れが
それより大きければ流れは移らないしということで。
部分的に流れが来る事もあります。ただ、試合全体で見たらそこの流れは結果に影響していない場合があり、解説者はそこについて触れないというとこでしょうかね。
聞いている人が野球経験者ばかりとは限らないので(ただでさえルールなど分かりにくいものですし)。
ただ個人の成績になると、その人の調子などによる影響が大きいのではないかと考えられると思います。塁が埋まってる状態で調子のいい人に回るとか、4番に回る(打てる確率の高い人)ときが流れがいいと感じやすいのですかね。
そこで打てなければ・・・となりますが。
トピ主さんは、多分「正解」をご存じで、あえて問題提起で留め、我々に「理論的な考え方」をするチャンスをくださり、我々のレベルまで目線をさげておられる「野球理論の先生」なんだと思います。
さてさて、40.箕河さんのお題はとても興味深いですね。
数字だけみても失点率3倍とは驚きです。
この事を解明し理論を習得すれば、今後のゲームで「失策発生時」の対処法と作戦立案におおいに役立ちます。
ただ、あれから私も先生のおっしゃるように「統計学に基づいた理論展開」を心掛けてはいるのですが、今回の失策のケースでも下記各種条件をどのように数値化して計算すればよいか気になってしょうがないのです。
○失策発生時の背景にて
・アウトカウント
・ランナーの有無
・イニングと点差
などなど細かい条件化では状況はまるで違うでしょう。
満塁でのタイムリーエラーなのか、ツーアウトランナー無しでのエラーなのか。
また、投手バテバテ状態でダメージの大きい失策なのか、投手絶好調で「ぜんぜんOK」とも思える失策なのか、、、。
あるいは、大量点差でリードし2〜3点いかれてもかまわない状況なのか、0対0の緊迫した展開なのか。
そして、凡フライをお見合いして躊躇しての落球なのか、果敢にトライした結果の積極的エラーなのかで、味方の精神的苦痛度と相手の歓喜度が大きく変わります(あ、コレ言うと「また精神論だ」と先生に怒らる)。
もはや、オツムの中が整理出来んのですよ。
先生からは、「本当に理論的に語る気持ちがあるのならば、
面倒くさがらずに数学(確率・統計)の勉強をして、
エクセルシートを開きながらデータ分析する必要がある」
とまで言われましたが、もっとヒントを欲しいのが正直な気持ちです。
『各種条件を数値化する方法』
まずはコレを学び、
『どの程度の条件までを考慮するのか/あるいは切り捨てるのか』
などの考え方と、
より正確な理論を導きだすための手法を伝授していただきたく思います。
さてさて、40.箕河さんのお題はとても興味深いですね。
数字だけみても失点率3倍とは驚きです。
この事を解明し理論を習得すれば、今後のゲームで「失策発生時」の対処法と作戦立案におおいに役立ちます。
ただ、あれから私も先生のおっしゃるように「統計学に基づいた理論展開」を心掛けてはいるのですが、今回の失策のケースでも下記各種条件をどのように数値化して計算すればよいか気になってしょうがないのです。
○失策発生時の背景にて
・アウトカウント
・ランナーの有無
・イニングと点差
などなど細かい条件化では状況はまるで違うでしょう。
満塁でのタイムリーエラーなのか、ツーアウトランナー無しでのエラーなのか。
また、投手バテバテ状態でダメージの大きい失策なのか、投手絶好調で「ぜんぜんOK」とも思える失策なのか、、、。
あるいは、大量点差でリードし2〜3点いかれてもかまわない状況なのか、0対0の緊迫した展開なのか。
そして、凡フライをお見合いして躊躇しての落球なのか、果敢にトライした結果の積極的エラーなのかで、味方の精神的苦痛度と相手の歓喜度が大きく変わります(あ、コレ言うと「また精神論だ」と先生に怒らる)。
もはや、オツムの中が整理出来んのですよ。
先生からは、「本当に理論的に語る気持ちがあるのならば、
面倒くさがらずに数学(確率・統計)の勉強をして、
エクセルシートを開きながらデータ分析する必要がある」
とまで言われましたが、もっとヒントを欲しいのが正直な気持ちです。
『各種条件を数値化する方法』
まずはコレを学び、
『どの程度の条件までを考慮するのか/あるいは切り捨てるのか』
などの考え方と、
より正確な理論を導きだすための手法を伝授していただきたく思います。
なんかごちゃごちゃしてきましたね。
とりあえず順番に。
伯爵さん>>38
>ちなみに、コメント27でのとむニコさんの内容を自らの経験で振り返ってみました。
>【コメント27】
>ご自身の中で確証バイアスが働いてるからこそ、
>チャンスにヒットを打てた = 相手の失投だった
>ここで一つ体験談をお話します。
これこそが確証バイアスなんですよ。
ご自身が信じていることがあって、それに見合った場面が、
見事にフラッシュバックされていますよね?
ここで幾つか考えてみました。
同様の場面で、仮に投手の失投でなくてもヒットは打てますよね?
逆に失投だったとしてもバットコントロールを一つミスれば凡打になりますよね?
だから、何を持って失投というのか、というのを打者が打つ前に調べるのが大事だと思いませんか?ホームランの後は失投が多くなると信じている人にとっては、次の打席の初球でヒットが出たら、それを『全て』失投とみなしてしまうのではないでしょうか?実際に伯爵さんに来た玉は失投だったかもしれません。でも他の人がヒットにした球は失投なのでしょうか?ベンチから見てても、私にはストライクゾーン内のどこを通っているのかは,特に左右についてはボール1個の正確さでは絶対にわかりません。
あるいは、伯爵さんは高めの甘い球をヒットに出来たと書きましたが、これが高めの苦手な人が伯爵さんと同じ思考をしたとして、必ずヒットに出来たといえるでしょうか?仮に凡打だったとしてもそれを外から見てる伯爵さんは『失投だったのに勿体無い』と言えるのでしょうか?大事なのはヒットが出たかどうかではありませんよね?仮にヒットが出なくても、そのときその投手は失投したわけです。それを、ご自身がヒットを打てた場面が思い出されるというのは、私にはやはり『ヒット=失投』と頭の中で刷り込まれてるように見えてならないのです。他の人の話を聞いても常に、良い結果を残したことばかりが上がってきます。だから私は確証バイアスに見えてならないので、まずはデータ・数字、と言っているのです。
もう一点、セオリーという点について。セオリーが全て正しいのでしょうか?例えば一番簡単な例が打順です。1番出塁率が高い人、2番器用でヒットも打てる、3番超打者、4番スラッガー、、、、というのが、もうどこでも確立されてるセオリーになってますよね。しかしはたしてそれが一番正しい打順なのでしょうか?中日Dの歌に代表されるように、都合のいい得点方法を頭の中で作り上げてるから、それが正しく見えるだけなのではないでしょうか?
しかし仮に1番福留・2番ウッズ・3番荒木・・・・ などの様にする監督が居ても、すぐに淘汰されるでしょう。何故なら『一般に信じられていることに反すること』に取り組むのなら100%結果を残さなければならないからです。仮に、その打順が本当は科学的に正しいものだとしても。その点、一般に信じられていることをやっていれば仮に結果が出なくてもそのことで責められません。
正しい正しく無いというのは、あくまで自分の中でそう『信じている』だけであって、外部に向かって主張するべきでは無いのではないと思います。信じているのはかまいません。しかし、自分の信じていることを他人に信じてもらうには、科学的方法論によるか、あるいは自分の言うことは問答無用で信じてもらえるような人になるしか無いと思います(プロ野球の監督とか解説者でしょうか)。ただ、いえることは、前者であればそれが真理だと言えるのに対し、後者であればそれはやはり『信じている』ことの域を過ぎないとおもいます。
私が前のコメントにも良く『信じている』といっているのはこのためです。
とりあえず順番に。
伯爵さん>>38
>ちなみに、コメント27でのとむニコさんの内容を自らの経験で振り返ってみました。
>【コメント27】
>ご自身の中で確証バイアスが働いてるからこそ、
>チャンスにヒットを打てた = 相手の失投だった
>ここで一つ体験談をお話します。
これこそが確証バイアスなんですよ。
ご自身が信じていることがあって、それに見合った場面が、
見事にフラッシュバックされていますよね?
ここで幾つか考えてみました。
同様の場面で、仮に投手の失投でなくてもヒットは打てますよね?
逆に失投だったとしてもバットコントロールを一つミスれば凡打になりますよね?
だから、何を持って失投というのか、というのを打者が打つ前に調べるのが大事だと思いませんか?ホームランの後は失投が多くなると信じている人にとっては、次の打席の初球でヒットが出たら、それを『全て』失投とみなしてしまうのではないでしょうか?実際に伯爵さんに来た玉は失投だったかもしれません。でも他の人がヒットにした球は失投なのでしょうか?ベンチから見てても、私にはストライクゾーン内のどこを通っているのかは,特に左右についてはボール1個の正確さでは絶対にわかりません。
あるいは、伯爵さんは高めの甘い球をヒットに出来たと書きましたが、これが高めの苦手な人が伯爵さんと同じ思考をしたとして、必ずヒットに出来たといえるでしょうか?仮に凡打だったとしてもそれを外から見てる伯爵さんは『失投だったのに勿体無い』と言えるのでしょうか?大事なのはヒットが出たかどうかではありませんよね?仮にヒットが出なくても、そのときその投手は失投したわけです。それを、ご自身がヒットを打てた場面が思い出されるというのは、私にはやはり『ヒット=失投』と頭の中で刷り込まれてるように見えてならないのです。他の人の話を聞いても常に、良い結果を残したことばかりが上がってきます。だから私は確証バイアスに見えてならないので、まずはデータ・数字、と言っているのです。
もう一点、セオリーという点について。セオリーが全て正しいのでしょうか?例えば一番簡単な例が打順です。1番出塁率が高い人、2番器用でヒットも打てる、3番超打者、4番スラッガー、、、、というのが、もうどこでも確立されてるセオリーになってますよね。しかしはたしてそれが一番正しい打順なのでしょうか?中日Dの歌に代表されるように、都合のいい得点方法を頭の中で作り上げてるから、それが正しく見えるだけなのではないでしょうか?
しかし仮に1番福留・2番ウッズ・3番荒木・・・・ などの様にする監督が居ても、すぐに淘汰されるでしょう。何故なら『一般に信じられていることに反すること』に取り組むのなら100%結果を残さなければならないからです。仮に、その打順が本当は科学的に正しいものだとしても。その点、一般に信じられていることをやっていれば仮に結果が出なくてもそのことで責められません。
正しい正しく無いというのは、あくまで自分の中でそう『信じている』だけであって、外部に向かって主張するべきでは無いのではないと思います。信じているのはかまいません。しかし、自分の信じていることを他人に信じてもらうには、科学的方法論によるか、あるいは自分の言うことは問答無用で信じてもらえるような人になるしか無いと思います(プロ野球の監督とか解説者でしょうか)。ただ、いえることは、前者であればそれが真理だと言えるのに対し、後者であればそれはやはり『信じている』ことの域を過ぎないとおもいます。
私が前のコメントにも良く『信じている』といっているのはこのためです。
箕河さん
素晴らしい示唆にとんだ例をありがとうございます。
しかしながらその思考過程には一部前提として正しく無い点があります。エラーが起これば、必然的に出塁・進塁が起こりえます。そのため、エラーの起きたイニングの防御率と全イニングの防御率のイニングを比べたら、100%後者が低くなります。何故なら後者には、ランナーが全く出ていない三者凡退のイニングも含まれていますので。
ならば比べるべきは、エラーが出たイニングの防御率と、エラー以外でランナーが一人でも出たイニングの防御率についてではないでしょうか。1イニングの被安打数が1200,被盗塁を50,与四死球300とすると69のエラーによる進塁出塁はそこまで多くないので1280イニングから3者凡退のイニング数を引いて防御率を計算した方がベターではないでしょうか。
ここで折角良いデータを頂いたので、私も検討してみました。
命題:一つのエラーが起きたイニングに連続してエラーは起きやすいか?
ここで逆の仮定をして見ます。つまり、一つ一つのエラーは独立だと仮定します。1280の事象のうちの69エラーは一つ一つが稀なことだとみなせるので、多数の母集団の中からの少ない確率で『独立に』起こる現象はポアソン分布 P(n,λ)=λ^n/n! EXP(-λ) に従います。こういうことは現実では保険会社などで行なわれています。例えば1年間に自動車1280台中、0事故の車が1218台、1回事故を起こす車が56台、2回事故を起こす車が5台、、、、といった形です。同様に1280イニング中に0エラーのイニングが1218、1エラーのイニングが56、2エラーのイニングが5、3エラーのイニングが1です。これがポアソン分布に従うか検討します。
全体で69エラーなのでλ=69/1280。これをポアソン分布に当てはめ,n=0,1,2,3を代入し確率を求め,1280を掛けて理論値を推定します。
結果を以下に示します
エラー 推定 実績
0 1212.83 1218
1 65.38 56
2 1.76 5
3 0.03 1
このあと、本当にポアソン分布に従っているかχ二乗適合度検定(推定値と実績のズレが、偶然起こりえることなのか、偶然では起こりえないくらい離れているのか)を行い確かめる必要があります。しかしながら母数がいささか少なすぎるため、適合度検定ができません。
しかしながら、如何でしょうか、上記の結果を見て。
エラーが起きた回にさらにエラーが起こるのは、偶然とは言えなさそうです。
偶然であれば1280イニングで1.76回程度しかおこりません。
しかし実際には5回も起こりました。エラーが3回起こることについても然りです。
これを確実に言うためには上記で書いたとおり適合度検定をする必要がありますが、
おそらく、エラーは完全に偶然で起こるわけではなさそうです。
エラーが起きたときは次のエラーを誘発しやすい、そう言えそうです!
どうでしょう?
面白くありませんか?
今まで漫然と、エラーが起きたら流れが良い悪い、とか言っていたのに、
それがほぼ数字で示されました。
(完全に示すには全球団のデータをいただければ計算します)
さて、こういうことを計算していないのに、
『エラーは続きやすい』と言っても
『完全に独立かもしれないだろ』と言われたときに、
反論する術(数学的な考察)が全くありません。
誰も説得できませんよね。
それが今回、確率の計算をしたことにより、
野球の一つの真理にたどり着いたといえるのではないでしょうか。
(ちょっと大げさですかね)
あと、私のことを怠慢だとおっしゃいましたが、前にも書いたとおり、私は野球の専門家ではありませんし、お金を貰っているわけでもないので詳細な分析は全くしていません。しかし野球は大好きです。 一方で、野球を専門にしている人が科学的に考える事なしに、自分の経験・師の教えを疑うことなく信じ、それで多くの人が影響を受けるのに疑問を感じているのです。 それが真理であるのかどうかも客観的に確かめようとせずに。
このトピックを見て、自分が数字を根拠とすることなしに信じていたことを、
ちょっとでも考えてくれる人が一人でもいたら幸です。
素晴らしい示唆にとんだ例をありがとうございます。
しかしながらその思考過程には一部前提として正しく無い点があります。エラーが起これば、必然的に出塁・進塁が起こりえます。そのため、エラーの起きたイニングの防御率と全イニングの防御率のイニングを比べたら、100%後者が低くなります。何故なら後者には、ランナーが全く出ていない三者凡退のイニングも含まれていますので。
ならば比べるべきは、エラーが出たイニングの防御率と、エラー以外でランナーが一人でも出たイニングの防御率についてではないでしょうか。1イニングの被安打数が1200,被盗塁を50,与四死球300とすると69のエラーによる進塁出塁はそこまで多くないので1280イニングから3者凡退のイニング数を引いて防御率を計算した方がベターではないでしょうか。
ここで折角良いデータを頂いたので、私も検討してみました。
命題:一つのエラーが起きたイニングに連続してエラーは起きやすいか?
ここで逆の仮定をして見ます。つまり、一つ一つのエラーは独立だと仮定します。1280の事象のうちの69エラーは一つ一つが稀なことだとみなせるので、多数の母集団の中からの少ない確率で『独立に』起こる現象はポアソン分布 P(n,λ)=λ^n/n! EXP(-λ) に従います。こういうことは現実では保険会社などで行なわれています。例えば1年間に自動車1280台中、0事故の車が1218台、1回事故を起こす車が56台、2回事故を起こす車が5台、、、、といった形です。同様に1280イニング中に0エラーのイニングが1218、1エラーのイニングが56、2エラーのイニングが5、3エラーのイニングが1です。これがポアソン分布に従うか検討します。
全体で69エラーなのでλ=69/1280。これをポアソン分布に当てはめ,n=0,1,2,3を代入し確率を求め,1280を掛けて理論値を推定します。
結果を以下に示します
エラー 推定 実績
0 1212.83 1218
1 65.38 56
2 1.76 5
3 0.03 1
このあと、本当にポアソン分布に従っているかχ二乗適合度検定(推定値と実績のズレが、偶然起こりえることなのか、偶然では起こりえないくらい離れているのか)を行い確かめる必要があります。しかしながら母数がいささか少なすぎるため、適合度検定ができません。
しかしながら、如何でしょうか、上記の結果を見て。
エラーが起きた回にさらにエラーが起こるのは、偶然とは言えなさそうです。
偶然であれば1280イニングで1.76回程度しかおこりません。
しかし実際には5回も起こりました。エラーが3回起こることについても然りです。
これを確実に言うためには上記で書いたとおり適合度検定をする必要がありますが、
おそらく、エラーは完全に偶然で起こるわけではなさそうです。
エラーが起きたときは次のエラーを誘発しやすい、そう言えそうです!
どうでしょう?
面白くありませんか?
今まで漫然と、エラーが起きたら流れが良い悪い、とか言っていたのに、
それがほぼ数字で示されました。
(完全に示すには全球団のデータをいただければ計算します)
さて、こういうことを計算していないのに、
『エラーは続きやすい』と言っても
『完全に独立かもしれないだろ』と言われたときに、
反論する術(数学的な考察)が全くありません。
誰も説得できませんよね。
それが今回、確率の計算をしたことにより、
野球の一つの真理にたどり着いたといえるのではないでしょうか。
(ちょっと大げさですかね)
あと、私のことを怠慢だとおっしゃいましたが、前にも書いたとおり、私は野球の専門家ではありませんし、お金を貰っているわけでもないので詳細な分析は全くしていません。しかし野球は大好きです。 一方で、野球を専門にしている人が科学的に考える事なしに、自分の経験・師の教えを疑うことなく信じ、それで多くの人が影響を受けるのに疑問を感じているのです。 それが真理であるのかどうかも客観的に確かめようとせずに。
このトピックを見て、自分が数字を根拠とすることなしに信じていたことを、
ちょっとでも考えてくれる人が一人でもいたら幸です。
>風の音さん
なにやら皮肉をひしひしと感じますがw
科学的方法論とは『ある前提』を置いたときに、
その前提の下で、誰がやっても同じ結果が得られることです。
たしかに野球はありとあらゆる場面があり、おそらく二度として同じものは無いでしょう。
でもそれを、実際はみなさん色々なところで単純化して考えていますよね?
例えば一番単純な例が打率についてです。打席に立つにも色々な状況がありますが、それらを全てひっくるめて『打率』としてその選手を見る指標の一つとしてみます。そのときに、対戦した投手の防御率の平均がどのくらいか、のデータは見たことがありません。例えばパリーグの投手防御率。日ハム、ロッテは防御率7位以上のピッチャーをそれぞれ3人擁しています。ということは、日ハム、ロッテの打者は他4球団は相対的に実力の低いピッチャーと対戦することになるため、打率が少し高めに出るかもしれませんよね?しかしながら、そういうことは無視して、とりあえず打率は打率として同じに見ていますよね(少なくとも私はこの点について言及した記事・ニュースは見たことがありません。それとも野球の専門家の中であればこれは多々取り上げられることなのでしょうか)。
このようにトコトンまで落とし込めば、疑問は無限に沸いてきます。何故なら世界は複雑ですから。それをあえて自分が納得できるところまで落とし込む必要があります。例えば、この例で言えば、そういう対戦投手の防御率の違いはとりあえず無視していることになります。それが『無視できる』ということを前提にして初めて、打率は意味を持ってくるのです。ですから、この前提を認められず、対戦投手の実力に左右されると主張する人にとっては、われわれが普段使う『打率』は打者の実力を表してるとは言えません。
仮に私が何かを分析したとしても、
『この前提が足りない』
『これをこう単純化するのはおかしい』
そう主張する人にとっては、私のその分析は無意味になります。ですから、科学的に考える際に大事なことは、多くの人が納得できる前提を見つけることです。
極端な話、少なくとも私たちは、明日ボールを右手に持ちそのボールを手放したら、ボールが下に落ちていくと信じていますよね?明日はまだ来ていません。しかし私たちはボールが落ちると信じています。ボールが落ちるという前提で、今を生きていますよね。だから、例えば
いや、あしたボールが落ちるか分らない。
神様がイタズラしてそのボールを支えるかもしれない
と主張する人がいたら、私はその人を説得する術がありません。ですから、ある前提を正しいと認めて、その上での話しになるのです。例えば物理学は、明日ボールが落ちることを前提に、今の理論があるのです。
ちなみに箕河さんや私の考察では『エラーは全て同一』と考えています。すなわち、2outランナー無しのエラー、ピンチの時のエラー、連打後のエラー、エラーは各々違いますが、そういうエラーを全て同様のものとみなしての考察です。ですから、『エラーは状況によって全く違う!』と言われる方には、私が『エラーは全て同一』とした前提の下に書いた>>44の考察は、受け入れられないでしょう。
しかし、そうやって全てを否定していくと、実際に一つ一つは全部違うので、それこそ個々の話になってしまいます。個々の話なんだから統計的な判断では無い!経験が全てだ!そうおっしゃられるかたを説得する術は私は持っていません。
これが、
>『どの程度の条件までを考慮するのか/あるいは切り捨てるのか』
についての答えです。自分で確かめるだけならば自分で満足するくらいまでで構いませんし、説得したい人がいるなら、説得したい人が満足するところまで切り捨てない、です。しかしながら極論で話したとおり、屁理屈(ボールが落ちない)を言おうと思えばいくらでも言えるので、まぁ多くの人が妥当だと認めてくれそうな点までです。それは私にはどこかわかりません。
>『各種条件を数値化する方法』
これについては細かいものが必要な数値なら必要なだけ、スコアブックででていますよね。仮に、テンパっているとか、イケイケムードで乗っているなど、あるいは流れ、など目に見えないことが左右しているかどうかを検証したいとします。そのときは、そういう数値化できない効用を全く0だと仮定して計算して、その計算と現実のデータとでは偶然では起こりえないような乖離があるかどうかを見ます。そして、偶然で起こりえるとは考えにくい(くらい低い確率だ)という結論が導かれたら、そのとき初めてその様な効用があったと理論付けるのが一般的な方法論です。
さて、本題で例えばの話は。
>>44で書いてることとしてください。
前提は『全てのエラーは状況には寄らないものである』です。
なにやら皮肉をひしひしと感じますがw
科学的方法論とは『ある前提』を置いたときに、
その前提の下で、誰がやっても同じ結果が得られることです。
たしかに野球はありとあらゆる場面があり、おそらく二度として同じものは無いでしょう。
でもそれを、実際はみなさん色々なところで単純化して考えていますよね?
例えば一番単純な例が打率についてです。打席に立つにも色々な状況がありますが、それらを全てひっくるめて『打率』としてその選手を見る指標の一つとしてみます。そのときに、対戦した投手の防御率の平均がどのくらいか、のデータは見たことがありません。例えばパリーグの投手防御率。日ハム、ロッテは防御率7位以上のピッチャーをそれぞれ3人擁しています。ということは、日ハム、ロッテの打者は他4球団は相対的に実力の低いピッチャーと対戦することになるため、打率が少し高めに出るかもしれませんよね?しかしながら、そういうことは無視して、とりあえず打率は打率として同じに見ていますよね(少なくとも私はこの点について言及した記事・ニュースは見たことがありません。それとも野球の専門家の中であればこれは多々取り上げられることなのでしょうか)。
このようにトコトンまで落とし込めば、疑問は無限に沸いてきます。何故なら世界は複雑ですから。それをあえて自分が納得できるところまで落とし込む必要があります。例えば、この例で言えば、そういう対戦投手の防御率の違いはとりあえず無視していることになります。それが『無視できる』ということを前提にして初めて、打率は意味を持ってくるのです。ですから、この前提を認められず、対戦投手の実力に左右されると主張する人にとっては、われわれが普段使う『打率』は打者の実力を表してるとは言えません。
仮に私が何かを分析したとしても、
『この前提が足りない』
『これをこう単純化するのはおかしい』
そう主張する人にとっては、私のその分析は無意味になります。ですから、科学的に考える際に大事なことは、多くの人が納得できる前提を見つけることです。
極端な話、少なくとも私たちは、明日ボールを右手に持ちそのボールを手放したら、ボールが下に落ちていくと信じていますよね?明日はまだ来ていません。しかし私たちはボールが落ちると信じています。ボールが落ちるという前提で、今を生きていますよね。だから、例えば
いや、あしたボールが落ちるか分らない。
神様がイタズラしてそのボールを支えるかもしれない
と主張する人がいたら、私はその人を説得する術がありません。ですから、ある前提を正しいと認めて、その上での話しになるのです。例えば物理学は、明日ボールが落ちることを前提に、今の理論があるのです。
ちなみに箕河さんや私の考察では『エラーは全て同一』と考えています。すなわち、2outランナー無しのエラー、ピンチの時のエラー、連打後のエラー、エラーは各々違いますが、そういうエラーを全て同様のものとみなしての考察です。ですから、『エラーは状況によって全く違う!』と言われる方には、私が『エラーは全て同一』とした前提の下に書いた>>44の考察は、受け入れられないでしょう。
しかし、そうやって全てを否定していくと、実際に一つ一つは全部違うので、それこそ個々の話になってしまいます。個々の話なんだから統計的な判断では無い!経験が全てだ!そうおっしゃられるかたを説得する術は私は持っていません。
これが、
>『どの程度の条件までを考慮するのか/あるいは切り捨てるのか』
についての答えです。自分で確かめるだけならば自分で満足するくらいまでで構いませんし、説得したい人がいるなら、説得したい人が満足するところまで切り捨てない、です。しかしながら極論で話したとおり、屁理屈(ボールが落ちない)を言おうと思えばいくらでも言えるので、まぁ多くの人が妥当だと認めてくれそうな点までです。それは私にはどこかわかりません。
>『各種条件を数値化する方法』
これについては細かいものが必要な数値なら必要なだけ、スコアブックででていますよね。仮に、テンパっているとか、イケイケムードで乗っているなど、あるいは流れ、など目に見えないことが左右しているかどうかを検証したいとします。そのときは、そういう数値化できない効用を全く0だと仮定して計算して、その計算と現実のデータとでは偶然では起こりえないような乖離があるかどうかを見ます。そして、偶然で起こりえるとは考えにくい(くらい低い確率だ)という結論が導かれたら、そのとき初めてその様な効用があったと理論付けるのが一般的な方法論です。
さて、本題で例えばの話は。
>>44で書いてることとしてください。
前提は『全てのエラーは状況には寄らないものである』です。
>とむニコ♪さん
皮肉だなんて、、、すいません、尊敬できる人だという期待を持っていただけです。
さて、今回のエラーの考察ですが、「エラーを全て同様のものとみなして」が前提であれば納得です。
私がゴチャゴチャ考え過ぎでした。
それに、44のポアソン分布による算出方法は目からウロコです。
保険会社が自動車事故に適用しているのは知っていましたが、エラー連鎖論に用いるのはさすがです。
ところで、42でセオリーに疑問を投げかけていらっしゃいますが、セオリーとは長い歴史の中で培われた統計や確率に基づいた最終結論であり、もっとも成功率の高い手法と理解しておりました。
「相手のウラをかく」「相手をかく乱する」等の目的でセオリーに反した作戦に出ることもありますが、それはセオリーを信じているのが前提での発想です。
てっきり、とむニコ♪さんの「正解」はセオリーの中にあるというオチを予想していただけに、とむニコ♪さんの思考の深さに驚くと同時にと私めの浅はかさを恥ずかしく思います。
やっぱりアナタは先生です。
皮肉だなんて、、、すいません、尊敬できる人だという期待を持っていただけです。
さて、今回のエラーの考察ですが、「エラーを全て同様のものとみなして」が前提であれば納得です。
私がゴチャゴチャ考え過ぎでした。
それに、44のポアソン分布による算出方法は目からウロコです。
保険会社が自動車事故に適用しているのは知っていましたが、エラー連鎖論に用いるのはさすがです。
ところで、42でセオリーに疑問を投げかけていらっしゃいますが、セオリーとは長い歴史の中で培われた統計や確率に基づいた最終結論であり、もっとも成功率の高い手法と理解しておりました。
「相手のウラをかく」「相手をかく乱する」等の目的でセオリーに反した作戦に出ることもありますが、それはセオリーを信じているのが前提での発想です。
てっきり、とむニコ♪さんの「正解」はセオリーの中にあるというオチを予想していただけに、とむニコ♪さんの思考の深さに驚くと同時にと私めの浅はかさを恥ずかしく思います。
やっぱりアナタは先生です。
流れは選手のメンタルが作り出すものだと思っています。
1プレーをきっかけに『流れが良くなった』あるいは『悪くなった』と考える“精神状態”が流れを作り、プレーに反映しているのだと思います。
流れが良くなったと考えればチームに勢いが生まれてのびのびプレーできるし、悪くなったと考えてしまえばムードが悪くなり淡泊なプレーになります。
乱暴に言ってしまえば“流れは存在しない”派ですが、精神状態がプレーに反映されると仮定すれば無視できない問題であり、チームに安定した流れをもたらすには禅の精神が不可欠となってきます。
一喜一憂せず、波のない、常に一定の精神状態を保つ。
イチローや松井が『打席に入るときはいつも同じ状態を心掛ける』のも安定したプレーを実現するためのメンタルコントロール法の一つだと思います。
全くの無感情であるべきとまでは言いませんが、プレーの安定を求めるには、精神の安定が土台になると思います。
1プレーをきっかけに『流れが良くなった』あるいは『悪くなった』と考える“精神状態”が流れを作り、プレーに反映しているのだと思います。
流れが良くなったと考えればチームに勢いが生まれてのびのびプレーできるし、悪くなったと考えてしまえばムードが悪くなり淡泊なプレーになります。
乱暴に言ってしまえば“流れは存在しない”派ですが、精神状態がプレーに反映されると仮定すれば無視できない問題であり、チームに安定した流れをもたらすには禅の精神が不可欠となってきます。
一喜一憂せず、波のない、常に一定の精神状態を保つ。
イチローや松井が『打席に入るときはいつも同じ状態を心掛ける』のも安定したプレーを実現するためのメンタルコントロール法の一つだと思います。
全くの無感情であるべきとまでは言いませんが、プレーの安定を求めるには、精神の安定が土台になると思います。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
野球理論 更新情報
-
最新のトピック
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
野球理論のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90054人
- 2位
- 酒好き
- 170690人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208287人