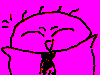2008年12月29日
13年度から高校で本格実施される新しい学習指導要領。22日に文部科学省が発表した改訂案は英語教育への力点の置き方が注目されたが、他にも様々な特徴が見て取れる。
■世界史―日本史・地理との「関連」ていねいに
「未履修問題」が06年に発覚し、教育のあり方が問われた世界史。今回の学習指導要領改訂案はその世界史を必修科目として維持する一方、日本史、世界史、地理の三科目それぞれについて相互に関連付けて教えるよう明記。世界史は特に、地理や日本史にからむ内容を充実させるよう求めた。「敷居の高さ」を取り払おうとする狙いがある。
東京都千代田区の大妻高校で日本史を担当する寺尾隆雄教諭(54)は、幕末のペリー来航を教える際、米国西海岸の地図を生徒に見せる。日本に開国を迫った背景には、鯨の油やひげを得るための捕鯨船の補給地を求めていた事情がある。生徒に教えるには、ゴールドラッシュなど当時の米国の情勢、風俗の説明が欠かせないという。
明治新政府の指導者、大久保利通が暗殺された「紀尾井坂の変」。現場は同高に近く、寺尾教諭は生徒に地図を示しながら、江戸から現代に至る地域の変遷を取り上げて興味をわかせる。「教える上で、歴史という時間軸と地理という空間軸は両方とも欠かせない。生徒も地図を見るとイメージがわき、しっかりと覚える」。次の指導要領を具現化したような教え方だ。今後、同様の取り組みが世界史などでも求められることになる。
08年度のセンター試験の世界史の受験者(AとBの合計)は約9万6千人。日本史(同)の約14万8千人、地理(同)の約11万3千人を大きく下回る。「ならば、最初から生徒みんなに教えることはない」と、指導要領で必修とされているにもかかわらず、高校側がルール無視で世界史を外したのが「未履修」問題だった。
世界史をめぐる状況は複雑だ。大学入試は知識偏重に傾いており、関東地方の公立高校の世界史教員は「入試を突破するために、進学校ほど詰め込み型の授業をせざるを得ない」とこぼす。そんな中で、指導要領改訂案がうたうように、日本史や地理とていねいに「関連づけ」しながら生き生きした授業ができるのか、疑問は残る。 世界史の「不人気」は、中学の歴史教育が日本史中心になっているため生徒の目が向きにくくなっているという背景もある。教員養成のあり方もからみ、高校の領域だけで解決できない問題は多い。
未履修問題の発覚後、各科目の研究者らによって発足した日本学術会議「高校地理歴史科教育に関する分科会」。地理と歴史双方の視点をいかに「融合」させるかという立場で議論を重ねてきた。
委員長を務める油井大三郎・東京女子大教授は改訂案について、「長期的には、新たな科目を設けるなどの対応をしないと根本的な解決にならない」と話す。分科会では、日本史と世界史を統合した「歴史基礎」とそれに対応する「地理基礎」という科目を新設して必修にする案なども出ており、今後も議論を続けるという。(宮本茂頼)
■各教科で道徳「充実」
06年に教育基本法が改正されてから、高校の学習指導要領が変わるのは初めて。今春発表された小中学校の指導要領同様、道徳教育の充実が盛り込まれた。基本法の「愛国心条項」を受け、道徳教育の目標として「我が国と郷土」を愛する日本人を育てることが新たに総則に盛り込まれたほか、道徳教育の充実に向けた「全体計画」を各校で定めることも義務化された。
道徳教育の充実は、教育基本法が教育目標に「豊かな情操と道徳心を培う」と掲げたことに対応した措置だ。
小中学校には「道徳の時間」が週1コマ程度あり、全体計画もつくっている。道徳教育のリーダー的立場である道徳主任を置く学校も少なくない。しかし、高校には「道徳の時間」はなく、「充実」を求められてもどう対応したらいいのか、現場で戸惑いの声も上がりそうだ。
道徳教育充実の方針は、各教科・科目の改訂案にも現れている。倫理では「生命に対する畏敬(いけい)の念」という言葉を新たに盛り込み、それに基づいて生き方などを考えさせるようにした。また、愛国心条項を反映した改訂として、日本史で衣食住や風習・信仰などの生活文化、国語で古典、保健体育で武道、音楽では民謡など日本の伝統音楽に関する学習をそれぞれ充実させることとした。(大西史晃)
■広がる学力差 一律の対応は困難
高校の学習指導要領の改訂案は、「習うべき英単語を4割増やし、英語の授業を英語で行う」「理・数で前回削減した分を戻す」など、「ゆとり」路線の変更が目につく。そして同時に、初めて「義務教育の内容も必要に応じて教える」と書いたことも特徴に挙げられる。
具体的には、数学の無理数の四則計算や因数分解など中学で学ぶ項目を高校でも再び取り上げることにし、理科でも「中学校との接続」を各科目で打ち出した。高校の指導要領の後ろに中学の指導要領を付けることも検討中だ。
文科省の担当者は「中学校を卒業する生徒がすべて中学段階の学習内容を身につけているわけではない現実を明記し、どんどん再学習をしてほしいというメッセージを出した」と話す。
今回の改訂案では、近年の「多様化路線」にも一定の歯止めをかけ、国・数・英で科目を再編して「共通科目」を新設した。「高校で少なくともこれだけは身につけてほしい」と文科省が考える基礎的な必修科目だ。その一方、教科書の検定基準の緩和と歩調を合わせ、指導要領は学ぶべき「最低基準」であり、発展的な内容をどんどん教えて構わないという要素も強めた。
文科省は近年、公立高校について都道府県や校長の裁量を広げ、カリキュラムの自由度も高めてきた。結果、難関大学を目指す進学重視校から中退者が毎年多数出るような学校まで、学力差が以前にも増して広がる状況が生まれている。高校進学率が97%に上るなか「高校を卒業することでどれぐらいの学力が保証されるのか」という問いかけは強まっている。
今回の改訂で掲げた「多様性と共通性のバランス」は、こうした「開いた学力の幅」に対処しようとした結果だといえる。
しかし、義務教育でもなく、学校によって授業の中身も生徒のタイプもまるで異なる高校の学習内容について、一つの指導要領で基準を示すのはもはや難しくなっているのではないか。
文科省内部では01年に「高等学校課」がなくなって以来、高校教育全般を専門的に担当する部署がない。省内でも「エアポケットになっている」という声は多い。社会構造が激変する中で、高校の位置づけをどう示すのか。しっかり議論して方向をさぐるときに来ている。(上野創)
13年度から高校で本格実施される新しい学習指導要領。22日に文部科学省が発表した改訂案は英語教育への力点の置き方が注目されたが、他にも様々な特徴が見て取れる。
■世界史―日本史・地理との「関連」ていねいに
「未履修問題」が06年に発覚し、教育のあり方が問われた世界史。今回の学習指導要領改訂案はその世界史を必修科目として維持する一方、日本史、世界史、地理の三科目それぞれについて相互に関連付けて教えるよう明記。世界史は特に、地理や日本史にからむ内容を充実させるよう求めた。「敷居の高さ」を取り払おうとする狙いがある。
東京都千代田区の大妻高校で日本史を担当する寺尾隆雄教諭(54)は、幕末のペリー来航を教える際、米国西海岸の地図を生徒に見せる。日本に開国を迫った背景には、鯨の油やひげを得るための捕鯨船の補給地を求めていた事情がある。生徒に教えるには、ゴールドラッシュなど当時の米国の情勢、風俗の説明が欠かせないという。
明治新政府の指導者、大久保利通が暗殺された「紀尾井坂の変」。現場は同高に近く、寺尾教諭は生徒に地図を示しながら、江戸から現代に至る地域の変遷を取り上げて興味をわかせる。「教える上で、歴史という時間軸と地理という空間軸は両方とも欠かせない。生徒も地図を見るとイメージがわき、しっかりと覚える」。次の指導要領を具現化したような教え方だ。今後、同様の取り組みが世界史などでも求められることになる。
08年度のセンター試験の世界史の受験者(AとBの合計)は約9万6千人。日本史(同)の約14万8千人、地理(同)の約11万3千人を大きく下回る。「ならば、最初から生徒みんなに教えることはない」と、指導要領で必修とされているにもかかわらず、高校側がルール無視で世界史を外したのが「未履修」問題だった。
世界史をめぐる状況は複雑だ。大学入試は知識偏重に傾いており、関東地方の公立高校の世界史教員は「入試を突破するために、進学校ほど詰め込み型の授業をせざるを得ない」とこぼす。そんな中で、指導要領改訂案がうたうように、日本史や地理とていねいに「関連づけ」しながら生き生きした授業ができるのか、疑問は残る。 世界史の「不人気」は、中学の歴史教育が日本史中心になっているため生徒の目が向きにくくなっているという背景もある。教員養成のあり方もからみ、高校の領域だけで解決できない問題は多い。
未履修問題の発覚後、各科目の研究者らによって発足した日本学術会議「高校地理歴史科教育に関する分科会」。地理と歴史双方の視点をいかに「融合」させるかという立場で議論を重ねてきた。
委員長を務める油井大三郎・東京女子大教授は改訂案について、「長期的には、新たな科目を設けるなどの対応をしないと根本的な解決にならない」と話す。分科会では、日本史と世界史を統合した「歴史基礎」とそれに対応する「地理基礎」という科目を新設して必修にする案なども出ており、今後も議論を続けるという。(宮本茂頼)
■各教科で道徳「充実」
06年に教育基本法が改正されてから、高校の学習指導要領が変わるのは初めて。今春発表された小中学校の指導要領同様、道徳教育の充実が盛り込まれた。基本法の「愛国心条項」を受け、道徳教育の目標として「我が国と郷土」を愛する日本人を育てることが新たに総則に盛り込まれたほか、道徳教育の充実に向けた「全体計画」を各校で定めることも義務化された。
道徳教育の充実は、教育基本法が教育目標に「豊かな情操と道徳心を培う」と掲げたことに対応した措置だ。
小中学校には「道徳の時間」が週1コマ程度あり、全体計画もつくっている。道徳教育のリーダー的立場である道徳主任を置く学校も少なくない。しかし、高校には「道徳の時間」はなく、「充実」を求められてもどう対応したらいいのか、現場で戸惑いの声も上がりそうだ。
道徳教育充実の方針は、各教科・科目の改訂案にも現れている。倫理では「生命に対する畏敬(いけい)の念」という言葉を新たに盛り込み、それに基づいて生き方などを考えさせるようにした。また、愛国心条項を反映した改訂として、日本史で衣食住や風習・信仰などの生活文化、国語で古典、保健体育で武道、音楽では民謡など日本の伝統音楽に関する学習をそれぞれ充実させることとした。(大西史晃)
■広がる学力差 一律の対応は困難
高校の学習指導要領の改訂案は、「習うべき英単語を4割増やし、英語の授業を英語で行う」「理・数で前回削減した分を戻す」など、「ゆとり」路線の変更が目につく。そして同時に、初めて「義務教育の内容も必要に応じて教える」と書いたことも特徴に挙げられる。
具体的には、数学の無理数の四則計算や因数分解など中学で学ぶ項目を高校でも再び取り上げることにし、理科でも「中学校との接続」を各科目で打ち出した。高校の指導要領の後ろに中学の指導要領を付けることも検討中だ。
文科省の担当者は「中学校を卒業する生徒がすべて中学段階の学習内容を身につけているわけではない現実を明記し、どんどん再学習をしてほしいというメッセージを出した」と話す。
今回の改訂案では、近年の「多様化路線」にも一定の歯止めをかけ、国・数・英で科目を再編して「共通科目」を新設した。「高校で少なくともこれだけは身につけてほしい」と文科省が考える基礎的な必修科目だ。その一方、教科書の検定基準の緩和と歩調を合わせ、指導要領は学ぶべき「最低基準」であり、発展的な内容をどんどん教えて構わないという要素も強めた。
文科省は近年、公立高校について都道府県や校長の裁量を広げ、カリキュラムの自由度も高めてきた。結果、難関大学を目指す進学重視校から中退者が毎年多数出るような学校まで、学力差が以前にも増して広がる状況が生まれている。高校進学率が97%に上るなか「高校を卒業することでどれぐらいの学力が保証されるのか」という問いかけは強まっている。
今回の改訂で掲げた「多様性と共通性のバランス」は、こうした「開いた学力の幅」に対処しようとした結果だといえる。
しかし、義務教育でもなく、学校によって授業の中身も生徒のタイプもまるで異なる高校の学習内容について、一つの指導要領で基準を示すのはもはや難しくなっているのではないか。
文科省内部では01年に「高等学校課」がなくなって以来、高校教育全般を専門的に担当する部署がない。省内でも「エアポケットになっている」という声は多い。社会構造が激変する中で、高校の位置づけをどう示すのか。しっかり議論して方向をさぐるときに来ている。(上野創)
|
|
|
|
|
|
|
|
理想教師への道! 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-