二見の夫婦岩から東の先にある神前海岸にはゴロゴロ岩が並んでいる。
その先に神前岬があり、大潮の干潮時にしか訪れることのできない潜島と呼ばれる海食洞門がある。
ここに冬至と夏至の太陽が通ると云われ、サルタヒコの上陸地点だったとか、池の浦にある粟皇子神社の遥拝所だったとも…
ここは神前海岸から岬に向かって岩場づたいに歩いてしか行けない場所で、普段は荒波で断崖絶壁の海でも、潮がひいたときだけ現れる海の道によってその洞門を潜ることができる。
この海岸では贄海(にえうみ)神事と呼ばれる、天照大神に奉る神饌を採る神事が行われていた。
神前岬の浜で旧暦6月15日に行っていた贄海神事のうち、道普請として潜島の洞門前の注連縄張りを行っていたが、今でも旧暦6月1日(7月大潮の頃)に近い日曜日に注連縄の張替神事がある。
伊勢の二見から昇った夏至の太陽は福岡の玄海灘に向かい、筑前二見ケ浦の夫婦岩へ沈む。
島根の東出雲には、佐太大神(サルタヒコ)の誕生地といわれる加賀の潜戸という洞門がある。
太平洋側と日本海側で、どちらも二見と対となるようにつながっている。
加賀の潜戸は(かがのくけど)の「くげど」とは洞窟の意味。
この洞窟の中には石が積まれ、死んだ子供の魂を弔う賽の河原となってる場所もあるそうです。
なので、加賀白山のククリヒメ信仰はここから来たのかもしれない。
この加賀(かか)も、海人族の太陽信仰からきている。
『出雲国風土記』によると、暗い岩屋で佐太大神が生まれる時、母神の支佐加姫が黄金の弓で矢を射たところ洞窟が光り輝いたとあり、「光加加やけり」の加加が加賀となったと云われてます。
『日本書紀』はサルタヒコの容姿について「鼻長は七咫、背長は七尺、目が八咫鏡のように、またホオズキのように照り輝いている」と記している。
岬は「ハナ」ともいい、 鼻長と背長はリアス式海岸にある断崖絶壁の岬の地形を表現しているのかもしれない。
その岬にある穴の開いた洞門に、朝日や夕陽の真っ赤な太陽が射し込めば、八咫鏡のように、ホオズキのように、ひかりカカやけり…
その先に神前岬があり、大潮の干潮時にしか訪れることのできない潜島と呼ばれる海食洞門がある。
ここに冬至と夏至の太陽が通ると云われ、サルタヒコの上陸地点だったとか、池の浦にある粟皇子神社の遥拝所だったとも…
ここは神前海岸から岬に向かって岩場づたいに歩いてしか行けない場所で、普段は荒波で断崖絶壁の海でも、潮がひいたときだけ現れる海の道によってその洞門を潜ることができる。
この海岸では贄海(にえうみ)神事と呼ばれる、天照大神に奉る神饌を採る神事が行われていた。
神前岬の浜で旧暦6月15日に行っていた贄海神事のうち、道普請として潜島の洞門前の注連縄張りを行っていたが、今でも旧暦6月1日(7月大潮の頃)に近い日曜日に注連縄の張替神事がある。
伊勢の二見から昇った夏至の太陽は福岡の玄海灘に向かい、筑前二見ケ浦の夫婦岩へ沈む。
島根の東出雲には、佐太大神(サルタヒコ)の誕生地といわれる加賀の潜戸という洞門がある。
太平洋側と日本海側で、どちらも二見と対となるようにつながっている。
加賀の潜戸は(かがのくけど)の「くげど」とは洞窟の意味。
この洞窟の中には石が積まれ、死んだ子供の魂を弔う賽の河原となってる場所もあるそうです。
なので、加賀白山のククリヒメ信仰はここから来たのかもしれない。
この加賀(かか)も、海人族の太陽信仰からきている。
『出雲国風土記』によると、暗い岩屋で佐太大神が生まれる時、母神の支佐加姫が黄金の弓で矢を射たところ洞窟が光り輝いたとあり、「光加加やけり」の加加が加賀となったと云われてます。
『日本書紀』はサルタヒコの容姿について「鼻長は七咫、背長は七尺、目が八咫鏡のように、またホオズキのように照り輝いている」と記している。
岬は「ハナ」ともいい、 鼻長と背長はリアス式海岸にある断崖絶壁の岬の地形を表現しているのかもしれない。
その岬にある穴の開いた洞門に、朝日や夕陽の真っ赤な太陽が射し込めば、八咫鏡のように、ホオズキのように、ひかりカカやけり…
|
|
|
|
コメント(5)
昨日訪れた二見の松下社は、素戔嗚尊が立ち寄った蘇民将来伝説の地。
他にも二見は、猿田彦大神降臨の霊地とか、倭姫の天照大神船寄りの聖跡とも云われている。
大潮の日の時間帯を選んで渡るということは、よっぽど計画的に日にちを合わせないと難しいため、潜島のことを知ってからもなかなか来れず、なんとか一度だけ訪れたことがある。
そのときもその当日がたまたま大潮で、潜島行きを急遽決行した。
今回は二度目。
前日、たまたま訪れた神前神社。
その山頂から夕陽が沈むとき、山の下の方からもキラキラ輝いていて不思議に思った。
後でわかったのけど、それがちょうど夫婦岩につながる神前海岸の沖合だった。
太陽はひとつのはずなのに、木漏れ日まじりの海に反射した太陽が幻想的な光の演出をしてくれていたのだった。
山を降り、岬への入口にある看板を見て、この海食洞門も含めみんなひとつにつながってることにやっと気づいた。
それまでバラバラな認識のまま点と点を辿りながら、岬を起点として隆起したひとつの大きな山が聖地であり、東の粟皇子神社も、南の蘇民の松下社も、北の神前神社もみんなつながっていることに気づいた。
しかも、文月三日の今日はぎりぎり大潮。
行くしかない!
他にも二見は、猿田彦大神降臨の霊地とか、倭姫の天照大神船寄りの聖跡とも云われている。
大潮の日の時間帯を選んで渡るということは、よっぽど計画的に日にちを合わせないと難しいため、潜島のことを知ってからもなかなか来れず、なんとか一度だけ訪れたことがある。
そのときもその当日がたまたま大潮で、潜島行きを急遽決行した。
今回は二度目。
前日、たまたま訪れた神前神社。
その山頂から夕陽が沈むとき、山の下の方からもキラキラ輝いていて不思議に思った。
後でわかったのけど、それがちょうど夫婦岩につながる神前海岸の沖合だった。
太陽はひとつのはずなのに、木漏れ日まじりの海に反射した太陽が幻想的な光の演出をしてくれていたのだった。
山を降り、岬への入口にある看板を見て、この海食洞門も含めみんなひとつにつながってることにやっと気づいた。
それまでバラバラな認識のまま点と点を辿りながら、岬を起点として隆起したひとつの大きな山が聖地であり、東の粟皇子神社も、南の蘇民の松下社も、北の神前神社もみんなつながっていることに気づいた。
しかも、文月三日の今日はぎりぎり大潮。
行くしかない!
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
謎のサルタヒコとおひらきまつり 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
謎のサルタヒコとおひらきまつりのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90063人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208311人
- 3位
- 酒好き
- 170692人
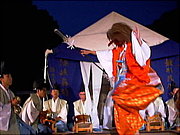


![縄文族ネットワーク [太陽の道]](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/10/98/1581098_84s.gif)




















