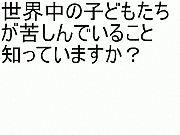クラスター爆弾という兵器を知っているでしょうか?
クラスター爆弾は、広範囲に渡って被害を及ぼし、無差別に市民を殺傷します。また、クラスターの不発弾によって多くの子ども達が被害にあっています。
最近では、イスラエルによってレバノンで大量のクラスター爆弾が使用され、被害者が出ていることが報告されています。
現在、70を超える国がクラスター爆弾を保有し、30を超える国が生産をしています。日本もクラスターの生産国であり、また保有国です。
そう、日本においても関係ないことではないんです。
僕自身、クラスター爆弾に含まれる劣化ウラン弾の放射能の影響で生まれたとされる、無脳症の子どもの写真を見て、国際協力に興味を持ちました。
それが今、廃絶にむけて動き出していることにとても興奮しています。しかし、日本が不支持というのは残念です。
ぜひぜひ、みなさんの力を貸してください。
ネット署名は↓
http://
森住卓さんのHPはとても衝撃を受けます
http://
クラスター爆弾は、広範囲に渡って被害を及ぼし、無差別に市民を殺傷します。また、クラスターの不発弾によって多くの子ども達が被害にあっています。
最近では、イスラエルによってレバノンで大量のクラスター爆弾が使用され、被害者が出ていることが報告されています。
現在、70を超える国がクラスター爆弾を保有し、30を超える国が生産をしています。日本もクラスターの生産国であり、また保有国です。
そう、日本においても関係ないことではないんです。
僕自身、クラスター爆弾に含まれる劣化ウラン弾の放射能の影響で生まれたとされる、無脳症の子どもの写真を見て、国際協力に興味を持ちました。
それが今、廃絶にむけて動き出していることにとても興奮しています。しかし、日本が不支持というのは残念です。
ぜひぜひ、みなさんの力を貸してください。
ネット署名は↓
http://
森住卓さんのHPはとても衝撃を受けます
http://
|
|
|
|
コメント(10)
■クラスター爆弾 リビアの使用を非難■
クラスター爆弾禁止条約(オスロ条約)の第2回締約国会議が、最大の被害国の一つレバノンで開幕した。
最終日にも採択する「ベイルート宣言」草案によると、加盟国はリビアのカダフィ政権の反体制派弾圧や、タイ・カンボジアの軍事衝突を念頭に「クラスター爆弾の最近の使用を非難」し、保有や開発を含めてクラスター爆弾を断念し、条約に加わるよう求めている。
宣言はまた、中東地域に加盟国が少ない点を指摘、即座の署名・批准を求めた。「すべての国への(条約)適用を促す」との文言で、クラスター爆弾の大量保有・使用国であるイスラエルにも条約加盟を要求している。
カダフィ政権は反体制派と攻防戦を続けた北中部ミスラタで、クラスター爆弾を使用したことが国際人権団体の調査で明らかになっている。
ミスラタではクラスター爆弾によるとみられる負傷者も出た。
また、タイとカンボジアが国境の山岳寺院を巡る軍事衝突で「クラスター爆弾を使用した」と互いを非難した。
なお、リビア、タイ、カンボジアは条約には未加盟である。
参照
毎日新聞 2011年9月13日
http://mainichi.jp/select/world/archive/news/2011/09/13/20110913dde007030051000c.html
『クラスター爆弾なんてもういらない。』
清水俊弘
2008年 合同出版
クラスター爆弾禁止条約(オスロ条約)の第2回締約国会議が、最大の被害国の一つレバノンで開幕した。
最終日にも採択する「ベイルート宣言」草案によると、加盟国はリビアのカダフィ政権の反体制派弾圧や、タイ・カンボジアの軍事衝突を念頭に「クラスター爆弾の最近の使用を非難」し、保有や開発を含めてクラスター爆弾を断念し、条約に加わるよう求めている。
宣言はまた、中東地域に加盟国が少ない点を指摘、即座の署名・批准を求めた。「すべての国への(条約)適用を促す」との文言で、クラスター爆弾の大量保有・使用国であるイスラエルにも条約加盟を要求している。
カダフィ政権は反体制派と攻防戦を続けた北中部ミスラタで、クラスター爆弾を使用したことが国際人権団体の調査で明らかになっている。
ミスラタではクラスター爆弾によるとみられる負傷者も出た。
また、タイとカンボジアが国境の山岳寺院を巡る軍事衝突で「クラスター爆弾を使用した」と互いを非難した。
なお、リビア、タイ、カンボジアは条約には未加盟である。
参照
毎日新聞 2011年9月13日
http://mainichi.jp/select/world/archive/news/2011/09/13/20110913dde007030051000c.html
『クラスター爆弾なんてもういらない。』
清水俊弘
2008年 合同出版
■クラスター爆弾 16カ国が廃棄・作業着手■
不発弾による市民の被害が絶えないクラスター爆弾の禁止条約(2008年12月署名、110カ国加盟)に加盟する同爆弾の保有国36カ国のうち、約4割にあたる16カ国がその廃棄を完了、もしくは作業に着手したことがわかった。
レバノンで開かれている条約締約国会議で明らかにされた。
8年以内の廃棄を定めた条約内容の実現状況が明らかにされたのは初めて。
日本はまだ廃棄計画を進行中という。
会議で示された「条約実施報告書」は、2010年の議長国ラオスが中心となり、2011年8月末時点の条約事項の実施状況や問題点をまとめた。
これまでにオーストリア、ベルギー、ポルトガル、スペインなど9カ国が廃棄作業を完了した。
ハンガリーは条約の批准は終えていないが、自主的に廃棄作業を終えた。
同爆弾を保有する36カ国の子爆弾の総数は1億4600万発で、このうち6444万8458発が廃棄された計算になる。
また、ドイツ、イギリス、フランス、ボスニア・ヘルツェゴビナなど7カ国も廃棄作業に着手している。
日本は、「(廃棄業者の)入札作業を開始」したばかりで、廃棄完了にはさらに時間がかかる見通し。
この他、クロアチアなど3カ国が廃棄計画を進めている。
一方、条約に定められた被害者支援を行う意向を表明したアンゴラなど15カ国の大半では支援作業が進められているが、報告書は「資金難が支援の拡充・維持の障害になっているようだ」と分析している。
参照
毎日新聞 2011年9月15日
http://mainichi.jp/select/world/news/20110916k0000m030101000c.html
『行動する市民が世界を変えた クラスター爆弾禁止運動とグローバルNGOパワー』
目加田説子
2009年 毎日新聞社
不発弾による市民の被害が絶えないクラスター爆弾の禁止条約(2008年12月署名、110カ国加盟)に加盟する同爆弾の保有国36カ国のうち、約4割にあたる16カ国がその廃棄を完了、もしくは作業に着手したことがわかった。
レバノンで開かれている条約締約国会議で明らかにされた。
8年以内の廃棄を定めた条約内容の実現状況が明らかにされたのは初めて。
日本はまだ廃棄計画を進行中という。
会議で示された「条約実施報告書」は、2010年の議長国ラオスが中心となり、2011年8月末時点の条約事項の実施状況や問題点をまとめた。
これまでにオーストリア、ベルギー、ポルトガル、スペインなど9カ国が廃棄作業を完了した。
ハンガリーは条約の批准は終えていないが、自主的に廃棄作業を終えた。
同爆弾を保有する36カ国の子爆弾の総数は1億4600万発で、このうち6444万8458発が廃棄された計算になる。
また、ドイツ、イギリス、フランス、ボスニア・ヘルツェゴビナなど7カ国も廃棄作業に着手している。
日本は、「(廃棄業者の)入札作業を開始」したばかりで、廃棄完了にはさらに時間がかかる見通し。
この他、クロアチアなど3カ国が廃棄計画を進めている。
一方、条約に定められた被害者支援を行う意向を表明したアンゴラなど15カ国の大半では支援作業が進められているが、報告書は「資金難が支援の拡充・維持の障害になっているようだ」と分析している。
参照
毎日新聞 2011年9月15日
http://mainichi.jp/select/world/news/20110916k0000m030101000c.html
『行動する市民が世界を変えた クラスター爆弾禁止運動とグローバルNGOパワー』
目加田説子
2009年 毎日新聞社
■クラスター爆弾や地雷 未撤去 アゼルバイジャン■
旧ソ連末期にアゼルバイジャン共和国(当時)とアルメニア系住民が衝突した「ナゴルノカラバフ紛争」で、大量のクラスター爆弾や地雷が使われた。
1994年の停戦から17年がたったが、残された兵器が住民を傷つける事故が後を絶たず、紛争の傷痕は消えていない。
アゼルバイジャンからの独立を宣言した「ナゴルノカラバフ共和国」の首都・ステパナケルト近郊の村落では、作業を始めてから2カ月で、クラスター爆弾の不発弾26発が発見されたという。
ナゴルノカラバフでは1988年、人口の8割を占めたアルメニア系住民がアゼルバイジャン当局と衝突し、隣国アルメニアが介入する大規模な紛争に発展した。
村で見つかったクラスター弾は、アゼルバイジャン軍が投下したものとみられる。
地雷撤去にあたる非政府組織(NGO)「ヘイロートラスト」によると、1994年の停戦合意後も「共和国」内でクラスター爆弾の不発弾や地雷による事故262件が発生し、340人が死傷している。
ナゴルノカラバフで2000年に撤去作業を始めたヘイロートラストは、地雷が敷設されたと推定される地域の89%、クラスター爆弾などが使われたと思われる地域の70%で撤去作業を終えたという。
しかし、ナゴルノカラバフ特有の事情が、撤去作業の継続を難しくしている一面もある。
たとえば、ヘイロートラストへ活動資金を提供している支援団体の中には、資金の使い道を「もともとのナゴルノカラバフ自治州領内の撤去作業に限定する」よう特定している組織があるという。
また、ヘイロートラストは現在、米国の慈善団体からの支援金を使って「占領地域」での撤去作業を実施しているが、この資金が2011年末で打ち切りとなる。
参照
毎日新聞 2011年11月10日
http://mainichi.jp/select/world/archive/news/2011/11/10/20111110ddm007030008000c.html
旧ソ連末期にアゼルバイジャン共和国(当時)とアルメニア系住民が衝突した「ナゴルノカラバフ紛争」で、大量のクラスター爆弾や地雷が使われた。
1994年の停戦から17年がたったが、残された兵器が住民を傷つける事故が後を絶たず、紛争の傷痕は消えていない。
アゼルバイジャンからの独立を宣言した「ナゴルノカラバフ共和国」の首都・ステパナケルト近郊の村落では、作業を始めてから2カ月で、クラスター爆弾の不発弾26発が発見されたという。
ナゴルノカラバフでは1988年、人口の8割を占めたアルメニア系住民がアゼルバイジャン当局と衝突し、隣国アルメニアが介入する大規模な紛争に発展した。
村で見つかったクラスター弾は、アゼルバイジャン軍が投下したものとみられる。
地雷撤去にあたる非政府組織(NGO)「ヘイロートラスト」によると、1994年の停戦合意後も「共和国」内でクラスター爆弾の不発弾や地雷による事故262件が発生し、340人が死傷している。
ナゴルノカラバフで2000年に撤去作業を始めたヘイロートラストは、地雷が敷設されたと推定される地域の89%、クラスター爆弾などが使われたと思われる地域の70%で撤去作業を終えたという。
しかし、ナゴルノカラバフ特有の事情が、撤去作業の継続を難しくしている一面もある。
たとえば、ヘイロートラストへ活動資金を提供している支援団体の中には、資金の使い道を「もともとのナゴルノカラバフ自治州領内の撤去作業に限定する」よう特定している組織があるという。
また、ヘイロートラストは現在、米国の慈善団体からの支援金を使って「占領地域」での撤去作業を実施しているが、この資金が2011年末で打ち切りとなる。
参照
毎日新聞 2011年11月10日
http://mainichi.jp/select/world/archive/news/2011/11/10/20111110ddm007030008000c.html
■クラスター爆弾禁止 「骨抜き」案 日本の立場は■
クラスター爆弾の全面禁止をうたう2008年締結のクラスター爆弾禁止条約(オスロ条約)を骨抜きにする新条約締結の動きが明らかになった。
新条約作りを主導するアメリカなどがクラスター爆弾の使用を続ける意思を明確に表示した「条約無効化工作」と言え、日本などオスロ条約批准国の中にも新条約案に理解を示す国が増えている。
しかし、規制を緩和する条約は、爆弾を大量保有する国が使用を正当化するだけでなく、他の国に圧力をかける手段として使われかねない。
オスロ条約加盟国のほとんどは、米露中など大量保有する国が参加しないオスロ条約は「実効性が不完全」だと考えてため、米露中も参加する軍縮会議「特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)締約国会議」での条約の議論は重要だとみなしている国が大半だ。
このため、新条約案に難色を示しているオスロ条約加盟国も、CCWで結論がまとまれば、正面から反対することは難しくなるとみられている。
アメリカが主導する現在の条約案には、「オスロ条約加盟国の権利や義務に影響しない」との付帯項目が記されているが、新条約に参加するオスロ条約加盟国は、いずれ爆弾を廃棄するのかどうかの決断を迫られるのは間違いない。
親米の立場を取る国でオスロ条約を批准していない国は、廃棄に取り組まない可能性が出てくる。
日本など批准済みの国は、アメリカの顔色をうかがいつつ、新型爆弾だけ保有する政治的決断をする可能性もある。
対人地雷については、部分的な禁止条約しか作れなかったのに失望した非政府組織やカナダなど有志国が、CCWとは別枠で全面禁止条約を提唱し、1997年に対人地雷禁止条約が締結された。
この条約には米露中は参加していないが、加盟国は158と国連加盟国の8割にあたり、この包囲網で保有国は事実上、地雷を使えなくなった。
このプロセスを踏襲したのがオスロ条約である。
対人地雷禁止条約が規制の緩い条約から全面禁止へと高まったのに対し、今回の規制の緩い条約案は全く逆を行く。
◆矛盾する条約も参加可能
相矛盾する複数の条約に参加する道を開いているのが、条約についての一般的ルールを定めた「条約法に関するウィーン条約」である。
日本など計111カ国が参加するこの条約は、ある条約について一部規定に留保することを認めており、留保を表明した国はその部分に関しては当該条約から拘束されない。
たとえば、日本は1978年に「国際人権規約」に署名した際、公務員のスト権や死刑の制限、高校・大学の無償化といった国内法と矛盾する条項を留保した。
また、ノルウェーなどは商業捕鯨の一時停止を決めた国際捕鯨委員会の規定を留保し、商業捕鯨を続けている。
クラスター爆弾についても、日本などオスロ条約加盟国が新条約に加盟した場合、留保を活用する可能性がある。
ただし、クラスター爆弾の全面禁止を定めたオスロ条約は「留保を付することはできない」と定めているため、留保し得るのは新条約だけである。
参照
毎日新聞 2011年11月21日
http://mainichi.jp/select/world/news/20111121k0000m030143000c.html
クラスター爆弾の全面禁止をうたう2008年締結のクラスター爆弾禁止条約(オスロ条約)を骨抜きにする新条約締結の動きが明らかになった。
新条約作りを主導するアメリカなどがクラスター爆弾の使用を続ける意思を明確に表示した「条約無効化工作」と言え、日本などオスロ条約批准国の中にも新条約案に理解を示す国が増えている。
しかし、規制を緩和する条約は、爆弾を大量保有する国が使用を正当化するだけでなく、他の国に圧力をかける手段として使われかねない。
オスロ条約加盟国のほとんどは、米露中など大量保有する国が参加しないオスロ条約は「実効性が不完全」だと考えてため、米露中も参加する軍縮会議「特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)締約国会議」での条約の議論は重要だとみなしている国が大半だ。
このため、新条約案に難色を示しているオスロ条約加盟国も、CCWで結論がまとまれば、正面から反対することは難しくなるとみられている。
アメリカが主導する現在の条約案には、「オスロ条約加盟国の権利や義務に影響しない」との付帯項目が記されているが、新条約に参加するオスロ条約加盟国は、いずれ爆弾を廃棄するのかどうかの決断を迫られるのは間違いない。
親米の立場を取る国でオスロ条約を批准していない国は、廃棄に取り組まない可能性が出てくる。
日本など批准済みの国は、アメリカの顔色をうかがいつつ、新型爆弾だけ保有する政治的決断をする可能性もある。
対人地雷については、部分的な禁止条約しか作れなかったのに失望した非政府組織やカナダなど有志国が、CCWとは別枠で全面禁止条約を提唱し、1997年に対人地雷禁止条約が締結された。
この条約には米露中は参加していないが、加盟国は158と国連加盟国の8割にあたり、この包囲網で保有国は事実上、地雷を使えなくなった。
このプロセスを踏襲したのがオスロ条約である。
対人地雷禁止条約が規制の緩い条約から全面禁止へと高まったのに対し、今回の規制の緩い条約案は全く逆を行く。
◆矛盾する条約も参加可能
相矛盾する複数の条約に参加する道を開いているのが、条約についての一般的ルールを定めた「条約法に関するウィーン条約」である。
日本など計111カ国が参加するこの条約は、ある条約について一部規定に留保することを認めており、留保を表明した国はその部分に関しては当該条約から拘束されない。
たとえば、日本は1978年に「国際人権規約」に署名した際、公務員のスト権や死刑の制限、高校・大学の無償化といった国内法と矛盾する条項を留保した。
また、ノルウェーなどは商業捕鯨の一時停止を決めた国際捕鯨委員会の規定を留保し、商業捕鯨を続けている。
クラスター爆弾についても、日本などオスロ条約加盟国が新条約に加盟した場合、留保を活用する可能性がある。
ただし、クラスター爆弾の全面禁止を定めたオスロ条約は「留保を付することはできない」と定めているため、留保し得るのは新条約だけである。
参照
毎日新聞 2011年11月21日
http://mainichi.jp/select/world/news/20111121k0000m030143000c.html
■世界の地雷被害 2010年は前年比5%増■
非政府組織(NGO)の連合体、地雷禁止国際キャンペーン(ICBL)は、2011年版の「地雷モニター報告」を発表し、地雷による2010年の被害者が世界全体で4191人に上り、前年より5%以上も増加したことが分かった。
2011年には、「アラブの春」と呼ばれる中東の民主化運動の活発化を背景に、リビアとシリアで新たな対人地雷の使用が確認された。
2011年に対人地雷の使用が確認されたのはほかにイスラエル、ミャンマーで、また、アフガニスタンなど4カ国で武装勢力によるとみられる使用が判明した。
参照
東京新聞 2011年11月23日
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2011112301001549.html
非政府組織(NGO)の連合体、地雷禁止国際キャンペーン(ICBL)は、2011年版の「地雷モニター報告」を発表し、地雷による2010年の被害者が世界全体で4191人に上り、前年より5%以上も増加したことが分かった。
2011年には、「アラブの春」と呼ばれる中東の民主化運動の活発化を背景に、リビアとシリアで新たな対人地雷の使用が確認された。
2011年に対人地雷の使用が確認されたのはほかにイスラエル、ミャンマーで、また、アフガニスタンなど4カ国で武装勢力によるとみられる使用が判明した。
参照
東京新聞 2011年11月23日
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2011112301001549.html
■クラスター爆弾 「骨抜き」案 廃案へ■
クラスター爆弾の全面禁止条約(オスロ条約)より規制の緩い条約案を審議していた軍縮会議「特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)締約国会議」は、ジュネーブの総会で条約案を採択できないまま閉幕した。
全会一致の支持が得られず、条約案は廃案となる。
オスロ条約を骨抜きにしようとする米露中(3カ国でクラスター爆弾の8〜9割を持つ)など大量保有国の外交工作が失敗したことで、オスロ条約支持派が勢いづきそうだ。
アメリカは、土壇場になって今回の条約案からクラスター爆弾の「使用」を巡る文言を削除する提案を行った。
「使用を合法化するわけではない」との論理で、爆弾の備蓄や移送だけを規制するよう条約案を変更し、支持拡大をはかった。
しかし、オスロ条約を支持する50の国は、反対の声明を発表し、議長は採択に必要な全会一致が得られないと判断して、採択を見送った。
採択が見送られた後、イスラエルやインドは「人道被害に対処する条約案が阻止された」とオスロ条約加盟国を非難。
クラスター爆弾使用には、「何の法的制限もない」と今後も使い続けると主張した。
アメリカなどが採択を目指した条約案の骨子は以下の3点である。
(1)1980年より前の爆弾は廃棄
(2)1980年以降の爆弾は最長12年の暫定保持を経て廃棄
(3)不発率の低い爆弾の使用を容認
2018年以降、不発率1%以下の新型爆弾を使うアメリカの方針と合致し、使用を合法化する狙いがあった。
オスロ条約加盟国は111で批准国は66で、当面の外交的支障がなくなったことで、加盟・批准国の増加に拍車がかかることが予想される。
一方、大量保有国側は今回の会議で不発弾による市民の死傷など人道被害への懸念を強く表明したことで、今後さらに、クラスター爆弾を使いづらくなりそうだ。
なお、日本は、最後まで骨抜き条約に反対を表明せず、オスロ条約に賛同するまで後手後手に回ったかつての失態をまた繰り返した。
参照
毎日新聞 2011年11月26日
http://mainichi.jp/select/world/archive/news/2011/11/26/20111126dde001030017000c.html
クラスター爆弾の全面禁止条約(オスロ条約)より規制の緩い条約案を審議していた軍縮会議「特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)締約国会議」は、ジュネーブの総会で条約案を採択できないまま閉幕した。
全会一致の支持が得られず、条約案は廃案となる。
オスロ条約を骨抜きにしようとする米露中(3カ国でクラスター爆弾の8〜9割を持つ)など大量保有国の外交工作が失敗したことで、オスロ条約支持派が勢いづきそうだ。
アメリカは、土壇場になって今回の条約案からクラスター爆弾の「使用」を巡る文言を削除する提案を行った。
「使用を合法化するわけではない」との論理で、爆弾の備蓄や移送だけを規制するよう条約案を変更し、支持拡大をはかった。
しかし、オスロ条約を支持する50の国は、反対の声明を発表し、議長は採択に必要な全会一致が得られないと判断して、採択を見送った。
採択が見送られた後、イスラエルやインドは「人道被害に対処する条約案が阻止された」とオスロ条約加盟国を非難。
クラスター爆弾使用には、「何の法的制限もない」と今後も使い続けると主張した。
アメリカなどが採択を目指した条約案の骨子は以下の3点である。
(1)1980年より前の爆弾は廃棄
(2)1980年以降の爆弾は最長12年の暫定保持を経て廃棄
(3)不発率の低い爆弾の使用を容認
2018年以降、不発率1%以下の新型爆弾を使うアメリカの方針と合致し、使用を合法化する狙いがあった。
オスロ条約加盟国は111で批准国は66で、当面の外交的支障がなくなったことで、加盟・批准国の増加に拍車がかかることが予想される。
一方、大量保有国側は今回の会議で不発弾による市民の死傷など人道被害への懸念を強く表明したことで、今後さらに、クラスター爆弾を使いづらくなりそうだ。
なお、日本は、最後まで骨抜き条約に反対を表明せず、オスロ条約に賛同するまで後手後手に回ったかつての失態をまた繰り返した。
参照
毎日新聞 2011年11月26日
http://mainichi.jp/select/world/archive/news/2011/11/26/20111126dde001030017000c.html
■スーダン軍が自国民にクラスター爆弾を使用か■
スーダンで民間人が暮らす村にクラスター爆弾が使用されたことを示すビデオをCNNが入手した。
映っているのはスーダン南部の村では、地面の大きな穴の中に、旧ソ連製のRBK−500というクラスター爆弾が不発のまま残っている。
周辺住民によれば、スーダン軍機による空爆はほぼ毎日、行われている。
クラスター爆弾には多数の小さな爆弾(子弾)が入っており、投下されるとそれが非常に広い範囲にばらまかれる。
問題は、危険が投下後も続くことだ。
専門家によれば、最近作られたクラスター爆弾の場合でも、子弾の約10%は不発弾となる。
RBK−500のような旧型ではその割合はずっと高くなる可能性があり、投下された場所一帯が地雷原と化すことになる。
「好奇心の強い子供が空爆後に家の外に出て、見たこともない面白いものがあると思って手や頭を吹き飛ばされた例は数多い」と、地雷や不発弾などの問題に取り組む団体「デンマーク地雷除去グループ」の関係者は言う。
南コルドファン州では、独立した南スーダンへの併合を求める反政府武装勢力と国軍との戦いが続いている。
武装勢力は食糧を地元の村々から得ているため、スーダン軍は空爆によって住民を村から追い出そうとしている可能性がある。
スーダン軍の広報官は、「わが軍は南コルドファンでクラスター爆弾を使っていない」と否定。
なお、スーダン政府はクラスター爆弾を禁止する条約(オスロ条約)に署名していない。
参照
CNN 2012年6月1日
http://www.cnn.co.jp/world/30006806.html
スーダンで民間人が暮らす村にクラスター爆弾が使用されたことを示すビデオをCNNが入手した。
映っているのはスーダン南部の村では、地面の大きな穴の中に、旧ソ連製のRBK−500というクラスター爆弾が不発のまま残っている。
周辺住民によれば、スーダン軍機による空爆はほぼ毎日、行われている。
クラスター爆弾には多数の小さな爆弾(子弾)が入っており、投下されるとそれが非常に広い範囲にばらまかれる。
問題は、危険が投下後も続くことだ。
専門家によれば、最近作られたクラスター爆弾の場合でも、子弾の約10%は不発弾となる。
RBK−500のような旧型ではその割合はずっと高くなる可能性があり、投下された場所一帯が地雷原と化すことになる。
「好奇心の強い子供が空爆後に家の外に出て、見たこともない面白いものがあると思って手や頭を吹き飛ばされた例は数多い」と、地雷や不発弾などの問題に取り組む団体「デンマーク地雷除去グループ」の関係者は言う。
南コルドファン州では、独立した南スーダンへの併合を求める反政府武装勢力と国軍との戦いが続いている。
武装勢力は食糧を地元の村々から得ているため、スーダン軍は空爆によって住民を村から追い出そうとしている可能性がある。
スーダン軍の広報官は、「わが軍は南コルドファンでクラスター爆弾を使っていない」と否定。
なお、スーダン政府はクラスター爆弾を禁止する条約(オスロ条約)に署名していない。
参照
CNN 2012年6月1日
http://www.cnn.co.jp/world/30006806.html
■クラスター爆弾 廃棄3年半前倒し 日本■
日本政府が保有するクラスター爆弾を期限より3年半早く、独仏に先駆け、2015年初めに前倒し廃棄することがわかった。
2013年からノルウェーとドイツに保有弾を移して破壊処理する。
クラスター爆弾禁止条約の批准国で8年以内の廃棄義務を負う国は19あり、技術や資金面で廃棄作業が滞る国もある。
日本の前倒し方針は、完全廃棄に向けた国際世論を加速しそうだ。
防衛・外務両省などによると、日本のクラスター爆弾は4種類で子爆弾にして約202万発ある。
ごく一部は2011年、北海道で処理したが、大部分の廃棄はノルウェーの会社と契約する。
2013年に完了する英、2014年のイタリアには後れを取るが、2015年末に完了する独や廃棄期限を示していない仏に先駆けた廃棄となる。
クラスター爆弾連合によると、オーストリアなど15カ国が既に廃棄を完了。
日本を含めた19カ国が廃棄に取り組む。
ギニアビサウなどアフリカ諸国やクロアチアは資金や技術面で困難を抱えており2018〜2020年までの廃棄期限を守れるよう国際協力も始まっている。
署名国ではカナダなど6カ国が保有し、批准後に廃棄義務を負う。
さらに、条約非加盟国では米露中はじめ48カ国がクラスター爆弾を保有しており、日本の積極姿勢はこうした国への外交的アピールになりそうだ。
参照
毎日新聞 2012年10月9日
http://mainichi.jp/select/news/20121009k0000m030089000c.html
日本政府が保有するクラスター爆弾を期限より3年半早く、独仏に先駆け、2015年初めに前倒し廃棄することがわかった。
2013年からノルウェーとドイツに保有弾を移して破壊処理する。
クラスター爆弾禁止条約の批准国で8年以内の廃棄義務を負う国は19あり、技術や資金面で廃棄作業が滞る国もある。
日本の前倒し方針は、完全廃棄に向けた国際世論を加速しそうだ。
防衛・外務両省などによると、日本のクラスター爆弾は4種類で子爆弾にして約202万発ある。
ごく一部は2011年、北海道で処理したが、大部分の廃棄はノルウェーの会社と契約する。
2013年に完了する英、2014年のイタリアには後れを取るが、2015年末に完了する独や廃棄期限を示していない仏に先駆けた廃棄となる。
クラスター爆弾連合によると、オーストリアなど15カ国が既に廃棄を完了。
日本を含めた19カ国が廃棄に取り組む。
ギニアビサウなどアフリカ諸国やクロアチアは資金や技術面で困難を抱えており2018〜2020年までの廃棄期限を守れるよう国際協力も始まっている。
署名国ではカナダなど6カ国が保有し、批准後に廃棄義務を負う。
さらに、条約非加盟国では米露中はじめ48カ国がクラスター爆弾を保有しており、日本の積極姿勢はこうした国への外交的アピールになりそうだ。
参照
毎日新聞 2012年10月9日
http://mainichi.jp/select/news/20121009k0000m030089000c.html
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
SaveChildrenCommunity 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
SaveChildrenCommunityのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37860人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90059人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208307人