枝野 幸男 衆議院議員(弁護士、
民主党・前政調会長、現・憲法調査会長)
の月1回開催されるオープンミーティングの
内容(動画)がご覧いただけます。
こちら(↓)からアクセスどうぞ。
http://
民主党随一の論客の動画で
大変内容が濃い素晴らしいコンテンツ満載♪
じっくり学べば、確実に政治力が高まりますので
お奨めです。
談合と天下り、特別会計と天下りの
テーマの他、興味深いコンテンツあり。
どうぞごゆっくりご覧ください。
枝野議員に謝意♪
民主党・前政調会長、現・憲法調査会長)
の月1回開催されるオープンミーティングの
内容(動画)がご覧いただけます。
こちら(↓)からアクセスどうぞ。
http://
民主党随一の論客の動画で
大変内容が濃い素晴らしいコンテンツ満載♪
じっくり学べば、確実に政治力が高まりますので
お奨めです。
談合と天下り、特別会計と天下りの
テーマの他、興味深いコンテンツあり。
どうぞごゆっくりご覧ください。
枝野議員に謝意♪
|
|
|
|
コメント(2)
枝野幸男 「オープンミーティング」
テーマ:談合はなぜなくならないのか?
2006.12.15(金)
防衛施設庁の官製談合に引き続き、宮崎県知事の辞職、福島県知事・和歌山県知事の逮捕と、公共事業の発注をめぐる談合事件が次々と明るみになってきています。
談合は、税金の明らかなムダづかいを生んでおり、国と地方の借金は増え続けるばかりです。この談合に対処すべく、民主党も「官製談合防止法案」を国会に提出しました。
そこで、今月は、談合の仕組みや対処案についてお話をさせていただきます。ぜひ、お誘いあわせの上、ご参加いただければ幸いです。
http://www.edano.gr.jp/om/0612om.html
テーマ:談合はなぜなくならないのか?
2006.12.15(金)
防衛施設庁の官製談合に引き続き、宮崎県知事の辞職、福島県知事・和歌山県知事の逮捕と、公共事業の発注をめぐる談合事件が次々と明るみになってきています。
談合は、税金の明らかなムダづかいを生んでおり、国と地方の借金は増え続けるばかりです。この談合に対処すべく、民主党も「官製談合防止法案」を国会に提出しました。
そこで、今月は、談合の仕組みや対処案についてお話をさせていただきます。ぜひ、お誘いあわせの上、ご参加いただければ幸いです。
http://www.edano.gr.jp/om/0612om.html
枝野幸男
オープンミーティング:「特殊法人とは何か 」
2001.09.08(土)
http://www.edano.gr.jp/om/0109om.html
特殊法人の廃止・民営化は、常に行政改革の中心テーマになります。それは特殊法人には税金の無駄遣いの典型的な例が見受けられるからです。しかしただ廃止・民営化をすればいいというものではなく、そこには様々な問題があります。
そこで本日は、特殊法人の抱える問題、そして根本的な問題として官僚の天下りの話をさせていただきたいと思います。
特殊法人とは
そもそも特殊法人とは何なのでしょうか。大雑把に言わせていただけば、行政の仕事と民間の仕事の間にあるものと捉えていいと思います。例えば警察や裁判所といった、役所でなければできない仕事というのがあります。また、民間の営利企業がやった方が良い仕事もあります。それ以外で、その2つの真ん中にある、役所がやった方がいいが、独立採算などで分離させ民間に近い形(「公社形態」といいます)を取った方がいいものがあります。その典型的なものが、特殊法人です。
例えば、もうすぐ完全民営化されますが、JRは特殊法人です。鉄道事業というのは、発展途上国など民間でする力のない国では、国の力を使ってやるしかありません。また、外務省の管轄で国際協力銀行というのがありますが、民間ではなかなかお金を貸さないところに国が貸そうという発想で生まれたものです。これらには、出資金や補助金という形で税金が使われています。特殊法人という形である以上、これは当たり前のことと言えます。民間でやって資金調達できるなら国でやる必要がないからです。
民間の力が弱かったり、国全体の社会資本整備が遅れていた時代には、このやり方は有効性があったと思います。しかし、今では問題点の方が多くなってしまっています。
問題点? ―必要のない組織が残る
特殊法人の問題点の一つとして、いったん組織を作ると、時代が変わり役割が無くなっても、守り維持し続けてしまうということがあります。その結果、無駄な公共事業などが行なわれることになります。
例えば本州四国連絡橋公団は、今まで3本の橋を作り、そのために最先端の技術が使われました。公団には優秀な技術者がたくさんいます。ですから工事が終了して仕事が減ると、人が余る状況になります。そこで人や技術を活用するために新しい計画を建てる、という本末転倒が起こるのです。その結果、必要のない橋ができることになります。
もう一つの例として、住宅金融公庫があります。これは住宅ローン専用の公庫です。かつては、銀行は個人の長期ローンなど基本的に組んではくれませんでした。しかし今や銀行にとって住宅ローンは企業よりずっと安全な貸し出し先です。公庫の必要性は無くなってきています。こうして、やらなくてもいい仕事が残っていってしまうのです。
また、潰れる心配がないため採算を度外視してしまいがちです。国鉄がJRになった後、工事の下請け費用などが3〜4割節約できたといいます。こうした無駄は日常的に行なわれていると見ていいでしょう。
▼ 廃止・民営化へのプロセス
しかし、ただ廃止や民営化すればいいという問題ではありません。そこには充分なプロセスが必要です。例えば住宅金融公庫などは、銀行に比べて利息が低いのですが、いきなり民営化して銀行と競争させれば金利が上がってしまいます。これは住宅を新築しようという人の腰を引かせる結果になり、景気の足をひっぱることになります。その対策として、住宅ローンを組んだ人を対象に補助金や減税などの制度をつくる必要があります。
また、大赤字を抱え、どうやっても採算の取れない特殊法人をどうするかという問題があります。例えば道路公団などは、もはや通行料では返せるはずのないほどの借金を抱えています。民営化しても潰れるだけです。採算の取れている公団とセットにしてまとめて民営化するか、JRのように借金を国が引き取って民営化するか(しかしこれは税金で返す結果になります)、などの方法を考えなくてはいけません。
また、完全に政府の仕事にしてしまう、という手段もあります。通行料を財源にして道路をつくるというのは、国にお金がない中で大量の道路をつくらなければいけなかった時期には有効な手段だったと思いますが、基本的な整備が済んだ今は、事業を縮小させて政府の直轄にしてもいいのではないかと思います。
これら一つ一つに細かい知恵を出して詰めていくには、ものすごい労力が必要になります。一つの特殊法人につき20〜30人程度のチームを組まなくてはできません。
これには霞ヶ関の官僚の力を借りなければできません。しかし、それには大きな問題があります。先日、石原伸晃行政改革担当大臣が各省庁に、廃止・民営化をする特殊法人のリスト提出を求めましたが、ほぼゼロ回答でした。官僚自身では改革できない理由があるのです。それが、天下りです。特殊法人が無くなるということは、官僚にとって退職後の行き先が無くなるということです。だから改革に抵抗するのです。
問題点? ―天下りと利権構造
天下りがなくならない限り、いくら特殊法人の数を減らしても意味が無いのです。官僚はあの手この手を使って天下り先を作ります。実はここ何年かで、特殊法人の数は減っています。その代わりに、社団法人や財団法人といった、公益法人への天下りが増えているのです。民間の力を借りるといってつくり、補助金を出したり権限を与えたりして、天下り先を増やしています。
例えば、車が道路上で故障したり鍵を失くしたときに救助に駆けつける、JAFという組織がありますが、これは公益法人です。自社さ政権の時に規制緩和をするまで、この業務は独占されていました。その代わりに役所からの天下りを受け入れていたのです。新しく公益法人ができる度、この問題が起きます。私が所属する法務委員会でも、法律扶助協会という、起訴前の容疑者にも無料で弁護士が相談に応じられるようにするための公益法人をつくるとき、法務官僚の天下り先になるのではないかと散々追及しました。
天下りをする官僚達の中には、2〜3年で特殊法人を転々とし、その度に何千万円という多額の退職金をもらっている、通称「渡り鳥」と呼ばれる人達がいます。国からの権限が欲しい公益法人との間で、利権構造ができ上がっているのです。
▼ 天下りの禁止
天下りを禁止すれば、役所が特殊法人を守る意味はなくなります。これをしなければ、根本的な解決にはなりません。現行の法律でも天下りは禁止されていますが、あくまで「民間の営利企業への」しかも「属していた部署に権限・影響力のある部門」のみ「退職してから5年以内」禁止なのです。これではあまり意味がありません。例えば、国土交通省で鉄道畑にいた人が航空会社に行き、航空畑にいた人が鉄道会社に行くのは許されているのです。また退職から5年経てばどこにでも行けるです。もっと厳しくしなくてはいけません。所属していた役所に権限の上で関わりのある場合は、公的機関、民間企業を問わず禁止するようにします。
また、天下りを促進するような、役所の人事慣行も変えます。現在、同期が高いポストに就き出世コースからあぶれた人から順に辞め、天下るという慣習ができています。早い人は40歳過ぎ位で辞めてしまいます。一方で、天下りがほとんどない役所というのがあります。外務省と検察庁です。この2つは、世界各国と、日本国中にポストがあるからです。しかし、例えば財務省は、各地に税務署があっても、30歳過ぎ位のキャリア官僚を署長として赴任させてしまうのです。こんなことをしないで、50歳位の、本省では局長クラスの職に就かなかった人が赴任するようにすれば、定年前に辞めないでいいようになります。また、採用を省庁別ではなく一括にし、省庁の人事を流動化させます。一つの省庁で勤めあげるのではなく、様々な役所に移動するような人事システムにして省庁への帰属意識をなくさせます。天下りをやめ、役所が改革に協力できるシステムを作るのです。
一部の例外はあります。それは民間人がある一定期間に政治任用によって役所の仕事に就いた場合です。行政改革の一環として、局長クラスは政治任用によって決めるべきだと思っていますが、その後もと居た企業などに戻る場合は、天下りにはならないようにします。あくまで、国家公務員試験を通って、長年務めてきた官僚を対象とします。
改革は一気に行なう
必要がなかったり無駄が多い特殊法人の廃止・民営化といった個別の改革とともに、天下りという根本的な問題の解決は、同時にやらなければ意味がありません。小泉首相や石原大臣は個別の改革をやろうとしていますが、それでは, 中途半端な改革に終わってしまうでしょう。しかしこの問題をこのまま放っておけば、民間を圧迫し景気の足を引っ張る、借金が増え続け多額の税金を投入せざるをえなくなる、などの問題が悪化するだけです。また何より、これだけ民間企業が厳しい中、公的機関だけが守られるという状況に対する不公平感が広がります。
小泉首相や石原大臣に意欲はあると思いますが、自民党政権で利権を断ち切る天下りの全面禁止を行なうのは不可能と言っていいでしょう。抜本的改革を現政権に求めては行きますが、やはり政権交代によってしか、改革は成し得ないと思っています。
http://www.edano.gr.jp/om/0109om.html
オープンミーティング:「特殊法人とは何か 」
2001.09.08(土)
http://www.edano.gr.jp/om/0109om.html
特殊法人の廃止・民営化は、常に行政改革の中心テーマになります。それは特殊法人には税金の無駄遣いの典型的な例が見受けられるからです。しかしただ廃止・民営化をすればいいというものではなく、そこには様々な問題があります。
そこで本日は、特殊法人の抱える問題、そして根本的な問題として官僚の天下りの話をさせていただきたいと思います。
特殊法人とは
そもそも特殊法人とは何なのでしょうか。大雑把に言わせていただけば、行政の仕事と民間の仕事の間にあるものと捉えていいと思います。例えば警察や裁判所といった、役所でなければできない仕事というのがあります。また、民間の営利企業がやった方が良い仕事もあります。それ以外で、その2つの真ん中にある、役所がやった方がいいが、独立採算などで分離させ民間に近い形(「公社形態」といいます)を取った方がいいものがあります。その典型的なものが、特殊法人です。
例えば、もうすぐ完全民営化されますが、JRは特殊法人です。鉄道事業というのは、発展途上国など民間でする力のない国では、国の力を使ってやるしかありません。また、外務省の管轄で国際協力銀行というのがありますが、民間ではなかなかお金を貸さないところに国が貸そうという発想で生まれたものです。これらには、出資金や補助金という形で税金が使われています。特殊法人という形である以上、これは当たり前のことと言えます。民間でやって資金調達できるなら国でやる必要がないからです。
民間の力が弱かったり、国全体の社会資本整備が遅れていた時代には、このやり方は有効性があったと思います。しかし、今では問題点の方が多くなってしまっています。
問題点? ―必要のない組織が残る
特殊法人の問題点の一つとして、いったん組織を作ると、時代が変わり役割が無くなっても、守り維持し続けてしまうということがあります。その結果、無駄な公共事業などが行なわれることになります。
例えば本州四国連絡橋公団は、今まで3本の橋を作り、そのために最先端の技術が使われました。公団には優秀な技術者がたくさんいます。ですから工事が終了して仕事が減ると、人が余る状況になります。そこで人や技術を活用するために新しい計画を建てる、という本末転倒が起こるのです。その結果、必要のない橋ができることになります。
もう一つの例として、住宅金融公庫があります。これは住宅ローン専用の公庫です。かつては、銀行は個人の長期ローンなど基本的に組んではくれませんでした。しかし今や銀行にとって住宅ローンは企業よりずっと安全な貸し出し先です。公庫の必要性は無くなってきています。こうして、やらなくてもいい仕事が残っていってしまうのです。
また、潰れる心配がないため採算を度外視してしまいがちです。国鉄がJRになった後、工事の下請け費用などが3〜4割節約できたといいます。こうした無駄は日常的に行なわれていると見ていいでしょう。
▼ 廃止・民営化へのプロセス
しかし、ただ廃止や民営化すればいいという問題ではありません。そこには充分なプロセスが必要です。例えば住宅金融公庫などは、銀行に比べて利息が低いのですが、いきなり民営化して銀行と競争させれば金利が上がってしまいます。これは住宅を新築しようという人の腰を引かせる結果になり、景気の足をひっぱることになります。その対策として、住宅ローンを組んだ人を対象に補助金や減税などの制度をつくる必要があります。
また、大赤字を抱え、どうやっても採算の取れない特殊法人をどうするかという問題があります。例えば道路公団などは、もはや通行料では返せるはずのないほどの借金を抱えています。民営化しても潰れるだけです。採算の取れている公団とセットにしてまとめて民営化するか、JRのように借金を国が引き取って民営化するか(しかしこれは税金で返す結果になります)、などの方法を考えなくてはいけません。
また、完全に政府の仕事にしてしまう、という手段もあります。通行料を財源にして道路をつくるというのは、国にお金がない中で大量の道路をつくらなければいけなかった時期には有効な手段だったと思いますが、基本的な整備が済んだ今は、事業を縮小させて政府の直轄にしてもいいのではないかと思います。
これら一つ一つに細かい知恵を出して詰めていくには、ものすごい労力が必要になります。一つの特殊法人につき20〜30人程度のチームを組まなくてはできません。
これには霞ヶ関の官僚の力を借りなければできません。しかし、それには大きな問題があります。先日、石原伸晃行政改革担当大臣が各省庁に、廃止・民営化をする特殊法人のリスト提出を求めましたが、ほぼゼロ回答でした。官僚自身では改革できない理由があるのです。それが、天下りです。特殊法人が無くなるということは、官僚にとって退職後の行き先が無くなるということです。だから改革に抵抗するのです。
問題点? ―天下りと利権構造
天下りがなくならない限り、いくら特殊法人の数を減らしても意味が無いのです。官僚はあの手この手を使って天下り先を作ります。実はここ何年かで、特殊法人の数は減っています。その代わりに、社団法人や財団法人といった、公益法人への天下りが増えているのです。民間の力を借りるといってつくり、補助金を出したり権限を与えたりして、天下り先を増やしています。
例えば、車が道路上で故障したり鍵を失くしたときに救助に駆けつける、JAFという組織がありますが、これは公益法人です。自社さ政権の時に規制緩和をするまで、この業務は独占されていました。その代わりに役所からの天下りを受け入れていたのです。新しく公益法人ができる度、この問題が起きます。私が所属する法務委員会でも、法律扶助協会という、起訴前の容疑者にも無料で弁護士が相談に応じられるようにするための公益法人をつくるとき、法務官僚の天下り先になるのではないかと散々追及しました。
天下りをする官僚達の中には、2〜3年で特殊法人を転々とし、その度に何千万円という多額の退職金をもらっている、通称「渡り鳥」と呼ばれる人達がいます。国からの権限が欲しい公益法人との間で、利権構造ができ上がっているのです。
▼ 天下りの禁止
天下りを禁止すれば、役所が特殊法人を守る意味はなくなります。これをしなければ、根本的な解決にはなりません。現行の法律でも天下りは禁止されていますが、あくまで「民間の営利企業への」しかも「属していた部署に権限・影響力のある部門」のみ「退職してから5年以内」禁止なのです。これではあまり意味がありません。例えば、国土交通省で鉄道畑にいた人が航空会社に行き、航空畑にいた人が鉄道会社に行くのは許されているのです。また退職から5年経てばどこにでも行けるです。もっと厳しくしなくてはいけません。所属していた役所に権限の上で関わりのある場合は、公的機関、民間企業を問わず禁止するようにします。
また、天下りを促進するような、役所の人事慣行も変えます。現在、同期が高いポストに就き出世コースからあぶれた人から順に辞め、天下るという慣習ができています。早い人は40歳過ぎ位で辞めてしまいます。一方で、天下りがほとんどない役所というのがあります。外務省と検察庁です。この2つは、世界各国と、日本国中にポストがあるからです。しかし、例えば財務省は、各地に税務署があっても、30歳過ぎ位のキャリア官僚を署長として赴任させてしまうのです。こんなことをしないで、50歳位の、本省では局長クラスの職に就かなかった人が赴任するようにすれば、定年前に辞めないでいいようになります。また、採用を省庁別ではなく一括にし、省庁の人事を流動化させます。一つの省庁で勤めあげるのではなく、様々な役所に移動するような人事システムにして省庁への帰属意識をなくさせます。天下りをやめ、役所が改革に協力できるシステムを作るのです。
一部の例外はあります。それは民間人がある一定期間に政治任用によって役所の仕事に就いた場合です。行政改革の一環として、局長クラスは政治任用によって決めるべきだと思っていますが、その後もと居た企業などに戻る場合は、天下りにはならないようにします。あくまで、国家公務員試験を通って、長年務めてきた官僚を対象とします。
改革は一気に行なう
必要がなかったり無駄が多い特殊法人の廃止・民営化といった個別の改革とともに、天下りという根本的な問題の解決は、同時にやらなければ意味がありません。小泉首相や石原大臣は個別の改革をやろうとしていますが、それでは, 中途半端な改革に終わってしまうでしょう。しかしこの問題をこのまま放っておけば、民間を圧迫し景気の足を引っ張る、借金が増え続け多額の税金を投入せざるをえなくなる、などの問題が悪化するだけです。また何より、これだけ民間企業が厳しい中、公的機関だけが守られるという状況に対する不公平感が広がります。
小泉首相や石原大臣に意欲はあると思いますが、自民党政権で利権を断ち切る天下りの全面禁止を行なうのは不可能と言っていいでしょう。抜本的改革を現政権に求めては行きますが、やはり政権交代によってしか、改革は成し得ないと思っています。
http://www.edano.gr.jp/om/0109om.html
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
天下りをなくそう! 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
天下りをなくそう!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6471人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19249人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208305人
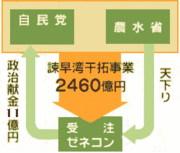









![[民主党]支持者の集い(政治政策)](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/22/69/1592269_165s.gif)













