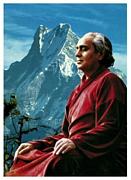インドのマスターである和尚の本に、「存在の詩」という本がある。
チベット密教のカギュー派に伝わる「マハームドラー」という高度な教えを題材にして、和尚が自らの教えを弟子を前にして語った講話を本にしたものだ。
その本の中で、和尚は「タントラ」の教えのエッセンスにつて、ヨガと対比することで語っている。
和尚は語る。
ヨガの終わるところからタントラが始まる・・・。
ヨガは努力の道であり、タントラは無努力の道である。
つまり、タントラは究極の教えであり、ヨガの終着地点が、タントラのスタート地点になるという。
そして、エンライトメント(ここでは、究極の悟りや覚醒を意味している)とは、努力とは無関係に「起こる」ものであり、誰もそれを準備することは出来ず、「起こす」ことはできない究極のハプニングであるとされている。
スピリチュアルな探究上の努力とエンライトメントとの間には、如何なる直截的な因果関係も無いというわけだ。
エンライトメントは、因果を超えて起こるものであり、そして、タントラは、まさに因果を超えてゆく道を指し示しているという。
ヨガは、まだ因果の内にあり、ほとんどの経典(スートラ)にある教えは、因果に基づいた教えとなっている。
しかし、そこには善悪、正邪などの二元性が存在し、そうした二元性は人間のマインドの作り出したものであり、
そうした二元性を超えてゆく道にこそ、究極へと至る真実の道があるという。
この講話に限らないけれども、こんな風に語る和尚の言葉には、多くの場合に、実に美しい響きが秘められている!
多くの探究者が、和尚の語る言葉に魅了されるのも、良くわかるというものだ。
「生」を美しい詩として語ることは、スピリチュアルな探究の道において、確かに、非常に重要な要素になり得ると思う。
自らの「生」が、まさに、ひとつの詩になったときには、スピリチュアルな探究に、神秘の次元が開示されるのは良くわかる。
和尚の語る、こうした無為の覚醒という教えは、確かに究極の何かを指し示している。
しかし、和尚の語る上記のような講話は、和尚が英語で講話をしていたという事情もあるのかもしれないけれども、現実のスピリチュアルな探究には、役に立たないと思われることが多いように思う。
そして、それはある意味、もしかしたら当たり前の話であって、上記のような和尚の語る講話の教えが、もし、スピリチュアルな探究の現実場面で極めて役に立つとしたら、それは、余程の探究の道のりを既に歩み終えて、相当に高いスピリチュアルな段階に至っている場合に限られるのではないかと思われるのだ。
ところで、僕の知人に、過去にヨガの先生を本格的にしていて、和尚の「存在の詩」と出逢ったのをキッカケに、ヨガの先生を辞めてしまったという人がいる。
その知人が語っていたことだけれども、ヨガをしているとエゴが強くなってしまうというのだ。
そして、ヨガの先生をしている人には、過去の自分たち同様に、エゴの強い人が非常に多いという。
しかし、私たちが何かを強い口調で否定するときには、概して、そうした否定している対象と同じ要素が、自分自身の中にも存在するケースが多いものだ。
その知人が、まさにそうした口調でヨガを否定し、自らの過去を否定するかのようなことを述べていたとき、僕には、そうしたことを語る今の彼女自身こそ、まさにエゴが強いという印象が否めなかった。
その知人は、ヨガの道を捨てて、タントラの道を選ぶことにした・・・といったようなことを語っていた。
そして、和尚の瞑想の技法を試してみたら、ヨガの技法などよりも、非常に画期的だったという。
人によって体験は異なるので、和尚の瞑想技法が画期的だという体験をする人もいれば、そうでない人もいる。
彼女の場合には、ヨガというしっかりとしたベースがあったからこそ、少なくとも最初の段階では、和尚の技法が非常に画期的に感じられたということも考えられなくはない。(和尚の技法もヨガの技法も、クンダリーニに関わっているという意味では、同じ土俵に属するものだと言える。 だから、ヨガの土台があれば、はじめて行う和尚の技法が、よりスピーディーな技法に感じられるということは、大いにあり得るように思う。)
しかし、エゴについての理解という点では、知人の理解は、あまりにも安直なものではないかと思えてしまったものだった。
そもそも、エゴとは何か・・・ということを、和尚自身は、あまり問題として採り上げていなかった。
それもあってか、知人がエゴという言葉を用いる際にも、フィーリングを基にした安易な理解がベースにあり、ヨガをすると、エゴが強まるから駄目だ・・・といった発想に簡単に飛びついているのが見受けられた。
「存在の詩」の中で、和尚はエゴについてこう語っている。
努力のあるところ、エゴが存在する。
何か目標に向かって努力するということ自体が、エゴに動機付けられた行為になっているし、何であれ、努力そのものがエゴを強化することになる。
流れ行くままに生きること、ゆったりと自然であること・・・そうした中でこそ、真に重要な物事は起こってゆく。
エゴによるマインドのコントロールを手放したところから、真実の物事は起こってゆく。
そして、究極の体験の中では、もはや体験する人は存在せず、体験そのものがあるだけだ。
エンライトメントとは、エゴが脱落した(「存在の詩」では、エゴが落ちる・・・という独特の表現をしている。)状態であり、完全なるエゴ無しの状態である。
私たちは、ハートの道、そして、究極のコミュニオン(精神的な交合を意味する・・・。和尚の造語)を通して、エンライトメントを達成するのだ。
こうした言葉自体は、実に美しい!!
しかし、こうした和尚のようなマスターの言葉は、決して真似してはいけないものだと思えてしまう。
美しさに魅了されるのは大いに良いとしても、真似をするのは、あまり好ましいことではないように思える。
というのも、和尚の語ることは、中身の判断は兎も角としても、究極の観点からの話であり、「存在の詩」で採り上げられているマハームドラーにしても、そもそも、悟りを得たマスターであるティロパが、悟りのまさに直前にある弟子のナロパに向けて語った、究極の真実に関わる話であるとされているのだから・・・。
それを自らの言葉として語れるのは、語られている中身に対しての、体験に裏打ちされた十分に深い理解と共感があってこそ、はじめて可能になることだと言えるに違いない。
ただ、それでも和尚の教えについて何ごとかを語る際には、和尚がまさにインド的なマスターだったという事情を、十分に考慮した方が良いように思う。
良し悪しは兎も角としても、夢のような美しい「詩」を語るのは、インド的な心性のひとつの特性であり、そして、和尚が弟子を導く際のポイントとしていたのは、バクティ的な要素とクンダリーニの覚醒だったことは、容易に見て取ることが出来ることだから・・・。
バクティとは、インド的な土壌の中で育まれた教えであり、マスターなどの聖なる存在に対しての「明け渡し」という意味合いが込められている。(単純な奉仕ということではない!)
また、クンダリーニという要素の重視も、元はといえば、インド的な土壌の中で生まれたスピリチュアルな伝統であり、しかも、それが道の全てという訳ではない。
和尚自身にしても、自分がまさにインド的なマスターであり、インドに生まれ、インドで育ったために、西洋社会に育った人々からは、理解されにくいメンタリティを有していることを、初期の講話の中では、弟子の前で釈明するような口調で述べていたものだった。
何故、こうしたことを問題とするのかというと、例えば、エゴと言う概念にしても、本来は厳密に、それが何であるのかを明らかにした上で、議論を進めるべきところを、和尚の講話を読む人の多くが、概して、曖昧なイメージでエゴについて論じる傾向があると思われるからだ。
そして、そうした曖昧なイメージによる議論が、スピリチュアルな探究上の看過できない誤解の要因になっているのを、しばしば眼にすることがあるからだ。
そもそも、ヨガをすることで、エゴが強まってしまうから駄目だ・・・みたいな議論は、残念ながら、とても幼稚な発想に過ぎない。
エネルギーを高めることが、もともと潜在していたエゴを露呈することに繋がる・・・というのは、事実として大いにあり得る話しだと思う。
でも、ヨガをしたら、エネルギーが高まり、その結果、エゴが強化されたとしても、それは通常はヨガの責任ではなく、その人自身の問題であるのは、容易に理解できるようなことだ。
それに、そもそも、一般的な話として、スピリチュアルな成長の過程で、少なくともある時期、エゴがより強化されるというのは、普通に見られることだと思う。
それは、決して間違ったことではなく、人間の成長過程では必然的なプロセスであるとも言える。
問題にすべきなのは、むしろ例えば、心理学的な観点から考えて、その人のエゴやマインドが、どの程度、病理的な要素を帯びているかといったことではないかと思う。
一般的に、エゴがあるから駄目・・・みたいな発想は、深い理解とは、およそ無縁な思いつき的な発想でしかない。
しかし、おそらく英語で語られていたがために、極めて単純化されてしまった和尚の講話を読む人の多くは、マインドについての分析や、エゴとは何かと言ったような、実は重要な問題を簡単にスルーしてしまう傾向がある。
ひとつには、和尚自身が、心理学を批判していたこと、哲学的な議論自体を無意味なものとして批判していたこと・・・などが、そうした傾向を助長してしまっているのだと思う。
しかし、和尚の講話は、そうした批判も含めて、究極の観点からの話であり、自分たちが、それを真に理解できる地点に到達していない限り、和尚が何かを批判しているのを、安易に引き合いに出しても、あまり意味が無いというのが正しいことのように思う。
和尚の語る言葉は、ある意味ではとても偏っており、究極の教えとしては「是」とされるとしても、自分たちの現実に引き寄せて考えた場合、あまり真実とはいえないことが多いのではないか?(しばしば言われるように、悟った人にとっての真実は、悟っていない人にとっての真実ではない。)
和尚の語る言葉が、私の現実であると言い得る人がいたら、それは余程のレベルの霊性修行の段階に至っている人に違いない。(笑)
しかし、そうした人ならば、決して和尚の言葉を真似るような語り方はしないに違いない。
前のトピックでも書いたように、和尚は、ほぼ9割の重要なニュアンスが失われてしまうような、英語での講話という選択をせざるを得なかったのだから・・・。
僕たちが日本語で何かを語る際には、自分の言葉で語ることができる。
和尚は、英語で微妙なニュアンスのスピリチュアルな話題を語っていたために、十二分に自分の言葉では語れなかったのに対して、私たちには、そうしたハンディは無いのだから・・・。
そして、自分の言葉で語る人は、相手が誰であれ、誰かの言葉を真似るような語り口はしないものだ。
チベット密教のカギュー派に伝わる「マハームドラー」という高度な教えを題材にして、和尚が自らの教えを弟子を前にして語った講話を本にしたものだ。
その本の中で、和尚は「タントラ」の教えのエッセンスにつて、ヨガと対比することで語っている。
和尚は語る。
ヨガの終わるところからタントラが始まる・・・。
ヨガは努力の道であり、タントラは無努力の道である。
つまり、タントラは究極の教えであり、ヨガの終着地点が、タントラのスタート地点になるという。
そして、エンライトメント(ここでは、究極の悟りや覚醒を意味している)とは、努力とは無関係に「起こる」ものであり、誰もそれを準備することは出来ず、「起こす」ことはできない究極のハプニングであるとされている。
スピリチュアルな探究上の努力とエンライトメントとの間には、如何なる直截的な因果関係も無いというわけだ。
エンライトメントは、因果を超えて起こるものであり、そして、タントラは、まさに因果を超えてゆく道を指し示しているという。
ヨガは、まだ因果の内にあり、ほとんどの経典(スートラ)にある教えは、因果に基づいた教えとなっている。
しかし、そこには善悪、正邪などの二元性が存在し、そうした二元性は人間のマインドの作り出したものであり、
そうした二元性を超えてゆく道にこそ、究極へと至る真実の道があるという。
この講話に限らないけれども、こんな風に語る和尚の言葉には、多くの場合に、実に美しい響きが秘められている!
多くの探究者が、和尚の語る言葉に魅了されるのも、良くわかるというものだ。
「生」を美しい詩として語ることは、スピリチュアルな探究の道において、確かに、非常に重要な要素になり得ると思う。
自らの「生」が、まさに、ひとつの詩になったときには、スピリチュアルな探究に、神秘の次元が開示されるのは良くわかる。
和尚の語る、こうした無為の覚醒という教えは、確かに究極の何かを指し示している。
しかし、和尚の語る上記のような講話は、和尚が英語で講話をしていたという事情もあるのかもしれないけれども、現実のスピリチュアルな探究には、役に立たないと思われることが多いように思う。
そして、それはある意味、もしかしたら当たり前の話であって、上記のような和尚の語る講話の教えが、もし、スピリチュアルな探究の現実場面で極めて役に立つとしたら、それは、余程の探究の道のりを既に歩み終えて、相当に高いスピリチュアルな段階に至っている場合に限られるのではないかと思われるのだ。
ところで、僕の知人に、過去にヨガの先生を本格的にしていて、和尚の「存在の詩」と出逢ったのをキッカケに、ヨガの先生を辞めてしまったという人がいる。
その知人が語っていたことだけれども、ヨガをしているとエゴが強くなってしまうというのだ。
そして、ヨガの先生をしている人には、過去の自分たち同様に、エゴの強い人が非常に多いという。
しかし、私たちが何かを強い口調で否定するときには、概して、そうした否定している対象と同じ要素が、自分自身の中にも存在するケースが多いものだ。
その知人が、まさにそうした口調でヨガを否定し、自らの過去を否定するかのようなことを述べていたとき、僕には、そうしたことを語る今の彼女自身こそ、まさにエゴが強いという印象が否めなかった。
その知人は、ヨガの道を捨てて、タントラの道を選ぶことにした・・・といったようなことを語っていた。
そして、和尚の瞑想の技法を試してみたら、ヨガの技法などよりも、非常に画期的だったという。
人によって体験は異なるので、和尚の瞑想技法が画期的だという体験をする人もいれば、そうでない人もいる。
彼女の場合には、ヨガというしっかりとしたベースがあったからこそ、少なくとも最初の段階では、和尚の技法が非常に画期的に感じられたということも考えられなくはない。(和尚の技法もヨガの技法も、クンダリーニに関わっているという意味では、同じ土俵に属するものだと言える。 だから、ヨガの土台があれば、はじめて行う和尚の技法が、よりスピーディーな技法に感じられるということは、大いにあり得るように思う。)
しかし、エゴについての理解という点では、知人の理解は、あまりにも安直なものではないかと思えてしまったものだった。
そもそも、エゴとは何か・・・ということを、和尚自身は、あまり問題として採り上げていなかった。
それもあってか、知人がエゴという言葉を用いる際にも、フィーリングを基にした安易な理解がベースにあり、ヨガをすると、エゴが強まるから駄目だ・・・といった発想に簡単に飛びついているのが見受けられた。
「存在の詩」の中で、和尚はエゴについてこう語っている。
努力のあるところ、エゴが存在する。
何か目標に向かって努力するということ自体が、エゴに動機付けられた行為になっているし、何であれ、努力そのものがエゴを強化することになる。
流れ行くままに生きること、ゆったりと自然であること・・・そうした中でこそ、真に重要な物事は起こってゆく。
エゴによるマインドのコントロールを手放したところから、真実の物事は起こってゆく。
そして、究極の体験の中では、もはや体験する人は存在せず、体験そのものがあるだけだ。
エンライトメントとは、エゴが脱落した(「存在の詩」では、エゴが落ちる・・・という独特の表現をしている。)状態であり、完全なるエゴ無しの状態である。
私たちは、ハートの道、そして、究極のコミュニオン(精神的な交合を意味する・・・。和尚の造語)を通して、エンライトメントを達成するのだ。
こうした言葉自体は、実に美しい!!
しかし、こうした和尚のようなマスターの言葉は、決して真似してはいけないものだと思えてしまう。
美しさに魅了されるのは大いに良いとしても、真似をするのは、あまり好ましいことではないように思える。
というのも、和尚の語ることは、中身の判断は兎も角としても、究極の観点からの話であり、「存在の詩」で採り上げられているマハームドラーにしても、そもそも、悟りを得たマスターであるティロパが、悟りのまさに直前にある弟子のナロパに向けて語った、究極の真実に関わる話であるとされているのだから・・・。
それを自らの言葉として語れるのは、語られている中身に対しての、体験に裏打ちされた十分に深い理解と共感があってこそ、はじめて可能になることだと言えるに違いない。
ただ、それでも和尚の教えについて何ごとかを語る際には、和尚がまさにインド的なマスターだったという事情を、十分に考慮した方が良いように思う。
良し悪しは兎も角としても、夢のような美しい「詩」を語るのは、インド的な心性のひとつの特性であり、そして、和尚が弟子を導く際のポイントとしていたのは、バクティ的な要素とクンダリーニの覚醒だったことは、容易に見て取ることが出来ることだから・・・。
バクティとは、インド的な土壌の中で育まれた教えであり、マスターなどの聖なる存在に対しての「明け渡し」という意味合いが込められている。(単純な奉仕ということではない!)
また、クンダリーニという要素の重視も、元はといえば、インド的な土壌の中で生まれたスピリチュアルな伝統であり、しかも、それが道の全てという訳ではない。
和尚自身にしても、自分がまさにインド的なマスターであり、インドに生まれ、インドで育ったために、西洋社会に育った人々からは、理解されにくいメンタリティを有していることを、初期の講話の中では、弟子の前で釈明するような口調で述べていたものだった。
何故、こうしたことを問題とするのかというと、例えば、エゴと言う概念にしても、本来は厳密に、それが何であるのかを明らかにした上で、議論を進めるべきところを、和尚の講話を読む人の多くが、概して、曖昧なイメージでエゴについて論じる傾向があると思われるからだ。
そして、そうした曖昧なイメージによる議論が、スピリチュアルな探究上の看過できない誤解の要因になっているのを、しばしば眼にすることがあるからだ。
そもそも、ヨガをすることで、エゴが強まってしまうから駄目だ・・・みたいな議論は、残念ながら、とても幼稚な発想に過ぎない。
エネルギーを高めることが、もともと潜在していたエゴを露呈することに繋がる・・・というのは、事実として大いにあり得る話しだと思う。
でも、ヨガをしたら、エネルギーが高まり、その結果、エゴが強化されたとしても、それは通常はヨガの責任ではなく、その人自身の問題であるのは、容易に理解できるようなことだ。
それに、そもそも、一般的な話として、スピリチュアルな成長の過程で、少なくともある時期、エゴがより強化されるというのは、普通に見られることだと思う。
それは、決して間違ったことではなく、人間の成長過程では必然的なプロセスであるとも言える。
問題にすべきなのは、むしろ例えば、心理学的な観点から考えて、その人のエゴやマインドが、どの程度、病理的な要素を帯びているかといったことではないかと思う。
一般的に、エゴがあるから駄目・・・みたいな発想は、深い理解とは、およそ無縁な思いつき的な発想でしかない。
しかし、おそらく英語で語られていたがために、極めて単純化されてしまった和尚の講話を読む人の多くは、マインドについての分析や、エゴとは何かと言ったような、実は重要な問題を簡単にスルーしてしまう傾向がある。
ひとつには、和尚自身が、心理学を批判していたこと、哲学的な議論自体を無意味なものとして批判していたこと・・・などが、そうした傾向を助長してしまっているのだと思う。
しかし、和尚の講話は、そうした批判も含めて、究極の観点からの話であり、自分たちが、それを真に理解できる地点に到達していない限り、和尚が何かを批判しているのを、安易に引き合いに出しても、あまり意味が無いというのが正しいことのように思う。
和尚の語る言葉は、ある意味ではとても偏っており、究極の教えとしては「是」とされるとしても、自分たちの現実に引き寄せて考えた場合、あまり真実とはいえないことが多いのではないか?(しばしば言われるように、悟った人にとっての真実は、悟っていない人にとっての真実ではない。)
和尚の語る言葉が、私の現実であると言い得る人がいたら、それは余程のレベルの霊性修行の段階に至っている人に違いない。(笑)
しかし、そうした人ならば、決して和尚の言葉を真似るような語り方はしないに違いない。
前のトピックでも書いたように、和尚は、ほぼ9割の重要なニュアンスが失われてしまうような、英語での講話という選択をせざるを得なかったのだから・・・。
僕たちが日本語で何かを語る際には、自分の言葉で語ることができる。
和尚は、英語で微妙なニュアンスのスピリチュアルな話題を語っていたために、十二分に自分の言葉では語れなかったのに対して、私たちには、そうしたハンディは無いのだから・・・。
そして、自分の言葉で語る人は、相手が誰であれ、誰かの言葉を真似るような語り口はしないものだ。
|
|
|
|
コメント(5)
エゴという言葉ですが、例えば、和尚がエゴという言葉を用いて何かを語るとき、英語のエゴという言葉のニュアンスによって指し示している事柄のイメージが左右されていることを考慮する必要があると思います。
そして、実際のところは、エゴが脱落する=エンライトメント といった場合の「エゴ」とは、日本語で言えば、ほぼ「自我」という概念に相当していると考えて良いと思います。
その辺の議論を厳密にすると、仏教上の概念やインド哲学上の概念との比較にまで、話は発展しそうですが、しかし、和尚自身が厳密に言葉を用いているわけでは全く無かったので、むしろ概念の定義と言った面倒な問題には、あまり触れる必要は無いように思います。
ただ、例えば、フロイトの心理学が、英語圏に紹介された際に、ドイツ語から英語への概念の翻訳上の問題を巡って、英語圏では、フロイトの理論が大きな誤解を蒙ったという指摘などがあることは、この際にも留意しておいた方が良いように思います。(トランスパーソナル心理学のケン・ウィルバーが、「進化の構造」という著書の中でこの件について述べています。)
というのは、フロイト理論のキー概念のひとつが、まさにここで問題としている「自我」(英語ではエゴ、元のドイツ語では、das Ich 他の2つのキー概念が、超自我、イドと呼ばれている。)という概念だからです。
フロイト理論の誤解のひとつは、自我(エゴ)の概念を巡ってのもので、英語の ego という言葉のニュアンスが、ドイツ語のdas Ich という言葉のニュアンスと異なっていることに由来したと言われています。
エゴという言葉には、日本語の自我の意味に加えて、エゴイズムというニュアンスが含まれますが、ドイツ語のdas Ich には、そうしたニュアンスは無く、元々、フロイト理論のdas Ich という概念では、当然のことながら、エゴイズムといったニュアンスは、含まれてはいなかったのです。
ところが、英語圏では、das Ich が英語に翻訳される際、ego と言い換えられたために、エゴに満ちた個人の情動が、人間を動かす内的動因の一つとされるに至り、それがフロイト理論に対しての本来の理解を歪める結果に繋がったのでした。
話を戻します。
エゴが消え去るのがエンライトメントである・・・というイメージが、和尚の本を読み、和尚の信奉者となる多くの人の間で、ほぼ定着したコンセンサスになっているように思うのですが、厳密な話をすると、これは正しくないのではないかと思います。
和尚の語っていたことには、厳密な話をすると、正しくなかったことも多いのではないかと、僕などは思うのですが、それは英語での講話だったから仕方が無かったという側面もあるだろうし、和尚のインド的なマスターとしてのタイプにも由来することだったと思うのです。
でも、だからこそ、和尚の本に接する際には、そうした事情を十分に踏まえておいた方が良い。
そうでないと、曖昧なイメージで見当違いのことを語ることにも繋がるのではないかと思います。
(実際に、そうしたケースが多いように見受けられます。)
和尚が、「エゴ」という言葉で指し示していたのが、ヒンディー語で何に該当するのかはわからないですが、日本語にすれば、ほぼ「自我」ということだと、和尚の本の内容からは想像できます。
つまり、ドイツ語にすれば、das Ich ということに、ほぼ近いわけです。
だから、和尚の語っていたことは、エゴイズムというニュアンスとは本来は無関係な話で、「自我」が消え去るという意味だったと解釈した方が妥当だと思えます。
しかし、和尚の語っていた言葉は、あくまで事実というよりは、詩的な表現だったという風に考えられます。
実際には、エンライトメントを達成したから、自我が消え去る・・・といったことは、あり得ないと思うからです。
更に言えば、英語でいうエゴですら、エンライトメントを達成したから消え去ると言えるのかどうかは、疑問があります。
「何か目標に向かって努力するということ自体が、エゴに動機付けられた行為になっているし、何であれ、努力そのものがエゴを強化することになる。」・・・といった和尚の講話ですが、そうなると、瞑想修行という観点から考えても、あまり額面どおりには受け取れない話ということになりそうです。
自我が強化されるから駄目だ・・・とは単純には言えないし、それにあくまで、和尚の語っていた言葉は、詩的な表現のなかに、深い真実を匂わせたものだったという捉え方をするのが正しいと思われるからです。
ちなみに、「存在の詩」を読んでヨガやタントラについて理解したと思った人がいたら、それは改めて考え直した方が良いと思います。(笑)
「ヨガの終わるところからタントラが始まる・・・」というのは、実際には、全く正しくないし、和尚自身、ヨガに関して、例えば、「The path of YOGA」といった本の中では、全く異なったことを語っているし、タントラについての理解に関しても、和尚の「存在の詩」で語られているタントラとは、一般的なタントラ理解から観たら、特殊なものだからです。
上記のことに限らないですが、和尚がこう語っていたから、これが真実に違いない・・・といった発想は、歪んだ現実認識をもたらす危険性が強いように思えます。
自分自身の体験がまずあり、それと照合してみて、何かヒントになる可能性がある・・・という意味では、和尚の詩的な語り口から、何か重要なニュアンスを汲み取れることもあるでしょうが。
例えば、和尚がそう語っていたから、哲学を否定し、心理学など意味が無いみたいに考えてしまう人たちを見かけることがあるのですが、これなどは、ほとんど笑い話みたいな話です。(哲学することには意味があり、心理学的な分析にも、非常に多くの場合に重要性があります。)
ヨガに対しての批判も同様ですし、他にも、そうした指摘が出来ることは、非常にたくさんあります。
和尚の講話は、概ね、究極の教えを、ある一面から語っていたといった捉え方をすることでのみ、正しく理解できるのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか?
そして、実際のところは、エゴが脱落する=エンライトメント といった場合の「エゴ」とは、日本語で言えば、ほぼ「自我」という概念に相当していると考えて良いと思います。
その辺の議論を厳密にすると、仏教上の概念やインド哲学上の概念との比較にまで、話は発展しそうですが、しかし、和尚自身が厳密に言葉を用いているわけでは全く無かったので、むしろ概念の定義と言った面倒な問題には、あまり触れる必要は無いように思います。
ただ、例えば、フロイトの心理学が、英語圏に紹介された際に、ドイツ語から英語への概念の翻訳上の問題を巡って、英語圏では、フロイトの理論が大きな誤解を蒙ったという指摘などがあることは、この際にも留意しておいた方が良いように思います。(トランスパーソナル心理学のケン・ウィルバーが、「進化の構造」という著書の中でこの件について述べています。)
というのは、フロイト理論のキー概念のひとつが、まさにここで問題としている「自我」(英語ではエゴ、元のドイツ語では、das Ich 他の2つのキー概念が、超自我、イドと呼ばれている。)という概念だからです。
フロイト理論の誤解のひとつは、自我(エゴ)の概念を巡ってのもので、英語の ego という言葉のニュアンスが、ドイツ語のdas Ich という言葉のニュアンスと異なっていることに由来したと言われています。
エゴという言葉には、日本語の自我の意味に加えて、エゴイズムというニュアンスが含まれますが、ドイツ語のdas Ich には、そうしたニュアンスは無く、元々、フロイト理論のdas Ich という概念では、当然のことながら、エゴイズムといったニュアンスは、含まれてはいなかったのです。
ところが、英語圏では、das Ich が英語に翻訳される際、ego と言い換えられたために、エゴに満ちた個人の情動が、人間を動かす内的動因の一つとされるに至り、それがフロイト理論に対しての本来の理解を歪める結果に繋がったのでした。
話を戻します。
エゴが消え去るのがエンライトメントである・・・というイメージが、和尚の本を読み、和尚の信奉者となる多くの人の間で、ほぼ定着したコンセンサスになっているように思うのですが、厳密な話をすると、これは正しくないのではないかと思います。
和尚の語っていたことには、厳密な話をすると、正しくなかったことも多いのではないかと、僕などは思うのですが、それは英語での講話だったから仕方が無かったという側面もあるだろうし、和尚のインド的なマスターとしてのタイプにも由来することだったと思うのです。
でも、だからこそ、和尚の本に接する際には、そうした事情を十分に踏まえておいた方が良い。
そうでないと、曖昧なイメージで見当違いのことを語ることにも繋がるのではないかと思います。
(実際に、そうしたケースが多いように見受けられます。)
和尚が、「エゴ」という言葉で指し示していたのが、ヒンディー語で何に該当するのかはわからないですが、日本語にすれば、ほぼ「自我」ということだと、和尚の本の内容からは想像できます。
つまり、ドイツ語にすれば、das Ich ということに、ほぼ近いわけです。
だから、和尚の語っていたことは、エゴイズムというニュアンスとは本来は無関係な話で、「自我」が消え去るという意味だったと解釈した方が妥当だと思えます。
しかし、和尚の語っていた言葉は、あくまで事実というよりは、詩的な表現だったという風に考えられます。
実際には、エンライトメントを達成したから、自我が消え去る・・・といったことは、あり得ないと思うからです。
更に言えば、英語でいうエゴですら、エンライトメントを達成したから消え去ると言えるのかどうかは、疑問があります。
「何か目標に向かって努力するということ自体が、エゴに動機付けられた行為になっているし、何であれ、努力そのものがエゴを強化することになる。」・・・といった和尚の講話ですが、そうなると、瞑想修行という観点から考えても、あまり額面どおりには受け取れない話ということになりそうです。
自我が強化されるから駄目だ・・・とは単純には言えないし、それにあくまで、和尚の語っていた言葉は、詩的な表現のなかに、深い真実を匂わせたものだったという捉え方をするのが正しいと思われるからです。
ちなみに、「存在の詩」を読んでヨガやタントラについて理解したと思った人がいたら、それは改めて考え直した方が良いと思います。(笑)
「ヨガの終わるところからタントラが始まる・・・」というのは、実際には、全く正しくないし、和尚自身、ヨガに関して、例えば、「The path of YOGA」といった本の中では、全く異なったことを語っているし、タントラについての理解に関しても、和尚の「存在の詩」で語られているタントラとは、一般的なタントラ理解から観たら、特殊なものだからです。
上記のことに限らないですが、和尚がこう語っていたから、これが真実に違いない・・・といった発想は、歪んだ現実認識をもたらす危険性が強いように思えます。
自分自身の体験がまずあり、それと照合してみて、何かヒントになる可能性がある・・・という意味では、和尚の詩的な語り口から、何か重要なニュアンスを汲み取れることもあるでしょうが。
例えば、和尚がそう語っていたから、哲学を否定し、心理学など意味が無いみたいに考えてしまう人たちを見かけることがあるのですが、これなどは、ほとんど笑い話みたいな話です。(哲学することには意味があり、心理学的な分析にも、非常に多くの場合に重要性があります。)
ヨガに対しての批判も同様ですし、他にも、そうした指摘が出来ることは、非常にたくさんあります。
和尚の講話は、概ね、究極の教えを、ある一面から語っていたといった捉え方をすることでのみ、正しく理解できるのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか?
☆★華蓮★☆ さん
>言葉にとらわれずようするに空だということですね?
確かに、それが真の理解に至る道ですね!
>人として経験するのではなく経験したことをすべて空として捉える。
その前の段階の話をしたかったわけですが、空性の認識という話題が出ましたので、そのことにも触れたいと思います。
空性の認識には、仏陀からナーガールジュナへと繋がる仏教の歴史が関わっていますよね。
ナーガールジュナになると、究極のリアリティをも実体が無いという意味での空として捉える見方になるようですが、☆★華蓮★☆ さんが、経験したことを全て空として捉えるということで仰っている意味合いは、おおよそわかるつもりです。
和尚の場合、オリジナルな技法として編み出したものが、和尚自身も語っているように、全て第2身体に関わる技法だったため、それも大いに影響してか、和尚の弟子の間では、空性の認識の知的側面が重視されていないと思うのですが、和尚を理解するにも、空性の認識という要素も重要だとは思います。
そして、経験を空として捉えるには、知的なプロセスも、それなりに介在するように思います。
>言葉にとらわれずようするに空だということですね?
確かに、それが真の理解に至る道ですね!
>人として経験するのではなく経験したことをすべて空として捉える。
その前の段階の話をしたかったわけですが、空性の認識という話題が出ましたので、そのことにも触れたいと思います。
空性の認識には、仏陀からナーガールジュナへと繋がる仏教の歴史が関わっていますよね。
ナーガールジュナになると、究極のリアリティをも実体が無いという意味での空として捉える見方になるようですが、☆★華蓮★☆ さんが、経験したことを全て空として捉えるということで仰っている意味合いは、おおよそわかるつもりです。
和尚の場合、オリジナルな技法として編み出したものが、和尚自身も語っているように、全て第2身体に関わる技法だったため、それも大いに影響してか、和尚の弟子の間では、空性の認識の知的側面が重視されていないと思うのですが、和尚を理解するにも、空性の認識という要素も重要だとは思います。
そして、経験を空として捉えるには、知的なプロセスも、それなりに介在するように思います。
TAKERU さん
コメントありがとうございます。
>わりと霊的な師の多くは始めからゴールに在れというメッセージを言いますし、それもわかるのですが……
やはりできないと思うのですよ。
インドでは、そうした師が多いように思います。
いわゆるアドヴァイタ的な教えを説く師などが、とりわけそうです。
和尚の場合には、いろいろ複雑な要素があるのですが、アドヴァイタ的な教えを説いていると同時に、教えにアクセスし易いのと、悪く言えば、判った気になりやすい・・・という点が指摘できると思います。
究極の話をしているのに、安易に自分に当てはめて捉えてしまいやすいと思うのです。
それは、究極の話が、同時に和尚の手法にもなっているということで、ますます促進されていると思います。
こうした冷めた見方は、和尚の信奉者の人たちからは、嫌われそうですが、しかし、外部に在るものの見解としては、重要だと思います。
そして、カルト的な傾向を助長しないためには、対話が必要です。
和尚のサニヤシンの人たちからの反論・批判を期待していたのですが、対話にならないのは残念ですね。(和尚の教え自体が素晴らしいので、余計に対話を期待していたのですが・・・)
確かに仰るとおりで、いきなり究極の話を持ち出すのは、極端なことだと思います。
>特に社会で行われていることのほとんどは生命に添うワークではないですし。
まさに同感です!
>一方で最近ひとをヒーリングしていて思うのですが、当たり前に過ごし、生き続けている自分自身という本人が、その意識がどれだけ自分自身と周囲によって束縛され、不自由であるか、癒しが進むごとに感じます。
様々な教えが、そこからの解放を説いていますが、和尚の教えに接する場合に限らず、足元の事実として、そうしたことを、どれだけ深く理解するかが、とても重要だと思います。
そうでないと、優れた教えに対しての本当の理解は、生まれないように思います。
>その状態でゴールに在ろうとするのもエゴ的に思えるのですね。
多くのひとの薄っぺらな感謝や喜びの仮面がそうであるように。
しかし真実や神、宇宙はエゴな思考ごときに操られるほど愚かじゃないですし。
仰ることの意味は、非常に良くわかります。
手厳しい批判だと感じますが、まさに真実を突いていると思います。
>わたしの場合、まず真実や人生の幸福とは何かを探究するのが一番最良の道だと感じています。
そしてその理解が道の方向性とプロセスを生みます。
>しかし理解はいつも進行形です。
>いつでも変更したり破棄する覚悟が必要ですね。真実のために。
こうしたことは、非常に重要な洞察ですね!
真実を、どこかのマスターの言葉に求めてはならないと思うのです。
自分自身の内側での、確かな気づき以外に、真実は無いというぐらいの姿勢が重要だと思います。
また、自らの理解を安易に他者と共有するのも、真実の姿勢ではないと思います。
確かな理解と共に歩みつつ、それに捉われない姿勢は、真理を探究する真剣さからしか生まれないと思います。
そうした意味でも、和尚に限らないですが、マスターの教えという枠を作ってしまい、枠に捉われてしまっては駄目だと思います。
貴重な指摘をしていただき、本当にありがとうございました。
コメントありがとうございます。
>わりと霊的な師の多くは始めからゴールに在れというメッセージを言いますし、それもわかるのですが……
やはりできないと思うのですよ。
インドでは、そうした師が多いように思います。
いわゆるアドヴァイタ的な教えを説く師などが、とりわけそうです。
和尚の場合には、いろいろ複雑な要素があるのですが、アドヴァイタ的な教えを説いていると同時に、教えにアクセスし易いのと、悪く言えば、判った気になりやすい・・・という点が指摘できると思います。
究極の話をしているのに、安易に自分に当てはめて捉えてしまいやすいと思うのです。
それは、究極の話が、同時に和尚の手法にもなっているということで、ますます促進されていると思います。
こうした冷めた見方は、和尚の信奉者の人たちからは、嫌われそうですが、しかし、外部に在るものの見解としては、重要だと思います。
そして、カルト的な傾向を助長しないためには、対話が必要です。
和尚のサニヤシンの人たちからの反論・批判を期待していたのですが、対話にならないのは残念ですね。(和尚の教え自体が素晴らしいので、余計に対話を期待していたのですが・・・)
確かに仰るとおりで、いきなり究極の話を持ち出すのは、極端なことだと思います。
>特に社会で行われていることのほとんどは生命に添うワークではないですし。
まさに同感です!
>一方で最近ひとをヒーリングしていて思うのですが、当たり前に過ごし、生き続けている自分自身という本人が、その意識がどれだけ自分自身と周囲によって束縛され、不自由であるか、癒しが進むごとに感じます。
様々な教えが、そこからの解放を説いていますが、和尚の教えに接する場合に限らず、足元の事実として、そうしたことを、どれだけ深く理解するかが、とても重要だと思います。
そうでないと、優れた教えに対しての本当の理解は、生まれないように思います。
>その状態でゴールに在ろうとするのもエゴ的に思えるのですね。
多くのひとの薄っぺらな感謝や喜びの仮面がそうであるように。
しかし真実や神、宇宙はエゴな思考ごときに操られるほど愚かじゃないですし。
仰ることの意味は、非常に良くわかります。
手厳しい批判だと感じますが、まさに真実を突いていると思います。
>わたしの場合、まず真実や人生の幸福とは何かを探究するのが一番最良の道だと感じています。
そしてその理解が道の方向性とプロセスを生みます。
>しかし理解はいつも進行形です。
>いつでも変更したり破棄する覚悟が必要ですね。真実のために。
こうしたことは、非常に重要な洞察ですね!
真実を、どこかのマスターの言葉に求めてはならないと思うのです。
自分自身の内側での、確かな気づき以外に、真実は無いというぐらいの姿勢が重要だと思います。
また、自らの理解を安易に他者と共有するのも、真実の姿勢ではないと思います。
確かな理解と共に歩みつつ、それに捉われない姿勢は、真理を探究する真剣さからしか生まれないと思います。
そうした意味でも、和尚に限らないですが、マスターの教えという枠を作ってしまい、枠に捉われてしまっては駄目だと思います。
貴重な指摘をしていただき、本当にありがとうございました。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
瞑想 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
瞑想のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90065人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208324人
- 3位
- 酒好き
- 170697人