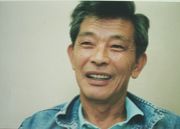「ミリキタニの猫」のプロデュースをしている通称マサさんが、「風のつぶやき」という文章を毎週のようにメールで配信しています。そこで私が興味を抱いたのが、荒貞夫という歌手です。
先日の第25回アジア系アメリカ映画祭でも、上映後の質疑応答で、ミリキタニさんは、大好きな荒貞夫の「男は泣かず」という歌をうたってお開きになりました。荒貞夫は戦時中、4ヶ月ほどツーリレーク収容所にいて、ミリキタニさんはそこで彼と知り合ったのです。
男は泣かず、の作曲者は古賀政男です。そう、「謎の森に棲む古賀政男」(講談社 1998)の、あの怪物、古賀政男です。アメリカつながりで荒貞夫のことが出てくるかとも思ったのですが、どうやらこの本では触れられていないようです。著者の下嶋哲郎さんは次のように書いています。
「ツールレイクへつぎつぎ送り込まれてくる危険分子の中に、ミュージシャンも多かった。ローワから横竹、梅本、マンザナーから大西、そしてグレナダから二世行進曲を歌った坂野雪人たちが送られてきた」
荒貞夫もそのうちの一人のミュージシャンだったのでしょう。詳しいことは今のところわかりません。わかるのは、下記の解説にあるように福島県で生まれ、大正六年四月渡米、在米邦人間の間で国粋歌手として知られた、ということ。それから以下のインターネットの情報だけです。萩原周二という人が書いたものです。引用します。
「昔、荒國誠先生に直接詩吟を習っていたころ、先生にこの丹田に力を入れることをいわれました。先生は、自分で詠いながら私に、丹田に手で触れさせたものでした。
荒國誠先生は、歌手名は荒貞夫といいました。戦前にオペラ歌手になりたくて、米国に渡りました。米国では、開拓の仕事をしながら、そしてやがて、先生は琵琶の名手だったのでそれを教えながら、オペラを学んだようです。
そしてやがて、ニューヨークのカーネギーホールに出演しました。そのときに先生の着たタキシードを、私も着せてもらったことがあります。私に実にぴったりでした。若き日の先生は、実にスマートだったのですが、やはりテナー歌手らしく、胸の張りはかなりなものでした。
だが、そこへ、不幸な日米戦争です。
先生は、カルフォルニアのマハトバの収容所にたくさんの日系人と一緒に収監になりました。この収容所の中で、先生はみなの前で詩吟を詠われました。ですから、荒國誠先生の詩吟の流派は、米国とカナダがもともとの主流です。
先生はハイテナーの歌手でしたが、あの高く強い詩吟の声を出すのには、この丹田から出しているのだということを教えてくれました。声は、あくまで丹田かから出していて、喉や口は、ただその空気の出し方を調節しているだけだということを、いつも教えてくれました」
さて、話を「男は泣かず」に戻します。このうたの歌詞は、インターネットで検索できず、日本の歌謡曲全集にも出ておらず、探すのに苦労しました。「古賀メロディ誕生70周年記念 古賀政男大全集~20世紀の遺産~」という16巻のCDの6巻目に収録されています。これも今は品切れですが、何とか調べました。以下に歌詞と解説を引用します。
男は泣かず 作詩:野村俊夫 作曲:古賀政男 歌:荒 貞夫
コロムビア100110a 1940年10月20日発売
月は夜空を 照らしても
男ごゝろを 知るものか
泣いて泣かない ひとすじを
花よかなしく なぜ恨む
道は雲間に 続くとも
なんで行かずに いらりょか
男一途の この胸に
吹くな涙の 小夜嵐
男なくときぁ たゞ泣かぬ
伊達に誇りが 捨てらりょか
たとえ嵐が 寄せよとも
強く笑って 生きようよ
*以下は「古賀メロディ誕生70年記念 古賀政男大全集 解説本」からの引用です。
クラシックの勉強をしていて中年になって突然流行歌の世界にデビューした東海林太郎を思わせる中年の新人デビューである。当時の歌詞カードを見ると、まずトップに蝶ネクタイが板についたシブい中年男性のポートレート、その下に「新人紹介」が詳しく載っている。これが時代を想わせてなかなかおもしろい。(原文のまま)
「荒貞夫氏は福島県出身、大正六年四月渡米、ハリウッド・ビックス・アート・スタディに入り、勉学の傍らメトロポリタン座の名歌手メノッテ・フラスコナ氏に十数年師事し、在米邦人間に国粋歌手として知られる。昭和十五年春、帰朝と共に我社専属となり、茲に流行歌曲王古賀政男氏の名曲を以て、レコード界に華々しくデビューすることとなった」
何だかこの五年前、イタリアオペラの勉強の行き、帰ってきて演歌調「無情の夢」をうたった児玉好雄とイメージがオーバーラップするが、こちらの方は堂々と胸を張ってオーソドックスにうたう男性的なバリトンで、心に響いたのだが火がつかなかった。この古賀メロディ一曲だけで消えたが、レコードが出たのは太平洋戦争の始まる一年前の昭和十五年十月、あるいはアメリカ帰りが響いたのかも。この時代灰田勝彦などもハワイ生まれの二世ということが響いて戦争が終るまで針のむしろに座らされているような状態があったものである。
引用は以上です。荒は古賀メロディ1曲で消えた。古賀政男だけがあれだけ戦争に協力しながら、戦後、なぜ何事もなかったかのように作曲家として生きられたのか。それは下嶋さんの「謎の森に棲む古賀政男」を読むとわかりますが、日系2世の協力があったのですね。
それにしても、荒貞夫のことをもっと知りたい。ミリキタニさんにも来日した折に、荒貞夫のことを聞いてみたいですね。
古賀政男と日系人、そして荒貞夫。面白いテーマだと思います。
先日の第25回アジア系アメリカ映画祭でも、上映後の質疑応答で、ミリキタニさんは、大好きな荒貞夫の「男は泣かず」という歌をうたってお開きになりました。荒貞夫は戦時中、4ヶ月ほどツーリレーク収容所にいて、ミリキタニさんはそこで彼と知り合ったのです。
男は泣かず、の作曲者は古賀政男です。そう、「謎の森に棲む古賀政男」(講談社 1998)の、あの怪物、古賀政男です。アメリカつながりで荒貞夫のことが出てくるかとも思ったのですが、どうやらこの本では触れられていないようです。著者の下嶋哲郎さんは次のように書いています。
「ツールレイクへつぎつぎ送り込まれてくる危険分子の中に、ミュージシャンも多かった。ローワから横竹、梅本、マンザナーから大西、そしてグレナダから二世行進曲を歌った坂野雪人たちが送られてきた」
荒貞夫もそのうちの一人のミュージシャンだったのでしょう。詳しいことは今のところわかりません。わかるのは、下記の解説にあるように福島県で生まれ、大正六年四月渡米、在米邦人間の間で国粋歌手として知られた、ということ。それから以下のインターネットの情報だけです。萩原周二という人が書いたものです。引用します。
「昔、荒國誠先生に直接詩吟を習っていたころ、先生にこの丹田に力を入れることをいわれました。先生は、自分で詠いながら私に、丹田に手で触れさせたものでした。
荒國誠先生は、歌手名は荒貞夫といいました。戦前にオペラ歌手になりたくて、米国に渡りました。米国では、開拓の仕事をしながら、そしてやがて、先生は琵琶の名手だったのでそれを教えながら、オペラを学んだようです。
そしてやがて、ニューヨークのカーネギーホールに出演しました。そのときに先生の着たタキシードを、私も着せてもらったことがあります。私に実にぴったりでした。若き日の先生は、実にスマートだったのですが、やはりテナー歌手らしく、胸の張りはかなりなものでした。
だが、そこへ、不幸な日米戦争です。
先生は、カルフォルニアのマハトバの収容所にたくさんの日系人と一緒に収監になりました。この収容所の中で、先生はみなの前で詩吟を詠われました。ですから、荒國誠先生の詩吟の流派は、米国とカナダがもともとの主流です。
先生はハイテナーの歌手でしたが、あの高く強い詩吟の声を出すのには、この丹田から出しているのだということを教えてくれました。声は、あくまで丹田かから出していて、喉や口は、ただその空気の出し方を調節しているだけだということを、いつも教えてくれました」
さて、話を「男は泣かず」に戻します。このうたの歌詞は、インターネットで検索できず、日本の歌謡曲全集にも出ておらず、探すのに苦労しました。「古賀メロディ誕生70周年記念 古賀政男大全集~20世紀の遺産~」という16巻のCDの6巻目に収録されています。これも今は品切れですが、何とか調べました。以下に歌詞と解説を引用します。
男は泣かず 作詩:野村俊夫 作曲:古賀政男 歌:荒 貞夫
コロムビア100110a 1940年10月20日発売
月は夜空を 照らしても
男ごゝろを 知るものか
泣いて泣かない ひとすじを
花よかなしく なぜ恨む
道は雲間に 続くとも
なんで行かずに いらりょか
男一途の この胸に
吹くな涙の 小夜嵐
男なくときぁ たゞ泣かぬ
伊達に誇りが 捨てらりょか
たとえ嵐が 寄せよとも
強く笑って 生きようよ
*以下は「古賀メロディ誕生70年記念 古賀政男大全集 解説本」からの引用です。
クラシックの勉強をしていて中年になって突然流行歌の世界にデビューした東海林太郎を思わせる中年の新人デビューである。当時の歌詞カードを見ると、まずトップに蝶ネクタイが板についたシブい中年男性のポートレート、その下に「新人紹介」が詳しく載っている。これが時代を想わせてなかなかおもしろい。(原文のまま)
「荒貞夫氏は福島県出身、大正六年四月渡米、ハリウッド・ビックス・アート・スタディに入り、勉学の傍らメトロポリタン座の名歌手メノッテ・フラスコナ氏に十数年師事し、在米邦人間に国粋歌手として知られる。昭和十五年春、帰朝と共に我社専属となり、茲に流行歌曲王古賀政男氏の名曲を以て、レコード界に華々しくデビューすることとなった」
何だかこの五年前、イタリアオペラの勉強の行き、帰ってきて演歌調「無情の夢」をうたった児玉好雄とイメージがオーバーラップするが、こちらの方は堂々と胸を張ってオーソドックスにうたう男性的なバリトンで、心に響いたのだが火がつかなかった。この古賀メロディ一曲だけで消えたが、レコードが出たのは太平洋戦争の始まる一年前の昭和十五年十月、あるいはアメリカ帰りが響いたのかも。この時代灰田勝彦などもハワイ生まれの二世ということが響いて戦争が終るまで針のむしろに座らされているような状態があったものである。
引用は以上です。荒は古賀メロディ1曲で消えた。古賀政男だけがあれだけ戦争に協力しながら、戦後、なぜ何事もなかったかのように作曲家として生きられたのか。それは下嶋さんの「謎の森に棲む古賀政男」を読むとわかりますが、日系2世の協力があったのですね。
それにしても、荒貞夫のことをもっと知りたい。ミリキタニさんにも来日した折に、荒貞夫のことを聞いてみたいですね。
古賀政男と日系人、そして荒貞夫。面白いテーマだと思います。
|
|
|
|
コメント(3)
うーむ。こういうエピソードは実に人間臭いですね。わたしたち日本人が掘りおこすべき事象であるとも思います。
灰田勝彦は、軍歌や軍国歌謡を何曲もレコーディングしていますが、内心は忸怩たる思いだったかもしれません。ただ、こういうのはこちらの勝手な類推であって、印象だけで判断するのは避けたいものです。勿論、軍歌を歌った歌手を批判などできませんしね。
しかし、自分を含め、日本のオトコどもは何故こういう「男気」とか「男泣き」とかいう歌詞を好むのか。(苦笑)収容所の頃、上原敏の股旅物歌謡曲が日系社会で大ヒットしたのは、移民者が博打打ちという渡世人に我が身を重ねたからだというソージ・カシワギの説明に説得力があったので、アジア系アメリカ文学研究会のジャーナルにはそう書きましたけど。
席亭はどう感じられますか?
追記:丹田は東洋医学のキモですね。
灰田勝彦は、軍歌や軍国歌謡を何曲もレコーディングしていますが、内心は忸怩たる思いだったかもしれません。ただ、こういうのはこちらの勝手な類推であって、印象だけで判断するのは避けたいものです。勿論、軍歌を歌った歌手を批判などできませんしね。
しかし、自分を含め、日本のオトコどもは何故こういう「男気」とか「男泣き」とかいう歌詞を好むのか。(苦笑)収容所の頃、上原敏の股旅物歌謡曲が日系社会で大ヒットしたのは、移民者が博打打ちという渡世人に我が身を重ねたからだというソージ・カシワギの説明に説得力があったので、アジア系アメリカ文学研究会のジャーナルにはそう書きましたけど。
席亭はどう感じられますか?
追記:丹田は東洋医学のキモですね。
ソージさんの説明は正しいと思います。そもそも、日本人は、寅さんが好きな国民ですから、ああいった生き方に憧れを抱くのでしょう。高倉健が人気があるのもああいった役柄だったからだと思います。落語家さんの中には、志ん生の生き方に憧れをいだいて入門する人がいますが、やはり志ん生のような破天荒な人生は、男の琴線に触れるのです。真剣師の小池重明にしてもそうですね。
あたしなんかも、落語家さんや、演劇人や映画人とつきあっているのは、単に落語、映画、芝居が好きだからでなく、彼らの持っている佇まいが好きだからです。一緒にいて心地いいのです。
男なくときぁ たゞ泣かぬ
伊達に誇りが 捨てらりょか
たとえ嵐が 寄せよとも
強く笑って 生きようよ
三力谷さんは、何十年もホームレスをしながら、ずっとこう心の中で口ずさんで生きてきたと思います。決してただで恵んでもらうことはしなかったらしいですから。
あたしなんかは落語にどっぷりはまっている人間ですから、男気なんて言われるとやはり弱いですね。浜野矩随、文七元結、中村仲蔵など、聞くたびに惚れます。
あたしなんかも、落語家さんや、演劇人や映画人とつきあっているのは、単に落語、映画、芝居が好きだからでなく、彼らの持っている佇まいが好きだからです。一緒にいて心地いいのです。
男なくときぁ たゞ泣かぬ
伊達に誇りが 捨てらりょか
たとえ嵐が 寄せよとも
強く笑って 生きようよ
三力谷さんは、何十年もホームレスをしながら、ずっとこう心の中で口ずさんで生きてきたと思います。決してただで恵んでもらうことはしなかったらしいですから。
あたしなんかは落語にどっぷりはまっている人間ですから、男気なんて言われるとやはり弱いですね。浜野矩随、文七元結、中村仲蔵など、聞くたびに惚れます。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
アジア系アメリカ人研究会 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-