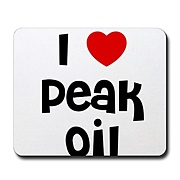[画像]中国国内における石油生産量と消費量。1993年に消費量が逆転し、輸入国となった。差が輸入量であり増加の一途をたどっている。ネット上にたくさん落ちていたので勝手に掲載。
日本で中国の問題と言えば、靖国問題等の歴史問題、反日教育・デモの問題、東シナ海ガス田開発等の領土問題、最近では北朝鮮との絡み等が注目されている。確かにそういった問題は重要である。しかし、私は中国の(広義の)石油戦略こそ、近い将来に最も重要な問題になるのではないかと懸念している。それは、誰が望んだわけでもなく時代の必然として起きるのではないか。
以下長くなるが、中国の石油戦略についてまとめてみたいと思う。
■発展する中国経済
近年の中国の経済は、虚構の部分や経済格差・環境問題・内紛等様々な問題を抱えてはいるものの、少なくともここ数年で急激な成長を遂げてきた事には間違いない。現在中国のGDPは、横ばい中の日本(4.7兆ドル)を越えて5兆ドルに達し、さらにあと5年で2倍に、25年で4倍になると言われている。※ちなみにアメリカのGDPは現在約10兆ドルで、5年後には15兆ドルになると推測されている。
特に、鉄鋼業やアルミなどエネルギー消費産業の成長が著しいため、経済成長がほぼエネルギー消費増加とリンクしている。しかも経済効率が悪く、GDPに対する石油の割合は日本の4倍、アメリカの2倍である。また、自家用車の急激な普及、石油化学工業の発達、電力需要の増加、従来の石炭基盤産業からのシフトに伴い石油そのものの需要も急速に増大している。しかも、天然ガスのインフラが殆ど整っていないため、余計に石油に頼らざるを得ない。石油消費を牽引している自動車の数は2383万台に達し(2003年)、年間販売台数は2003年に439万台、2010年には700万から900万台に達すると予測され、日本を抜いて世界第二位の車市場に成長する見込み。今後も引き続きエネルギー需要・石油消費量が増えていく事は明白である。
■減少に転じる国内生産
国内の石油生産はほぼ横ばいか微増状態であるが、既生産率は60%を過ぎており、2003年時点の可採年数は12.7年しかない。さらに主要油田の含水率は90%以上にもなっており、近い将来に生産量が減少に転じるのは必死である。
■高まる輸入依存率
急激な経済成長に石油生産は追いつかず、中国は1993年ついに石油輸入国に転じた。その後輸入依存率は上昇し、1998年に約20%、2004年度で約45%にも達した。※トピック頭の画像参照。
国家統計局や財政部などが2005年に作成した「中国生産力発展研究」によると、「石油の輸入依存度は絶対に50%を超えてはならない」としながらも、 2010年には54.4%、2020年には59.7%に達するとの悲観的な予測を行っている。
アメリカの軍事シンクタンクのランド社も、2020年には 60%に達するとの分析を行っている。中国地質学院の予測では、依存度は2020年に70%に及ぶ可能性を指摘している。
中国の石油関係者の間では、50%を超える輸入依存度は、国際石油市場の原油価格変動に対応して国内の石油価格を制御する手段を中国はもはや持てなくなることを意味し、そのことは「将来の自律的な政治・経済運営に影を落とすことになる」と危機感をもって認識されている。
■世界の石油生産量
世界の一日辺りの石油消費量は
6000万バレル(1977年)
↓18年
7000万バレル(1995年)
↓ 8年
8000万バレル(2003年)うち米2000万、中国700万バレル
↓
↓22年
↓
12000万バレル(2025年)? 米2900万、中国2800万バレル?
と、特に近年急速に増加している。2025年には少なくとも1億2000万バレルになると予想され、この増加分の殆どは中国でその次がアメリカやインドである。多くの経済専門家や石油業界関係者などの楽観派は、今後2030年までに約16兆ドル(日本の"GDP"の3.4倍!)の投資がなされれば一日1億バレルは可能であるとしている。しかし、地質学者の中には現在の技術では一日に1億バレル以上の生産は不可能との意見も多く、さらに、多くの見方に反して生産量はもっと早い時期に減少に転じる(ピークオイル論)との意見もある。
■高まる投資リスク
多くの楽観論者の論拠となる巨額な投資が行われる可能性は確かにある。しかし、今後石油開発の投資リスクはますます増大すると考えられ、これが一番の不確定要素である。主にあげられるリスクとしては、
▼1.採掘費用が高くつく油田(深海・北極・オイルサンド等)ばかり残っている為、利益率が悪い。
▼2.今後再び世界の石油依存率が高まるOPEC諸国の政治・経済情勢が不安定であること。
▼3.近年の価格高騰により石油価格のトレンドが予測不可能となったこと。
▼4.石油会社や産油国政府が公開する埋蔵量データの信憑性が怪しくなり、投資家の信頼を損っていること。
▼5.より多くの石油が海峡やパイプラインなどを通ることにリスクが増大すること。
が挙げられる。
■投資家心理に委ねられた未来
現在自由市場となった石油において、投資家心理は重要なファクターとなっている。実際、近年の価格高騰は主だった供給不安があったわけではない。単なるアメリカにおける石油精錬能力不足を端としたショックが世界の石油市場に順番に伝播したと考えられている。しかし、原因が取り除かれても価格が下がらなかったのは、投資家やオイルディーラーの先行き不安が影響しており、それだけリスクプレミアム(リスクの代償として投資家が期待する利益分)が高まったことになる。投資家心理が冷めればさらにリスクプレミアムが高まり、開発にはより多く利益が期待されるため、(上記のリスク等のため)さらに冷めてしまうという悪循環に陥る。巨大な資金を保有している投資家の多くは自身の生活は保障されており、よほど危険な賭けや慈善事業的な投資をする人間はごく一部である。結局今まで通りの"投資すれば必ず儲かる"案件でなくなってしまえば、石油はもはや魅力的な商品とはならず、投資家心理は別の対象にシフトしてしまうのではないか。実際、最近アメリカのメジャーは深海油田開発を相次いで断念しているし、欧米の有能な投資家や証券マン、ディーラーは、07年で仕事を辞め、貯金を携え南の島へ隠遁生活を始める人も多いとか。
手を出せるのは中国国営企業ぐらいか?
■需要が供給を越すとき
このように、不確定要素が多すぎて生産量予測が大変難しいためにいつ頃になるかは断言出来ないが、近い将来、中国とアメリカの経済成長に伴う石油消費を、世界の石油生産が現実的に賄えなく可能性がある。もしそうなった時、またはそうなる懸念が顕実化するだけでも、自国のプライドを賭けた二国間における石油争奪戦が激化する恐れがある。
■「資源パラノイア」と化した中国
CNN香港のウィリー・ラム氏は、中国のアグレッシブな資源確保ための行動、特に石油・ガス利権の確保のためには軍事力にも辞さないという態度は、「ある種の強迫観念からきている」と分析し、「資源パラノイア」という造語を使い始めた。
中国は現在、見境無い国家的な資源確保に乗り出している。アメリカと友好的なサウジアラビアやカナダ等からの輸入契約や資源開発に乗り出し、これから消費量の増加するアメリカの取り分を奪い取ろうとしている。また、スーダンやベネズエラ、イラン等、国連やアメリカと敵対している国々にも次々と乗り出し、兵器と引き換えにしたり、国際ルールやアメリカを無視した行動をとり続けている。2004年中国政府の息のかかったCNOOC(中国海洋石油公司)が、アメリカの大手天然ガス会社ウノカルを買収しようとする動きがあった。これらの行動は、アメリカ政府に対する宣戦布告とも言える。アメリカエネルギー省は2006年2月、「中国が世界中で行っている資源開発が、アメリカの安全保障上の脅威になる」との報告書を提出した。国防総省も、2006年2月3日にQDR(Quadrennial Defense Review)を発表し、中国を敵対する能力をもつ国とし、軍事的封じ込め戦略を展開している。
■輸送ルートの確保
中国は石油資源確保のほか、石油輸送ルートの安全確保という軍事色の濃厚な戦略も重視している。もしシーレーンを確保できず、万が一アメリカから妨害されれば、その経済活動は窒息してしまう。その為にも、南シナ海から台湾海峡、東シナ海、そして西太平洋における制海権の確保は至上命題となっている。そこで中国は周辺海域を、すでに「中国の海」と規定し、この海域を守るためにも西太平洋を制覇しようと海軍力増強に躍起となっている。その中国にとって台湾併合はどうしても成し遂げなければならない大目標となり、台湾を巡っていつかアメリカと対決する日に備えて、ロシアと協力してさらなる軍備拡大を続けている。
■米中戦争勃発?
中国の動きは、第二次大戦前の植民地獲得戦略の再現ともいえる。第二次大戦前、世界の国々は国家戦略の最も重要な部分として石油獲得を考え、全力を挙げて中東やアジアの石油資源を手に入れようとした。第二次大戦前と違っているのは、中国の国家戦略が「アメリカに対する挑戦」になっている点だ。
この様なことから、今は気がつかなくても、中国とアメリカは時間が経てば経つほど石油を巡った対立を必然的に深めてしまうことになる。急激な生産減が現実となった場合、両国とも自国の石油を確保するために軍事的なカードを使わざるを得ない。情勢が不安定な地域における紛争等を皮切りに(台湾・イラン・イスラエル・北朝鮮・アフリカetc.)、二国をとりまく陣営を巻き込んだ最終戦争が起きかねない。もちろん日本も巻き込まれるだろう。コリージョン・コース(当事者双方が自覚していない衝突必死のコース)である。それを避ける為には、中国かアメリカのどちらかが、政府判断として自国の経済成長を断念しなければならないが、世界一プライドが高く、資本主義経済を突き進む両国がそのような判断をすることは想像し難い。
確かに現在は、北朝鮮情勢を通じて米中間は急速に接近し、朝鮮半島非核化という共通の目的を持って友好関係を深めているようにも見える。しかし、これはむしろ中国にとって好都合で、世間の関心が北朝鮮に向いている間に、自国の石油戦略を自由に行うことが出来る。また、表面的にでもアメリカとの友好関係をアピールすることで、逆にアメリカ側が中国に対して強い態度で出づらくなっていることも同時に好都合である。アメリカにとっても、中国が本当にアメリカと敵対出来る力を持つ前までは、中東問題に力を注ぎたいはず。つまり現在の米中友好ムードは両国にとって好都合であり、だから日本人の多くは、将来の米中対立や米中戦争の懸念の話に現実感を持てないのだろう。北朝鮮に気をとられるように仕組まれている。将来的には、アメリカは何でもいいから世界を敵に回すに匹敵する行動を中国から引き出して(台湾併合問題・スーダン・北朝鮮絡みなど)、それを止めるという正義の口実によって、中国を潰して自国の利益を確保するというシナリオが最善で、2,3年後に必ずけしかける(人民元引き上げ要求・輸入関税・台湾独立への後押し等)だろう。
もちろん、そうなる前に別の大きな展開が待っている可能性もある。中国・アメリカ経済の崩壊等である。それはそれで悲劇的なのだが、そのような米中対立回避シナリオに関しては、また別のところで議論したいと思う。
---
以下、中国の石油戦略行動についての具体的な情報。
【中東における情勢】
▼アメリカは一日2000万バレルの石油を消費し、そのうち600万バレル以上は中東から輸入している。中国は一日700万バレルの消費量のうちの約70%、一日500万バレルを中東から輸入している。 中国経済がこのまま拡大していけば、2025年にはその5倍の2500万バレルを中東から輸入するようになるだろうと想定されている。
▼アメリカ政府の調べによると中国は、通常のビジネスとして中東から石油を買っているだけでなく、特にイランなどとは兵器や技術なども取引の材料にして石油を手に入れている。今中国がもっともたくさんの石油と天然ガスを輸入しているのはイランである。
[イラン]
▼ 中国はイランに対する原子力発電を中心に独自の核技術の輸出に力をいれている。CIAは中国がミサイルや核爆弾の技術も売っているのではないかと疑っている。中国とイランのビジネス上の取引高は年間120億ドルにも達している。イランは同様の取引をロシアとも行っている。
▼中国はイランとの間に石油パイプラインを設置し、一日600万バレルを超すイランの石油の大半を中国に直接運び込もうと考えている。イランは日本との関係が強く、中東では最も日本びいきの国といわれてきたが、イランの石油はもはや中国に支配されようとしている。
▼2004年、国連の安全保障理事会が現地視察を含めてイランの核開発に干渉しようとしたときに、中国はこれを妨害し、その代償としてイランと膨大な石油取引の契約を結んでいる。
▼2004年11月中国がイランとの天然ガスの購入契約を結んだ際、「もしアメリカがイランに対する経済措置を国連で提案したら我々は拒否権を行使する」との声明を敢えて出した。
▼中国政府が考えているのは、イランを軍事的に強くして湾岸地域における反米勢力の中心にすることである。中国のエネルギー政策がそのまま国防政策と強く関わっていることは明白である。
[サウジアラビア]
▼サウジアラビアは世界の石油埋蔵量の4分の1を持っていることで知られている。
▼2004年、中国はサウジアラビアと協定を結び、天然資源開発のための共同事業を開始した。ここで注目すべきは、サウジアラビアはアメリカ政府が同じような共同開発を持ちかけたのに対して色よい返事をしなかった。今のところアメリカとサウジアラビアの共同事業は成立していない。
▼石油業界の情報によれば、中国はサウジアラビアのサウジ・アラムコと共同でサウジアラビア国内に製油施設をつくることになった。この製油施設は中国が初めて外国に作るもので、サウジ・アラムコが25%出資することになっている。正式には2005年7月に両国間で調印が行われたといわれている。また、アメリカ政府の情報によれば、サウジ・アラムコは出資額を25%から30%に増やすという。
▼サウジアラビアの国立石油企業サウジ・アラムコは、実質的にはアメリカ資本そのものだとこれまでは言われてきたが、いつのまにか中国がこのサウジ・アラムコの株を20%取得してしまった。
▼中東におけるアメリカの聖域といわれたサウジアラビアは明らかにワシントンに距離を置くようになり、北京に近づき始めている。もっとも、最近はアメリカ側からもサウジと距離を置くようになりつつある。日本とサウジアラビアもきわめて良好な関係と言われてきたが、中国に接近するとともに、アジアにおける友好国の拠点を日本から中国に移しつつある。サウジアラビアが中国に接近した最大の理由は兵器の供給だといわれている。
▼サウジアラビアはイスラム急進派の拠点である。9・11の実行者達はほとんどがサウジアラビア人だった。新しくとうじょうしたアブドッラー国王が革新派であることから、王家とイスラム急進派の対立が急に激しくなり、破壊活動などが増えている。この状況に目をつけた中国が兵器の供給や安全保障上の協力を持ちかけ、両者が接近しているのである。このことは、中東全体の政治的な情勢を大きく変えることになりかねない。
【カナダと中南米】
▼これまで中南米はアメリカの裏庭といわれ、カナダもアメリカの勢力範囲で外国は介入できない場所であった。アメリカは中南米だけからで石油消費の60%以上を輸入している。また、カナダ・ベネズエラ・メキシコの3カ国からの輸入量の合計は一日500万バレルを越えており、OPEC各国からアメリカが輸入している量に匹敵し、全輸入量の約40%となる。(アメリカが一日あたり輸入をしている1278万5000バレルの石油のうち一番多いのはカナダからで195万バレル、サウジアラビアから162万バレル、ベネズエラから158 万バレル、メキシコから142万バレル、ナイジェリアから109万バレル。)
▼中国は中南米のあらゆる国々(政権が腐敗している国も含め)に資金を提供し、援助することによって石油を手にし始めている。アメリカはこれからも需要増傾向だが、中国が参入することでこれまでの安定した供給源を徐々に奪われることになる。そうなれば、アメリカははるか遠くの国々か、政治的に不安定な中南米のほかの国々、西アフリカ、カスピ海、中央アジアの国々とも石油輸入の交渉を行わざるを得ない。
▼アメリカにとって苦しいのは、中国が契約を結ぼうとしている中南米の国のいくつかは政治的にきわめて不安定で、腐敗していたり共産主義勢力が強かったりする国々だという事である。中国は依然として共産主義体制をとっており、非人道的な政治を続けているが、こうした中国のやり方が、中南米の専制国家になじみやすいとも言える。
[カナダ]
▼中国はカナダ政府と21世紀の石油開発について協力し合うという声明を発表している。石油、天然ガス、オイルサンドの開発、環境対策などについて共同事業を行う取り決めを行おうとしている。
▼ペトロチャイナ・インターナショナルは、カナダの巨大石油パイプライン企業エンブリッジと話し合いをはじめ、カナダのアルバータから太平洋沿岸まで、一日20万バレルの石油を運ぶプロジェクトを立ち上げている。
▼アメリカの調査機関IAGSの分析によると、中国とカナダの間で取り決められた一連の石油開発やパイプライン事業が実現するとカナダから一日あたりアメリカに輸出される195万1000バレルの3分の1が中国に奪われることになる。
[ベネズエラ]
▼中国は、内戦の続くベネズエラの国内情勢と、アメリカとの険悪な関係を知りながらベネズエラに進出している。
▼2005年、中国の石油会社がベネズエラ国内で油田を開発し製油施設を建設するという契約をチャペス大統領と結んだ。内容は、まず3億5000万ドルでベネズエラ東部の15の油田開発をすること。それに続いて6000万ドルで天然ガスの開発を行い、その上で一日12万バレルの石油を中国が輸入するというもの。
▼ベネズエラは太平洋岸に港を持っていないので、パナマ運河を使って中国に石油を輸出しようにも、パナマ運河は狭すぎて中国の巨大なタンカーが通れない。そこで中国とベネズエラ政府は2004年7月、ベネズエラからコロンビアの太平洋岸の港まで石油パイプを施設する契約をコロンビア政府と結んだ。
[キューバ・エクアドル・ペルー・ブラジル・アルゼンチン・メキシコ]
▼中国は、キューバのカストロ政権を援助することになった。中国石油化工集団公司(SINOPEC)がキューバと契約し、製油業に乗り出すことになった。
▼中国はエクアドルのエネルギー企業と契約を結び、一億ドルを投下して石油採掘を行うことになった。エクアドルの政府はベネズエラに劣らず腐敗しており、政治的な混乱が続いている。
▼中国は、民主主義勢力を弾圧しているペルー政府と覚書を交換し、石油・天然ガスの開発についての技術援助と資金の提供を申し出ている。
▼中国とブラジルは既に多くの契約を結んでいるが、近年100億ドル以上のエネルギー共同開発の契約にも調印した。
▼アルゼンチンは、今後十年間に、天然ガスや石油の開発を行うために中国と50億ドルの投資を行う契約を結んだ。
▼『ウォールストリート・ジャーナル』紙が2005年1月に伝えたところによれば、メキシコが石油の輸出先として中国を検討し始めている。
【西アフリカと中央アジア】
▼中国は西アフリカと中央アジアで、世界で最も腐敗し、最も専制的な国々と手を組み石油獲得戦略を推進している。中南米における非民主的な前近代的な国家よりも、さらに遅れた地域、近代社会と敵対する危険な国々とも手を組んでいる。このような中国の石油戦略は、アメリカと対立するだけではなく近代社会そのものに対する挑戦でもある。
▼中央アジアは天然ガスや地下資源が豊富で知られている。ウズベキスタンとカザフスタンはもともと親米派であったが、近年中国との天然ガス計画と共に親中路線に転向しつつある。
▼日本には「アフリカでは石油が採掘できない」と言う人々が多く、石油連盟の関係者も西アフリカを石油の産出地域とはみなしていない。こうした情報のなさが国際社会における日本の立場を苦しくしている。BP統計によれば、実際にはアフリカ全体で見ればいまや一日にあわせて900万バレルの石油が掘り出されている。900万バレルといえばサウジアラビアの産出量に匹敵する、無視できない量である。もっともアフリカの石油産出国は20カ国にもおよび、その量が非常に少ない国もある。
▼ナイジェリアは一日250万バレル、アルジェリア190万バレル、アンゴラ90万バレル、スーダン30万バレルを掘り出している。
▼こうしたアフリカの国々、特に石油を産出するアフリカの国々は世界で最も近代化が遅れており、人権無視の、民主主義のかけらもないようなところが多い。その中で最も程度が悪いといわれるスーダンとナイジェリアに対し、中国は石油目的丸出しで近づき、きわめて親しい関係となり、国際的に大変懸念されている。
[スーダン]
▼中国が輸入する石油量の7%がスーダンから来ている。中国はスーダンから石油を買うだけでなく、積極的に油田の開発に協力し、現在紅海に至る1400キロのパイプラインを建設している。中国はこの工事に投資しただけでなく、石油関係の労働者を装った数十万規模の人民解放軍を送り込み、油田開発とパイプラインの建設、警備に当たらせている。
▼スーダン政府は世界最悪の集団虐殺行為(1万人以上とも)を行っているとして世界中から非難されているが、中国は石油の見返りにスーダン政府に兵器を提供している。
▼2004年9月、国連の安全保障理事会はスーダン政府が凶悪な軍事政権を支援することをやめない場合には経済制裁を行うと決議したが、中国はこの決議「1564」に公然と違反している。こうなると、中国はアメリカの国益だけでなく、国際社会のルールともぶつかりあう。
▼2006年11月、中国・アフリカサミットが開催された。石油目的丸出しで凶悪なスーダン政府に近づく中国に、世界各国から批判が集中した。
[カザフスタンとウズベキスタン]
▼中国は中央アジアでも、民主主義と国際ルールを破って石油を獲得しようとしている。中央アジアのカザフスタンとウズベキスタンは石油資源だけではなく、あらゆる地下資源に恵まれており、天然ガスについては全世界の埋蔵量の半分近くがあるという説もある。中国はこの二つの国に特に強い関心を持ち、働きかけをはじめているが、かなりの成功を収めつつある。
▼カザフスタンとウズベキスタンはもともとイスラム過激派の標的になっている。アフガニスタンなどから侵入したアルカイダが政府転覆を計っているとも言われる。このため、カザフスタンとウズベキスタンはアメリカに協力し、テロリストとの戦いに加わってきた。またアメリカに天然ガスや石油を輸出する約束をしてきたが、そこに中国が介入してきた。中国はまずカザフスタンと戦略同盟協定を結び、カザフスタンとの間に石油と天然ガスのパイプラインをつくる構想を推し進めている。カザフスタンはアメリカと中国を天秤にかけることになった。
▼ウズベキスタンは、アフガニスタンに対する戦争の開始以来アメリカに協力的で、アメリカ軍の空軍基地を作らせることに同意した。だが2005年5月、ウズベキスタンのイスラム・カリモフ大統領は、民主政権と選挙を求めて立ち上がった民衆数百人をアンディジャンで虐殺した。アメリカをはじめ世界各国はカリモフ大統領を非難し、国際的な調査を要求した。ところが中国は直ちにカリモフ大統領を支持し、民衆虐殺をテロリストに対する戦いと規定し、国際的な調査に反対した。その中国政府の声明が発表された数日後、約6億ドルのエネルギー提供条約が、ウズベキスタンと中国の間で結ばれた。
▼上海でアジア各国による安全保障会議が行われた際にも、アジア諸国を煽動してアメリカをウズベキスタンの軍事基地から追い出す決議を行い、アメリカの影響力を縮小することに成功している。
【ロシア】
▼メンゲス博士の『中国・高まりつつある脅威』という本によると、中国は1000億ドルでロシアの極東地域の資源を買い取り、その資源から得た利益の20%をロシアに支払い、またロシアから3000億ドルの兵器を買い取るという交渉をしている、とある。
▼ロシアは、ナホトカパイプラインの経路を、中国経由にするかしないかを決めかねている。それは、今後中国と対立することになった場合でも、自由に日本やアメリカに輸出できるようにするためと言われている(事実確認中)。
※追記11/4
本来ならば、インドネシアを中心とした東南アジアにおける破格の買収劇や、ロシアやカスピ海油田とのパイプライン抗争など、他にも重要な事件は多数発生しているが、挙げればきりが無いので、特にアメリカとの絡みが重要であると思われる事柄に絞ったつもり。
参考にしたサイトや書籍は、今後主だったものに絞って、ここにリストアップする予定(参考書籍トピックのところには含まれています)。
11/9更新
日本で中国の問題と言えば、靖国問題等の歴史問題、反日教育・デモの問題、東シナ海ガス田開発等の領土問題、最近では北朝鮮との絡み等が注目されている。確かにそういった問題は重要である。しかし、私は中国の(広義の)石油戦略こそ、近い将来に最も重要な問題になるのではないかと懸念している。それは、誰が望んだわけでもなく時代の必然として起きるのではないか。
以下長くなるが、中国の石油戦略についてまとめてみたいと思う。
■発展する中国経済
近年の中国の経済は、虚構の部分や経済格差・環境問題・内紛等様々な問題を抱えてはいるものの、少なくともここ数年で急激な成長を遂げてきた事には間違いない。現在中国のGDPは、横ばい中の日本(4.7兆ドル)を越えて5兆ドルに達し、さらにあと5年で2倍に、25年で4倍になると言われている。※ちなみにアメリカのGDPは現在約10兆ドルで、5年後には15兆ドルになると推測されている。
特に、鉄鋼業やアルミなどエネルギー消費産業の成長が著しいため、経済成長がほぼエネルギー消費増加とリンクしている。しかも経済効率が悪く、GDPに対する石油の割合は日本の4倍、アメリカの2倍である。また、自家用車の急激な普及、石油化学工業の発達、電力需要の増加、従来の石炭基盤産業からのシフトに伴い石油そのものの需要も急速に増大している。しかも、天然ガスのインフラが殆ど整っていないため、余計に石油に頼らざるを得ない。石油消費を牽引している自動車の数は2383万台に達し(2003年)、年間販売台数は2003年に439万台、2010年には700万から900万台に達すると予測され、日本を抜いて世界第二位の車市場に成長する見込み。今後も引き続きエネルギー需要・石油消費量が増えていく事は明白である。
■減少に転じる国内生産
国内の石油生産はほぼ横ばいか微増状態であるが、既生産率は60%を過ぎており、2003年時点の可採年数は12.7年しかない。さらに主要油田の含水率は90%以上にもなっており、近い将来に生産量が減少に転じるのは必死である。
■高まる輸入依存率
急激な経済成長に石油生産は追いつかず、中国は1993年ついに石油輸入国に転じた。その後輸入依存率は上昇し、1998年に約20%、2004年度で約45%にも達した。※トピック頭の画像参照。
国家統計局や財政部などが2005年に作成した「中国生産力発展研究」によると、「石油の輸入依存度は絶対に50%を超えてはならない」としながらも、 2010年には54.4%、2020年には59.7%に達するとの悲観的な予測を行っている。
アメリカの軍事シンクタンクのランド社も、2020年には 60%に達するとの分析を行っている。中国地質学院の予測では、依存度は2020年に70%に及ぶ可能性を指摘している。
中国の石油関係者の間では、50%を超える輸入依存度は、国際石油市場の原油価格変動に対応して国内の石油価格を制御する手段を中国はもはや持てなくなることを意味し、そのことは「将来の自律的な政治・経済運営に影を落とすことになる」と危機感をもって認識されている。
■世界の石油生産量
世界の一日辺りの石油消費量は
6000万バレル(1977年)
↓18年
7000万バレル(1995年)
↓ 8年
8000万バレル(2003年)うち米2000万、中国700万バレル
↓
↓22年
↓
12000万バレル(2025年)? 米2900万、中国2800万バレル?
と、特に近年急速に増加している。2025年には少なくとも1億2000万バレルになると予想され、この増加分の殆どは中国でその次がアメリカやインドである。多くの経済専門家や石油業界関係者などの楽観派は、今後2030年までに約16兆ドル(日本の"GDP"の3.4倍!)の投資がなされれば一日1億バレルは可能であるとしている。しかし、地質学者の中には現在の技術では一日に1億バレル以上の生産は不可能との意見も多く、さらに、多くの見方に反して生産量はもっと早い時期に減少に転じる(ピークオイル論)との意見もある。
■高まる投資リスク
多くの楽観論者の論拠となる巨額な投資が行われる可能性は確かにある。しかし、今後石油開発の投資リスクはますます増大すると考えられ、これが一番の不確定要素である。主にあげられるリスクとしては、
▼1.採掘費用が高くつく油田(深海・北極・オイルサンド等)ばかり残っている為、利益率が悪い。
▼2.今後再び世界の石油依存率が高まるOPEC諸国の政治・経済情勢が不安定であること。
▼3.近年の価格高騰により石油価格のトレンドが予測不可能となったこと。
▼4.石油会社や産油国政府が公開する埋蔵量データの信憑性が怪しくなり、投資家の信頼を損っていること。
▼5.より多くの石油が海峡やパイプラインなどを通ることにリスクが増大すること。
が挙げられる。
■投資家心理に委ねられた未来
現在自由市場となった石油において、投資家心理は重要なファクターとなっている。実際、近年の価格高騰は主だった供給不安があったわけではない。単なるアメリカにおける石油精錬能力不足を端としたショックが世界の石油市場に順番に伝播したと考えられている。しかし、原因が取り除かれても価格が下がらなかったのは、投資家やオイルディーラーの先行き不安が影響しており、それだけリスクプレミアム(リスクの代償として投資家が期待する利益分)が高まったことになる。投資家心理が冷めればさらにリスクプレミアムが高まり、開発にはより多く利益が期待されるため、(上記のリスク等のため)さらに冷めてしまうという悪循環に陥る。巨大な資金を保有している投資家の多くは自身の生活は保障されており、よほど危険な賭けや慈善事業的な投資をする人間はごく一部である。結局今まで通りの"投資すれば必ず儲かる"案件でなくなってしまえば、石油はもはや魅力的な商品とはならず、投資家心理は別の対象にシフトしてしまうのではないか。実際、最近アメリカのメジャーは深海油田開発を相次いで断念しているし、欧米の有能な投資家や証券マン、ディーラーは、07年で仕事を辞め、貯金を携え南の島へ隠遁生活を始める人も多いとか。
手を出せるのは中国国営企業ぐらいか?
■需要が供給を越すとき
このように、不確定要素が多すぎて生産量予測が大変難しいためにいつ頃になるかは断言出来ないが、近い将来、中国とアメリカの経済成長に伴う石油消費を、世界の石油生産が現実的に賄えなく可能性がある。もしそうなった時、またはそうなる懸念が顕実化するだけでも、自国のプライドを賭けた二国間における石油争奪戦が激化する恐れがある。
■「資源パラノイア」と化した中国
CNN香港のウィリー・ラム氏は、中国のアグレッシブな資源確保ための行動、特に石油・ガス利権の確保のためには軍事力にも辞さないという態度は、「ある種の強迫観念からきている」と分析し、「資源パラノイア」という造語を使い始めた。
中国は現在、見境無い国家的な資源確保に乗り出している。アメリカと友好的なサウジアラビアやカナダ等からの輸入契約や資源開発に乗り出し、これから消費量の増加するアメリカの取り分を奪い取ろうとしている。また、スーダンやベネズエラ、イラン等、国連やアメリカと敵対している国々にも次々と乗り出し、兵器と引き換えにしたり、国際ルールやアメリカを無視した行動をとり続けている。2004年中国政府の息のかかったCNOOC(中国海洋石油公司)が、アメリカの大手天然ガス会社ウノカルを買収しようとする動きがあった。これらの行動は、アメリカ政府に対する宣戦布告とも言える。アメリカエネルギー省は2006年2月、「中国が世界中で行っている資源開発が、アメリカの安全保障上の脅威になる」との報告書を提出した。国防総省も、2006年2月3日にQDR(Quadrennial Defense Review)を発表し、中国を敵対する能力をもつ国とし、軍事的封じ込め戦略を展開している。
■輸送ルートの確保
中国は石油資源確保のほか、石油輸送ルートの安全確保という軍事色の濃厚な戦略も重視している。もしシーレーンを確保できず、万が一アメリカから妨害されれば、その経済活動は窒息してしまう。その為にも、南シナ海から台湾海峡、東シナ海、そして西太平洋における制海権の確保は至上命題となっている。そこで中国は周辺海域を、すでに「中国の海」と規定し、この海域を守るためにも西太平洋を制覇しようと海軍力増強に躍起となっている。その中国にとって台湾併合はどうしても成し遂げなければならない大目標となり、台湾を巡っていつかアメリカと対決する日に備えて、ロシアと協力してさらなる軍備拡大を続けている。
■米中戦争勃発?
中国の動きは、第二次大戦前の植民地獲得戦略の再現ともいえる。第二次大戦前、世界の国々は国家戦略の最も重要な部分として石油獲得を考え、全力を挙げて中東やアジアの石油資源を手に入れようとした。第二次大戦前と違っているのは、中国の国家戦略が「アメリカに対する挑戦」になっている点だ。
この様なことから、今は気がつかなくても、中国とアメリカは時間が経てば経つほど石油を巡った対立を必然的に深めてしまうことになる。急激な生産減が現実となった場合、両国とも自国の石油を確保するために軍事的なカードを使わざるを得ない。情勢が不安定な地域における紛争等を皮切りに(台湾・イラン・イスラエル・北朝鮮・アフリカetc.)、二国をとりまく陣営を巻き込んだ最終戦争が起きかねない。もちろん日本も巻き込まれるだろう。コリージョン・コース(当事者双方が自覚していない衝突必死のコース)である。それを避ける為には、中国かアメリカのどちらかが、政府判断として自国の経済成長を断念しなければならないが、世界一プライドが高く、資本主義経済を突き進む両国がそのような判断をすることは想像し難い。
確かに現在は、北朝鮮情勢を通じて米中間は急速に接近し、朝鮮半島非核化という共通の目的を持って友好関係を深めているようにも見える。しかし、これはむしろ中国にとって好都合で、世間の関心が北朝鮮に向いている間に、自国の石油戦略を自由に行うことが出来る。また、表面的にでもアメリカとの友好関係をアピールすることで、逆にアメリカ側が中国に対して強い態度で出づらくなっていることも同時に好都合である。アメリカにとっても、中国が本当にアメリカと敵対出来る力を持つ前までは、中東問題に力を注ぎたいはず。つまり現在の米中友好ムードは両国にとって好都合であり、だから日本人の多くは、将来の米中対立や米中戦争の懸念の話に現実感を持てないのだろう。北朝鮮に気をとられるように仕組まれている。将来的には、アメリカは何でもいいから世界を敵に回すに匹敵する行動を中国から引き出して(台湾併合問題・スーダン・北朝鮮絡みなど)、それを止めるという正義の口実によって、中国を潰して自国の利益を確保するというシナリオが最善で、2,3年後に必ずけしかける(人民元引き上げ要求・輸入関税・台湾独立への後押し等)だろう。
もちろん、そうなる前に別の大きな展開が待っている可能性もある。中国・アメリカ経済の崩壊等である。それはそれで悲劇的なのだが、そのような米中対立回避シナリオに関しては、また別のところで議論したいと思う。
---
以下、中国の石油戦略行動についての具体的な情報。
【中東における情勢】
▼アメリカは一日2000万バレルの石油を消費し、そのうち600万バレル以上は中東から輸入している。中国は一日700万バレルの消費量のうちの約70%、一日500万バレルを中東から輸入している。 中国経済がこのまま拡大していけば、2025年にはその5倍の2500万バレルを中東から輸入するようになるだろうと想定されている。
▼アメリカ政府の調べによると中国は、通常のビジネスとして中東から石油を買っているだけでなく、特にイランなどとは兵器や技術なども取引の材料にして石油を手に入れている。今中国がもっともたくさんの石油と天然ガスを輸入しているのはイランである。
[イラン]
▼ 中国はイランに対する原子力発電を中心に独自の核技術の輸出に力をいれている。CIAは中国がミサイルや核爆弾の技術も売っているのではないかと疑っている。中国とイランのビジネス上の取引高は年間120億ドルにも達している。イランは同様の取引をロシアとも行っている。
▼中国はイランとの間に石油パイプラインを設置し、一日600万バレルを超すイランの石油の大半を中国に直接運び込もうと考えている。イランは日本との関係が強く、中東では最も日本びいきの国といわれてきたが、イランの石油はもはや中国に支配されようとしている。
▼2004年、国連の安全保障理事会が現地視察を含めてイランの核開発に干渉しようとしたときに、中国はこれを妨害し、その代償としてイランと膨大な石油取引の契約を結んでいる。
▼2004年11月中国がイランとの天然ガスの購入契約を結んだ際、「もしアメリカがイランに対する経済措置を国連で提案したら我々は拒否権を行使する」との声明を敢えて出した。
▼中国政府が考えているのは、イランを軍事的に強くして湾岸地域における反米勢力の中心にすることである。中国のエネルギー政策がそのまま国防政策と強く関わっていることは明白である。
[サウジアラビア]
▼サウジアラビアは世界の石油埋蔵量の4分の1を持っていることで知られている。
▼2004年、中国はサウジアラビアと協定を結び、天然資源開発のための共同事業を開始した。ここで注目すべきは、サウジアラビアはアメリカ政府が同じような共同開発を持ちかけたのに対して色よい返事をしなかった。今のところアメリカとサウジアラビアの共同事業は成立していない。
▼石油業界の情報によれば、中国はサウジアラビアのサウジ・アラムコと共同でサウジアラビア国内に製油施設をつくることになった。この製油施設は中国が初めて外国に作るもので、サウジ・アラムコが25%出資することになっている。正式には2005年7月に両国間で調印が行われたといわれている。また、アメリカ政府の情報によれば、サウジ・アラムコは出資額を25%から30%に増やすという。
▼サウジアラビアの国立石油企業サウジ・アラムコは、実質的にはアメリカ資本そのものだとこれまでは言われてきたが、いつのまにか中国がこのサウジ・アラムコの株を20%取得してしまった。
▼中東におけるアメリカの聖域といわれたサウジアラビアは明らかにワシントンに距離を置くようになり、北京に近づき始めている。もっとも、最近はアメリカ側からもサウジと距離を置くようになりつつある。日本とサウジアラビアもきわめて良好な関係と言われてきたが、中国に接近するとともに、アジアにおける友好国の拠点を日本から中国に移しつつある。サウジアラビアが中国に接近した最大の理由は兵器の供給だといわれている。
▼サウジアラビアはイスラム急進派の拠点である。9・11の実行者達はほとんどがサウジアラビア人だった。新しくとうじょうしたアブドッラー国王が革新派であることから、王家とイスラム急進派の対立が急に激しくなり、破壊活動などが増えている。この状況に目をつけた中国が兵器の供給や安全保障上の協力を持ちかけ、両者が接近しているのである。このことは、中東全体の政治的な情勢を大きく変えることになりかねない。
【カナダと中南米】
▼これまで中南米はアメリカの裏庭といわれ、カナダもアメリカの勢力範囲で外国は介入できない場所であった。アメリカは中南米だけからで石油消費の60%以上を輸入している。また、カナダ・ベネズエラ・メキシコの3カ国からの輸入量の合計は一日500万バレルを越えており、OPEC各国からアメリカが輸入している量に匹敵し、全輸入量の約40%となる。(アメリカが一日あたり輸入をしている1278万5000バレルの石油のうち一番多いのはカナダからで195万バレル、サウジアラビアから162万バレル、ベネズエラから158 万バレル、メキシコから142万バレル、ナイジェリアから109万バレル。)
▼中国は中南米のあらゆる国々(政権が腐敗している国も含め)に資金を提供し、援助することによって石油を手にし始めている。アメリカはこれからも需要増傾向だが、中国が参入することでこれまでの安定した供給源を徐々に奪われることになる。そうなれば、アメリカははるか遠くの国々か、政治的に不安定な中南米のほかの国々、西アフリカ、カスピ海、中央アジアの国々とも石油輸入の交渉を行わざるを得ない。
▼アメリカにとって苦しいのは、中国が契約を結ぼうとしている中南米の国のいくつかは政治的にきわめて不安定で、腐敗していたり共産主義勢力が強かったりする国々だという事である。中国は依然として共産主義体制をとっており、非人道的な政治を続けているが、こうした中国のやり方が、中南米の専制国家になじみやすいとも言える。
[カナダ]
▼中国はカナダ政府と21世紀の石油開発について協力し合うという声明を発表している。石油、天然ガス、オイルサンドの開発、環境対策などについて共同事業を行う取り決めを行おうとしている。
▼ペトロチャイナ・インターナショナルは、カナダの巨大石油パイプライン企業エンブリッジと話し合いをはじめ、カナダのアルバータから太平洋沿岸まで、一日20万バレルの石油を運ぶプロジェクトを立ち上げている。
▼アメリカの調査機関IAGSの分析によると、中国とカナダの間で取り決められた一連の石油開発やパイプライン事業が実現するとカナダから一日あたりアメリカに輸出される195万1000バレルの3分の1が中国に奪われることになる。
[ベネズエラ]
▼中国は、内戦の続くベネズエラの国内情勢と、アメリカとの険悪な関係を知りながらベネズエラに進出している。
▼2005年、中国の石油会社がベネズエラ国内で油田を開発し製油施設を建設するという契約をチャペス大統領と結んだ。内容は、まず3億5000万ドルでベネズエラ東部の15の油田開発をすること。それに続いて6000万ドルで天然ガスの開発を行い、その上で一日12万バレルの石油を中国が輸入するというもの。
▼ベネズエラは太平洋岸に港を持っていないので、パナマ運河を使って中国に石油を輸出しようにも、パナマ運河は狭すぎて中国の巨大なタンカーが通れない。そこで中国とベネズエラ政府は2004年7月、ベネズエラからコロンビアの太平洋岸の港まで石油パイプを施設する契約をコロンビア政府と結んだ。
[キューバ・エクアドル・ペルー・ブラジル・アルゼンチン・メキシコ]
▼中国は、キューバのカストロ政権を援助することになった。中国石油化工集団公司(SINOPEC)がキューバと契約し、製油業に乗り出すことになった。
▼中国はエクアドルのエネルギー企業と契約を結び、一億ドルを投下して石油採掘を行うことになった。エクアドルの政府はベネズエラに劣らず腐敗しており、政治的な混乱が続いている。
▼中国は、民主主義勢力を弾圧しているペルー政府と覚書を交換し、石油・天然ガスの開発についての技術援助と資金の提供を申し出ている。
▼中国とブラジルは既に多くの契約を結んでいるが、近年100億ドル以上のエネルギー共同開発の契約にも調印した。
▼アルゼンチンは、今後十年間に、天然ガスや石油の開発を行うために中国と50億ドルの投資を行う契約を結んだ。
▼『ウォールストリート・ジャーナル』紙が2005年1月に伝えたところによれば、メキシコが石油の輸出先として中国を検討し始めている。
【西アフリカと中央アジア】
▼中国は西アフリカと中央アジアで、世界で最も腐敗し、最も専制的な国々と手を組み石油獲得戦略を推進している。中南米における非民主的な前近代的な国家よりも、さらに遅れた地域、近代社会と敵対する危険な国々とも手を組んでいる。このような中国の石油戦略は、アメリカと対立するだけではなく近代社会そのものに対する挑戦でもある。
▼中央アジアは天然ガスや地下資源が豊富で知られている。ウズベキスタンとカザフスタンはもともと親米派であったが、近年中国との天然ガス計画と共に親中路線に転向しつつある。
▼日本には「アフリカでは石油が採掘できない」と言う人々が多く、石油連盟の関係者も西アフリカを石油の産出地域とはみなしていない。こうした情報のなさが国際社会における日本の立場を苦しくしている。BP統計によれば、実際にはアフリカ全体で見ればいまや一日にあわせて900万バレルの石油が掘り出されている。900万バレルといえばサウジアラビアの産出量に匹敵する、無視できない量である。もっともアフリカの石油産出国は20カ国にもおよび、その量が非常に少ない国もある。
▼ナイジェリアは一日250万バレル、アルジェリア190万バレル、アンゴラ90万バレル、スーダン30万バレルを掘り出している。
▼こうしたアフリカの国々、特に石油を産出するアフリカの国々は世界で最も近代化が遅れており、人権無視の、民主主義のかけらもないようなところが多い。その中で最も程度が悪いといわれるスーダンとナイジェリアに対し、中国は石油目的丸出しで近づき、きわめて親しい関係となり、国際的に大変懸念されている。
[スーダン]
▼中国が輸入する石油量の7%がスーダンから来ている。中国はスーダンから石油を買うだけでなく、積極的に油田の開発に協力し、現在紅海に至る1400キロのパイプラインを建設している。中国はこの工事に投資しただけでなく、石油関係の労働者を装った数十万規模の人民解放軍を送り込み、油田開発とパイプラインの建設、警備に当たらせている。
▼スーダン政府は世界最悪の集団虐殺行為(1万人以上とも)を行っているとして世界中から非難されているが、中国は石油の見返りにスーダン政府に兵器を提供している。
▼2004年9月、国連の安全保障理事会はスーダン政府が凶悪な軍事政権を支援することをやめない場合には経済制裁を行うと決議したが、中国はこの決議「1564」に公然と違反している。こうなると、中国はアメリカの国益だけでなく、国際社会のルールともぶつかりあう。
▼2006年11月、中国・アフリカサミットが開催された。石油目的丸出しで凶悪なスーダン政府に近づく中国に、世界各国から批判が集中した。
[カザフスタンとウズベキスタン]
▼中国は中央アジアでも、民主主義と国際ルールを破って石油を獲得しようとしている。中央アジアのカザフスタンとウズベキスタンは石油資源だけではなく、あらゆる地下資源に恵まれており、天然ガスについては全世界の埋蔵量の半分近くがあるという説もある。中国はこの二つの国に特に強い関心を持ち、働きかけをはじめているが、かなりの成功を収めつつある。
▼カザフスタンとウズベキスタンはもともとイスラム過激派の標的になっている。アフガニスタンなどから侵入したアルカイダが政府転覆を計っているとも言われる。このため、カザフスタンとウズベキスタンはアメリカに協力し、テロリストとの戦いに加わってきた。またアメリカに天然ガスや石油を輸出する約束をしてきたが、そこに中国が介入してきた。中国はまずカザフスタンと戦略同盟協定を結び、カザフスタンとの間に石油と天然ガスのパイプラインをつくる構想を推し進めている。カザフスタンはアメリカと中国を天秤にかけることになった。
▼ウズベキスタンは、アフガニスタンに対する戦争の開始以来アメリカに協力的で、アメリカ軍の空軍基地を作らせることに同意した。だが2005年5月、ウズベキスタンのイスラム・カリモフ大統領は、民主政権と選挙を求めて立ち上がった民衆数百人をアンディジャンで虐殺した。アメリカをはじめ世界各国はカリモフ大統領を非難し、国際的な調査を要求した。ところが中国は直ちにカリモフ大統領を支持し、民衆虐殺をテロリストに対する戦いと規定し、国際的な調査に反対した。その中国政府の声明が発表された数日後、約6億ドルのエネルギー提供条約が、ウズベキスタンと中国の間で結ばれた。
▼上海でアジア各国による安全保障会議が行われた際にも、アジア諸国を煽動してアメリカをウズベキスタンの軍事基地から追い出す決議を行い、アメリカの影響力を縮小することに成功している。
【ロシア】
▼メンゲス博士の『中国・高まりつつある脅威』という本によると、中国は1000億ドルでロシアの極東地域の資源を買い取り、その資源から得た利益の20%をロシアに支払い、またロシアから3000億ドルの兵器を買い取るという交渉をしている、とある。
▼ロシアは、ナホトカパイプラインの経路を、中国経由にするかしないかを決めかねている。それは、今後中国と対立することになった場合でも、自由に日本やアメリカに輸出できるようにするためと言われている(事実確認中)。
※追記11/4
本来ならば、インドネシアを中心とした東南アジアにおける破格の買収劇や、ロシアやカスピ海油田とのパイプライン抗争など、他にも重要な事件は多数発生しているが、挙げればきりが無いので、特にアメリカとの絡みが重要であると思われる事柄に絞ったつもり。
参考にしたサイトや書籍は、今後主だったものに絞って、ここにリストアップする予定(参考書籍トピックのところには含まれています)。
11/9更新
|
|
|
|
コメント(133)
中国、今年も海外からの石油輸入拡大へ
発信時間: 2010-01-18 | チャイナネット
国家エネルギー局の張国宝局長は先に開かれた「全国エネルギー業務会議」で、エネルギー構造の調整とエネルギー供給の保障強化を今年のエネルギー事業の重点に置き、非化石燃料の一次エネルギー消費に占める割合を前年比0.5%増に引き上げる考えを示した。エネルギーの安全確保に向け、国は海外のエネルギー資源の利用を拡大する方針だ。
張局長は、成長方式の停滞と緊急保障力の脆弱さが中国のエネルギーの発展を制約する長期的なボトルネックになりつつあるとし、今年の主要目標として、▽第一に、一次エネルギー生産量は標準石炭にして前年比3.6%増の28億5000万トン▽非化石燃料の一次エネルギー消費に占める割合を前年比0.5%増---にすることをかかげた。
中国は今年、2国間や多国間によるエネルギー協力メカニズムを利用して、エネルギーの安全や気候変動、技術資金などの問題をめぐって主要エネルギー生産国や消費国との政策対話や交流を強化していき、エネルギー資源国との実務的協力を検討し、協力分野や範囲を一層拡大していく方針だ。
国家発展改革委員会の張暁強副主任は17日、同委員会の初期統計に基づき、限度額以上の非金融項目で中国側が昨年協議した対外投資額は490億ドルにおよび、投資の重点分野はエネルギーや資源製造業で、中国側の協議投資額の約83%も占めたことを明らかにした。
また昨年は、中国のエネルギー資源の輸入量が大幅に増加し、なかでも鉄鋼砂の輸入が前年比42%増の6.3億トン、原油の輸入が前年比1%増の約2.04トンに増え、国内の石油消費の輸入依存率は52%に達した。中国のエネルギー消費は今後数年は増加していくほか、中国企業の対外投資は資源やエネルギー、ハイテク、先進製造業などの分野に依然として重点が置かれる見通しだ。
「人民網日本語版」2010年1月18日
http://japanese.china.org.cn/business/txt/2010-01/18/content_19262344.htm
発信時間: 2010-01-18 | チャイナネット
国家エネルギー局の張国宝局長は先に開かれた「全国エネルギー業務会議」で、エネルギー構造の調整とエネルギー供給の保障強化を今年のエネルギー事業の重点に置き、非化石燃料の一次エネルギー消費に占める割合を前年比0.5%増に引き上げる考えを示した。エネルギーの安全確保に向け、国は海外のエネルギー資源の利用を拡大する方針だ。
張局長は、成長方式の停滞と緊急保障力の脆弱さが中国のエネルギーの発展を制約する長期的なボトルネックになりつつあるとし、今年の主要目標として、▽第一に、一次エネルギー生産量は標準石炭にして前年比3.6%増の28億5000万トン▽非化石燃料の一次エネルギー消費に占める割合を前年比0.5%増---にすることをかかげた。
中国は今年、2国間や多国間によるエネルギー協力メカニズムを利用して、エネルギーの安全や気候変動、技術資金などの問題をめぐって主要エネルギー生産国や消費国との政策対話や交流を強化していき、エネルギー資源国との実務的協力を検討し、協力分野や範囲を一層拡大していく方針だ。
国家発展改革委員会の張暁強副主任は17日、同委員会の初期統計に基づき、限度額以上の非金融項目で中国側が昨年協議した対外投資額は490億ドルにおよび、投資の重点分野はエネルギーや資源製造業で、中国側の協議投資額の約83%も占めたことを明らかにした。
また昨年は、中国のエネルギー資源の輸入量が大幅に増加し、なかでも鉄鋼砂の輸入が前年比42%増の6.3億トン、原油の輸入が前年比1%増の約2.04トンに増え、国内の石油消費の輸入依存率は52%に達した。中国のエネルギー消費は今後数年は増加していくほか、中国企業の対外投資は資源やエネルギー、ハイテク、先進製造業などの分野に依然として重点が置かれる見通しだ。
「人民網日本語版」2010年1月18日
http://japanese.china.org.cn/business/txt/2010-01/18/content_19262344.htm
中国石油の市場価値、世界一に
発信時間: 2010-01-08 | チャイナネット
金融危機以降、世界の上場企業の市場価値が激変し、中国の大手企業が頭角を現し始めた。
工商銀行が7日発表したデータによると、昨年末の時点で中国石油は3531億7400万ドルで市場価値が世界最大の企業となり、工商銀行は2689億8200万ドルと世界第4位に順位を上げた。
昨年末の市場価値ランキングによると、トップ5の上場企業は順に中国石油、米総合エネルギー会社のエクソンモービル(3237億1700万ドル)、マイクロソフト(2706億3600万ドル)、工商銀行、ウォルマート(2036億5400万ドル)。
また、世界トップ10の銀行は順に工商銀行、中国建設銀行(2014億5500万ドル)、英HSBC(2007億2500万ドル)、米JPモルガン・チェース(1710億5300万ドル)、中国銀行(1539億7200万ドル)、バンク・オブ・アメリカ(1496億4800万ドル)、米ウェルズ・ファーゴ(1379億9500万ドル)、スペインのBSCH(1360億200万ドル)、仏BNPパリバ(948億9300万ドル)、米シティバンク(935億4300万ドル)だった。
昨年末の工商銀行A株の終値は5.44元、H株の終値は6.44香港ドルで、08年末よりもそれぞれ54%と58%上がった。
「人民網日本語版」2010年1月8日
http://japanese.china.org.cn/business/txt/2010-01/08/content_19205591.htm
発信時間: 2010-01-08 | チャイナネット
金融危機以降、世界の上場企業の市場価値が激変し、中国の大手企業が頭角を現し始めた。
工商銀行が7日発表したデータによると、昨年末の時点で中国石油は3531億7400万ドルで市場価値が世界最大の企業となり、工商銀行は2689億8200万ドルと世界第4位に順位を上げた。
昨年末の市場価値ランキングによると、トップ5の上場企業は順に中国石油、米総合エネルギー会社のエクソンモービル(3237億1700万ドル)、マイクロソフト(2706億3600万ドル)、工商銀行、ウォルマート(2036億5400万ドル)。
また、世界トップ10の銀行は順に工商銀行、中国建設銀行(2014億5500万ドル)、英HSBC(2007億2500万ドル)、米JPモルガン・チェース(1710億5300万ドル)、中国銀行(1539億7200万ドル)、バンク・オブ・アメリカ(1496億4800万ドル)、米ウェルズ・ファーゴ(1379億9500万ドル)、スペインのBSCH(1360億200万ドル)、仏BNPパリバ(948億9300万ドル)、米シティバンク(935億4300万ドル)だった。
昨年末の工商銀行A株の終値は5.44元、H株の終値は6.44香港ドルで、08年末よりもそれぞれ54%と58%上がった。
「人民網日本語版」2010年1月8日
http://japanese.china.org.cn/business/txt/2010-01/08/content_19205591.htm
日本の「バブルの悲劇」が中国で再発することはない(上)
発信時間: 2010-01-19 | チャイナネット
最新の英エコノミスト誌には、中国経済の現状を分析し、今後を予測する評論が掲載された。主な内容は次の通り。
有力な貨幣政策と巨額な経済刺激策のサポートで、中国は他の国よりすばやく不況から回復し、2009年第4半期の経済成長率は10%以上だった。しかし多くの経済学者は、中国経済の将来に対して疑っている。それは中国の経済回復の基礎は安定しておらず、80年代のバブル崩壊前の日本と似ているか、それよりもっと危険だと考えているからだ。西側諸国の経済情勢がまだ安定していないという状況で中国のバブルが弾ければ、中国自身に危害が及ぶだけでなく、世界中に連鎖反応を引き起こすことは間違いない。
国民の高い貯金率や、貨幣の為替レートを引き下げるために対外貿易を後押しする政府のやり方などは、表面的には確かに今の中国は当時の日本とよく似ている。また80年代末に国際社会は、日本が米国に代わって世界一の経済大国となると信じていたが、これも現在の中国に対する学者たちの予測と似ている。こうした中で盛んに議論されているのが、近いうちに中国経済のバブルが弾けるという悲観論だ。その代表的な人物が投資家のジェームズ・チャノス氏である。
中国経済の今後を悲観するのには3つの理由がある。それは高すぎる資産評価と投資過剰、高額な貸付だ。しかしこの3つの面を詳細に研究すると、実際の中国の情況は非常に楽観的だ。
資本市場の現状は楽観的
資本市場を証券市場で見ると、現在の株価収益率は28で、中国証券市場のかつての長期平均値を下回っている。しかしバブル崩壊前の日本は70近くに達していた。
もちろん中国の不動産市場が過熱している兆しもあるが、全国の住宅の平均伸び率を見ると、中国の不動産市場がバブル期に入ったとはまだ言えない。中国の住宅価格の伸び率と1人当たりの年間収入の平均伸び率の割合が、西側諸国よりずっと高いのは事実だ。しかし住宅を持っており年間収入がほとんど変わらない農民数が多いという中国の特殊な事情から、簡単にその割合を西側諸国と比べることができない。
その他にも中国の各世帯のローン額は、80年代中期の日本より低く、可処分収入の35%に過ぎない。不動産業の繁栄はローンではなく主に貯金が支えているため、全体的には不動産業は健全に発展している。
中国ではまだ巨額なローンにより不動産業にバブルの危機をもたらしたことはないが、北京や上海などの大都市の住宅価格は高すぎて一般市民は購入できないと状況は、社会の大きな問題になっている。これに対して中国政府側は、政府の提供する中低所得者向け低価格の「経済適用住宅」を増やし、急速に値上がりしている住宅価格を抑制するなど、関連の新政策を打ち出している。
「生産過剰」とは誇張した言い方
2009年の中国の固定資産投資総額は国内総生産(GDP)の47%を占めた。これは20年前の日本を10ポイントを上回り、西側諸国の平均率20%よりもはるかに高い。しかし固定資産への投資率が高すぎることから、中国での生産が過剰になると判断することはできない。
それは中国人1人あたりの資本保有率が、米国や日本の5%に過ぎないからだ。鉄鋼やセメントなど一部の工業分野では、確かに生産過剰という問題を抱えているが、全体的に見て中国が生産過剰だという言い方は誇張している。
鉄鋼業を例として挙げると、中国で鉄鋼の生産が明らかに過剰を迎えたのは、世界の不況による建築材料のニーズの減少と深い関わりがある。現在、中国鉄鋼業の一人当たりの生産率が米国を上回っているのは、中米の経済が違った発展段階にあるからで、米国経済が急騰した1920年代の米国の数字は今の中国よりもっと高かった。
中国の一部の工業生産高が昨年に大幅に増えた原因は、国がインフラ整備に投資したためだ。中国政府の経済刺激策の一部の投資は確かに無駄になったかもしれないが、全体的に見ればこの資金は主に鉄道や道路、電気輸送網などの建設に投入された。これは長期的に見ると中国の将来の持続可能な経済成長にプラスである。
中国のインフラはすでに完備しており、これ以上投資を続けるのは無駄だと一部の経済学者は考えているようだが、これは客観的な見方ではない。中国は広く人口が多い。また地形は複雑で、多くの貧困な農村地域でのインフラ整備はまだ整っていない。
「チャイナネット」 2010年1月19日
http://japanese.china.org.cn/business/txt/2010-01/19/content_19270276.htm
http://japanese.china.org.cn/business/txt/2010-01/19/content_19270276_2.htm
発信時間: 2010-01-19 | チャイナネット
最新の英エコノミスト誌には、中国経済の現状を分析し、今後を予測する評論が掲載された。主な内容は次の通り。
有力な貨幣政策と巨額な経済刺激策のサポートで、中国は他の国よりすばやく不況から回復し、2009年第4半期の経済成長率は10%以上だった。しかし多くの経済学者は、中国経済の将来に対して疑っている。それは中国の経済回復の基礎は安定しておらず、80年代のバブル崩壊前の日本と似ているか、それよりもっと危険だと考えているからだ。西側諸国の経済情勢がまだ安定していないという状況で中国のバブルが弾ければ、中国自身に危害が及ぶだけでなく、世界中に連鎖反応を引き起こすことは間違いない。
国民の高い貯金率や、貨幣の為替レートを引き下げるために対外貿易を後押しする政府のやり方などは、表面的には確かに今の中国は当時の日本とよく似ている。また80年代末に国際社会は、日本が米国に代わって世界一の経済大国となると信じていたが、これも現在の中国に対する学者たちの予測と似ている。こうした中で盛んに議論されているのが、近いうちに中国経済のバブルが弾けるという悲観論だ。その代表的な人物が投資家のジェームズ・チャノス氏である。
中国経済の今後を悲観するのには3つの理由がある。それは高すぎる資産評価と投資過剰、高額な貸付だ。しかしこの3つの面を詳細に研究すると、実際の中国の情況は非常に楽観的だ。
資本市場の現状は楽観的
資本市場を証券市場で見ると、現在の株価収益率は28で、中国証券市場のかつての長期平均値を下回っている。しかしバブル崩壊前の日本は70近くに達していた。
もちろん中国の不動産市場が過熱している兆しもあるが、全国の住宅の平均伸び率を見ると、中国の不動産市場がバブル期に入ったとはまだ言えない。中国の住宅価格の伸び率と1人当たりの年間収入の平均伸び率の割合が、西側諸国よりずっと高いのは事実だ。しかし住宅を持っており年間収入がほとんど変わらない農民数が多いという中国の特殊な事情から、簡単にその割合を西側諸国と比べることができない。
その他にも中国の各世帯のローン額は、80年代中期の日本より低く、可処分収入の35%に過ぎない。不動産業の繁栄はローンではなく主に貯金が支えているため、全体的には不動産業は健全に発展している。
中国ではまだ巨額なローンにより不動産業にバブルの危機をもたらしたことはないが、北京や上海などの大都市の住宅価格は高すぎて一般市民は購入できないと状況は、社会の大きな問題になっている。これに対して中国政府側は、政府の提供する中低所得者向け低価格の「経済適用住宅」を増やし、急速に値上がりしている住宅価格を抑制するなど、関連の新政策を打ち出している。
「生産過剰」とは誇張した言い方
2009年の中国の固定資産投資総額は国内総生産(GDP)の47%を占めた。これは20年前の日本を10ポイントを上回り、西側諸国の平均率20%よりもはるかに高い。しかし固定資産への投資率が高すぎることから、中国での生産が過剰になると判断することはできない。
それは中国人1人あたりの資本保有率が、米国や日本の5%に過ぎないからだ。鉄鋼やセメントなど一部の工業分野では、確かに生産過剰という問題を抱えているが、全体的に見て中国が生産過剰だという言い方は誇張している。
鉄鋼業を例として挙げると、中国で鉄鋼の生産が明らかに過剰を迎えたのは、世界の不況による建築材料のニーズの減少と深い関わりがある。現在、中国鉄鋼業の一人当たりの生産率が米国を上回っているのは、中米の経済が違った発展段階にあるからで、米国経済が急騰した1920年代の米国の数字は今の中国よりもっと高かった。
中国の一部の工業生産高が昨年に大幅に増えた原因は、国がインフラ整備に投資したためだ。中国政府の経済刺激策の一部の投資は確かに無駄になったかもしれないが、全体的に見ればこの資金は主に鉄道や道路、電気輸送網などの建設に投入された。これは長期的に見ると中国の将来の持続可能な経済成長にプラスである。
中国のインフラはすでに完備しており、これ以上投資を続けるのは無駄だと一部の経済学者は考えているようだが、これは客観的な見方ではない。中国は広く人口が多い。また地形は複雑で、多くの貧困な農村地域でのインフラ整備はまだ整っていない。
「チャイナネット」 2010年1月19日
http://japanese.china.org.cn/business/txt/2010-01/19/content_19270276.htm
http://japanese.china.org.cn/business/txt/2010-01/19/content_19270276_2.htm
日本の「バブルの悲劇」が中国で再発することはない(下)
発信時間: 2010-01-20 | チャイナネット
多額の貸付金は昨年の状況
中国の銀行の貸付額が多すぎるという問題は、確かに以前の日本とよく似ており、これに関しては中国政府も憂慮し対策を講じている。しかしこれは去年に発生した新しい問題で、ここ数年来の状況ではない。ゴールドマン・サックスのエコノミーアナリストであるマイケル・ブキャナン氏の調査によると、中国の2004年の貸付額は西側の全ての先進諸国より低かった。
昨年の銀行の貸付額が多すぎたのには多くの理由がある。それは特殊な時期の特殊な事柄と言えるだろう。ある権威機構は、昨年の中国での新規貸付の中で不良貸付の割合は約20%で、GDP総額の5%に過ぎないことから、まだ安全ラインにいると推定している。
中国の政府側が発表したデータによると、中国のGDPにおける国債総額の割合は20%以下だ。しかし国内外の専門家は、この比率は過小評価されたもので、この数字には地方政府の債務や資産管理会社によって管理された銀行の不良資産は含まれていない可能性が高いと見ている。実際この2つの項目を加えても、GDPにおける国債の割合は50%にもならず、大多数の西側諸国よりも低い。
一部のバブル崩壊は中国経済の成長に影響しない
もし中国が今の貸付規模やスピードを維持すれば、バブルの発生や投資過剰の可能性は大きくなり、ここ数年、勢いよく成長し続けてきた中国経済が急速に衰退し不況になるという見方が一般的だ。しかしこれは中国が必ず直面する結末なのだろうか。
中国人1人当たりのGDPは20年前の日本とかなり大きな差があり、当時の米国にはもっと及ばない。そのため中国の経済には大きく成長する余地があり、たとえある分野でバブルが弾けたとしても、迅速に回復することはできる。
日本の教訓から学ぶべきことは?
日本の経済が破綻した原因は、円の切り上げを認めず、長期にわたって切り上げを抑えたことにある。そして強力に日本円を推し進めて金融緩和政策を実施したため、金融分野で深刻なバブルが発生した。
中国は日本から次の2つの教訓を得る必要がある。まずはできるだけ早く人民元の切り上げを認めることだ。切り上げは徐々に行い急激には実施しないこと。次は過度の金融緩和政策を実施しないことで、この2点を注意すれば中国経済の崩壊は目の前で起こらず、避けられないことはない。
「チャイナネット」 2010年1月20日
http://japanese.china.org.cn/business/txt/2010-01/20/content_19276638.htm
発信時間: 2010-01-20 | チャイナネット
多額の貸付金は昨年の状況
中国の銀行の貸付額が多すぎるという問題は、確かに以前の日本とよく似ており、これに関しては中国政府も憂慮し対策を講じている。しかしこれは去年に発生した新しい問題で、ここ数年来の状況ではない。ゴールドマン・サックスのエコノミーアナリストであるマイケル・ブキャナン氏の調査によると、中国の2004年の貸付額は西側の全ての先進諸国より低かった。
昨年の銀行の貸付額が多すぎたのには多くの理由がある。それは特殊な時期の特殊な事柄と言えるだろう。ある権威機構は、昨年の中国での新規貸付の中で不良貸付の割合は約20%で、GDP総額の5%に過ぎないことから、まだ安全ラインにいると推定している。
中国の政府側が発表したデータによると、中国のGDPにおける国債総額の割合は20%以下だ。しかし国内外の専門家は、この比率は過小評価されたもので、この数字には地方政府の債務や資産管理会社によって管理された銀行の不良資産は含まれていない可能性が高いと見ている。実際この2つの項目を加えても、GDPにおける国債の割合は50%にもならず、大多数の西側諸国よりも低い。
一部のバブル崩壊は中国経済の成長に影響しない
もし中国が今の貸付規模やスピードを維持すれば、バブルの発生や投資過剰の可能性は大きくなり、ここ数年、勢いよく成長し続けてきた中国経済が急速に衰退し不況になるという見方が一般的だ。しかしこれは中国が必ず直面する結末なのだろうか。
中国人1人当たりのGDPは20年前の日本とかなり大きな差があり、当時の米国にはもっと及ばない。そのため中国の経済には大きく成長する余地があり、たとえある分野でバブルが弾けたとしても、迅速に回復することはできる。
日本の教訓から学ぶべきことは?
日本の経済が破綻した原因は、円の切り上げを認めず、長期にわたって切り上げを抑えたことにある。そして強力に日本円を推し進めて金融緩和政策を実施したため、金融分野で深刻なバブルが発生した。
中国は日本から次の2つの教訓を得る必要がある。まずはできるだけ早く人民元の切り上げを認めることだ。切り上げは徐々に行い急激には実施しないこと。次は過度の金融緩和政策を実施しないことで、この2点を注意すれば中国経済の崩壊は目の前で起こらず、避けられないことはない。
「チャイナネット」 2010年1月20日
http://japanese.china.org.cn/business/txt/2010-01/20/content_19276638.htm
●昨年の中国原油対外依存度50%超過 既に警鐘が鳴らされる
税関総署が先日公布したデータによると、昨年12月に中国原油輸入量2126万トン
という記録がつくられたことによって、中国2009年の年間原油輸入量も初めて2億
トン(2.04億トン)を超過し、年間原油対外依存度は50%の「国際警戒線」を超過
した。
〈原油対外依存度は52%と推測〉
昨年以降、前年度同時期と比較し、中国国内原油生産は常に下降傾向を保ってい
る。国家統計局は、今月下旬に各業界データを発表するが、最も楽観的推測におい
ても年間中国国内原油生産は19億トン前後が予測され、年間中国原油対外依存度は
52%前後に到達するとされる。
1993年に中国が初めて石油輸入国になって以降、その原油対外依存度は当時の6%
から上昇を続け、2006年には45%を突破、その後は毎年平均2%前後の速度で上昇、
2007年には47%、2008年には49%、2009年には50%の警戒線を突破。たった16年の間
である。
とどまることを知らない原油対外依存度の上昇により、多種多様な中国エネルギ
ー業界の中でも、石油業界は非常に重要視されている。「第一財経日報」の取材を
受けて、多くのエネルギー専門家は皆、石油こそが中国エネルギー安全の「最も逼
迫した問題」と見ている。
業界では、中国経済の急速な発展が、「産業の血液」としての石油需要の急激な
成長を決定すると分析されていた。2009年初めには、経済危機の中で低空飛行状態
にあった中国経済によって、この50%というスローガンへの到達年度は遅くなると
考えられていた。
しかし、過去1年の間で、中国経済は低迷から回復に向かい、V字型回復ルートを
描き出した。経済学者は共通して、2009年中国GDPを「8%に保てば心配なし」とし、
経済回復がエネルギー産業をも回復に導くと予測した。
同時に、2009年には、中国海洋石油恵州製油プロジェクト、中国石化福建プロジ
ェクト、中国石化天津プロジェクト等を含む、何千万トン級の新大型製油化プロジ
ェクトが中国沿海地区で相次いで開始され、生産準備や生産ニーズにおいても、海
外に対する原油ニーズは同様に高まった。
このほか、実施中の国家戦略としての石油備蓄及び国内原油生産下降により、中
国の原油輸入は拡大していった。
中期的に見れば、自動車生産販売量が世界1位となった国家にとって、その原油
対外依存度が継続して上昇することは、言うまでもない命題である。
2008年末に承認された「全国鉱山物資源計画(2008─2015)」が出した予測に基
づけば、2020年までに、中国原油対外依存度は60%に到達するとされている。とこ
ろが、昨年公表された「エネルギー白書」による予測では、10年後に中国の原油対
外依存度は64%に到達するとなっている。
税関総署が先日公布したデータによると、昨年12月に中国原油輸入量2126万トン
という記録がつくられたことによって、中国2009年の年間原油輸入量も初めて2億
トン(2.04億トン)を超過し、年間原油対外依存度は50%の「国際警戒線」を超過
した。
〈原油対外依存度は52%と推測〉
昨年以降、前年度同時期と比較し、中国国内原油生産は常に下降傾向を保ってい
る。国家統計局は、今月下旬に各業界データを発表するが、最も楽観的推測におい
ても年間中国国内原油生産は19億トン前後が予測され、年間中国原油対外依存度は
52%前後に到達するとされる。
1993年に中国が初めて石油輸入国になって以降、その原油対外依存度は当時の6%
から上昇を続け、2006年には45%を突破、その後は毎年平均2%前後の速度で上昇、
2007年には47%、2008年には49%、2009年には50%の警戒線を突破。たった16年の間
である。
とどまることを知らない原油対外依存度の上昇により、多種多様な中国エネルギ
ー業界の中でも、石油業界は非常に重要視されている。「第一財経日報」の取材を
受けて、多くのエネルギー専門家は皆、石油こそが中国エネルギー安全の「最も逼
迫した問題」と見ている。
業界では、中国経済の急速な発展が、「産業の血液」としての石油需要の急激な
成長を決定すると分析されていた。2009年初めには、経済危機の中で低空飛行状態
にあった中国経済によって、この50%というスローガンへの到達年度は遅くなると
考えられていた。
しかし、過去1年の間で、中国経済は低迷から回復に向かい、V字型回復ルートを
描き出した。経済学者は共通して、2009年中国GDPを「8%に保てば心配なし」とし、
経済回復がエネルギー産業をも回復に導くと予測した。
同時に、2009年には、中国海洋石油恵州製油プロジェクト、中国石化福建プロジ
ェクト、中国石化天津プロジェクト等を含む、何千万トン級の新大型製油化プロジ
ェクトが中国沿海地区で相次いで開始され、生産準備や生産ニーズにおいても、海
外に対する原油ニーズは同様に高まった。
このほか、実施中の国家戦略としての石油備蓄及び国内原油生産下降により、中
国の原油輸入は拡大していった。
中期的に見れば、自動車生産販売量が世界1位となった国家にとって、その原油
対外依存度が継続して上昇することは、言うまでもない命題である。
2008年末に承認された「全国鉱山物資源計画(2008─2015)」が出した予測に基
づけば、2020年までに、中国原油対外依存度は60%に到達するとされている。とこ
ろが、昨年公表された「エネルギー白書」による予測では、10年後に中国の原油対
外依存度は64%に到達するとなっている。
〈世界の終わりではないが、警鐘は既に鳴らされている〉
しかし、原油対外依存度が50%を超過しても、中国にとっては世界の末日という
わけではない。国際的に各主要経済体の原油対外依存度はどこも比較的高いことを
見るべきである。
中国近郊の日本や韓国を例にとれば、その対外依存度はどちらも90%以上となっ
ているが、世界三大石油生産国となっているアメリカ(ロシアやサウジに次ぐ)で
も、その原油対外依存度は60%以上である。
「この数字は重要であるが、実際、過度に重視する必要はない。私たちは国際間
におけるエネルギー協力こそより重要視するべきで、国内エネルギー需要の管理と
供給をきちんと行わなくてはならない」中国石油大学エネルギー戦略研究センター
の執行主任、王震氏が本誌に述べた言葉である。
王震氏によると、中国は長期にわたってエネルギー供給を過度に重要視してきた
が、需要サイドからエネルギー管理を行うことは少なかった。「私たちはどのよう
にエネルギーを使用すればよいのか、これは私たちが本当にきちんと行わなければ
ならない仕事である。例えば、組織のエネルギー価値を上げる、エネルギー消耗を
減らす、効率性を上げ排出を減らすといった具合である」
しかし、アモイ大学にある中国エネルギー経済研究センター主任の林伯強氏は、
中国原油対外依存度の50%超過で、既に中国への警鐘が鳴らされていると見る。
「アメリカの依存度が中国のそれよりも高そうだというところを見てはいけない。
そうではなくて、アメリカのエネルギー消費は基本的に既にピークに達していると
ころに着目しなければならない。それに対し、中国の将来におけるエネルギー需要
は依然として大きいが、国内石油生産量は既にピークに到達している。これはつま
り、中国の今後における石油消費の増大分は、すべて海外からの輸入に頼るという
ことである。もし、我々が取り組まなければ、中国の石油対外依存度は確実にアメ
リカのそれを超過する。70%に達する可能性さえあるのだ」
発展途上のエネルギー消費大国として、対外依存度70%になり得る石油需要とい
うのは、国際的に石油価格の決定権がない状況で極めて危険である。しかし、中国
石油企業に海外進出させれば、その途中経過において海外の石油権益を多く獲得す
ることができるだろうというのが林伯強氏の意見だ。
〔第一財経日報2010年1月13日〕
しかし、原油対外依存度が50%を超過しても、中国にとっては世界の末日という
わけではない。国際的に各主要経済体の原油対外依存度はどこも比較的高いことを
見るべきである。
中国近郊の日本や韓国を例にとれば、その対外依存度はどちらも90%以上となっ
ているが、世界三大石油生産国となっているアメリカ(ロシアやサウジに次ぐ)で
も、その原油対外依存度は60%以上である。
「この数字は重要であるが、実際、過度に重視する必要はない。私たちは国際間
におけるエネルギー協力こそより重要視するべきで、国内エネルギー需要の管理と
供給をきちんと行わなくてはならない」中国石油大学エネルギー戦略研究センター
の執行主任、王震氏が本誌に述べた言葉である。
王震氏によると、中国は長期にわたってエネルギー供給を過度に重要視してきた
が、需要サイドからエネルギー管理を行うことは少なかった。「私たちはどのよう
にエネルギーを使用すればよいのか、これは私たちが本当にきちんと行わなければ
ならない仕事である。例えば、組織のエネルギー価値を上げる、エネルギー消耗を
減らす、効率性を上げ排出を減らすといった具合である」
しかし、アモイ大学にある中国エネルギー経済研究センター主任の林伯強氏は、
中国原油対外依存度の50%超過で、既に中国への警鐘が鳴らされていると見る。
「アメリカの依存度が中国のそれよりも高そうだというところを見てはいけない。
そうではなくて、アメリカのエネルギー消費は基本的に既にピークに達していると
ころに着目しなければならない。それに対し、中国の将来におけるエネルギー需要
は依然として大きいが、国内石油生産量は既にピークに到達している。これはつま
り、中国の今後における石油消費の増大分は、すべて海外からの輸入に頼るという
ことである。もし、我々が取り組まなければ、中国の石油対外依存度は確実にアメ
リカのそれを超過する。70%に達する可能性さえあるのだ」
発展途上のエネルギー消費大国として、対外依存度70%になり得る石油需要とい
うのは、国際的に石油価格の決定権がない状況で極めて危険である。しかし、中国
石油企業に海外進出させれば、その途中経過において海外の石油権益を多く獲得す
ることができるだろうというのが林伯強氏の意見だ。
〔第一財経日報2010年1月13日〕
●中国車両保有数1.86億台超 運転者は2億人に迫る
7日公安部からの取材によれば、2009年末現在、全国の車両保有数は既に1.86億
台を超え、全国の運転手は2億人近くになった。
公安部の統計データによれば、2009年末までの全国の車両保有数は1億8658万658
台。そのうち自動車は7619万3055台、オートバイは9453万658台、トレーラーは120
万1519台、道路通行するトラクターは1463万3456台、その他車両は2万1970台。全
国の車両運転者は1億9976万5889人、そのうち自動車の運転者は1億3820万3911人。
2009年以降、国際金融危機に対応し、経済の安定や比較的早い増加を確保するた
め、国が一連の自動車、オートバイの消費を促進する政策を打ち出し、これが消費
市場を有効に刺激したことから、車両保有は増加速度を強め、また運転者も相応し
て大幅に増加した。車両は1669万台、運転者は1910万人増加した。
〔新華網2010年1月7日〕
7日公安部からの取材によれば、2009年末現在、全国の車両保有数は既に1.86億
台を超え、全国の運転手は2億人近くになった。
公安部の統計データによれば、2009年末までの全国の車両保有数は1億8658万658
台。そのうち自動車は7619万3055台、オートバイは9453万658台、トレーラーは120
万1519台、道路通行するトラクターは1463万3456台、その他車両は2万1970台。全
国の車両運転者は1億9976万5889人、そのうち自動車の運転者は1億3820万3911人。
2009年以降、国際金融危機に対応し、経済の安定や比較的早い増加を確保するた
め、国が一連の自動車、オートバイの消費を促進する政策を打ち出し、これが消費
市場を有効に刺激したことから、車両保有は増加速度を強め、また運転者も相応し
て大幅に増加した。車両は1669万台、運転者は1910万人増加した。
〔新華網2010年1月7日〕
中国のSLBM実験失敗、発射した潜水艦に落下=台湾紙
25日付台湾紙自由時報は、中国人民解放軍が数カ月前に黄海(韓国名・西海)の海中で潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)の巨浪2号の発射実験を行ったところ、海面に出てもミサイルが正常に点火しないまま海中に落下。ミサイルは発射した海中の潜水艦と衝突し、潜水艦が沈没寸前の状況に陥ったと伝えた。
同紙の記事を引用したマレーシア華字紙・星洲日報によると、巨浪2号は米本土に到達する射程8000キロの性能を備え、ゴルフ級弾道ミサイル潜水艦から発射された。事故当時、ミサイルを発射した潜水艦は、落下した重さ10トン余りのミサイルが直撃し、艦体が大きく破損したが、緊急修理後に自力で帰港し、大規模な修理を受けたという。
中国のポータルサイト大手「新浪網」は、軍事専門家の話として、「中国は潜水艦を離れたミサイルが水面に浮上する際、一定の角度を維持する高難度の技術が不足しており、海中での発射実験は失敗が多い」と指摘した。
香港=李恒洙(イ・ハンス)特派員
あらら
25日付台湾紙自由時報は、中国人民解放軍が数カ月前に黄海(韓国名・西海)の海中で潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)の巨浪2号の発射実験を行ったところ、海面に出てもミサイルが正常に点火しないまま海中に落下。ミサイルは発射した海中の潜水艦と衝突し、潜水艦が沈没寸前の状況に陥ったと伝えた。
同紙の記事を引用したマレーシア華字紙・星洲日報によると、巨浪2号は米本土に到達する射程8000キロの性能を備え、ゴルフ級弾道ミサイル潜水艦から発射された。事故当時、ミサイルを発射した潜水艦は、落下した重さ10トン余りのミサイルが直撃し、艦体が大きく破損したが、緊急修理後に自力で帰港し、大規模な修理を受けたという。
中国のポータルサイト大手「新浪網」は、軍事専門家の話として、「中国は潜水艦を離れたミサイルが水面に浮上する際、一定の角度を維持する高難度の技術が不足しており、海中での発射実験は失敗が多い」と指摘した。
香港=李恒洙(イ・ハンス)特派員
あらら
■日本語で読める中国環境ニュース
□CRI
中国、気候変動問題解決での相違点をなくすよう各国に要求
http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=windowsmedia
中国国家エネルギー委員会、設立 温家宝首相が主任に
http://japanese.cri.cn/881/2010/01/27/142s153888.htm
国務院常務会議、「国家環境保護」評価報告を採択
http://japanese.cri.cn/881/2010/01/27/142s153895.htm
中国の建設によるモンゴル最大の水力発電所、竣工
http://japanese.cri.cn/881/2010/01/29/144s153999.htm
中国、農村環境改善に3年で120億元
http://japanese.cri.cn/881/2010/01/28/146s153961.htm
エネルギー委員会設立"関連戦略のマクロ的把握に有利"
http://japanese.cri.cn/881/2010/01/27/142s153894.htm
中国、遅れている産業の整理を加速
http://japanese.cri.cn/881/2010/01/27/146s153877.htm
新興4カ国気候変動閣僚級会合、インドで開催
http://japanese.cri.cn/881/2010/01/25/146s153700.htm
中国・アラブ協力フォーラム第2回エネ協力会議、開幕
http://japanese.cri.cn/881/2010/01/27/145s153851.htm
中国、二酸化硫黄の排出量、40万トン削減を目指す
http://japanese.cri.cn/881/2010/01/25/146s153712.htm
中国税関、絶滅危ぐ動植物の密輸取締りに成果
http://japanese.cri.cn/881/2010/01/25/144s153738.htm
中国、「国際生物多様性年」のイベントを開催
http://japanese.cri.cn/881/2010/01/26/142s153793.htm
中国が建設中の原子力発電規模世界最大
http://japanese.cri.cn/881/2010/01/29/147s154025.htm
□人民網
環保部、2010年排出削減目標を発表
http://j.peopledaily.com.cn/94475/6879085.html
北京 自動車環境税導入へ
http://j.peopledaily.com.cn/94476/6880618.html
北京で新エネルギーの公共バスを引き続き増加
http://j.peopledaily.com.cn/94475/6880664.html
国務院常務会議 中国の環境汚染問題は未解決
http://j.peopledaily.com.cn/94475/6881763.html
高効率省エネエアコン 市場シェア50%超
http://j.peopledaily.com.cn/94476/6878032.html
国家エネルギー委員会の発足が意味するもの
http://j.peopledaily.com.cn/94476/6881729.html
上海、崇明島を世界レベルの生態環境島に
http://j.peopledaily.com.cn/95952/6877798.html
中国大陸6カ所に風力発電基地を設置へ
http://j.peopledaily.com.cn/95952/6882568.html
中国初 排出権取引が可能なクレジットカードを発行
http://j.peopledaily.com.cn/95952/6882729.html
中国、温室効果ガス排出緩和に関する報告を近く国連に提出へ
http://j.peopledaily.com.cn/94474/6880530.html
国家エネルギー委員会が発足、温家宝総理が主任に
http://j.peopledaily.com.cn/94474/6881431.html
2010年は国際生物多様性年 中国も行動をスタート
http://j.peopledaily.com.cn/95952/6880271.html
□中国情報局
電気自動車を300台まで追加導入へ−北京
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=0129&f=national_0129_002.shtml
中国の環境汚染「どうにも止まらない状態」…政府会議で確認
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=0128&f=national_0128_027.shtml
中国が「国家エネルギー委員会」を設立、その任務と意図は
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=0128&f=politics_0128_005.shtml
黄河の水資源が危機的状況、20年後に20億立方メートル減少
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=0128&f=national_0128_002.shtml
自動車対象「環境税」徴収へ、排気量に応じて基準―中国
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=0127&f=business_0127_076.shtml
国家新エネルギー科技モデル都市の建設を開始−江西
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=0126&f=business_0126_070.shtml
出光興産、中国の石炭火力発電所に省エネコンサルティングを実施
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=0126&f=business_0126_046.shtml
中国税関、絶滅危惧種に関して76の密輸事件を摘発
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=0126&f=national_0126_004.shtml
□CRI
中国、気候変動問題解決での相違点をなくすよう各国に要求
http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=windowsmedia
中国国家エネルギー委員会、設立 温家宝首相が主任に
http://japanese.cri.cn/881/2010/01/27/142s153888.htm
国務院常務会議、「国家環境保護」評価報告を採択
http://japanese.cri.cn/881/2010/01/27/142s153895.htm
中国の建設によるモンゴル最大の水力発電所、竣工
http://japanese.cri.cn/881/2010/01/29/144s153999.htm
中国、農村環境改善に3年で120億元
http://japanese.cri.cn/881/2010/01/28/146s153961.htm
エネルギー委員会設立"関連戦略のマクロ的把握に有利"
http://japanese.cri.cn/881/2010/01/27/142s153894.htm
中国、遅れている産業の整理を加速
http://japanese.cri.cn/881/2010/01/27/146s153877.htm
新興4カ国気候変動閣僚級会合、インドで開催
http://japanese.cri.cn/881/2010/01/25/146s153700.htm
中国・アラブ協力フォーラム第2回エネ協力会議、開幕
http://japanese.cri.cn/881/2010/01/27/145s153851.htm
中国、二酸化硫黄の排出量、40万トン削減を目指す
http://japanese.cri.cn/881/2010/01/25/146s153712.htm
中国税関、絶滅危ぐ動植物の密輸取締りに成果
http://japanese.cri.cn/881/2010/01/25/144s153738.htm
中国、「国際生物多様性年」のイベントを開催
http://japanese.cri.cn/881/2010/01/26/142s153793.htm
中国が建設中の原子力発電規模世界最大
http://japanese.cri.cn/881/2010/01/29/147s154025.htm
□人民網
環保部、2010年排出削減目標を発表
http://j.peopledaily.com.cn/94475/6879085.html
北京 自動車環境税導入へ
http://j.peopledaily.com.cn/94476/6880618.html
北京で新エネルギーの公共バスを引き続き増加
http://j.peopledaily.com.cn/94475/6880664.html
国務院常務会議 中国の環境汚染問題は未解決
http://j.peopledaily.com.cn/94475/6881763.html
高効率省エネエアコン 市場シェア50%超
http://j.peopledaily.com.cn/94476/6878032.html
国家エネルギー委員会の発足が意味するもの
http://j.peopledaily.com.cn/94476/6881729.html
上海、崇明島を世界レベルの生態環境島に
http://j.peopledaily.com.cn/95952/6877798.html
中国大陸6カ所に風力発電基地を設置へ
http://j.peopledaily.com.cn/95952/6882568.html
中国初 排出権取引が可能なクレジットカードを発行
http://j.peopledaily.com.cn/95952/6882729.html
中国、温室効果ガス排出緩和に関する報告を近く国連に提出へ
http://j.peopledaily.com.cn/94474/6880530.html
国家エネルギー委員会が発足、温家宝総理が主任に
http://j.peopledaily.com.cn/94474/6881431.html
2010年は国際生物多様性年 中国も行動をスタート
http://j.peopledaily.com.cn/95952/6880271.html
□中国情報局
電気自動車を300台まで追加導入へ−北京
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=0129&f=national_0129_002.shtml
中国の環境汚染「どうにも止まらない状態」…政府会議で確認
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=0128&f=national_0128_027.shtml
中国が「国家エネルギー委員会」を設立、その任務と意図は
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=0128&f=politics_0128_005.shtml
黄河の水資源が危機的状況、20年後に20億立方メートル減少
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=0128&f=national_0128_002.shtml
自動車対象「環境税」徴収へ、排気量に応じて基準―中国
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=0127&f=business_0127_076.shtml
国家新エネルギー科技モデル都市の建設を開始−江西
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=0126&f=business_0126_070.shtml
出光興産、中国の石炭火力発電所に省エネコンサルティングを実施
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=0126&f=business_0126_046.shtml
中国税関、絶滅危惧種に関して76の密輸事件を摘発
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=0126&f=national_0126_004.shtml
□チャイナネット
北京、自転車利用を拡大
http://japanese.china.org.cn/life/txt/2010-01/25/content_19301853.htm
2010年の中国の自動車購入に関する新政策
http://japanese.china.org.cn/business/txt/2010-01/28/content_19324431.htm
中国の省エネエアコン市場シェアが50%超に
http://japanese.china.org.cn/business/txt/2010-01/25/content_19302922.htm
北京、新エネルギーバスを追加導入へ
http://japanese.china.org.cn/business/txt/2010-01/28/content_19321900.htm
ハ陽湖生態経済区計画が江西省のエコ発展を促進
http://japanese.china.org.cn/business/txt/2010-01/28/content_19324208.htm
江西新余、世界レベルの新エネルギー基地を建設
http://japanese.china.org.cn/business/txt/2010-01/25/content_19303527.htm
ニュース解読:国家エネルギー委員会の設立から受け取るもの
http://japanese.china.org.cn/business/txt/2010-01/28/content_19322857.htm
黄河の流量が20年後には20億立方メートル減少
http://japanese.china.org.cn/environment/txt/2010-01/27/content_19315150.htm
□日経
中国、エネルギー政策の統括組織を新設
http://www.nikkei.co.jp/china/news/index.aspx?n=ATGM2703C%2027012010
シャープ、中国でソーラーパネル搭載の携帯発売
http://www.nikkei.co.jp/china/news/index.aspx?n=AT5D27008%2027012010
三菱化学、中国で車用塩ビの生産能力倍増 環境車需要見込む
http://www.nikkei.co.jp/china/news/index.aspx?n=ATDD220A4%2026012010
ブリヂストン、中国のタイヤ4工場で海外工場初の「0.5%ゼロ・エミッション」達成
http://eco.nikkeibp.co.jp/article/news/20100125/103042/
□新華通信ネットジャパン
国務院常務会議、「国家環境保護十一五規画中間期評価報告」を原則承認
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245432/
国家エネルギー委員会を創設、温家宝氏が主任を任命
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245404/
大口ユーザーの電力直接購入テストケースを拡大
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245186/
車内空気汚染に関する基準、制定へ
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245337/
黒龍江省:中国風電国際、クリーンエネルギープロジェクト建設を加速
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245180/
江蘇省:ソーラー技術の重点実験室、常州に立地
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245472/
山東省:10年には240万トンの製鉄能力を淘汰
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245395/
10年、西北5省(区)をカバーする「送電網ハイウェイ」を敷設
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245388/
湖北省:三峡ダム、5600箱のチョウザメ網箱を取り除く
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245312/
山西省:ほとんどの地域で軽度の干ばつが発生
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245297/
中国、30年来海面が70ミリ上昇
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245489/
中国消費者は代替エネルギー車指向、日本・米国消費者の指向を上回る
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245436/
黒龍江省:綏フェン河中国区間初の汚水処理工場を操業開始
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245393/
太古地産と清華大学が建築省エネ研究基金を設立
http://www.xinhua.jp/industry/245183/
国務院常務会議を召集し、遅れた生産能力の淘汰を指示=温家宝首相
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245119/
10年の電力投資が約6600億元=中電聯
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245505/
山東省:発電用石炭在庫が8日分まで減少
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245441/
浙江省:10年、230億元以上を投資し電力網を建設
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245364/
黒龍江省:中国風電国際、クリーンエネルギープロジェクト建設推進へ
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245328/
北京、自転車利用を拡大
http://japanese.china.org.cn/life/txt/2010-01/25/content_19301853.htm
2010年の中国の自動車購入に関する新政策
http://japanese.china.org.cn/business/txt/2010-01/28/content_19324431.htm
中国の省エネエアコン市場シェアが50%超に
http://japanese.china.org.cn/business/txt/2010-01/25/content_19302922.htm
北京、新エネルギーバスを追加導入へ
http://japanese.china.org.cn/business/txt/2010-01/28/content_19321900.htm
ハ陽湖生態経済区計画が江西省のエコ発展を促進
http://japanese.china.org.cn/business/txt/2010-01/28/content_19324208.htm
江西新余、世界レベルの新エネルギー基地を建設
http://japanese.china.org.cn/business/txt/2010-01/25/content_19303527.htm
ニュース解読:国家エネルギー委員会の設立から受け取るもの
http://japanese.china.org.cn/business/txt/2010-01/28/content_19322857.htm
黄河の流量が20年後には20億立方メートル減少
http://japanese.china.org.cn/environment/txt/2010-01/27/content_19315150.htm
□日経
中国、エネルギー政策の統括組織を新設
http://www.nikkei.co.jp/china/news/index.aspx?n=ATGM2703C%2027012010
シャープ、中国でソーラーパネル搭載の携帯発売
http://www.nikkei.co.jp/china/news/index.aspx?n=AT5D27008%2027012010
三菱化学、中国で車用塩ビの生産能力倍増 環境車需要見込む
http://www.nikkei.co.jp/china/news/index.aspx?n=ATDD220A4%2026012010
ブリヂストン、中国のタイヤ4工場で海外工場初の「0.5%ゼロ・エミッション」達成
http://eco.nikkeibp.co.jp/article/news/20100125/103042/
□新華通信ネットジャパン
国務院常務会議、「国家環境保護十一五規画中間期評価報告」を原則承認
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245432/
国家エネルギー委員会を創設、温家宝氏が主任を任命
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245404/
大口ユーザーの電力直接購入テストケースを拡大
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245186/
車内空気汚染に関する基準、制定へ
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245337/
黒龍江省:中国風電国際、クリーンエネルギープロジェクト建設を加速
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245180/
江蘇省:ソーラー技術の重点実験室、常州に立地
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245472/
山東省:10年には240万トンの製鉄能力を淘汰
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245395/
10年、西北5省(区)をカバーする「送電網ハイウェイ」を敷設
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245388/
湖北省:三峡ダム、5600箱のチョウザメ網箱を取り除く
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245312/
山西省:ほとんどの地域で軽度の干ばつが発生
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245297/
中国、30年来海面が70ミリ上昇
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245489/
中国消費者は代替エネルギー車指向、日本・米国消費者の指向を上回る
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245436/
黒龍江省:綏フェン河中国区間初の汚水処理工場を操業開始
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245393/
太古地産と清華大学が建築省エネ研究基金を設立
http://www.xinhua.jp/industry/245183/
国務院常務会議を召集し、遅れた生産能力の淘汰を指示=温家宝首相
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245119/
10年の電力投資が約6600億元=中電聯
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245505/
山東省:発電用石炭在庫が8日分まで減少
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245441/
浙江省:10年、230億元以上を投資し電力網を建設
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245364/
黒龍江省:中国風電国際、クリーンエネルギープロジェクト建設推進へ
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/245328/
□その他
中国のクリーンエネルギー技術の研究進展
http://www.spc.jst.go.jp/hottopics/r1002_weiguang.html
中国における太陽エネルギー利用技術の開発および産業の現状
http://www.spc.jst.go.jp/hottopics/1002low_carbon/r1002_miao.html
中国における低炭素社会づくりの取り組み
http://www.spc.jst.go.jp/hottopics/1002low_carbon/r1002_onogi.html
中‐米の研究者、環境汚染とがん研究で協力を強化
http://crds.jst.go.jp/watcher/data/832-009.html
中国が自主設計したアジア最大の浚渫船、引渡し完了
http://www.spc.jst.go.jp/news/100104/topic_2_01.html
2010年は国際生物多様性年 中国も行動をスタート
http://www.spc.jst.go.jp/news/100104/topic_3_03.html
中国、風力エネルギーの詳細評価を年内に完了へ
http://crds.jst.go.jp/watcher/data/833-007.html
遺棄化学兵器処理で日中 処理プラント建設見送りへ
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100128/plc1001280214001-n1.htm
中国のトキ生息環境整備、日本も協力
http://www.yomiuri.co.jp/eco/news/20100129-OYT1T01133.htm
養豚メタン回収CDMに挑戦 「小規模事業」で初の国家承認へ
http://www.shwalker.com/biz/contents/biz_3_2073_20100111142741.html
トキの生息地分散化を支援 日中共同で環境保全策
http://sankei.jp.msn.com/world/china/100129/chn1001291321001-n1.htm
環保部:2010年環境汚染物質排出削減目標を発表
http://www.chinapress.jp/economy/19908/
中国など新興4カ国、温暖化ガス削減計画の期限内提出を明言
http://jp.reuters.com/article/worldNews/idJPJAPAN-13496720100125?rpc=165
中国環境ビジネスのリーディングカンパニー
http://money.quick.co.jp/pr/eco/report/asia_vo11.html
重金属汚染が表面化、09年に血中鉛濃度が基準値以上の住民4035人―中国
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100128-00000007-rcdc-cn
中国国務院、国家能源委員会の設置を決定 主任は温家宝首相
http://www.asiam.co.jp/news_box.php?topic=013041
中国国家能源委員会 海外メディアは新設の背後にあるエネルギー外交に注目
http://www.asiam.co.jp/news_box.php?topic=013044
中国 今後は能源委員会がエネルギー戦略計画を主導
http://www.asiam.co.jp/news_box.php?topic=013047
中国湖北省 3年内に21の新エネルギー発電所建設
http://www.asiam.co.jp/news_newe.php?topic=013037
【省エネルギー】
1.工業信息化部、工業分野の省エネに向けた4大対策を表明
2.上海市、交通分野「節能減排」プロジェクトに最高1千万元を補助
3.重慶市、グリーン建築評価標準を制定
【エネルギー全般】
4.昨年石油備蓄コストは58USD/バレル、原油パイプライン輸入も本格化
5.海南省と蘭州市に石油備蓄基地を建設
6.シノペック子会社9社を四川に設立、精製油から非石油製品の販売へ
【新エネルギー】
7.上海汽車(SAIC)、新エネ車産業化に5年間で120億元投資
【環境保護・汚染物質排出削減】
8.上海市、太湖汚染対策エリア、補助金支給により汚水パイプラインを整備
9.土壌汚染の修復工事、全国に先駆けて重慶市がスタート
http://www.jetro.go.jp/mail/u/l?p=_piDs_pMZQoZ
中国のクリーンエネルギー技術の研究進展
http://www.spc.jst.go.jp/hottopics/r1002_weiguang.html
中国における太陽エネルギー利用技術の開発および産業の現状
http://www.spc.jst.go.jp/hottopics/1002low_carbon/r1002_miao.html
中国における低炭素社会づくりの取り組み
http://www.spc.jst.go.jp/hottopics/1002low_carbon/r1002_onogi.html
中‐米の研究者、環境汚染とがん研究で協力を強化
http://crds.jst.go.jp/watcher/data/832-009.html
中国が自主設計したアジア最大の浚渫船、引渡し完了
http://www.spc.jst.go.jp/news/100104/topic_2_01.html
2010年は国際生物多様性年 中国も行動をスタート
http://www.spc.jst.go.jp/news/100104/topic_3_03.html
中国、風力エネルギーの詳細評価を年内に完了へ
http://crds.jst.go.jp/watcher/data/833-007.html
遺棄化学兵器処理で日中 処理プラント建設見送りへ
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100128/plc1001280214001-n1.htm
中国のトキ生息環境整備、日本も協力
http://www.yomiuri.co.jp/eco/news/20100129-OYT1T01133.htm
養豚メタン回収CDMに挑戦 「小規模事業」で初の国家承認へ
http://www.shwalker.com/biz/contents/biz_3_2073_20100111142741.html
トキの生息地分散化を支援 日中共同で環境保全策
http://sankei.jp.msn.com/world/china/100129/chn1001291321001-n1.htm
環保部:2010年環境汚染物質排出削減目標を発表
http://www.chinapress.jp/economy/19908/
中国など新興4カ国、温暖化ガス削減計画の期限内提出を明言
http://jp.reuters.com/article/worldNews/idJPJAPAN-13496720100125?rpc=165
中国環境ビジネスのリーディングカンパニー
http://money.quick.co.jp/pr/eco/report/asia_vo11.html
重金属汚染が表面化、09年に血中鉛濃度が基準値以上の住民4035人―中国
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100128-00000007-rcdc-cn
中国国務院、国家能源委員会の設置を決定 主任は温家宝首相
http://www.asiam.co.jp/news_box.php?topic=013041
中国国家能源委員会 海外メディアは新設の背後にあるエネルギー外交に注目
http://www.asiam.co.jp/news_box.php?topic=013044
中国 今後は能源委員会がエネルギー戦略計画を主導
http://www.asiam.co.jp/news_box.php?topic=013047
中国湖北省 3年内に21の新エネルギー発電所建設
http://www.asiam.co.jp/news_newe.php?topic=013037
【省エネルギー】
1.工業信息化部、工業分野の省エネに向けた4大対策を表明
2.上海市、交通分野「節能減排」プロジェクトに最高1千万元を補助
3.重慶市、グリーン建築評価標準を制定
【エネルギー全般】
4.昨年石油備蓄コストは58USD/バレル、原油パイプライン輸入も本格化
5.海南省と蘭州市に石油備蓄基地を建設
6.シノペック子会社9社を四川に設立、精製油から非石油製品の販売へ
【新エネルギー】
7.上海汽車(SAIC)、新エネ車産業化に5年間で120億元投資
【環境保護・汚染物質排出削減】
8.上海市、太湖汚染対策エリア、補助金支給により汚水パイプラインを整備
9.土壌汚染の修復工事、全国に先駆けて重慶市がスタート
http://www.jetro.go.jp/mail/u/l?p=_piDs_pMZQoZ
原油自給率50%割れで、中国に「国際価格が直撃」の不安感 −yahoo!ニュース−
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100204-00000013-scn-cn
中国人民ラジオ局によると、国家エネルギー資源局がこのほど、中国の原油自給率が50%を切ったことを明らかにしたため、「心理的」な影響が出ている。専門家は「心配しすぎだが、価格面で懸念すべき点はある」と指摘した。
同局によると、2009年における中国の原油生産量は1.89億トンで、輸入量は1.99億トンだった。中国が初めて原油を輸入したのは1993年。同年の外依存率は6%だったが、その後は毎年2ポイント程度上昇し続けた。09年には国内生産量そのものも28年ぶりで低下し、初めて対外依存率が50%を超えた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100204-00000013-scn-cn
中国人民ラジオ局によると、国家エネルギー資源局がこのほど、中国の原油自給率が50%を切ったことを明らかにしたため、「心理的」な影響が出ている。専門家は「心配しすぎだが、価格面で懸念すべき点はある」と指摘した。
同局によると、2009年における中国の原油生産量は1.89億トンで、輸入量は1.99億トンだった。中国が初めて原油を輸入したのは1993年。同年の外依存率は6%だったが、その後は毎年2ポイント程度上昇し続けた。09年には国内生産量そのものも28年ぶりで低下し、初めて対外依存率が50%を超えた。
しょうへいへいさん
93、100にも関連ニュースがあります。
かつて中国は50%以上を死守と言っていたのですが、数年前から諦めたと見えて、将来6割、7割を依存することになるという見解を表明してきました。
中国の石油企業は、企業ごとの可採年数が10年程度と短いので、開発投資に資金が集中するかもしれません。
特に、国内最大の油田である大慶油田(Daqing Oil field)の減産が激しく、実際は周辺やモンゴルあたりの細かい油田の生産量もすべて大慶油田の生産量として算出して、減産をごまかしているようです。
写真は以前に大慶に行った時のものです。油田の上に街があるので、まちの至る所にポンプがあります。
93、100にも関連ニュースがあります。
かつて中国は50%以上を死守と言っていたのですが、数年前から諦めたと見えて、将来6割、7割を依存することになるという見解を表明してきました。
中国の石油企業は、企業ごとの可採年数が10年程度と短いので、開発投資に資金が集中するかもしれません。
特に、国内最大の油田である大慶油田(Daqing Oil field)の減産が激しく、実際は周辺やモンゴルあたりの細かい油田の生産量もすべて大慶油田の生産量として算出して、減産をごまかしているようです。
写真は以前に大慶に行った時のものです。油田の上に街があるので、まちの至る所にポンプがあります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「宮崎正弘の国際ニュース・早読み」
平成22年(2010年)2月16日(火曜日)
通巻2877号
△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
あの人口過剰の中国で、なぜ労働者が不足しているのか
珠江デルタ、長江デルタなどの輸出基地で工場が稼働しないほどに
***************************************
労働者不足の理由はと聞かれて、公の見解は「高齢者」の急増にあるという。
復旦大学客員教授の王豊によれば、「09年に中国の高齢者人口は1億6900万人で、全人口比の12・79%、今後も年に1000万人が高齢者入りする」と予測する。
そして高齢化社会に突入した中国の労働問題は、今後「教育、年金、成長モデルの転換、労働生産性向上」などの諸問題となるだろう、とする。
(? あまりにキレイゴト過ぎませんか)。
中国政府は労働者不足を地理的要因と判断して、沿海部の工場を内陸部へ移転させ、地方で工場が出来れば、ちかくの農村からの出稼ぎ労働者を存分に吸収できるとした。
実際に安徽省、江西省、湖南省などへの移転が顕著に見られた。
しかし内陸部は労賃が安くても、ふたつの深刻な問題を抱える。
第一は労働の質の悪さ、第二は完成した製品をトラック、鉄道で沿海部の輸出港へ運搬する費用。倉庫代の追加などで、結局、内陸部が沿海部より二割ほど賃金が安くとも、総合的コストは変わらないことになる。
中国国務院発展研究センターは「農村から沿海部の工業部門への労働移動は2億3000万人」とはじき出した。
さて現下の中国でおきている労働者不足は上記のような事情で起きていることではない。
事態はもっと深刻であり、労働者不足は激甚である。
▲労働人口の構造的問題:リーマンショック「以前」と「以後」の顕著な差異
リーマンショック以前までの労働者不足は主として建築現場で見られた。
職を斡旋するブローカーが、労働者を刑務所のごとき施設へぶち込み、重労働をさせたあげく、約束の賃金を払わない(半年、一年ごとにまとめて支払う)。豚小屋のような宿舎に残飯のような食事まで給与からごっそり天引きされる。
これでは約束が違うとして、春節(旧正月休暇)が明けても地方から労働者は帰らなかった。
「宮崎正弘の国際ニュース・早読み」
平成22年(2010年)2月16日(火曜日)
通巻2877号
△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
あの人口過剰の中国で、なぜ労働者が不足しているのか
珠江デルタ、長江デルタなどの輸出基地で工場が稼働しないほどに
***************************************
労働者不足の理由はと聞かれて、公の見解は「高齢者」の急増にあるという。
復旦大学客員教授の王豊によれば、「09年に中国の高齢者人口は1億6900万人で、全人口比の12・79%、今後も年に1000万人が高齢者入りする」と予測する。
そして高齢化社会に突入した中国の労働問題は、今後「教育、年金、成長モデルの転換、労働生産性向上」などの諸問題となるだろう、とする。
(? あまりにキレイゴト過ぎませんか)。
中国政府は労働者不足を地理的要因と判断して、沿海部の工場を内陸部へ移転させ、地方で工場が出来れば、ちかくの農村からの出稼ぎ労働者を存分に吸収できるとした。
実際に安徽省、江西省、湖南省などへの移転が顕著に見られた。
しかし内陸部は労賃が安くても、ふたつの深刻な問題を抱える。
第一は労働の質の悪さ、第二は完成した製品をトラック、鉄道で沿海部の輸出港へ運搬する費用。倉庫代の追加などで、結局、内陸部が沿海部より二割ほど賃金が安くとも、総合的コストは変わらないことになる。
中国国務院発展研究センターは「農村から沿海部の工業部門への労働移動は2億3000万人」とはじき出した。
さて現下の中国でおきている労働者不足は上記のような事情で起きていることではない。
事態はもっと深刻であり、労働者不足は激甚である。
▲労働人口の構造的問題:リーマンショック「以前」と「以後」の顕著な差異
リーマンショック以前までの労働者不足は主として建築現場で見られた。
職を斡旋するブローカーが、労働者を刑務所のごとき施設へぶち込み、重労働をさせたあげく、約束の賃金を払わない(半年、一年ごとにまとめて支払う)。豚小屋のような宿舎に残飯のような食事まで給与からごっそり天引きされる。
これでは約束が違うとして、春節(旧正月休暇)が明けても地方から労働者は帰らなかった。
そこで中国企業はさかんに海外進出を加速する。これまではベトナムやバングラデシュに繊維産業の工場移転だったが、政府の資源戦略とセットになって、極東シベリア、パキスタン、アフガニスタンからアルジェリア、スーダン、アンゴラへとすすみ、当該地域でも労働者を奴隷のように酷使するため、あちこちに反中国暴動が頻発する。
リーマンショック以後、労働不足状況は輸出基地を襲った。
とくに広東省は中国全体の輸出の三分の一を占め、深センから東莞、広州へといたる一大ベルト地帯は日本、台湾、香港企業が工場進出。マカオから真珠海、中山、仏山から広州へと至るルートは主として香港企業が進出した。
広州周辺は自動車の部品工場がひしめく。
自動車部品、IT関連、コンピュータ部品を除き、玩具、スポーツシューズ、雑貨など「労賃が安い」輸出製品の一大生産拠点に異変が起きたのだ。
対米輸出が激減し、工場の労働者への不払いが生じた。一部に暴動、ストライキ、工場閉鎖、廃業など深刻な不況に直面した。広州では外国人労働者へも不満が向けられ、治安が悪化した。
09年春、政府のテコ入れにより、4兆元の財政出動があって景気が回復し、輸出はEU諸国、産油国、ならびにアフリカ向けが回復したが、現場では深刻な労働者不足に直面していた。
そうやすやすと労働者が集まらなくなったのである。
労働者はブローカーの甘言に乗らず、高い賃金をもとめて建設ブームに沸く地方都市や建設現場に散った。
このため沿海部、とくに珠江デルタの輸出基地には戻らず、多くの工場は生産設備の七割稼働が関の山、つねに労働者を募集するも集まらず、ついには最低賃金値上げに踏み切る(江蘇省が890元に値上げした)。
なんとか努力して労働者をあつめ、輸出を拡大してきたが、またまた「恐怖の春節」がやってきた。
経営側から見れば、正月休みがあけても労働者が戻らない懼れが高い。
労働側から見れば、奴隷のように働かされ、不衛生でぎゅうぎゅう詰めの宿泊施設、電気がない。冷蔵庫もない宿舎で、満足な食事は供されず、土日もなく働かされ、残業手当がつくかどうかも分からない職場には二度と帰らない、と決意するだろう。
かくて「躍進中国」の印象が強い輸出現場では、かつて体験したことのない労働不足という危機に陥った。
◎○◎○◎
リーマンショック以後、労働不足状況は輸出基地を襲った。
とくに広東省は中国全体の輸出の三分の一を占め、深センから東莞、広州へといたる一大ベルト地帯は日本、台湾、香港企業が工場進出。マカオから真珠海、中山、仏山から広州へと至るルートは主として香港企業が進出した。
広州周辺は自動車の部品工場がひしめく。
自動車部品、IT関連、コンピュータ部品を除き、玩具、スポーツシューズ、雑貨など「労賃が安い」輸出製品の一大生産拠点に異変が起きたのだ。
対米輸出が激減し、工場の労働者への不払いが生じた。一部に暴動、ストライキ、工場閉鎖、廃業など深刻な不況に直面した。広州では外国人労働者へも不満が向けられ、治安が悪化した。
09年春、政府のテコ入れにより、4兆元の財政出動があって景気が回復し、輸出はEU諸国、産油国、ならびにアフリカ向けが回復したが、現場では深刻な労働者不足に直面していた。
そうやすやすと労働者が集まらなくなったのである。
労働者はブローカーの甘言に乗らず、高い賃金をもとめて建設ブームに沸く地方都市や建設現場に散った。
このため沿海部、とくに珠江デルタの輸出基地には戻らず、多くの工場は生産設備の七割稼働が関の山、つねに労働者を募集するも集まらず、ついには最低賃金値上げに踏み切る(江蘇省が890元に値上げした)。
なんとか努力して労働者をあつめ、輸出を拡大してきたが、またまた「恐怖の春節」がやってきた。
経営側から見れば、正月休みがあけても労働者が戻らない懼れが高い。
労働側から見れば、奴隷のように働かされ、不衛生でぎゅうぎゅう詰めの宿泊施設、電気がない。冷蔵庫もない宿舎で、満足な食事は供されず、土日もなく働かされ、残業手当がつくかどうかも分からない職場には二度と帰らない、と決意するだろう。
かくて「躍進中国」の印象が強い輸出現場では、かつて体験したことのない労働不足という危機に陥った。
◎○◎○◎
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「宮崎正弘の国際ニュース・早読み」
平成22年(2010年)3月27日(土曜日)
通巻2921号 <3月26日発行>
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
中国の核兵器貯蔵の全容、米国シンクタンクが詳細な報告書
「プロジェクト2049」が暴いた中国の核兵器隠匿と運搬状況
****************************************
中国共産党にとって、これほど不愉快なことはないだろう。内部の国民どころか共産党の幹部にさえ教えていない核兵器の秘匿場所、その操作システムを余すところなく米国のシンクタンクが“ばらした”のだから。
バージニア州にある超党派のシンクタンク「プロジェクト2049」は中国の西北部、陝西省の太白山付近にある「基地22」という秘密都市(地図には出ていない)の地下に建設された大規模な核兵器貯蔵庫ならびに、核兵器の操作システムを報告書にまとめた。
このニュースを最初に伝えたのは「デフェンス・ニュース」(三月初旬号)。その後、産経新聞も3月18日付けで伝えた。中国内では英字版の「環境時報」が報じたのみ。
最大の衝撃はなにか?
秦嶺山脈のなかのひとつ、太白山をまるごと堀って、450キロ平方にも及ぶ貯蔵基地と鉄道による連絡網、まるで地下要塞がすでに完成している事実だ。
ここにおよそ400発の核弾頭を秘匿しているという。
しかも、この要塞は大陸間弾道弾発射基地としての地下サイロの役割ばかりか、秦嶺山脈のトンネルをあちこち縦横に繋げて、運搬ルートを多様化させ、列車とトラックにより中国の六カ所にあるミサイル発射基地と結んでいるという機動性向上の事実。
報告書をまとめた中心人物はマーク・ストークス元駐北京米国大使館付き駐在武官。ペンタゴンの専門家として知られるが、世界的は軍事評論の世界では無名に近い。
「おりしも米議会はオバマのヘルスケア騒動に明け暮れて、この衝撃的報告書は議論の片隅に押しやられたのも、米国内の保守派の政治利用を恐れたからだ」(アジアタイムズ、3月26日付け)。
むろん、防衛とは何かが分からない政治屋が防衛大臣をつとめる我が国では、この衝撃の報告書に関心が払われた形跡もない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「宮崎正弘の国際ニュース・早読み」
平成22年(2010年)3月27日(土曜日)
通巻2921号 <3月26日発行>
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
中国の核兵器貯蔵の全容、米国シンクタンクが詳細な報告書
「プロジェクト2049」が暴いた中国の核兵器隠匿と運搬状況
****************************************
中国共産党にとって、これほど不愉快なことはないだろう。内部の国民どころか共産党の幹部にさえ教えていない核兵器の秘匿場所、その操作システムを余すところなく米国のシンクタンクが“ばらした”のだから。
バージニア州にある超党派のシンクタンク「プロジェクト2049」は中国の西北部、陝西省の太白山付近にある「基地22」という秘密都市(地図には出ていない)の地下に建設された大規模な核兵器貯蔵庫ならびに、核兵器の操作システムを報告書にまとめた。
このニュースを最初に伝えたのは「デフェンス・ニュース」(三月初旬号)。その後、産経新聞も3月18日付けで伝えた。中国内では英字版の「環境時報」が報じたのみ。
最大の衝撃はなにか?
秦嶺山脈のなかのひとつ、太白山をまるごと堀って、450キロ平方にも及ぶ貯蔵基地と鉄道による連絡網、まるで地下要塞がすでに完成している事実だ。
ここにおよそ400発の核弾頭を秘匿しているという。
しかも、この要塞は大陸間弾道弾発射基地としての地下サイロの役割ばかりか、秦嶺山脈のトンネルをあちこち縦横に繋げて、運搬ルートを多様化させ、列車とトラックにより中国の六カ所にあるミサイル発射基地と結んでいるという機動性向上の事実。
報告書をまとめた中心人物はマーク・ストークス元駐北京米国大使館付き駐在武官。ペンタゴンの専門家として知られるが、世界的は軍事評論の世界では無名に近い。
「おりしも米議会はオバマのヘルスケア騒動に明け暮れて、この衝撃的報告書は議論の片隅に押しやられたのも、米国内の保守派の政治利用を恐れたからだ」(アジアタイムズ、3月26日付け)。
むろん、防衛とは何かが分からない政治屋が防衛大臣をつとめる我が国では、この衝撃の報告書に関心が払われた形跡もない。
この4月14日の朝に起きた中国の地震,中国西部の青海省玉樹チベット族自治州玉
樹県,震源地は玉樹県の中心地、結古鎮(人口約2万3000人)近くで、震源の深
さは約33キロ。2008年5月の四川大地震の震源地から600キロ余り離れてい
る。大変な惨事で,まだ全容も分からない状態であるが,激しいヒマラヤ造山運動の
中での地震であるが,注目すべきは,ダム開発の進む長江やメコン川の上流に当たる
。
殆どのニュースは,玉樹など,集落の悲惨な状況を伝えているが,その中にただ数行
だが,英国紙の記述で,中小規模のダムへの影響を伝えたものがある。ダムに大きな
亀裂が生じて,漏水が起こり,この対策に関係者が走り回っている,しかし,ダムの
大きさや状況の詳報は未だ伝えられていないと言う。この震源地の下流では,世界最
高のアーチダム,小湾ダムが工事中である。詳報を待ちたい。
【日刊 アジアのエネルギー最前線】中国青海省玉樹の地震でダムにも影響
http://my.reset.jp/adachihayao/index.htm
より
樹県,震源地は玉樹県の中心地、結古鎮(人口約2万3000人)近くで、震源の深
さは約33キロ。2008年5月の四川大地震の震源地から600キロ余り離れてい
る。大変な惨事で,まだ全容も分からない状態であるが,激しいヒマラヤ造山運動の
中での地震であるが,注目すべきは,ダム開発の進む長江やメコン川の上流に当たる
。
殆どのニュースは,玉樹など,集落の悲惨な状況を伝えているが,その中にただ数行
だが,英国紙の記述で,中小規模のダムへの影響を伝えたものがある。ダムに大きな
亀裂が生じて,漏水が起こり,この対策に関係者が走り回っている,しかし,ダムの
大きさや状況の詳報は未だ伝えられていないと言う。この震源地の下流では,世界最
高のアーチダム,小湾ダムが工事中である。詳報を待ちたい。
【日刊 アジアのエネルギー最前線】中国青海省玉樹の地震でダムにも影響
http://my.reset.jp/adachihayao/index.htm
より
中国の5月原油生産、石油精製量とも過去最高を更新
2010/06/11 16:58[エネルギー][時事通信社]
【北京ロイターES=時事】11日の中国国家統計局の発表によると、5月の国内原油生産量は前月比2.1%増の日量404万バレルと過去最高を更新した。
石油精製量も前月比0.7%増の日量843万バレルとなり、過去最高を更新した。前年同期比では14.8%増。
ガソリンの生産量は前月比6.5%増の651万6000トン、ディーゼルの生産量は同4.7%増の1330万1000トン。
5月の中国発電量、前年比18.9%増=国家統計局
2010/06/11 16:59[エネルギー][時事通信社]
【北京ロイターES=時事】11日の中国国家統計局の発表の暫定統計によると、5月の同国の発電量は前年同月比18.9%増の3404億7000万キロワット時だった。
内訳は、火力が21.6%増の2709億3000万キロワット時、水力が5.7%増の558億7000万キロワット時、原子力が2.4%減の52億9000万キロワット時、風力が122%増の40億4000万キロワット時。
2010/06/11 16:58[エネルギー][時事通信社]
【北京ロイターES=時事】11日の中国国家統計局の発表によると、5月の国内原油生産量は前月比2.1%増の日量404万バレルと過去最高を更新した。
石油精製量も前月比0.7%増の日量843万バレルとなり、過去最高を更新した。前年同期比では14.8%増。
ガソリンの生産量は前月比6.5%増の651万6000トン、ディーゼルの生産量は同4.7%増の1330万1000トン。
5月の中国発電量、前年比18.9%増=国家統計局
2010/06/11 16:59[エネルギー][時事通信社]
【北京ロイターES=時事】11日の中国国家統計局の発表の暫定統計によると、5月の同国の発電量は前年同月比18.9%増の3404億7000万キロワット時だった。
内訳は、火力が21.6%増の2709億3000万キロワット時、水力が5.7%増の558億7000万キロワット時、原子力が2.4%減の52億9000万キロワット時、風力が122%増の40億4000万キロワット時。
中国の寧夏回族自治区、10年内に石炭液化プラント着工へ=南アとの合弁−区長
2010/06/23 10:33[エネルギー][時事通信社]
【北京ロイターES=時事】中国の寧夏回族自治区の区長は21日、南アフリカ共和国の化学・エネルギー企業サソルが計画する石炭液化プラント建設について、2010年内に着工できるものと期待していると述べた。中国政府の承認はまだ下りていない。
区長は記者団に対し、「建設は今年末に開始できると見込んでいる」とし、専門家による調査が完了すれば、実際のスケジュールが明確になるだろうと説明した。
この石化液化プラント建設は中国の炭鉱最大手、神華集団とサソルの合弁事業。4月に実施した調査によれば、生産量は日量9万3000バレルの見通し。
2010/06/23 10:33[エネルギー][時事通信社]
【北京ロイターES=時事】中国の寧夏回族自治区の区長は21日、南アフリカ共和国の化学・エネルギー企業サソルが計画する石炭液化プラント建設について、2010年内に着工できるものと期待していると述べた。中国政府の承認はまだ下りていない。
区長は記者団に対し、「建設は今年末に開始できると見込んでいる」とし、専門家による調査が完了すれば、実際のスケジュールが明確になるだろうと説明した。
この石化液化プラント建設は中国の炭鉱最大手、神華集団とサソルの合弁事業。4月に実施した調査によれば、生産量は日量9万3000バレルの見通し。
中国エネルギー消費量、米国抜き世界最大に -YOMIURI ONLINE-
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20100720-OYT1T00383.htm
□□□
中国の2009年のエネルギー消費量が米国を抜き、世界最大となったことが19日、分かった。米ウォール・ストリート・ジャーナル紙(電子版)が報じた。
国際エネルギー機関(IEA)の最新データによると、昨年1年間の中国のエネルギー消費量は原油換算で22億5200万トンとなり、21億7000万トンだった米国を約4%上回った。原油や原子力、石炭などすべてのエネルギー源を原油換算した消費量は、米国が1900年初めから約100年間、首位の座にあった。IEAは、「中国の経済成長と製造業の急拡大を象徴している」としている。
□□□
いつかは交代するとは思ってましたが、、、
歴史的だぁ
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20100720-OYT1T00383.htm
□□□
中国の2009年のエネルギー消費量が米国を抜き、世界最大となったことが19日、分かった。米ウォール・ストリート・ジャーナル紙(電子版)が報じた。
国際エネルギー機関(IEA)の最新データによると、昨年1年間の中国のエネルギー消費量は原油換算で22億5200万トンとなり、21億7000万トンだった米国を約4%上回った。原油や原子力、石炭などすべてのエネルギー源を原油換算した消費量は、米国が1900年初めから約100年間、首位の座にあった。IEAは、「中国の経済成長と製造業の急拡大を象徴している」としている。
□□□
いつかは交代するとは思ってましたが、、、
歴史的だぁ
中国の海外での鉱物資源買収が急増
2010年 7月 22日 14:56 JST
http://jp.wsj.com/Economy/Global-Economy/node_84518
中国が、海外での鉱業資産の買収に成功するようになってきた。つい数年前までは海外の大型買収での失敗が目立っていたが、最近ではさまざまな中国企業が洗練化した手法で買収案件を次々に実現させている。
調査会社ディーロジックによると、中国・香港の企業が関与した昨年の海外での鉱業関係の買収・投資は130億ドル(約1兆1300億円)と、2005年の100倍に達した。
中国企業の海外の鉱業資産への買収・投資は今年も昨年と同様のペースで伸びており、今年これまでの買収・投資案件は76件を数え、総額で83億ドルに上っている。
米ヘリテージ財団のデレック・シザーズ氏によると、2014年には中国の鉱業関係の買収・投資は1000億ドルを超えると予想されている。ディーロジック によれば、昨年の鉱業部門の国際的な合併・買収(M&A)に占める中国勢の比率は金額で全体の3分の1となり、04年の1%以下、07年の7.4%から急 増した。
かつては中国による海外資産の買い取りは、大手の国有企業による完全買収が多く、無骨だとみられていた。しかし最近では、民間企 業の経営者から香港の投資家、さらには中国の政府系投資ファンド(SWF)まで、合弁事業や少数株式の取得など柔軟かつ洗練された手法を駆使して、投資に 乗り出している。
中国が次々に鉱物資源の買収を成功させるようになった時期は、世界的な金融危機と重なっている。この時期の鉱物資源関連の国際的なM&Aのうち、中国が3分の1を締めた。07年には7.4%、04年には1%にも満たなかった。
中国銀行の投資銀行部門の鉱業チーム責任者によれば、金融危機を受けて、それまでほとんど拒否されていた中国の投資家による海外投資が実現するようになった。「鉱業会社の方がプロジェクトの資金手当てのため中国に期待するようになっている」という。
記者: Phred Dvorak
2010年 7月 22日 14:56 JST
http://jp.wsj.com/Economy/Global-Economy/node_84518
中国が、海外での鉱業資産の買収に成功するようになってきた。つい数年前までは海外の大型買収での失敗が目立っていたが、最近ではさまざまな中国企業が洗練化した手法で買収案件を次々に実現させている。
調査会社ディーロジックによると、中国・香港の企業が関与した昨年の海外での鉱業関係の買収・投資は130億ドル(約1兆1300億円)と、2005年の100倍に達した。
中国企業の海外の鉱業資産への買収・投資は今年も昨年と同様のペースで伸びており、今年これまでの買収・投資案件は76件を数え、総額で83億ドルに上っている。
米ヘリテージ財団のデレック・シザーズ氏によると、2014年には中国の鉱業関係の買収・投資は1000億ドルを超えると予想されている。ディーロジック によれば、昨年の鉱業部門の国際的な合併・買収(M&A)に占める中国勢の比率は金額で全体の3分の1となり、04年の1%以下、07年の7.4%から急 増した。
かつては中国による海外資産の買い取りは、大手の国有企業による完全買収が多く、無骨だとみられていた。しかし最近では、民間企 業の経営者から香港の投資家、さらには中国の政府系投資ファンド(SWF)まで、合弁事業や少数株式の取得など柔軟かつ洗練された手法を駆使して、投資に 乗り出している。
中国が次々に鉱物資源の買収を成功させるようになった時期は、世界的な金融危機と重なっている。この時期の鉱物資源関連の国際的なM&Aのうち、中国が3分の1を締めた。07年には7.4%、04年には1%にも満たなかった。
中国銀行の投資銀行部門の鉱業チーム責任者によれば、金融危機を受けて、それまでほとんど拒否されていた中国の投資家による海外投資が実現するようになった。「鉱業会社の方がプロジェクトの資金手当てのため中国に期待するようになっている」という。
記者: Phred Dvorak
中国、50カ国以上で資源に関与 米国防総省の報告書
【ワシントン共同】中国が、原油などの天然資源を世界中から幅広く獲得するため、50カ国以上でエネルギープロジェクトに投資したり、開発にかかわっていることが19日までに分かった。米国防総省が、中国の軍事動向に関する年次報告書の中で明らかにした。
報告書は「エネルギー自給は既に中国にとって選択肢ではない」と指摘し、2015年までに原油の3分の2を輸入するようになると予測。中国がペルシャ湾、中央アジア、アフリカ、北米で原油の獲得を続けるとしている。
また08年には80%以上がマラッカ海峡を通る海上輸送だったが、カザフスタンやミャンマーなどからの陸上パイプライン建設を行い、リスク分散を積極的に進めることが中国のエネルギー戦略だと分析している。
2010/08/20 07:45
【ワシントン共同】中国が、原油などの天然資源を世界中から幅広く獲得するため、50カ国以上でエネルギープロジェクトに投資したり、開発にかかわっていることが19日までに分かった。米国防総省が、中国の軍事動向に関する年次報告書の中で明らかにした。
報告書は「エネルギー自給は既に中国にとって選択肢ではない」と指摘し、2015年までに原油の3分の2を輸入するようになると予測。中国がペルシャ湾、中央アジア、アフリカ、北米で原油の獲得を続けるとしている。
また08年には80%以上がマラッカ海峡を通る海上輸送だったが、カザフスタンやミャンマーなどからの陸上パイプライン建設を行い、リスク分散を積極的に進めることが中国のエネルギー戦略だと分析している。
2010/08/20 07:45
中国の自動車台数、2020年に2億台突破へ=政府高官
2010年 09月 6日 11:08 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-17096720100906
[上海 6日 ロイター] 中国工業情報省のWang Fuchang次官は5日、自動車業界の会議で、中国の自動車台数は2020年に2億台を上回るとの見通しを示した。6日付の中国証券報が報じた。
同次官は、自動車台数の大幅増加が、環境とエネルギー安全保障に関する問題を提起すると指摘した。
中国は、世界の自動車業界が昨年の販売台数の急激な落ち込みからの回復に依然苦闘するなか、好調な販売台数を上げている。
第2・四半期の初めごろから減速の兆候が見られてきたものの、主に当局による低燃費車向け補助金制度に支援されて8月には力強く回復した。
2010年 09月 6日 11:08 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-17096720100906
[上海 6日 ロイター] 中国工業情報省のWang Fuchang次官は5日、自動車業界の会議で、中国の自動車台数は2020年に2億台を上回るとの見通しを示した。6日付の中国証券報が報じた。
同次官は、自動車台数の大幅増加が、環境とエネルギー安全保障に関する問題を提起すると指摘した。
中国は、世界の自動車業界が昨年の販売台数の急激な落ち込みからの回復に依然苦闘するなか、好調な販売台数を上げている。
第2・四半期の初めごろから減速の兆候が見られてきたものの、主に当局による低燃費車向け補助金制度に支援されて8月には力強く回復した。
第11次5ヵ年規画期の新規製油能力はすべて増加した自動車が消費 (10/09/07)
2010/09/10
http://www.asiam.co.jp/news_oilgas.php?topic=013416
国家発展改革委員会産業協調司の陳斌司長は9月4日、第11次5ヵ年規画期に中国の製油能力は約1億トン増えたが、そのほとんどは新たに増えた自動車が消費したと述べた。
陳斌司長によると、2009年の中国の自動車保有台数は6,200万台に上り、1億3,480万トンの石油製品を消費した。これはガソリン・軽油総生産量の63.2%に当たる。2003年比では1,600万トンの純増。うち自動車用ガソリン消費量は6,260万トン、ガソリン生産量7,192万トンの87%を占めた。また、自動車用軽油消費量は7,220万トンで、軽油総生産量1億4,124万トンのうち51%を占めた。中国は石油消費の大きい車種の比率が高く、省エネ型自動車の比率は小さい。乗用車1台当たりの石油消費は先進国の水準をはるかに上回っている。
自動車市場の現在の成長スピードで計算すると、1年間で増える自動車が消費する石油製品は2,000万トンの製油所の新規建設に相当する。
陳斌司長は、中国の自動車産業の発展は希望に満ちているが、エネルギー供給の増加や交通渋滞、環境悪化などの圧力も大きいと指摘し、消費の促進と社会発展の調和を取ることは大きな難題になっていると言う。構造調整を加速し、自動車消費の伸びと社会の協調的な発展を促進することは、自動車産業にとって大きな課題である。
(中国石油報 9月7日)
2010/09/10
http://www.asiam.co.jp/news_oilgas.php?topic=013416
国家発展改革委員会産業協調司の陳斌司長は9月4日、第11次5ヵ年規画期に中国の製油能力は約1億トン増えたが、そのほとんどは新たに増えた自動車が消費したと述べた。
陳斌司長によると、2009年の中国の自動車保有台数は6,200万台に上り、1億3,480万トンの石油製品を消費した。これはガソリン・軽油総生産量の63.2%に当たる。2003年比では1,600万トンの純増。うち自動車用ガソリン消費量は6,260万トン、ガソリン生産量7,192万トンの87%を占めた。また、自動車用軽油消費量は7,220万トンで、軽油総生産量1億4,124万トンのうち51%を占めた。中国は石油消費の大きい車種の比率が高く、省エネ型自動車の比率は小さい。乗用車1台当たりの石油消費は先進国の水準をはるかに上回っている。
自動車市場の現在の成長スピードで計算すると、1年間で増える自動車が消費する石油製品は2,000万トンの製油所の新規建設に相当する。
陳斌司長は、中国の自動車産業の発展は希望に満ちているが、エネルギー供給の増加や交通渋滞、環境悪化などの圧力も大きいと指摘し、消費の促進と社会発展の調和を取ることは大きな難題になっていると言う。構造調整を加速し、自動車消費の伸びと社会の協調的な発展を促進することは、自動車産業にとって大きな課題である。
(中国石油報 9月7日)
中国、原発拡大のスピード緩め安全優先に軸足を移す?
【コラム】 2010/03/05(金) 13:18
中国が、原子力発電の拡大から安全の確保に軸足を移す動きを見せている。環境保護部の原子力安全管理部(核安全管理司)は2月5日、中国核工業集団公司、中国広東核電集団公司、中国電力投資集団公司、国家核電技術有限公司に対して、原子力発電所の建設段階での安全を強化することを目的とした通知を「国家核安全局」名で出した。
「放射性汚染防止法」、「民用核施設安全監督管理条例」、「民用核安全設備監督管理条例」を根拠として、原子力発電所の建設段階での品質を高め、安全を確保するのがねらいだ。4社だけを対象にしているのは、この4社が原子力発電所の建設・運転にあたっての実質的な中心企業であるためだ。
通知はまず4社に対して、原子力発電所の建設段階の品質と安全に関する責任を全面的に負うことを要求している。また、設計や調達、施工、調整試験を含む、原子炉部分の工事元請け契約をプラントメーカーと締結するとともに、契約の中で双方が建設段階における安全と品質の責任と義務を負うことをあらかじめ取り決める必要があるとした。
そのうえで、元請け業者が原子炉部分の工事において直接責任を負い、取り決めにしたがい、それぞれの責任と義務を果たすことを求めている。通知では、元請け業者に対して、原子炉部分および安全設備の設計管理、調達、施工管理を単独でできる能力があることを条件として定めている。そして、4社は、こうした資質を持たない業者に仕事を任せてはならないと明確に規定した。
元請け業者に対して要求している条件は、きわめて具体的だ。まず、元請け業者は、要員を最低でも1000名確保する必要があるとしたうえで、このうち設計管理要員100名、プロジェクト管理要員100名、調達要員200名、現場施工管理要員200名、調整・試験要員200名を確保しなければならないとしている。また、大学本科以上の学歴を持った人員が最低でも70%、各工程の人員の中で2年以上の経験を持った人員が最低でも50%を占める必要があるとした。
原子力発電所の建設を同時に複数請け負う業者も当然でてくる。通知は、1件のプロジェクトに参加する人員は最低でも500名を確保するとしたうえで、設備の据付と調整・試験等、工事がピークに達する時点での専任要員については最低でも200名、このうち原子力発電所の建設経験を持った人員が全体の50%を上回ることが必要としている。このほか、品質保証専任の要員を最低でも30名確保することを要求している。
さらに、元請け業者に求められる要件として、法人資格を有することや、民事用原子力安全設備設計許可証を保有すること、国務院の主管部門が発給する資格証書、たとえば「核工業行業設計甲級資質」、「核電工程諮詢甲級資質」、「特殊設備設計(圧力容器等)許可証」等を保有することなどをあげた。この10年内に、原子炉部分および安全設備の設計あるいは設計管理、施工管理、調整・試験で実績があることも要件としている。
こうした条件をクリア―できる中国国内の原子力発電プラントメーカーは限られてくる。しかも、実力があっても、抱えている人員の数によって請け負うことができるプロジェクトの件数も決まってしまう。各プラントメーカーが何件の原子力発電プロジェクトを平行してできるかは、各プロジェクトの進捗具合によっても違ってくると思われるが、今回の通知は、当然、各プラントメーカーがどれだけの要員を抱えているかを承知したうえでのものであり、“入口規制”による安全の担保という見方もできる。
【コラム】 2010/03/05(金) 13:18
中国が、原子力発電の拡大から安全の確保に軸足を移す動きを見せている。環境保護部の原子力安全管理部(核安全管理司)は2月5日、中国核工業集団公司、中国広東核電集団公司、中国電力投資集団公司、国家核電技術有限公司に対して、原子力発電所の建設段階での安全を強化することを目的とした通知を「国家核安全局」名で出した。
「放射性汚染防止法」、「民用核施設安全監督管理条例」、「民用核安全設備監督管理条例」を根拠として、原子力発電所の建設段階での品質を高め、安全を確保するのがねらいだ。4社だけを対象にしているのは、この4社が原子力発電所の建設・運転にあたっての実質的な中心企業であるためだ。
通知はまず4社に対して、原子力発電所の建設段階の品質と安全に関する責任を全面的に負うことを要求している。また、設計や調達、施工、調整試験を含む、原子炉部分の工事元請け契約をプラントメーカーと締結するとともに、契約の中で双方が建設段階における安全と品質の責任と義務を負うことをあらかじめ取り決める必要があるとした。
そのうえで、元請け業者が原子炉部分の工事において直接責任を負い、取り決めにしたがい、それぞれの責任と義務を果たすことを求めている。通知では、元請け業者に対して、原子炉部分および安全設備の設計管理、調達、施工管理を単独でできる能力があることを条件として定めている。そして、4社は、こうした資質を持たない業者に仕事を任せてはならないと明確に規定した。
元請け業者に対して要求している条件は、きわめて具体的だ。まず、元請け業者は、要員を最低でも1000名確保する必要があるとしたうえで、このうち設計管理要員100名、プロジェクト管理要員100名、調達要員200名、現場施工管理要員200名、調整・試験要員200名を確保しなければならないとしている。また、大学本科以上の学歴を持った人員が最低でも70%、各工程の人員の中で2年以上の経験を持った人員が最低でも50%を占める必要があるとした。
原子力発電所の建設を同時に複数請け負う業者も当然でてくる。通知は、1件のプロジェクトに参加する人員は最低でも500名を確保するとしたうえで、設備の据付と調整・試験等、工事がピークに達する時点での専任要員については最低でも200名、このうち原子力発電所の建設経験を持った人員が全体の50%を上回ることが必要としている。このほか、品質保証専任の要員を最低でも30名確保することを要求している。
さらに、元請け業者に求められる要件として、法人資格を有することや、民事用原子力安全設備設計許可証を保有すること、国務院の主管部門が発給する資格証書、たとえば「核工業行業設計甲級資質」、「核電工程諮詢甲級資質」、「特殊設備設計(圧力容器等)許可証」等を保有することなどをあげた。この10年内に、原子炉部分および安全設備の設計あるいは設計管理、施工管理、調整・試験で実績があることも要件としている。
こうした条件をクリア―できる中国国内の原子力発電プラントメーカーは限られてくる。しかも、実力があっても、抱えている人員の数によって請け負うことができるプロジェクトの件数も決まってしまう。各プラントメーカーが何件の原子力発電プロジェクトを平行してできるかは、各プロジェクトの進捗具合によっても違ってくると思われるが、今回の通知は、当然、各プラントメーカーがどれだけの要員を抱えているかを承知したうえでのものであり、“入口規制”による安全の担保という見方もできる。
今回の通知が、中国の原子力発電計画をスローダウンさせることにつながるかどうかについては判断できない。しかし、2010年に入り、中国の原子力界で安全確保が話題にのぼりだしたことは間違いない。
中国核能行業(産業)協会の張華祝・理事長は2月、「中国能源報」の記者とのインタビューの中で、原子力安全は常におろそかにすることができない重要な問題であると語った。同理事長は、インタビューで興味深い発言をしている。2009年の中国原子力界の大きな動きを紹介する中で、原子力発電の国産化において大きな進展が見られたとする一方で、原子力発電所の安全と工事の品質が一気に重要視されるようになったという指摘だ。
中国の原子力発電所の稼働率は世界的に見ても優れている。ただし、稼働中の原子力発電所は、秦山(国産化率70%)を除いて、ほとんどが輸入した原子力発電所だ。中国国内ではこれから、国産化率を高めた原子力発電所が続々と建設・運転に入る。
中国で建設中の原子力発電所は昨年末時点で21基、合計設備容量では2348万キロワットとなった。運転中(908万キロワット)と合わせると32基、3256万キロワットに達する。昨年は新規に9基が着工した。今年も1月に入って福建省の寧徳・3号機が着工した。中国では、これから毎年、8基程度の原子力発電所が着工するとみられている。
中国国家エネルギー局の張国宝・局長は、新華社とのインタビュー(3月2日)で、米国はかつてピーク時に61基、またフランスは40基の原子力発電所を同時に建設していたとする一方で、原子力発電の拡大も必要だが、原子力安全(の確保)はもっと重要との見解を示した。
2009年あたりから、中国の原子力発電計画の拠り所となっている「原子力発電中長期発展規画(計画)」の改定が話題にのぼりはじめた。当初、09年内にも公表されるとの見方もあったが、まだ公表には至っていない。また、現行規画で4000万キロワットとなっていた2020年時点における稼働中の原子力発電目標を改定では7000万〜8000万キロワットに上方修正するとの関係者の発言が目立った。ところが、最近の報道では、2020年の目標は6000万キロワット程度になるのではないかとの関係者の発言が紹介されている。
国家エネルギー局が中国初の「原子力安全規画(計画)」の策定に着手したというニュースもある(2月3日付「中国能源網」)。原子力安全については、「原子力発電中長期発展規画」や「原子力産業『第11次5カ年』発展規画」の中でも言及されているが、単独で原子力安全に関する国家計画の策定に着手した背景には、原子力安全を最重要視する中国政府の方針がある。
同規画は、まだドラフト作成の初期段階にある。中国の原子力規制当局である「国家核安全局」の関係者は、作成作業に参加する意向を示している。原子力安全規画の作成が、国家エネルギー局によって行われているのは、いかにも中国的だが、環境保護部原子力安全管理部(核安全管理司)による今回の通知は、規制当局として現在できる最良の決定を下したと見るべきであろう。
最後に「国家核安全局」について簡単に紹介しておこう。同局の局長を務める環境保護部の李干傑・副部長は、原子力規制当局の現状として、人材が不足していることに加えて技術手段が立ち遅れ、しかも予算が十分ではないなどの課題を抱えていると指摘している。
原子力安全の監督・管理に従事するスタッフは300名程度という。これに対して、1件の新規プロジェクトに要する審査要員は年間50名、稼働中のユニットに要する審査要員は年間20名、また稼働中のユニットでは1基あたり3名の現地検査官が必要という。こうしたことから、現在の300名体制を1000人規模まで拡大する計画が浮上してきている。(執筆者:窪田秀雄 日本テピア・テピア総合研究所副所長 編集担当:サーチナ・メディア事業部)
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=0305&f=column_0305_004.shtml
中国核能行業(産業)協会の張華祝・理事長は2月、「中国能源報」の記者とのインタビューの中で、原子力安全は常におろそかにすることができない重要な問題であると語った。同理事長は、インタビューで興味深い発言をしている。2009年の中国原子力界の大きな動きを紹介する中で、原子力発電の国産化において大きな進展が見られたとする一方で、原子力発電所の安全と工事の品質が一気に重要視されるようになったという指摘だ。
中国の原子力発電所の稼働率は世界的に見ても優れている。ただし、稼働中の原子力発電所は、秦山(国産化率70%)を除いて、ほとんどが輸入した原子力発電所だ。中国国内ではこれから、国産化率を高めた原子力発電所が続々と建設・運転に入る。
中国で建設中の原子力発電所は昨年末時点で21基、合計設備容量では2348万キロワットとなった。運転中(908万キロワット)と合わせると32基、3256万キロワットに達する。昨年は新規に9基が着工した。今年も1月に入って福建省の寧徳・3号機が着工した。中国では、これから毎年、8基程度の原子力発電所が着工するとみられている。
中国国家エネルギー局の張国宝・局長は、新華社とのインタビュー(3月2日)で、米国はかつてピーク時に61基、またフランスは40基の原子力発電所を同時に建設していたとする一方で、原子力発電の拡大も必要だが、原子力安全(の確保)はもっと重要との見解を示した。
2009年あたりから、中国の原子力発電計画の拠り所となっている「原子力発電中長期発展規画(計画)」の改定が話題にのぼりはじめた。当初、09年内にも公表されるとの見方もあったが、まだ公表には至っていない。また、現行規画で4000万キロワットとなっていた2020年時点における稼働中の原子力発電目標を改定では7000万〜8000万キロワットに上方修正するとの関係者の発言が目立った。ところが、最近の報道では、2020年の目標は6000万キロワット程度になるのではないかとの関係者の発言が紹介されている。
国家エネルギー局が中国初の「原子力安全規画(計画)」の策定に着手したというニュースもある(2月3日付「中国能源網」)。原子力安全については、「原子力発電中長期発展規画」や「原子力産業『第11次5カ年』発展規画」の中でも言及されているが、単独で原子力安全に関する国家計画の策定に着手した背景には、原子力安全を最重要視する中国政府の方針がある。
同規画は、まだドラフト作成の初期段階にある。中国の原子力規制当局である「国家核安全局」の関係者は、作成作業に参加する意向を示している。原子力安全規画の作成が、国家エネルギー局によって行われているのは、いかにも中国的だが、環境保護部原子力安全管理部(核安全管理司)による今回の通知は、規制当局として現在できる最良の決定を下したと見るべきであろう。
最後に「国家核安全局」について簡単に紹介しておこう。同局の局長を務める環境保護部の李干傑・副部長は、原子力規制当局の現状として、人材が不足していることに加えて技術手段が立ち遅れ、しかも予算が十分ではないなどの課題を抱えていると指摘している。
原子力安全の監督・管理に従事するスタッフは300名程度という。これに対して、1件の新規プロジェクトに要する審査要員は年間50名、稼働中のユニットに要する審査要員は年間20名、また稼働中のユニットでは1基あたり3名の現地検査官が必要という。こうしたことから、現在の300名体制を1000人規模まで拡大する計画が浮上してきている。(執筆者:窪田秀雄 日本テピア・テピア総合研究所副所長 編集担当:サーチナ・メディア事業部)
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=0305&f=column_0305_004.shtml
中国、2020 年に水力発電設備容量を3.8 億kW へ
国家エネルギー局の張国宝局長は8 月26 日、北京で開かれた「中国水力発電100 周年記
念大会」で講演し、2020 年の省エネ・排出削減目標を達成するため、2020 年までに水力発
電設備容量を現在の2 億kW から 3.8 億kW へ拡大する方針を明らかにした。
水力は石炭火力に次ぐ中国の主要な一次エネルギー源で、国内で開発利用が可能な水力
資源は5 億4,200 万kW と見られている。張局長は、現在の発電量は1 億8,500 億kW で利
用率は34%前後にとどまり先進国の60-70%の利用率に及ばない点を指摘し、設備容量の
拡大は可能との考えを強調した。
中国、次世代新エネルギー自動車開発の官民企業連合が成立
国務院国有資産管理委員会の主導により中国国有企業と自動車メーカー等16 社が共同で
次世代新エネルギー自動車の研究開発を行う企業連合が結成された。第一汽車、東風汽車、
長安汽車の自動車メーカー3 社の他、電機の東方電気、国家電網、南方電網、中国石化等の
エネルギー企業が参加する。
各社の経営資源を持ち寄って共同研究開発を行い、次世代新エネルギー自動車の技術標
準を早期に確立することを目指す。そのうえで国際的競争力をもつ電気自動車を製品化し
ブランド育成を図る。2010 年8 月18 日付「上海証券報」が伝えた。
中国では政府主導による電気自動車普及のインフラ整備が進む。国家電網は今年末まで
に、75 ヵ所の充電ステーションと6,209 ヵ所の簡易充電スタンドを整備する。中国石化は
北京市をモデル地区として、市内の全大型給油所の「油・電総合サービス化」を進め、順
次全国へ展開する計画を明らかにしている。
中国政府、石炭生産の総量規制を導入へ
中国国家エネルギー局の吴吟副局長は、先頃行われた国際石炭発展フォーラム組織委員
会議で、「12 次5 ヵ年」期間(2011-2015 年)に石炭生産の総量規制を導入する考えを明ら
かにした。2010 年8 月13 日付「中国証券報」が伝えた。
中国の石炭産出量は2009 年に30 億トンを超え、世界全体の生産量の4 割強に達した。
中国の石炭産業は集中度が低く、上位10 社の生産量の合計は国全体の20%程度で、オース
トラリアの50%、南アフリカの60%と比較して低い。吴吟副局長は、生産効率を向上させ
環境面への影響を抑えるため、合併の推進により産業集中度を高めることが「12 次5 ヵ年」
期間中の課題との認識を示した。
中国の石油輸入依存度が55%を超過
中国石化工業連合会はこのほど、今年上半期(1 月〜6 月)までの石油消費量が2 億2,000
万トンに達し前年同期に比べて15.1%の増加を示したとしたうえで、輸入依存度が55.14%
に達したことを明らかにした。石油の輸入依存度は、前年同期に比べて4.2 ポイント上昇
した。8 月11 日付「新華網」が伝えた。
http://www.tepia.co.jp/image/tepia_monthly/tepia-monthly201008.pdf
より
国家エネルギー局の張国宝局長は8 月26 日、北京で開かれた「中国水力発電100 周年記
念大会」で講演し、2020 年の省エネ・排出削減目標を達成するため、2020 年までに水力発
電設備容量を現在の2 億kW から 3.8 億kW へ拡大する方針を明らかにした。
水力は石炭火力に次ぐ中国の主要な一次エネルギー源で、国内で開発利用が可能な水力
資源は5 億4,200 万kW と見られている。張局長は、現在の発電量は1 億8,500 億kW で利
用率は34%前後にとどまり先進国の60-70%の利用率に及ばない点を指摘し、設備容量の
拡大は可能との考えを強調した。
中国、次世代新エネルギー自動車開発の官民企業連合が成立
国務院国有資産管理委員会の主導により中国国有企業と自動車メーカー等16 社が共同で
次世代新エネルギー自動車の研究開発を行う企業連合が結成された。第一汽車、東風汽車、
長安汽車の自動車メーカー3 社の他、電機の東方電気、国家電網、南方電網、中国石化等の
エネルギー企業が参加する。
各社の経営資源を持ち寄って共同研究開発を行い、次世代新エネルギー自動車の技術標
準を早期に確立することを目指す。そのうえで国際的競争力をもつ電気自動車を製品化し
ブランド育成を図る。2010 年8 月18 日付「上海証券報」が伝えた。
中国では政府主導による電気自動車普及のインフラ整備が進む。国家電網は今年末まで
に、75 ヵ所の充電ステーションと6,209 ヵ所の簡易充電スタンドを整備する。中国石化は
北京市をモデル地区として、市内の全大型給油所の「油・電総合サービス化」を進め、順
次全国へ展開する計画を明らかにしている。
中国政府、石炭生産の総量規制を導入へ
中国国家エネルギー局の吴吟副局長は、先頃行われた国際石炭発展フォーラム組織委員
会議で、「12 次5 ヵ年」期間(2011-2015 年)に石炭生産の総量規制を導入する考えを明ら
かにした。2010 年8 月13 日付「中国証券報」が伝えた。
中国の石炭産出量は2009 年に30 億トンを超え、世界全体の生産量の4 割強に達した。
中国の石炭産業は集中度が低く、上位10 社の生産量の合計は国全体の20%程度で、オース
トラリアの50%、南アフリカの60%と比較して低い。吴吟副局長は、生産効率を向上させ
環境面への影響を抑えるため、合併の推進により産業集中度を高めることが「12 次5 ヵ年」
期間中の課題との認識を示した。
中国の石油輸入依存度が55%を超過
中国石化工業連合会はこのほど、今年上半期(1 月〜6 月)までの石油消費量が2 億2,000
万トンに達し前年同期に比べて15.1%の増加を示したとしたうえで、輸入依存度が55.14%
に達したことを明らかにした。石油の輸入依存度は、前年同期に比べて4.2 ポイント上昇
した。8 月11 日付「新華網」が伝えた。
http://www.tepia.co.jp/image/tepia_monthly/tepia-monthly201008.pdf
より
中国海洋石油、米チェサピークの資産権益を取得へ −ロイター通信−
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-17614120101011
中国海洋石油(CNOOC)(0883.HK: 株価, 企業情報, レポート)は、米天然ガス生産会社チェサピーク・エナジー(CHK.N: 株価, 企業情報, レポート)がテキサス州南部に保有するシェール層、イーグル・フォードの33.3%の権益を約11億ドルで取得する方針で合意した。
両社によると、CNOOCはこれに加え、チェサピークの掘削やその他の関連費用の75%を10億8000万ドルまで支払うことで合意。チェサピークの試算によると、2012年末までに同額に達する見通し。
中国の急速な経済成長を背景に、アナリストの間ではCNOOCが今後、積極的な生産拡張計画の一環として海外投資を拡大させる可能性があると指摘。Mirae Asset Securitiesのアジア・エネルギー・リサーチ部門責任者ゴードン・クワン氏は、同社がカナダのオイルサンド業界やブラジルの深海油田開発で存在感を増してくる可能性があると述べた。
米中間では大幅な貿易不均衡をめぐって緊張感が高まっているが、CNOOCとチェサピークの合意はユノカルの場合とは異なり買収ではなく資産権益の取得であることから、当局の承認が下りる可能性が比較的高いとみられている。
天然ガスの価格が低迷する一方で、シェールガスへの関心は高まりつつある。シェールガスは米国のガス生産の15─20%を占めるが、今後4倍に増加すると予想され、エネルギー各社による競争が激化している。
シェールガスが今後4倍に増加って、本当ですかね?
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-17614120101011
中国海洋石油(CNOOC)(0883.HK: 株価, 企業情報, レポート)は、米天然ガス生産会社チェサピーク・エナジー(CHK.N: 株価, 企業情報, レポート)がテキサス州南部に保有するシェール層、イーグル・フォードの33.3%の権益を約11億ドルで取得する方針で合意した。
両社によると、CNOOCはこれに加え、チェサピークの掘削やその他の関連費用の75%を10億8000万ドルまで支払うことで合意。チェサピークの試算によると、2012年末までに同額に達する見通し。
中国の急速な経済成長を背景に、アナリストの間ではCNOOCが今後、積極的な生産拡張計画の一環として海外投資を拡大させる可能性があると指摘。Mirae Asset Securitiesのアジア・エネルギー・リサーチ部門責任者ゴードン・クワン氏は、同社がカナダのオイルサンド業界やブラジルの深海油田開発で存在感を増してくる可能性があると述べた。
米中間では大幅な貿易不均衡をめぐって緊張感が高まっているが、CNOOCとチェサピークの合意はユノカルの場合とは異なり買収ではなく資産権益の取得であることから、当局の承認が下りる可能性が比較的高いとみられている。
天然ガスの価格が低迷する一方で、シェールガスへの関心は高まりつつある。シェールガスは米国のガス生産の15─20%を占めるが、今後4倍に増加すると予想され、エネルギー各社による競争が激化している。
シェールガスが今後4倍に増加って、本当ですかね?
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ピークオイル 更新情報
ピークオイルのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90068人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208325人
- 3位
- 酒好き
- 170699人