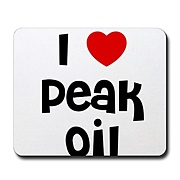[画像] "WEO2006" "THE PRIZE" "LIMIT TO GROWTH"
このコミュのレポートや書き込みに使用している私の蔵書。
「○○はどんな内容なんですか?」などの質問や、「こんな本もありますよ」などの情報提供など歓迎。
管理人のお勧め度(***)をつけてみました(11/19)
■石油業界
『石油の生産量はピークに来たのか〜ピークオイルの本質と21世紀のエネルギー〜』***
根岸敏雄 石油文化社 2006/4/25
■科学技術論
『石油最終争奪戦〜世界を震撼させる『ピークオイル』の真実〜』***
石井吉徳 B&Tブックス 日刊工業新聞社 2006/7/30
『ピーク・オイル・パニック〜迫る石油危機と代替エネルギーの可能性〜』*
ジェレミーレゲット 作品社 2006/9/25
『豊かな石油時代が終わる〜人類は何処へ行くのか〜』*
(社)日本工学アカデミー・環境フォーラム偏 丸善 2004/10/20
『エネルギー〜風と太陽へのソフトランディング〜』
小島紀徳 日本評論社 2003/12/10
『地球環境 危機からの脱出〜科学技術が人類を救う〜』
レスター・ブラウン/デヴィッド・ハウエル/黒川清/薬師寺泰蔵/十市勉/植田和弘/藤嶋昭/松井孝典 ウェッジ選書 2005/7/29
『エネルギー・環境・社会〜現代技術社会論〜』
京都大学大学院エネルギー科学研究科 エネルギー社会・環境科学専攻 丸善 2004/3/30
『新エネルギー最前線〜環境調和型エネルギーシステムの構築を目指して〜』**
吉川暹[編] 化学同人 2006/9/30
『誤解だらけのエネルギー問題』**
浜松照秀 日刊工業新聞社 2006/3/27
■国際機関
『世界のエネルギー展望2004』***
OECD/IEA エネルギーフォーラム 2005/12/8
『国際エネルギー・レジーム〜エネルギー・地球温暖化問題と知識〜』
松井賢一 エネルギーフォーラム 2006/2/20
■経済系
『石油を読む〜地政学的発想を超えて〜』***
藤和彦 日経文庫 2005/2/15
『富の未来(上)(下)』*
アルビン・トフラー/ハイジ・トフラー 講談社 2006/6/7
『知られていない原油価格高騰の謎』*
芥田知至 技術評論社 2006/5/5
『資源インフレ〜日本を襲う経済リスクの正体』
柴田明夫 日本経済新聞社 2006/7/10
『市場対国家〜世界を作り変える歴史的攻防〜(上)(下)』
ダニエル・ヤーギン/ジョゼフ・スタニスロー 日系ビジネス人文庫 2001/11/1
『石油の経済学〜原油高騰に打ち勝つ〜』
萩田穣 アートデイズ 2005/1/10
『THE FINAL ENERGY CRISIS』
Andrew McKillop/Sheila Newman PLUTO PRESS 2005/7/8
『中国のエネルギー動向〜海外石油・天然ガス獲得の現状/中国のエネルギー産業の展望』
ジェトロ(日本貿易振興機構) 2006/7/21
■国際情勢
『石油の世紀〜支配者たちの興亡〜(上)(下)』***
ダニエル・ヤーギン 日本放送出版協会 1991/4/20
『石油の歴史〜ロックフェラーから湾岸戦争後の世界まで〜』
エティエンヌ・ダルモン/ジャン・カリエ 白水社 2006/8/5
『石油の終焉〜生活が変わる、社会が変わる、国際関係がかわる〜』**
ポール・ロバーツ 光文社 2005/5/30
『ピーク・オイル〜石油争乱と21世紀経済の行方〜』**
リンダ・マクウェイグ 作品社 2005/9/10
『SHOWDOWN --WHY CHINA WANTS WAR WITH THE UNITED STATES--』**
J ED BABBIN/EDWARD TIMPERLAKE REGNERY PUBLISHING, INC. 2006/5/22
『ボロボロになった覇権国家〜次を狙う列強の野望と日本の選択〜』***
北野幸伯 風雲舎 2005/1/25
『米中石油戦争がはじまった〜アメリカを知らない中国は敗れる〜』***
日高義樹 PHP研究所 2006/2/3
『米中冷戦の始まりを知らない日本人』***
日高義樹 徳間書店 2006/6/30
『石油と戦争〜エネルギー地政学から読む国際政治〜』**
中堂幸政 現代書館 2006/1/25
『ザ・グレート・ゲーム〜石油争奪戦の内幕〜』
宮崎正弘 小学館文庫 2003/7/1
『米国か、ちゅうごくか〜これからの世界潮流と日本の選択〜』***
吉田春樹 PHP研究所 2007/1/25
『陰謀国家アメリカの石油戦争〜イラン戦争は勃発するか〜』
スティーブン・ペレティエ ビジネス社 2006/3/20
『米中が激突する日』*
黄文雄 PHP研究所 2006/5/8
『石油をめぐる世界紛争地図』
トビー・シェリー 東洋経済新報社 2005/12/15
『世界を動かす石油戦略』
石井彰/藤和彦 ちくま新書 2003/1/20
『石油地政学〜中東とアメリカ〜』
畑中美樹 中公新書 2003/11/1
『21世紀の新グレート・ゲーム〜エネルギー資源獲得の新潮流〜』*
島敏夫/中津孝司 昇洋書房 2001/4/20
『エネルギー大潮流〜石油文明が終わり、新しい社会が出現する〜』
クリストファー・フレイビン/ニコラス・レンセン ダイヤモンド社 1995/10/26
『THE PARTY'S OVER -Oil, War and the Fate of Industrial Societies- RIVISED AND UPDATED EDITION』
Richard Heinberg NEW SOCIETY PUBLISHERS 2005/7/13
『石油大国ロシアの復活』
木村眞澄 アジア経済研究所 2005/3/31
■総論・その他
『成長の限界 人類の選択』***
ドネラ・H・メドウズ/デニス・L・メドウズ/ヨルゲン・ランダース ダイアモンド社 2005/3/10
『環境・エネルギー・社会〜環境社会学を求めて〜』**
C・R・ハムフェリー/F・H・バトル ミネルバ書房 1991/10/20
『環境危機をあおってはいけない〜地球環境のホントの実態〜』**
ビョルン・ロンボルグ 文藝春秋 2003/6/30
『現代思想としての環境問題〜脳と遺伝子の共生〜』
佐倉統 中公新書 1992/5/15
『戦略的意思決定』
生天目章 朝倉書店 2001/3/20
『論理パラドクス』**
三浦俊彦 二見書房 2002/10/
『激動エネルギーの10年』
新井光雄 ERC出版 2006/3/27
『進化とゲーム理論〜闘争の論理〜』*
J・メイナード・スミス 産業図書 1985/7/12
『GROWING ARTIFICIAL SOCIETIES/人工社会』**
JOSHUA M.EPSTEIN/ROBERT 共立出版 1999/12/25
『国際政治〜恐怖と希望』(UMAさん紹介)***
高坂正尭 中公新書 1966/8/25
■雑誌
『世界』05' 11月号
『選択』06' 5、6、7、8月号***
このコミュのレポートや書き込みに使用している私の蔵書。
「○○はどんな内容なんですか?」などの質問や、「こんな本もありますよ」などの情報提供など歓迎。
管理人のお勧め度(***)をつけてみました(11/19)
■石油業界
『石油の生産量はピークに来たのか〜ピークオイルの本質と21世紀のエネルギー〜』***
根岸敏雄 石油文化社 2006/4/25
■科学技術論
『石油最終争奪戦〜世界を震撼させる『ピークオイル』の真実〜』***
石井吉徳 B&Tブックス 日刊工業新聞社 2006/7/30
『ピーク・オイル・パニック〜迫る石油危機と代替エネルギーの可能性〜』*
ジェレミーレゲット 作品社 2006/9/25
『豊かな石油時代が終わる〜人類は何処へ行くのか〜』*
(社)日本工学アカデミー・環境フォーラム偏 丸善 2004/10/20
『エネルギー〜風と太陽へのソフトランディング〜』
小島紀徳 日本評論社 2003/12/10
『地球環境 危機からの脱出〜科学技術が人類を救う〜』
レスター・ブラウン/デヴィッド・ハウエル/黒川清/薬師寺泰蔵/十市勉/植田和弘/藤嶋昭/松井孝典 ウェッジ選書 2005/7/29
『エネルギー・環境・社会〜現代技術社会論〜』
京都大学大学院エネルギー科学研究科 エネルギー社会・環境科学専攻 丸善 2004/3/30
『新エネルギー最前線〜環境調和型エネルギーシステムの構築を目指して〜』**
吉川暹[編] 化学同人 2006/9/30
『誤解だらけのエネルギー問題』**
浜松照秀 日刊工業新聞社 2006/3/27
■国際機関
『世界のエネルギー展望2004』***
OECD/IEA エネルギーフォーラム 2005/12/8
『国際エネルギー・レジーム〜エネルギー・地球温暖化問題と知識〜』
松井賢一 エネルギーフォーラム 2006/2/20
■経済系
『石油を読む〜地政学的発想を超えて〜』***
藤和彦 日経文庫 2005/2/15
『富の未来(上)(下)』*
アルビン・トフラー/ハイジ・トフラー 講談社 2006/6/7
『知られていない原油価格高騰の謎』*
芥田知至 技術評論社 2006/5/5
『資源インフレ〜日本を襲う経済リスクの正体』
柴田明夫 日本経済新聞社 2006/7/10
『市場対国家〜世界を作り変える歴史的攻防〜(上)(下)』
ダニエル・ヤーギン/ジョゼフ・スタニスロー 日系ビジネス人文庫 2001/11/1
『石油の経済学〜原油高騰に打ち勝つ〜』
萩田穣 アートデイズ 2005/1/10
『THE FINAL ENERGY CRISIS』
Andrew McKillop/Sheila Newman PLUTO PRESS 2005/7/8
『中国のエネルギー動向〜海外石油・天然ガス獲得の現状/中国のエネルギー産業の展望』
ジェトロ(日本貿易振興機構) 2006/7/21
■国際情勢
『石油の世紀〜支配者たちの興亡〜(上)(下)』***
ダニエル・ヤーギン 日本放送出版協会 1991/4/20
『石油の歴史〜ロックフェラーから湾岸戦争後の世界まで〜』
エティエンヌ・ダルモン/ジャン・カリエ 白水社 2006/8/5
『石油の終焉〜生活が変わる、社会が変わる、国際関係がかわる〜』**
ポール・ロバーツ 光文社 2005/5/30
『ピーク・オイル〜石油争乱と21世紀経済の行方〜』**
リンダ・マクウェイグ 作品社 2005/9/10
『SHOWDOWN --WHY CHINA WANTS WAR WITH THE UNITED STATES--』**
J ED BABBIN/EDWARD TIMPERLAKE REGNERY PUBLISHING, INC. 2006/5/22
『ボロボロになった覇権国家〜次を狙う列強の野望と日本の選択〜』***
北野幸伯 風雲舎 2005/1/25
『米中石油戦争がはじまった〜アメリカを知らない中国は敗れる〜』***
日高義樹 PHP研究所 2006/2/3
『米中冷戦の始まりを知らない日本人』***
日高義樹 徳間書店 2006/6/30
『石油と戦争〜エネルギー地政学から読む国際政治〜』**
中堂幸政 現代書館 2006/1/25
『ザ・グレート・ゲーム〜石油争奪戦の内幕〜』
宮崎正弘 小学館文庫 2003/7/1
『米国か、ちゅうごくか〜これからの世界潮流と日本の選択〜』***
吉田春樹 PHP研究所 2007/1/25
『陰謀国家アメリカの石油戦争〜イラン戦争は勃発するか〜』
スティーブン・ペレティエ ビジネス社 2006/3/20
『米中が激突する日』*
黄文雄 PHP研究所 2006/5/8
『石油をめぐる世界紛争地図』
トビー・シェリー 東洋経済新報社 2005/12/15
『世界を動かす石油戦略』
石井彰/藤和彦 ちくま新書 2003/1/20
『石油地政学〜中東とアメリカ〜』
畑中美樹 中公新書 2003/11/1
『21世紀の新グレート・ゲーム〜エネルギー資源獲得の新潮流〜』*
島敏夫/中津孝司 昇洋書房 2001/4/20
『エネルギー大潮流〜石油文明が終わり、新しい社会が出現する〜』
クリストファー・フレイビン/ニコラス・レンセン ダイヤモンド社 1995/10/26
『THE PARTY'S OVER -Oil, War and the Fate of Industrial Societies- RIVISED AND UPDATED EDITION』
Richard Heinberg NEW SOCIETY PUBLISHERS 2005/7/13
『石油大国ロシアの復活』
木村眞澄 アジア経済研究所 2005/3/31
■総論・その他
『成長の限界 人類の選択』***
ドネラ・H・メドウズ/デニス・L・メドウズ/ヨルゲン・ランダース ダイアモンド社 2005/3/10
『環境・エネルギー・社会〜環境社会学を求めて〜』**
C・R・ハムフェリー/F・H・バトル ミネルバ書房 1991/10/20
『環境危機をあおってはいけない〜地球環境のホントの実態〜』**
ビョルン・ロンボルグ 文藝春秋 2003/6/30
『現代思想としての環境問題〜脳と遺伝子の共生〜』
佐倉統 中公新書 1992/5/15
『戦略的意思決定』
生天目章 朝倉書店 2001/3/20
『論理パラドクス』**
三浦俊彦 二見書房 2002/10/
『激動エネルギーの10年』
新井光雄 ERC出版 2006/3/27
『進化とゲーム理論〜闘争の論理〜』*
J・メイナード・スミス 産業図書 1985/7/12
『GROWING ARTIFICIAL SOCIETIES/人工社会』**
JOSHUA M.EPSTEIN/ROBERT 共立出版 1999/12/25
『国際政治〜恐怖と希望』(UMAさん紹介)***
高坂正尭 中公新書 1966/8/25
■雑誌
『世界』05' 11月号
『選択』06' 5、6、7、8月号***
|
|
|
|
コメント(94)
そういえば、つい最近、上記の「ハゲタカ」読みました。
東南アジアの核開発を止める為に、日本が原発を5年以内に廃止するという事を国際社会に押し付けられます。そこで、原発開発関係者が立ち上がり、地熱発電の開発に生涯をかけるといった内容です。外資系投資会社の若い女性社員が、日本の地熱発電会社を再建するという視点で描かれています。
この本で描かれているほど、地熱発電のポテンシャルがあるのかどうかは解りませんが、やりようによってはかなりいけないかなあ。
最大の地熱発電所は、10万キロワット程度の規模で、原発に遠く及びません。おまけに開発のコストとリスクが高い。
技術的な部分や、設定などは?な箇所も多少ありますし、原発が廃止されてしまうという設定はいささかショッキングですが(喜ぶ人もいると思いますが)、日本の未来の為に命をかけて戦う登場人物には、ちょっと感動しました。
真山さんはこういう話好きですね☆
地熱発電について何も知らないという方には、結構おすすめかもです。
あと、外資による合併話とか。
東南アジアの核開発を止める為に、日本が原発を5年以内に廃止するという事を国際社会に押し付けられます。そこで、原発開発関係者が立ち上がり、地熱発電の開発に生涯をかけるといった内容です。外資系投資会社の若い女性社員が、日本の地熱発電会社を再建するという視点で描かれています。
この本で描かれているほど、地熱発電のポテンシャルがあるのかどうかは解りませんが、やりようによってはかなりいけないかなあ。
最大の地熱発電所は、10万キロワット程度の規模で、原発に遠く及びません。おまけに開発のコストとリスクが高い。
技術的な部分や、設定などは?な箇所も多少ありますし、原発が廃止されてしまうという設定はいささかショッキングですが(喜ぶ人もいると思いますが)、日本の未来の為に命をかけて戦う登場人物には、ちょっと感動しました。
真山さんはこういう話好きですね☆
地熱発電について何も知らないという方には、結構おすすめかもです。
あと、外資による合併話とか。
【[書籍]]石油ピークが来た」】のトピックで、スーパーTSさんが「石油もう一つの危機」(石井彰)についてコメントしてくださったので、こちらで私からも一言。
内容については、概ねスーパーTSさんが書かれていた通りで、昨今の価格高騰の主な原因として、莫大な米年金基金のごく一部が、商品ファンドなどを通じて石油市場に大量に流入し始めているなど、価格の構造変化について多くの人が気がついていないと指摘している点が彼の最近の強い主張なわけですが。
ピークオイルについては、いつもの様に一蹴しています。
筆者は、世界でただ二つ、ちゃんとした石油データを持っているのはCERAとウッドマッケンジーであり、IEAでもEIAでもUSGSでもOPECでもIFPでもこの二つのデータを引用しているという。これら二つの供給予測カーブを提示し、2030年前にピークが来る見込みは全くないと主張しています。よって、昨今の価格高騰を、ピークオイルによるものという考えは的外れだと。
ただ、先日の10/26のもったいない学会シンポジウムで、石井吉徳先生が、反ピークオイルの筆頭団体?であるCERAが、年率マイナス4%の減退をようやく最近言い始めたおっしゃっていました。私はまだ確認していませんが。
とある石油調査の関係者も、最近はCERAの方がむしろますます業界から取り残されていると言っていました。
真相はわかりませんね。
運営方針&雑記のトピックで、daiさんもこの本について300番ぐらいにいくつか興味深いコメントしていますので、是非ご覧になって下さい。
内容については、概ねスーパーTSさんが書かれていた通りで、昨今の価格高騰の主な原因として、莫大な米年金基金のごく一部が、商品ファンドなどを通じて石油市場に大量に流入し始めているなど、価格の構造変化について多くの人が気がついていないと指摘している点が彼の最近の強い主張なわけですが。
ピークオイルについては、いつもの様に一蹴しています。
筆者は、世界でただ二つ、ちゃんとした石油データを持っているのはCERAとウッドマッケンジーであり、IEAでもEIAでもUSGSでもOPECでもIFPでもこの二つのデータを引用しているという。これら二つの供給予測カーブを提示し、2030年前にピークが来る見込みは全くないと主張しています。よって、昨今の価格高騰を、ピークオイルによるものという考えは的外れだと。
ただ、先日の10/26のもったいない学会シンポジウムで、石井吉徳先生が、反ピークオイルの筆頭団体?であるCERAが、年率マイナス4%の減退をようやく最近言い始めたおっしゃっていました。私はまだ確認していませんが。
とある石油調査の関係者も、最近はCERAの方がむしろますます業界から取り残されていると言っていました。
真相はわかりませんね。
運営方針&雑記のトピックで、daiさんもこの本について300番ぐらいにいくつか興味深いコメントしていますので、是非ご覧になって下さい。
グリーンスパン元FRB議長の新刊より。
全部は大変なので・・・
(下)の第24章「長期的なエネルギーの逼迫」より私が「お」と思った箇所。賛否は別。一部要約にしてます。
p.251
投資家が石油市場に参入したことで、世界の原油供給が増えたわけでないが、投資家の活動によって価格調整のスピードが上がり、OPECの地下に埋蔵された原油の一部が、先進国の地上の在庫になったのである。これによって石油の安全性が高まり、ひいては長期的な価格圧力を弱めるとわたしはみている。
p.251(要旨)
原油価格が上がると、投機家と石油業界が結託して大規模な価格つり上げを行っているというような陰謀を糾弾する声が高まり、議会の調査が多く行われて来た。陰謀説は刺激的であるが、現実は遥かに凡庸だ。ただ市場の力が効率的に働いているだけなのだ。
p.252
投機によって在庫の積み増しが行われていなければ、世界は、過去よりもはるかに深刻な石油ショックを経験する事になった
p.253
アメリカでは、1976年以降、新設された製油所はない
p.255
1972年から81年にかけての石油製品価格の高騰によって、世界の消費の伸びが殆ど止まっている。
p.257(要約)
1979年、エネルギー省は、当時の石油消費のトレンドを基に、世界の原油価格は1995年時点で1バレル当たり150ドル強(2006年基準の実質ベース)になると予想していた。予想を下回ったのは、市場の力がはたらいたから。
p.263
カナダはアサバスカのオイルサンドの開発の為に天然ガス供給のかなりの部分を使っている。
p.263
2006年、アメリカのLNG輸入の3分の2はトリニダード・トバコから
(アメリカのエネルギー消費に占めるLNGの割合は2%)
p.270
エネルギー省の「中位推計」では、世界の原油生産がピークを迎える時期を今世紀半ばと予想している。
p.271
(ハイブリッド車に試乗してみて)
唯一の難点は、アクセルを踏むと、不気味な程静かに加速することだ。ガソリンエンジンの回転音を響かせる音響システムを備えたモデルなら、売れるのではないかと思う。人間は予想通りのことが起こる心地よさを求めるものだ。
p.272
エネルギー省の予測によれば、現在、小型乗用車は2億2千万台だが、それがプラグイン・ハイブリッド車であれば、その84%が発電能力を増やす必要がなく、電力の使用量が少ない夜間に充電出来るという。
p.273
OPEC加盟国の生産統計については、殆どの国が非公開としている。このため、輸出向けに港を出るタンカー数と大きさから、生産量が推計されている。タンカーの載貨重量を推計するため、喫水線を調べる。
p.276
農業省とエネルギー省の共同研究では、農産物やバイオマスから抽出された燃料は、「現在の国内の消費量の3分の1以上を持続的に供給できる可能性がある」と予測しており、予測の信頼性は高い。
p.279
中東のきわめて危うい情勢に言及していない世界の需要予測は、世界経済の成長を止めかねない巨大な問題を避けている。(中略)
わたしにわかっているのは、中東の未来が、長期のエネルギー予測でもっとも重要な検討項目であるという点である。
全部は大変なので・・・
(下)の第24章「長期的なエネルギーの逼迫」より私が「お」と思った箇所。賛否は別。一部要約にしてます。
p.251
投資家が石油市場に参入したことで、世界の原油供給が増えたわけでないが、投資家の活動によって価格調整のスピードが上がり、OPECの地下に埋蔵された原油の一部が、先進国の地上の在庫になったのである。これによって石油の安全性が高まり、ひいては長期的な価格圧力を弱めるとわたしはみている。
p.251(要旨)
原油価格が上がると、投機家と石油業界が結託して大規模な価格つり上げを行っているというような陰謀を糾弾する声が高まり、議会の調査が多く行われて来た。陰謀説は刺激的であるが、現実は遥かに凡庸だ。ただ市場の力が効率的に働いているだけなのだ。
p.252
投機によって在庫の積み増しが行われていなければ、世界は、過去よりもはるかに深刻な石油ショックを経験する事になった
p.253
アメリカでは、1976年以降、新設された製油所はない
p.255
1972年から81年にかけての石油製品価格の高騰によって、世界の消費の伸びが殆ど止まっている。
p.257(要約)
1979年、エネルギー省は、当時の石油消費のトレンドを基に、世界の原油価格は1995年時点で1バレル当たり150ドル強(2006年基準の実質ベース)になると予想していた。予想を下回ったのは、市場の力がはたらいたから。
p.263
カナダはアサバスカのオイルサンドの開発の為に天然ガス供給のかなりの部分を使っている。
p.263
2006年、アメリカのLNG輸入の3分の2はトリニダード・トバコから
(アメリカのエネルギー消費に占めるLNGの割合は2%)
p.270
エネルギー省の「中位推計」では、世界の原油生産がピークを迎える時期を今世紀半ばと予想している。
p.271
(ハイブリッド車に試乗してみて)
唯一の難点は、アクセルを踏むと、不気味な程静かに加速することだ。ガソリンエンジンの回転音を響かせる音響システムを備えたモデルなら、売れるのではないかと思う。人間は予想通りのことが起こる心地よさを求めるものだ。
p.272
エネルギー省の予測によれば、現在、小型乗用車は2億2千万台だが、それがプラグイン・ハイブリッド車であれば、その84%が発電能力を増やす必要がなく、電力の使用量が少ない夜間に充電出来るという。
p.273
OPEC加盟国の生産統計については、殆どの国が非公開としている。このため、輸出向けに港を出るタンカー数と大きさから、生産量が推計されている。タンカーの載貨重量を推計するため、喫水線を調べる。
p.276
農業省とエネルギー省の共同研究では、農産物やバイオマスから抽出された燃料は、「現在の国内の消費量の3分の1以上を持続的に供給できる可能性がある」と予測しており、予測の信頼性は高い。
p.279
中東のきわめて危うい情勢に言及していない世界の需要予測は、世界経済の成長を止めかねない巨大な問題を避けている。(中略)
わたしにわかっているのは、中東の未来が、長期のエネルギー予測でもっとも重要な検討項目であるという点である。
ぬりさん
興味深い内容ですね。読んでいる余裕はなさそうですが。
> p.252
> 投機によって在庫の積み増しが行われていなければ、世界は、
> 過去よりもはるかに深刻な石油ショックを経験する事になった
いつも書いているように、現物に触らない投機は石油現物価格に本質的な影響を与えないだろうと私は考えています。そして現物に触る投機に関しても
・投機家がアクセスできる空き油槽所って、そんなにあるのだろうか?
・油槽所(付随する輸送インフラを含めて)って、そんなに簡単に建設できるのだろうか?
という2つの疑問があるので、あまり大きな影響力を持たないだろうと推測しています(事実にもとづく推測ではなく、疑問にもとづく推測です)。
直接現物に触る投機というよりも、現実には石油流通関連企業が在庫を積増しし、それに対して投機資金が(社債や株を通じて)流入するというのがむしろありそうなパターンと考えています。ところが、価格上昇のニュースと平行して入ってくるニュースでは、「在庫が積み上らない」「在庫が増えないことが価格上昇に拍車」的な内容がむしろ多い。価格が上がって在庫が増えているという情報は見た記憶がないのです。
まあ、私の情報源は日本のマスメディアがほとんどですから、ちゃんとした情報に接していない可能性も大きい。したがって自分の結論を強く主張するつもりはありません。ただ、普通に新聞やテレビを見る限りにおいて、どうしても投機資金が[直接売買を通じて]現物価格をつり上げるメカニズムが見えてこないのです。
なお、直接売買を通じずに、つまり先物指標(NYMEX-WTI期近物価格)を通じての影響については、まだよく理解していません。
興味深い内容ですね。読んでいる余裕はなさそうですが。
> p.252
> 投機によって在庫の積み増しが行われていなければ、世界は、
> 過去よりもはるかに深刻な石油ショックを経験する事になった
いつも書いているように、現物に触らない投機は石油現物価格に本質的な影響を与えないだろうと私は考えています。そして現物に触る投機に関しても
・投機家がアクセスできる空き油槽所って、そんなにあるのだろうか?
・油槽所(付随する輸送インフラを含めて)って、そんなに簡単に建設できるのだろうか?
という2つの疑問があるので、あまり大きな影響力を持たないだろうと推測しています(事実にもとづく推測ではなく、疑問にもとづく推測です)。
直接現物に触る投機というよりも、現実には石油流通関連企業が在庫を積増しし、それに対して投機資金が(社債や株を通じて)流入するというのがむしろありそうなパターンと考えています。ところが、価格上昇のニュースと平行して入ってくるニュースでは、「在庫が積み上らない」「在庫が増えないことが価格上昇に拍車」的な内容がむしろ多い。価格が上がって在庫が増えているという情報は見た記憶がないのです。
まあ、私の情報源は日本のマスメディアがほとんどですから、ちゃんとした情報に接していない可能性も大きい。したがって自分の結論を強く主張するつもりはありません。ただ、普通に新聞やテレビを見る限りにおいて、どうしても投機資金が[直接売買を通じて]現物価格をつり上げるメカニズムが見えてこないのです。
なお、直接売買を通じずに、つまり先物指標(NYMEX-WTI期近物価格)を通じての影響については、まだよく理解していません。
はじめましてm(__)m
さて、石井吉徳さんの『石油ピークが来た』
を買って読み始めたのですが...
その中で、20ページに
「2007年に出された第四回目のIPCCレポートは温暖化がもう現実のこととなっていると危機感を強くしているが、」
という記述があるんですけど、私は
「なんでIPCCの発表をウノミにしてしまうんだろう?」
と思いまして。
というのも、先日たまたま書店で
『地球温暖化は本当か?』矢沢 潔(技術評論社)1580円+税
という本を見つけまして、気になったので買って読んだらとんでもなかったと。
このコミュの方々は地球に関する意識が高い方が集まっていらっしゃるとお見受けしますので、
是非この本に目を通していただいて、その上で石油問題とか環境問題とかの意見交換ができたら
いいなとは思っているのですが。
よろしくお願いしますm(__)m
さて、石井吉徳さんの『石油ピークが来た』
を買って読み始めたのですが...
その中で、20ページに
「2007年に出された第四回目のIPCCレポートは温暖化がもう現実のこととなっていると危機感を強くしているが、」
という記述があるんですけど、私は
「なんでIPCCの発表をウノミにしてしまうんだろう?」
と思いまして。
というのも、先日たまたま書店で
『地球温暖化は本当か?』矢沢 潔(技術評論社)1580円+税
という本を見つけまして、気になったので買って読んだらとんでもなかったと。
このコミュの方々は地球に関する意識が高い方が集まっていらっしゃるとお見受けしますので、
是非この本に目を通していただいて、その上で石油問題とか環境問題とかの意見交換ができたら
いいなとは思っているのですが。
よろしくお願いしますm(__)m
ふぁんたHさん
はじめまして。「石油ピークが来た」読んでますか。最近「読んだよ」と言ってくる人が周りにもちらほらいます。
IPCCは、世界中の人が鵜呑みにしてもいいものを目指して作られているからではないでしょうか。一般の人は、その正当性の評価をする暇も興味もありませんから。
ロンボルグなど、反論本も多く存在しますが、好みの問題になっている気もします。
「地球温暖化は本当か」
私も、温暖化の話をする時、この本を参考にする事も多いですが、かなり懐疑的な見方が多いようですね。しかし、IPCCの報告書には、この本に書いてあるような懐疑的な見方に対し、かなり網羅的に反証していることも、"一般"の懐疑論者はあまり知りません。
環境問題は本当に問題かという問題もあると思います。
世界的に見ると、日本は懐疑的な人がまだまだ多いと思います。
環境問題に興味がある人は大半なのに、行動に移す人が少ないとうことも、懐疑論者が多いことも、風土や国民性から出て来てるのかなと思ったりします。
人間は都合のいい情報の方が信じやすく出来てますから。
私は、真否はともかく、環境問題よりも、ピークオイルの方が重要だと思っているので、このコミュニティをやっているわけですが。
ピークオイルと環境問題の関わりは、
「環境問題、温暖化問題とピークオイル」
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=17493673&comm_id=1322211
にもありますので、是非覗いてみて下さい。
はじめまして。「石油ピークが来た」読んでますか。最近「読んだよ」と言ってくる人が周りにもちらほらいます。
IPCCは、世界中の人が鵜呑みにしてもいいものを目指して作られているからではないでしょうか。一般の人は、その正当性の評価をする暇も興味もありませんから。
ロンボルグなど、反論本も多く存在しますが、好みの問題になっている気もします。
「地球温暖化は本当か」
私も、温暖化の話をする時、この本を参考にする事も多いですが、かなり懐疑的な見方が多いようですね。しかし、IPCCの報告書には、この本に書いてあるような懐疑的な見方に対し、かなり網羅的に反証していることも、"一般"の懐疑論者はあまり知りません。
環境問題は本当に問題かという問題もあると思います。
世界的に見ると、日本は懐疑的な人がまだまだ多いと思います。
環境問題に興味がある人は大半なのに、行動に移す人が少ないとうことも、懐疑論者が多いことも、風土や国民性から出て来てるのかなと思ったりします。
人間は都合のいい情報の方が信じやすく出来てますから。
私は、真否はともかく、環境問題よりも、ピークオイルの方が重要だと思っているので、このコミュニティをやっているわけですが。
ピークオイルと環境問題の関わりは、
「環境問題、温暖化問題とピークオイル」
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=17493673&comm_id=1322211
にもありますので、是非覗いてみて下さい。
ふぁんたH さん、温暖化説に対して懐疑的になる人が少なからずいることにはマットウな理由があるのだと思います。
ASPO でマシューシモンズが紹介していましたが、Google で “ Peak Oil “ でヒットするのは 310万件、かたや “ Global Warming “ だと 8050万件ヒットするのだそうな。
その差 26倍 ! どちらも同じように憂鬱で、同じように世界的な問題なのに、なぜこんなに差が出るのでしょう。変ですよね。深刻さにおいては、Peak Oil の方にこそ、差し迫ったものがあるのに。
原発をつくりたがる人々にとって、温暖化説は格好の材料でしょう。どんどん宣伝します。逆に、ピークオイルの方は広範に知れ渡るとなると困る人々がいる。
今後一方的にガソリン代があがっていくことが大衆に知られると、クルマは売れなくなり、自動車会社は困るでしょう。高速道路はこの上さらにつくる根拠がなくなります。これには政治家もゼネコンも困ります。航空会社はお先真っ暗で、株をもっている人はただの紙切れになる前に売り抜けようとするでしょう。ただでさえ必要性に疑問がある地方空港など建設できなくなります。停電が頻発するようになることが予期できるようになると、エレベーターが必要な高層マンションは誰も買いたいとは思わなくなるでしょう。信用経済も崩壊、現行の政治・文化の諸制度が崩壊するとなれば、その上であぐらをかいて権益を得ている人たちはピークオイルは、どうしても秘密にしておきたいことになります。
マスメディアも、スポンサーの意向に反するようなことは決してしません。
温暖化説の科学的な真偽は究極のところわかりませんし、どのみち人類は理性的に化石燃料の燃焼を減らすことはできないでしょう。
ただ、エライ人たちの変な思惑に絡めとられるのはイヤだ、という発想はありだと思うのです。
ASPO でマシューシモンズが紹介していましたが、Google で “ Peak Oil “ でヒットするのは 310万件、かたや “ Global Warming “ だと 8050万件ヒットするのだそうな。
その差 26倍 ! どちらも同じように憂鬱で、同じように世界的な問題なのに、なぜこんなに差が出るのでしょう。変ですよね。深刻さにおいては、Peak Oil の方にこそ、差し迫ったものがあるのに。
原発をつくりたがる人々にとって、温暖化説は格好の材料でしょう。どんどん宣伝します。逆に、ピークオイルの方は広範に知れ渡るとなると困る人々がいる。
今後一方的にガソリン代があがっていくことが大衆に知られると、クルマは売れなくなり、自動車会社は困るでしょう。高速道路はこの上さらにつくる根拠がなくなります。これには政治家もゼネコンも困ります。航空会社はお先真っ暗で、株をもっている人はただの紙切れになる前に売り抜けようとするでしょう。ただでさえ必要性に疑問がある地方空港など建設できなくなります。停電が頻発するようになることが予期できるようになると、エレベーターが必要な高層マンションは誰も買いたいとは思わなくなるでしょう。信用経済も崩壊、現行の政治・文化の諸制度が崩壊するとなれば、その上であぐらをかいて権益を得ている人たちはピークオイルは、どうしても秘密にしておきたいことになります。
マスメディアも、スポンサーの意向に反するようなことは決してしません。
温暖化説の科学的な真偽は究極のところわかりませんし、どのみち人類は理性的に化石燃料の燃焼を減らすことはできないでしょう。
ただ、エライ人たちの変な思惑に絡めとられるのはイヤだ、という発想はありだと思うのです。
Dr. Kさん
久しぶりにこちらに。
官僚が作る(民間委託も一部してると思いますが)白書には、本当の事は書けないので、行間などに書き手のメッセージを忍ばせて、満足しているとかいないとか。
まあ、少なくともわかった上でやっているんだと思いますよ。批判されることも含め。
☆
久しぶりに、小説を読みました。
「ペトロバグ―禁断の石油生成菌」
高嶋 哲夫 (著)
文春文庫
文庫版が昨年11月に出たので買ったのですが、ようやく開いてみました。
高嶋氏は、映画「ミッドナイトイーグル」が昨年11月に公開され注目を集め、それで「ペトロバグ」も文春文庫に収録されたようで、店頭に出ていたので手に取ってみました。
元々は、宝島社から「ペトロバクテリアを追え!」(2001)、とその文庫版「ペトロバグ」(2001)が出版されています。
主人公の友人兼ライバルの研究者として、ジョン・キャンベル(キャンベル研究所所長)という人物が出てくるのですが、遺伝子が専門の生物学者で、○リン・キャンベル氏とは無関係のようです(笑)。
話は、炭素を含む化合物を、空気中の二酸化炭素と水を使って石油に変えてしまうバクテリアを日本人研究者が発見し、それを巡ってOPECや石油メジャーが争いあうという内容なのですが・・・。
自分にはこんな小説は書けないので、あまり文句は言えませんが、正直にいって安っぽく感じてしまいました。何事もすぐ「ジャップめ」と罵るアメリカ人、すぐに「アラー」を持ち出すOPEC首脳、いかにもという感じの頭ぼさぼさ科学者像・・・。いとも簡単に素人に殺される殺し屋、やたら多い爆発、都合良く進化するバクテリア。あれだけの物質変化に必要なエネルギーをどこから得てるのだろうか。
娯楽作品なので、あまり文句をいっても仕方がありませんが、事実を巧みに織り交ぜ、いかにもありそうな話ってのも私は好きなんですが。
映画は成功したのかな?
久しぶりにこちらに。
官僚が作る(民間委託も一部してると思いますが)白書には、本当の事は書けないので、行間などに書き手のメッセージを忍ばせて、満足しているとかいないとか。
まあ、少なくともわかった上でやっているんだと思いますよ。批判されることも含め。
☆
久しぶりに、小説を読みました。
「ペトロバグ―禁断の石油生成菌」
高嶋 哲夫 (著)
文春文庫
文庫版が昨年11月に出たので買ったのですが、ようやく開いてみました。
高嶋氏は、映画「ミッドナイトイーグル」が昨年11月に公開され注目を集め、それで「ペトロバグ」も文春文庫に収録されたようで、店頭に出ていたので手に取ってみました。
元々は、宝島社から「ペトロバクテリアを追え!」(2001)、とその文庫版「ペトロバグ」(2001)が出版されています。
主人公の友人兼ライバルの研究者として、ジョン・キャンベル(キャンベル研究所所長)という人物が出てくるのですが、遺伝子が専門の生物学者で、○リン・キャンベル氏とは無関係のようです(笑)。
話は、炭素を含む化合物を、空気中の二酸化炭素と水を使って石油に変えてしまうバクテリアを日本人研究者が発見し、それを巡ってOPECや石油メジャーが争いあうという内容なのですが・・・。
自分にはこんな小説は書けないので、あまり文句は言えませんが、正直にいって安っぽく感じてしまいました。何事もすぐ「ジャップめ」と罵るアメリカ人、すぐに「アラー」を持ち出すOPEC首脳、いかにもという感じの頭ぼさぼさ科学者像・・・。いとも簡単に素人に殺される殺し屋、やたら多い爆発、都合良く進化するバクテリア。あれだけの物質変化に必要なエネルギーをどこから得てるのだろうか。
娯楽作品なので、あまり文句をいっても仕方がありませんが、事実を巧みに織り交ぜ、いかにもありそうな話ってのも私は好きなんですが。
映画は成功したのかな?
書評がたまってるので、もう一つ。
「テロマネーを封鎖せよ 米国の国際金融戦略の内幕を描く」
ジョン・B・テイラー
GLOBAL FINANCIAL WARRIORS
The untold story of international finance in the post-9/11 world
John B. Taylor
日経BP社
2007.11.26
2001年から2005年まで、米国財務省次官を務めたテイラー氏の回顧録。
アメリカの最近の金融戦略の生々しい実像を収録した類を見ない書物だと思います。
滝田洋一 著の「通貨を読む」<第二版>に、この本の内容について言及があり、気になっていたのですが、邦題はちと陳腐ですね。
9.11後のテロ資金凍結の国際協調、アフガニスタンやアルゼンチン、トルコへの経済援助や駆け引き、IMF、世界銀行改革、イラク金融政策などで辣腕を振るったテイラー。すごいことが行われてたんだなと関心しました。
本当に言えないことは書いてないのでしょうが。
日本絡みの記述は、当時の溝口財務官が2003年頃からの大量ドル買い介入を行ったことについて。テイラーは、日本のドル買い介入に強い反対はせず容認し、日本が非不胎化(日銀が日本国債などの資産を購入し円の増価を相殺する(不胎化)をしない)の介入をすることで、通貨供給量を増やせるようにはからったこと。日本が介入した時には直ちに電子メールで連絡をすること、大規模な場合は電話で報告することになっていたこと。などが明らかにされています。
また、2003.7.9にレストランで開催された「G3」(日、米、EU)の会合で、溝口財務官が116円/ドルをラインにドル買いしていたことや、そうした中心レート介入(一定レンジで相場を安定させるように介入しようというアイディア)を溝口氏が提案し、米+EUが拒否したことなど、その時に使われたメモのコピーも掲載して記述しています。
実際の外交はこうした交渉努力の上に成り立っているのだと、感心しました。
その大きさ、限界も含めて。
「テロマネーを封鎖せよ 米国の国際金融戦略の内幕を描く」
ジョン・B・テイラー
GLOBAL FINANCIAL WARRIORS
The untold story of international finance in the post-9/11 world
John B. Taylor
日経BP社
2007.11.26
2001年から2005年まで、米国財務省次官を務めたテイラー氏の回顧録。
アメリカの最近の金融戦略の生々しい実像を収録した類を見ない書物だと思います。
滝田洋一 著の「通貨を読む」<第二版>に、この本の内容について言及があり、気になっていたのですが、邦題はちと陳腐ですね。
9.11後のテロ資金凍結の国際協調、アフガニスタンやアルゼンチン、トルコへの経済援助や駆け引き、IMF、世界銀行改革、イラク金融政策などで辣腕を振るったテイラー。すごいことが行われてたんだなと関心しました。
本当に言えないことは書いてないのでしょうが。
日本絡みの記述は、当時の溝口財務官が2003年頃からの大量ドル買い介入を行ったことについて。テイラーは、日本のドル買い介入に強い反対はせず容認し、日本が非不胎化(日銀が日本国債などの資産を購入し円の増価を相殺する(不胎化)をしない)の介入をすることで、通貨供給量を増やせるようにはからったこと。日本が介入した時には直ちに電子メールで連絡をすること、大規模な場合は電話で報告することになっていたこと。などが明らかにされています。
また、2003.7.9にレストランで開催された「G3」(日、米、EU)の会合で、溝口財務官が116円/ドルをラインにドル買いしていたことや、そうした中心レート介入(一定レンジで相場を安定させるように介入しようというアイディア)を溝口氏が提案し、米+EUが拒否したことなど、その時に使われたメモのコピーも掲載して記述しています。
実際の外交はこうした交渉努力の上に成り立っているのだと、感心しました。
その大きさ、限界も含めて。
多分わからない方もいると思うので、蛇足ながら解説。
daiさん71の書き込みに出て来るのは、サムサム・バクティアリ博士(Dr. Ali Morteza Samsam Bakhtiari )で、国営イラン石油会社副社長、テヘラン大学講師(イラン史)、2006-2007ピーク説、中東の油田埋蔵量は公開情報の半分くらいしか無いと暴露したことでも有名。
恥ずかしながら、先ほど知ったのですが、昨年10/30にお亡くなりになっていました。1946年生まれとのことですので、享年61歳くらいでしょうか。ご冥福をお祈りします。
公式サイト
http://www.sfu.ca/~asamsamb/sb.htm
Dr. Kさんが、
>" 偽 " が大はやりだけど、こちらはシュードでも " シュード " ではありません。
と書いていましたが、シュード(psuedo=擬)コリシスティスの名前の由来は、形態はコリシスティス(Chorisystis)という緑藻類に近いが、遺伝子解析を行うとかけ離れているため、新種と見なしpsuedoをつけて名付けたみたいです。エリプソイディア(ellipsoidea)は細胞の形が回転楕円体(ellipsoid)である事に由来する種名。
ちなみに、コリシスティスにも軽油を作る能力はあるみたいです。
daiさん71の書き込みに出て来るのは、サムサム・バクティアリ博士(Dr. Ali Morteza Samsam Bakhtiari )で、国営イラン石油会社副社長、テヘラン大学講師(イラン史)、2006-2007ピーク説、中東の油田埋蔵量は公開情報の半分くらいしか無いと暴露したことでも有名。
恥ずかしながら、先ほど知ったのですが、昨年10/30にお亡くなりになっていました。1946年生まれとのことですので、享年61歳くらいでしょうか。ご冥福をお祈りします。
公式サイト
http://www.sfu.ca/~asamsamb/sb.htm
Dr. Kさんが、
>" 偽 " が大はやりだけど、こちらはシュードでも " シュード " ではありません。
と書いていましたが、シュード(psuedo=擬)コリシスティスの名前の由来は、形態はコリシスティス(Chorisystis)という緑藻類に近いが、遺伝子解析を行うとかけ離れているため、新種と見なしpsuedoをつけて名付けたみたいです。エリプソイディア(ellipsoidea)は細胞の形が回転楕円体(ellipsoid)である事に由来する種名。
ちなみに、コリシスティスにも軽油を作る能力はあるみたいです。
Dr.Kさん
早速、フィードバックありがとうございます。
はい、講談社に勤めています。
いま、会社で新しく立ち上げるエコ関連のサイトのために動いています。
枝廣さんの企画もそのためです。
貸し出し利息によって膨張し続けるマネーシステムと限界のあるエネルギー、資源によって成立している経済の矛盾激化についての問題点、僕自身も非常に気になっています。
人類的スケールの抑うつも大きな問題点ですね。
この前に、枝廣さんに1992年リオの地球サミットで12歳で、各国首脳を前に、大人の環境問題への責任を鋭く指摘する伝説のスピーチを行ったセバン・鈴木さんにインタビューをしてもらったのですが、その時も、セバンさんがポジティブでいることが、この戦いの半分を占める大切なことだと語っていたのが印象に残っています。
今日、ぬりさんに紹介してもらったイギリスのTransission Initiativeの研究会に参加したのですが、そこに来ていた方は、一様に、活き活きと前向きに生きている方々でした。
早速、フィードバックありがとうございます。
はい、講談社に勤めています。
いま、会社で新しく立ち上げるエコ関連のサイトのために動いています。
枝廣さんの企画もそのためです。
貸し出し利息によって膨張し続けるマネーシステムと限界のあるエネルギー、資源によって成立している経済の矛盾激化についての問題点、僕自身も非常に気になっています。
人類的スケールの抑うつも大きな問題点ですね。
この前に、枝廣さんに1992年リオの地球サミットで12歳で、各国首脳を前に、大人の環境問題への責任を鋭く指摘する伝説のスピーチを行ったセバン・鈴木さんにインタビューをしてもらったのですが、その時も、セバンさんがポジティブでいることが、この戦いの半分を占める大切なことだと語っていたのが印象に残っています。
今日、ぬりさんに紹介してもらったイギリスのTransission Initiativeの研究会に参加したのですが、そこに来ていた方は、一様に、活き活きと前向きに生きている方々でした。
石油がわかれば世界が読める
瀬川 幸一 編
ISBN:9784022732071
定価:756円(税込)
発売日:2008年4月11日
新書判並製 224ページ 新書107
原油大高騰のウラになにがある? 地球温暖化をめぐる脱石油で食料戦争勃発? 石油資源は枯渇しない?米中ロシアの資源争奪戦の台風の眼は石油?石油にまつわる資源探査から応用化学、地政学まで、石油学会に集う第一線研究者たちが共同執筆。それぞれの専門分野から「石油」に切り込む。
☆
出てすぐに読んだのですが、レビューする時間がなく更新できませんでした。
共感出来るコメント記事を発見したので合わせてリンクしておきます
4次元エコウォッチング(安井至)
石油学会の業界癒着本を斬る――電気自動車を再検討(08/06/18)
http://eco.nikkei.co.jp/column/ecowatching/article.aspx?id=MMECcd000016062008&page=1
瀬川 幸一 編
ISBN:9784022732071
定価:756円(税込)
発売日:2008年4月11日
新書判並製 224ページ 新書107
原油大高騰のウラになにがある? 地球温暖化をめぐる脱石油で食料戦争勃発? 石油資源は枯渇しない?米中ロシアの資源争奪戦の台風の眼は石油?石油にまつわる資源探査から応用化学、地政学まで、石油学会に集う第一線研究者たちが共同執筆。それぞれの専門分野から「石油」に切り込む。
☆
出てすぐに読んだのですが、レビューする時間がなく更新できませんでした。
共感出来るコメント記事を発見したので合わせてリンクしておきます
4次元エコウォッチング(安井至)
石油学会の業界癒着本を斬る――電気自動車を再検討(08/06/18)
http://eco.nikkei.co.jp/column/ecowatching/article.aspx?id=MMECcd000016062008&page=1
本の紹介:『プランB3.0』byレスターブラウン
http://www.janjanblog.jp/user/stopglobalwarming/stopglobalwarming/14518.html
--
特にピークオイル問題との関連で言えば、
「(プランB2.0を発行した)二年前、石油増産の可能性は、オイルメジャーや権威筋の予測よりも、大幅に少ないことを示す早期兆候があった。だが、いまでは、ピークオイルはすぐそこに迫っている可能性がある。二年前、石油は一バレル五〇ドルだったが、本書を執筆している二〇〇七年後半の時点で、九〇ドルを超え、なおも上値を追っている。」(はじめに、より)
としており、
第?部「世界は今後どうなってしまうのだろうか」不安をもたらす現状の章の始め
の第2章丸々を使って、「ピークオイルとフード・セキュリティー」という章で詳細に解説しています。
小見出しは以下の通り。
ピークオイル−先細りの石油資源
石油に依存している今日の農業と食料
一変した食料の展望−過去最低の世界の穀物在庫
食料vsバイオ燃料
ピークオイル後の世界
フード・セキュリティーと破綻国家
もちろん、この本の売りは、ハンセンらによるグリーランドの氷床融解の警告や北極の海氷のアルベドフィードバック問題が明らかになったことで、レスターブラウンの危機感が高まっているせいで、はるかに野心的な温暖化対策目標が設定されていることなのです。
ですが、このピークオイル問題と食料問題が出てきたこと、あたりが新しいバージョンアップを必要とした問題意識なんだろうと思います。
--
http://www.janjanblog.jp/user/stopglobalwarming/stopglobalwarming/14518.html
--
特にピークオイル問題との関連で言えば、
「(プランB2.0を発行した)二年前、石油増産の可能性は、オイルメジャーや権威筋の予測よりも、大幅に少ないことを示す早期兆候があった。だが、いまでは、ピークオイルはすぐそこに迫っている可能性がある。二年前、石油は一バレル五〇ドルだったが、本書を執筆している二〇〇七年後半の時点で、九〇ドルを超え、なおも上値を追っている。」(はじめに、より)
としており、
第?部「世界は今後どうなってしまうのだろうか」不安をもたらす現状の章の始め
の第2章丸々を使って、「ピークオイルとフード・セキュリティー」という章で詳細に解説しています。
小見出しは以下の通り。
ピークオイル−先細りの石油資源
石油に依存している今日の農業と食料
一変した食料の展望−過去最低の世界の穀物在庫
食料vsバイオ燃料
ピークオイル後の世界
フード・セキュリティーと破綻国家
もちろん、この本の売りは、ハンセンらによるグリーランドの氷床融解の警告や北極の海氷のアルベドフィードバック問題が明らかになったことで、レスターブラウンの危機感が高まっているせいで、はるかに野心的な温暖化対策目標が設定されていることなのです。
ですが、このピークオイル問題と食料問題が出てきたこと、あたりが新しいバージョンアップを必要とした問題意識なんだろうと思います。
--
もったいない学会会員の清水典之氏の本
「脱・石油社会」日本は逆襲する (Kobunsha Paperbacks (130)) (単行本(ソフトカバー))
http://www.amazon.co.jp/%E3%80%8C%E8%84%B1%E3%83%BB%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%80%8D%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AF%E9%80%86%E8%A5%B2%E3%81%99%E3%82%8B-Kobunsha-Paperbacks-130-%E6%B8%85%E6%B0%B4%E5%85%B8%E4%B9%8B/dp/4334934552/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1233483697&sr=8-1
が本屋さんにあったので買って見ました。
「原子力と二次電池で勝利せよ!」とのこと。
まあ、ピークオイル論を原発推進に使いたがる人は遅かれ早かれ出てくると思ってましたが。
「脱・石油社会」日本は逆襲する (Kobunsha Paperbacks (130)) (単行本(ソフトカバー))
http://www.amazon.co.jp/%E3%80%8C%E8%84%B1%E3%83%BB%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%80%8D%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AF%E9%80%86%E8%A5%B2%E3%81%99%E3%82%8B-Kobunsha-Paperbacks-130-%E6%B8%85%E6%B0%B4%E5%85%B8%E4%B9%8B/dp/4334934552/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1233483697&sr=8-1
が本屋さんにあったので買って見ました。
「原子力と二次電池で勝利せよ!」とのこと。
まあ、ピークオイル論を原発推進に使いたがる人は遅かれ早かれ出てくると思ってましたが。
おぐおぐさん
私も読みました。
二次電池の項目に、NBonlineの人気コラム「宮田秀明の「経営の設計学」」で有名な東大の宮田先生らが率いる、「二次電池による社会システム・イノベーション」を引き合いに出していましたね。
私はこのフォーラムのキックオフミーティングから全部参加していますが、二次電池の権威である堀江さんを向かえ、かなり気合をいれた産学連携を標榜してはいますが、現時点では内容が霧散していてお世辞にも実効性のある団体にはまだなっていないと思います。根底にあるのは、電気自動車で使い古したバッテリーを、社会で別用途でリユース流通させたり、自然エネルギー発電の出力平準化に流用しよう(というビジネスモデルをぶち上げよう)というアイディアなのですが、電気自動車の普及が前提にあったり、出力特性の違いなどはあまり考慮されていないなど、紹介するのは早すぎると思います。フォーラムをオープンにするかクローズにするかで大学側ともめている感じ?ですし、専門家は、まだ傍観している状態かと。
日本でおそらく唯一ピークオイルの研究をしている、茂木源人准教授も参加していますね。
私もこの手の本はあまり好きにはなれませんね。悲観から無理やり楽観という感じがします。
私も読みました。
二次電池の項目に、NBonlineの人気コラム「宮田秀明の「経営の設計学」」で有名な東大の宮田先生らが率いる、「二次電池による社会システム・イノベーション」を引き合いに出していましたね。
私はこのフォーラムのキックオフミーティングから全部参加していますが、二次電池の権威である堀江さんを向かえ、かなり気合をいれた産学連携を標榜してはいますが、現時点では内容が霧散していてお世辞にも実効性のある団体にはまだなっていないと思います。根底にあるのは、電気自動車で使い古したバッテリーを、社会で別用途でリユース流通させたり、自然エネルギー発電の出力平準化に流用しよう(というビジネスモデルをぶち上げよう)というアイディアなのですが、電気自動車の普及が前提にあったり、出力特性の違いなどはあまり考慮されていないなど、紹介するのは早すぎると思います。フォーラムをオープンにするかクローズにするかで大学側ともめている感じ?ですし、専門家は、まだ傍観している状態かと。
日本でおそらく唯一ピークオイルの研究をしている、茂木源人准教授も参加していますね。
私もこの手の本はあまり好きにはなれませんね。悲観から無理やり楽観という感じがします。
JOGMEC(石油天然ガス・金属鉱物資源機構)から、「石油資源の行方」という書籍がもうすぐ発売されるようです。
JOGMECですから、ピークオイルに関しては否定的なんでしょうけど。
シリーズ 21世紀のエネルギー 8
石油資源の行方
石油資源はあとどれくらいあるのか
日本エネルギー学会 編
JOGMEC調査部 編
判 型:A5
ページ:188頁
ISBN:978-4-339-06828-3
定 価:2,415円(本体2,300円+税5%)
石油はいつどこでどのように作られ,あとどれくらいあるのだろうか。それに答えるべく,世界の新しい石油の発見も含め,地下に眠る石油資源についてその供給側面を技術的見地からわかりやすく紹介。21世紀の石油資源の行方を追う。
JOGMECですから、ピークオイルに関しては否定的なんでしょうけど。
シリーズ 21世紀のエネルギー 8
石油資源の行方
石油資源はあとどれくらいあるのか
日本エネルギー学会 編
JOGMEC調査部 編
判 型:A5
ページ:188頁
ISBN:978-4-339-06828-3
定 価:2,415円(本体2,300円+税5%)
石油はいつどこでどのように作られ,あとどれくらいあるのだろうか。それに答えるべく,世界の新しい石油の発見も含め,地下に眠る石油資源についてその供給側面を技術的見地からわかりやすく紹介。21世紀の石油資源の行方を追う。
読書ノート
経済成長の主要因はエネルギー / The Economic Growth Engine (Ayres & Warr)
* Robert U. AYRES & Benjamin WARR, 2009年: The Economic Growth Engine: How Energy and Work Drive Material Prosperity. Cheltenham Glos. UK: Edward Elgar, 411 pp.
http://macroscope.world.coocan.jp/ja/reading/ayres_warr.html
自分で読んだわけじゃないですが、増田先生の書評?が更新されていましたので紹介。
経済成長の主要因はエネルギー / The Economic Growth Engine (Ayres & Warr)
* Robert U. AYRES & Benjamin WARR, 2009年: The Economic Growth Engine: How Energy and Work Drive Material Prosperity. Cheltenham Glos. UK: Edward Elgar, 411 pp.
http://macroscope.world.coocan.jp/ja/reading/ayres_warr.html
自分で読んだわけじゃないですが、増田先生の書評?が更新されていましたので紹介。
大計なき国家・日本の末路 (単行本)
ー日本とドイツの戦後を分けたものー
クライン 孝子 (著)
(著者まえがきより)
<<先の大戦におけるドイツのロシアに対する怨念は、
日本と同様かそれ以上に大きいものがある。
大戦中にドイツが失った領土問題もいまだくすぶり、
完全に解決したわけではない。
だがドイツは、未来志向で現実路線に徹することで、
確実にその成果を手にしているのだ。
片や日本はどうか。
日本でもサハリン沖の天然ガス田を共同開発し、
日ロ間を結ぶパイプラインを建設する計画が検討されてはいた。
だが、もろもろの事情から計画は白紙撤回され、
サハリンの天然ガスは全量が中国に回されてしまった。
かくしてエネルギー獲得競争において、
日本はここでもまた、大きく立ち遅れてしまった。
その原因は何か。
一つには、北方領土をめぐる日本の頑な態度に、
ロシアが業を煮やしたことは疑いの余地がない。
戦後六〇余年、日本はこの問題では一歩も引かぬ態度で交渉
にのぞみ、その間両国は、得るものが何もなかった。
いうなれば、不毛の議論のまま、いたずらに時を過ごしてきたのだ。
では、欧州では、この交渉をどのように見ているであろうか。
「戦争で負けて失った領土を取り戻したいと思うなら、
もう一度戦争して勝つことだ」
この一言で、終わりである。
それが長い間戦争を繰り返してきた欧州人にとっての
歴史の常識であり、
戦争に負けていながら、過去の条約や取り決めを持ちだして
領土の返還を要求するなど、ナンセンス以外の何物でもない。
これこそ「敗戦」というものの非情な現実なのである。
忍従するところは忍従し、
戦勝国の言い分を聞き流すところは聞き流し、
最終的には、
再軍備を成し遂げ、
自主憲法を持ち、
米国からの服属を脱して独自外交を展開するドイツ!
片や、戦勝国の言い分をそのまま真に受け、従属の優等生と
なることで国家の芯を抜かれてしまった日本。
現在の日本のおかれた状況は、まさに末期的と言ってよい。
だが考えてみれば、日本人はこれまでもこうした歴史的危機に
何度も直面し、その都度立ち上がってきたのだ。
私は日本民族のその力を信じたい>>
ー日本とドイツの戦後を分けたものー
クライン 孝子 (著)
(著者まえがきより)
<<先の大戦におけるドイツのロシアに対する怨念は、
日本と同様かそれ以上に大きいものがある。
大戦中にドイツが失った領土問題もいまだくすぶり、
完全に解決したわけではない。
だがドイツは、未来志向で現実路線に徹することで、
確実にその成果を手にしているのだ。
片や日本はどうか。
日本でもサハリン沖の天然ガス田を共同開発し、
日ロ間を結ぶパイプラインを建設する計画が検討されてはいた。
だが、もろもろの事情から計画は白紙撤回され、
サハリンの天然ガスは全量が中国に回されてしまった。
かくしてエネルギー獲得競争において、
日本はここでもまた、大きく立ち遅れてしまった。
その原因は何か。
一つには、北方領土をめぐる日本の頑な態度に、
ロシアが業を煮やしたことは疑いの余地がない。
戦後六〇余年、日本はこの問題では一歩も引かぬ態度で交渉
にのぞみ、その間両国は、得るものが何もなかった。
いうなれば、不毛の議論のまま、いたずらに時を過ごしてきたのだ。
では、欧州では、この交渉をどのように見ているであろうか。
「戦争で負けて失った領土を取り戻したいと思うなら、
もう一度戦争して勝つことだ」
この一言で、終わりである。
それが長い間戦争を繰り返してきた欧州人にとっての
歴史の常識であり、
戦争に負けていながら、過去の条約や取り決めを持ちだして
領土の返還を要求するなど、ナンセンス以外の何物でもない。
これこそ「敗戦」というものの非情な現実なのである。
忍従するところは忍従し、
戦勝国の言い分を聞き流すところは聞き流し、
最終的には、
再軍備を成し遂げ、
自主憲法を持ち、
米国からの服属を脱して独自外交を展開するドイツ!
片や、戦勝国の言い分をそのまま真に受け、従属の優等生と
なることで国家の芯を抜かれてしまった日本。
現在の日本のおかれた状況は、まさに末期的と言ってよい。
だが考えてみれば、日本人はこれまでもこうした歴史的危機に
何度も直面し、その都度立ち上がってきたのだ。
私は日本民族のその力を信じたい>>
知らなきゃヤバイ!石油ピークで食糧危機が訪れる (B&Tブックス) (単行本)
石井 吉徳 (著)
2009.9.30
いつの間にー。
目次
1 石油ピークは食糧ピーク、そして文明ピーク(残りの石油埋蔵量は1兆バーレル。しかもこれまでより質が悪い
「石油ピーク」―広がる油田発見と消費量のギャップ ほか)
2 石油に替わる新エネルギーはあるのか?(石油は太陽エネルギーが濃縮された太古の遺産である
太陽エネルギーは脱石油の救世主となるか ほか)
3 石油ピークが現代社会の常識を変える(皆が期待する幾何級数的な経済成長は、有限地球では無理
大食の車に人は負ける!バイオ燃料は食料と競合する ほか)
4 石油ピーク後の生きる道「日本のプランB」(3Rは最初のReduceが大事、リサイクルはエネルギー問題
石油ピーク後に生き残る道は、自国を知ること。日本は世界六位の海岸線長大国 ほか)
石井 吉徳 (著)
2009.9.30
いつの間にー。
目次
1 石油ピークは食糧ピーク、そして文明ピーク(残りの石油埋蔵量は1兆バーレル。しかもこれまでより質が悪い
「石油ピーク」―広がる油田発見と消費量のギャップ ほか)
2 石油に替わる新エネルギーはあるのか?(石油は太陽エネルギーが濃縮された太古の遺産である
太陽エネルギーは脱石油の救世主となるか ほか)
3 石油ピークが現代社会の常識を変える(皆が期待する幾何級数的な経済成長は、有限地球では無理
大食の車に人は負ける!バイオ燃料は食料と競合する ほか)
4 石油ピーク後の生きる道「日本のプランB」(3Rは最初のReduceが大事、リサイクルはエネルギー問題
石油ピーク後に生き残る道は、自国を知ること。日本は世界六位の海岸線長大国 ほか)
『原油100ドル時代の成長戦略』柴田明夫・著
http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100220/ecc1002200505015-n1.htm
◇◇
金融危機もあり、一時の投機マネーがひいたことから価格がやや安定した原油。しかし、実際の需要も世界規模では静かに増加の一途をたどっている。資源量が増加しない以上、価格が今後も上昇するのは必至だ。
原油100ドル時代はすぐそこまで来ているのだ。
工業化を推し進める中国は、将来の資源争奪戦を見越して、石油など海外資源の権益確保や、戦略備蓄などの国家資源戦略を打ち出している。
一方、日本にとっての原油価格上昇は、世界に先駆けて資源浪費型の産業構造から太陽エネルギーなどの新エネルギー型に転換する最大の好機ともいえる。新興国が台頭する世界経済にあって、日本はどう生き残るのかを探る。(1365円、朝日新聞出版)
◇◇
実は、まだ読んでないのですが、SankeiBizに記事があったので。
解説から察するに、著者は新エネルギー推進みたいですね。
買いに行ってみます。
http://www.sankeibiz.jp/econome/news/100220/ecc1002200505015-n1.htm
◇◇
金融危機もあり、一時の投機マネーがひいたことから価格がやや安定した原油。しかし、実際の需要も世界規模では静かに増加の一途をたどっている。資源量が増加しない以上、価格が今後も上昇するのは必至だ。
原油100ドル時代はすぐそこまで来ているのだ。
工業化を推し進める中国は、将来の資源争奪戦を見越して、石油など海外資源の権益確保や、戦略備蓄などの国家資源戦略を打ち出している。
一方、日本にとっての原油価格上昇は、世界に先駆けて資源浪費型の産業構造から太陽エネルギーなどの新エネルギー型に転換する最大の好機ともいえる。新興国が台頭する世界経済にあって、日本はどう生き残るのかを探る。(1365円、朝日新聞出版)
◇◇
実は、まだ読んでないのですが、SankeiBizに記事があったので。
解説から察するに、著者は新エネルギー推進みたいですね。
買いに行ってみます。
超マクロ展望 世界経済の真実 http://amzn.to/gIpqkG
水野 和夫 (著), 萱野 稔人 (著)
新書: 240ページ
出版社: 集英社 (2010/11/17)
水野氏は著名なエコノミストですが、主流派とは異なり歴史的な視点から経済を
語る異色の人物で、最近は宗教学者との対談「資本主義2.0」なども行っています。
ぶっちゃけ、ちょっとぶっ飛び気味なところもあり、萱野氏の主張もどこまで信用していいのやらといった感じなのですが、ある程度踏み込んで思い切った議論をしないと、面白くもないと思うので、難しいところかとは思います。
そういう意味では、ある程度社会的信用が確立している水野氏の対談本としてはギリギリのラインかもしれません。
読んでいて驚いたのは、この本では資源価格の高騰が現在の世界経済の行き詰まりの根本原因であるかのような記述がいくつもあったことです。
特に、日本の長期デフレや、金融緩和をしてもインフレに向かわないことも、資源価格の高騰(および経済のグローバル化)に根本原因があるとしています。
端折って述べれば、資源価格が商品の価格に転嫁出来ないほど上昇してきた結果、インフレ(物価上昇)によって資源価格高騰の悪影響を吸収できなくなり、人件費カット→デフレに向かわざるを得ないということです。グローバル化により安い商品が入ってきていることや、労働コストを世界レベルで競争しなければならないことも影響しています。
現在、米国のQE2(量的金融緩和第二弾)が行われたり、日本でも成長戦略のためのさらなる金融緩和が議論されていますが、実物経済での成長が見込めない(資源価格が高くなることで、対後進国との交易条件が悪化)状態で、適度なインフレを期待して金融緩和をしてマネタリーベースを増やせば、金融商品(株式や長期債券、石油や小麦などのコモディティ投資)にお金がまわるだけで、あたらしいバブルを生むだけで、期待した成長は得られないと述べています。
現在の経済学者は、上記のような成長理論にいまも期待しており、希望的観測で成長ありきで将来設計をしているため、より財政問題が深刻化すると警告しています。ゼロ成長、マイナス成長を前提とした議論が必要でしょう。
脱成長の議論は様々ありますが、資源価格の重要性を説いた本書を潮田さんが毎日新聞でジェフ・ルービンと並べて紹介された気持ちが分かるような気が致しました。
水説:不況の「石油の指紋」=潮田道夫
http://mainichi.jp/select/opinion/ushioda/news/20101215ddm003070095000c.html
この記事は英字配信もされており
Rising oil prices, the recession and a new world order
http://mdn.mainichi.jp/perspectives/news/20101215p2a00m0na011000c.html
EnergyBulletin等でも紹介されています。
http://www.energybulletin.net/stories/2010-12-16/energy-economics-and-world-power-dec-16
水野 和夫 (著), 萱野 稔人 (著)
新書: 240ページ
出版社: 集英社 (2010/11/17)
水野氏は著名なエコノミストですが、主流派とは異なり歴史的な視点から経済を
語る異色の人物で、最近は宗教学者との対談「資本主義2.0」なども行っています。
ぶっちゃけ、ちょっとぶっ飛び気味なところもあり、萱野氏の主張もどこまで信用していいのやらといった感じなのですが、ある程度踏み込んで思い切った議論をしないと、面白くもないと思うので、難しいところかとは思います。
そういう意味では、ある程度社会的信用が確立している水野氏の対談本としてはギリギリのラインかもしれません。
読んでいて驚いたのは、この本では資源価格の高騰が現在の世界経済の行き詰まりの根本原因であるかのような記述がいくつもあったことです。
特に、日本の長期デフレや、金融緩和をしてもインフレに向かわないことも、資源価格の高騰(および経済のグローバル化)に根本原因があるとしています。
端折って述べれば、資源価格が商品の価格に転嫁出来ないほど上昇してきた結果、インフレ(物価上昇)によって資源価格高騰の悪影響を吸収できなくなり、人件費カット→デフレに向かわざるを得ないということです。グローバル化により安い商品が入ってきていることや、労働コストを世界レベルで競争しなければならないことも影響しています。
現在、米国のQE2(量的金融緩和第二弾)が行われたり、日本でも成長戦略のためのさらなる金融緩和が議論されていますが、実物経済での成長が見込めない(資源価格が高くなることで、対後進国との交易条件が悪化)状態で、適度なインフレを期待して金融緩和をしてマネタリーベースを増やせば、金融商品(株式や長期債券、石油や小麦などのコモディティ投資)にお金がまわるだけで、あたらしいバブルを生むだけで、期待した成長は得られないと述べています。
現在の経済学者は、上記のような成長理論にいまも期待しており、希望的観測で成長ありきで将来設計をしているため、より財政問題が深刻化すると警告しています。ゼロ成長、マイナス成長を前提とした議論が必要でしょう。
脱成長の議論は様々ありますが、資源価格の重要性を説いた本書を潮田さんが毎日新聞でジェフ・ルービンと並べて紹介された気持ちが分かるような気が致しました。
水説:不況の「石油の指紋」=潮田道夫
http://mainichi.jp/select/opinion/ushioda/news/20101215ddm003070095000c.html
この記事は英字配信もされており
Rising oil prices, the recession and a new world order
http://mdn.mainichi.jp/perspectives/news/20101215p2a00m0na011000c.html
EnergyBulletin等でも紹介されています。
http://www.energybulletin.net/stories/2010-12-16/energy-economics-and-world-power-dec-16
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ピークオイル 更新情報
ピークオイルのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37839人
- 2位
- 酒好き
- 170670人
- 3位
- マイミク募集はここで。
- 89534人