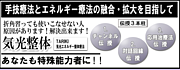以前「食物アレルギーの生徒が、給食で死んだ」というニュースがありましたが
患者さんの中にも食物アレルギーの方が居られます。
食物アレルギーの患者さんも増加の一途のようで、
アレルギー食品表示などの対応しか出来ていないのが現状のようです。
食物アレルギーですが・・私は、人工乳や、早すぎる離乳食が原因だと見ています。
すなわち、まだ腸の消化吸収機能や、防御機能が未熟な状態の乳児に対して
「離乳食は早ければ早いほどイイ」などという誤った指導が変更されない限り、
増え続けることになると、懸念しています。
(○ロックスのような履物が流行っていますが・・外反母趾の原因・指導と同じように・・)
胃腸の防御機能が未熟な乳児に母乳以外の食物を与えれば・・
未熟な腸を巣通りして、食物アレルギーになるのは当然ではないでしょうか!?
*******
吉野丈夫博士の“ちょっと待って○○治療”シリーズ小冊子などでも・・
妊娠前の母親の食生活や、ホルモン治療なども子供へ悪影響が及ぶようです。
私が購読している月刊誌の記事の中に、
母乳とミルクの違いが書かれていたので、引用して紹介します。
『「宇宙の法則」と心の持ち方、そして病気について』
鶴見クリニック院長:鶴見隆史
6月号の投稿の最後の表より
◎酵素:ミルク⇒ない:母乳⇒ある
◎免疫物質:ミルク⇒ない:母乳⇒ある
◎カルシウム:ミルク⇒母乳の4倍:母乳⇒ミルクの4分1
◎タンパクの質:ミルク⇒カゼイン;母乳⇒ホエイ
◎たんぱくの量:ミルク⇒母乳の4倍:母乳⇒ミルクの4分の1
7月号の投稿文
●『ミルク(牛)にカルシウムが多い理由と、母乳に少ない理由』
ミルク(牛)にカルシウムが多いのは当たり前だ。
牛は急速に骨を作り成長しなくてはならないからだ。人間はそれではいけない。
ゆっくりと少しづつ出来ていかないといけないようにできているのだ。
(略)
人間はそれ故、生後の2年間程重要な期間はないとなる。
将来才能を発揮する能力も、全身の健康のベースも、この2年間でしっかり作られる。
もしミルク(牛)のようにカルシウムが4倍も多い場合、
骨ばっかり急速に仕上がっていく。
こうなると、最も大切な所が後回しになりやすい。
バランスが崩れやすいのだ。
人間は、最も大切なところを含め、
全身がしっかりとバランスよく構築されなくてはいけない。
そのために、あらゆる栄養素をバランスよく供給する必要がある。
その最善のバランスされた栄養素こそ母乳にほかならない。
●『ミルク(牛)と母乳のタンパク質の質と量』
ミルク(牛)がカゼインタンパクで、量も4倍も多いのは当たり前だ。
牛は脳を作るより骨格をなにより作り上げなくてはいけないからだ。
牛には知的な能力など全く必要ない。
必要なのは600kgを支える筋肉と骨。
そのために、牛にとっては吸収が可能な、カゼインタンパク質を中心としたタンパクと、
カルシウムたっぷりのミルクがむしろ必要となる。
カゼインというニカワ状のタンパクは、人にとっては毒性は高いが、
牛にとってはありがたいものと言える。
足、腰、骨格を作るに必要なものは、何よりタンパク質とカルシウムだが、
その目的に応じて存在するのが、牛のミルクに他ならない。
しかし、人間にとっては、
この多すぎてかつ質の悪い(人間にとって)カゼインタンパクの供給は毒にしかならない。
前にも書いたが、カゼインタンパクはニカワ状のタンパク質で、これを人間が飲むと、
腸で炎症が起こったり、腐敗現象が起こる。
特に赤ちゃんには大変なダメージとなる。
つまり、
ミルク(牛)のカゼインタンパクは、人間にとっては毒にしかならない代物といえる。
量が4倍も多いのも問題だ。ただでさえ腸内腐敗をしやすいミルクだが、
4倍も多いことは、腐敗をさらに助長させることになるからだ。
それ故、ミルク(牛)にタンパク質が多いからといって、
栄養があるなどととても言えない。
人は栄養素はまんべんなくバランスよく存在したものでないといけないのだ。
ミネラル、ビタミン、酵素、良い脂質、適度なタンパク質、そしてブドウ糖。
タンパクばかり多いことが栄養があるとか、カルシウムが多いことが栄養があると
思っていたスポック博士は、全く目先だけの人でしかなかったと言える。
●『抱き癖について』
スポック博士は、自身は積極的に抱き癖をつけるなとは書いていないが、
この本が出てからいつの間にか、どういうわけか「抱き癖をとつけることは良くない」
「抱き癖は甘えの構図」という情報が飛び交うようになった。
日本では昭和40年代後半から言われ始めた。
その理由は、スポック博士の育児書が、「暮らしの手帖」で全訳され、掲載されたからだ。
スポックの本には、はっきりと書かれてはいないのに、
何故この本を契機にこんなことが言われたのだろうか。
思うに、
スポックの指導があまりにもミルク(牛)による子育てに傾斜していたからではないか?
「生後3ヶ月したら母乳とミルク(牛)は混合で」、
「生後すぐから混合でも構わない」
「場合によっては初めからミルク(牛)オンリーで構わない」。
こんな主張は次に飛躍する。
「母乳で育てることは、しっかり抱いておっぱいを吸わせるが、
ミルク(牛)で育てることは、しっかり抱かなくても
哺乳瓶を赤ちゃんの口にくわえさせれば良い。ということは抱くという必要もない」
この理屈は、「抱き癖は甘えにつながる」に飛躍したのではないか?
きっと誰かが「ミルクっ子なら抱かないでも良いのだから。抱くことはやらなくても良い」
となり、その理屈をつけるために「抱く」と甘えの構図を作り上げることを
何かで発表したのではないかと思われる。
その結果、とんでもない情報が乱れ飛んだのだと思う。
しかし、これ程馬鹿馬鹿しい大嘘もない。
実は、抱いて、抱いて、抱きまくって、母乳で育てた子は、
大人になって単に健康になっているのみならず、
心のきれいな、精神性の高い人が多いというデータもある。
「抱き癖=甘え」ではない。
母乳=抱き癖は情緒、人間味、愛につながる。
3年もしっかりと母乳と抱き癖で育った子は、極めて「愛」を知る子供となるのだ。
その結果、感受性豊かで、優しい性格になり、
老人や子供を思いやり労わる心温かい人になっていくことが多い。
こういった人は、仕事も優秀だし、趣味も豊富で、心の深い人が多い。
こういう良い人格のベースは、母親にたっぷりと愛をもらって育った結果なのだ。
赤ちゃんを抱くということは極めて大事なことだ。
強いスキンシップは、後年人を愛せる土壌になっていくからである。
抱き癖などではない。
抱いて愛が育つのだ。
スポックの悪い波紋は、こんなところにも出ているのである。
以下、省略
******* *******
「いいねタウン」の気光整体東陽
http://
|
|
|
|
|
|
|
|
名人治療家をめざそう! 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
名人治療家をめざそう!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37836人
- 2位
- 酒好き
- 170666人
- 3位
- マイミク募集はここで。
- 89532人