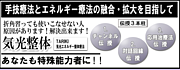約10年前「腱鞘炎」と診断され(治療効果がないので)
次に、「リウマチ」と診断されて、10年間に渡る「リウマチ治療」で、
関節も変形し“本物のリウマチ”に!
「このまま行くと、ますます“深みに入り込んでいくようで恐い”」
と、来院されている女性がいます。
また、
先月「妻が(病院で)リウマチと言われたが・・治せる?」と問い合わせがありました。
以下の『リウマチに対する現代医療』をパソコンで打っていたら・・
その彼の奥さんが、7月2日、
「毎朝、手がこわばって・・手も、腕も痛いし・・」と、来院されました。
私の「靭帯理論(靭帯−交感神経―骨格筋緊張)」で、彼女の身体を使いながら
リウマチなどでは全くないことを、体感して頂きました。
私の説明と、彼女の自覚症状がピッタリ会うものですから安心して頂いたようです。
(「リウマチの疑いがある」と病院で言われて、かなりのショックだったようです。)
勿論、その場で痛みも解消されて・・(その後のアドバイスも)
何故“本物のリウマチにさせられる”のか?その理由(わけ)を、以下に紹介します。
******* ******* *******
(株)アーデンモアのコミュニケーション紙『Triangle No.13』(2012・2)
吉野丈夫 描きおろし「病気と薬」13 自然治癒力と対症療法(5)の全文紹介です。
【リウマチに対する現代医療】
例えば、朝起きると指先が固まっているなどの症状を訴えますと、
医師はまずリウマチを疑います。
そして、血液検査をし、とりあえず痛み止めを処方するでしょう。
鎮痛剤は、内服薬だけでなく、ハップ薬(貼付薬)などの外用薬も
同時に処方するかもしれません。
これはリウマチを前提としての投薬ですから、
はじめから強い薬を処方するのが一般的です。
すべての解熱鎮痛薬、消炎鎮痛剤は
プロスタグランディン(発熱・発痛・治癒ホルモン)の合成阻害薬です。
図1に重大な副作用を示したインドメタシンは、
「バファリン」の成分であるアスピリンと比べると、
鎮痛効果では約30倍、プロスタグランディン合成阻害効果では166倍という
強力な薬剤です。
「ロキソニン」はさらに強力で、インドメタシンと比べてさらに10〜20倍の強さの薬です。
したがって、「痛み」の対処ということではよく効くはずです。
******* *******
図1; インドメタシンカプセル:非ステロイド性消炎・鎮痛・解熱剤 劇薬
(1)重大な副作用
1)ショック、アナフィラキシー様症状(いずれも頻度不明)
2)消化管穿孔、消化管出血、消化管潰瘍、腸管の狭窄・閉塞、潰瘍性大腸炎
(いずれも頻度不明)
3)再生不良性貧血、溶血性貧血、骨髄抑制、無顆粒球症(いずれも頻度不明)
4)皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、
中毒性表皮壊死症(Lyell症候群)剥脱性皮膚炎(いずれも頻度不明)
5)喘息発作(アスピリン喘息)(頻度不明)
6)急性腎不全、間質性腎炎、ネフローゼ症候群(いずれも頻度不明)
7)痙攣、昏睡、錯乱(いずれも頻度不明)
8)性器出血(頻度不明)
9)うっ血性心不全、肺水腫(いずれも頻度不明)
10)血管浮腫(頻度不明)
11)肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)
******* *******
●しかし、根本解決にはならないどころか、
こわばりを悪化させることにもなりかねない薬剤です。
鎮痛剤はプロスタグランディンの合成を阻害することによって痛みを緩和しますが、
その結果強い交感神経支配に転じます。
すると、白血球の中の顆粒球が増えてきます。
【私注:新潟大学大学院教授の安保徹先生の自律神経バランス免疫理論;
大まかに言えば・・
交感神経の神経伝達物質(アドレナリンなど)のレセプターを持つのが顆粒球であり、
副交感神経の神経伝達物質(アセチルコリン)のレセプターを持つのがリンパ球
即ち、白血球は自律神経のコントロール支配下にある。】
顆粒球は活性酸素(悪玉酸素)を発生しますから、炎症が再発するのです。
活性酸素は炎症の原因物質です。
つまり、一時的な痛み止め効果はあるものの、
炎症を再発させ、次の痛みの原因を作ってしまうのが、解熱鎮痛剤の正体なのです。
●こわばりは治らないけれど痛みには効くので鎮痛剤を使い続けていると、
1〜2ヶ月後には血液検査でもリウマチ反応が確認されるようになり
「やっぱりリウマチでしたね」と、リウマチの診断をされることになります。
リウマチと診断されると、鎮痛剤に加えてステロイド薬や、免疫抑制薬など、
さらに強い薬が処方されることになります。
これらの薬剤もより強力な「痛み止め」であり、治していく薬(根治薬)でもなければ、
症状が進むのを遅らせる薬でもありません。
逆に、症状の悪化に拍車を掛ける薬剤であるのは間違いないのです。
●ステロイド剤は活性酸素を除去しますので、
一時的ではありますが強力な消炎作用を発揮します。
しかし、活性酸素と結びついたステロイドは酸化し、酸化ステロイドへと変性します。
酸化ステロイドは組織に蓄積して活性酸素を発生させ続けます。
したがって、よりひどい炎症を再発させることになるのです。
●ステロイド薬が特に危険なのは、
組織に蓄積して排泄しにくい物質になってしまう点にあります。
ステロイド薬でアトピー性皮膚炎の治療をしていた人が脱ステロイド治療を開始すると、
間もなく強烈なリバウンドに襲われるという事実は、酸化ステロイドの蓄積の害を
如実に物語っているのです。
参考までに、ステロイド薬の添付文書を図2に引用しておきます。
******* *******
図2; プレドニゾロン錠 合成副腎皮質ホルモン剤
(1)重大な副作用(頻度不明)
1)誘発感染症、感染症の憎悪
2)続発性副腎皮質機能不全、糖尿病
3)消化管潰瘍、消化管穿孔、消化管出血
4)膵炎
5)精神変調、うつ状態、痙攣
6)骨粗鬆症、大腿骨及び上腕骨等の骨頭無菌性壊死、ミオパチー
7)緑内障、後囊白内障、中心性漿液性網脈絡膜症、
多発性後極部網膜色素上皮症
8)血栓症
9)心筋梗塞、脳梗塞、動脈瘤
10)硬膜外脂肪腫
11)腱断裂
******* *******
●免疫抑制薬とは、簡単に言えば治癒反応を止めてしまうものです。
細胞が破壊された時には血流を促して細胞を再生しようとするメカニズムが、
身体には既にインプットされています。
副交感神経が働き、血管が拡張し、
血流が促進する反応は、自然治癒反応そのものなのですが、
この時に、発熱したり、腫れたり、痛みが出たりという不快症状も現れます。
つまり、発熱も腫れも痛みも治癒反応であるということです。
この治癒反応そのものを抑えつけてしまうのが、免疫抑制薬の働きです。
したがって、「痛み」は軽減するのです。
免疫抑制薬としては、臓器移植時に使う「タクロリムス」という薬剤が有名です。
これを軟膏にしたものが、アトピー治療に使われている「プロトピック」です。
また、抗がん薬はすべて、細胞再生を妨げる強力な免疫抑制薬と言えます。
●免疫抑制薬は「細胞毒」と言い換えても過言ではありません。
図3の「リウマトレックス」はリウマチの治療薬として処方されるものですが、
その作用の仕方は免疫抑制薬そのものです。
この医師向け添付文書の重大な副作用を参照していただければ、
細胞毒であり進行を抑える薬などではあり得ないことは明らかでしょう。
******* *******
図3; リウマトレックス 抗リウマチ剤 劇薬
(1) 重大な副作用
1)ショック、アナフィラキシー様症状(いずれも頻度不明)
2)骨髄抑制(0.1〜5%未満)
3)感染症(0.1〜5%未満)
4)劇症肝炎、肝不全(いずれも頻度不明)
5)急性腎不全、尿細管壊死、重症ネフロパチー(いずれも頻度不明)
6)間質性肺炎(0.1〜5%未満)、肺線維症(0.1%未満)胸水(頻度不明)
7)中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)、
皮膚粘膜眼症候群(Steven-Johnson症候群)(いずれも頻度不明)
8)出血性腸炎、壊死性腸炎(いずれも頻度不明)
9)膵炎(0.1%未満)
10)骨粗鬆症(頻度不明)
11)脳症(白質脳症を含む)(頻度不明)
******* *******
●このようにして「インドメタシン」や「ロキソニン」からスタートした治療が、
+ステロイド、+免疫抑制薬となり、大量の活性酸素が発生し、
やがて骨を溶かして関節を変形させ、本物のリウマチ患者になってしまうのです。
ステロイド薬や免疫抑制薬が骨を溶かす(骨粗鬆症)というのは、
次のようなプロセスをたどった結果です。
骨は、ミネラル:タンパク質=1:3の割合で構成されています。
ミネラルの大部分はカルシウムであり、タンパク質の大部分はコラーゲンですので、
単純に、カルシウム:コラーゲン=1:3と考えても良いでしょう。
つまり、コラーゲンの中にカルシウムが練り込まれたものが骨なのです。
皮膚の新陳代謝サイクルは約1ヶ月です。
骨の場合は約1年かかります。
新陳代謝のサイクルの長さにはだいぶ差がありますが、
皮膚も骨も主成分はコラーゲンです。
図4を参照して下さい。
コラーゲンには必ず、それを分解するコラゲナーゼという酵素が付いています。
さらにコラゲナーゼが適切な時期まで働かないようにロックしておくために、
コラゲナーゼインヒビターというタンパク質も付いています。
つまり、コラーゲンと、コラゲナーゼと、コラゲナーゼインヒビターが
3つ揃って1つのセットになっているのです。
******* *******
図4; コラーゲンの代謝のしくみ
◎:コラーゲン □:コラゲナーゼ △:コラゲナーゼインヒビター
◎□△←活性酸素 (活性酸素がコラゲナーゼインヒビターを破壊)
◎←□ (コラゲナーゼがコラーゲンを分解)
◎□△ (新しいコラーゲンが入れ替わる)
******* *******
活性酸素によってコラゲナーゼインヒビターが破壊されると、ロックが解除されて
コラゲナーゼが働き、コラーゲンが分解されます。
この代謝サイクルが皮膚では約1ヶ月であり、骨では約1年ということです。
活性酸素は悪玉酸素と呼ばれてはいるものの、
新陳代謝の起点となる働きを担っているのです。
●アトピーの人の皮膚がゴワゴワと固くなるのは、
酸化ステロイドが発生させる大量の活性酸素によって、
コラゲナーゼインヒビターが次々と破壊されるため、
コラーゲンがハイペースで分解されて皮膚が角質化したためと考えられます。
つまり、本来は1ヶ月で角質化する皮膚が1ヶ月持たないということです。
同様に骨も、本来約1年で代謝すべきものが、
大量の活性酸素によって、コラーゲンがハイペースで分解されると、
コラーゲンに練り込まれていたカルシウムも流出してしまうのです。
このようなメカニズムで、ステロイド薬による骨粗鬆症、
免疫抑制薬による骨粗鬆症が発生すると考えられます。
解熱鎮痛薬・ステロイド薬・免疫抑制薬を用いたリウマチ治療は
いずれも「5つの自然治癒システム」と矛盾するのは明らかです。
*******
5つの自然治癒システム
1、免疫システム
2、細胞再生システム
3、解毒・代謝・排泄システム
4、活性酸素除去システム
5、微生物との共生システム
*******
●インドメタシンなどの解熱鎮痛薬治療は、強力に交感神経を支配しますので、
血流は阻害され、「2、細胞再生システム」の逆をやることになります。
活性酸素も増加しますので「4、活性酸素除去システム」の逆の治療にもなります。
ステロイド薬でも同様に血流が阻害されます。
一時的には活性酸素が除去されますので
「4、活性酸素除去システム」そのものを行うように見えますが、
あくまでも「一時的」に過ぎません。
酸化ステロイドへと変性した後は、大量の活性酸素を発生させ続けるので、大変危険です。
また、酸化ステロイドは血管にも蓄積しますので、
「3、解毒・代謝・排泄システム」にも反した治療と言えます。
免疫抑制薬に到っては、血流を阻害し、細胞の再生を妨げ、肝・腎機能を低下させ、
活性酸素を増加し、腸の善玉菌を減少させるのですから、1〜5、すべてに反した治療です。
●つまり、現在行われているリウマチ治療は「痛みの緩和」だけの治療であり、
治癒を目的とするものでも、悪化を遅らせるものでもありません。
むしろ、悪化に拍車をかける治療であるというのが結論です。
次に、「リウマチ」と診断されて、10年間に渡る「リウマチ治療」で、
関節も変形し“本物のリウマチ”に!
「このまま行くと、ますます“深みに入り込んでいくようで恐い”」
と、来院されている女性がいます。
また、
先月「妻が(病院で)リウマチと言われたが・・治せる?」と問い合わせがありました。
以下の『リウマチに対する現代医療』をパソコンで打っていたら・・
その彼の奥さんが、7月2日、
「毎朝、手がこわばって・・手も、腕も痛いし・・」と、来院されました。
私の「靭帯理論(靭帯−交感神経―骨格筋緊張)」で、彼女の身体を使いながら
リウマチなどでは全くないことを、体感して頂きました。
私の説明と、彼女の自覚症状がピッタリ会うものですから安心して頂いたようです。
(「リウマチの疑いがある」と病院で言われて、かなりのショックだったようです。)
勿論、その場で痛みも解消されて・・(その後のアドバイスも)
何故“本物のリウマチにさせられる”のか?その理由(わけ)を、以下に紹介します。
******* ******* *******
(株)アーデンモアのコミュニケーション紙『Triangle No.13』(2012・2)
吉野丈夫 描きおろし「病気と薬」13 自然治癒力と対症療法(5)の全文紹介です。
【リウマチに対する現代医療】
例えば、朝起きると指先が固まっているなどの症状を訴えますと、
医師はまずリウマチを疑います。
そして、血液検査をし、とりあえず痛み止めを処方するでしょう。
鎮痛剤は、内服薬だけでなく、ハップ薬(貼付薬)などの外用薬も
同時に処方するかもしれません。
これはリウマチを前提としての投薬ですから、
はじめから強い薬を処方するのが一般的です。
すべての解熱鎮痛薬、消炎鎮痛剤は
プロスタグランディン(発熱・発痛・治癒ホルモン)の合成阻害薬です。
図1に重大な副作用を示したインドメタシンは、
「バファリン」の成分であるアスピリンと比べると、
鎮痛効果では約30倍、プロスタグランディン合成阻害効果では166倍という
強力な薬剤です。
「ロキソニン」はさらに強力で、インドメタシンと比べてさらに10〜20倍の強さの薬です。
したがって、「痛み」の対処ということではよく効くはずです。
******* *******
図1; インドメタシンカプセル:非ステロイド性消炎・鎮痛・解熱剤 劇薬
(1)重大な副作用
1)ショック、アナフィラキシー様症状(いずれも頻度不明)
2)消化管穿孔、消化管出血、消化管潰瘍、腸管の狭窄・閉塞、潰瘍性大腸炎
(いずれも頻度不明)
3)再生不良性貧血、溶血性貧血、骨髄抑制、無顆粒球症(いずれも頻度不明)
4)皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、
中毒性表皮壊死症(Lyell症候群)剥脱性皮膚炎(いずれも頻度不明)
5)喘息発作(アスピリン喘息)(頻度不明)
6)急性腎不全、間質性腎炎、ネフローゼ症候群(いずれも頻度不明)
7)痙攣、昏睡、錯乱(いずれも頻度不明)
8)性器出血(頻度不明)
9)うっ血性心不全、肺水腫(いずれも頻度不明)
10)血管浮腫(頻度不明)
11)肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)
******* *******
●しかし、根本解決にはならないどころか、
こわばりを悪化させることにもなりかねない薬剤です。
鎮痛剤はプロスタグランディンの合成を阻害することによって痛みを緩和しますが、
その結果強い交感神経支配に転じます。
すると、白血球の中の顆粒球が増えてきます。
【私注:新潟大学大学院教授の安保徹先生の自律神経バランス免疫理論;
大まかに言えば・・
交感神経の神経伝達物質(アドレナリンなど)のレセプターを持つのが顆粒球であり、
副交感神経の神経伝達物質(アセチルコリン)のレセプターを持つのがリンパ球
即ち、白血球は自律神経のコントロール支配下にある。】
顆粒球は活性酸素(悪玉酸素)を発生しますから、炎症が再発するのです。
活性酸素は炎症の原因物質です。
つまり、一時的な痛み止め効果はあるものの、
炎症を再発させ、次の痛みの原因を作ってしまうのが、解熱鎮痛剤の正体なのです。
●こわばりは治らないけれど痛みには効くので鎮痛剤を使い続けていると、
1〜2ヶ月後には血液検査でもリウマチ反応が確認されるようになり
「やっぱりリウマチでしたね」と、リウマチの診断をされることになります。
リウマチと診断されると、鎮痛剤に加えてステロイド薬や、免疫抑制薬など、
さらに強い薬が処方されることになります。
これらの薬剤もより強力な「痛み止め」であり、治していく薬(根治薬)でもなければ、
症状が進むのを遅らせる薬でもありません。
逆に、症状の悪化に拍車を掛ける薬剤であるのは間違いないのです。
●ステロイド剤は活性酸素を除去しますので、
一時的ではありますが強力な消炎作用を発揮します。
しかし、活性酸素と結びついたステロイドは酸化し、酸化ステロイドへと変性します。
酸化ステロイドは組織に蓄積して活性酸素を発生させ続けます。
したがって、よりひどい炎症を再発させることになるのです。
●ステロイド薬が特に危険なのは、
組織に蓄積して排泄しにくい物質になってしまう点にあります。
ステロイド薬でアトピー性皮膚炎の治療をしていた人が脱ステロイド治療を開始すると、
間もなく強烈なリバウンドに襲われるという事実は、酸化ステロイドの蓄積の害を
如実に物語っているのです。
参考までに、ステロイド薬の添付文書を図2に引用しておきます。
******* *******
図2; プレドニゾロン錠 合成副腎皮質ホルモン剤
(1)重大な副作用(頻度不明)
1)誘発感染症、感染症の憎悪
2)続発性副腎皮質機能不全、糖尿病
3)消化管潰瘍、消化管穿孔、消化管出血
4)膵炎
5)精神変調、うつ状態、痙攣
6)骨粗鬆症、大腿骨及び上腕骨等の骨頭無菌性壊死、ミオパチー
7)緑内障、後囊白内障、中心性漿液性網脈絡膜症、
多発性後極部網膜色素上皮症
8)血栓症
9)心筋梗塞、脳梗塞、動脈瘤
10)硬膜外脂肪腫
11)腱断裂
******* *******
●免疫抑制薬とは、簡単に言えば治癒反応を止めてしまうものです。
細胞が破壊された時には血流を促して細胞を再生しようとするメカニズムが、
身体には既にインプットされています。
副交感神経が働き、血管が拡張し、
血流が促進する反応は、自然治癒反応そのものなのですが、
この時に、発熱したり、腫れたり、痛みが出たりという不快症状も現れます。
つまり、発熱も腫れも痛みも治癒反応であるということです。
この治癒反応そのものを抑えつけてしまうのが、免疫抑制薬の働きです。
したがって、「痛み」は軽減するのです。
免疫抑制薬としては、臓器移植時に使う「タクロリムス」という薬剤が有名です。
これを軟膏にしたものが、アトピー治療に使われている「プロトピック」です。
また、抗がん薬はすべて、細胞再生を妨げる強力な免疫抑制薬と言えます。
●免疫抑制薬は「細胞毒」と言い換えても過言ではありません。
図3の「リウマトレックス」はリウマチの治療薬として処方されるものですが、
その作用の仕方は免疫抑制薬そのものです。
この医師向け添付文書の重大な副作用を参照していただければ、
細胞毒であり進行を抑える薬などではあり得ないことは明らかでしょう。
******* *******
図3; リウマトレックス 抗リウマチ剤 劇薬
(1) 重大な副作用
1)ショック、アナフィラキシー様症状(いずれも頻度不明)
2)骨髄抑制(0.1〜5%未満)
3)感染症(0.1〜5%未満)
4)劇症肝炎、肝不全(いずれも頻度不明)
5)急性腎不全、尿細管壊死、重症ネフロパチー(いずれも頻度不明)
6)間質性肺炎(0.1〜5%未満)、肺線維症(0.1%未満)胸水(頻度不明)
7)中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)、
皮膚粘膜眼症候群(Steven-Johnson症候群)(いずれも頻度不明)
8)出血性腸炎、壊死性腸炎(いずれも頻度不明)
9)膵炎(0.1%未満)
10)骨粗鬆症(頻度不明)
11)脳症(白質脳症を含む)(頻度不明)
******* *******
●このようにして「インドメタシン」や「ロキソニン」からスタートした治療が、
+ステロイド、+免疫抑制薬となり、大量の活性酸素が発生し、
やがて骨を溶かして関節を変形させ、本物のリウマチ患者になってしまうのです。
ステロイド薬や免疫抑制薬が骨を溶かす(骨粗鬆症)というのは、
次のようなプロセスをたどった結果です。
骨は、ミネラル:タンパク質=1:3の割合で構成されています。
ミネラルの大部分はカルシウムであり、タンパク質の大部分はコラーゲンですので、
単純に、カルシウム:コラーゲン=1:3と考えても良いでしょう。
つまり、コラーゲンの中にカルシウムが練り込まれたものが骨なのです。
皮膚の新陳代謝サイクルは約1ヶ月です。
骨の場合は約1年かかります。
新陳代謝のサイクルの長さにはだいぶ差がありますが、
皮膚も骨も主成分はコラーゲンです。
図4を参照して下さい。
コラーゲンには必ず、それを分解するコラゲナーゼという酵素が付いています。
さらにコラゲナーゼが適切な時期まで働かないようにロックしておくために、
コラゲナーゼインヒビターというタンパク質も付いています。
つまり、コラーゲンと、コラゲナーゼと、コラゲナーゼインヒビターが
3つ揃って1つのセットになっているのです。
******* *******
図4; コラーゲンの代謝のしくみ
◎:コラーゲン □:コラゲナーゼ △:コラゲナーゼインヒビター
◎□△←活性酸素 (活性酸素がコラゲナーゼインヒビターを破壊)
◎←□ (コラゲナーゼがコラーゲンを分解)
◎□△ (新しいコラーゲンが入れ替わる)
******* *******
活性酸素によってコラゲナーゼインヒビターが破壊されると、ロックが解除されて
コラゲナーゼが働き、コラーゲンが分解されます。
この代謝サイクルが皮膚では約1ヶ月であり、骨では約1年ということです。
活性酸素は悪玉酸素と呼ばれてはいるものの、
新陳代謝の起点となる働きを担っているのです。
●アトピーの人の皮膚がゴワゴワと固くなるのは、
酸化ステロイドが発生させる大量の活性酸素によって、
コラゲナーゼインヒビターが次々と破壊されるため、
コラーゲンがハイペースで分解されて皮膚が角質化したためと考えられます。
つまり、本来は1ヶ月で角質化する皮膚が1ヶ月持たないということです。
同様に骨も、本来約1年で代謝すべきものが、
大量の活性酸素によって、コラーゲンがハイペースで分解されると、
コラーゲンに練り込まれていたカルシウムも流出してしまうのです。
このようなメカニズムで、ステロイド薬による骨粗鬆症、
免疫抑制薬による骨粗鬆症が発生すると考えられます。
解熱鎮痛薬・ステロイド薬・免疫抑制薬を用いたリウマチ治療は
いずれも「5つの自然治癒システム」と矛盾するのは明らかです。
*******
5つの自然治癒システム
1、免疫システム
2、細胞再生システム
3、解毒・代謝・排泄システム
4、活性酸素除去システム
5、微生物との共生システム
*******
●インドメタシンなどの解熱鎮痛薬治療は、強力に交感神経を支配しますので、
血流は阻害され、「2、細胞再生システム」の逆をやることになります。
活性酸素も増加しますので「4、活性酸素除去システム」の逆の治療にもなります。
ステロイド薬でも同様に血流が阻害されます。
一時的には活性酸素が除去されますので
「4、活性酸素除去システム」そのものを行うように見えますが、
あくまでも「一時的」に過ぎません。
酸化ステロイドへと変性した後は、大量の活性酸素を発生させ続けるので、大変危険です。
また、酸化ステロイドは血管にも蓄積しますので、
「3、解毒・代謝・排泄システム」にも反した治療と言えます。
免疫抑制薬に到っては、血流を阻害し、細胞の再生を妨げ、肝・腎機能を低下させ、
活性酸素を増加し、腸の善玉菌を減少させるのですから、1〜5、すべてに反した治療です。
●つまり、現在行われているリウマチ治療は「痛みの緩和」だけの治療であり、
治癒を目的とするものでも、悪化を遅らせるものでもありません。
むしろ、悪化に拍車をかける治療であるというのが結論です。
|
|
|
|
|
|
|
|
名人治療家をめざそう! 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
名人治療家をめざそう!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37847人
- 3位
- 楽天イーグルス
- 31945人