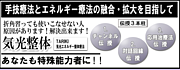生理学博士:吉野丈夫先生の“ちょっと待って”シリーズを1冊ずつ読んでいますが
ますます、薬害の知識が大切であると痛感しているところです。
精一杯引用して紹介します。
********
『はじめに』
他のいろいろな病気について論述しても、がんについて書くことはこれまでしてきませんでした。書こうと思っても書く気にならなかったのです。
がんに関する情報が少ないわけではありません。なぜ発症するのか、どうすれば治癒するのか、治癒に至らないとしてもできるだけの長寿を達成するために何をすればいいのか、
三大治療(手術・抗がん剤・放射線)についての是非、また、免疫療法など他の療法についての是非などなど、他の病気と同様に筆者なりの考えを提示することはできます。
では、なぜ書く気にならなかったのか?たぶん、無力感かもしれません。他の病気であれば筆者の考えに賛同し、「HMSで治癒しよう」と決意し、実践してくれる人は多く、そして実際に数多くの治癒体験も出ています。しかし、がんに関してはたとえカウンセリングをしても、最終的に三大治療を選択してしまい、残念なことになっている例が多いのです。
がんに関して多くの人が抱く恐れと、筆者が抱いているイメージにはギャップがあります。
多くの人は、「がんは他の病気と比べて最悪のものである。不治の病であり、ひどい苦しみの中で世を去っていく」イメージを持っていると思います。
筆者はそうは思いません。がんと診断されたとしても、実は治癒しやすい「弱虫がんもどき」であるケースが多いのです。たとえ本物のがんであったとしても、免疫が勝てばがんは自然治癒、自然消滅するのです。仮に免疫が敗れ、寿命が尽きるとしても、三大治療さえしなければ安らかに旅立つことが可能なのです。
このギャップが「言っても無駄だ」というあきらめの気持ちを起こさせていたのかもしれません。
しかし、がんについての論述を避けて通ることはできませんし、どうせ書くなら、皆さんに筆者と同じイメージをもってもらえるようなものにしたいと思っています。
「がん治癒論」を書きます。この本を手にした人が、次々とがん治癒に成功して欲しいと思います。
******** *******
私は、日常施術・治療を通して・・がん患者さんに関して、
「はじめに」に書かれているのと、同じような気持ちを持つものですが・・
(私のがん患者治療初体験は2001年:中高度非ホジキン悪性リンパ腫第4期と診断された方でした)しかし、折角、(担当医の最終診断で「不思議や!4分の一に縮小している」と言われた)本人は、私の治療継続を願ったにもかかわらず、家族の反対で・・結局、抗がん剤、放射線治療を受けて・・
11年後の現在もお元気ですが(冷えやシビレなどの)副作用で今も苦しんで居られます。
“ちょっと待って”から続けます。
******* *******
1「がんもどき」理論
慶応義塾大学医学部講師:近藤誠先生の『患者よ、がんと闘うな』は、多くの人に衝撃を与えた著書だと思います。特に「抗がん剤」「手術」治療を行なっている医療関係者にとっては、そのほとんどを否定されてしまったわけですから、激震だったと言っても過言ではないでしょう。
では、その後12年が経過した2008年現在、がん治療は変化したでしょうか・乳がんにおける乳房温存療法が増えた点は前進したようですが、それ以外はあまり変わっていません。
ちょっと長くなりますが、近藤先生の最近の著書を引用致します。2008年5月時点での「あとがき」です。
『名医の「有害な治療」「死を早める手術」−患者が知らない医の本音−』よりp.359~364
あとがき−検査や治療の現在
ここでは、対談後から2008年現在にいたるまで、がんの検査や治療の面でどのような変化が見られたのか、あるいは見られなかったのか、簡単に紹介しておきたい。
●手術
一部の臓器で、手術範囲の縮小化や、他の治療法への鞍替え傾向が生じている。
例えば乳がんでは、かっての標準法だった乳房全摘術が減り、乳房部分切除にとどめて乳房を残す、いわゆる乳房温存療法の施行率が5割を超えた。また早期胃がんの場合、なるべく内視鏡でちりょうして胃袋を残そうという風潮にもなっている。が、問題も残っている。
例えば、乳房温存療法が可能なのに、乳房の部分切除をするより格好が良くなるからと、全摘手術と同時に乳房再生術を行うことが一部に広がりつつある。ところが再建乳房は、人工的な乳房だから、実のところそう格好よくなるわけではない。また、お腹や背中から筋肉を切り取って移動させるという大がかりな手術だと、失敗しやすく、再建した乳房が壊死に陥るなど、ひどい後遺症が続発している。大きな手術や複雑な手術をしたい、という外科医の性根は、何年経っても矯正不能のようである。
早期胃がんの内視鏡治療にしても、技術的に困難となれば、結局胃切除手術になってしまう。そのうえ、もし「がんもどき」理論が正しければ、胃切除も内視鏡治療も、行う意味はないことになる。
●抗がん剤治療
全国統計はないが、抗がん剤治療は、10年前よりむしろ盛んになっているのではないか。多種類の臓器のがんで、若年者にも高齢者にも、また初期のがんにも進行がんにも、抗がん剤治療が行われている。
そうなったのは、がん告知の影響が大きいのだろう。一昔前まで、がん告知はタブーだったから、患者本人に「抗がん剤」とは言えず、うやむやのうちに抗がん剤を処方していた。しかしそれでは限界がある。患者は最初から飲まず、あるいは飲んでいても、副作用が出たら即座に止める人が多かった。それが現在では、患者本人に遠慮なく「がんだ」と告げるようになったので、「抗がん剤治療」と言われた患者は、恐怖や不安もあって担当医の言うがままになりやすいのである。
患者・家族が抗がん剤治療を選ぶについては、「良い新薬が出た」「今度の抗がん剤は、以前のより有効性が高いらしい」といった、マスコミ報道やインターネット情報の影響もあるだろう。
しかし、どんなに大勢に使われていようと、どのような新薬が開発されようと、抗がん剤の本質は変わらない。「細胞毒」である。抗がん剤の基本思想は、がん細胞を死滅させる、というものだが、がん細胞は正常細胞から分化したものであり、構造と機能がほぼ共通している。それゆえ、がん細胞だけを死滅させることは不可能で、正常細胞や正常組織も同様に死滅してしまう。そのうえ、死滅の割合やその影響は、がん細胞よりも正常細胞のほうが大きいのが通常である。こうして、どんな新薬も、「細胞毒」であるかぎり、抗がん剤の治療の限界を打破することはできない。
●放射線治療
多くの臓器で、手術から放射線治療への鞍替えが進んでいる。しかし、欧米に比べると、放射線治療を受ける患者はまだ少ない。つまり、多くの患者が、無駄な臓器全摘出をうけさせられている。子宮頸がんや膀胱がんで全摘出を勧められたら、別の病院の(!)放射線治療科を訪ねてみるべきである。
留意すべきは、一つには、放射線治療にも、手術と同じように「やりすぎ」の懸念があることである。徹底を期そうとすると、外科医は「できるだけ広く切りたい」となるが、放射線医は「できるだけたくさん照射したい」となりがちなのだ。しかし過剰照射になれば、合併症・後遺症の危険が何倍にもなってしまう。
今一つは、放射線治療に関しても、治療の必要性を考えてみなければならない。治療することを前提とするなら、手術よりも放射線治療のほうがすぐれている場合がほとんどである。平成の天皇は健診で前立腺がんが見つかり、全摘術になったが、放射線治療の方がベターだったと考える。しかし、検診発見がんは9割以上が「がんもどき」だから、放射線治療も必要でなかったのではないか。
●がん検診
がん検診に関しては、格別進展は見られない。集団検診や職場健診で、がんの検査が行われ続けているけれども、がん検診が有効だというデータは出てこない。
目を外国に転じると、乳がんのマンモグラフィ(乳房レントゲン撮影)検診の根拠となっていた試験結果を見直した学者がいて、マンモグラフィ検診では死亡数は減らない、と発表した。それで、ちゃぶ台をひっくり返したような騒ぎになり、当然のように検診肯定派が「乳がん死亡数を減らす」と猛反発した。しかし、発表データを見ると、総死亡数が減らないことは明らかで、そのことは検診肯定派も認めている。ということは、もし乳がん死亡数が減っているなら、(総死亡数が減らない以上)乳がん以外の死亡数が増えていることになるから、やはり意味はない。無理な反発である。それでも、検診実施主体を肯定派が占めて(否定派は検診事業に携わっていない)、総死亡数が変わらないということを公衆に伝えないから、マンモグラフィ検診は行われ続けている。
日本では、これまで、マンモグラフィ検診は一般的には実施されていなかったのだけれども、このような議論が生じたあとに、検診専門家も厚生労働省も、マンモグラフィ検診推進の旗を振り出した。逆のようだが、本当のことである。
――その目的は稼業隆盛にあるとでも考えなければ、説明がつかない。――ともかくも、マンモグラフィ検診を受ける女性が急増し、検診で発見される乳がんが増えている。その結果、非常に多数の女性が、乳房まで失っている。
けれども、そういう診療行為の妥当性には、ほかならぬ外科医自身から疑問が提起されている。乳房温存療法の有効性を世界で始めて立証した、イタリアの外科医(世間で言えば、大権威である)が、検診で発見される乳がんの多数を占める「非浸潤がん」(「乳管内がん」ともいう)は、本物のがんにふさわしい性質を備えていない、と言うのである。そして、非浸潤「がん」と呼ぶのを止めて、良性疾患を意味する病名に変更したほうがよい、と書いている(『Lancet』2005年、365巻、1727ぺージ)。これはつまり、非浸潤がんは「がんもどき」だ、と語っているのと同じである。
この10年で肺がん検診への「CT断層撮影装置」という精密機器の導入も進んだ。これを受けると、微小肺がんが以前の何倍も発見される。しかし無秩序に行われているから、説得力のあるデータは生まれず、肺がん死亡が減ったかどうか、皆目分からない。ところが最近、外国から試験結果が報告された。それによると、CT検診によっても、肺がん死亡率の減少は認められなかった。
CT検診で一番の問題は、その被曝線量の多さである。放射線の発がん効果は、被曝線量に比例するが、通常の胸部レントゲン撮影に比べて、CTの被曝は数十倍〜数百倍にもなる。他方で肺がん検診を受けようという人の大部分は、喫煙歴があって、もともと肺がんリスクが高い。したがって、非喫煙者に比べ、放射線の発がん効果がより高くなる可能性がある(少なくとも低くはならないだろう)。こういうことから私は、CT検診を受け続ける人は、長い目でみて、肺がんリスクをさらに高め、逆に寿命を縮める可能性が高いと見ている。
以上、近藤誠先生の言う「がんもどき」は、「転移しない良性の腫瘍」と理解すれば良いと思います。
近藤先生は、「がんもどき」も「がん」も一緒にして、徹底的な治療?をしている医療の実態に問題を投げかけたのです。実際に様々なダータの裏付けのもとに論ぜられておりますので、「がんもどき」理論は信頼性の高いものだと思います。
******** ********* *******
私の父も、(私が治療家になる前)“肺がん”を発見され、医師の弟が勤める県外の病院で手術。手遅れで余命6ヶ月との診断。(開胸されただけ)・・
その時、私は“最新の医学治療”を受けたら6ヶ月と理解して、どうしたら止めさせることが出来るかと考えていました。
病院からの帰宅後、放射線と、抗がん剤治療に通いましたが、数回目のとき、「病院で治療を受けると辛い」と言い出し、これ幸いに、すべての薬剤・治療を中止し、食事療法を提案・・(この時は、父は素直に同意してくれ実行しました)医師の弟から6ヶ月持たないから覚悟しろと言われましたが、6ヶ月過ぎる頃、顔色は良くなり、体重も増加傾向に・・
1年後には仕事にも復帰し、そのまま元気に過ごしましたが、
丸2年目の冬、少々風邪を引いたのがキッカケで・・当時の担当医が福井に変わったからと弟からの連絡で・・出向いたのが命取りでした。
担当医は風邪はそっちのけで、がんがどうなっているのか?と検査。「大きくも、小さくもなっていないが・・元気になったのだから、この際叩きましょう!ちょっと高いがイイ薬がありますから」と、始めて、(その時は、私の言うことは聞かなくなっていました)・・ちょうど6ヶ月後に父は逝きました。
父の“肺がん”は転移していないので近藤流に言えば「がんもどき」だったのでしょう。
父は、抗がん剤で殺されたということになりますか。
ますます、薬害の知識が大切であると痛感しているところです。
精一杯引用して紹介します。
********
『はじめに』
他のいろいろな病気について論述しても、がんについて書くことはこれまでしてきませんでした。書こうと思っても書く気にならなかったのです。
がんに関する情報が少ないわけではありません。なぜ発症するのか、どうすれば治癒するのか、治癒に至らないとしてもできるだけの長寿を達成するために何をすればいいのか、
三大治療(手術・抗がん剤・放射線)についての是非、また、免疫療法など他の療法についての是非などなど、他の病気と同様に筆者なりの考えを提示することはできます。
では、なぜ書く気にならなかったのか?たぶん、無力感かもしれません。他の病気であれば筆者の考えに賛同し、「HMSで治癒しよう」と決意し、実践してくれる人は多く、そして実際に数多くの治癒体験も出ています。しかし、がんに関してはたとえカウンセリングをしても、最終的に三大治療を選択してしまい、残念なことになっている例が多いのです。
がんに関して多くの人が抱く恐れと、筆者が抱いているイメージにはギャップがあります。
多くの人は、「がんは他の病気と比べて最悪のものである。不治の病であり、ひどい苦しみの中で世を去っていく」イメージを持っていると思います。
筆者はそうは思いません。がんと診断されたとしても、実は治癒しやすい「弱虫がんもどき」であるケースが多いのです。たとえ本物のがんであったとしても、免疫が勝てばがんは自然治癒、自然消滅するのです。仮に免疫が敗れ、寿命が尽きるとしても、三大治療さえしなければ安らかに旅立つことが可能なのです。
このギャップが「言っても無駄だ」というあきらめの気持ちを起こさせていたのかもしれません。
しかし、がんについての論述を避けて通ることはできませんし、どうせ書くなら、皆さんに筆者と同じイメージをもってもらえるようなものにしたいと思っています。
「がん治癒論」を書きます。この本を手にした人が、次々とがん治癒に成功して欲しいと思います。
******** *******
私は、日常施術・治療を通して・・がん患者さんに関して、
「はじめに」に書かれているのと、同じような気持ちを持つものですが・・
(私のがん患者治療初体験は2001年:中高度非ホジキン悪性リンパ腫第4期と診断された方でした)しかし、折角、(担当医の最終診断で「不思議や!4分の一に縮小している」と言われた)本人は、私の治療継続を願ったにもかかわらず、家族の反対で・・結局、抗がん剤、放射線治療を受けて・・
11年後の現在もお元気ですが(冷えやシビレなどの)副作用で今も苦しんで居られます。
“ちょっと待って”から続けます。
******* *******
1「がんもどき」理論
慶応義塾大学医学部講師:近藤誠先生の『患者よ、がんと闘うな』は、多くの人に衝撃を与えた著書だと思います。特に「抗がん剤」「手術」治療を行なっている医療関係者にとっては、そのほとんどを否定されてしまったわけですから、激震だったと言っても過言ではないでしょう。
では、その後12年が経過した2008年現在、がん治療は変化したでしょうか・乳がんにおける乳房温存療法が増えた点は前進したようですが、それ以外はあまり変わっていません。
ちょっと長くなりますが、近藤先生の最近の著書を引用致します。2008年5月時点での「あとがき」です。
『名医の「有害な治療」「死を早める手術」−患者が知らない医の本音−』よりp.359~364
あとがき−検査や治療の現在
ここでは、対談後から2008年現在にいたるまで、がんの検査や治療の面でどのような変化が見られたのか、あるいは見られなかったのか、簡単に紹介しておきたい。
●手術
一部の臓器で、手術範囲の縮小化や、他の治療法への鞍替え傾向が生じている。
例えば乳がんでは、かっての標準法だった乳房全摘術が減り、乳房部分切除にとどめて乳房を残す、いわゆる乳房温存療法の施行率が5割を超えた。また早期胃がんの場合、なるべく内視鏡でちりょうして胃袋を残そうという風潮にもなっている。が、問題も残っている。
例えば、乳房温存療法が可能なのに、乳房の部分切除をするより格好が良くなるからと、全摘手術と同時に乳房再生術を行うことが一部に広がりつつある。ところが再建乳房は、人工的な乳房だから、実のところそう格好よくなるわけではない。また、お腹や背中から筋肉を切り取って移動させるという大がかりな手術だと、失敗しやすく、再建した乳房が壊死に陥るなど、ひどい後遺症が続発している。大きな手術や複雑な手術をしたい、という外科医の性根は、何年経っても矯正不能のようである。
早期胃がんの内視鏡治療にしても、技術的に困難となれば、結局胃切除手術になってしまう。そのうえ、もし「がんもどき」理論が正しければ、胃切除も内視鏡治療も、行う意味はないことになる。
●抗がん剤治療
全国統計はないが、抗がん剤治療は、10年前よりむしろ盛んになっているのではないか。多種類の臓器のがんで、若年者にも高齢者にも、また初期のがんにも進行がんにも、抗がん剤治療が行われている。
そうなったのは、がん告知の影響が大きいのだろう。一昔前まで、がん告知はタブーだったから、患者本人に「抗がん剤」とは言えず、うやむやのうちに抗がん剤を処方していた。しかしそれでは限界がある。患者は最初から飲まず、あるいは飲んでいても、副作用が出たら即座に止める人が多かった。それが現在では、患者本人に遠慮なく「がんだ」と告げるようになったので、「抗がん剤治療」と言われた患者は、恐怖や不安もあって担当医の言うがままになりやすいのである。
患者・家族が抗がん剤治療を選ぶについては、「良い新薬が出た」「今度の抗がん剤は、以前のより有効性が高いらしい」といった、マスコミ報道やインターネット情報の影響もあるだろう。
しかし、どんなに大勢に使われていようと、どのような新薬が開発されようと、抗がん剤の本質は変わらない。「細胞毒」である。抗がん剤の基本思想は、がん細胞を死滅させる、というものだが、がん細胞は正常細胞から分化したものであり、構造と機能がほぼ共通している。それゆえ、がん細胞だけを死滅させることは不可能で、正常細胞や正常組織も同様に死滅してしまう。そのうえ、死滅の割合やその影響は、がん細胞よりも正常細胞のほうが大きいのが通常である。こうして、どんな新薬も、「細胞毒」であるかぎり、抗がん剤の治療の限界を打破することはできない。
●放射線治療
多くの臓器で、手術から放射線治療への鞍替えが進んでいる。しかし、欧米に比べると、放射線治療を受ける患者はまだ少ない。つまり、多くの患者が、無駄な臓器全摘出をうけさせられている。子宮頸がんや膀胱がんで全摘出を勧められたら、別の病院の(!)放射線治療科を訪ねてみるべきである。
留意すべきは、一つには、放射線治療にも、手術と同じように「やりすぎ」の懸念があることである。徹底を期そうとすると、外科医は「できるだけ広く切りたい」となるが、放射線医は「できるだけたくさん照射したい」となりがちなのだ。しかし過剰照射になれば、合併症・後遺症の危険が何倍にもなってしまう。
今一つは、放射線治療に関しても、治療の必要性を考えてみなければならない。治療することを前提とするなら、手術よりも放射線治療のほうがすぐれている場合がほとんどである。平成の天皇は健診で前立腺がんが見つかり、全摘術になったが、放射線治療の方がベターだったと考える。しかし、検診発見がんは9割以上が「がんもどき」だから、放射線治療も必要でなかったのではないか。
●がん検診
がん検診に関しては、格別進展は見られない。集団検診や職場健診で、がんの検査が行われ続けているけれども、がん検診が有効だというデータは出てこない。
目を外国に転じると、乳がんのマンモグラフィ(乳房レントゲン撮影)検診の根拠となっていた試験結果を見直した学者がいて、マンモグラフィ検診では死亡数は減らない、と発表した。それで、ちゃぶ台をひっくり返したような騒ぎになり、当然のように検診肯定派が「乳がん死亡数を減らす」と猛反発した。しかし、発表データを見ると、総死亡数が減らないことは明らかで、そのことは検診肯定派も認めている。ということは、もし乳がん死亡数が減っているなら、(総死亡数が減らない以上)乳がん以外の死亡数が増えていることになるから、やはり意味はない。無理な反発である。それでも、検診実施主体を肯定派が占めて(否定派は検診事業に携わっていない)、総死亡数が変わらないということを公衆に伝えないから、マンモグラフィ検診は行われ続けている。
日本では、これまで、マンモグラフィ検診は一般的には実施されていなかったのだけれども、このような議論が生じたあとに、検診専門家も厚生労働省も、マンモグラフィ検診推進の旗を振り出した。逆のようだが、本当のことである。
――その目的は稼業隆盛にあるとでも考えなければ、説明がつかない。――ともかくも、マンモグラフィ検診を受ける女性が急増し、検診で発見される乳がんが増えている。その結果、非常に多数の女性が、乳房まで失っている。
けれども、そういう診療行為の妥当性には、ほかならぬ外科医自身から疑問が提起されている。乳房温存療法の有効性を世界で始めて立証した、イタリアの外科医(世間で言えば、大権威である)が、検診で発見される乳がんの多数を占める「非浸潤がん」(「乳管内がん」ともいう)は、本物のがんにふさわしい性質を備えていない、と言うのである。そして、非浸潤「がん」と呼ぶのを止めて、良性疾患を意味する病名に変更したほうがよい、と書いている(『Lancet』2005年、365巻、1727ぺージ)。これはつまり、非浸潤がんは「がんもどき」だ、と語っているのと同じである。
この10年で肺がん検診への「CT断層撮影装置」という精密機器の導入も進んだ。これを受けると、微小肺がんが以前の何倍も発見される。しかし無秩序に行われているから、説得力のあるデータは生まれず、肺がん死亡が減ったかどうか、皆目分からない。ところが最近、外国から試験結果が報告された。それによると、CT検診によっても、肺がん死亡率の減少は認められなかった。
CT検診で一番の問題は、その被曝線量の多さである。放射線の発がん効果は、被曝線量に比例するが、通常の胸部レントゲン撮影に比べて、CTの被曝は数十倍〜数百倍にもなる。他方で肺がん検診を受けようという人の大部分は、喫煙歴があって、もともと肺がんリスクが高い。したがって、非喫煙者に比べ、放射線の発がん効果がより高くなる可能性がある(少なくとも低くはならないだろう)。こういうことから私は、CT検診を受け続ける人は、長い目でみて、肺がんリスクをさらに高め、逆に寿命を縮める可能性が高いと見ている。
以上、近藤誠先生の言う「がんもどき」は、「転移しない良性の腫瘍」と理解すれば良いと思います。
近藤先生は、「がんもどき」も「がん」も一緒にして、徹底的な治療?をしている医療の実態に問題を投げかけたのです。実際に様々なダータの裏付けのもとに論ぜられておりますので、「がんもどき」理論は信頼性の高いものだと思います。
******** ********* *******
私の父も、(私が治療家になる前)“肺がん”を発見され、医師の弟が勤める県外の病院で手術。手遅れで余命6ヶ月との診断。(開胸されただけ)・・
その時、私は“最新の医学治療”を受けたら6ヶ月と理解して、どうしたら止めさせることが出来るかと考えていました。
病院からの帰宅後、放射線と、抗がん剤治療に通いましたが、数回目のとき、「病院で治療を受けると辛い」と言い出し、これ幸いに、すべての薬剤・治療を中止し、食事療法を提案・・(この時は、父は素直に同意してくれ実行しました)医師の弟から6ヶ月持たないから覚悟しろと言われましたが、6ヶ月過ぎる頃、顔色は良くなり、体重も増加傾向に・・
1年後には仕事にも復帰し、そのまま元気に過ごしましたが、
丸2年目の冬、少々風邪を引いたのがキッカケで・・当時の担当医が福井に変わったからと弟からの連絡で・・出向いたのが命取りでした。
担当医は風邪はそっちのけで、がんがどうなっているのか?と検査。「大きくも、小さくもなっていないが・・元気になったのだから、この際叩きましょう!ちょっと高いがイイ薬がありますから」と、始めて、(その時は、私の言うことは聞かなくなっていました)・・ちょうど6ヶ月後に父は逝きました。
父の“肺がん”は転移していないので近藤流に言えば「がんもどき」だったのでしょう。
父は、抗がん剤で殺されたということになりますか。
|
|
|
|
|
|
|
|
名人治療家をめざそう! 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
名人治療家をめざそう!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 楽天イーグルス
- 31948人
- 2位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37152人
- 3位
- 一行で笑わせろ!
- 82527人