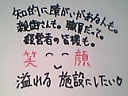障害者自立支援法に基づく 障害程度区分判定 シュミレーション
下案を作成するにあたっての視点
新しい基準に沿っての区分判定となります。この法律に基づいて認定された区分で、現在の法状況下では利用できるサービスが限定されることになります。
○○は知的障害者援護施設(入所更生)として施設入所支援は区分4以上(50歳以上は 区分3以上)でないと利用できない。そして施設運営という視点でも、区分ごとの単価設定がされているので、少しでも区分が高い利用者を施設入所させることが求められる制度になっている現状です。
そういった状況下でこれから一人ひとり新しい障害程度区分の判定が行われていくことになり ますが、必要な形できちんとした障害程度認定される工夫をしていきたいと思います。
現在の実態から如何にサービスを必要としているか。ということを概況調査で伝えるかが大事に なってきます。一次判定で106項目の調査からコンピュータ判定で如何に区分を上げられるか。
医師意見書と二次判定の市町村審査会では、最大2段階しか上がらない。とのことでコンピュータ判定で区分1と判定されたら、最高区分3にどうあがいてもしかならない。50歳未満の方は入所 施設を利用することさえも許されない。という形になります。
少しでも一番最初の概況調査で判定にのるよう、事前シュミレーション。本人との面談事前練習を詰めたいと思います。
判定の場には 総務Aと男性B主任。女性ならC副主任が立ち会います。
当日までの流れは以下の通りです。
区分判定が行われる利用者の生活担当職員
以前行ったシュミレーションを基に、この下案作成マニュアルを照らし合わせながら改めて書き換え。
総務・主任or副主任
その書き直されたシュミレーションを総務が改めて確認。
詰めなおし、当日立ち会う主任若しくは副主任と再確認。
その人の現在の状況をより多角的に見ることができるよう、手間はかかりますが、複数の職員が 携わるよう考えました。
今回の判定の有効期間は、「3年間。」
山の子が新法に沿った事業として移行する年度は現段階では未定ですが、3年以内に移行する 可能性がないわけではありません。そういう意味では、実際の判定と同じ位置づけで最大限の準備をして判定に臨みたいと考えています。
P.S. 大きな環境変化ということで、こっちから望めば、再認定は可能なよう。今回の判定がそのままということにはならないようです。
お手数ですがご協力下さい。
よろしくお願いします。
別紙 認定調査票の各項目を以下の視点を踏まえて、改めて確認・検討してみてください。
各項目共通点として、状況に応じてできたり・できなかったり。という事柄に関しては、頻度の
高い状況に基づいて判断することになります。
あくまで以下の記載は、補佐的な情報として。まとめてあるので、一般的に理解できる事柄に
関しては省略してあります。
1−1 麻痺等の有無
対象者が可能な限り努力して動かそうとしても動かない。或いは動きがあっても日常生活に支障があるかどうか。筋力低下・その他様々な原因による筋肉の随意的な運動機能の低下含む。
(立ち上がりや歩行の不安定・ふらつき、伝い歩き、杖歩行等)
自室に篭り意欲が無く動こうとしない。意欲が低下し、筋力がかなり低下している。
等も特記事項に記載。
Ex)左右上肢に麻痺があり、食事はこぼしが多いが、一人でスプーンで食べている。
⇒日常生活に支障あり。
1−2 間接の動く範囲
対象者が可能な限り力を抜いた状態で他動的に間接を動かしたときに、関節の動く範囲が 著しく狭くなっているか。その他は、1−1と同様の視点。
著しく狭い。⇒日常生活に支障があるかどうか。で判断。
2−1 寝返り
布団なしの状態で自分でできる。或いはベッド柵など何かにつかまればできるかどうか。
きちんと横向きにならなくても、横たわったまま左右のどちらかに向きを変えられるか。
2−2 起き上がり
布団無しで寝た状態から上半身を起こす行為。ベッド柵・介護者の手などにつかまれば
できるかどうか。起き上がりの過程・状態は問わない。
3.できない;途中まで自分でできても最後の部分で介助が必要な場合も含む。
Ex)介助なしで何かに掴まればできるが、めまいの為普段は自分で起き上がりをしない場合。
⇒「2.何かにつかまればできる。」とし、特記事項に「めまいのため普段は自分では起き上がりをしないで、介助されている。」と記載する。
2−3 座位保持
寝た状態から座位に至るまでに介助が必要かどうかにかかわりなく、上半身を起こして座位(椅子もしくはベッドに座った状態でベッドサイドに足を下げて座る状態)の状態を10分間 保持できるかどうか。
見守りが必要な場合は、特記事項に記載。(知的障害、精神障害や自閉症などの行動障害で、多動によりじっとしていない。)
Ex)他動などの行動障害で10分間座位保持できない場合。
⇒行動障害を除けば、座位可能であると判断した場合「1.できる。」
2.自分の手で支えればできる;背もたれは必要ないが、自分の手で支える必要あり。
3.支えてもらえばできる;背もたれがないと、介護者の手で支えがないと座位保てない。
2−4 両足での立位保持
立ち上がるまでの介助は関係なく、平らな床の上で10秒立位を保持できるか。
2−5 歩行
立った状態から5m程度歩くこと。見守り等が必要な場合は「特記事項」に記載。
2.何かにつかまればできる;片方の腕を介助者が支える。又は介助者に対象者がつかまれば歩行できる場合も含む。
3.できない;医療上の必要により歩行制限が行われている場合。何かにつかまったり支えられても5m以上歩行できない場合も含む。
Ex)ひざ立ちによる移動が可能な場合。
⇒「1.つかまらないでできる」に該当。なお、「ひざ立ちによる移動であるため、屋外は車椅子での移動」等の状況を「特記事項」に記載。
2−6 移乗
「ベッドから車椅子へ」「車いすからトイレへ」などの乗り移りの際、実際に見守りや介助が行われているかどうかに基づいて判断する。
2.見守り等;介助なしで移乗できるが、精神面の不安定などで常に必要など、見守り等を行っている場合。移乗する際に、対象者が安全に乗り移ることができるよう、一連の移乗動作に合わせて介護者が車いす等をでん部(お尻)の下に挿し入れるような場合も含む。
2−7 移動
日常生活(食事・排泄・着替え・洗面・入浴又は訓練などを含む。)において、必要な 場所への移動にあたり実際に見守りや介助が行われているか。
訓練や買い物、趣味などの日常的な外出も含む。
2.見守り等;介助なしで移動できるが、しばしば転ぶなどで助言や見守りが必要だったり、場面の変化等においての不適応行動や意欲のなさ等に対しての一時的な 声かけや見守りが必要な場合も含む。
3.一部介助;介助者が必要な場所へ移動するために手を添えたり、体を支えたり、敷居 などの段差で車椅子を押す等の介助が行われている場合も含まれる。
常に声かけしなければならない場合や強い促し、助言が必要な場合も含む。
4.全介助;自分では移動が全くできない場合(常に車いすを押す。強い促しによっても 行動できない等の日常生活における全場面で介助を必要とする場合。)。
目的もなく屋内・屋外の徘徊や多動があり、日常生活における全場面で介助を必要とする場合も含む。全く動かない・医療上移動を禁止されているも含む。
3−1 立ち上がり
椅子やベッド。車いす等に座っている状態から立ち上がる行為を行う際にベッド柵や 手すり、壁などにつかまらないで立ち上がることができるか。障害等により動作が緩慢であるなど、見守り等が必要な場合は「特記事項」にその状態を記載。
1.つかまらないでできる;習慣的に手を軽くついて立ち上がる場合も含む。
2.何かにつかまればできる;介護者が引き上げるほどの程度ではなく、支えがあれば 基本的に自分で立ち上がることができる。
3.できない;身体の一部を介護者が支える・手で引き上げるなど、介助がないとできない。
3−2 片足での立位保持
立ち上がりまでの介助は関係なく、平らな床の上で自分で左右いずれかの片足を上げた 状態のまま立位を1秒間程度保持できるかどうか。
3.できない;どのような状況でも全く片足で立つことができない場合。自分では片足を 上げられない場合。介護者に支えられた状態でなければ片足を上げられない。
3−3 洗身
入浴時に自分で身体を洗うか。身体を洗うのに介助が行われているかどうか。浴室内で スポンジやタオル等に石鹸やボディシャンプー等を付けて洗うこと。洗髪・洗顔行為は含まない。浴槽の出入りは含まない。
能力があっても介助が行われている場合は、実際に行われている介助の程度や対象者の 能力を総合的に勘案して判断する。
2.一部介助;介助者が石鹸等を付けて、身体の一部を洗う等の場合。見守り等を行う場合。自分では十分に洗身できないがために、手伝ってもらう場合。部分的に洗い直しをする場合も含む。介護者が常時離れることができず、声かけをしなければ自分でやらない場合で、強い促し・助言があることにより洗身する場合も含む。
3.全介助;「洗身」という行為の目的がわからないため、自分で一連の洗身を行っても、介護者が全て洗い直しをする場合。
4.行っていない;日常的に洗身を行っていない場合(洗身が嫌な場合)。
清拭のみ行っている場合。
4−1 じょくそう(床ずれ)等の有無
じょくそう(床ずれ)の有無。並びにじょくそう以外で処置や手入れが必要な皮膚疾患の有無のみについて評価。じょくそう以外の皮膚疾患等(口腔を含まない)とは、水虫や疥癬、開放創等を含む処置や手入れを必要とする状況。
大きさ、程度及び処置や手入れの有無は問わない。調査日から14日以内に遡っての状況を総合的に勘案して判断。再発性の場合に限り調査日より14日以内に遡って症状がない場合でも、過去1ヶ月の状況について「特記事項」に記載する。(じょくそうは改善されているが、一ヶ月前は仙骨部にじょくそうがあった。←「1.ない」と判断。)
特記すべき事項があれば要点を「特記事項」に記載。(仙骨部に発赤がみられる。右足親指に爪白癬がみられる。)
《じょくそう以外の皮膚疾患に該当する例》
・ 水虫や疥癬。開放創等。
・ 気管切開部、胃ろう、人工肛門、脱肛などで、その周囲に炎症等の手入れが必要な皮膚疾患があることが確認できる。
・ 処置や手入れが必要な 慢性湿疹、アトピー性皮膚炎、乾癬、鶏目、たこ。
《じょくそう以外の皮膚疾患に該当しない例》
・ 目薬の点眼処置。 ・ 外耳炎や中耳炎の耳垂れ。
・ 痔。 ・ 人工肛門の周囲に炎症等がなく、単にパウチ交換だけの場合を言う。
・ 気管切開部、胃ろう、脱肛だが、周囲に炎症等がなく、処置や手入れが必要ない場合。
4−2 えん下
咀しゃく(食べ物を噛む)とは異なり、えん下(飲み込む)という行為ができるかどうかのみに着目して評価する。咀しゃく力、口腔内の状況(歯がない等)について評価する項目ではない。食物を口に運ぶ行為については、「4−3食事摂取」。
固形物か液体かどうか等、食物の形状(普通食、刻み食、ミキサー食、流動食)によって異なる場合は、日頃の状況に基づいて判断し、「特記事項」に内容を記載。
知的障害者や精神障害者等の経過の中で、精神的な状況又は意欲低下等の理由から飲み 込もうとしないなど、実際に介助がなされているかどうかに基づいて判断。
2.見守り;飲み込む際に見守り等が行われている場合であって、「できる」「できない」のいずれにも含まれない場合をいう。(「えん下はできるが、口にいっぱいに 入れて、むせやすく見守りが必要。」「声かけしないと飲み込もうとしないため、見守りが必要。」等、詳細を「特記事項」に記載。)
4−3 食事摂取
通常の食事の介助が行われているかどうか。(自助具等の使用の有無。要する時間や 対象者の能力は問わず。)
時間がかかる。落ち着いて食事に集中しない等の場合、その状態を「特記事項」に記載。精神的な状況又は意欲低下等の理由から食事摂取の介助を受けている場合はその状況
に基づき判断する。(「食事を促しても反応が無く、口に運ぶと口を開け食べる。」等、 その詳細を「特記事項」に記載。)
* 食事の介助;スプーンフィーディングや食卓上で刻みながら口に運ぶ場合。又は
食べこぼしの掃除などを想定。
1.できる;箸やスプーンの他に自助具等を使用すれば自分で食事が摂れている場合。視覚障害者で配膳の際におかずの種類や配列を知らせると自分で摂取できる場合。
2.見守り等;他人の食事を食べないようにする為、見守り等をしている場合。食事を摂るよう促すなど、声かけ・見守り等をしている場合も含まれる。視覚障害者で、器をひっくり返すなどがよくあり、見守り等が行われている場合。
3.一部介助;食事の際に食卓上で、皮をむく。魚の骨を取るなど食べやすくする為に 何らかの介助が行われている場合。
4.全介助;能力があるかどうかにかかわらず、現在自分では全く摂取していない場合。
介助なしに自分で摂取できるが、早食い等で自分で摂取させると健康上の問題があるなどの判断で、全て介助している場合。
Ex)・特定の食品をとるように促す、「おつゆも飲まないとだめですよ。」は?
⇒「2.見守り等」特定の食品を極端に摂取するが、声かけ程度で他の食品を 食べる場合も同様。
・介助者等が台所や厨房でほぐしたり刻んだりした状態にしてある時に、対象者が その状態の食べ物を自分で食べられる場合は?
⇒「1.できる。」食べやすく調理された状態で卓上に上がった場合は、それを 本人が自分で食べられるかどうかの判断になり、特記事項に「おかずは、刻み食にすれば食べられる。」等詳細を記載。
4−4 飲水
通常の飲水(飲水量が適正量かどうかの判断も含む)の介助が行われているかどうかに着目して評価する。
精神的な状況または意欲低下等の理由から対象者が自ら飲水をしない。或いは一度に過剰な飲水をする場合でも実際に介助がなされているかどうか。
1.できる;自分で水道やペットボトル等から水、お茶、ジュース等をコップや茶碗に 入れて適正量を判断し飲める場合。
2.見守り等;茶碗、コップ等に入れられた物を手の届く範囲におけば、自分で飲める場合。
適正量を調整するために介護者等が茶碗、コップ等を手の届く範囲におく必要がある場合。
3.一部介助;茶碗、コップ等を手渡すか、口元まで運ぶ等の介助が行われる場合。自分で摂取することができても、口渇感が乏しい場合や、1回の水分量が多い場合又はコントロールできず、声かけ(注意)や制止があれば止めるなどの場合。
4.全介助;自分では全く飲水をしていない場合。
医療上の必要により飲水を禁止されている場合。
自分で摂取することができても、全く口渇感を訴えない場合や、1回の飲水量が多い場合。コントロールができず、声かけ(注意)や制止をしても止めない場合。
4−5 排尿
自分で排尿に関わる一連の行為(尿意、トイレまでの移動、ズボン・パンツの上げ下げ、
トイレへの排尿、排尿後の後始末など)を行っているか。排尿後の後始末には、ポータブル
トイレや尿器等の掃除。除去したカテーテルの後始末が含まれる。
昼間は介助なく自分で排尿にかかる一連の行為を行っているが、夜間のみオムツを使用していたり、ポータブルトイレを使用している場合には、日頃の対象者がもっとも頻度の高い排尿の状況により判断し、その内容を「特記事項」に記載する。
精神的な状況又は意識の低下等の理由から排尿の介助を受けている場合はその状況に 基づき判断する。この場合は、「意欲の低下により、尿意の反応がなく、訴えることもない。」等、その詳細を「特記事項」に記載。
行動障害で「トイレ以外の特定の場所に固執して排尿する。」等、障害特有の行動により、特別な介助が必要な場合は「4.全介助」とし、その詳細を「特記事項」に記載。
1.できる;尿意はないが、自分で時間を決めるなどして排尿にかかる一連の行為を 行っている場合。
2.見守り等;一連の行為を介助なしで行っているが、集中性に欠けるなど声かけが必要な場合。声かけしないとトイレ以外の場所で排尿する場合。
3.一部介助;一連の行為のうち以下の1項目のみ該当する場合。
・トイレまでの移動。或いはポータブルトイレへの移乗に介助が必要。
・排尿動作に介助が必要。 ・排尿後の後始末に介助が必要。
4.全介助;一連の行為のうち上記から2項目以上該当する場合。
又、以下の場合いずれか1項目以上に該当する場合も含まれる。
但し、自分で準備・後始末等を行っている場合を除く。
・集尿器を使用している場合。 ・オムツを使用している場合。
・介護者により間欠導尿が行われている場合。
・尿カテーテルを留置している場合。
4−6 排便
全般的に排尿 と同様。
5−1 清潔
日頃からその行為を行っているかどうか。生活習慣、施設の方針、介護者の都合等によって、通常行っていない場合等は、例外的に対象者の能力を総合的に勘案して判断し、判断の理由を「特記事項」に記載。対象者が自身の清潔保持に関心が乏しいため必要な場合も含まれる。
ア.口腔清潔(はみがき等);一連の行為(歯ブラシやうがい用の水を用意する。歯磨き粉を ブラシにつける等の準備、義歯をはずす、うがいをする等)を自分で行っているかどうか。口腔洗浄剤・義歯の場合も清潔保持と うがいができているかどうかで判断。「特記事項」に記載。
イ.洗顔;一連の行為(タオルの準備、蛇口をひねる、衣服の濡れの確認、タオルで拭く等)を 自分で行っているかどうか。
ウ.洗髪;一連の行為(くしやブラシの準備等も含む)を自分で行っているかどうか。頭髪がない。又は短く刈っている場合は、頭を拭いたり整髪に関する類似の行為について判断し、判断した内容を「特記事項」に記載。
エ.爪切り;一連の行為(つめ切りの準備。切った爪を捨てる等)を自分で行っているかどうか。
日頃やすり等の他の器具を用いている場合は、日頃の状況に基づいて能力を判断し、判断した内容を「特記事項」に記載。
精神的な状況。又は意欲低下などの理由から清潔に対する関心や意識がない等により介助を受けている状況により判断する。「意欲の低下により、清潔に対する意識がなく、訴えることもない。」なども含み、この場合その詳細を「特記事項」に記載。
2.一部介助;一連の行為に対して部分的に介助が行われていたり、一連の行為に強い促しをしている場合。常時の見守りや確認、強い促しが必要だったり、行われている場合。
口腔;はみがき中の見守り等、磨き残しの確認が必要な場合。
義歯の出し入れはできるが、義歯を磨く動作は介護者が行っている場合。
洗顔;洗顔中の見守り等、衣服が濡れていないかの確認などが必要な場合。
蒸しタオル等で顔を拭くことはできるが、手で顔を洗うことができない場合。
つめ切り;見守りや確認が必要な場合。
左右どちらか片方。手はできるが、足はできない等の場合。
3.全介助;強い助言や指導をしても行わない場合。介助が行われていないが、明らかに 能力がない場合。口腔清潔、洗顔で、本人が行った箇所を含めて全てを介助者がやり直す場合。口をゆすいで吐き出す行為だけ。顔を濡らすだけの場合。 総義歯で義歯洗浄は全介助の場合。
5−2 衣服着脱
普段着用している衣服について、衣服(上衣、ズボン・パンツ)の着脱を自分で行っているかどうか。衣服の種類(ボタンの有無、ゴム付きフリーサイズズボン等)等は、時候に合った服装の準備、必要な枚数だけ衣服を出すこと。着脱を促す為の声かけ等着脱までの行為は含まれない。
障害の状況により介助されている場合は、その介助されている障害の状況に応じて判断し、
その判断の理由を「特記事項」に記載する。
日常的に頻回に着用している衣服の状況に基づいて判断する。(ボタンのないトレーナー等)
時間がかかる場合は「特記事項」に記載。
精神的な状況。又は意欲低下などの理由から着脱の介助を受けている状況により判断する。「意欲の低下により、着脱を促しても反応がなく、着替えようともしない。」なども、その 詳細を「特記事項」に記載。
2.見守り等;介助なしに自分で上衣、ズボン・パンツの着脱をしているが、前後を時々 間違えるために、見守りし声かけが必要など、見守りが行われている場合。
3.一部介助;着脱に何らかの介助が行われている場合。
手が回せないがために介護者が常に上衣を持っていなければならなかったり、麻痺側のみ着せる場合。
ズボン・パンツに関しては、自分で行っていても最後に介護者がシャツをズボン・
パンツ等に入れなおす場合等も含む。
5−3 薬の内服
一連の行為(薬を飲む時間や量を理解する。薬や水を手元に用意する。薬を口に入れる、 飲み込む。)について、現在の状況で介助を受けているか否か。
インスリン注射、塗り薬の塗布等、内服薬以外のものは含まれない。
投薬を受けていても、飲むことを忘れる。飲むことを避ける場合には、その対応に基づいて判断し、その対応について「特記事項」に記載する。
投薬を受けていない場合は、対象者の能力を総合的に勘案して判断し、その判断について 「特記事項」に記載する。
施設入所者で一括して管理されているため、自己管理の機会がない場合は、本人が自己管理した場合を総合的に勘案して判断し、その判断について「特記事項」に記載する。
服薬の必要性を認識しない、或いは副作用を過度に心配するといった状況のため服薬の介助が必要な場合も含む。
1.できる;薬を飲む時間や量を理解し、介助なしで自分で内服薬を服用している場合。
2.一部介助;薬を飲む際の見守り、飲む量の指示や確認等が行われている。或いは、飲む薬や水を手元に用意する。オブラートに包むなど、何らかの介助が行われている。重度の障害者で薬や飲む量は理解しており、介護者に指示して薬を 用意してもらい、飲ませてもらっている場合。薬の管理はできないが、手渡しされた後、水と共に服薬する行為を自分で行っている場合。薬の量や時間は理解しているが、介護者が指示しないと失念しがちな場合。
3.全介助; 飲む時間を忘れたり、飲む量もわからない。或いは重度の障害や手指の麻痺・
障害により自分では飲めないために、薬の内服に関わる行為全てに介助が行わ
れている場合。
薬を飲む時間や量を理解しておらず、介護者が薬を口の中に入れることに より対象者は飲み込むのみの場合。
薬を飲む時間や量は理解しているが、服薬に抵抗があり、服薬するように 介護者が長時間(社会通念上の判断)の働きかけをする場合も含まれる。
些細幸い
5−4 金銭の管理
自分の所持金(預金通帳や小銭)の支出入の把握、管理、出し入れする金額の計算を自分で行っているかどうか。及びそれが適切であるか否かに着目して評価するものであり、現在の 状況で介助を受けているかどうか。
実際に自分で金銭の出し入れに関する行為を行っているかどうかは問わない。
基本的に施設や家族等が管理を行っている場合は、対象者の身の回りの物品の管理状況、 計算能力に基づいて総合的に判断。その判断について「特記事項」に記載。
金銭管理の状況が判断できない場合は、家族や介護者等から聞き取った内容を踏まえて判断する。「収入と支出の理解、概念がなく、借金してでも使うため、金銭管理はできない。」等、その詳細を「特記事項」に記載。
1.できる;自分の所持金の支出入の把握や管理を自分で行っている。出し入れする金額の計算を介助者なしで自分で行っている場合。
2.一部介助;小遣い使用の助言・指導等金銭管理に何らかの介助が行われている。
或いは小遣い銭として、小額のみ自己管理している場合。
3.全介助;金銭の管理について全てに介助が行われている場合。
一日の必要額を家族が準備し、その必要額の管理も自分で行えない場合。
5−5 電話の利用
一連の行為(かけたり、受けたりの操作。電話の内容を理解して話す。必要な伝言をする等)を自分で行っているか。
電話を利用する機会がない場合、対象者の日頃の能力を総合的に勘案して判断。その判断について「特記事項」に記載。
2.一部介助;見守り等が行われている場合。視覚障害者・知的障害者などで、誰かが
ダイヤルすれば、相手と話せる場合。
3.全介助;一連の行為全てに介助が行われている場合。又は「電話」というものの 理解がない場合。
Ex)いたずら電話をする為、使わないよう管理されている場合。
⇒一連の行為全てに介助が必要である為、使わぬよう管理されている。「3.全介助」
Ex)精神障害者で、電話利用に係る一連の行為はできるが、相手の都合も考えず脅迫症状に基づき電話を頻回にかけたり、必要のない所へかける等の行動をとる為、家族が注意 したり、指導の必要な場合。
⇒「2.一部介助」なお、その状況を「特記事項」に記載。
Ex)決まった相手2.3箇所のみ、一連の行為を一人で行うことができる場合。
⇒「1.できる。」特記事項に「○○と△△以外の電話の利用には、ダイヤルして あげれば可能。」と記載。
5−6 日常の意思決定
毎日の暮らしにおける課題や活動を実際にどの程度判断しているかという、日常の意思決定(服を選ぶ、起床や食事すべき時間がわかる。自分にできることとできないことがわかる。
必要時に援助を求める。など)を行う為の認知判断能力を評価。対象者自ら決めているのか。決断ができず混乱していないか。対象者にはできるはずだという思い込みはないか。
普段とは異なる旅行やレストランといった状況でも食事メニューを注文したり、周囲の人に必要な援助を依頼する等、適切な意思決定ができるかどうか。と判断。
日によって妥当な判断ができる時とできない時がある場合には、原則として頻回な状況を
聞き取った内容を踏まえて判断する。
対象者に能力があるにも関わらず、精神的な状況。又は意欲低下等の理由から意思決定を していない場合や意思決定を介護者が行っている場合等は、その能力について聞き取った内容を総合的に踏まえて判断する。
1.できる;判断が首尾一貫して理にかなっており、妥当な場合。自分で判断できない・迷う場面では、自分から他者に助言・援助を求めることができる。
2.特別な場合を除いてできる;日常では妥当な判断をするが、新しい課題や状況では
指示や合図を必要とする。
3.日常的に困難;日常生活でも決断できず混乱したり、妥当でない意思決定判断をする。
Ex)トイレはできるが、他の項目はできない。
⇒日常生活全体の中で判断。できたり・できなかったりする場合は、頻度の高い方。
Ex)「妥当でない意思決定判断」とは。
⇒室内のスリッパのまま外に出る。など…
6−1 視力
見えるかどうかについてのみ着目。
見えているものの名称を正しく表現できるかや理解力は問わない。
見えるかどうかの判断には会話だけでなく、身振り等にも基づいて判断。
1.普通(日常生活に支障がない);新聞・雑誌等の字が見える。字が見えているか判断
がつかないが、日常生活に支障がない程度の視力を
有している。
4.ほとんど見えない;目の前に置いた視力確認表の図が見えない。
5.見えているのか判断不可能;意思疎通ができず、見えているのか日常生活に支障が あるのか判断できない場合。
6−2 聴力
聞こえるかどうかのみに着目して評価。聞いた内容を理解しているかどうかの知的能力は
問わない。
普通に話しても聞こえない対象者には、耳元で大声で話す。
知的障害者等で音に対する反応に障害があっても、声や音が聞こえているかどうか、日頃の
対象者の反応に詳しい介護者の助言から判断。どういう反応であったか「特記事項」に記載。
2.普通の声がやっと聞き取れる;普通の声で話すと聞き取りにくく、聞き間違えたり する場合。
5.聞こえているのか判断不可能;意思疎通ができず、聞こえてるのか判断できない場合。
6−3−ア 意思の伝達
対象者が意思を伝達できるか(受け手に自分の意思を表示し伝わること。)どうかのみに 着目して評価するもの。意思伝達の手段(手話・筆談・身振り・メール・トーキングエイド等)や相手。背景疾患は問わない。
意思の伝達に変動がある場合は、もっとも頻回に表出される状況を介護者等から聞き取り 総合的に判断。その内容を「特記事項」に記載。
1.対象者が意思を他者に伝達できる;手段を問わず、常時誰にでも伝達ができる場合。
2.ときどき伝達できる;通常は対象者が家族等の介護者に対して意思の伝達ができる。 しかしその内容や状況によっては出来る時とできないときが ある場合。この場合の頻度は「特記事項」に記載。
3.ほとんど伝達できない;通常家族等の介護者に対しても意思の伝達ができないが、ある
事柄や特定の人に対してなら、まれに意思の伝達ができる場合。
4.できない;意思の伝達ができない。或いはできているかどうか、わからない場合。
6−3−イ 本人独自の表現方法を用いた意思表示
重度のコミュニケーション障害を有している場合の意思表示の仕方。日常生活や外出時において独自の表現(独特のジェスチャーや仕草)を使用し意思表示する場合を問う。
2.時々、独自の方法でないと意思表示できないことがある;
時々頭をぶつけたり、腕を掴んだり等通常とは違う行動でしか自らの意思を表現
できないことがある場合。「3」の常時必要な場合以外は、この項目。
3.常に、独自の方法でないと意思表示できない。;上記の通常とは違う行動でしか 自らの意思を表現できない場合。
4.意思表示ができない;独自の方法を用いても、意思表示できない場合。
6−4−ア 介護者の指示への反応
必要である指示に対してその意味を理解して何らかの反応ができるかどうか。
指示を守るかどうか。背景疾患を問うものではない。
反応の伝達手段は問わず、介護者の指示を理解して何らかの言葉や態度。行動の変化を起こすかどうか。介護者の指示も手話・身振り・絵・写真…伝われば何でもよい。
1.指示が通じる;「嫌だ」と答える場合も。
聞こえない振りをしても、反応していることが明らかな場合。
2.指示が時々通じる;そのときによって、反応したりしなかったりする場合。
頻度は「特記事項」に記載。
3.指示が通じない;指示に反応しない。通じてるかどうかの判断ができない場合。
6−4−イ 言葉以外のコミュニケーション手段を用いた説明の理解
重度のコミュニケーション障害を有している場合の説明に対しての理解。日常生活や
外出時において言葉以外の表現(ジェスチャーや絵カード等)を使用し説明する場合を問う。
1.日常生活においては、言葉以外の方法(ジェスチャー、絵カード等)を用いなく
ても説明を理解できる。;習慣化されていない日常生活や外出時においてだけ、
言葉以外の方法を用いる必要がある場合も含む。
4.言葉以外の方法を用いても、説明を理解できない。;
説明に対して応答はしているが、理解できているかどうか判断できない場合。
6−5 記憶・理解
記憶や理解度を問うもの。
ア.毎日の日課を理解する;施設プログラム等についておおよそのスケジュールを理解してるか。
イ.生年月日や年齢を答える;いずれか一方を答えることができればよい。
エ.自分の名前を答える;旧姓等を問わず、姓か名前のどちらかを答えられればよい。
愛称で答えても日常生活上問題が生じていないのであれば可。
オ.今の季節を理解する;多少のズレがあってもよい。
カ.自分がいる場所を答える;施設の場合の居室・視説明・施設の所在地のいずれでもよい。
1.できる;いつでもほぼ正確な解答ができる場合。
数日のずれ。姓を聞いて名前を思い出す。等も含む。
時間がかかっても答えることができる場合も含まれる。
言葉が不明瞭で筆記もできないが、対象者の反応から理解していると判断 した場合も含む。
2.できない;できたりできなかったりする場合や回答の正誤が確認できない場合。
調査員が質問したときには回答できても、家族からの聞き取りによると 忘れていることが多い場合も含む。
7 行動
日常生活において行動上の障害があるかどうか、またある場合にはその頻度を評価する。
日常生活への支障については、周囲の人に与える影響について総合的に勘案して判断。
調査時の状況のみから判断せず、過去1年間程度の期間の生活状況の変動も踏まえて判断する。
(ア〜ト)(へ〜ヤ)
1.ない;その行動上の障害が(過去1回以上あったとしても)過去1ヶ月間に1度も 現れたことがない場合やほとんど月1回以上の頻度では現れない場合。
2.ときどきある;少なくとも1ヶ月に1回以上の頻度。2つ以上の状況を例示している 選択肢について、いずれかが、「ときどきある」場合も含まれる。その頻度は「特記事項」へ記載。
3.ある;少なくとも1週間に1回以上の頻度。2つ以上の状況を例示している選択肢に ついて、いずれか1つでも「ある」場合。
ア.物を盗られたなどと被害的になること;実際に盗られていないものを盗られたという等。
現実の誇張は含まれない。
イ.作話をし周囲に言いふらすこと;作話をしても、特定の人にのみ話をする場合は該当しない。
自分に都合のいいように事実と異なる話をすることも含む。
エ.泣いたり笑ったり感情が不安定になること;些細なきっかけで悲しんで涙ぐんだり、不安や 恐怖から感情的にうめく等、明らかに感情が 不安定になる。
オ.夜間不眠あるいは昼夜の逆転;夜間不眠の訴えが何日間か続いたり、明らかに昼夜が逆転するなどし、そのために日常生活に支障が生じている場合。不眠の原因は問わない。睡眠薬等の投与により睡眠がうまくコントロールされていれば「1.ない」。
カ.暴言や暴行;対象は人間。「ネ」と同一の行為を基で判断するのは可。
ク.大声を出すこと;日常生活で声が大きい場合等は含まない。
ケ.助言や介護に抵抗すること;対象者と介護者の人間関係的要素も含まれるが、明らかに介護者の助言や介護に抵抗し、介護に支障がある場合。単に助言しても従わない場合は含まれない。
コ.目的もなく動き回る;歩き回る。車椅子で動き回る。床やベッドの上で這い回るなど、その
目的が周囲の者に理解しがたい行動をとり続ける場合。「ナ」の多動と
同じ行為を基に考えることは可能。
Ex)自閉症の人が電気を消して回ったり、窓を閉めて回ったりする場合。
⇒理由が周囲には理解しがたい場合。
サ.「家に帰る」等と言い落ち着きがないこと;施設等で「家に帰る」と言ったり、外に出ようとしたり、自宅にいても「家に帰る」等と言って落ち着きがなくなる場合。単にそう言っているだけで落ち着いている場合は含まれない。
Ex)「家に帰る」等の訴えはないが、隙があれば無断外出をしようとする場合。
⇒該当する。
シ.外出すると施設などに一人で戻れなくなる;施設などで居室等から出て、自室に自力で戻れ なくなる場合も含む。
ス.一人で外に出たがり目が離せない;周囲の制止に従わず、外に出たがる為に目が離せない。 環境上の工夫等で外に出ない。歩けない等の場合は含ず。
セ.色んなものを集めたり、無断で持ってくること;収集癖。周囲の迷惑とならない。紐や包装紙等を集める等の趣味は含まれない。「ノ」と同一の行為を基に判断することは可能。
収集癖;特定のものだけ集め、「癖」の域に達している場合。極めて小さなゴミだけを集め、
ティッシュ等の大きなゴミは興味ない。時計だけをどこからともなく持ってくる等。
ソ.火の始末や火元の管理;環境上の工夫等で火元に近づくことがなかったり、周囲の人々に よって火元が完全に管理されている場合は含まれない。
タ.物や衣類を壊したり、破いたりすること;日常生活に支障が生じる場合。捨てる等で支障が 出る場合も含まれる。その行動の原因は問わない。
チ.不潔な行為を行う(排泄物を弄ぶ);弄便(尿)など排泄物を弄ぶ。尿を撒き散らす場合。 体が清潔でないことは含まない。
ツ.食べられないものを口に入れること;異食行動。異食しそうなもの等を周囲に置かない場合は含まれない。完全に飲み込まなくても口の中に入れれば異食行動。「3B.ほぼ毎日ある」を選んだ場合は、 その頻度を「特記事項」に記載。
テ.ひどい物忘れ;日常生活に支障が生じる場合。
ト.特定の物や人に対する強いこだわり;日常生活に支障が生じる場合。支障がなければこだわりが強くても「ない」に該当。
(ナ〜フ)
1.ない;過去1年間に1度もない場合や、数ヶ月に1回以上の頻度では現れない場合。
2.希にある;少なくとも数ヶ月に1回以上の頻度。2つ以上の状況を例示している選択肢について、いずれか一つでも「ある」場合。
5.ほぼ毎日;週5回以上、かつ1日1回以上現れる場合。
ナ.多動または行動の停止;行動障害で特定の物や人に対する興味関心が強く、思い通りに ならないと多動になったり、こだわりが強くなり動かなくなって しまう場合。「コ」の目的もなく動き回ること。と同一の行為を基にした判断は可能。
Ex)自閉的傾向が強く計画以外の行動ができない場合。突然の予定変更により行動が停止
したり落ち着かなくなる場合や、食事の時間になっても予定の作業が終わっていない為、
作業を続け次の行動食事への切り替えができない場合。 ⇒ 該当。
ニ.パニックや不安定な行動;予定等の変更が受け入れられず大声を出して泣き叫ぶ等のパニックや行動が不安定になる場合。精神障害で不安・恐怖・焦燥等に かられて衝動的な行動がある場合も含む。
ヌ.自分の体を叩いたり傷つけたりする;自ら傷跡が残るほど自分の体に傷をつけたりする行為。
精神障害で、手首を切る・頭髪を抜く等の行為も含む。
習慣性のもの、パニック等の不安定な行動時の突発的なものも両方含む。その頻度や状況を「特記事項」に記載。
ネ.叩いたり蹴ったり器物を壊したりする等の行為;他人を叩く・髪の毛を引っ張る・蹴る等の 行為や壁を壊したりガラスを割ったりする等の行為がある場合。対象は人間を含め他の物まで含む。「カ」と同一の行為を基でも可。
ノ.他人に突然抱きついたり、断りもなく物を持ってくる行為;興味や関心が優先したり、適切な
意思表示ができない等により他人に突然抱きついたり、断りもなく物を持ってきてしまう行為がある場合。
善悪という適切な判断能力がないための行為。「セ」と同一の行為を基に判断することも可能。
(ハ・ヒ)
4.日に1回以上;概ね一日に1回から2・3回程度。
5.日に頻回;一日に何度もあり、何回とは言えないほど頻回にある場合。
ハ.環境の変化により、突発的に通常と違う声を出すこと;本人の欲求が受け入れられなかったり、
制止されたりした時や、非常に興味関心の
強いものや人を見たときに起こる場合。
Ex)常時通常と違う声を発していて、環境の変化によるかどうか判断できない場合。
⇒「5.日に頻回」
ヒ.突然走っていなくなるような突発的行動;興味や関心が強い物や人を見つけたら、断りもなくそちらへ走っていってしまう等の場合。興味の対象が不明の場合も含む。突然人を突き飛ばす。許可なく他人宅に入り、冷蔵庫を開けるなど。
フ.過食・反すう等の食事に関する行動;食に関する行動障害或いは複数の行動が認められる場合。
食事に支障を来たすもの。
Ex)過飲・拒食・食器に手を入れたままかき混ぜる。食器に吐き出し、それを再び食べ始める。
へ.気分が憂鬱で悲観的になったり、時には思考力が低下すること;抑うつ気分によりひどく
悲観的で合ったり考えがまとまらない為日常生活に支障をきた
す場合。時に死にたいといった素振りを示し、危険を防止する
ために誰かがそばについている等の配慮が必要とされる場合。
ホ.再三の手洗いや繰り返しの確認の為、日常動作に時間がかかること;ある考えに固執したり、特定の行為を反復したり、或いは儀式的な行為にとらわれることで日常生活に支障をきたす。必要以上に手を洗う。施錠を確認する等。
マ.他者と交流することの不安や緊張の為外出できないこと;長期(一ヶ月以上)にわたって 引きこもりも含む。
Ex)1月に4日以上引きこもりの日がある場合。
⇒「3.ある」その状況を特記事項に記載。
(外出を全くしようとしない。通院以外は外出しない等。)
ミ.一日中横になっていたり、自室に閉じこもって何もしないでいること;行動を計画したり実行したりする意欲が乏しいため、周りから言われないと何にもしないでいる場合。
Ex)重度の知的障害で意欲や理解力が低いため、そのような状態が見られる。
⇒ 該当する。
ム.話がまとまらず、会話にならないこと;話のないように一貫性がない。話題を次々に変える。質問に対して全く意図しない反応が返ってくる等により会話が成立しない場合。興奮したときに一時的に話がまとまらない場合は除く。
モ.現実には合わず高く自己を評価すること;現実にはそぐわない特別な地位や能力が自分胃あると信じてそれを主張する場合。
Ex)実行するのは難しいが「仕事はできる。」「調理はできる。」と意思表示する場合
;誇大妄想を想定しており、単に『○○できる。』では該当しない。
ヤ.他者に対して疑い深く拒否的である;他者を信頼しない態度で、相手の善意を疑い、話し合いや本人の為になされた提案を受け入れない場合。
Ex)理解力が低いため相手の考えや意見を理解できず本人のためになされた提案を受け入れ
ない場合。 ⇒ 「他者に対して疑い深く拒否的」であることが判断基準。該当せず。
9−1 調理(献立を含む)
一連の行為(簡単な食事について、献立をたて、調理し後片付け(調理器具を洗う・
しまう。ゴミの後始末)まで)についてを評価。
配膳・下膳、買い物は含まれない。普段行っていない場合は、日頃の生活状況・他の家事
の状況等の聞き入れを勘案し、総合的に判断。その判断した状況を「特記事項」に記載。
1.できる;一人で出来る場合。普段の家事全般についてできており、果物を剥いたり、
お茶やコーヒーなどを出したりする能力等を勘案した場合、調理が一通り
可能と判断できる場合。
2.見守り、一部介助;見守りや食材を切る、煮る、炒める等の直接的な援助が部分的に必要な場合。普段の家事全般について比較的できており、果物を剥いたり、お湯を沸かす、お茶やコーヒーなどを出したりする能力などを勘案した場合、直接的な援助が部分的に行えば可能と判断できる場合。
3.全介助;1人で一連の行為ができず、一連の行為を通じて直接的援助が必要な場合。
Ex)後片付けのみができる場合;1人では一連の行為ができず、殆どが直接的援助が必要な為「3.全介助」
9−2 食事の配膳・下膳(運ぶこと)
一連の行為(盛り付け、配膳・下膳(1人で出来るかどうか)、食器洗い、食器の
後片付け)ができるかどうか。
普段行ってない場合は、日頃の生活状況の聞き取りや本人の他の家事の状況等を勘案し
総合的に判断する。この場合判断した状況を「特記事項」に記載。
1.できる;一人でできる場合。普段の家事全般についてできており、お客に対するお茶
菓子や果物の盛り付け、御茶屋コーヒーを出したりする能力を勘案した場合、
配膳・下膳が一通り可能だと判断できる場合。
2.見守り・一部介助;常に見守りや直接的な援助が部分的に必要な場合。普段の家事
全般について比較的できており、お客に対するお茶菓子や果物の
盛り付け、お茶やコーヒー等を出したりする能力等を勘案した
場合、声かけや直接的な援助が部分的に行えば配膳・下膳が 一通り可能と判断できる場合。
9−3 掃除(整理整頓を含む)
一連の行為(掃除機の準備・操作・掃除する部屋の整理、掃除機の後片付け)について評価。
掃除機や箒を使って普段自分の使用している部屋等を掃除すること。自分の持ち物の整理
整頓ができるか。普段行っていない場合は、日頃の生活状況の聞き取りや本人のほかの家事の状況等を勘案し総合的に判断。この場合、判断した状況を「特記事項」に記載する。
1.できる;一人でできる場合。普段の家事全般についてできて、居住環境も整理整頓
されている等の能力等を勘案した場合、掃除が一通り可能のと判断できる場合。
2.見守り・一部介助;常に見守りや整理整頓で直接的な援助が部分的に必要な場合。
普段の家事全般について比較的できており、居住環境も不充分 ではあるが比較的整理整頓されている等、直接的な援助が部分的に行われれば、掃除が一通り可能と判断できる場合。
3.全介助;一人では一連の行為ができず、一連の行為を通じて直接的援助が必要な場合。
Ex)掃除機の準備や後片付けのみができる場合。
⇒一人では一連の行為ができず、ほとんどが直接的援助が必要なため「3.全介助」
9−4 洗濯
通常の日常生活で行っている洗濯の一連の行為(洗濯物を洗濯機に入れる。操作を行う。
洗剤を準備する。洗濯物を乾かす・取り込む・たたむ・片付けるまで。)についての評価。
普段行っていない場合は、日頃の生活状況の聞き取りや本人のほかの家事の状況等を勘案
し総合的に判断。この場合、判断した状況を「特記事項」に記載する。
1.できる;一人でできる場合。対象者の普段着ている衣類等から判断した場合、清潔
な衣類を着ており、衣類等がよく整理されている等、洗濯が一通り可能と
判断できる場合。
2.見守り・一部介助;常に見守りや洗濯機の操作等で直接的な援助が部分的に必要な場合。対象者の普段着ている衣類等から判断した場合、比較的清潔な衣類を着ており、衣類等が不十分なところもあるが比較的整理 されているなど、直接的な援助が部分的に行われれば選択が一通り可能と判断できる場合。
Ex)洗濯物をたたんだり、片付けたりすることのみができる場合。
⇒洗濯物をたたんだり、片付けることができる方なら、洗濯物を洗濯機に
入れる。洗剤を準備する。洗濯物を乾かす・取り込む…と一連の行為も
通常はできるのではないかと考え、調査にあたり能力勘案する必要あり。
9−5 入浴の準備と後片付け
一連の行為(浴槽に水を張る。お湯を沸かす。入浴用品の準備・後片付け。着替えを準備。
風呂場の後片付けまで)について評価で、浴槽に入ることや洗身は含まれない。普段行って
いない場合は、日頃の生活状況の家族等からの聞き取りや本人のほかの家事の状況等を
勘案し総合的に判断する。この場合判断した状況を「特記事項」に記載する。
1.できる;一人でできる。普段の家事全般についてできており、居住環境も整理整頓
されている等も勘案した場合、入浴の準備が一通り可能と判断できる場合。
2.見守り・一部介助;常に見守りや水張り・お湯沸し等で直接的な援助が部分的に必要な場合。普段の家事全般について比較的できており、居住環境も不十分ではあるが比較的整理整頓されている等、直接的な援助が部分的に行われれば、入浴の準備が一通り可能と判断できる場合。
9−6 買い物
コンビニやデパートで、適切に必要な商品を選び、代金を支払うこと。店までの移動は
含まれない。普段行っていない場合は、日頃の生活状況を家族等から聞き入れした状況等を
勘案し総合的に判断する。この場合、判断した状況を「特記事項」に記載する。
1.できる;一人でできる場合。普段のお小遣いに管理等の能力等を勘案した場合、
買い物が一通り可能と判断できる場合。
2.見守り・一部介助;常に見守りや商品の選定、金銭の計算等で直接的な援助が 部分的に必要な場合。
9−7 交通手段の利用
一連の行為(目的地(学校や施設など普段通いなれた場所・目的地)へ行く交通機関を
選ぶ。バスや駅まで移動する。切符を購入する。乗車する。目的地で降車する。目的地まで
行く。まで)を一人で適切にできるかどうか。
地域の交通手段が目的地まで適切に利用できるか。
普段利用していない場合は、日頃の生活状況を家族等から聞き取った状況等を勘案し、
総合的に判断する。この場合判断した状況を「特記事項」に記載する。
1.できる;一人でできる場合。普段の外出や社会生活などの能力等を勘案したら、
交通手段の利用が一通り可能と判断できる場合。
2.見守り、一部介助;常に見守りや切符の購入、移乗等で直接的な援助が部分的に 必要な場合。普段の外出等から勘案すると、部分的な声かけや介助があれば交通手段の利用が一通り可能と判断できる場合。
Ex)何度か練習すれば決まった目的地への移動が可能になる場合。
⇒ 「1.できる」
9−8 文字の視覚的認識使用
文字が見えるかどうかに着目して、その状況により文字が使用できるかを評価する。
文字の理解等の知的能力は問わない。点字の活用は含まない。補助具等で文字の大きさの 変更等を行った場合は、「特記事項」に記載。
1.できる;文字が読めない場合であっても、文字が見える場合も含まれる。
2.一部介助;文字のサイズ変更、白黒反転等、他者が文字を修正すれば文字を活用できる場合。自由な書式や文字の大きさなら、視覚的に文字を活用できるが、一定の書式や文字の大きさを規定されると、活用が困難になる場合。 (金融機関の書類、申込書等の書式には文字が小さすぎて書き込めない。)
3.全介助;文字を音声化するなど、視覚以外の方法でしか活用できない場合。
Ex)視覚障害はないが知的障害により文字が読めない場合。
⇒視覚障害に着目した項目であるので、見えるが文字を読めない場合でも 「1.できる」
下案を作成するにあたっての視点
新しい基準に沿っての区分判定となります。この法律に基づいて認定された区分で、現在の法状況下では利用できるサービスが限定されることになります。
○○は知的障害者援護施設(入所更生)として施設入所支援は区分4以上(50歳以上は 区分3以上)でないと利用できない。そして施設運営という視点でも、区分ごとの単価設定がされているので、少しでも区分が高い利用者を施設入所させることが求められる制度になっている現状です。
そういった状況下でこれから一人ひとり新しい障害程度区分の判定が行われていくことになり ますが、必要な形できちんとした障害程度認定される工夫をしていきたいと思います。
現在の実態から如何にサービスを必要としているか。ということを概況調査で伝えるかが大事に なってきます。一次判定で106項目の調査からコンピュータ判定で如何に区分を上げられるか。
医師意見書と二次判定の市町村審査会では、最大2段階しか上がらない。とのことでコンピュータ判定で区分1と判定されたら、最高区分3にどうあがいてもしかならない。50歳未満の方は入所 施設を利用することさえも許されない。という形になります。
少しでも一番最初の概況調査で判定にのるよう、事前シュミレーション。本人との面談事前練習を詰めたいと思います。
判定の場には 総務Aと男性B主任。女性ならC副主任が立ち会います。
当日までの流れは以下の通りです。
区分判定が行われる利用者の生活担当職員
以前行ったシュミレーションを基に、この下案作成マニュアルを照らし合わせながら改めて書き換え。
総務・主任or副主任
その書き直されたシュミレーションを総務が改めて確認。
詰めなおし、当日立ち会う主任若しくは副主任と再確認。
その人の現在の状況をより多角的に見ることができるよう、手間はかかりますが、複数の職員が 携わるよう考えました。
今回の判定の有効期間は、「3年間。」
山の子が新法に沿った事業として移行する年度は現段階では未定ですが、3年以内に移行する 可能性がないわけではありません。そういう意味では、実際の判定と同じ位置づけで最大限の準備をして判定に臨みたいと考えています。
P.S. 大きな環境変化ということで、こっちから望めば、再認定は可能なよう。今回の判定がそのままということにはならないようです。
お手数ですがご協力下さい。
よろしくお願いします。
別紙 認定調査票の各項目を以下の視点を踏まえて、改めて確認・検討してみてください。
各項目共通点として、状況に応じてできたり・できなかったり。という事柄に関しては、頻度の
高い状況に基づいて判断することになります。
あくまで以下の記載は、補佐的な情報として。まとめてあるので、一般的に理解できる事柄に
関しては省略してあります。
1−1 麻痺等の有無
対象者が可能な限り努力して動かそうとしても動かない。或いは動きがあっても日常生活に支障があるかどうか。筋力低下・その他様々な原因による筋肉の随意的な運動機能の低下含む。
(立ち上がりや歩行の不安定・ふらつき、伝い歩き、杖歩行等)
自室に篭り意欲が無く動こうとしない。意欲が低下し、筋力がかなり低下している。
等も特記事項に記載。
Ex)左右上肢に麻痺があり、食事はこぼしが多いが、一人でスプーンで食べている。
⇒日常生活に支障あり。
1−2 間接の動く範囲
対象者が可能な限り力を抜いた状態で他動的に間接を動かしたときに、関節の動く範囲が 著しく狭くなっているか。その他は、1−1と同様の視点。
著しく狭い。⇒日常生活に支障があるかどうか。で判断。
2−1 寝返り
布団なしの状態で自分でできる。或いはベッド柵など何かにつかまればできるかどうか。
きちんと横向きにならなくても、横たわったまま左右のどちらかに向きを変えられるか。
2−2 起き上がり
布団無しで寝た状態から上半身を起こす行為。ベッド柵・介護者の手などにつかまれば
できるかどうか。起き上がりの過程・状態は問わない。
3.できない;途中まで自分でできても最後の部分で介助が必要な場合も含む。
Ex)介助なしで何かに掴まればできるが、めまいの為普段は自分で起き上がりをしない場合。
⇒「2.何かにつかまればできる。」とし、特記事項に「めまいのため普段は自分では起き上がりをしないで、介助されている。」と記載する。
2−3 座位保持
寝た状態から座位に至るまでに介助が必要かどうかにかかわりなく、上半身を起こして座位(椅子もしくはベッドに座った状態でベッドサイドに足を下げて座る状態)の状態を10分間 保持できるかどうか。
見守りが必要な場合は、特記事項に記載。(知的障害、精神障害や自閉症などの行動障害で、多動によりじっとしていない。)
Ex)他動などの行動障害で10分間座位保持できない場合。
⇒行動障害を除けば、座位可能であると判断した場合「1.できる。」
2.自分の手で支えればできる;背もたれは必要ないが、自分の手で支える必要あり。
3.支えてもらえばできる;背もたれがないと、介護者の手で支えがないと座位保てない。
2−4 両足での立位保持
立ち上がるまでの介助は関係なく、平らな床の上で10秒立位を保持できるか。
2−5 歩行
立った状態から5m程度歩くこと。見守り等が必要な場合は「特記事項」に記載。
2.何かにつかまればできる;片方の腕を介助者が支える。又は介助者に対象者がつかまれば歩行できる場合も含む。
3.できない;医療上の必要により歩行制限が行われている場合。何かにつかまったり支えられても5m以上歩行できない場合も含む。
Ex)ひざ立ちによる移動が可能な場合。
⇒「1.つかまらないでできる」に該当。なお、「ひざ立ちによる移動であるため、屋外は車椅子での移動」等の状況を「特記事項」に記載。
2−6 移乗
「ベッドから車椅子へ」「車いすからトイレへ」などの乗り移りの際、実際に見守りや介助が行われているかどうかに基づいて判断する。
2.見守り等;介助なしで移乗できるが、精神面の不安定などで常に必要など、見守り等を行っている場合。移乗する際に、対象者が安全に乗り移ることができるよう、一連の移乗動作に合わせて介護者が車いす等をでん部(お尻)の下に挿し入れるような場合も含む。
2−7 移動
日常生活(食事・排泄・着替え・洗面・入浴又は訓練などを含む。)において、必要な 場所への移動にあたり実際に見守りや介助が行われているか。
訓練や買い物、趣味などの日常的な外出も含む。
2.見守り等;介助なしで移動できるが、しばしば転ぶなどで助言や見守りが必要だったり、場面の変化等においての不適応行動や意欲のなさ等に対しての一時的な 声かけや見守りが必要な場合も含む。
3.一部介助;介助者が必要な場所へ移動するために手を添えたり、体を支えたり、敷居 などの段差で車椅子を押す等の介助が行われている場合も含まれる。
常に声かけしなければならない場合や強い促し、助言が必要な場合も含む。
4.全介助;自分では移動が全くできない場合(常に車いすを押す。強い促しによっても 行動できない等の日常生活における全場面で介助を必要とする場合。)。
目的もなく屋内・屋外の徘徊や多動があり、日常生活における全場面で介助を必要とする場合も含む。全く動かない・医療上移動を禁止されているも含む。
3−1 立ち上がり
椅子やベッド。車いす等に座っている状態から立ち上がる行為を行う際にベッド柵や 手すり、壁などにつかまらないで立ち上がることができるか。障害等により動作が緩慢であるなど、見守り等が必要な場合は「特記事項」にその状態を記載。
1.つかまらないでできる;習慣的に手を軽くついて立ち上がる場合も含む。
2.何かにつかまればできる;介護者が引き上げるほどの程度ではなく、支えがあれば 基本的に自分で立ち上がることができる。
3.できない;身体の一部を介護者が支える・手で引き上げるなど、介助がないとできない。
3−2 片足での立位保持
立ち上がりまでの介助は関係なく、平らな床の上で自分で左右いずれかの片足を上げた 状態のまま立位を1秒間程度保持できるかどうか。
3.できない;どのような状況でも全く片足で立つことができない場合。自分では片足を 上げられない場合。介護者に支えられた状態でなければ片足を上げられない。
3−3 洗身
入浴時に自分で身体を洗うか。身体を洗うのに介助が行われているかどうか。浴室内で スポンジやタオル等に石鹸やボディシャンプー等を付けて洗うこと。洗髪・洗顔行為は含まない。浴槽の出入りは含まない。
能力があっても介助が行われている場合は、実際に行われている介助の程度や対象者の 能力を総合的に勘案して判断する。
2.一部介助;介助者が石鹸等を付けて、身体の一部を洗う等の場合。見守り等を行う場合。自分では十分に洗身できないがために、手伝ってもらう場合。部分的に洗い直しをする場合も含む。介護者が常時離れることができず、声かけをしなければ自分でやらない場合で、強い促し・助言があることにより洗身する場合も含む。
3.全介助;「洗身」という行為の目的がわからないため、自分で一連の洗身を行っても、介護者が全て洗い直しをする場合。
4.行っていない;日常的に洗身を行っていない場合(洗身が嫌な場合)。
清拭のみ行っている場合。
4−1 じょくそう(床ずれ)等の有無
じょくそう(床ずれ)の有無。並びにじょくそう以外で処置や手入れが必要な皮膚疾患の有無のみについて評価。じょくそう以外の皮膚疾患等(口腔を含まない)とは、水虫や疥癬、開放創等を含む処置や手入れを必要とする状況。
大きさ、程度及び処置や手入れの有無は問わない。調査日から14日以内に遡っての状況を総合的に勘案して判断。再発性の場合に限り調査日より14日以内に遡って症状がない場合でも、過去1ヶ月の状況について「特記事項」に記載する。(じょくそうは改善されているが、一ヶ月前は仙骨部にじょくそうがあった。←「1.ない」と判断。)
特記すべき事項があれば要点を「特記事項」に記載。(仙骨部に発赤がみられる。右足親指に爪白癬がみられる。)
《じょくそう以外の皮膚疾患に該当する例》
・ 水虫や疥癬。開放創等。
・ 気管切開部、胃ろう、人工肛門、脱肛などで、その周囲に炎症等の手入れが必要な皮膚疾患があることが確認できる。
・ 処置や手入れが必要な 慢性湿疹、アトピー性皮膚炎、乾癬、鶏目、たこ。
《じょくそう以外の皮膚疾患に該当しない例》
・ 目薬の点眼処置。 ・ 外耳炎や中耳炎の耳垂れ。
・ 痔。 ・ 人工肛門の周囲に炎症等がなく、単にパウチ交換だけの場合を言う。
・ 気管切開部、胃ろう、脱肛だが、周囲に炎症等がなく、処置や手入れが必要ない場合。
4−2 えん下
咀しゃく(食べ物を噛む)とは異なり、えん下(飲み込む)という行為ができるかどうかのみに着目して評価する。咀しゃく力、口腔内の状況(歯がない等)について評価する項目ではない。食物を口に運ぶ行為については、「4−3食事摂取」。
固形物か液体かどうか等、食物の形状(普通食、刻み食、ミキサー食、流動食)によって異なる場合は、日頃の状況に基づいて判断し、「特記事項」に内容を記載。
知的障害者や精神障害者等の経過の中で、精神的な状況又は意欲低下等の理由から飲み 込もうとしないなど、実際に介助がなされているかどうかに基づいて判断。
2.見守り;飲み込む際に見守り等が行われている場合であって、「できる」「できない」のいずれにも含まれない場合をいう。(「えん下はできるが、口にいっぱいに 入れて、むせやすく見守りが必要。」「声かけしないと飲み込もうとしないため、見守りが必要。」等、詳細を「特記事項」に記載。)
4−3 食事摂取
通常の食事の介助が行われているかどうか。(自助具等の使用の有無。要する時間や 対象者の能力は問わず。)
時間がかかる。落ち着いて食事に集中しない等の場合、その状態を「特記事項」に記載。精神的な状況又は意欲低下等の理由から食事摂取の介助を受けている場合はその状況
に基づき判断する。(「食事を促しても反応が無く、口に運ぶと口を開け食べる。」等、 その詳細を「特記事項」に記載。)
* 食事の介助;スプーンフィーディングや食卓上で刻みながら口に運ぶ場合。又は
食べこぼしの掃除などを想定。
1.できる;箸やスプーンの他に自助具等を使用すれば自分で食事が摂れている場合。視覚障害者で配膳の際におかずの種類や配列を知らせると自分で摂取できる場合。
2.見守り等;他人の食事を食べないようにする為、見守り等をしている場合。食事を摂るよう促すなど、声かけ・見守り等をしている場合も含まれる。視覚障害者で、器をひっくり返すなどがよくあり、見守り等が行われている場合。
3.一部介助;食事の際に食卓上で、皮をむく。魚の骨を取るなど食べやすくする為に 何らかの介助が行われている場合。
4.全介助;能力があるかどうかにかかわらず、現在自分では全く摂取していない場合。
介助なしに自分で摂取できるが、早食い等で自分で摂取させると健康上の問題があるなどの判断で、全て介助している場合。
Ex)・特定の食品をとるように促す、「おつゆも飲まないとだめですよ。」は?
⇒「2.見守り等」特定の食品を極端に摂取するが、声かけ程度で他の食品を 食べる場合も同様。
・介助者等が台所や厨房でほぐしたり刻んだりした状態にしてある時に、対象者が その状態の食べ物を自分で食べられる場合は?
⇒「1.できる。」食べやすく調理された状態で卓上に上がった場合は、それを 本人が自分で食べられるかどうかの判断になり、特記事項に「おかずは、刻み食にすれば食べられる。」等詳細を記載。
4−4 飲水
通常の飲水(飲水量が適正量かどうかの判断も含む)の介助が行われているかどうかに着目して評価する。
精神的な状況または意欲低下等の理由から対象者が自ら飲水をしない。或いは一度に過剰な飲水をする場合でも実際に介助がなされているかどうか。
1.できる;自分で水道やペットボトル等から水、お茶、ジュース等をコップや茶碗に 入れて適正量を判断し飲める場合。
2.見守り等;茶碗、コップ等に入れられた物を手の届く範囲におけば、自分で飲める場合。
適正量を調整するために介護者等が茶碗、コップ等を手の届く範囲におく必要がある場合。
3.一部介助;茶碗、コップ等を手渡すか、口元まで運ぶ等の介助が行われる場合。自分で摂取することができても、口渇感が乏しい場合や、1回の水分量が多い場合又はコントロールできず、声かけ(注意)や制止があれば止めるなどの場合。
4.全介助;自分では全く飲水をしていない場合。
医療上の必要により飲水を禁止されている場合。
自分で摂取することができても、全く口渇感を訴えない場合や、1回の飲水量が多い場合。コントロールができず、声かけ(注意)や制止をしても止めない場合。
4−5 排尿
自分で排尿に関わる一連の行為(尿意、トイレまでの移動、ズボン・パンツの上げ下げ、
トイレへの排尿、排尿後の後始末など)を行っているか。排尿後の後始末には、ポータブル
トイレや尿器等の掃除。除去したカテーテルの後始末が含まれる。
昼間は介助なく自分で排尿にかかる一連の行為を行っているが、夜間のみオムツを使用していたり、ポータブルトイレを使用している場合には、日頃の対象者がもっとも頻度の高い排尿の状況により判断し、その内容を「特記事項」に記載する。
精神的な状況又は意識の低下等の理由から排尿の介助を受けている場合はその状況に 基づき判断する。この場合は、「意欲の低下により、尿意の反応がなく、訴えることもない。」等、その詳細を「特記事項」に記載。
行動障害で「トイレ以外の特定の場所に固執して排尿する。」等、障害特有の行動により、特別な介助が必要な場合は「4.全介助」とし、その詳細を「特記事項」に記載。
1.できる;尿意はないが、自分で時間を決めるなどして排尿にかかる一連の行為を 行っている場合。
2.見守り等;一連の行為を介助なしで行っているが、集中性に欠けるなど声かけが必要な場合。声かけしないとトイレ以外の場所で排尿する場合。
3.一部介助;一連の行為のうち以下の1項目のみ該当する場合。
・トイレまでの移動。或いはポータブルトイレへの移乗に介助が必要。
・排尿動作に介助が必要。 ・排尿後の後始末に介助が必要。
4.全介助;一連の行為のうち上記から2項目以上該当する場合。
又、以下の場合いずれか1項目以上に該当する場合も含まれる。
但し、自分で準備・後始末等を行っている場合を除く。
・集尿器を使用している場合。 ・オムツを使用している場合。
・介護者により間欠導尿が行われている場合。
・尿カテーテルを留置している場合。
4−6 排便
全般的に排尿 と同様。
5−1 清潔
日頃からその行為を行っているかどうか。生活習慣、施設の方針、介護者の都合等によって、通常行っていない場合等は、例外的に対象者の能力を総合的に勘案して判断し、判断の理由を「特記事項」に記載。対象者が自身の清潔保持に関心が乏しいため必要な場合も含まれる。
ア.口腔清潔(はみがき等);一連の行為(歯ブラシやうがい用の水を用意する。歯磨き粉を ブラシにつける等の準備、義歯をはずす、うがいをする等)を自分で行っているかどうか。口腔洗浄剤・義歯の場合も清潔保持と うがいができているかどうかで判断。「特記事項」に記載。
イ.洗顔;一連の行為(タオルの準備、蛇口をひねる、衣服の濡れの確認、タオルで拭く等)を 自分で行っているかどうか。
ウ.洗髪;一連の行為(くしやブラシの準備等も含む)を自分で行っているかどうか。頭髪がない。又は短く刈っている場合は、頭を拭いたり整髪に関する類似の行為について判断し、判断した内容を「特記事項」に記載。
エ.爪切り;一連の行為(つめ切りの準備。切った爪を捨てる等)を自分で行っているかどうか。
日頃やすり等の他の器具を用いている場合は、日頃の状況に基づいて能力を判断し、判断した内容を「特記事項」に記載。
精神的な状況。又は意欲低下などの理由から清潔に対する関心や意識がない等により介助を受けている状況により判断する。「意欲の低下により、清潔に対する意識がなく、訴えることもない。」なども含み、この場合その詳細を「特記事項」に記載。
2.一部介助;一連の行為に対して部分的に介助が行われていたり、一連の行為に強い促しをしている場合。常時の見守りや確認、強い促しが必要だったり、行われている場合。
口腔;はみがき中の見守り等、磨き残しの確認が必要な場合。
義歯の出し入れはできるが、義歯を磨く動作は介護者が行っている場合。
洗顔;洗顔中の見守り等、衣服が濡れていないかの確認などが必要な場合。
蒸しタオル等で顔を拭くことはできるが、手で顔を洗うことができない場合。
つめ切り;見守りや確認が必要な場合。
左右どちらか片方。手はできるが、足はできない等の場合。
3.全介助;強い助言や指導をしても行わない場合。介助が行われていないが、明らかに 能力がない場合。口腔清潔、洗顔で、本人が行った箇所を含めて全てを介助者がやり直す場合。口をゆすいで吐き出す行為だけ。顔を濡らすだけの場合。 総義歯で義歯洗浄は全介助の場合。
5−2 衣服着脱
普段着用している衣服について、衣服(上衣、ズボン・パンツ)の着脱を自分で行っているかどうか。衣服の種類(ボタンの有無、ゴム付きフリーサイズズボン等)等は、時候に合った服装の準備、必要な枚数だけ衣服を出すこと。着脱を促す為の声かけ等着脱までの行為は含まれない。
障害の状況により介助されている場合は、その介助されている障害の状況に応じて判断し、
その判断の理由を「特記事項」に記載する。
日常的に頻回に着用している衣服の状況に基づいて判断する。(ボタンのないトレーナー等)
時間がかかる場合は「特記事項」に記載。
精神的な状況。又は意欲低下などの理由から着脱の介助を受けている状況により判断する。「意欲の低下により、着脱を促しても反応がなく、着替えようともしない。」なども、その 詳細を「特記事項」に記載。
2.見守り等;介助なしに自分で上衣、ズボン・パンツの着脱をしているが、前後を時々 間違えるために、見守りし声かけが必要など、見守りが行われている場合。
3.一部介助;着脱に何らかの介助が行われている場合。
手が回せないがために介護者が常に上衣を持っていなければならなかったり、麻痺側のみ着せる場合。
ズボン・パンツに関しては、自分で行っていても最後に介護者がシャツをズボン・
パンツ等に入れなおす場合等も含む。
5−3 薬の内服
一連の行為(薬を飲む時間や量を理解する。薬や水を手元に用意する。薬を口に入れる、 飲み込む。)について、現在の状況で介助を受けているか否か。
インスリン注射、塗り薬の塗布等、内服薬以外のものは含まれない。
投薬を受けていても、飲むことを忘れる。飲むことを避ける場合には、その対応に基づいて判断し、その対応について「特記事項」に記載する。
投薬を受けていない場合は、対象者の能力を総合的に勘案して判断し、その判断について 「特記事項」に記載する。
施設入所者で一括して管理されているため、自己管理の機会がない場合は、本人が自己管理した場合を総合的に勘案して判断し、その判断について「特記事項」に記載する。
服薬の必要性を認識しない、或いは副作用を過度に心配するといった状況のため服薬の介助が必要な場合も含む。
1.できる;薬を飲む時間や量を理解し、介助なしで自分で内服薬を服用している場合。
2.一部介助;薬を飲む際の見守り、飲む量の指示や確認等が行われている。或いは、飲む薬や水を手元に用意する。オブラートに包むなど、何らかの介助が行われている。重度の障害者で薬や飲む量は理解しており、介護者に指示して薬を 用意してもらい、飲ませてもらっている場合。薬の管理はできないが、手渡しされた後、水と共に服薬する行為を自分で行っている場合。薬の量や時間は理解しているが、介護者が指示しないと失念しがちな場合。
3.全介助; 飲む時間を忘れたり、飲む量もわからない。或いは重度の障害や手指の麻痺・
障害により自分では飲めないために、薬の内服に関わる行為全てに介助が行わ
れている場合。
薬を飲む時間や量を理解しておらず、介護者が薬を口の中に入れることに より対象者は飲み込むのみの場合。
薬を飲む時間や量は理解しているが、服薬に抵抗があり、服薬するように 介護者が長時間(社会通念上の判断)の働きかけをする場合も含まれる。
些細幸い
5−4 金銭の管理
自分の所持金(預金通帳や小銭)の支出入の把握、管理、出し入れする金額の計算を自分で行っているかどうか。及びそれが適切であるか否かに着目して評価するものであり、現在の 状況で介助を受けているかどうか。
実際に自分で金銭の出し入れに関する行為を行っているかどうかは問わない。
基本的に施設や家族等が管理を行っている場合は、対象者の身の回りの物品の管理状況、 計算能力に基づいて総合的に判断。その判断について「特記事項」に記載。
金銭管理の状況が判断できない場合は、家族や介護者等から聞き取った内容を踏まえて判断する。「収入と支出の理解、概念がなく、借金してでも使うため、金銭管理はできない。」等、その詳細を「特記事項」に記載。
1.できる;自分の所持金の支出入の把握や管理を自分で行っている。出し入れする金額の計算を介助者なしで自分で行っている場合。
2.一部介助;小遣い使用の助言・指導等金銭管理に何らかの介助が行われている。
或いは小遣い銭として、小額のみ自己管理している場合。
3.全介助;金銭の管理について全てに介助が行われている場合。
一日の必要額を家族が準備し、その必要額の管理も自分で行えない場合。
5−5 電話の利用
一連の行為(かけたり、受けたりの操作。電話の内容を理解して話す。必要な伝言をする等)を自分で行っているか。
電話を利用する機会がない場合、対象者の日頃の能力を総合的に勘案して判断。その判断について「特記事項」に記載。
2.一部介助;見守り等が行われている場合。視覚障害者・知的障害者などで、誰かが
ダイヤルすれば、相手と話せる場合。
3.全介助;一連の行為全てに介助が行われている場合。又は「電話」というものの 理解がない場合。
Ex)いたずら電話をする為、使わないよう管理されている場合。
⇒一連の行為全てに介助が必要である為、使わぬよう管理されている。「3.全介助」
Ex)精神障害者で、電話利用に係る一連の行為はできるが、相手の都合も考えず脅迫症状に基づき電話を頻回にかけたり、必要のない所へかける等の行動をとる為、家族が注意 したり、指導の必要な場合。
⇒「2.一部介助」なお、その状況を「特記事項」に記載。
Ex)決まった相手2.3箇所のみ、一連の行為を一人で行うことができる場合。
⇒「1.できる。」特記事項に「○○と△△以外の電話の利用には、ダイヤルして あげれば可能。」と記載。
5−6 日常の意思決定
毎日の暮らしにおける課題や活動を実際にどの程度判断しているかという、日常の意思決定(服を選ぶ、起床や食事すべき時間がわかる。自分にできることとできないことがわかる。
必要時に援助を求める。など)を行う為の認知判断能力を評価。対象者自ら決めているのか。決断ができず混乱していないか。対象者にはできるはずだという思い込みはないか。
普段とは異なる旅行やレストランといった状況でも食事メニューを注文したり、周囲の人に必要な援助を依頼する等、適切な意思決定ができるかどうか。と判断。
日によって妥当な判断ができる時とできない時がある場合には、原則として頻回な状況を
聞き取った内容を踏まえて判断する。
対象者に能力があるにも関わらず、精神的な状況。又は意欲低下等の理由から意思決定を していない場合や意思決定を介護者が行っている場合等は、その能力について聞き取った内容を総合的に踏まえて判断する。
1.できる;判断が首尾一貫して理にかなっており、妥当な場合。自分で判断できない・迷う場面では、自分から他者に助言・援助を求めることができる。
2.特別な場合を除いてできる;日常では妥当な判断をするが、新しい課題や状況では
指示や合図を必要とする。
3.日常的に困難;日常生活でも決断できず混乱したり、妥当でない意思決定判断をする。
Ex)トイレはできるが、他の項目はできない。
⇒日常生活全体の中で判断。できたり・できなかったりする場合は、頻度の高い方。
Ex)「妥当でない意思決定判断」とは。
⇒室内のスリッパのまま外に出る。など…
6−1 視力
見えるかどうかについてのみ着目。
見えているものの名称を正しく表現できるかや理解力は問わない。
見えるかどうかの判断には会話だけでなく、身振り等にも基づいて判断。
1.普通(日常生活に支障がない);新聞・雑誌等の字が見える。字が見えているか判断
がつかないが、日常生活に支障がない程度の視力を
有している。
4.ほとんど見えない;目の前に置いた視力確認表の図が見えない。
5.見えているのか判断不可能;意思疎通ができず、見えているのか日常生活に支障が あるのか判断できない場合。
6−2 聴力
聞こえるかどうかのみに着目して評価。聞いた内容を理解しているかどうかの知的能力は
問わない。
普通に話しても聞こえない対象者には、耳元で大声で話す。
知的障害者等で音に対する反応に障害があっても、声や音が聞こえているかどうか、日頃の
対象者の反応に詳しい介護者の助言から判断。どういう反応であったか「特記事項」に記載。
2.普通の声がやっと聞き取れる;普通の声で話すと聞き取りにくく、聞き間違えたり する場合。
5.聞こえているのか判断不可能;意思疎通ができず、聞こえてるのか判断できない場合。
6−3−ア 意思の伝達
対象者が意思を伝達できるか(受け手に自分の意思を表示し伝わること。)どうかのみに 着目して評価するもの。意思伝達の手段(手話・筆談・身振り・メール・トーキングエイド等)や相手。背景疾患は問わない。
意思の伝達に変動がある場合は、もっとも頻回に表出される状況を介護者等から聞き取り 総合的に判断。その内容を「特記事項」に記載。
1.対象者が意思を他者に伝達できる;手段を問わず、常時誰にでも伝達ができる場合。
2.ときどき伝達できる;通常は対象者が家族等の介護者に対して意思の伝達ができる。 しかしその内容や状況によっては出来る時とできないときが ある場合。この場合の頻度は「特記事項」に記載。
3.ほとんど伝達できない;通常家族等の介護者に対しても意思の伝達ができないが、ある
事柄や特定の人に対してなら、まれに意思の伝達ができる場合。
4.できない;意思の伝達ができない。或いはできているかどうか、わからない場合。
6−3−イ 本人独自の表現方法を用いた意思表示
重度のコミュニケーション障害を有している場合の意思表示の仕方。日常生活や外出時において独自の表現(独特のジェスチャーや仕草)を使用し意思表示する場合を問う。
2.時々、独自の方法でないと意思表示できないことがある;
時々頭をぶつけたり、腕を掴んだり等通常とは違う行動でしか自らの意思を表現
できないことがある場合。「3」の常時必要な場合以外は、この項目。
3.常に、独自の方法でないと意思表示できない。;上記の通常とは違う行動でしか 自らの意思を表現できない場合。
4.意思表示ができない;独自の方法を用いても、意思表示できない場合。
6−4−ア 介護者の指示への反応
必要である指示に対してその意味を理解して何らかの反応ができるかどうか。
指示を守るかどうか。背景疾患を問うものではない。
反応の伝達手段は問わず、介護者の指示を理解して何らかの言葉や態度。行動の変化を起こすかどうか。介護者の指示も手話・身振り・絵・写真…伝われば何でもよい。
1.指示が通じる;「嫌だ」と答える場合も。
聞こえない振りをしても、反応していることが明らかな場合。
2.指示が時々通じる;そのときによって、反応したりしなかったりする場合。
頻度は「特記事項」に記載。
3.指示が通じない;指示に反応しない。通じてるかどうかの判断ができない場合。
6−4−イ 言葉以外のコミュニケーション手段を用いた説明の理解
重度のコミュニケーション障害を有している場合の説明に対しての理解。日常生活や
外出時において言葉以外の表現(ジェスチャーや絵カード等)を使用し説明する場合を問う。
1.日常生活においては、言葉以外の方法(ジェスチャー、絵カード等)を用いなく
ても説明を理解できる。;習慣化されていない日常生活や外出時においてだけ、
言葉以外の方法を用いる必要がある場合も含む。
4.言葉以外の方法を用いても、説明を理解できない。;
説明に対して応答はしているが、理解できているかどうか判断できない場合。
6−5 記憶・理解
記憶や理解度を問うもの。
ア.毎日の日課を理解する;施設プログラム等についておおよそのスケジュールを理解してるか。
イ.生年月日や年齢を答える;いずれか一方を答えることができればよい。
エ.自分の名前を答える;旧姓等を問わず、姓か名前のどちらかを答えられればよい。
愛称で答えても日常生活上問題が生じていないのであれば可。
オ.今の季節を理解する;多少のズレがあってもよい。
カ.自分がいる場所を答える;施設の場合の居室・視説明・施設の所在地のいずれでもよい。
1.できる;いつでもほぼ正確な解答ができる場合。
数日のずれ。姓を聞いて名前を思い出す。等も含む。
時間がかかっても答えることができる場合も含まれる。
言葉が不明瞭で筆記もできないが、対象者の反応から理解していると判断 した場合も含む。
2.できない;できたりできなかったりする場合や回答の正誤が確認できない場合。
調査員が質問したときには回答できても、家族からの聞き取りによると 忘れていることが多い場合も含む。
7 行動
日常生活において行動上の障害があるかどうか、またある場合にはその頻度を評価する。
日常生活への支障については、周囲の人に与える影響について総合的に勘案して判断。
調査時の状況のみから判断せず、過去1年間程度の期間の生活状況の変動も踏まえて判断する。
(ア〜ト)(へ〜ヤ)
1.ない;その行動上の障害が(過去1回以上あったとしても)過去1ヶ月間に1度も 現れたことがない場合やほとんど月1回以上の頻度では現れない場合。
2.ときどきある;少なくとも1ヶ月に1回以上の頻度。2つ以上の状況を例示している 選択肢について、いずれかが、「ときどきある」場合も含まれる。その頻度は「特記事項」へ記載。
3.ある;少なくとも1週間に1回以上の頻度。2つ以上の状況を例示している選択肢に ついて、いずれか1つでも「ある」場合。
ア.物を盗られたなどと被害的になること;実際に盗られていないものを盗られたという等。
現実の誇張は含まれない。
イ.作話をし周囲に言いふらすこと;作話をしても、特定の人にのみ話をする場合は該当しない。
自分に都合のいいように事実と異なる話をすることも含む。
エ.泣いたり笑ったり感情が不安定になること;些細なきっかけで悲しんで涙ぐんだり、不安や 恐怖から感情的にうめく等、明らかに感情が 不安定になる。
オ.夜間不眠あるいは昼夜の逆転;夜間不眠の訴えが何日間か続いたり、明らかに昼夜が逆転するなどし、そのために日常生活に支障が生じている場合。不眠の原因は問わない。睡眠薬等の投与により睡眠がうまくコントロールされていれば「1.ない」。
カ.暴言や暴行;対象は人間。「ネ」と同一の行為を基で判断するのは可。
ク.大声を出すこと;日常生活で声が大きい場合等は含まない。
ケ.助言や介護に抵抗すること;対象者と介護者の人間関係的要素も含まれるが、明らかに介護者の助言や介護に抵抗し、介護に支障がある場合。単に助言しても従わない場合は含まれない。
コ.目的もなく動き回る;歩き回る。車椅子で動き回る。床やベッドの上で這い回るなど、その
目的が周囲の者に理解しがたい行動をとり続ける場合。「ナ」の多動と
同じ行為を基に考えることは可能。
Ex)自閉症の人が電気を消して回ったり、窓を閉めて回ったりする場合。
⇒理由が周囲には理解しがたい場合。
サ.「家に帰る」等と言い落ち着きがないこと;施設等で「家に帰る」と言ったり、外に出ようとしたり、自宅にいても「家に帰る」等と言って落ち着きがなくなる場合。単にそう言っているだけで落ち着いている場合は含まれない。
Ex)「家に帰る」等の訴えはないが、隙があれば無断外出をしようとする場合。
⇒該当する。
シ.外出すると施設などに一人で戻れなくなる;施設などで居室等から出て、自室に自力で戻れ なくなる場合も含む。
ス.一人で外に出たがり目が離せない;周囲の制止に従わず、外に出たがる為に目が離せない。 環境上の工夫等で外に出ない。歩けない等の場合は含ず。
セ.色んなものを集めたり、無断で持ってくること;収集癖。周囲の迷惑とならない。紐や包装紙等を集める等の趣味は含まれない。「ノ」と同一の行為を基に判断することは可能。
収集癖;特定のものだけ集め、「癖」の域に達している場合。極めて小さなゴミだけを集め、
ティッシュ等の大きなゴミは興味ない。時計だけをどこからともなく持ってくる等。
ソ.火の始末や火元の管理;環境上の工夫等で火元に近づくことがなかったり、周囲の人々に よって火元が完全に管理されている場合は含まれない。
タ.物や衣類を壊したり、破いたりすること;日常生活に支障が生じる場合。捨てる等で支障が 出る場合も含まれる。その行動の原因は問わない。
チ.不潔な行為を行う(排泄物を弄ぶ);弄便(尿)など排泄物を弄ぶ。尿を撒き散らす場合。 体が清潔でないことは含まない。
ツ.食べられないものを口に入れること;異食行動。異食しそうなもの等を周囲に置かない場合は含まれない。完全に飲み込まなくても口の中に入れれば異食行動。「3B.ほぼ毎日ある」を選んだ場合は、 その頻度を「特記事項」に記載。
テ.ひどい物忘れ;日常生活に支障が生じる場合。
ト.特定の物や人に対する強いこだわり;日常生活に支障が生じる場合。支障がなければこだわりが強くても「ない」に該当。
(ナ〜フ)
1.ない;過去1年間に1度もない場合や、数ヶ月に1回以上の頻度では現れない場合。
2.希にある;少なくとも数ヶ月に1回以上の頻度。2つ以上の状況を例示している選択肢について、いずれか一つでも「ある」場合。
5.ほぼ毎日;週5回以上、かつ1日1回以上現れる場合。
ナ.多動または行動の停止;行動障害で特定の物や人に対する興味関心が強く、思い通りに ならないと多動になったり、こだわりが強くなり動かなくなって しまう場合。「コ」の目的もなく動き回ること。と同一の行為を基にした判断は可能。
Ex)自閉的傾向が強く計画以外の行動ができない場合。突然の予定変更により行動が停止
したり落ち着かなくなる場合や、食事の時間になっても予定の作業が終わっていない為、
作業を続け次の行動食事への切り替えができない場合。 ⇒ 該当。
ニ.パニックや不安定な行動;予定等の変更が受け入れられず大声を出して泣き叫ぶ等のパニックや行動が不安定になる場合。精神障害で不安・恐怖・焦燥等に かられて衝動的な行動がある場合も含む。
ヌ.自分の体を叩いたり傷つけたりする;自ら傷跡が残るほど自分の体に傷をつけたりする行為。
精神障害で、手首を切る・頭髪を抜く等の行為も含む。
習慣性のもの、パニック等の不安定な行動時の突発的なものも両方含む。その頻度や状況を「特記事項」に記載。
ネ.叩いたり蹴ったり器物を壊したりする等の行為;他人を叩く・髪の毛を引っ張る・蹴る等の 行為や壁を壊したりガラスを割ったりする等の行為がある場合。対象は人間を含め他の物まで含む。「カ」と同一の行為を基でも可。
ノ.他人に突然抱きついたり、断りもなく物を持ってくる行為;興味や関心が優先したり、適切な
意思表示ができない等により他人に突然抱きついたり、断りもなく物を持ってきてしまう行為がある場合。
善悪という適切な判断能力がないための行為。「セ」と同一の行為を基に判断することも可能。
(ハ・ヒ)
4.日に1回以上;概ね一日に1回から2・3回程度。
5.日に頻回;一日に何度もあり、何回とは言えないほど頻回にある場合。
ハ.環境の変化により、突発的に通常と違う声を出すこと;本人の欲求が受け入れられなかったり、
制止されたりした時や、非常に興味関心の
強いものや人を見たときに起こる場合。
Ex)常時通常と違う声を発していて、環境の変化によるかどうか判断できない場合。
⇒「5.日に頻回」
ヒ.突然走っていなくなるような突発的行動;興味や関心が強い物や人を見つけたら、断りもなくそちらへ走っていってしまう等の場合。興味の対象が不明の場合も含む。突然人を突き飛ばす。許可なく他人宅に入り、冷蔵庫を開けるなど。
フ.過食・反すう等の食事に関する行動;食に関する行動障害或いは複数の行動が認められる場合。
食事に支障を来たすもの。
Ex)過飲・拒食・食器に手を入れたままかき混ぜる。食器に吐き出し、それを再び食べ始める。
へ.気分が憂鬱で悲観的になったり、時には思考力が低下すること;抑うつ気分によりひどく
悲観的で合ったり考えがまとまらない為日常生活に支障をきた
す場合。時に死にたいといった素振りを示し、危険を防止する
ために誰かがそばについている等の配慮が必要とされる場合。
ホ.再三の手洗いや繰り返しの確認の為、日常動作に時間がかかること;ある考えに固執したり、特定の行為を反復したり、或いは儀式的な行為にとらわれることで日常生活に支障をきたす。必要以上に手を洗う。施錠を確認する等。
マ.他者と交流することの不安や緊張の為外出できないこと;長期(一ヶ月以上)にわたって 引きこもりも含む。
Ex)1月に4日以上引きこもりの日がある場合。
⇒「3.ある」その状況を特記事項に記載。
(外出を全くしようとしない。通院以外は外出しない等。)
ミ.一日中横になっていたり、自室に閉じこもって何もしないでいること;行動を計画したり実行したりする意欲が乏しいため、周りから言われないと何にもしないでいる場合。
Ex)重度の知的障害で意欲や理解力が低いため、そのような状態が見られる。
⇒ 該当する。
ム.話がまとまらず、会話にならないこと;話のないように一貫性がない。話題を次々に変える。質問に対して全く意図しない反応が返ってくる等により会話が成立しない場合。興奮したときに一時的に話がまとまらない場合は除く。
モ.現実には合わず高く自己を評価すること;現実にはそぐわない特別な地位や能力が自分胃あると信じてそれを主張する場合。
Ex)実行するのは難しいが「仕事はできる。」「調理はできる。」と意思表示する場合
;誇大妄想を想定しており、単に『○○できる。』では該当しない。
ヤ.他者に対して疑い深く拒否的である;他者を信頼しない態度で、相手の善意を疑い、話し合いや本人の為になされた提案を受け入れない場合。
Ex)理解力が低いため相手の考えや意見を理解できず本人のためになされた提案を受け入れ
ない場合。 ⇒ 「他者に対して疑い深く拒否的」であることが判断基準。該当せず。
9−1 調理(献立を含む)
一連の行為(簡単な食事について、献立をたて、調理し後片付け(調理器具を洗う・
しまう。ゴミの後始末)まで)についてを評価。
配膳・下膳、買い物は含まれない。普段行っていない場合は、日頃の生活状況・他の家事
の状況等の聞き入れを勘案し、総合的に判断。その判断した状況を「特記事項」に記載。
1.できる;一人で出来る場合。普段の家事全般についてできており、果物を剥いたり、
お茶やコーヒーなどを出したりする能力等を勘案した場合、調理が一通り
可能と判断できる場合。
2.見守り、一部介助;見守りや食材を切る、煮る、炒める等の直接的な援助が部分的に必要な場合。普段の家事全般について比較的できており、果物を剥いたり、お湯を沸かす、お茶やコーヒーなどを出したりする能力などを勘案した場合、直接的な援助が部分的に行えば可能と判断できる場合。
3.全介助;1人で一連の行為ができず、一連の行為を通じて直接的援助が必要な場合。
Ex)後片付けのみができる場合;1人では一連の行為ができず、殆どが直接的援助が必要な為「3.全介助」
9−2 食事の配膳・下膳(運ぶこと)
一連の行為(盛り付け、配膳・下膳(1人で出来るかどうか)、食器洗い、食器の
後片付け)ができるかどうか。
普段行ってない場合は、日頃の生活状況の聞き取りや本人の他の家事の状況等を勘案し
総合的に判断する。この場合判断した状況を「特記事項」に記載。
1.できる;一人でできる場合。普段の家事全般についてできており、お客に対するお茶
菓子や果物の盛り付け、御茶屋コーヒーを出したりする能力を勘案した場合、
配膳・下膳が一通り可能だと判断できる場合。
2.見守り・一部介助;常に見守りや直接的な援助が部分的に必要な場合。普段の家事
全般について比較的できており、お客に対するお茶菓子や果物の
盛り付け、お茶やコーヒー等を出したりする能力等を勘案した
場合、声かけや直接的な援助が部分的に行えば配膳・下膳が 一通り可能と判断できる場合。
9−3 掃除(整理整頓を含む)
一連の行為(掃除機の準備・操作・掃除する部屋の整理、掃除機の後片付け)について評価。
掃除機や箒を使って普段自分の使用している部屋等を掃除すること。自分の持ち物の整理
整頓ができるか。普段行っていない場合は、日頃の生活状況の聞き取りや本人のほかの家事の状況等を勘案し総合的に判断。この場合、判断した状況を「特記事項」に記載する。
1.できる;一人でできる場合。普段の家事全般についてできて、居住環境も整理整頓
されている等の能力等を勘案した場合、掃除が一通り可能のと判断できる場合。
2.見守り・一部介助;常に見守りや整理整頓で直接的な援助が部分的に必要な場合。
普段の家事全般について比較的できており、居住環境も不充分 ではあるが比較的整理整頓されている等、直接的な援助が部分的に行われれば、掃除が一通り可能と判断できる場合。
3.全介助;一人では一連の行為ができず、一連の行為を通じて直接的援助が必要な場合。
Ex)掃除機の準備や後片付けのみができる場合。
⇒一人では一連の行為ができず、ほとんどが直接的援助が必要なため「3.全介助」
9−4 洗濯
通常の日常生活で行っている洗濯の一連の行為(洗濯物を洗濯機に入れる。操作を行う。
洗剤を準備する。洗濯物を乾かす・取り込む・たたむ・片付けるまで。)についての評価。
普段行っていない場合は、日頃の生活状況の聞き取りや本人のほかの家事の状況等を勘案
し総合的に判断。この場合、判断した状況を「特記事項」に記載する。
1.できる;一人でできる場合。対象者の普段着ている衣類等から判断した場合、清潔
な衣類を着ており、衣類等がよく整理されている等、洗濯が一通り可能と
判断できる場合。
2.見守り・一部介助;常に見守りや洗濯機の操作等で直接的な援助が部分的に必要な場合。対象者の普段着ている衣類等から判断した場合、比較的清潔な衣類を着ており、衣類等が不十分なところもあるが比較的整理 されているなど、直接的な援助が部分的に行われれば選択が一通り可能と判断できる場合。
Ex)洗濯物をたたんだり、片付けたりすることのみができる場合。
⇒洗濯物をたたんだり、片付けることができる方なら、洗濯物を洗濯機に
入れる。洗剤を準備する。洗濯物を乾かす・取り込む…と一連の行為も
通常はできるのではないかと考え、調査にあたり能力勘案する必要あり。
9−5 入浴の準備と後片付け
一連の行為(浴槽に水を張る。お湯を沸かす。入浴用品の準備・後片付け。着替えを準備。
風呂場の後片付けまで)について評価で、浴槽に入ることや洗身は含まれない。普段行って
いない場合は、日頃の生活状況の家族等からの聞き取りや本人のほかの家事の状況等を
勘案し総合的に判断する。この場合判断した状況を「特記事項」に記載する。
1.できる;一人でできる。普段の家事全般についてできており、居住環境も整理整頓
されている等も勘案した場合、入浴の準備が一通り可能と判断できる場合。
2.見守り・一部介助;常に見守りや水張り・お湯沸し等で直接的な援助が部分的に必要な場合。普段の家事全般について比較的できており、居住環境も不十分ではあるが比較的整理整頓されている等、直接的な援助が部分的に行われれば、入浴の準備が一通り可能と判断できる場合。
9−6 買い物
コンビニやデパートで、適切に必要な商品を選び、代金を支払うこと。店までの移動は
含まれない。普段行っていない場合は、日頃の生活状況を家族等から聞き入れした状況等を
勘案し総合的に判断する。この場合、判断した状況を「特記事項」に記載する。
1.できる;一人でできる場合。普段のお小遣いに管理等の能力等を勘案した場合、
買い物が一通り可能と判断できる場合。
2.見守り・一部介助;常に見守りや商品の選定、金銭の計算等で直接的な援助が 部分的に必要な場合。
9−7 交通手段の利用
一連の行為(目的地(学校や施設など普段通いなれた場所・目的地)へ行く交通機関を
選ぶ。バスや駅まで移動する。切符を購入する。乗車する。目的地で降車する。目的地まで
行く。まで)を一人で適切にできるかどうか。
地域の交通手段が目的地まで適切に利用できるか。
普段利用していない場合は、日頃の生活状況を家族等から聞き取った状況等を勘案し、
総合的に判断する。この場合判断した状況を「特記事項」に記載する。
1.できる;一人でできる場合。普段の外出や社会生活などの能力等を勘案したら、
交通手段の利用が一通り可能と判断できる場合。
2.見守り、一部介助;常に見守りや切符の購入、移乗等で直接的な援助が部分的に 必要な場合。普段の外出等から勘案すると、部分的な声かけや介助があれば交通手段の利用が一通り可能と判断できる場合。
Ex)何度か練習すれば決まった目的地への移動が可能になる場合。
⇒ 「1.できる」
9−8 文字の視覚的認識使用
文字が見えるかどうかに着目して、その状況により文字が使用できるかを評価する。
文字の理解等の知的能力は問わない。点字の活用は含まない。補助具等で文字の大きさの 変更等を行った場合は、「特記事項」に記載。
1.できる;文字が読めない場合であっても、文字が見える場合も含まれる。
2.一部介助;文字のサイズ変更、白黒反転等、他者が文字を修正すれば文字を活用できる場合。自由な書式や文字の大きさなら、視覚的に文字を活用できるが、一定の書式や文字の大きさを規定されると、活用が困難になる場合。 (金融機関の書類、申込書等の書式には文字が小さすぎて書き込めない。)
3.全介助;文字を音声化するなど、視覚以外の方法でしか活用できない場合。
Ex)視覚障害はないが知的障害により文字が読めない場合。
⇒視覚障害に着目した項目であるので、見えるが文字を読めない場合でも 「1.できる」
|
|
|
|
|
|
|
|
施設カイゼン委員会 知的本部 更新情報
-
最新のアンケート
施設カイゼン委員会 知的本部のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90034人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6416人
- 3位
- 独り言
- 9044人