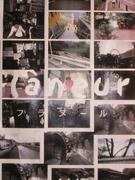今回も地図を参加者に配ったが、ふたつの市を跨ぐため、詳細地図を二分割にしたうえに、地域情報の切り貼りを施してみました。地図はご存知『ニュータイプエアリアマップ東京区分地図』(昭文社、1999年度版)を引用した書物は『東京セレクション「水の巻」』より「国分寺」(藤森照信・選/写真=高梨豊)および『東京セレクション「花の巻」』より「府中」(滝田ゆう・選/写真=高梨豊)(それぞれ住まい学大系015/014)のエッセーと街のデータ(1988年)、『続・昭和二十年東京地図 周縁のこと』(文・西井一夫/写真・平嶋彰彦、筑摩書房)「其の十 調布・府中・国分寺」のエッセー、「三億円犯人決算報告書」は「1975『遊』8・此の遊八号文学の夢を観る観る裡に遠方の遊星に変じると遊。[特集叛文学非文学]」所収「計算する文学・もう卓上計算器を買いましたか?」(工作舎)より。
(国分寺・府中あるくかい地図)
http://
(国分寺のほう)
http://
(府中のほう)
http://
ただし見づらいため、カズキさんの方式に倣い、自分もやってみるが、アドビのソフトもなくやっとできたのがトップ写真左の地図。下方がぼけているがご容赦願いたい。行路はa〜o地点、例によって更なる逸脱はs地点。今回のs地点(要するに夜通し連中の拠点)は三つ目の市である多摩市は聖蹟桜ヶ丘である。
【a地点以前】(私事も含む、参加者の()内は参加度数)
国分寺駅南口に集合ということで、参加者のほとんどは遠方の地であったに違いない。ぼくもそうでわざわざ面倒臭い乗り継ぎで(南武線<武蔵溝の口〜府中本町>→武蔵野線<府中本町〜西国分寺>→中央線<西国分寺〜国分寺>)出かけた。地図作りで早朝に寝たため寝不足で途上の車内で寝ながら揺られようと思うが、乗り馴れない列車の風景に見いって寝つけず11時頃辿り着き、ドトールなき国分寺はコロラドでエスプレッソを飲みつつ、銘々を待つこととする。
(国分寺駅といえば南口)
http://
(スタ丼の店が南口にある)
http://
待ち合わせ場所は駅南口だが改札口で待つこと10分。まかしょさん(初)に、dropさん(初)に、高山学派のショードヴァルさん(2)、スズチューさん(2)が続いてあらわる。今昨次郎くんも到着していた模様で、南口で有さん(初)、それいゆ*さんと待っていると、背後から近づいてきたのがkannさん(初)の総勢9名で活動開始。
【a地点】〔11:45-12:40〕(本町2丁目)
腹ごしらえに北口のカレー屋(名前は忘れた)でランチを食べる。大きめのナンにカレー、サラダ、ドリンクがついて千円はしなかったと思う。味はほどほど。dropさんは『魁男塾』全巻を持っているのだが、処分したいという。スズチューさんは購入したいそうだから、譲ってもらったらどうだろう。男連中は少年漫画の話を何故だかし始める。
【b地点】〔12:51-13:30〕(南町2丁目16番地)
南口駅ビルから左手を進んで右手に程なく「東京都立殿ヶ谷戸庭園」(国分寺市南町2丁目16番地)が見えてくる。
(東京都立殿ヶ谷戸庭園)
http://
(あるくかい、庭園入場)
http://
(園内地図)
http://
(入り口の縁起もの盆栽?)
http://
拝観料は大人150円。入場受付に大きく書かれた「admission fee(有料)」を「admission free(無料)」と誰かが読み違えそうになる。庭園の敷地はさほど広くなく、都市のなかにひっそりとある自然地帯が心地よい。園内の草木は武蔵野の野草が植えられている。植物に明るくないので大部省略するが、ぼくは「ホタルブクロ」が見たかった。子供の頃によんだ絵本『大きな一年生と小さな二年生』(古田足日 作、中山正美 絵、偕成社)に出てくる大柄だが気弱な男の子(1年生)が男気勝る年長のおちびな女の子を喜ばせたい一心に、雑草生い茂る近所の山地を短パンでもぐるように歩き、傷だらけになりながら崖のたもとでホタルブクロを採取してくる経験が、彼の心身の成長を促す「ビルドゥンスク・ロマン」(教養小説)の風合いであった。途中少年が近所のおばさんからのどの渇きにと差し入れてくれた濃厚なカルピスに、唾を飲みながら読んだ記憶がある。
(園内をあるく)
http://
http://
ショードヴァルさんは地元の伊豆の景観とほどよく似ていると言っていた。起伏に富んでいるのは段丘崖の地形を庭園としているからで、園内の「次郎弁天池」の湧き水は「国分寺崖線」(通称「ハケ」といって、表土の下には、立川ローム層、武蔵野ローム層、武蔵野礫層の三層から成り、最下層に雨水が蓄えられ、湧き水をもたらしている。)のそれで、「野川」の水源の一部となっている。
(次郎弁天池を見下ろす)
http://
「馬頭(ばとう)観音」というくねくねうねった小径は、蛇の尾か蛇の頭のような渦巻きに思われた。江戸末期の国分寺には旅の安全を祈願した馬頭観音があったそうだ。馬が農耕だけではなく街道をゆく物資運搬の役割を担っていた。
(馬頭観音の立て札)
http://
(草木に紛れて石臼が?)
http://
紅葉亭という武家造り(今昨次郎曰く)の建物は庭園を望む見晴らし台の和風家屋(茶室だそうだ)と、洋風の内装を併せもつ質朴な雰囲気を醸しだしている。洋風部分の、広い食卓のある静謐な空間にいながら目に綾な山水が、勉強会やお茶を飲むのにうってつけなところである。三菱財閥岩崎彦弥太氏の別邸だった。
退園間際にふいに見つけた重厚な倉庫らしき建物は関係者以外立ち入り禁止であったが、たまたま開錠されていて今くん、それいゆ*さんが覗き見のために入っていって戻ってこない?Bdropくんが門番さながら見張るなか、ぼくもミイラ取りのミイラよろしく少しばかり覗かせてもらう。
(倉庫と門番)
http://
(倉庫内の作業部屋?)
http://
【c地点】〔13:30-14:05〕(南町3丁目〜西元町3丁目〜泉町二丁目)
(庭園を後にしたぼくらは、南町3丁目の緩やかな坂道をくだりふたたび勾配を上った)
http://
のぼり着いた丘の左手には、「都立武蔵国分寺公園」(国分寺市泉2丁目)のなだらかな平地が広がっていて、みんな嬉々として吸い寄せられていく。
(都立武蔵国分寺公園)
http://
(公園のトイレ建物)
http://
高台ということもあって「富士見」の丘としても有名な(「関東の富士山百景」に選出)公園だそうだが、もともと旧国鉄精算事業団用地として更地だった場所(「中央鉄道学園」跡地、民営化に伴い1987年閉鎖。教習用車輛などがあった)で、平成14年開園だからまだ日が浅い。郊外らしく西国分寺方面には高層住宅団地が建ち並び、ぐるりを周回していると、わずかながら走行する中央線のオレンジ車輛が垣間見られた。国分寺の「武蔵野」のイメージというよりは、国立方面に連なる郊外の人工的印象の強く残る土地だった。
余談だが、中央線を越えた国分寺の北口方面には、あの「イエスの方舟」事件で話題となった場所があることを付け加えておこう。(日吉町1丁目39番地)「イエスの方舟」事件とは、千石剛賢、通称「オッチャン」が1960(昭和35)年国分寺市恋ケ窪につくった「極東キリスト集会」(のちに「イエスの方舟」と改称)と銘打った10人ほどの聖書研究会がもとで、1970(昭45)年には、聖書を通じて家族となった26名ほどの女性が、内藤橋派出所の隣にテント小屋をつくって共同生活が営まれた。「イエスの方舟」は、ハーレムというレッテルをマスコミに貼られ、追われるようにして漂流し現在も続いているらしい。方舟の女性たちは女給となったそうだが、最近逮捕された囲い妻の占い師の件とは訳が違うだろう。
(藤棚)
http://
(高層住宅団地)
http://
http://
そんなことはお構いなく、運動不足の院生、勤め人の銘々は、今くんが下見の際府中はトイザラスで購入した腑抜けた球でキャッチボールに興じ、陽光を浴びて休日をエンジョイしていた。キャッチボールが出来るとは思わなかったと、dropさん、まかしょさんなど皆喜んでいた。今くんはへぼ肩だった。
(郊外広場のキャッチボール大会)
http://
【c-d地点】〔14:05-14:25〕(泉町1丁目〜西元町1丁目)
体をほどよく(?)動かしたあと、「お鷹の道」へと向かう。坂の階段に差しかかる原っぱは「the 武蔵野」といった光景。
(the武蔵野)
http://
(坂階段からお鷹の道へ)
http://
階段を降りきったすぐひだり脇には「真姿(ますがた)の池湧水群」といわれて、環境庁の「名水百選」に選定されるような清水が流れ、水汲人もいるほどだ。848(嘉祥元)年不治の癩病で醜くなった玉造小町という美女が、国分寺に21日ほど平癒祈願に参詣しているとひとりの童子があらわれ、「この池にて洗うべし」と告げられ、勧められたとおりに洗うと7日ほどでもとの美しい「真姿」に戻ったという全治三週間のめでたき話。そういえば、傷を癒しているのかただ羽を休らっているのか知れぬが、一羽の鳩も清水に浸かってじっとうずくまっていた。
(真姿の池湧水群とお鷹の道)
http://
http://
(清水に浸かるおとなしい鳩)
http://
清水だから野菜もよく育つとあって、ここ国分寺には個人農家がこさえた野菜の直売所がいくつも分布している。ここお鷹の道にも「本多俊一さん直売所」があって、近郊ならではの贅沢な自然と共生がはかれるというものである。この清き流れに誘われてか、蛍もあらわれることが立て札に記されていた。
(本多俊一さん直売所)
http://
(本多さん家)
http://
たまたまkannさんとの話にのぼっていた世田谷の等々力渓谷とこの一帯の趣きが著しく似ているとぼくは感じたのだがそれもそのはず。ハケは小金井、三鷹、調布、狛江と市を貫きながら、成城学園、二子玉川、等々力などの世田谷へと連なっているのである。
お鷹の道一帯は、「本多さん家」の家屋が軒を並べている。江戸時代に尾張徳川家の御鷹場があったこの一帯で、本多家が由緒正しき家柄の名士であることは間違いない。詳しいことは知らないが、国分寺市には「本多」という町名さえある。
【d地点】〔14:25-14:50〕(西元町1丁目13番地)
本多家の敷地内の小径を練り歩いていくと、現在の「武蔵国分寺」と、その楼門が見えてくる。楼門に掲げられた木板に書かれた墨字を「あいだみつを」か何かですか、とショードヴァルさんがとぼける。そんな筈もなく弘法大師の筆によるものだ。
(現在の武蔵国分寺)
http://
(武蔵国分寺楼門)
http://
(楼門の弘法大師の筆文)
http://
楼門の建物などを見ながら今くんの、国分寺というネットワーク・システムについての説明が開陳される(女子はあまり聞いていなそうだ)。東大寺という総国分寺を中心にした仏教のネットワークの各端末が全国に散らばる国分寺(国分僧寺・国分尼寺)で、日時を決めて一斉に同じ経典を読んでいることを想像したら、すごい光景である。天平13(741)年3月24日の詔(『続日本紀』)によれば、聖武天皇(701〜756、第45代)がこの詔を発せられるに到った動機は、当時流行した天然痘(朝鮮半島から九州に入り全国に蔓延したらしい)と飢饉から国や国民を護るべく、国分寺が建立されたのだそうだ。当時の武蔵国分寺は東西880メートル、南北550メートルの広大な敷地に20年余の歳月をかけて国分僧寺と国分尼寺が完成したものだ。国分寺墓地をしり目に歩いていくとすぐ、国分寺史跡の公園が広がっている。
(国分寺墓地)
http://
(武蔵国分寺跡)
http://
今くんやそれいゆ*さんらは枯れ芝のうえをマフラーなんかが絡むのもお構いなく、寝転がって空を仰いでいる。歴史のロマンに思いを馳せるといったところ。思わず呟いていた「雲一つない」(kannさん)澄み渡る青空と木々のコントラストが、どこかで見たような写真で、今となって思い出したのだが、おセンチな文章が添えられた辻仁成の『ここにいないあなたへ』(写真=安珠、集英社)だった。(何であんな本買ったのだろう)お粗末。
(澄み渡る紺碧の空)
http://
(『ここにいないあなたへ』の写真)
http://
【d-e地点】〔14:50-15:10〕(国分寺市西元町2・3丁目〜府中市栄町3丁目)
国分寺跡の向かいは平坦な民家が建ち並ぶ一帯。区画整理されたごく普通の住宅地といった印象で、低い苗木が丈を並べた畑がところどころ鉤裂きのように現れる(たぶん植木屋が庭木のために栽培しているのだろう)。京王線に乗って都心から離れていくとき、車窓を流れる調布や府中の一帯みたく桑畑と民家の組合せから成るそんな光景を想像してみれば事足りる。分倍河原によく似たこの場所が府中市に接近していることを知らせてくれる。国分寺のあまやかな風土から遠ざかっていくことをにわかに感じる。
(幻想的な?植林地)
http://
府中市の公道を歩いていると目につくのが、鉄のゴミ収集箱。カラスも立ち入れない頑丈な造りになっていて、少々大きめだが何時でもゴミを出せるから住民には便利である。
(府中市のゴミ箱)
http://
「東八道路」の大通りを横断し(右手を見遣れば所沢方面に通ずる交通表示が。東武東上線から見えてくる埼玉県の入り口の景観を彷彿とさせる)、「府中第九小学校」の校庭脇を練り歩くと(「こんにちわ!」という元気のよい小学生のかけ声あり)、「学園通り」にさしかかる。目の前にはあまりにも白い「府中刑務所」の塀が向かい手に立ちはだかっている。塀の向かいは第九小学校や府中高校が面している。(こんなところに学び舎があるなんて!)
(学園通りの府中刑務所の塀)
http://
【e地点】〔15:10-15:20〕(栄町3丁目)
今くんが下調べした歩道橋から刑務所の内部を覗き見する。歩道橋を覆うプラスチック板の隙き間から少しばかり所内の様子を窺うことができる。通りのガラス張りのビルにも刑務所の外観が反映されている。府中街道を遠くに見ながら、東芝府中工場を見れなかったのは少し残念に思う。もちろん府中刑務所と東芝府中を結びつけるのは、かの有名な「3億円強奪事件」である。昭和43(1968)年府中刑務所の横で、東芝府中のボーナス3億円を積んだ日本信託銀行国分寺支店の現金輸送車に白バイの警官男が近づき、爆弾が仕掛けられているから降りろと警告。点検するふりをしながら発煙筒をたいた男はそのまま輸送車に乗りこんで逃げ果せた事件だ。(府中刑務所とはたとえば、戦後魔もない昭和20年に徳田球一ら政治犯が移送された場所である)そんなことを思い浮かべながら周囲を眺めてみる。府中刑務所開所は昭和10(1935)年のこと、昭和12年の日中戦争がはじまって、受刑者は仮釈放扱いで応召がはじまり、13(1938)年の総動員法で全国の受刑者の労働力は軍事施設の設営に一役買うことになる。(危険な仕事にすすんで従事させられたということである)東芝府中工場が府中刑務所の向かいにできたのは昭和15(1940)年のこと。年を追うごとにやはり受刑者を労働力として受け入れている。(労働力の不足から朝鮮人や台湾人の労働者も募っている)19年の戦時には軍需会社に指定されて年の終りには5千人以上に膨れ上がる大工場だった。
(府中刑務所を覗き見る)
http://
http://
http://
「学園通り」の府中刑務所の塀は美的景観を認定された銘が途中で掲示されていて、銘々「えぇ〜」という驚きの一声。舗装された歩道にはわずかばかりの下草が顔を覗かせているだけの、真っ白な一直線の壁面通りにすぎないが、確かに不思議なほど真っ白で不潔な印象はまったくない。内部の印象が外に溢れださないという一点で評価されたのかもわからない。
【e-f地点】〔15:20-15:50〕(栄町3・2丁目〜晴見町4・3・1丁目〜寿町1丁目〜府中町1丁目)
広大な府中刑務所の一角に辿り着き、少し佇む。ただ呆然とするしかない空虚さに浸されている。壁の向かいにはお構いなく住宅が軒を並べている。2階立ての家屋ばかりで高さはないが、ベランダから刑務所の内部を毎日覗く気分はどんなものだろう。ビル刑務所の前だと少し土地が安いのかなとまかしょくんが呟く。すき好んでこんなところに住みたいとは思わないだろうけど、静けさは保証されているような場所である。
(府中刑務所の一角から)
http://
塀に沿ってひたすら歩いていくと、府中刑務所の入り口門にさしかかる。門の近くには刑務所前郵便局のATMボックスがある。門から続く大きな通りは大学構内のように両脇に銀杏並木に縁取られていた。刑務所の塀の向かいの住宅地は所員の刑務所官舎である。
(府中刑務所入り口)
http://
しばらくすると、町の小さな賑わいが聞こえてきそうな商店街らしき色合いが目にちらつき始める。町の匂いが再び訪うと思い少し安堵する。が、くたびれた商店街で、住宅地の内部に突然現われたひょろ長い商店の連なりに戸惑いながら歩く。廃墟3秒前だな、という失礼な今君のコメントに苦笑して眺めていると突如、大きな団地が右手に見えてくる。そうか、団地に併せてつくられた商店街なんだなあと納得する。団地族に夢見る心地が巣食っていたのはいつの世ぞ。団地も番地も同じく「晴見」という名前が冠されている。
(晴見町の晴見団地)
http://
「晴見団地」という名前負けした公営団地を過ぎると、府中駅に続く雑踏がさらに安堵感をもたらしてくれて気が逸る。国分寺跡からまったくコーヒーブレイクをいれていなかったうえ、初参加組の疲労度合もさすがに気にかかるところ。「結構疲れた」(まかしょくん)、「疲れた」(スズチューさん、ショードヴァルさん)「全然平気」(kannさん)など意見もまちまちだが、何キロ歩いたかなあという疑問とも文句ともつかぬ言葉が口を出るということは、疲れが見え始めている証拠なのだろう。ようやく府中市街に入り、桜通りにある水出し珈琲、アメリカンワッフルと銘打った喫茶店「おらんだ屋」(府中町1-25-9)でひと休み。アメリカン・ワッフルとはモロンバンのワッフルでも、ベルギーワッフルでもなく、マンホールのような四角いでこぼこ穴の平らなまん丸ワッフルで、フォークとナイフで切り分けて食べるタイプ。果汁シロップや生クリームのかかった温かいワッフルが紅茶や珈琲にうってつけである。水出し珈琲というのでちょっと期待し過ぎたが、まあ美味しい部類に入るか。
(おらんだ屋)
http://
【h地点】〔17:05-17:15〕(府中町2丁目20番地)
おらんだ屋で優に1時間ほどゆっくりと過ごしたあと、用事でdropくんと別れ(お疲れさまでした)、次なる地へ向かう途中、ついつい足止めを進んでしてしまう。そう古本やである。「古書 夢の絵本堂」(府中町2-20-13-105)という小さな町の文房具屋さんのような趣きの店は、小振りながら外国の絵本や洋書、文学やエンタメ、雑誌まで程よく並べられていたと思う。それいゆ*さんはドイツ・リアリズム(だったか)絵画の図録、ショードヴァルさんは漫画に関する文庫本、ぼくは『文芸雑誌 海』のバックナンバーを購入した。あるくかいは古本覗きは暗黙の禁止だったのはいつの頃だったろうか。
(夢の絵本堂)
http://
【h-i地点】〔17:15-17:30〕(府中町2・3丁目〜緑町1・2丁目〜浅間町1丁目)
薄暗くなってきて、急に足取りが早くなっていくのはぼくの性。暗さが増すと目標物が見えなくなってくるのと、日が暮れたら帰るという律儀な習慣を持つ人もたぶんいるからだ。今くんが下見をしたとはいえ、不案内であることに変わりはなく、信用ならないので先頭きって歩く。が、やはりみんなペースをまもってゆっくり歩く。「小金井街道」を横断し、知らず知らずのうちに10メートルくらい離れながら(多分また始まったというようなうすら笑いを浮かべて後背から窺っているのだろう)、メンバーを導く。角に差しかかっては振り返ってみんなの位置を確認し、ようやく「府中の森公園」の入り口に辿り着いた。公園の真上にはきれいな、月がでていた。
(月がでていた)
http://
【j地点】〔17:35-17:40〕(浅間町1丁目)
公園の立て札に不審者注意の呼びかけ(kannさん思わず身構える)もそっちのけで、次なる目的地を目指す。公園の自然に「武蔵野」(今くん)を見いだす者もいるが、ぼくは広々した公園に「光が丘公園」のような不穏な空気を感じていた。公園の記念碑の建つ噴水の広場で少しばかり佇む。有さんが歳を感じると言いながら、静かにベンチで一服している。
(府中の森の記念碑と噴水)
http://
【k地点】〔17:40-55〕(浅間町1丁目)
首都にほど近い府中市など多摩地区は、平坦で広大な土地を利用した軍事施設が明治以降造営されていった。府中にはこうした旧在日米空軍基地の廃墟が今もあり、その痕跡を消すかのように府中の森公園という平和公園ができているのだが、いまだ拭いされない不気味さがそこはかとなく漂っている。以前に訪ねた多摩霊園も暗闇のなかを練り歩いて気味が悪かったが、「航空自衛隊府中基地」もフェンスに遮蔽されて内部を歩くことはかなわないだけに、少年の冒険心がフェンス越しにのぞけ、彼方への羨望で食入るように見つめた。夜になってしまったのではっきり見通せないのだが、倉庫が建ち並び、生い茂る薮のなかをきれいに隈どられた白い道は、大型車が行き来したように踏みならされているのだろう。青黒い闇のなかで基地跡の風景は白く靄がかかっていて、亡霊が建物から気となって立ち上ってくるようだった。ゴシック・ロマンスではないが怖いもの見たさとぞくぞくする思いが先行する。スティーブン・キングの小説の風景のようであった。写真に収められなかったのが残念である。
(航空自衛隊府中基地)
http://
【l地点】〔17:55-18:05〕(浅間町1丁目)
「陸軍燃料廠(しょう)府中米軍基地跡」をやはりフェンス越しに眺める。昭和14(1939)年燃料や潤滑油確保のために建設された工場だが、敗戦とともに占領軍の司令部が置かれることになった場所である。ここはまさに廃墟の相を呈していて、ひび割れた窓や、窓枠から赤錆が壁に滲み垂れていて、綻びながらじっと建っているよりほかない運めを自認するような建築物だった。
(陸軍燃料廠府中米軍基地跡)
http://
http://
【l-m地点】〔18:10-18:25〕(浅間町1丁目〜緑町2・1丁目〜府中町2丁目)
kannさん、スズチューさんが用事のため、府中駅を目指して歩く。府中駅構内で見送ったあと(お疲れさまでした)、最後の砦へ急ぐ。
【n地点】〔18:25-18:30〕(宮町1丁目)
伊勢丹でトイレ休憩をする。トイレ近くのベンチでみな腰かけるが、ショードヴァルさんは座るとまた辛くなるので立ったままだ。疲れましたかと声をかけると、そんなことはないが太腿がという答えに随分無理な歩きを強いているのかも知れないと心配になる。最終地点まで目と鼻の先なのでもう少しの辛抱を。戦後、京王府中駅南口には「府中マーケット」が朝鮮人の手にかかって勃興した。府中の闇市には「パンパン」(売春婦の謂)がたむろし、新宿からチンピラも集まってきて、「コロニアルな原色的雰囲気の漂うギンギンのイメージ」(西井一夫)だったそうだ。新宿内藤町の遊郭のネットワークも、京王線が並走する甲州街道を通じていたといえる。この府中のイメージに府中競馬の賭博が加わることも必至だったのであろう。「府中宿」というだけあって、東西の甲州街道、南北の3つの縦線、すなわち武蔵野線が一部並走する府中街道、国分寺駅から垂直下の国分寺街道、武蔵小金井からは小金井街道が集め来たる土地が府中にほかならない。街道があるということはさまざまなものが流れてくることは想像に難くない。
【o地点】〔18:30-18:45〕(宮町3丁目)
最後の砦は、「大国魂神社」である。すっかり暗くなった神社だが、「くらやみ祭り」に相応しいと勝手に決めこみながら参拝に向かう。
(大國魂神社大鳥居)
http://
(大国魂神社中雀門)
http://
http://
府中という地名は701(大宝元)年、大陸は中国の唐にならった大宝律令に定められて、国司が配置され、国司の政庁が置かれたところが国府と呼ばれるようになる。この国府の中心という意味から「府中」と呼ばれるようになったといわれる。府中は全国にも名を留めているが(たとえば広島には府中市や安芸郡府中町が存在する)、重要なのは府中のそばには国分寺が必ずといってよいほど建設されたことである。ここ東京の府中は武蔵国の国府が設営されたのである。国分寺が府中と接していることも必然の理だったのである。国分寺に比べて府中がほの暗い印象を齎すのは、昭和という激動の時代に依っているのかも知れない。「くらやみ祭り」(大国魂神社例大祭)は深夜から早朝にかけて行われたそうだが(30年前まで)、神様を見ると目がつぶれるという敬意からくるものだといわれる。「国土安穏と五穀豊穣を祈る祭礼」で古代の国府祭として始まり、全国の神職が集まって祈願したものだそうだ。ありとあらゆる灯火が消された闇夜のさなか神輿が出御し、そのかざりの揺れ音だけが通行を知らせるほど静かなものだったらしく、文字通りくらやみを現出させていたのだ。深い鎮守の森のような大国魂神社の境内の暗がりから市街を眺むれば、現在の府中駅前のキラキラした人工灯の示す繁栄ぶりは、もはやくらやみが不可能だと突きつけんばかりであるが、それに抗うよう神社の闇は永きにわたって保存され続けてきたように思われる。府中の駅前の繁華街はやはり覆い隠せてはいまい。京王線の高架ホームを軸にしたペデストリアンデッキ(横断歩道橋)によって、商店街やデパートと連結させた合理的商業システムの明るさも、傘下である地上の端々に暗がりを忍びこませ、潜ませているように思われてならない。その闇が古代から続く大国魂神社のくらやみに出来していると勝手に想像してみると、府中のほの暗さも何となく得心がゆく。
【p地点】〔19:00-21:30〕(宮西町1-2-1)
「かまどか」というチェーンの居酒屋で酒を呑む。府中なのに席につくのに少し待たされて、みな納得がゆかない様子。今回あるくことで得た町の表情や疲れなんかをビールや日本酒の力を借りてテーブルの上で綯い交ぜにしながら、あれやこれやと延々と話す。途中ショードヴァルさんが用事で抜ける(本当にお疲れさまでした)。
【s地点】〔21:45以降〕(多摩市桜ヶ丘1丁目〜関戸2丁目〜一ノ宮2丁目)
m_w_oxygenくんが府中にやってきたことをよいことに、再び酒を飲もうと誘って、府中を後にすることに決める。有さんが都心へと家路を急ぐ(お疲れさまでした)のに対し、ぼくらはさらに西へと京王線に乗って多摩川を越え、府中市から多摩市へと移動。「聖蹟桜ヶ丘駅」に到着。それいゆ*さん、まかしょさんはあの「耳をすませば」を観ていながら舞台地を訪ね歩いたことがないだけに、少しあのくねくね坂を見せてやりたいと思う。今くんやoxygenくんはあまり遠くまで行きたくないと懸念。南口を出て「川崎街道」を渡って少し歩けば(途中スターバックスでぼくとoxygenくんは珈琲を買った、渋る今くんのためにバニラクリームフラペチーノを買ってやる)、「大栗川」にかかる「霞ヶ関橋」にさしかかり、もうあの坂道「いろは坂」が迎えてくれる。初心者の二人組は途中嬉々としてどんどん先に進んでいってしまい、見失って坂道の途中まで上って探すはめになった。(結局坂下で待っていたのであったが)駅前に戻って、それいゆ*さんと別れて男4人でやきとり屋で朝の4時まで語らいあった(すみません、店名忘れました)。庶民的ながら味もよく、値段も良心的というほかなく、この辺に来たらまた一杯やりたい。あるくかいにとっての重要な話も出来た大変生産的な場になった。oxygenくんがうとうとしてきたこともあってここで夜を明かすのもなにかと、ファミレスを目指して川崎街道をボール蹴りしながら歩き、ジョナサンで珈琲を飲んで帰宅の準備をする。みんな眠さでバカバカしいことを言いながら談笑(味噌汁セットにライスやパンをつけるだの、それをお前が頼めだの)。結局聖蹟桜ヶ丘で分倍河原までの上りの各駅停車を待合室で待ちながら(トイレの近いoxygenくんが途中いなくなり、急行を一本遅らせる)、まかしょくんは中央線に接続するために南武線で立川へ、ぼくらは南武線で川崎方面へ向かった。京王線のリュックの迷惑な乗客のポスターがoxygenくんに酷似していた。
(国分寺・府中あるくかい地図)
http://
(国分寺のほう)
http://
(府中のほう)
http://
ただし見づらいため、カズキさんの方式に倣い、自分もやってみるが、アドビのソフトもなくやっとできたのがトップ写真左の地図。下方がぼけているがご容赦願いたい。行路はa〜o地点、例によって更なる逸脱はs地点。今回のs地点(要するに夜通し連中の拠点)は三つ目の市である多摩市は聖蹟桜ヶ丘である。
【a地点以前】(私事も含む、参加者の()内は参加度数)
国分寺駅南口に集合ということで、参加者のほとんどは遠方の地であったに違いない。ぼくもそうでわざわざ面倒臭い乗り継ぎで(南武線<武蔵溝の口〜府中本町>→武蔵野線<府中本町〜西国分寺>→中央線<西国分寺〜国分寺>)出かけた。地図作りで早朝に寝たため寝不足で途上の車内で寝ながら揺られようと思うが、乗り馴れない列車の風景に見いって寝つけず11時頃辿り着き、ドトールなき国分寺はコロラドでエスプレッソを飲みつつ、銘々を待つこととする。
(国分寺駅といえば南口)
http://
(スタ丼の店が南口にある)
http://
待ち合わせ場所は駅南口だが改札口で待つこと10分。まかしょさん(初)に、dropさん(初)に、高山学派のショードヴァルさん(2)、スズチューさん(2)が続いてあらわる。今昨次郎くんも到着していた模様で、南口で有さん(初)、それいゆ*さんと待っていると、背後から近づいてきたのがkannさん(初)の総勢9名で活動開始。
【a地点】〔11:45-12:40〕(本町2丁目)
腹ごしらえに北口のカレー屋(名前は忘れた)でランチを食べる。大きめのナンにカレー、サラダ、ドリンクがついて千円はしなかったと思う。味はほどほど。dropさんは『魁男塾』全巻を持っているのだが、処分したいという。スズチューさんは購入したいそうだから、譲ってもらったらどうだろう。男連中は少年漫画の話を何故だかし始める。
【b地点】〔12:51-13:30〕(南町2丁目16番地)
南口駅ビルから左手を進んで右手に程なく「東京都立殿ヶ谷戸庭園」(国分寺市南町2丁目16番地)が見えてくる。
(東京都立殿ヶ谷戸庭園)
http://
(あるくかい、庭園入場)
http://
(園内地図)
http://
(入り口の縁起もの盆栽?)
http://
拝観料は大人150円。入場受付に大きく書かれた「admission fee(有料)」を「admission free(無料)」と誰かが読み違えそうになる。庭園の敷地はさほど広くなく、都市のなかにひっそりとある自然地帯が心地よい。園内の草木は武蔵野の野草が植えられている。植物に明るくないので大部省略するが、ぼくは「ホタルブクロ」が見たかった。子供の頃によんだ絵本『大きな一年生と小さな二年生』(古田足日 作、中山正美 絵、偕成社)に出てくる大柄だが気弱な男の子(1年生)が男気勝る年長のおちびな女の子を喜ばせたい一心に、雑草生い茂る近所の山地を短パンでもぐるように歩き、傷だらけになりながら崖のたもとでホタルブクロを採取してくる経験が、彼の心身の成長を促す「ビルドゥンスク・ロマン」(教養小説)の風合いであった。途中少年が近所のおばさんからのどの渇きにと差し入れてくれた濃厚なカルピスに、唾を飲みながら読んだ記憶がある。
(園内をあるく)
http://
http://
ショードヴァルさんは地元の伊豆の景観とほどよく似ていると言っていた。起伏に富んでいるのは段丘崖の地形を庭園としているからで、園内の「次郎弁天池」の湧き水は「国分寺崖線」(通称「ハケ」といって、表土の下には、立川ローム層、武蔵野ローム層、武蔵野礫層の三層から成り、最下層に雨水が蓄えられ、湧き水をもたらしている。)のそれで、「野川」の水源の一部となっている。
(次郎弁天池を見下ろす)
http://
「馬頭(ばとう)観音」というくねくねうねった小径は、蛇の尾か蛇の頭のような渦巻きに思われた。江戸末期の国分寺には旅の安全を祈願した馬頭観音があったそうだ。馬が農耕だけではなく街道をゆく物資運搬の役割を担っていた。
(馬頭観音の立て札)
http://
(草木に紛れて石臼が?)
http://
紅葉亭という武家造り(今昨次郎曰く)の建物は庭園を望む見晴らし台の和風家屋(茶室だそうだ)と、洋風の内装を併せもつ質朴な雰囲気を醸しだしている。洋風部分の、広い食卓のある静謐な空間にいながら目に綾な山水が、勉強会やお茶を飲むのにうってつけなところである。三菱財閥岩崎彦弥太氏の別邸だった。
退園間際にふいに見つけた重厚な倉庫らしき建物は関係者以外立ち入り禁止であったが、たまたま開錠されていて今くん、それいゆ*さんが覗き見のために入っていって戻ってこない?Bdropくんが門番さながら見張るなか、ぼくもミイラ取りのミイラよろしく少しばかり覗かせてもらう。
(倉庫と門番)
http://
(倉庫内の作業部屋?)
http://
【c地点】〔13:30-14:05〕(南町3丁目〜西元町3丁目〜泉町二丁目)
(庭園を後にしたぼくらは、南町3丁目の緩やかな坂道をくだりふたたび勾配を上った)
http://
のぼり着いた丘の左手には、「都立武蔵国分寺公園」(国分寺市泉2丁目)のなだらかな平地が広がっていて、みんな嬉々として吸い寄せられていく。
(都立武蔵国分寺公園)
http://
(公園のトイレ建物)
http://
高台ということもあって「富士見」の丘としても有名な(「関東の富士山百景」に選出)公園だそうだが、もともと旧国鉄精算事業団用地として更地だった場所(「中央鉄道学園」跡地、民営化に伴い1987年閉鎖。教習用車輛などがあった)で、平成14年開園だからまだ日が浅い。郊外らしく西国分寺方面には高層住宅団地が建ち並び、ぐるりを周回していると、わずかながら走行する中央線のオレンジ車輛が垣間見られた。国分寺の「武蔵野」のイメージというよりは、国立方面に連なる郊外の人工的印象の強く残る土地だった。
余談だが、中央線を越えた国分寺の北口方面には、あの「イエスの方舟」事件で話題となった場所があることを付け加えておこう。(日吉町1丁目39番地)「イエスの方舟」事件とは、千石剛賢、通称「オッチャン」が1960(昭和35)年国分寺市恋ケ窪につくった「極東キリスト集会」(のちに「イエスの方舟」と改称)と銘打った10人ほどの聖書研究会がもとで、1970(昭45)年には、聖書を通じて家族となった26名ほどの女性が、内藤橋派出所の隣にテント小屋をつくって共同生活が営まれた。「イエスの方舟」は、ハーレムというレッテルをマスコミに貼られ、追われるようにして漂流し現在も続いているらしい。方舟の女性たちは女給となったそうだが、最近逮捕された囲い妻の占い師の件とは訳が違うだろう。
(藤棚)
http://
(高層住宅団地)
http://
http://
そんなことはお構いなく、運動不足の院生、勤め人の銘々は、今くんが下見の際府中はトイザラスで購入した腑抜けた球でキャッチボールに興じ、陽光を浴びて休日をエンジョイしていた。キャッチボールが出来るとは思わなかったと、dropさん、まかしょさんなど皆喜んでいた。今くんはへぼ肩だった。
(郊外広場のキャッチボール大会)
http://
【c-d地点】〔14:05-14:25〕(泉町1丁目〜西元町1丁目)
体をほどよく(?)動かしたあと、「お鷹の道」へと向かう。坂の階段に差しかかる原っぱは「the 武蔵野」といった光景。
(the武蔵野)
http://
(坂階段からお鷹の道へ)
http://
階段を降りきったすぐひだり脇には「真姿(ますがた)の池湧水群」といわれて、環境庁の「名水百選」に選定されるような清水が流れ、水汲人もいるほどだ。848(嘉祥元)年不治の癩病で醜くなった玉造小町という美女が、国分寺に21日ほど平癒祈願に参詣しているとひとりの童子があらわれ、「この池にて洗うべし」と告げられ、勧められたとおりに洗うと7日ほどでもとの美しい「真姿」に戻ったという全治三週間のめでたき話。そういえば、傷を癒しているのかただ羽を休らっているのか知れぬが、一羽の鳩も清水に浸かってじっとうずくまっていた。
(真姿の池湧水群とお鷹の道)
http://
http://
(清水に浸かるおとなしい鳩)
http://
清水だから野菜もよく育つとあって、ここ国分寺には個人農家がこさえた野菜の直売所がいくつも分布している。ここお鷹の道にも「本多俊一さん直売所」があって、近郊ならではの贅沢な自然と共生がはかれるというものである。この清き流れに誘われてか、蛍もあらわれることが立て札に記されていた。
(本多俊一さん直売所)
http://
(本多さん家)
http://
たまたまkannさんとの話にのぼっていた世田谷の等々力渓谷とこの一帯の趣きが著しく似ているとぼくは感じたのだがそれもそのはず。ハケは小金井、三鷹、調布、狛江と市を貫きながら、成城学園、二子玉川、等々力などの世田谷へと連なっているのである。
お鷹の道一帯は、「本多さん家」の家屋が軒を並べている。江戸時代に尾張徳川家の御鷹場があったこの一帯で、本多家が由緒正しき家柄の名士であることは間違いない。詳しいことは知らないが、国分寺市には「本多」という町名さえある。
【d地点】〔14:25-14:50〕(西元町1丁目13番地)
本多家の敷地内の小径を練り歩いていくと、現在の「武蔵国分寺」と、その楼門が見えてくる。楼門に掲げられた木板に書かれた墨字を「あいだみつを」か何かですか、とショードヴァルさんがとぼける。そんな筈もなく弘法大師の筆によるものだ。
(現在の武蔵国分寺)
http://
(武蔵国分寺楼門)
http://
(楼門の弘法大師の筆文)
http://
楼門の建物などを見ながら今くんの、国分寺というネットワーク・システムについての説明が開陳される(女子はあまり聞いていなそうだ)。東大寺という総国分寺を中心にした仏教のネットワークの各端末が全国に散らばる国分寺(国分僧寺・国分尼寺)で、日時を決めて一斉に同じ経典を読んでいることを想像したら、すごい光景である。天平13(741)年3月24日の詔(『続日本紀』)によれば、聖武天皇(701〜756、第45代)がこの詔を発せられるに到った動機は、当時流行した天然痘(朝鮮半島から九州に入り全国に蔓延したらしい)と飢饉から国や国民を護るべく、国分寺が建立されたのだそうだ。当時の武蔵国分寺は東西880メートル、南北550メートルの広大な敷地に20年余の歳月をかけて国分僧寺と国分尼寺が完成したものだ。国分寺墓地をしり目に歩いていくとすぐ、国分寺史跡の公園が広がっている。
(国分寺墓地)
http://
(武蔵国分寺跡)
http://
今くんやそれいゆ*さんらは枯れ芝のうえをマフラーなんかが絡むのもお構いなく、寝転がって空を仰いでいる。歴史のロマンに思いを馳せるといったところ。思わず呟いていた「雲一つない」(kannさん)澄み渡る青空と木々のコントラストが、どこかで見たような写真で、今となって思い出したのだが、おセンチな文章が添えられた辻仁成の『ここにいないあなたへ』(写真=安珠、集英社)だった。(何であんな本買ったのだろう)お粗末。
(澄み渡る紺碧の空)
http://
(『ここにいないあなたへ』の写真)
http://
【d-e地点】〔14:50-15:10〕(国分寺市西元町2・3丁目〜府中市栄町3丁目)
国分寺跡の向かいは平坦な民家が建ち並ぶ一帯。区画整理されたごく普通の住宅地といった印象で、低い苗木が丈を並べた畑がところどころ鉤裂きのように現れる(たぶん植木屋が庭木のために栽培しているのだろう)。京王線に乗って都心から離れていくとき、車窓を流れる調布や府中の一帯みたく桑畑と民家の組合せから成るそんな光景を想像してみれば事足りる。分倍河原によく似たこの場所が府中市に接近していることを知らせてくれる。国分寺のあまやかな風土から遠ざかっていくことをにわかに感じる。
(幻想的な?植林地)
http://
府中市の公道を歩いていると目につくのが、鉄のゴミ収集箱。カラスも立ち入れない頑丈な造りになっていて、少々大きめだが何時でもゴミを出せるから住民には便利である。
(府中市のゴミ箱)
http://
「東八道路」の大通りを横断し(右手を見遣れば所沢方面に通ずる交通表示が。東武東上線から見えてくる埼玉県の入り口の景観を彷彿とさせる)、「府中第九小学校」の校庭脇を練り歩くと(「こんにちわ!」という元気のよい小学生のかけ声あり)、「学園通り」にさしかかる。目の前にはあまりにも白い「府中刑務所」の塀が向かい手に立ちはだかっている。塀の向かいは第九小学校や府中高校が面している。(こんなところに学び舎があるなんて!)
(学園通りの府中刑務所の塀)
http://
【e地点】〔15:10-15:20〕(栄町3丁目)
今くんが下調べした歩道橋から刑務所の内部を覗き見する。歩道橋を覆うプラスチック板の隙き間から少しばかり所内の様子を窺うことができる。通りのガラス張りのビルにも刑務所の外観が反映されている。府中街道を遠くに見ながら、東芝府中工場を見れなかったのは少し残念に思う。もちろん府中刑務所と東芝府中を結びつけるのは、かの有名な「3億円強奪事件」である。昭和43(1968)年府中刑務所の横で、東芝府中のボーナス3億円を積んだ日本信託銀行国分寺支店の現金輸送車に白バイの警官男が近づき、爆弾が仕掛けられているから降りろと警告。点検するふりをしながら発煙筒をたいた男はそのまま輸送車に乗りこんで逃げ果せた事件だ。(府中刑務所とはたとえば、戦後魔もない昭和20年に徳田球一ら政治犯が移送された場所である)そんなことを思い浮かべながら周囲を眺めてみる。府中刑務所開所は昭和10(1935)年のこと、昭和12年の日中戦争がはじまって、受刑者は仮釈放扱いで応召がはじまり、13(1938)年の総動員法で全国の受刑者の労働力は軍事施設の設営に一役買うことになる。(危険な仕事にすすんで従事させられたということである)東芝府中工場が府中刑務所の向かいにできたのは昭和15(1940)年のこと。年を追うごとにやはり受刑者を労働力として受け入れている。(労働力の不足から朝鮮人や台湾人の労働者も募っている)19年の戦時には軍需会社に指定されて年の終りには5千人以上に膨れ上がる大工場だった。
(府中刑務所を覗き見る)
http://
http://
http://
「学園通り」の府中刑務所の塀は美的景観を認定された銘が途中で掲示されていて、銘々「えぇ〜」という驚きの一声。舗装された歩道にはわずかばかりの下草が顔を覗かせているだけの、真っ白な一直線の壁面通りにすぎないが、確かに不思議なほど真っ白で不潔な印象はまったくない。内部の印象が外に溢れださないという一点で評価されたのかもわからない。
【e-f地点】〔15:20-15:50〕(栄町3・2丁目〜晴見町4・3・1丁目〜寿町1丁目〜府中町1丁目)
広大な府中刑務所の一角に辿り着き、少し佇む。ただ呆然とするしかない空虚さに浸されている。壁の向かいにはお構いなく住宅が軒を並べている。2階立ての家屋ばかりで高さはないが、ベランダから刑務所の内部を毎日覗く気分はどんなものだろう。ビル刑務所の前だと少し土地が安いのかなとまかしょくんが呟く。すき好んでこんなところに住みたいとは思わないだろうけど、静けさは保証されているような場所である。
(府中刑務所の一角から)
http://
塀に沿ってひたすら歩いていくと、府中刑務所の入り口門にさしかかる。門の近くには刑務所前郵便局のATMボックスがある。門から続く大きな通りは大学構内のように両脇に銀杏並木に縁取られていた。刑務所の塀の向かいの住宅地は所員の刑務所官舎である。
(府中刑務所入り口)
http://
しばらくすると、町の小さな賑わいが聞こえてきそうな商店街らしき色合いが目にちらつき始める。町の匂いが再び訪うと思い少し安堵する。が、くたびれた商店街で、住宅地の内部に突然現われたひょろ長い商店の連なりに戸惑いながら歩く。廃墟3秒前だな、という失礼な今君のコメントに苦笑して眺めていると突如、大きな団地が右手に見えてくる。そうか、団地に併せてつくられた商店街なんだなあと納得する。団地族に夢見る心地が巣食っていたのはいつの世ぞ。団地も番地も同じく「晴見」という名前が冠されている。
(晴見町の晴見団地)
http://
「晴見団地」という名前負けした公営団地を過ぎると、府中駅に続く雑踏がさらに安堵感をもたらしてくれて気が逸る。国分寺跡からまったくコーヒーブレイクをいれていなかったうえ、初参加組の疲労度合もさすがに気にかかるところ。「結構疲れた」(まかしょくん)、「疲れた」(スズチューさん、ショードヴァルさん)「全然平気」(kannさん)など意見もまちまちだが、何キロ歩いたかなあという疑問とも文句ともつかぬ言葉が口を出るということは、疲れが見え始めている証拠なのだろう。ようやく府中市街に入り、桜通りにある水出し珈琲、アメリカンワッフルと銘打った喫茶店「おらんだ屋」(府中町1-25-9)でひと休み。アメリカン・ワッフルとはモロンバンのワッフルでも、ベルギーワッフルでもなく、マンホールのような四角いでこぼこ穴の平らなまん丸ワッフルで、フォークとナイフで切り分けて食べるタイプ。果汁シロップや生クリームのかかった温かいワッフルが紅茶や珈琲にうってつけである。水出し珈琲というのでちょっと期待し過ぎたが、まあ美味しい部類に入るか。
(おらんだ屋)
http://
【h地点】〔17:05-17:15〕(府中町2丁目20番地)
おらんだ屋で優に1時間ほどゆっくりと過ごしたあと、用事でdropくんと別れ(お疲れさまでした)、次なる地へ向かう途中、ついつい足止めを進んでしてしまう。そう古本やである。「古書 夢の絵本堂」(府中町2-20-13-105)という小さな町の文房具屋さんのような趣きの店は、小振りながら外国の絵本や洋書、文学やエンタメ、雑誌まで程よく並べられていたと思う。それいゆ*さんはドイツ・リアリズム(だったか)絵画の図録、ショードヴァルさんは漫画に関する文庫本、ぼくは『文芸雑誌 海』のバックナンバーを購入した。あるくかいは古本覗きは暗黙の禁止だったのはいつの頃だったろうか。
(夢の絵本堂)
http://
【h-i地点】〔17:15-17:30〕(府中町2・3丁目〜緑町1・2丁目〜浅間町1丁目)
薄暗くなってきて、急に足取りが早くなっていくのはぼくの性。暗さが増すと目標物が見えなくなってくるのと、日が暮れたら帰るという律儀な習慣を持つ人もたぶんいるからだ。今くんが下見をしたとはいえ、不案内であることに変わりはなく、信用ならないので先頭きって歩く。が、やはりみんなペースをまもってゆっくり歩く。「小金井街道」を横断し、知らず知らずのうちに10メートルくらい離れながら(多分また始まったというようなうすら笑いを浮かべて後背から窺っているのだろう)、メンバーを導く。角に差しかかっては振り返ってみんなの位置を確認し、ようやく「府中の森公園」の入り口に辿り着いた。公園の真上にはきれいな、月がでていた。
(月がでていた)
http://
【j地点】〔17:35-17:40〕(浅間町1丁目)
公園の立て札に不審者注意の呼びかけ(kannさん思わず身構える)もそっちのけで、次なる目的地を目指す。公園の自然に「武蔵野」(今くん)を見いだす者もいるが、ぼくは広々した公園に「光が丘公園」のような不穏な空気を感じていた。公園の記念碑の建つ噴水の広場で少しばかり佇む。有さんが歳を感じると言いながら、静かにベンチで一服している。
(府中の森の記念碑と噴水)
http://
【k地点】〔17:40-55〕(浅間町1丁目)
首都にほど近い府中市など多摩地区は、平坦で広大な土地を利用した軍事施設が明治以降造営されていった。府中にはこうした旧在日米空軍基地の廃墟が今もあり、その痕跡を消すかのように府中の森公園という平和公園ができているのだが、いまだ拭いされない不気味さがそこはかとなく漂っている。以前に訪ねた多摩霊園も暗闇のなかを練り歩いて気味が悪かったが、「航空自衛隊府中基地」もフェンスに遮蔽されて内部を歩くことはかなわないだけに、少年の冒険心がフェンス越しにのぞけ、彼方への羨望で食入るように見つめた。夜になってしまったのではっきり見通せないのだが、倉庫が建ち並び、生い茂る薮のなかをきれいに隈どられた白い道は、大型車が行き来したように踏みならされているのだろう。青黒い闇のなかで基地跡の風景は白く靄がかかっていて、亡霊が建物から気となって立ち上ってくるようだった。ゴシック・ロマンスではないが怖いもの見たさとぞくぞくする思いが先行する。スティーブン・キングの小説の風景のようであった。写真に収められなかったのが残念である。
(航空自衛隊府中基地)
http://
【l地点】〔17:55-18:05〕(浅間町1丁目)
「陸軍燃料廠(しょう)府中米軍基地跡」をやはりフェンス越しに眺める。昭和14(1939)年燃料や潤滑油確保のために建設された工場だが、敗戦とともに占領軍の司令部が置かれることになった場所である。ここはまさに廃墟の相を呈していて、ひび割れた窓や、窓枠から赤錆が壁に滲み垂れていて、綻びながらじっと建っているよりほかない運めを自認するような建築物だった。
(陸軍燃料廠府中米軍基地跡)
http://
http://
【l-m地点】〔18:10-18:25〕(浅間町1丁目〜緑町2・1丁目〜府中町2丁目)
kannさん、スズチューさんが用事のため、府中駅を目指して歩く。府中駅構内で見送ったあと(お疲れさまでした)、最後の砦へ急ぐ。
【n地点】〔18:25-18:30〕(宮町1丁目)
伊勢丹でトイレ休憩をする。トイレ近くのベンチでみな腰かけるが、ショードヴァルさんは座るとまた辛くなるので立ったままだ。疲れましたかと声をかけると、そんなことはないが太腿がという答えに随分無理な歩きを強いているのかも知れないと心配になる。最終地点まで目と鼻の先なのでもう少しの辛抱を。戦後、京王府中駅南口には「府中マーケット」が朝鮮人の手にかかって勃興した。府中の闇市には「パンパン」(売春婦の謂)がたむろし、新宿からチンピラも集まってきて、「コロニアルな原色的雰囲気の漂うギンギンのイメージ」(西井一夫)だったそうだ。新宿内藤町の遊郭のネットワークも、京王線が並走する甲州街道を通じていたといえる。この府中のイメージに府中競馬の賭博が加わることも必至だったのであろう。「府中宿」というだけあって、東西の甲州街道、南北の3つの縦線、すなわち武蔵野線が一部並走する府中街道、国分寺駅から垂直下の国分寺街道、武蔵小金井からは小金井街道が集め来たる土地が府中にほかならない。街道があるということはさまざまなものが流れてくることは想像に難くない。
【o地点】〔18:30-18:45〕(宮町3丁目)
最後の砦は、「大国魂神社」である。すっかり暗くなった神社だが、「くらやみ祭り」に相応しいと勝手に決めこみながら参拝に向かう。
(大國魂神社大鳥居)
http://
(大国魂神社中雀門)
http://
http://
府中という地名は701(大宝元)年、大陸は中国の唐にならった大宝律令に定められて、国司が配置され、国司の政庁が置かれたところが国府と呼ばれるようになる。この国府の中心という意味から「府中」と呼ばれるようになったといわれる。府中は全国にも名を留めているが(たとえば広島には府中市や安芸郡府中町が存在する)、重要なのは府中のそばには国分寺が必ずといってよいほど建設されたことである。ここ東京の府中は武蔵国の国府が設営されたのである。国分寺が府中と接していることも必然の理だったのである。国分寺に比べて府中がほの暗い印象を齎すのは、昭和という激動の時代に依っているのかも知れない。「くらやみ祭り」(大国魂神社例大祭)は深夜から早朝にかけて行われたそうだが(30年前まで)、神様を見ると目がつぶれるという敬意からくるものだといわれる。「国土安穏と五穀豊穣を祈る祭礼」で古代の国府祭として始まり、全国の神職が集まって祈願したものだそうだ。ありとあらゆる灯火が消された闇夜のさなか神輿が出御し、そのかざりの揺れ音だけが通行を知らせるほど静かなものだったらしく、文字通りくらやみを現出させていたのだ。深い鎮守の森のような大国魂神社の境内の暗がりから市街を眺むれば、現在の府中駅前のキラキラした人工灯の示す繁栄ぶりは、もはやくらやみが不可能だと突きつけんばかりであるが、それに抗うよう神社の闇は永きにわたって保存され続けてきたように思われる。府中の駅前の繁華街はやはり覆い隠せてはいまい。京王線の高架ホームを軸にしたペデストリアンデッキ(横断歩道橋)によって、商店街やデパートと連結させた合理的商業システムの明るさも、傘下である地上の端々に暗がりを忍びこませ、潜ませているように思われてならない。その闇が古代から続く大国魂神社のくらやみに出来していると勝手に想像してみると、府中のほの暗さも何となく得心がゆく。
【p地点】〔19:00-21:30〕(宮西町1-2-1)
「かまどか」というチェーンの居酒屋で酒を呑む。府中なのに席につくのに少し待たされて、みな納得がゆかない様子。今回あるくことで得た町の表情や疲れなんかをビールや日本酒の力を借りてテーブルの上で綯い交ぜにしながら、あれやこれやと延々と話す。途中ショードヴァルさんが用事で抜ける(本当にお疲れさまでした)。
【s地点】〔21:45以降〕(多摩市桜ヶ丘1丁目〜関戸2丁目〜一ノ宮2丁目)
m_w_oxygenくんが府中にやってきたことをよいことに、再び酒を飲もうと誘って、府中を後にすることに決める。有さんが都心へと家路を急ぐ(お疲れさまでした)のに対し、ぼくらはさらに西へと京王線に乗って多摩川を越え、府中市から多摩市へと移動。「聖蹟桜ヶ丘駅」に到着。それいゆ*さん、まかしょさんはあの「耳をすませば」を観ていながら舞台地を訪ね歩いたことがないだけに、少しあのくねくね坂を見せてやりたいと思う。今くんやoxygenくんはあまり遠くまで行きたくないと懸念。南口を出て「川崎街道」を渡って少し歩けば(途中スターバックスでぼくとoxygenくんは珈琲を買った、渋る今くんのためにバニラクリームフラペチーノを買ってやる)、「大栗川」にかかる「霞ヶ関橋」にさしかかり、もうあの坂道「いろは坂」が迎えてくれる。初心者の二人組は途中嬉々としてどんどん先に進んでいってしまい、見失って坂道の途中まで上って探すはめになった。(結局坂下で待っていたのであったが)駅前に戻って、それいゆ*さんと別れて男4人でやきとり屋で朝の4時まで語らいあった(すみません、店名忘れました)。庶民的ながら味もよく、値段も良心的というほかなく、この辺に来たらまた一杯やりたい。あるくかいにとっての重要な話も出来た大変生産的な場になった。oxygenくんがうとうとしてきたこともあってここで夜を明かすのもなにかと、ファミレスを目指して川崎街道をボール蹴りしながら歩き、ジョナサンで珈琲を飲んで帰宅の準備をする。みんな眠さでバカバカしいことを言いながら談笑(味噌汁セットにライスやパンをつけるだの、それをお前が頼めだの)。結局聖蹟桜ヶ丘で分倍河原までの上りの各駅停車を待合室で待ちながら(トイレの近いoxygenくんが途中いなくなり、急行を一本遅らせる)、まかしょくんは中央線に接続するために南武線で立川へ、ぼくらは南武線で川崎方面へ向かった。京王線のリュックの迷惑な乗客のポスターがoxygenくんに酷似していた。
|
|
|
|
|
|
|
|
あるくかい 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
あるくかいのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75503人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208297人
- 3位
- 音楽が無いと生きていけない
- 196031人