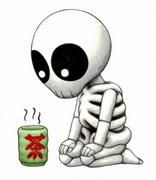6日午前11時から師匠のお宅の初釜(本当は稽古始めということで「会始め」と言っています)におよばれでした。
基本的にはどこもそうでしょうが、「本年も年相変わりませず」と言うことで内容は恒例の物です。
暮れの夜咄では、(^^;ゞ時間を間違えてしまって、皆さんのご迷惑をおかけしたので時計をしっかりチェックしていきました。
寄り付き:
軸「つくばねと百人一首の絵」の綺麗な絵、筆者は忘れました。
軸前には万年青が活けてあり、横の丸三宝にお米と結び昆布が飾ってありました。
待合い:堀内兼中斎宗心宗匠・分明斎宗完宗匠合筆富士の画賛
本席:福岡甘木の安長寺の黙崖和尚筆二行
丸三宝に熨斗飾り
脇床:三宝に三升餅
手前座:
釜:宗旦好み繰口累座 浄味作
炉縁:真塗り老松蒔絵 久田尋牛斎宗匠書き付け
棚:松の木及台子(天板が金閣寺、地板が楠寺の古材)
久田家先代書き付け
水指:利休好み真塗り手桶(大) 堅地屋清兵衛作
杓立て・建水:広島名産 銅蟲(どうちゅう)
濃茶
茶入:不審庵写信楽大福茶入 兼中斎直書 銘八千代
茶碗:而妙斎好雪月花島台 先代吉村楽入作
茶杓:兼中斎書付 銘白鶴
菓子器:真塗縁高
菓子:若草まんぢゅう
茶:実相の昔 西条園詰
初炭
香合:覚々斎好 ぶりぶり
炭斗:木地炭台
火箸:菊頭松竹梅金象眼素張
羽箒:鶴
鐶:浄雪作 大角豆
釜敷:籐組
灰器:兼中斎好 焼貫 楽入作
灰匙:利休形 一政堂作
後座床
花入:自作青竹二重切
結び柳・赤白椿・梅
薄茶
棗:利休好菊桐一双の内「真塗菊中棗」
堀内五代不識斎書付 春斎(利斎別号)作
茶碗:古萩 他 数茶碗
茶杓:黙崖和尚書付 銘古今
菓子器:真塗菊桐蒔絵亀足縁高
菓子:二条駿河屋 煎餅 笹
後炭
香合:楽入作 干支イノシシ
炭斗:出雲不昧公時代 籐組
初釜初日で、総勢12名の大人数でのお招きでした。
初釜の時は年の順という習いがあるらしいのですが、皆さんが年の順より男子優先だからということで私が正客に高上がり(><;
しかも、次客さんは夜咄で迷惑をおかけした老先生(><)
それでも、和気藹々と4時間を過ごさせていただきました。
写真1:待合いの軸
写真2:初座床「春 千林に入る 処々に花」
写真3:懐石膳
飯、汁:白味噌・蕪・たたき菜・溶きガラシ
向付:大根なます・輪切り蜜柑(大根なますで伊勢の二見浦の夫婦岩を表し、蜜柑が日の出を表すそうです。昔蜜柑は薬と考えられていたので、縁起物です。)
基本的にはどこもそうでしょうが、「本年も年相変わりませず」と言うことで内容は恒例の物です。
暮れの夜咄では、(^^;ゞ時間を間違えてしまって、皆さんのご迷惑をおかけしたので時計をしっかりチェックしていきました。
寄り付き:
軸「つくばねと百人一首の絵」の綺麗な絵、筆者は忘れました。
軸前には万年青が活けてあり、横の丸三宝にお米と結び昆布が飾ってありました。
待合い:堀内兼中斎宗心宗匠・分明斎宗完宗匠合筆富士の画賛
本席:福岡甘木の安長寺の黙崖和尚筆二行
丸三宝に熨斗飾り
脇床:三宝に三升餅
手前座:
釜:宗旦好み繰口累座 浄味作
炉縁:真塗り老松蒔絵 久田尋牛斎宗匠書き付け
棚:松の木及台子(天板が金閣寺、地板が楠寺の古材)
久田家先代書き付け
水指:利休好み真塗り手桶(大) 堅地屋清兵衛作
杓立て・建水:広島名産 銅蟲(どうちゅう)
濃茶
茶入:不審庵写信楽大福茶入 兼中斎直書 銘八千代
茶碗:而妙斎好雪月花島台 先代吉村楽入作
茶杓:兼中斎書付 銘白鶴
菓子器:真塗縁高
菓子:若草まんぢゅう
茶:実相の昔 西条園詰
初炭
香合:覚々斎好 ぶりぶり
炭斗:木地炭台
火箸:菊頭松竹梅金象眼素張
羽箒:鶴
鐶:浄雪作 大角豆
釜敷:籐組
灰器:兼中斎好 焼貫 楽入作
灰匙:利休形 一政堂作
後座床
花入:自作青竹二重切
結び柳・赤白椿・梅
薄茶
棗:利休好菊桐一双の内「真塗菊中棗」
堀内五代不識斎書付 春斎(利斎別号)作
茶碗:古萩 他 数茶碗
茶杓:黙崖和尚書付 銘古今
菓子器:真塗菊桐蒔絵亀足縁高
菓子:二条駿河屋 煎餅 笹
後炭
香合:楽入作 干支イノシシ
炭斗:出雲不昧公時代 籐組
初釜初日で、総勢12名の大人数でのお招きでした。
初釜の時は年の順という習いがあるらしいのですが、皆さんが年の順より男子優先だからということで私が正客に高上がり(><;
しかも、次客さんは夜咄で迷惑をおかけした老先生(><)
それでも、和気藹々と4時間を過ごさせていただきました。
写真1:待合いの軸
写真2:初座床「春 千林に入る 処々に花」
写真3:懐石膳
飯、汁:白味噌・蕪・たたき菜・溶きガラシ
向付:大根なます・輪切り蜜柑(大根なますで伊勢の二見浦の夫婦岩を表し、蜜柑が日の出を表すそうです。昔蜜柑は薬と考えられていたので、縁起物です。)
|
|
|
|
|
|
|
|
ゲイの茶道同好会(ゲイオンリー) 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-