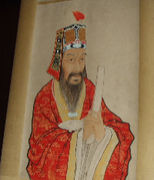(教養とは?)生活秩序に関する精錬された智慧
総裁選を見ていた長老から、「教養ないね」とテレビ演説を見ながら、意見が出ていると聞きます。
昭和の批評家・小林秀雄氏の言葉を糸口にして、教養とは何か、どう育てるか、考える機会になればと思います。小林秀雄語録集「人生の鍛錬」より、
(本 文)
一体、一般教養などという空爆たるものを目指して、どうして教養というものが得られましょうか。教養とは、生活秩序に関する精錬された生きた智慧を言うのでしょう。これは、生活体験に基いて得られるもので、書物もこの場合多少は参考になる、という次第のものだと思う。教養とは、身について、その人の口のきき方だとか挙動だとかに、自ずから現れる言い難い性質が、その特徴であって、教養のあるところを見せようという様な筋のものではあるまい。(「読書週間」21‐23)
鋭い洞察に、ドキッとします。また、次の一説もあります。
(本 文)
私は、本屋の番頭をしている関係上、学者というものの生態をよく感じておりますから、学者と聞けば教養ある人と思う様な感傷的な見解は持っておりませぬ。ノーベル賞をとる事が、何が人間としての価値と関係がありましょうか。私は、決して馬鹿ではないのに人生に迷って途方にくれている人の方が好きですし、教養ある人と思われます。(「読書週間」21‐27)(中略)
本屋の主人(小林秀雄)の目を通した識者への注文は、高く崇高なものでありますが、日常の行動もつぶさに検証している姿勢が、素晴らしいと思います。
佐藤一斎の「言志四録」にも自分を高める修養の方法が説かれています。
「学は自得するを貴ぶ。人徒(いたず)らに目を持って字有るの読む。故に字に局して、通透(つうとう)するを得ず。
当(まさ)に心を以て字無きの書を読むべし。乃(すなわ)ち洞(とう)して自得する有らん」(「言志後録」138)
(注)洞:深い悟り
(解 釈)
学問は本心において体得することが大事である。ところが、世の中の人はいたらずに目で文字の書かれた書物を読むだけである。そのために、文字に囚われて、その背後にある物事の道理を見通すことができない。
心眼を開き、文字の書かれていない書、すなわち実社会の諸々の事象を読み解いて、自らの修養とするべきである。そうすれば、悟り得て自らの本心に体得することができるだろう。
(感 想)
偉人たちの言葉には、共通する部分が多々あります。書物を読むことは参考になるが、要は実生活の中で、どう実践し、反省し、更に高い品格を求めて、自分を高めることに務めるかにあると思います。
教養とは、生活に活かしてこそつかめる、人格形成の道程なのかもしれません。
*参考資料:
1.「人生の鍛錬」小林秀雄語録集、新潮社
2.「佐藤一斎 一日一言」〜『言志四録』を読む〜、渡邊五郎三郎編
総裁選を見ていた長老から、「教養ないね」とテレビ演説を見ながら、意見が出ていると聞きます。
昭和の批評家・小林秀雄氏の言葉を糸口にして、教養とは何か、どう育てるか、考える機会になればと思います。小林秀雄語録集「人生の鍛錬」より、
(本 文)
一体、一般教養などという空爆たるものを目指して、どうして教養というものが得られましょうか。教養とは、生活秩序に関する精錬された生きた智慧を言うのでしょう。これは、生活体験に基いて得られるもので、書物もこの場合多少は参考になる、という次第のものだと思う。教養とは、身について、その人の口のきき方だとか挙動だとかに、自ずから現れる言い難い性質が、その特徴であって、教養のあるところを見せようという様な筋のものではあるまい。(「読書週間」21‐23)
鋭い洞察に、ドキッとします。また、次の一説もあります。
(本 文)
私は、本屋の番頭をしている関係上、学者というものの生態をよく感じておりますから、学者と聞けば教養ある人と思う様な感傷的な見解は持っておりませぬ。ノーベル賞をとる事が、何が人間としての価値と関係がありましょうか。私は、決して馬鹿ではないのに人生に迷って途方にくれている人の方が好きですし、教養ある人と思われます。(「読書週間」21‐27)(中略)
本屋の主人(小林秀雄)の目を通した識者への注文は、高く崇高なものでありますが、日常の行動もつぶさに検証している姿勢が、素晴らしいと思います。
佐藤一斎の「言志四録」にも自分を高める修養の方法が説かれています。
「学は自得するを貴ぶ。人徒(いたず)らに目を持って字有るの読む。故に字に局して、通透(つうとう)するを得ず。
当(まさ)に心を以て字無きの書を読むべし。乃(すなわ)ち洞(とう)して自得する有らん」(「言志後録」138)
(注)洞:深い悟り
(解 釈)
学問は本心において体得することが大事である。ところが、世の中の人はいたらずに目で文字の書かれた書物を読むだけである。そのために、文字に囚われて、その背後にある物事の道理を見通すことができない。
心眼を開き、文字の書かれていない書、すなわち実社会の諸々の事象を読み解いて、自らの修養とするべきである。そうすれば、悟り得て自らの本心に体得することができるだろう。
(感 想)
偉人たちの言葉には、共通する部分が多々あります。書物を読むことは参考になるが、要は実生活の中で、どう実践し、反省し、更に高い品格を求めて、自分を高めることに務めるかにあると思います。
教養とは、生活に活かしてこそつかめる、人格形成の道程なのかもしれません。
*参考資料:
1.「人生の鍛錬」小林秀雄語録集、新潮社
2.「佐藤一斎 一日一言」〜『言志四録』を読む〜、渡邊五郎三郎編
|
|
|
|
|
|
|
|
心を育てる言葉 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-