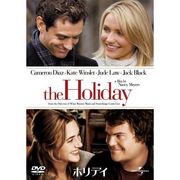『ヒトラーの贋札』の感想〜総集編〜
私は昨年後半、2回にわたりこの『ヒトラーの贋札』に感想を述べています。
かなり、余計なことも話していて、いつか〜総集編〜を書かなければと思っていました。しかし、もうひとつ気になっていた映画、『ゆれる』(監督・原案・脚本:西川美和)の感想の方が先になってしまいました(7月21日トピック)。
でも逆に、この『ヒトラーの贋札』をもう一度、ゆっくりと観ることができました。
映画にはいろんなジャンルがあり、みんなそれぞれを楽しんで観ていると思います。
この『ヒトラーの贋札』は史実に基づいた作品である、といった紹介が沢山あります。しかし、監督は監督なりにこの作品をつくっているし、一度表現されたものは、ひとつの作品として「独立」するものです。しかもそれを観る私たちは、己の心境や現況、追っている主題や趣味、いわばそのときの気分において「観る」のは様々でありましょう。それでいいではないですか。
それを、「貴方の観る仕方は間違っている」とか「それは独善的すぎる」とか言うのは如何なものでありましょう。何もマルクスの思想を研究しているのではありません。意見や中傷は、私にとっていいものです。それが、単に「長い!」の3文字でコメントするのは、人間として恥ずべきものです。それならば、読まなければいいし、わざわざコメントすることはないでしょう。ひどいのになると、「少し読んだが、途中で吐き気がしてパソコンの電源を切ったぜ、この水虫野郎・・・!」てな、ものもあります。でも私は、途中まで読んでいただいてどうもありがとう、と嬉しくなります。要するに、○○○○的現象でしょう。
ともかく、前の「感想」には、1日に300人のご訪問者をいただきました。この場を借りてお礼申し上げます。
前置きが長くなって申し訳ありません。
★
『ヒトラーの贋札』は、確かに史実を、映画化したものです。
引用します。
【ナチス・ドイツが第二次世界大戦中の1943年から敗戦まで英米経済を混乱させる目的で実行された"ベルンハルト作戦"。国家による偽札偽造事件としては史上最大規模だと言われおり、製造はザクセンハウゼン強制収容所に集められたユダヤ人技術者たちに行わせていました。この驚愕の事実をユダヤ人技術者の視点から描いた映画が『ヒトラーの贋札』です。実際に"ベルンハルト作戦"に関わった印刷技師アドルフ・ブルガーの『ヒトラーの贋札 悪魔の工房 』を基調に、作戦を実行すれば憎きナチを助ける、拒否すれば殺されるというジレンマに苦しむユダヤ人技術者の姿をフィクションを織り交ぜながら描いたドラマです。】
でも、私にはそんなことはどうでもいいのです。私が私の主題としてもっているのは、「生き方」、「自由感」、そして人たちの「関係性」です。その「気分」において、私はこの『ヒトラーの贋札』を観て感動するのでした。
ナナナ
シーンは、モンテカルロのカジノの近くの、碧い海と浜辺のさざ波から始まります。浜辺には「終戦」を知らせる新聞。そしてエンディングもその夜の浜辺であり、朝を迎えます。
すでに“終戦”になっており、主人公はある「解放感」を味わい、然る後、また「生きる」を繰り返す「自由感」を示します・
その、浜辺の側にあるカジノのルーレット中に「回顧」が始まります。
彼、主人公はカール・マルコヴィックス演じるサロモン・ソロヴィッチ。その言説から、元、ソ連(ロシア)にいたユダヤ人で、ここドイツで「贋札」や「パスポート偽造」を生業としています。
ある日、彼を知る、若きパルチザンが、素敵な女性パルチザンのパスポートの偽造依頼に一緒に訪れます。アルゼンチンのパスポートを。ああ、これも私のあこがれの地であります。彼は彼女と性交渉を行いながら、これを仕上げます。あの女性の下着は、確か「ペチコート」というのでしょうか?セクシーです。
そこに、当時刑事で後に、デーフィト・シュトリーゾフ演じるフリードリヒ・ヘルツォーク親衛隊少佐が踏み込み彼を逮捕します。
そして彼は、収容所に送られます。映画のイントロはそのように始まります。
★ ★
収容所ではいろいろなシーンがありますが、何れにしても、彼、主人公、サロモン・ソロヴィッチは、生きることにとてもしたたかです。絵を書いたりして、看守たちに取り入ったり、恫喝したり、なかなかです。
〜中略します〜
主人公と何人かの仲間は、贋札づくりの「ベルンハルト作戦」に従事させられます。
その指令を出したのが、彼を逮捕し、今はフリードリヒ・ヘルツォーク親衛隊少佐になっている、あの主人公を逮捕した刑事でした、彼はヒムラーの指示の元、これを実行するナチス少佐でした。映画中おもしろいのは、何と彼は自ら、「俺は元共産党員だったが、あの、自由だとか、人権だとか・・・というのが面倒くさくって、ナチになったのさ」と言います。
これは通常の映画では、単なる抑圧者として登場しますが、後で述べるように、とても重要な、この映画の「伏線」です。
近くにアウシュビッツがあります。ユダヤ人はこの存在と「ガス室」をとても恐れています。
何れにしても、この「ベルンハルト作戦」に従事させられた囚人たちは、他の囚人とは異なり、ややいい待遇?を受けますが、眼の前で起こる射殺などの迫害に恐怖しています。そして、彼らの僅かな希望?は、あくまでも「生きよう」という決意であり絶望です。
その中に、あくまでもナチスに抵抗し、この「ベルンハルト作戦」を失敗させようと言う、いわば反ナチス・ユダヤ青年がいます。それはアウグスト・ディール演じるアドルフ・ブルガーです。
彼はこの「ベルンハルト作戦」をサボタージュし、抵抗します。主人公にもそれを切々と訴えます。囚人みんなには、“仲間意識”があり、みんなその青年を嫌います。主人公とも反目しますが、何せ何れもいつ殺される身です。
なかなか、良い贋札ができないのに、少佐はいらつきます。仲間みんなは知っています。良い贋札ができないのは、アドルフ・ブルガーのサボタージュであることを。「あの野郎さえいなければ・・・」っていう雰囲気にあります。でも主人公は、この青年にも反目するようで理解を示しています。それで、仲間に、彼のサボタージュ行為を密告したら、『殺すぞ!』って言う。にもかかわらず青年は・・・・!
あのポンドの贋札づくりに成功した。そして、ナチスのエージェントが、イギリスの銀行に“自信満々に”訪れる光景はとてもおもしろい。おかしなもんだが拍手を贈りたい。まあ、その従事収容者も、少佐も、立場を違えても喝采したであろう。あの青年アドルフ・ブルガーを除いて。
戦況はナチスにとって不利になっている。
囚人たちは、ソ連が解放してくれると信じている。囚人たちは、空爆の音が、次第に市街戦に変わって来ていることを知っている。ナチスが何か落ち着かない。もう囚人のことなんてどうでもいい雰囲気。
ここ「幽閉の地」にも情報は入っているものと思う。しかし解放したのは、米軍であったという驚嘆がある。
「肺結核」の若者がいる。
囚人の医師と相談し、薬を得るために、狡猾に少佐に迫る。
少佐は、主人公を、我が家に誘う。
そこには、普通の家族生活、「日常」と言えるものがある。少佐は言う。「私は家族には暴力をふるわない。そう教えている」と。う〜む。
何とか、薬を手に入れる。
主人公は、仲間のクリンガー医師にそれを渡す。あれ、その「肺結核」の若者がいない。主人公は探す。そして、収容所の隙間から見たのは、その若者の「自殺行為」である。ナチのホルスト親衛隊小隊長によって、ピストルで撃たれる。そしてこう言う、「人間として死んだな・・・!」って。ここで、主人公サロモン・ソロヴィッチは「切れる」。
遅遅として進まない、「ドルの贋札」製造。
執拗に抵抗する、青年アドルフ・ブルガー、映画中で彼の妻はアウシュビッツで銃殺された。それをみんなは知っている。しかし、彼がその抵抗を維持できるのは、サロモン・ソロヴィッチがいるからだ。青年はそれを知っているはずだ。この拮抗。それと迫り来るナチの敗北的情況。緊迫。
主人公は、トイレ掃除中、ホルスト親衛隊小隊長に小便を頭にかけられる。屈辱。
フリードリヒ・ヘルツォーク親衛隊少佐は囚人たちに、あがきの脅迫をする。恐怖。
そこに主人公サロモン・ソロヴィッチが、見事に完成させた「ドルの贋札」をもってくる。少佐は納得し、囚人にささやかな饗宴をあたえる。
恐怖と緊迫の中での饗宴。それはどんな気分であろう。
その中で唱われる『フニクリフニクラ』と、若者がみごとに唱う『歌』(どう探しても分からない)は、哀愁に満ちていて、とてもいい。ナチ共も拍手するくらいだから、名曲であろう。『ダブリンの街角で』であろうか。誰か教えて下さい。そして、歌は後述するように、「イタリア語」であろうが、学識のない私には分からない。(最初の感想では、マリアマリと思ったが・・・)。
あわただしくなる。そう、解放軍が迫っているからだ。
ナチは、贋札づくりの機械類の処分を命じる。アルプスに隠すらしい。それと撤退を開始する。
夕刻、フリードリヒ・ヘルツォーク親衛隊少佐がこっそりとあらわれ、隠していた「贋札」を鞄に入れ持ち去ろうとする。そこに彫刻刀のようなナイフをもった主人公が待ち伏せしている。もみあっている内に、主人公は少佐のピストルを奪う。殺さないでくれ、と哀願する少佐。主人公は言う。「しょんべん漏らしているぜ」って。でも、けっきょく殺さないで逃がしたようだ。逃がしたというのではなく、「止めた」のだ。
ついに解放される。
抵抗ユダヤ人がやってきて、多少ましな服装の仲間たちを疑い、ある者は、ただちに殺せと言う。仲間は刻印された腕を見せる。そのときの気分は如何なものであろう。
青年アドルフ・ブルガーは、仲間に、サボタージュしたことを褒められる。苦しい笑いの中に涙を見せ、だんだん自分を追い込んで行く。
彼は自殺する。
ざっと、ストーリーを一回りした。
★★★
ふたたびモンテカルロのカジノの近くの、暗い浜辺。すべてを、いわば自暴的に放棄し、ぼんやりしている主人公サロモン・ソロヴィッチに、あの女性(ドロレス・チャップリン)があらわれる。「大金なくしたわね」。主人公は答えず、ふたりは踊る。曲は哀愁に満ちたタンゴである。おそらく『手に手をとって』であろうか?光景が明るくなる。まだ、踊っている。主人公は言う。「なに、また贋札つくるさ」。ん〜、いいエンディングだ。
最後の字幕中も、この『タンゴ』は続く。
ミスマッチのようでいて、心を打つ。
なんと言ったって、タンゴ(Tango)は、カディス発祥。そうアンダルシアなのだから。
★★★★
〜私の雑感を付け加えます〜
私の観方を申します。この映画の主人公の「生き方」が素晴らしく心を打ちます。全ての強圧に耐え、体験しながらも、「イデオロギー」や「人種」などからは自立(自由でもいいです)した生き方です。とても「解放感」がある。
それと、冒頭に、アルゼンチンのパスポート作成の依頼があります。まさにアルゼンチンは当時、中立?をとったのでヒトラー政権の反対者はここに亡命します。でも、敗戦後、今度はヒトラーの残党がアルゼンチンに入るのです。確か、ナチの大物もここで逮捕された記憶があります。アルゼンチンの人口の内、現在は2%がドイツ人です(このことは僕の興味以外の何者でもないけれども)。
それと、史実とは違うけれども、映画中、主人公はソ連にいたと言っています。また、家族が収容所で死んだと言っています。これにはそうとうな示唆を感じます。何もヒトラーだけが人種偏見を持っていたわけではない。ファシズムを突然変異(そんなことはあり得ません)ではなく、超資本主義、国家主義ととらえた方が歴史の流れに合います。事実、スターリンもユダヤ人をラーゲリ(収容所)に入れ、シベリアに流刑しています。ですから、収容所の所長の発言、「俺は共産党員だったが、あれはめんどう臭くってナチになったのさ・・・!」というところで主人公と微妙に絡んで来ることのおもしろさがあります。きっと、映画では、主人公の家族はソ連のラーゲリで死んだようになっているのかもしれません。
主人公の贋札作りに反対し、抵抗を促す青年がいます。彼の妻はアウシュビッツで射殺されました。でも、主人公は彼を疎んじる仲間に、「仲間(青年)を裏切ったら殺すぞ!」って言います。このことに評論家は大概、「ユダヤ人としてのプライド?」と「抵抗」を想定しています。
私は違うと思います。彼が言う仲間とは、贋札づくりをする収容所の仲間のことであり、すでに深い悲しみの中から彼はユダヤ人からも自立していると思われます。
ポイントはもうひとつあり、その青年が自殺する流れです。彼は介抱されたものの妻を失ってしまい、解放後、反対してきた仲間にも許されたことで自殺したのでは無いと思います。解放され平和?になったことで、逆に彼が生きる(あるいは存在する)「根拠」(拠点と言いたい)を失ったことによるのではないかと私は考えます。彼も戦争犠牲者のひとつのあり方として描かれているのだと捉えました。
だんだん、解放軍がやってくる気配が彼らには分かっていたと思います(おそらく戦時中であっても収容所には情報は入っていたと思います)。そして、解放してくれたのはソ連ではなく連合軍であったという皮肉もあります。ワルシャワでもソ連=スターリンは許されないことをしていますよね。ここもまた面白いと思いました。
話しがそれますが、ロシアの民衆詩人エセーニンは民衆にも愛されますし、彼が批判をしたレーニンも彼を讃えます。しかし、世はボルシェビキの天下、民衆はこぞってコムソムル、コムソムルに流れて行きます。エセーニンはそれをとても憂います。でも晩年、故郷を愛し、さらに愛する母を失い、彼はだんだん絶望の淵に立ち、そして自殺します。血で「さ・よ・な・ら」って書いて・・・!私は稚拙ですがこのように解釈しています。「エセーニンは民衆に愛されたが故に、世の中の移ろいに悩み、ついに民衆との乖離を感じ自殺に至ったのではないか?つまり生存の(あるいは知の)拠点を失ったのではないか?と。
過去の大学闘争の活動家も、結局敗北し、己の存在拠点を失い放浪し、あるものはその存在拠点を宗教に求めたりするのを、私は沢山見ています。
その意味でも、「ヒトラーの贋札」の主人公は、様々で辛い経験の中から、民族を超え、イデオロギーを超えてしっかりと地に足をつけて自立し(あるいは自由)、「時の移ろいの中」を、その場その場の「現実をしっかりと歩んで行く」生き様に私は好感が持てて、我が観察に勝手に納得しているのです。
人物をあるいは人物のあり方を対比させたりするのは映画に多く見られることです。ですから何も『ヒトラーの贋札』だけではなく、これも私が好きな『LAコンフィデンシャル』、『ショーシャンクの空の下』でも表現されています。
また、数日前に書いた『ゆれる』の映画も主題を執拗に追っています。
しかし、『ヒトラーの贋札』は、その人間の生き様の対比のさせ方が強烈です。しかし、自然に穏やかにそれを表現しているところがこの映画の優れた面です。
『ヒトラーの贋札』は、もちろん「ナチ収容所での贋札つくり」ですが、作者が時代背景をここにとって表現しているのはとても感心します。そして、その戦争の中で生きる“人の生き方”として、大きく言うとまず主人公、反対を唱える青年、それに忘れてならないのはナチ収容所少佐の存在です。
繰り返しますが、少佐は映画の中で、「俺はむかし共産党員だったのだ、しかしあれはこむずかしくてナチになったのさ・・・」という面白い人物像に仕上げています。
それに主人公の存在。彼は言います、「俺は前にロシアにいた、家族も収容所で死んだ(ソ連のラーゲリとユダヤ迫害を想定させていて面白い)・・・」と。この絡みが映画の流れの柱になっていることに気付いて欲しいと思っています。主人公は寡黙でありますが、ひょっとしてロシアでは共産党員ではなかったのか?そしてスターリンの迫害にあうに至ったのではないか?と想像させます。その落ちが、作品後半で、主人公が、逃げ出す少佐を殺さなかった。つまり、“同期のよしみ?”の少しの情けと、「そんなことしてもどうってことじゃねーな」っていう秀でた生き方と思いが静かでありながらも圧倒的です。
つまり、コムニズムもファシズムもそんなものは同じでどうでもいい。作品の骨格を成す三人は、何れにしても「戦争の被害者」であり、作品は「時代の生き方」を三様で観せています。ちょっと横道に入りますが、私は高校生の若き頃、終戦?を超えてそのまま民主主義を説く先生をとても嫌い、その先生を痛烈に批判しました。先生はそれを自戒し、逆に私をとても心配してくれました。「何か、きみも、あまりにとらわれるなよ・・・」って言われている気がしました。また、私が反体制思想犯としてぶち込まれ(私はこのことを何とも思っていません)、その後に釈放され、街角で会った担当刑事はこう言いました、「おまえにはしてやられたよ〜。でもねえ、俺はおまえが好きだよ。どうかお母さんを大切にしてあげてね・・・!」。
“人あるいは人の生き方に”興味を持つ私は、この映画を観ながら過去を追憶し、今の自分はどうか?を問うています。
贋札造りに抵抗し交戦を促す青年、このあり方はもうひとつの意味を持っていて、「もうひとつの生き方を」表しています。彼は収容所内では仲間に“分かるけれど、困った存在・・・”です。
私が言う「存在拠点の喪失」は、きっとドイツの壁の崩壊の時も同じような現象あるいは心象として起きたのに違いありません。西と東がひとつになる。そうすると、簡単に言えば西を崇拝し生きてきた人々、東を崇拝し生きてきた人々は混乱の極みでしょう。いろいろなことがあったでしょう。そして、それをやがて乗り越えたのでしょう。
その頃、日本ではどうであったでしょう。
私が言いたい、あるいはこの映画が描きたかったのは、“そんなものからは自由であった方がいい”というもので、僕のことばで言えば「自立した生き方」です。言葉尻を捉えられて言われると困りますが、あらゆるものを相対化してしまう知力であります。共産主義からナチになった少佐。何れも「生きていく」のでしょう。それが民衆の知恵です。そこを見抜かない?と、結局、知の虜になってあやまちを犯します。そうです、ここではじめて、私は私が好きなエセーニンに象徴的な知の脆弱さに気付きました。
最後に笑い話をひとつ。日独伊三国同盟。初期に、あの女好きのムッソリーニは、ちょびひげヒトラーが大嫌いなのです。それで、ユダヤ迫害には不機嫌で、「ユダヤ難民所」をつくるんです。それで、この映画の中では、歌にイタリア民謡や歌曲が覆いのかなあ、なんて思います。
ムッソリーニは愛人を連れて逃げますが、とある村のパルチザンに捕まり処刑されます。そして、「逆さ吊り」にされ、晒し者にされます。ちょびひげヒトラーは、ここことにとても驚き、死後、我が肢体を焼け、と命令した、という伝えもあります。笑えます・・・・・
この『ヒトラーの贋札』で、仲間たちは皆、「解放まで生きよう」、「戦争が終わるまで生き抜こう」、「とにかく生きるのだ」と決意しています。私には、それは無言で狡獪で実行で、そして何物にも囚われない解放性をもった主人公が、組織したようにみえる。
「時代をどう生きるか」と問うとき、主人公、抵抗の青年、ナチの少佐も現実に生きている。残念なのは抵抗の青年の自殺だ。そこに、「知」の、「抵抗」の弱さを知る。
時代が変わったって、私たちも今生きている。いろんな生き方がある。ITのしっぽで儲ける者、少少の成功で傲慢になる者、大学を出てキャバレーの呼び込みをやっているM青年、アメリカ帰りの英語しか話せない日本人の売春婦、私に寄りひっしに女になろうとしたレズビアン、活路を見いだせない主婦、失業者のしたたかさ。
どうしようもない困窮。平気でそれを裏切る友情。
でも『生きる』ことには変わりはない。
しかし、私には権力とハーモニーして「義援ブーム」に乗る者たちは、“都合良く生きる”者たちにしかみえない。
私は、そんな情況の中で、「原形は存在し現象する」という概念を創造し、それをもって、私を縛ってきた「エセーニン」をあっという間に超えた。
ああ、映画の主人公には、どんな「原形」があったのだろうと考える。
とにかく生きよう!
『ヒトラーの贋札』は私の今の生き方を問うた。
今、私は「自前の思想」に「協調」をシンフォニーさせている。協調は私の場合、妥協ではなく、いわば「耕す」というもので、「ビジョンを持て」ということだ。
それは、アンダルシアの、北アフリカ人、出自の未だ不明な、西インドからきたジプシー、ユダヤ人、アラブ人の『融合』に起因する。
ふたたび、浜辺で踊る主人公と女性(ドロレス・チャップリン)、それに流れるタンゴ『手に手をとって』。「また、贋札造りをするさ・・・・」。
わあっ、たまりません!
★★★★★
1.この『ヒトラーの贋札』の感想〜総集編〜は、以前に2部作でトピックしたものを、まとめ、さらにストーリーを追ってみたものです。また、余計なものは省きました。
2.映画中に、流れる音楽をいくら調べても分かりませんでした。どなたか、教えて下さい。
3.最後に、この映画を薦めてくれた友に感謝します。
スタッフ [編集]
• 監督…シュテファン・ルツォヴィツキー
• 製作…ヨーゼフ・アイヒホルツァー
• 脚本…シュテファン・ルツォヴィツキー
• 音楽…マリウス・ルーラント
• 撮影監督…ベネディクト・ノイエンフェルス
• 撮影…ダニエル・パール
キャスト [編集]
• サロモン・ソロヴィッチ…カール・マルコヴィックス
• アドルフ・ブルガー…アウグスト・ディール
• フリードリヒ・ヘルツォーク親衛隊少佐…デーフィト・シュトリーゾフ
• アグライア…マリー・ボイマー
• クリンガー医師…アウグスト・ツィルナー
• ホルスト親衛隊小隊長:…マルティン・ブラムバッハ
• カジノの令嬢…ドロレス・チャップリン
その他 [編集]
• 第57回ベルリン国際映画祭コンペティション部門正式出品
• 第80回アカデミー賞外国語映画賞 オーストリア代表作品
私は昨年後半、2回にわたりこの『ヒトラーの贋札』に感想を述べています。
かなり、余計なことも話していて、いつか〜総集編〜を書かなければと思っていました。しかし、もうひとつ気になっていた映画、『ゆれる』(監督・原案・脚本:西川美和)の感想の方が先になってしまいました(7月21日トピック)。
でも逆に、この『ヒトラーの贋札』をもう一度、ゆっくりと観ることができました。
映画にはいろんなジャンルがあり、みんなそれぞれを楽しんで観ていると思います。
この『ヒトラーの贋札』は史実に基づいた作品である、といった紹介が沢山あります。しかし、監督は監督なりにこの作品をつくっているし、一度表現されたものは、ひとつの作品として「独立」するものです。しかもそれを観る私たちは、己の心境や現況、追っている主題や趣味、いわばそのときの気分において「観る」のは様々でありましょう。それでいいではないですか。
それを、「貴方の観る仕方は間違っている」とか「それは独善的すぎる」とか言うのは如何なものでありましょう。何もマルクスの思想を研究しているのではありません。意見や中傷は、私にとっていいものです。それが、単に「長い!」の3文字でコメントするのは、人間として恥ずべきものです。それならば、読まなければいいし、わざわざコメントすることはないでしょう。ひどいのになると、「少し読んだが、途中で吐き気がしてパソコンの電源を切ったぜ、この水虫野郎・・・!」てな、ものもあります。でも私は、途中まで読んでいただいてどうもありがとう、と嬉しくなります。要するに、○○○○的現象でしょう。
ともかく、前の「感想」には、1日に300人のご訪問者をいただきました。この場を借りてお礼申し上げます。
前置きが長くなって申し訳ありません。
★
『ヒトラーの贋札』は、確かに史実を、映画化したものです。
引用します。
【ナチス・ドイツが第二次世界大戦中の1943年から敗戦まで英米経済を混乱させる目的で実行された"ベルンハルト作戦"。国家による偽札偽造事件としては史上最大規模だと言われおり、製造はザクセンハウゼン強制収容所に集められたユダヤ人技術者たちに行わせていました。この驚愕の事実をユダヤ人技術者の視点から描いた映画が『ヒトラーの贋札』です。実際に"ベルンハルト作戦"に関わった印刷技師アドルフ・ブルガーの『ヒトラーの贋札 悪魔の工房 』を基調に、作戦を実行すれば憎きナチを助ける、拒否すれば殺されるというジレンマに苦しむユダヤ人技術者の姿をフィクションを織り交ぜながら描いたドラマです。】
でも、私にはそんなことはどうでもいいのです。私が私の主題としてもっているのは、「生き方」、「自由感」、そして人たちの「関係性」です。その「気分」において、私はこの『ヒトラーの贋札』を観て感動するのでした。
ナナナ
シーンは、モンテカルロのカジノの近くの、碧い海と浜辺のさざ波から始まります。浜辺には「終戦」を知らせる新聞。そしてエンディングもその夜の浜辺であり、朝を迎えます。
すでに“終戦”になっており、主人公はある「解放感」を味わい、然る後、また「生きる」を繰り返す「自由感」を示します・
その、浜辺の側にあるカジノのルーレット中に「回顧」が始まります。
彼、主人公はカール・マルコヴィックス演じるサロモン・ソロヴィッチ。その言説から、元、ソ連(ロシア)にいたユダヤ人で、ここドイツで「贋札」や「パスポート偽造」を生業としています。
ある日、彼を知る、若きパルチザンが、素敵な女性パルチザンのパスポートの偽造依頼に一緒に訪れます。アルゼンチンのパスポートを。ああ、これも私のあこがれの地であります。彼は彼女と性交渉を行いながら、これを仕上げます。あの女性の下着は、確か「ペチコート」というのでしょうか?セクシーです。
そこに、当時刑事で後に、デーフィト・シュトリーゾフ演じるフリードリヒ・ヘルツォーク親衛隊少佐が踏み込み彼を逮捕します。
そして彼は、収容所に送られます。映画のイントロはそのように始まります。
★ ★
収容所ではいろいろなシーンがありますが、何れにしても、彼、主人公、サロモン・ソロヴィッチは、生きることにとてもしたたかです。絵を書いたりして、看守たちに取り入ったり、恫喝したり、なかなかです。
〜中略します〜
主人公と何人かの仲間は、贋札づくりの「ベルンハルト作戦」に従事させられます。
その指令を出したのが、彼を逮捕し、今はフリードリヒ・ヘルツォーク親衛隊少佐になっている、あの主人公を逮捕した刑事でした、彼はヒムラーの指示の元、これを実行するナチス少佐でした。映画中おもしろいのは、何と彼は自ら、「俺は元共産党員だったが、あの、自由だとか、人権だとか・・・というのが面倒くさくって、ナチになったのさ」と言います。
これは通常の映画では、単なる抑圧者として登場しますが、後で述べるように、とても重要な、この映画の「伏線」です。
近くにアウシュビッツがあります。ユダヤ人はこの存在と「ガス室」をとても恐れています。
何れにしても、この「ベルンハルト作戦」に従事させられた囚人たちは、他の囚人とは異なり、ややいい待遇?を受けますが、眼の前で起こる射殺などの迫害に恐怖しています。そして、彼らの僅かな希望?は、あくまでも「生きよう」という決意であり絶望です。
その中に、あくまでもナチスに抵抗し、この「ベルンハルト作戦」を失敗させようと言う、いわば反ナチス・ユダヤ青年がいます。それはアウグスト・ディール演じるアドルフ・ブルガーです。
彼はこの「ベルンハルト作戦」をサボタージュし、抵抗します。主人公にもそれを切々と訴えます。囚人みんなには、“仲間意識”があり、みんなその青年を嫌います。主人公とも反目しますが、何せ何れもいつ殺される身です。
なかなか、良い贋札ができないのに、少佐はいらつきます。仲間みんなは知っています。良い贋札ができないのは、アドルフ・ブルガーのサボタージュであることを。「あの野郎さえいなければ・・・」っていう雰囲気にあります。でも主人公は、この青年にも反目するようで理解を示しています。それで、仲間に、彼のサボタージュ行為を密告したら、『殺すぞ!』って言う。にもかかわらず青年は・・・・!
あのポンドの贋札づくりに成功した。そして、ナチスのエージェントが、イギリスの銀行に“自信満々に”訪れる光景はとてもおもしろい。おかしなもんだが拍手を贈りたい。まあ、その従事収容者も、少佐も、立場を違えても喝采したであろう。あの青年アドルフ・ブルガーを除いて。
戦況はナチスにとって不利になっている。
囚人たちは、ソ連が解放してくれると信じている。囚人たちは、空爆の音が、次第に市街戦に変わって来ていることを知っている。ナチスが何か落ち着かない。もう囚人のことなんてどうでもいい雰囲気。
ここ「幽閉の地」にも情報は入っているものと思う。しかし解放したのは、米軍であったという驚嘆がある。
「肺結核」の若者がいる。
囚人の医師と相談し、薬を得るために、狡猾に少佐に迫る。
少佐は、主人公を、我が家に誘う。
そこには、普通の家族生活、「日常」と言えるものがある。少佐は言う。「私は家族には暴力をふるわない。そう教えている」と。う〜む。
何とか、薬を手に入れる。
主人公は、仲間のクリンガー医師にそれを渡す。あれ、その「肺結核」の若者がいない。主人公は探す。そして、収容所の隙間から見たのは、その若者の「自殺行為」である。ナチのホルスト親衛隊小隊長によって、ピストルで撃たれる。そしてこう言う、「人間として死んだな・・・!」って。ここで、主人公サロモン・ソロヴィッチは「切れる」。
遅遅として進まない、「ドルの贋札」製造。
執拗に抵抗する、青年アドルフ・ブルガー、映画中で彼の妻はアウシュビッツで銃殺された。それをみんなは知っている。しかし、彼がその抵抗を維持できるのは、サロモン・ソロヴィッチがいるからだ。青年はそれを知っているはずだ。この拮抗。それと迫り来るナチの敗北的情況。緊迫。
主人公は、トイレ掃除中、ホルスト親衛隊小隊長に小便を頭にかけられる。屈辱。
フリードリヒ・ヘルツォーク親衛隊少佐は囚人たちに、あがきの脅迫をする。恐怖。
そこに主人公サロモン・ソロヴィッチが、見事に完成させた「ドルの贋札」をもってくる。少佐は納得し、囚人にささやかな饗宴をあたえる。
恐怖と緊迫の中での饗宴。それはどんな気分であろう。
その中で唱われる『フニクリフニクラ』と、若者がみごとに唱う『歌』(どう探しても分からない)は、哀愁に満ちていて、とてもいい。ナチ共も拍手するくらいだから、名曲であろう。『ダブリンの街角で』であろうか。誰か教えて下さい。そして、歌は後述するように、「イタリア語」であろうが、学識のない私には分からない。(最初の感想では、マリアマリと思ったが・・・)。
あわただしくなる。そう、解放軍が迫っているからだ。
ナチは、贋札づくりの機械類の処分を命じる。アルプスに隠すらしい。それと撤退を開始する。
夕刻、フリードリヒ・ヘルツォーク親衛隊少佐がこっそりとあらわれ、隠していた「贋札」を鞄に入れ持ち去ろうとする。そこに彫刻刀のようなナイフをもった主人公が待ち伏せしている。もみあっている内に、主人公は少佐のピストルを奪う。殺さないでくれ、と哀願する少佐。主人公は言う。「しょんべん漏らしているぜ」って。でも、けっきょく殺さないで逃がしたようだ。逃がしたというのではなく、「止めた」のだ。
ついに解放される。
抵抗ユダヤ人がやってきて、多少ましな服装の仲間たちを疑い、ある者は、ただちに殺せと言う。仲間は刻印された腕を見せる。そのときの気分は如何なものであろう。
青年アドルフ・ブルガーは、仲間に、サボタージュしたことを褒められる。苦しい笑いの中に涙を見せ、だんだん自分を追い込んで行く。
彼は自殺する。
ざっと、ストーリーを一回りした。
★★★
ふたたびモンテカルロのカジノの近くの、暗い浜辺。すべてを、いわば自暴的に放棄し、ぼんやりしている主人公サロモン・ソロヴィッチに、あの女性(ドロレス・チャップリン)があらわれる。「大金なくしたわね」。主人公は答えず、ふたりは踊る。曲は哀愁に満ちたタンゴである。おそらく『手に手をとって』であろうか?光景が明るくなる。まだ、踊っている。主人公は言う。「なに、また贋札つくるさ」。ん〜、いいエンディングだ。
最後の字幕中も、この『タンゴ』は続く。
ミスマッチのようでいて、心を打つ。
なんと言ったって、タンゴ(Tango)は、カディス発祥。そうアンダルシアなのだから。
★★★★
〜私の雑感を付け加えます〜
私の観方を申します。この映画の主人公の「生き方」が素晴らしく心を打ちます。全ての強圧に耐え、体験しながらも、「イデオロギー」や「人種」などからは自立(自由でもいいです)した生き方です。とても「解放感」がある。
それと、冒頭に、アルゼンチンのパスポート作成の依頼があります。まさにアルゼンチンは当時、中立?をとったのでヒトラー政権の反対者はここに亡命します。でも、敗戦後、今度はヒトラーの残党がアルゼンチンに入るのです。確か、ナチの大物もここで逮捕された記憶があります。アルゼンチンの人口の内、現在は2%がドイツ人です(このことは僕の興味以外の何者でもないけれども)。
それと、史実とは違うけれども、映画中、主人公はソ連にいたと言っています。また、家族が収容所で死んだと言っています。これにはそうとうな示唆を感じます。何もヒトラーだけが人種偏見を持っていたわけではない。ファシズムを突然変異(そんなことはあり得ません)ではなく、超資本主義、国家主義ととらえた方が歴史の流れに合います。事実、スターリンもユダヤ人をラーゲリ(収容所)に入れ、シベリアに流刑しています。ですから、収容所の所長の発言、「俺は共産党員だったが、あれはめんどう臭くってナチになったのさ・・・!」というところで主人公と微妙に絡んで来ることのおもしろさがあります。きっと、映画では、主人公の家族はソ連のラーゲリで死んだようになっているのかもしれません。
主人公の贋札作りに反対し、抵抗を促す青年がいます。彼の妻はアウシュビッツで射殺されました。でも、主人公は彼を疎んじる仲間に、「仲間(青年)を裏切ったら殺すぞ!」って言います。このことに評論家は大概、「ユダヤ人としてのプライド?」と「抵抗」を想定しています。
私は違うと思います。彼が言う仲間とは、贋札づくりをする収容所の仲間のことであり、すでに深い悲しみの中から彼はユダヤ人からも自立していると思われます。
ポイントはもうひとつあり、その青年が自殺する流れです。彼は介抱されたものの妻を失ってしまい、解放後、反対してきた仲間にも許されたことで自殺したのでは無いと思います。解放され平和?になったことで、逆に彼が生きる(あるいは存在する)「根拠」(拠点と言いたい)を失ったことによるのではないかと私は考えます。彼も戦争犠牲者のひとつのあり方として描かれているのだと捉えました。
だんだん、解放軍がやってくる気配が彼らには分かっていたと思います(おそらく戦時中であっても収容所には情報は入っていたと思います)。そして、解放してくれたのはソ連ではなく連合軍であったという皮肉もあります。ワルシャワでもソ連=スターリンは許されないことをしていますよね。ここもまた面白いと思いました。
話しがそれますが、ロシアの民衆詩人エセーニンは民衆にも愛されますし、彼が批判をしたレーニンも彼を讃えます。しかし、世はボルシェビキの天下、民衆はこぞってコムソムル、コムソムルに流れて行きます。エセーニンはそれをとても憂います。でも晩年、故郷を愛し、さらに愛する母を失い、彼はだんだん絶望の淵に立ち、そして自殺します。血で「さ・よ・な・ら」って書いて・・・!私は稚拙ですがこのように解釈しています。「エセーニンは民衆に愛されたが故に、世の中の移ろいに悩み、ついに民衆との乖離を感じ自殺に至ったのではないか?つまり生存の(あるいは知の)拠点を失ったのではないか?と。
過去の大学闘争の活動家も、結局敗北し、己の存在拠点を失い放浪し、あるものはその存在拠点を宗教に求めたりするのを、私は沢山見ています。
その意味でも、「ヒトラーの贋札」の主人公は、様々で辛い経験の中から、民族を超え、イデオロギーを超えてしっかりと地に足をつけて自立し(あるいは自由)、「時の移ろいの中」を、その場その場の「現実をしっかりと歩んで行く」生き様に私は好感が持てて、我が観察に勝手に納得しているのです。
人物をあるいは人物のあり方を対比させたりするのは映画に多く見られることです。ですから何も『ヒトラーの贋札』だけではなく、これも私が好きな『LAコンフィデンシャル』、『ショーシャンクの空の下』でも表現されています。
また、数日前に書いた『ゆれる』の映画も主題を執拗に追っています。
しかし、『ヒトラーの贋札』は、その人間の生き様の対比のさせ方が強烈です。しかし、自然に穏やかにそれを表現しているところがこの映画の優れた面です。
『ヒトラーの贋札』は、もちろん「ナチ収容所での贋札つくり」ですが、作者が時代背景をここにとって表現しているのはとても感心します。そして、その戦争の中で生きる“人の生き方”として、大きく言うとまず主人公、反対を唱える青年、それに忘れてならないのはナチ収容所少佐の存在です。
繰り返しますが、少佐は映画の中で、「俺はむかし共産党員だったのだ、しかしあれはこむずかしくてナチになったのさ・・・」という面白い人物像に仕上げています。
それに主人公の存在。彼は言います、「俺は前にロシアにいた、家族も収容所で死んだ(ソ連のラーゲリとユダヤ迫害を想定させていて面白い)・・・」と。この絡みが映画の流れの柱になっていることに気付いて欲しいと思っています。主人公は寡黙でありますが、ひょっとしてロシアでは共産党員ではなかったのか?そしてスターリンの迫害にあうに至ったのではないか?と想像させます。その落ちが、作品後半で、主人公が、逃げ出す少佐を殺さなかった。つまり、“同期のよしみ?”の少しの情けと、「そんなことしてもどうってことじゃねーな」っていう秀でた生き方と思いが静かでありながらも圧倒的です。
つまり、コムニズムもファシズムもそんなものは同じでどうでもいい。作品の骨格を成す三人は、何れにしても「戦争の被害者」であり、作品は「時代の生き方」を三様で観せています。ちょっと横道に入りますが、私は高校生の若き頃、終戦?を超えてそのまま民主主義を説く先生をとても嫌い、その先生を痛烈に批判しました。先生はそれを自戒し、逆に私をとても心配してくれました。「何か、きみも、あまりにとらわれるなよ・・・」って言われている気がしました。また、私が反体制思想犯としてぶち込まれ(私はこのことを何とも思っていません)、その後に釈放され、街角で会った担当刑事はこう言いました、「おまえにはしてやられたよ〜。でもねえ、俺はおまえが好きだよ。どうかお母さんを大切にしてあげてね・・・!」。
“人あるいは人の生き方に”興味を持つ私は、この映画を観ながら過去を追憶し、今の自分はどうか?を問うています。
贋札造りに抵抗し交戦を促す青年、このあり方はもうひとつの意味を持っていて、「もうひとつの生き方を」表しています。彼は収容所内では仲間に“分かるけれど、困った存在・・・”です。
私が言う「存在拠点の喪失」は、きっとドイツの壁の崩壊の時も同じような現象あるいは心象として起きたのに違いありません。西と東がひとつになる。そうすると、簡単に言えば西を崇拝し生きてきた人々、東を崇拝し生きてきた人々は混乱の極みでしょう。いろいろなことがあったでしょう。そして、それをやがて乗り越えたのでしょう。
その頃、日本ではどうであったでしょう。
私が言いたい、あるいはこの映画が描きたかったのは、“そんなものからは自由であった方がいい”というもので、僕のことばで言えば「自立した生き方」です。言葉尻を捉えられて言われると困りますが、あらゆるものを相対化してしまう知力であります。共産主義からナチになった少佐。何れも「生きていく」のでしょう。それが民衆の知恵です。そこを見抜かない?と、結局、知の虜になってあやまちを犯します。そうです、ここではじめて、私は私が好きなエセーニンに象徴的な知の脆弱さに気付きました。
最後に笑い話をひとつ。日独伊三国同盟。初期に、あの女好きのムッソリーニは、ちょびひげヒトラーが大嫌いなのです。それで、ユダヤ迫害には不機嫌で、「ユダヤ難民所」をつくるんです。それで、この映画の中では、歌にイタリア民謡や歌曲が覆いのかなあ、なんて思います。
ムッソリーニは愛人を連れて逃げますが、とある村のパルチザンに捕まり処刑されます。そして、「逆さ吊り」にされ、晒し者にされます。ちょびひげヒトラーは、ここことにとても驚き、死後、我が肢体を焼け、と命令した、という伝えもあります。笑えます・・・・・
この『ヒトラーの贋札』で、仲間たちは皆、「解放まで生きよう」、「戦争が終わるまで生き抜こう」、「とにかく生きるのだ」と決意しています。私には、それは無言で狡獪で実行で、そして何物にも囚われない解放性をもった主人公が、組織したようにみえる。
「時代をどう生きるか」と問うとき、主人公、抵抗の青年、ナチの少佐も現実に生きている。残念なのは抵抗の青年の自殺だ。そこに、「知」の、「抵抗」の弱さを知る。
時代が変わったって、私たちも今生きている。いろんな生き方がある。ITのしっぽで儲ける者、少少の成功で傲慢になる者、大学を出てキャバレーの呼び込みをやっているM青年、アメリカ帰りの英語しか話せない日本人の売春婦、私に寄りひっしに女になろうとしたレズビアン、活路を見いだせない主婦、失業者のしたたかさ。
どうしようもない困窮。平気でそれを裏切る友情。
でも『生きる』ことには変わりはない。
しかし、私には権力とハーモニーして「義援ブーム」に乗る者たちは、“都合良く生きる”者たちにしかみえない。
私は、そんな情況の中で、「原形は存在し現象する」という概念を創造し、それをもって、私を縛ってきた「エセーニン」をあっという間に超えた。
ああ、映画の主人公には、どんな「原形」があったのだろうと考える。
とにかく生きよう!
『ヒトラーの贋札』は私の今の生き方を問うた。
今、私は「自前の思想」に「協調」をシンフォニーさせている。協調は私の場合、妥協ではなく、いわば「耕す」というもので、「ビジョンを持て」ということだ。
それは、アンダルシアの、北アフリカ人、出自の未だ不明な、西インドからきたジプシー、ユダヤ人、アラブ人の『融合』に起因する。
ふたたび、浜辺で踊る主人公と女性(ドロレス・チャップリン)、それに流れるタンゴ『手に手をとって』。「また、贋札造りをするさ・・・・」。
わあっ、たまりません!
★★★★★
1.この『ヒトラーの贋札』の感想〜総集編〜は、以前に2部作でトピックしたものを、まとめ、さらにストーリーを追ってみたものです。また、余計なものは省きました。
2.映画中に、流れる音楽をいくら調べても分かりませんでした。どなたか、教えて下さい。
3.最後に、この映画を薦めてくれた友に感謝します。
スタッフ [編集]
• 監督…シュテファン・ルツォヴィツキー
• 製作…ヨーゼフ・アイヒホルツァー
• 脚本…シュテファン・ルツォヴィツキー
• 音楽…マリウス・ルーラント
• 撮影監督…ベネディクト・ノイエンフェルス
• 撮影…ダニエル・パール
キャスト [編集]
• サロモン・ソロヴィッチ…カール・マルコヴィックス
• アドルフ・ブルガー…アウグスト・ディール
• フリードリヒ・ヘルツォーク親衛隊少佐…デーフィト・シュトリーゾフ
• アグライア…マリー・ボイマー
• クリンガー医師…アウグスト・ツィルナー
• ホルスト親衛隊小隊長:…マルティン・ブラムバッハ
• カジノの令嬢…ドロレス・チャップリン
その他 [編集]
• 第57回ベルリン国際映画祭コンペティション部門正式出品
• 第80回アカデミー賞外国語映画賞 オーストリア代表作品
|
|
|
|
|
|
|
|
★気軽に映画評論しよ☆ 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
★気軽に映画評論しよ☆のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75498人
- 2位
- 音楽が無いと生きていけない
- 196033人
- 3位
- 独り言
- 9047人