|
|
|
|
コメント(12)
DMEの話題にのり。。。
DMEの最大の問題点は、容量あたりの熱量ではないでしょうか。
基本的に、液体状態での搭載なのですが、軽油の半分のカロリーしか無いので、軽油の倍積まないと、同じ距離を走れません。(要するに、リットル換算の燃費は半分になる)
LPGなどのような、高圧タンクでの搭載になるので、タンクの形状に自由度が無く(基本的に円柱型)タンク自体の重量も増えます。
あとは、インフラ整備でしょう。それを考えると、10年で実用化できるかどうか。。。と言った所でしょうか。
ただ、自社で基地局をもてるような、近距離運送系やバス系では比較的可能かと思いますが、DME自体の知名度が低く、国はロシアからの天然ガスを押す方向なので、難しいでしょう。
おそらく、日野あたりが「DMEで行く!」とか宣言すれば、一気に各社本腰になるでしょう。
DMEの最大の問題点は、容量あたりの熱量ではないでしょうか。
基本的に、液体状態での搭載なのですが、軽油の半分のカロリーしか無いので、軽油の倍積まないと、同じ距離を走れません。(要するに、リットル換算の燃費は半分になる)
LPGなどのような、高圧タンクでの搭載になるので、タンクの形状に自由度が無く(基本的に円柱型)タンク自体の重量も増えます。
あとは、インフラ整備でしょう。それを考えると、10年で実用化できるかどうか。。。と言った所でしょうか。
ただ、自社で基地局をもてるような、近距離運送系やバス系では比較的可能かと思いますが、DME自体の知名度が低く、国はロシアからの天然ガスを押す方向なので、難しいでしょう。
おそらく、日野あたりが「DMEで行く!」とか宣言すれば、一気に各社本腰になるでしょう。
欧州では既に菜種油をベースとしたバイオマスディーゼル燃料が自動車用に普及しつつありますね。
硫黄分を含まないので触媒にも優しいでしょう。このあたり、規制強化で閉め出した日本のやり方が馬鹿に思えます。
それから、ガソリンエンジンでは、HCCIという燃焼技術を各自動車メーカーが頑張ってるようです。
ディーゼル同様に圧縮空気に燃料を吹いて自己着火させる方式で、これも欧州が主だったような・・・。
いやはや、デ○ソーはいつになったらボ○シュの先を行けるんだか。
日本郵船は船速を落とすことで燃費を向上させているようですね。
燃料消費は船速の3乗に比例するのだとか。皆さんスピードを控えましょう(笑)
硫黄分を含まないので触媒にも優しいでしょう。このあたり、規制強化で閉め出した日本のやり方が馬鹿に思えます。
それから、ガソリンエンジンでは、HCCIという燃焼技術を各自動車メーカーが頑張ってるようです。
ディーゼル同様に圧縮空気に燃料を吹いて自己着火させる方式で、これも欧州が主だったような・・・。
いやはや、デ○ソーはいつになったらボ○シュの先を行けるんだか。
日本郵船は船速を落とすことで燃費を向上させているようですね。
燃料消費は船速の3乗に比例するのだとか。皆さんスピードを控えましょう(笑)
確かに今や次世代燃料と言うと、
DME・バイオメタノール(混合も含む)等など有りますが、
やっぱり私もコストの問題で先ずは混合バイオ燃料が
有望かと思いますよ。
DMEは確かに合成ができますが、まだまだコストが高すぎるし、
バイオ燃料のみは、しんちゃんさんの仰るとおりエンジンの耐久性と供給がまだまだ。
特に耐久性はゴム樹脂部品の劣化が大きな問題です。
供給は、東南アジアでタロイモやサトウキビの大量生産を各社
研究しているようですから、その内なんとかなるかも知れませんね。
因みにHCCIは私も大学時代に研究してましたが、
あれはガソリンとディーゼルのあいの子(むしろディーゼル寄り)で、
既にいくつかのディーゼルエンジンでは、完全とはいかないまでも、
一部の運転領域でHCCIチックな燃焼を採用している様です。
ただ完全なHCCIは極端にピーキーなエンジンなので、
制御が難しく、まだまだこれからの様ですよ。
(暴走又は回らないとか、トルクが出ないか黒煙出しまくりになり易く、両立する領域は恐ろしく小さいんですよ〜)
DME・バイオメタノール(混合も含む)等など有りますが、
やっぱり私もコストの問題で先ずは混合バイオ燃料が
有望かと思いますよ。
DMEは確かに合成ができますが、まだまだコストが高すぎるし、
バイオ燃料のみは、しんちゃんさんの仰るとおりエンジンの耐久性と供給がまだまだ。
特に耐久性はゴム樹脂部品の劣化が大きな問題です。
供給は、東南アジアでタロイモやサトウキビの大量生産を各社
研究しているようですから、その内なんとかなるかも知れませんね。
因みにHCCIは私も大学時代に研究してましたが、
あれはガソリンとディーゼルのあいの子(むしろディーゼル寄り)で、
既にいくつかのディーゼルエンジンでは、完全とはいかないまでも、
一部の運転領域でHCCIチックな燃焼を採用している様です。
ただ完全なHCCIは極端にピーキーなエンジンなので、
制御が難しく、まだまだこれからの様ですよ。
(暴走又は回らないとか、トルクが出ないか黒煙出しまくりになり易く、両立する領域は恐ろしく小さいんですよ〜)
>>8
横スレ失礼
「燃焼スピードが遅い」のは,あくまで0.3, 0.4付近の「希薄混合」ではの話です.等量比0.7ですでにガソリンを上回るはずです.
しかし水素はストイキでは燃焼できませんので(0.7ですら難しいのでは)やはり「遅く」せざるを得ないのかな.
私はどうも水素とレシプロとの相性はよろしくないように思える.
理由としてノッキングが考えられると思われがちだが,つまりは燃焼時に容易に衝撃波が発生する点でしょう.
着火温度はガソリンのような炭化水素よりも高いことと燃焼速度が非常に高いことからエンドガス自着火はガソリンよりも発生しにくい可能性も考えられる.
しかしストイキ付近では既に火炎中に衝撃波を伴うようになり結果ノッキングと同じ結果を生んでしまう.したがって燃料混合にムラが生じれば全く使い物にならない.
それから燃焼時生成ガス組成の関係上動力の発生源となる筒内圧が得られ難い点である.その上ガス温度は高めであるなどレシプロには不都合が二重になって尚よろしくない.
結果メカロス分と冷却損失分が多くなり,効率が落ちてしまう.
さらに拍車をかけるように,水素火炎は消炎距離が小さく火炎からシリンダー壁面の距離がガソリンの場合より接近するため冷却損失分がさらに増量される(同じ燃焼ガス温度でも壁面に食われる熱量が多い).
車内の水素供給系,貯蔵系の安全性や搭載性を含めると車用にはあまりに不都合過ぎる.
ちなみに燃料電池は私の知る限り,総合効率(原料から生成し実際にエンジンで動力を得るまで一貫して比較した効率)があまりに悪い.あんなモノがメーカーや大学にアピールされるのは非専門家から受けが良いため,時間稼ぎと研究費ふんだくりに利用されているだけ.
そもそもH2生成にCO2をガソリン燃焼時と同じように排出するからクリーンとは言い切れない.コンバッション方式ならNOx大量放出で何の解決にもならないし.
横スレ失礼
「燃焼スピードが遅い」のは,あくまで0.3, 0.4付近の「希薄混合」ではの話です.等量比0.7ですでにガソリンを上回るはずです.
しかし水素はストイキでは燃焼できませんので(0.7ですら難しいのでは)やはり「遅く」せざるを得ないのかな.
私はどうも水素とレシプロとの相性はよろしくないように思える.
理由としてノッキングが考えられると思われがちだが,つまりは燃焼時に容易に衝撃波が発生する点でしょう.
着火温度はガソリンのような炭化水素よりも高いことと燃焼速度が非常に高いことからエンドガス自着火はガソリンよりも発生しにくい可能性も考えられる.
しかしストイキ付近では既に火炎中に衝撃波を伴うようになり結果ノッキングと同じ結果を生んでしまう.したがって燃料混合にムラが生じれば全く使い物にならない.
それから燃焼時生成ガス組成の関係上動力の発生源となる筒内圧が得られ難い点である.その上ガス温度は高めであるなどレシプロには不都合が二重になって尚よろしくない.
結果メカロス分と冷却損失分が多くなり,効率が落ちてしまう.
さらに拍車をかけるように,水素火炎は消炎距離が小さく火炎からシリンダー壁面の距離がガソリンの場合より接近するため冷却損失分がさらに増量される(同じ燃焼ガス温度でも壁面に食われる熱量が多い).
車内の水素供給系,貯蔵系の安全性や搭載性を含めると車用にはあまりに不都合過ぎる.
ちなみに燃料電池は私の知る限り,総合効率(原料から生成し実際にエンジンで動力を得るまで一貫して比較した効率)があまりに悪い.あんなモノがメーカーや大学にアピールされるのは非専門家から受けが良いため,時間稼ぎと研究費ふんだくりに利用されているだけ.
そもそもH2生成にCO2をガソリン燃焼時と同じように排出するからクリーンとは言い切れない.コンバッション方式ならNOx大量放出で何の解決にもならないし.
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
Engines 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
Enginesのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55348人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 89996人
- 3位
- 酒好き
- 170648人
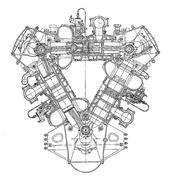


![ジェットエンジン [Jet Engine]](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/26/52/1142652_190s.jpg)







![MD-11など[後発エンジン]が好き](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/84/67/138467_106s.jpg)












