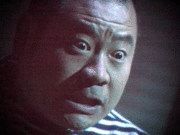※以前全英版で投稿させていただいた話の日本語バージョンです。
ちなみにコピペです。
英語バージョンはこちら↓
http://
どこかへ出かけたとき・・・たとえば旅行先や近所等どこでもいいが・・・むやみに「石」を拾ってはいけない、と言われる。日本人はもともと「自然信仰」が根深い民族だから、「樹木」や「石」「山」「川」「洞くつ」のように、自然界が産んだ様々なものに霊や神が宿るとし、永年あがめてきた。
だからその辺に他愛もなく転がっている石にも、もしかしたら「何か」が宿っているかもしれない、というのがこの言葉の意味だ。
信仰心が薄れた昨今でも、わたしたちはどこかでそれを信じている。そうして、「石を拾ってはいけない」なんて親から教え込まれると、例えそんな教訓を信じていなくとも、頭のかたすみに言葉がこびり着いて離れない。
わたしは信心深い人間ではないが、いまの生活に支障をきたさない範囲では、先人の教えに従うタチだ。だから石が欲しければ店で買うし、人工の物でも構わないと思う。だが、世の中にはどうしてもそういう物を欲しがる人間もいる。
友人に金魚に凝っている奴がいて、そのこだわりようは半端ではなかった。彼は新しく購入した大型水槽を彩る「石」を探していた。
気に入りの「石」を求めて、彼は方々のアクアリウムショップや園芸店を歩いたらしいが、なかなかピンとくる「石」がみつからない。ある日、彼はわたしに電話をかけてきて、「川に行かないか?」と、誘ってきた。
友人の目当てはもちろん「石」だ。河原を歩いて好みの石を拾ってくるのが目的だった。わたしはとても嫌な感じがして、そういう物を持ち帰らない方がいいと忠告した。だが彼は取り合わなかった。運良く(?)、二人で訪れた河原で彼は探し求めていた好みの「石」を見つけ、家に持ち帰った。
彼が石を持ち帰って1ヶ月ほど経った頃、別の友人からこんな噂を聞いた。アクアリウムに凝っている例の友人が、体調を崩して自宅療養しているらしい・・・と。
わたしは胸騒ぎがし、友人を見舞うことにした。あくる日は平日だったが、夏休みということで、家には小学校一年になる彼の子どもがいた。奥さんは勤めに出ているらしく、彼は大きなマスクをしたまま、不馴れな手付きで麦茶を出してくれた。
わたしの見舞いを喜んで、リビングをかいがいしく行き来する彼の姿は健康そのものだ。てきぱき動くし、顔色もいい。マスクをしているからには悪い夏風邪でもひいたのだろう、ぐらいにか思わなかった。
子どもがテレビゲームに夢中になっている隣で何時間か会話を楽しんで、その間、彼は麦茶のおかわりだの、スイカだの、かき氷だのを定期的にふるまってくれた。
彼の住まいはかなり田舎で、エアコンが無い。真夏でも、山から吹き降ろす涼しい風が心地よく風鈴を鳴らしてくれる。だがその日は異常に蒸し暑く、おまけに無風状態だった。汗っかきのわたしを気づかい、彼はなるべく冷たくて水分のあるものを出してくれたのだ。
その優しさに感謝しつつ、わたしは不思議に思った。わたしに飲み物やスイカを勧める彼が、まったく何も口にしていないことに。
マスクをとって、何か飲んだ方がいいんじゃないか?
わたしが言うと、彼の表情は強ばった。
いや・・・ちょっと、みっともなくて、人前じゃマスクをとれないんだ。
彼は訳を話した。会社を休んでいるのは別段体調が悪いわけではない。ある日突然、極度の顔面神経痛で鼻から下の右半分が麻痺してしまい、口を閉じる事ができない。食べ物もボトボト食べこぼすし、ヨダレも垂れ放題。サービス業だからこんな顔でお客さんの前に出る訳にも行かず、病院にいっても原因不明、おまけに治療しても改善しない。本当に途方に暮れている。彼は静かにそう語った。
その時だ、ゲームをしていた彼の息子がやってきて、しんみりしていた私たちに突然こう言った。
お父さんの顔がへんになったのは石のせいだよ。頭が戻りたいんだよ、きっと。
初めは何を言っているのかわからなかった。友人は「テレビの観すぎだ!!」と言って子どもを叱ったが、わたしはそんな友人をなだめ、どうしてそう思うのか子どもに訊いた。
彼の息子はわたしをリビングに飾られた大型水槽の前に連れて行き、美しくアレンジされたアクアリウムを指差した。流木や水草の間に、先日彼が河原で拾った石が置かれていた。彼の子どもは、この石が「何かの頭」だと言う。
小さなメロン大の石は、確かに、幼い子どもの頭ぐらいのサイズだが、別段「顔」には見えない。だが彼の息子はしげしげと石を見つめ、気味悪がった。わたしがしゃがんでその子の背丈まで視線を下げると、確かにそこに「顔」が現れた。
水槽の上にセットされた照明の具合で、子どもの目線からはあきらかな「顔」が見えていたのだ。永い年月の間にすっかり磨耗してしまった「お地蔵さんの頭」がそこにあった。
これが顔面神経痛の原因という証拠はないが、とにかくすぐに「石」を元の場所に戻した方がいいと言うわたしの言葉に従い、友人は「石」を元の河原に戻し、丁重に謝ったらしい。彼はその後三日ほどで職場に復帰し、偶然か、顔面神経痛も完治した。
「石」を無闇に拾ってくるものじゃない・・・偶然か本当か、皆さんも気をつけたほうがいい。
ちなみにコピペです。
英語バージョンはこちら↓
http://
どこかへ出かけたとき・・・たとえば旅行先や近所等どこでもいいが・・・むやみに「石」を拾ってはいけない、と言われる。日本人はもともと「自然信仰」が根深い民族だから、「樹木」や「石」「山」「川」「洞くつ」のように、自然界が産んだ様々なものに霊や神が宿るとし、永年あがめてきた。
だからその辺に他愛もなく転がっている石にも、もしかしたら「何か」が宿っているかもしれない、というのがこの言葉の意味だ。
信仰心が薄れた昨今でも、わたしたちはどこかでそれを信じている。そうして、「石を拾ってはいけない」なんて親から教え込まれると、例えそんな教訓を信じていなくとも、頭のかたすみに言葉がこびり着いて離れない。
わたしは信心深い人間ではないが、いまの生活に支障をきたさない範囲では、先人の教えに従うタチだ。だから石が欲しければ店で買うし、人工の物でも構わないと思う。だが、世の中にはどうしてもそういう物を欲しがる人間もいる。
友人に金魚に凝っている奴がいて、そのこだわりようは半端ではなかった。彼は新しく購入した大型水槽を彩る「石」を探していた。
気に入りの「石」を求めて、彼は方々のアクアリウムショップや園芸店を歩いたらしいが、なかなかピンとくる「石」がみつからない。ある日、彼はわたしに電話をかけてきて、「川に行かないか?」と、誘ってきた。
友人の目当てはもちろん「石」だ。河原を歩いて好みの石を拾ってくるのが目的だった。わたしはとても嫌な感じがして、そういう物を持ち帰らない方がいいと忠告した。だが彼は取り合わなかった。運良く(?)、二人で訪れた河原で彼は探し求めていた好みの「石」を見つけ、家に持ち帰った。
彼が石を持ち帰って1ヶ月ほど経った頃、別の友人からこんな噂を聞いた。アクアリウムに凝っている例の友人が、体調を崩して自宅療養しているらしい・・・と。
わたしは胸騒ぎがし、友人を見舞うことにした。あくる日は平日だったが、夏休みということで、家には小学校一年になる彼の子どもがいた。奥さんは勤めに出ているらしく、彼は大きなマスクをしたまま、不馴れな手付きで麦茶を出してくれた。
わたしの見舞いを喜んで、リビングをかいがいしく行き来する彼の姿は健康そのものだ。てきぱき動くし、顔色もいい。マスクをしているからには悪い夏風邪でもひいたのだろう、ぐらいにか思わなかった。
子どもがテレビゲームに夢中になっている隣で何時間か会話を楽しんで、その間、彼は麦茶のおかわりだの、スイカだの、かき氷だのを定期的にふるまってくれた。
彼の住まいはかなり田舎で、エアコンが無い。真夏でも、山から吹き降ろす涼しい風が心地よく風鈴を鳴らしてくれる。だがその日は異常に蒸し暑く、おまけに無風状態だった。汗っかきのわたしを気づかい、彼はなるべく冷たくて水分のあるものを出してくれたのだ。
その優しさに感謝しつつ、わたしは不思議に思った。わたしに飲み物やスイカを勧める彼が、まったく何も口にしていないことに。
マスクをとって、何か飲んだ方がいいんじゃないか?
わたしが言うと、彼の表情は強ばった。
いや・・・ちょっと、みっともなくて、人前じゃマスクをとれないんだ。
彼は訳を話した。会社を休んでいるのは別段体調が悪いわけではない。ある日突然、極度の顔面神経痛で鼻から下の右半分が麻痺してしまい、口を閉じる事ができない。食べ物もボトボト食べこぼすし、ヨダレも垂れ放題。サービス業だからこんな顔でお客さんの前に出る訳にも行かず、病院にいっても原因不明、おまけに治療しても改善しない。本当に途方に暮れている。彼は静かにそう語った。
その時だ、ゲームをしていた彼の息子がやってきて、しんみりしていた私たちに突然こう言った。
お父さんの顔がへんになったのは石のせいだよ。頭が戻りたいんだよ、きっと。
初めは何を言っているのかわからなかった。友人は「テレビの観すぎだ!!」と言って子どもを叱ったが、わたしはそんな友人をなだめ、どうしてそう思うのか子どもに訊いた。
彼の息子はわたしをリビングに飾られた大型水槽の前に連れて行き、美しくアレンジされたアクアリウムを指差した。流木や水草の間に、先日彼が河原で拾った石が置かれていた。彼の子どもは、この石が「何かの頭」だと言う。
小さなメロン大の石は、確かに、幼い子どもの頭ぐらいのサイズだが、別段「顔」には見えない。だが彼の息子はしげしげと石を見つめ、気味悪がった。わたしがしゃがんでその子の背丈まで視線を下げると、確かにそこに「顔」が現れた。
水槽の上にセットされた照明の具合で、子どもの目線からはあきらかな「顔」が見えていたのだ。永い年月の間にすっかり磨耗してしまった「お地蔵さんの頭」がそこにあった。
これが顔面神経痛の原因という証拠はないが、とにかくすぐに「石」を元の場所に戻した方がいいと言うわたしの言葉に従い、友人は「石」を元の河原に戻し、丁重に謝ったらしい。彼はその後三日ほどで職場に復帰し、偶然か、顔面神経痛も完治した。
「石」を無闇に拾ってくるものじゃない・・・偶然か本当か、皆さんも気をつけたほうがいい。
|
|
|
|
|
|
|
|
とにかく怖い話。 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
とにかく怖い話。のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55345人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37847人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人