ボストン日本人研究者交流会(第79回)のご案内です。
(マルチポストでお知らせしております)
今回は、MITの上田善文さんから、脳における記憶の仕組みについて最新の研究を
ご紹介いただきます。早稲田大学教授でハーバード大学リサーチフェローの山本武
彦先生からは、科学技術が国家の安全保障にどう影響しているのかについて論じて
いただきます。脳研究をはじめとして皆様が関わる最先端の技術・研究が、実は国
家間の力のバランスにどう影響するのか、大きく視野を広げてみる格好の機会かと
思われます。皆様ぜひ奮ってご参加ください。
なお、参加のお申し込みはWebフォームにてお願いいたします(登録作業を潤滑に
するためです)。
◆日時:2009月3月14日(土)16:00より(受付開始15:30)。その後、近辺で懇親会
★発表会: 16:00-19:30
★懇親会: 19:45-
◆報告会会場: MITのE51-315教室
http://
◆申し込み期限: 3月12日(木)午後9時
※事前申し込みのない方の参加はお断りする場合があります。
◆参加のお申し込みは下記のWebフォームにてご連絡下さい。
https:/
※パートナーの方は、備考欄にお名前、懇親会参加の可否だけ表記していただけれ
ば結構です。
なお、Webサイトに接続できない方は、従来通りメールでのお申し込みも受けいた
します。下記の6項目を記入して次のメールアドレスまでお送りください。
bostonJRF-owner@egroups.co.jp
★氏名
★米国での所属
★日本での所属
★研究・専門テーマ(現在あるいは過去)
★懇親会参加の可否
★発表できるテーマ(可能であれば)
◆今月のテーマ
---------------------------------------------------
【テーマ1】
「記憶したときに脳において何が起きているのだろう?」
The Picower Institute for Learning and Memory Department of Brain and
Cognitive Sciences Massachusetts Institute of Technology
RIKEN-MIT Neuroscience Research Center
上田 善文
皆さんが、最近見た美しい風景はどんなところでしょうか?ナイアガラの滝?いや
いや、ボストンの町並み?皆さん、なんらかの答えを持っているはずです。これら
、感動とともに記憶したことは、みなさんの脳裏に焼きついて、しばらくの間、忘
れないでしょう。それでは、記憶する過程で皆さんの脳の中では何が起きているの
でしょうか?
脳は、1000億個の神経細胞の集合体です。これら膨大な数の神経細胞は、ネットワ
ークを構築し互いに連絡を取り合っています。ですので、これらの神経細胞達が、
何かを記憶する際に何らかの質的変化を起しているのでしょう。
今回の発表においては、神経細胞において、記憶する前と記憶した後での質的変化
とは、一体何なのか?また、どこまでわかっているのか?ということを、発表者が
日々行っている研究を通して、また、近年明らかになった事実などを含めてわかり
やすく話していきたいと考えています。
【テーマ2】
「東アジアにおける科学技術活動のもつ安全保障上の意味」
早稲田大学政治経済学術院教授
Research Fellow, Belfer Center for Science and International Affairs at
the John F. Kennedy School of Government, Harvard University
山本 武彦
―日米関係の枠組みのなかで―
科学技術の発展は、一面で持続的経済成長を促す要因となり、他面で国家の安全
保障や国際安全保障のあり方に重要な変化を及ぼす要因となってきた。言い換えれ
ば、日進月歩の勢いで進む科学技術活動は、人間生活の進歩にとって欠かす事の出
来ない成果を生み出すと同時に、大量破壊兵器や高度通常兵器の技術革新を促すと
いう二面性を常に纏う。こうした二面性を前提にして国々の政策決定者は、科学技
術が宿命として抱える国家安全保障と国際安全保障の契機を意識しながら自国の科
学技術政策の策定に勤しむ。
どの国家も自国の与件を前提にして安全保障政策を策定するが、自国の生存に関
る地戦略を次のような公式にしたがって描き出し、そしてそれぞれの国情に応じて
自国の地戦略的利益を追求してきた。
地戦略(geo-strategy)=地政学(geo-politics)+地経学(geo-economics)
問題は、このような公式に科学技術活動がどのような影響を及ぼすかである。結論
を先取りしていえば、科学技術活動は地政学と地経学を接続する媒介変数としての
意味をもち、政府は自国の国益のためにこれを「囲い込む」誘惑に駆られる。すな
わち、地技学(geo-science and technology)的な意味づけを与えてしまう。 わけ
ても軍事科学や軍事技術の最先端分野の研究は、自国の地政学的利益を確保するた
めにその内容は秘匿対象とされる。しかも、これらの科学技術活動のほとんどは民
生目的をも共時的に追求する。いわば、軍事・民生両用の科学技術活動として展開
される。最先端の研究であればあるほど、それらは国家安全保障上の目的と国際競
争力維持の目的から研究内容は秘匿対象となる。
このような問題意識から、アメリカが1980年代以降、現在に至るまでに一貫
して追求してきた地技学アプローチが、日米関係の枠組みのなかでどのように作動
し、時には対立の局面を彩り、ときには協調の力学を生み出してきたか、その赤裸
々な実相を描き出す。
---------------------------------------------------
◆参加費用
諸経費をまかなうため、以下の参加費用をお願いしております。
☆報告会+懇親会参加 $20
☆報告会のみ参加 $5
◆参加資格および会の趣旨は、こちらをご覧下さい。
http://
ボストン日本人研究者交流会のホームページ
http://
メーリングリストへの登録はこちらにお願いします。
bostonJRF-subscribe@yahoogroups.jp
◆問い合わせ先
bostonJRF-owner@egroups.co.jp
みなさまの参加をお待ちしております。
ボストン日本人研究者交流会、幹事一同
野澤 良久
Makoto Life Sciences Inc., Visiting Researcher
開発 徹
MIT Sloan School of Management, Graduate Student
高野 裕子
United Health Group Ingenix, Business Analyst
小野 雅裕
MIT Department of Aeronautics and Astronautics, PhD Candidate
北川 拓也
Harvard University Physics Department
荻野周史
Brigham and Women's Hospital, Dana-Farber Cancer Institute, Harvard
Medical School, and Harvard School of Public Health, Associate Professor
(マルチポストでお知らせしております)
今回は、MITの上田善文さんから、脳における記憶の仕組みについて最新の研究を
ご紹介いただきます。早稲田大学教授でハーバード大学リサーチフェローの山本武
彦先生からは、科学技術が国家の安全保障にどう影響しているのかについて論じて
いただきます。脳研究をはじめとして皆様が関わる最先端の技術・研究が、実は国
家間の力のバランスにどう影響するのか、大きく視野を広げてみる格好の機会かと
思われます。皆様ぜひ奮ってご参加ください。
なお、参加のお申し込みはWebフォームにてお願いいたします(登録作業を潤滑に
するためです)。
◆日時:2009月3月14日(土)16:00より(受付開始15:30)。その後、近辺で懇親会
★発表会: 16:00-19:30
★懇親会: 19:45-
◆報告会会場: MITのE51-315教室
http://
◆申し込み期限: 3月12日(木)午後9時
※事前申し込みのない方の参加はお断りする場合があります。
◆参加のお申し込みは下記のWebフォームにてご連絡下さい。
https:/
※パートナーの方は、備考欄にお名前、懇親会参加の可否だけ表記していただけれ
ば結構です。
なお、Webサイトに接続できない方は、従来通りメールでのお申し込みも受けいた
します。下記の6項目を記入して次のメールアドレスまでお送りください。
bostonJRF-owner@egroups.co.jp
★氏名
★米国での所属
★日本での所属
★研究・専門テーマ(現在あるいは過去)
★懇親会参加の可否
★発表できるテーマ(可能であれば)
◆今月のテーマ
---------------------------------------------------
【テーマ1】
「記憶したときに脳において何が起きているのだろう?」
The Picower Institute for Learning and Memory Department of Brain and
Cognitive Sciences Massachusetts Institute of Technology
RIKEN-MIT Neuroscience Research Center
上田 善文
皆さんが、最近見た美しい風景はどんなところでしょうか?ナイアガラの滝?いや
いや、ボストンの町並み?皆さん、なんらかの答えを持っているはずです。これら
、感動とともに記憶したことは、みなさんの脳裏に焼きついて、しばらくの間、忘
れないでしょう。それでは、記憶する過程で皆さんの脳の中では何が起きているの
でしょうか?
脳は、1000億個の神経細胞の集合体です。これら膨大な数の神経細胞は、ネットワ
ークを構築し互いに連絡を取り合っています。ですので、これらの神経細胞達が、
何かを記憶する際に何らかの質的変化を起しているのでしょう。
今回の発表においては、神経細胞において、記憶する前と記憶した後での質的変化
とは、一体何なのか?また、どこまでわかっているのか?ということを、発表者が
日々行っている研究を通して、また、近年明らかになった事実などを含めてわかり
やすく話していきたいと考えています。
【テーマ2】
「東アジアにおける科学技術活動のもつ安全保障上の意味」
早稲田大学政治経済学術院教授
Research Fellow, Belfer Center for Science and International Affairs at
the John F. Kennedy School of Government, Harvard University
山本 武彦
―日米関係の枠組みのなかで―
科学技術の発展は、一面で持続的経済成長を促す要因となり、他面で国家の安全
保障や国際安全保障のあり方に重要な変化を及ぼす要因となってきた。言い換えれ
ば、日進月歩の勢いで進む科学技術活動は、人間生活の進歩にとって欠かす事の出
来ない成果を生み出すと同時に、大量破壊兵器や高度通常兵器の技術革新を促すと
いう二面性を常に纏う。こうした二面性を前提にして国々の政策決定者は、科学技
術が宿命として抱える国家安全保障と国際安全保障の契機を意識しながら自国の科
学技術政策の策定に勤しむ。
どの国家も自国の与件を前提にして安全保障政策を策定するが、自国の生存に関
る地戦略を次のような公式にしたがって描き出し、そしてそれぞれの国情に応じて
自国の地戦略的利益を追求してきた。
地戦略(geo-strategy)=地政学(geo-politics)+地経学(geo-economics)
問題は、このような公式に科学技術活動がどのような影響を及ぼすかである。結論
を先取りしていえば、科学技術活動は地政学と地経学を接続する媒介変数としての
意味をもち、政府は自国の国益のためにこれを「囲い込む」誘惑に駆られる。すな
わち、地技学(geo-science and technology)的な意味づけを与えてしまう。 わけ
ても軍事科学や軍事技術の最先端分野の研究は、自国の地政学的利益を確保するた
めにその内容は秘匿対象とされる。しかも、これらの科学技術活動のほとんどは民
生目的をも共時的に追求する。いわば、軍事・民生両用の科学技術活動として展開
される。最先端の研究であればあるほど、それらは国家安全保障上の目的と国際競
争力維持の目的から研究内容は秘匿対象となる。
このような問題意識から、アメリカが1980年代以降、現在に至るまでに一貫
して追求してきた地技学アプローチが、日米関係の枠組みのなかでどのように作動
し、時には対立の局面を彩り、ときには協調の力学を生み出してきたか、その赤裸
々な実相を描き出す。
---------------------------------------------------
◆参加費用
諸経費をまかなうため、以下の参加費用をお願いしております。
☆報告会+懇親会参加 $20
☆報告会のみ参加 $5
◆参加資格および会の趣旨は、こちらをご覧下さい。
http://
ボストン日本人研究者交流会のホームページ
http://
メーリングリストへの登録はこちらにお願いします。
bostonJRF-subscribe@yahoogroups.jp
◆問い合わせ先
bostonJRF-owner@egroups.co.jp
みなさまの参加をお待ちしております。
ボストン日本人研究者交流会、幹事一同
野澤 良久
Makoto Life Sciences Inc., Visiting Researcher
開発 徹
MIT Sloan School of Management, Graduate Student
高野 裕子
United Health Group Ingenix, Business Analyst
小野 雅裕
MIT Department of Aeronautics and Astronautics, PhD Candidate
北川 拓也
Harvard University Physics Department
荻野周史
Brigham and Women's Hospital, Dana-Farber Cancer Institute, Harvard
Medical School, and Harvard School of Public Health, Associate Professor
|
|
|
|
|
|
|
|
Harvard Medical School Boston 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
Harvard Medical School Bostonのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90050人
- 2位
- 酒好き
- 170693人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208292人
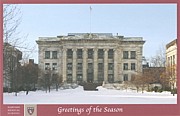

![[dir]ボストン/Boston](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/35/7/2033507_131s.gif)





















