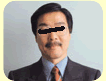最後に、二日前に届いた福岡大学の論文を載せておきます!まだ見てないと思うんで目だけ通してもらえたら助かります♪
第一章 百貨店の現状
現在、百貨店は売上減少が非常に大きく、それに伴い、来客数も減少している。地方百貨店においては、2000〜2002年の間で負債総額50億円以上の倒産が20社を超えている。その原因として、消化仕入れによる仕入方法、カテゴリーキラーの出現、大手ショッピングセンターの攻勢などが考えられる。このような問題点を打開するためには、顧客満足度を高めるため、顧客ニーズに対応可能な仕入方法を実践し、百貨店独自のPBを開発するなど、新たな魅力を創造しなければならない。
百貨店が登場するまで、人々は購入する意思がないにもかかわらず商品を眺めたり、複数の店舗を比較しながらどの商品を購入しようか迷ったりすることはなかった。百貨店において陳列販売が導入されるまで、消費者が買い物の楽しさを味わう環境は整備されていなかったのである。
百貨店の登場によって、小売店は単なる商品の購入場所ではなく、広く一般に開かれた楽しい空間になっていった。百貨店の高層はまちのランドマークであり、壮麗な装飾が施された店内には清潔なトイレが完備され、店によっては休憩室で無料のお菓子が振舞われた。その上、屋上には遊園地があり、店内では、展覧会やイベントが常に開かれている。しかも、百貨店の店内は、商品の購入と関係なくぶらぶら楽しむことが可能であった。
また、百貨店の取扱商品は幅広く、衣料品を中心に、家具や宝飾品から食料品まで斬新な商品が膨大に陳列されていた。そのため、従来の業種店とは異なり、一店舗で必要な商品すべてが取り揃えられることとなった。つまり、消費者は百貨店で新しい商品に出会い、その商品を通して、新しいライフスタイルを自らの生活に取り入れていったのである。
このように、今までの百貨店は消費者にとって新しい文化を吸収する場、優越感を得る場、楽しい場の代表であった。
第二章 経営悪化した原因
しかし、一章で述べたような、場であるはずの百貨店が今、衰退の危機にある。そのようになってしまった原因として以下の4つの点が挙げられる。
まず、第一点は「ターゲットを絞れていない」点である。従来、百貨店とは高級であり、消費者の憧れの場であるものであった。しかし、関東大震災や第二次世界大戦の影響で、日用品・食料品の需要が高まり、それに対応していくことによって百貨店が大衆化するようになった。また、その後人々の生活がある程度落ち着きを見せると、作っては売れる大量消費時代に入り、それから経済成長期に入り、人々は質の高い高級品を求めるよりはむしろ、新しいもの、戦後からの経済成長をはたした日本の豊かさが象徴されたものを求めるようになった。このように、百貨店は豊かな日本を求める消費者の需要に合わせて、次第に大衆化していってしまったのである。
このような大衆化は、物が売れた高度経済成長期やバブル景気下ではさほど問題は無かった。しかし、バブルが崩壊すると、人々は消費をしにくくなったため、大量に生産しても物が売れなくなってしまった。つまり、ターゲットを子供からお年寄りまでの幅広い年齢に設定していたため、品揃え時に莫大な費用を抱えることになってしまい、しかも、それが消費者にとって不必要なものであれば、消費者は購入しないのであるから、多大なリスクを抱えることになるのである。
この問題を解決するために、百貨店はターゲットを設定し、そのターゲットに見合った売り場作りを心がけようとした。しかし、大衆化時代の名残か、ターゲットは設定したものの、徹底して店全体の構成を考えている百貨店は少ないように思える。その上、現代の百貨店では、特にヤング層を動員することに力を入れている。団塊ジュニアマーケットの有望性は高く評価されているが、もともとの百貨店の支持顧客である40代以上の顧客への対応をなおざりにし、支持をなくしたことが、百貨店の存在基盤をも危うくしてしまった原因である。この40代以上の顧客は、これからの高齢化社会を考えていく上で、消費パワーを秘めた、決して軽視できない重要なマーケットであり、しかも今後30年は売り場を支えてくれる大切な世代である。百貨店はこのことを深く考える必要がある。
第二に「品揃えが同質化している」という点が挙げられる。バブル景気時には百貨店は消化仕入を採用していた。消化仕入とは、メーカー側が売り場に商品在庫を置き、売れた数量分だけ百貨店がメーカー側に支払うというものであり、百貨店側には、利益は少ないがリスクがなく、コストがかからずトレンドが追えるという利点があった。そして売れ残った商品は、メーカーが最終的に在庫として抱えることになる。その時の掛け率もおおよその基準はあるものの、ケースごとに決められていく。場合によっては、売り場作りも、年間を通じての細かい品揃えも、接客販売もすべてメーカー側が負担・運営するという条件もある。メーカー側にはこのような条件が一見不利に見えるが、実際には売場をメーカー側のコンセプトどおりに展開できること、価格主導権を持てること、情報発信が可能であり顧客の情報も得られること、百貨店の集客力や信頼を利用できることなどメーカー側にとっての利益の方が多く、売上を伸ばしていったのである。この消化仕入は物が売れたバブル景気下では、百貨店の売り場担当者がほとんど何もしなくても順調に売上がはじきだされる仕組みであったが、バブルの崩壊と共に、右肩上がりの売上がもはや見込めなくなると、売り場のあらゆることをメーカー側に任せていた百貨店では、客が物を買わなくなって売上が落ちてきても、新たな策を講じるノウハウが蓄積されていなかった。それどころか、消費市場の変化に気づかず、バブル時代の売り場をそのまま継続している百貨店も少なくなかったのである。売上が落ちているのに、どんな策を講じていいのかわからない。多くの百貨店は目先の売上を取るために、売れ筋を追いかけること奔走する。不利な条件にも関わらず、スーパーブランドを導入したり、アパレルが週単位で売れ筋を迅速に追加投入するシステムを確立し始めたりしたのである。このようにして百貨店は始めて経験した厳しい市場環境に対応しようとした結果、品揃えが同質化してしまい、一店舗独自の個性が見られなくなってしまったのである。かつては、ブランドと契約して百貨店ごとに独自の商品を持ち、その品揃えや様相は個々にさまざまなものを持っていたが、品揃えが同質化してしまった百貨店には魅力を感じられず、消費者に「百貨店はどこに行っても同じ」という感覚を植えつけてしまったのである。
第三に「メーカーの販売能力に頼りすぎて貸し場業的存在になっている」点が挙げられる。前述のように、バブル景気下の百貨店はメーカーに頼りっきりの経営を行っていた。しかし、バブルが崩壊すると同時に、メーカーからの派遣社員制度により百貨店販売員の能力の低さ、知識の無さ、販売ノウハウの無さが浮き彫りになっていった。例として百貨店販売員は顧客に対し、サイズがろくに合っていないのに、「裾が長ければめくって着るとおしゃれですよ。」あるいは「今はこれくらい大きめが流行りですから。」といった強引なセールストークで押し切ろうとするケースが頻繁にみられる。また、顧客にとっては、必要なときに来て欲しいというのが販売員に対する要望であるのに、実状はいて欲しくないときに来て、来て欲しいときにいないというものになってしまっている。必要なときに必要な知識を提供して欲しいという顧客のニーズに応えるため、販売員は、顧客の立場に立った接客をすることに努力していくことが必要である。また、時代が進むにつれ、顧客はもはや大量に消費しなくなり、マーケットの主導権は消費者に移行し、より魅力のあるもの、本当にほしいものしか買わなくなった。百貨店の売り場に魅力を感じなければ商品を買わないのである。メーカーに頼りっきりの経営を行っていた百貨店は顧客サイドに立った魅力的な売り場作りをするノウハウがなかった。現在の販売能力のない販売員では、減少していく売上を食い止めることもできなければ、売り場を魅力的にし、顧客を引き付けることもできない。
もともと、買取制とはメーカーから商品を買い取り百貨店が売る形式である。これであると消化仕入に比べ人件費が少なく、百貨店自らの価格設定ができ利益はあがるのが一番の特徴である。またメーカーに「〜して欲しい」と指示できるのである。いわばメーカーよりも立場は上なのである。そのため百貨店の販売員は商品知識・販売ノウハウが必要になり、消化仕入に比べ販売責任が重くなる。それと売れ残りリスクがあり、もちろん売れ残ったら百貨店が買い取ったものなので百貨店が処理しなくてはならない。メーカーに頼らず、買取制を行い、自らの販売員で販売を行おうという百貨店も出てきたが、販売能力の乏しい販売員では、売上をあげることができず、結局またメーカーに頼らざるを得なくなってしまったという事例もある。今までどおりメーカー頼りの消化仕入を行うことによって品揃えを豊富にし、顧客のニーズに応えることができ、人的コストも削減することができる。しかし、消化仕入のままでは、百貨店の利益が少なくなるばかりでなく、メーカーを超えての顧客への提案ができなくなる。かといって、今のまま買取制に移行すると逆に損失を出してしまう可能性の方が高い。したがって百貨店は現在の貸し場業的存在を改め、売れ筋ばかり追いかけるのではなく、コンセプトにあった売り場作りを心がけることが大切である。
第四に「衣料品の質が低下している」という点が挙げられる。衣料品の国内生産が減少し、海外生産が増大しているということも関係しているが、本来百貨店はメーカーと協力して独自の製品を作っていたため、多少高額になったとしても、質の高い商品を提供することができた。しかし、現在は消化仕入を採用しているので、商品の質がそのまま価格に反映されているわけではない。価格設定の内訳には、販売経費や売れ残り分のコストなどが上乗せされるのである。また、消化仕入の場合はメーカー側に全てを任せているので、商品管理を百貨店が行わない。したがって、メーカー基準の管理しかできないのである。メーカーと協力して独自に製品を開発していた時代では、質がそのまま価格に反映されていたため、消費者には「高級品ほど安心・安全である」という観念を持った人も少なくなかった。しかし、そのような人々が現在の百貨店の商品を見て、質がいいとは思えないのである。低品質の商品の価格がコスト分上乗せされているので、高価格の商品の質がいいとは、一概に言えなくなってしまったのである。また、メーカーによる商品管理もSCMなどの導入により簡潔化されてきた。最終段階で販売員が検品しないのであるから、商品の搬送途中などに傷がついてしまった場合、傷物が店頭にならんでしまう。こうした衣料品の質の低下は百貨店の信頼を欠くことにつながってしまう。この問題を打開するためには、百貨店がメーカーと協力し、価格に見合った商品を提供できるようなシステムを作ること、また、販売員による最終段階での商品の検品の徹底などを行う必要がある。百貨店には今まで培ってきた信頼と実績がある。消費者の満足を得るためにも商品の質を落として信頼を落とすようなことは決してあってはならないことである。
第三章 百貨店の魅力を向上させるには
第二章で述べた衰退の原因、欠点を改善させる必要があり、現在十分な集客パワーを持ち合わせ、強力であるカテゴリーキラーやショッピングセンター等のライバルとの差別化を図り、その失われた百貨店全体の魅力を再び向上させ、存在価値を高める必要があると言えよう。その後、ある程度百貨店のビジョンが確立され、安定した後に個々の百貨店の差別化を行えば、十分な相乗効果が得られるに違いない。前者が第一段階であり、後者がそれを基盤として構築する第二段階とでも言おう。これらの2ステップを踏むことでより力強いものとなるであろう。この章では第一段階において効果的と推測される我々の策を挙げていくことにする。
まず百貨店の現在の欠点を改善させるためにはやはり対象とするターゲット層を絞り、なおかつ他の百貨店との差別化を図ることが望ましいであろう。まずターゲットの限定についてであるが、従来の一般的ニーズを平均的に満たそうとするコンシューマー発想から、一点集中の「こういう客」というようにターゲットを具体化し、コンセプトを確立するカスタマー発想へとのシフトが望ましいと言えよう。まず現在「2007年問題」として取り上げられているように、団塊の世代と言われる方たちが一斉に定年退職を迎えると言われている60代以降、いわゆるシニア層が挙げられるであろう。このような社会現象を各業界も着目している。定年退職を迎えることで余暇も増え、また退職金等の給付により、現役世代と比較して時間と資金にも余裕が出てくるため、これらの世代をうまく刺激することで、これらの財力は莫大な可能性を秘めていると見込むことが十分可能であるからである。また次に、子供がある程度自立し、学費などの負担も比較的軽減され始める40〜50代いわゆるマチュア層が挙げられる。前者のシニア層にも共通して言えることであるが、これらの中高年と言われる年齢層、いわゆるマチュア層とシニア層を含む40〜60代は、商品等に対する高級志向・ホンモノ志向が強い傾向が見られ、また「美」に対する意識も高いため、実年齢よりも若い世代のものを身に付けていることも多く、様々なことに興味を持っているのである。そのため、このような年代はファッションや趣味等に対して出費を惜しまないため、少々値が張っても、高品質・信頼性が保証されているものであれば購入するのである。このように十分な需要が予測可能であるからこそ、ターゲットとする年齢層を絞り、本来百貨店の方針の根源にある「高級」というイメージを再確立し、このような世代に提供していけば、本来の百貨店の魅力を十分に発揮することができ、成功ビジョンは具体化されると言っても過言はないであろう。そのためにはコンセプトを明確にし、百貨店のイメージというものをも明確にしていく必要があると言えよう。この場合のコンセプトとは、やはり「高級さ」であり、どの業界もこの深刻な不況下において価格競争を強いられ、いかに低価格で販売するかに重点をおいているのが現状であるが、このような時代であるからこそ他との差別化が必要であるのである。「高級」をコンセプトとしている商業施設はない状況下で、百貨店の持ち合わせる「高級感」という要素は差別化を行う上で、最強のツールであろう。だからこそ「高級さ」の定義を徹底して定めて実現させる必要があるのである。現在の百貨店においても、高級さを感じさせる要素はない訳ではないが、中途半端で建前だけになっている点が多々見られる。そういった部分が現在の百貨店の低迷に少なくともリンクしているとも言えよう。まず、取り扱う商品が重要となるが、安売りというイメージのあるバーゲンを廃止し、高価ではあるが高品質である商品を取り揃えることで、価格競争下にあるスーパーなどで見られる「EDLP(Every Day Low Price)」という恒常的に低価格の商品を提供するスタイルと対極をなす、「EDHP(Every Day High Price)」という恒常的に高価格の商品を提供するスタイルを維持し、より一層『高級感』を追求していくのが望ましいと言えよう。こういったスタイルを取ることで、過剰な広告費が削減されるというメリットも持ち合わせている。またより安定したコンセプト確立の徹底のためには取り扱う商品はもちろんのこと、製品の品質詳細表示の徹底による安全保障やトイレなどの施設の充実や定員の対応・マナーの教育等に関しても、徹底して取り組むべきであろう。これらを行うことで「百貨店=高級」の方程式が成り立つに違いない。
ここで我々が考えた差別化を図る案を述べることにしよう。まず、中年層をターゲットにするからにはやはり、長時間百貨店に滞在しても疲労回復や息抜き、食事が可能である「いこいの場」が必要であろう。現在レストランは上層階に配置されている傾向が見られるが、体力面等を配慮するとやはり下層階が望ましいであろう。休憩スペースと言っても通路に設置されているベンチ程度である。この点に関して言うと、現在の百貨店においていこいの場が絶対的に不足していると言えよう。せっかく中高年の人々が高級志向で購買意欲を持っているのにも関わらず、そういった設備や施設が不十分であるがゆえに、非行動的になり、意欲を喪失してしまうという悪循環に陥ってしまっているのである。だから現在設置されているベンチとは別に、ターゲットである中年層の嗜好や環境に合わせて、いこいの場を設けるべきではないだろうか。そのような配慮が魅力の向上にリンクするのである。また次に、品質の安全性を向上させることが顧客の安心感を生み、信用・信頼される百貨店という概念を定着させることが必要であろう。その1つとして、製品の品質表示の徹底が挙げられる。品物によって表示方法や程度が異なるが、その品物に適した品質表示を行うことが望ましい。例えば、アパレル関係の製品であれば国名や性質、食品であれば産地や生産者などのように製品によって表示方法・要素を変化させる必要があると言えよう。ただ表示する、ただ多くの情報を載せるのではなく、必要な情報がパッと見ただけですぐに分かるような工夫を行うべきである。次に提案する案として、販売員の質の向上が挙げられる。現在の百貨店の場合、百貨店にテナントとして入っている店舗においてメーカーから派遣された従業員によって構成されている傾向にある。このような場合、自社ブランド製品を販売し、自社の売上高やマージンを増加させることだけに執着し、ご来店される顧客に見合うファッションをコーディネートするなどの本来のサービスを提供する点においては二の次になり、十分に行えていないという事態に陥ってしまい、販売員の質の低下が信頼性を低下させてしまう可能性がある。こういった事態を阻止するべく、現在の販売員に欠落しているコーディネート能力の強化やブランドの枠を超えて様々なブランドの商品の中からアイテムを抽出し、コーディネートを行う専門的なスキルを持った人材の育成を行う必要がある。現在このようなコーディネーターは数少なく、このようなスキルを十分身に付けるまでにはかなりの経験と時間を要することはやむを得ない。しかし、百貨店というフィールドにおいてコーディネーターの必要性・需要は絶大である。だからこそコーディネーターの育成を徹底して行い、様々な顧客の好み、ニーズに応じたファッションスタイルの提供を行うことで、顧客の信頼を得て確実な需要を得る必要があるのである。これらのコーディネートをサポートするべく、テナントの販売員はトレンドのアイテム情報をより正確にかつ迅速にコーディネーターに対して、また顧客に対して提供することが重要となってくるのである。こういった一人ひとりの顧客を対象に提供するサービスは美意識が高く高級志向の中高年に対してはかなり好感を抱かれ、自分専用のサービスを心地よく思うに違いない。サービス提供の面での差別化は効果的であろう。次にサービス提供に関連して、やはり百貨店の現在のメリットである交通面における利便性を徹底させるべきである。現在、商業施設と都心を循環するバスを定期的に運行させたり、購入金額がある一定の額を超えたら片道分の賃金が無料となったり、商業施設と交通機関の提携サービスが実施されているが、交通機関が充実している絶好の立地に位置する百貨店が十分な集客が期待できるサービスを提供することで、集客面において絶大な効果を発揮することが可能であると言っても過言ではないだろう。さらに現在導入され、普及し始めているインターネットを媒体とするネットショッピングについて述べることにしよう。やはり最大の難関はターゲットとする中高年がパソコンやインターネットに疎く、馴染みが希薄であるという点である。しかし、そういった年代の方々が利用したくなるような充実した機能・サービス・利便性を提供することでネット利用の意欲を向上させ、難関と思われた弱みが一転して強みに変わる可能性をも秘めているのではないだろうか。また、カテゴリーキラーやショッピングセンター(SC)のメリットとも言えるエンターテイメント性の要素を徹底追求し、百貨店にも導入することで明確なビジョン形成に効果的であると言えよう。
以上で述べたような策を実践し、より追求していくことによって、百貨店全体の魅力を向上させることが可能となり、現在客足が遠のいている百貨店に再び賑わいが戻ることを期待したい。
第四章 個々の百貨店の差別化
ここからは第三章で挙げたような案を実践し、百貨店全体の魅力を向上させた後、個々の百貨店における差別化つまり第二段階として行うべき案を述べていく。他の百貨店との差別化についてであるが、現在の百貨店を見て一目瞭然であるように、どこの百貨店も多少の差はあってもおおまかなスタンスに関してはどんぐりの背比べ状態であるのは言うまでもなかろう。このような同質化が百貨店の魅力を低迷させている要因のひとつとして挙げられる。これらの深刻な同質化を打開するべく、各々の百貨店が他にはない個性・魅力を際立たせる必要があるのである。
まず、メーカーとコラボレーションをして生み出す百貨店独自のPB(プライベート・ブランド)商品が挙げられる。百貨店業界で不動の一位を確立し、君臨する伊勢丹は顧客の声から生まれ、顧客の声と一緒に成長するというテーマで「オンリーアイ」というフレーズを用いて、厳選された商品を提供している。そこに行かなければ購入することのできないPB商品は言わば、他の百貨店との差別化を行う上でかなり強力なツールと言っても過言ではないだろう。現在PB商品を持っている百貨店は少ないし、また持ってはいても伸び悩み、その強力なツールをうまく活用しきれていない傾向が見られる。PB商品という強力なツールをうまく活用せずにいるのは宝の持ち腐れである。PB商品の本来の潜在能力を発揮するためには独自開発ももちろん良いが、百貨店はやはりPB商品開発においては能力的に劣る点があるため、様々なブランドとコラボレーションをすることで支援による安定した財政面におけるサポートやブランドが有するカリスマ性、ブランド側のアイデアを大いにフル活用することで、魅力のあるPB商品を協力し合って作成し、消費者の購買意欲を刺激し、結果的に百貨店の魅力を引き出すこともなし得るであろう。各百貨店が各々PB商品を提供することで、差別化はより一層明確になり、個々の輪郭が鮮明に形成されるに違いない。これらによって同質化されたどんぐりの背比べ状態も解消され、各々の百貨店がそれぞれ輝きを放つことも十分実現可能であろう。
また中高年をターゲットとするからには起床時間が早い等のライフスタイルを考慮して、開閉時間の調節を行うことも効果的であろう。
さらに、百貨店全体の魅力の向上においても挙げたが、「いこいの場」の雰囲気作りやコンセプト次第で全体だけでなく、個々の百貨店の差別化も図れるのではなかろうか。例えば、同世代の人たちと語らうコミュニケーションの場を設けるなどはどうであろうか。そこでは催し物や展示会をステージなどで行ったり、地域に根付いた新鮮な農産物や水産物を用いて調理した料理などをバイキング感覚で振る舞ったり、産地直送の産物を販売したりして、かしこまった感じではなく、一人で来られる方やうまく馴染むことが苦手な方でも気軽に足を運べて、様々な方に「体と心のリラックス」をして頂くことが可能な雰囲気作りを心掛けることが効果的であろう。このようにその地域によってテーマ設定を行い、百貨店における同質化を回避すべきである。ただひとつこの案には考慮すべき点がある。それは快適なコミュニケーションの場を提供するため、アットホームな雰囲気作りが行き過ぎると地域色が濃くなりすぎて、先に述べた「高級さ」の追求に関してはかけ離れてしまうという問題が危惧されるという点である。これらの矛盾点を回避するためには、過剰にならない程度に地域性を取り入れつつ、かつ適度に規律付けを行い、いこいの場の雰囲気作りとして建具や壁紙、照明、家具等で高級感を醸し出すことが重要となってくるのである。こういった雰囲気作りを行うことで中年層の意欲を刺激し、憩いを求めて足を運ぶ方やそういった施設があるということでゆっくりと買い物をされる方など、様々な面で能動的に作用するのである。
またカテゴリーキラーやSC等のライバルが持ち合わせるメリットであるエンターテイメント性の要素を導入することが挙げられる。これも全体の魅力を向上させる案として挙げたが、個々の百貨店における差別化においても効果的なツールだろう。例として、そごう横浜店のダイニングパーク横浜が挙げられる。単なるレストラン街ではなく、「百貨店=高級」というイメージを崩すことなくエンターテイメント性をうまく盛り込み、新しい施設を誕生させている。フロアの内装はヨーロッパの街並み等を模し、店内中央には庭園を設置しているのである。この庭園は一日の時間の流れを演出するため、照明を夕方になると明かりが落ちるなど横浜の日照とリンクさせて調整している。また店内にはこの庭園を眺めながら食事を楽しむことのできる店舗や、庭園とは別に横浜の港を眺望できる店舗などを設置している。このように従来の百貨店に欠落していたエンターテイメント性を大きく反映させると同時に、横浜でしか出来ない、その場所でしか味わうことの出来ないという他の百貨店との差別化も確立されていると言えよう。
第五章 将来の百貨店の展望
それでは、百貨店がどうしたら衰退の危機を脱出し、活気を取り戻すかを一章からの流れにそって簡単に説明したい。
百貨店の差別化により、徹底した高級感が口コミで広がり、イメージがアップする。すると今までは百貨店からアパレルメーカーに出店を希望していたものが、逆にメーカー側からこの百貨店に入店を希望するようになる。もちろん高級路線を行く百貨店に入店を希望ということは有名なブランドである。その有名ブランドとコラボレーションを組みPBの開発をする。ここがターニングポイントでそれまでは消化仕入を行うが、この有名ブランドからの入店があった頃から買取制に移行し百貨店側がメーカーに指示を出せるようにする。また、コラボレーションで作ったPBを期間限定発売するなどこの店にしかないPBにプラスαを加えることにより購買意欲が増し、百貨店のイメージはさらにアップするのである。買取制による最大のリスクである、売れ残りをどうするかについては百貨店とは別にアウトレットモールとの提携を組み百貨店の中でなくそこで売るという形を取れば問題は解決される。
以上、対象とするターゲット層の限定と差別化を軸に具体案などを用いて三章と四章で二段階構成で論じてきたが、百貨店自体は以前のように活気を取り戻して輝きを放ち、魅力のあるものへと再び返り咲く力は十分持ち合わせているので、現在のスタイルにおける欠点を正面から捉えて、我々が思案したような改善策を見出し実現していくことで、百貨店が再び「百貨店」らしさを取り戻し、誰にも真似しがたい不動のものとなる日が到来することを心待ちにしている。
参考引用・文献
石原武政・矢作敏行著『日本の流通100年』有斐閣、2004年、380pp
川島蓉子著『伊勢丹な人々』日本済新聞社、2005年、216pp
11251文字
第一章 百貨店の現状
現在、百貨店は売上減少が非常に大きく、それに伴い、来客数も減少している。地方百貨店においては、2000〜2002年の間で負債総額50億円以上の倒産が20社を超えている。その原因として、消化仕入れによる仕入方法、カテゴリーキラーの出現、大手ショッピングセンターの攻勢などが考えられる。このような問題点を打開するためには、顧客満足度を高めるため、顧客ニーズに対応可能な仕入方法を実践し、百貨店独自のPBを開発するなど、新たな魅力を創造しなければならない。
百貨店が登場するまで、人々は購入する意思がないにもかかわらず商品を眺めたり、複数の店舗を比較しながらどの商品を購入しようか迷ったりすることはなかった。百貨店において陳列販売が導入されるまで、消費者が買い物の楽しさを味わう環境は整備されていなかったのである。
百貨店の登場によって、小売店は単なる商品の購入場所ではなく、広く一般に開かれた楽しい空間になっていった。百貨店の高層はまちのランドマークであり、壮麗な装飾が施された店内には清潔なトイレが完備され、店によっては休憩室で無料のお菓子が振舞われた。その上、屋上には遊園地があり、店内では、展覧会やイベントが常に開かれている。しかも、百貨店の店内は、商品の購入と関係なくぶらぶら楽しむことが可能であった。
また、百貨店の取扱商品は幅広く、衣料品を中心に、家具や宝飾品から食料品まで斬新な商品が膨大に陳列されていた。そのため、従来の業種店とは異なり、一店舗で必要な商品すべてが取り揃えられることとなった。つまり、消費者は百貨店で新しい商品に出会い、その商品を通して、新しいライフスタイルを自らの生活に取り入れていったのである。
このように、今までの百貨店は消費者にとって新しい文化を吸収する場、優越感を得る場、楽しい場の代表であった。
第二章 経営悪化した原因
しかし、一章で述べたような、場であるはずの百貨店が今、衰退の危機にある。そのようになってしまった原因として以下の4つの点が挙げられる。
まず、第一点は「ターゲットを絞れていない」点である。従来、百貨店とは高級であり、消費者の憧れの場であるものであった。しかし、関東大震災や第二次世界大戦の影響で、日用品・食料品の需要が高まり、それに対応していくことによって百貨店が大衆化するようになった。また、その後人々の生活がある程度落ち着きを見せると、作っては売れる大量消費時代に入り、それから経済成長期に入り、人々は質の高い高級品を求めるよりはむしろ、新しいもの、戦後からの経済成長をはたした日本の豊かさが象徴されたものを求めるようになった。このように、百貨店は豊かな日本を求める消費者の需要に合わせて、次第に大衆化していってしまったのである。
このような大衆化は、物が売れた高度経済成長期やバブル景気下ではさほど問題は無かった。しかし、バブルが崩壊すると、人々は消費をしにくくなったため、大量に生産しても物が売れなくなってしまった。つまり、ターゲットを子供からお年寄りまでの幅広い年齢に設定していたため、品揃え時に莫大な費用を抱えることになってしまい、しかも、それが消費者にとって不必要なものであれば、消費者は購入しないのであるから、多大なリスクを抱えることになるのである。
この問題を解決するために、百貨店はターゲットを設定し、そのターゲットに見合った売り場作りを心がけようとした。しかし、大衆化時代の名残か、ターゲットは設定したものの、徹底して店全体の構成を考えている百貨店は少ないように思える。その上、現代の百貨店では、特にヤング層を動員することに力を入れている。団塊ジュニアマーケットの有望性は高く評価されているが、もともとの百貨店の支持顧客である40代以上の顧客への対応をなおざりにし、支持をなくしたことが、百貨店の存在基盤をも危うくしてしまった原因である。この40代以上の顧客は、これからの高齢化社会を考えていく上で、消費パワーを秘めた、決して軽視できない重要なマーケットであり、しかも今後30年は売り場を支えてくれる大切な世代である。百貨店はこのことを深く考える必要がある。
第二に「品揃えが同質化している」という点が挙げられる。バブル景気時には百貨店は消化仕入を採用していた。消化仕入とは、メーカー側が売り場に商品在庫を置き、売れた数量分だけ百貨店がメーカー側に支払うというものであり、百貨店側には、利益は少ないがリスクがなく、コストがかからずトレンドが追えるという利点があった。そして売れ残った商品は、メーカーが最終的に在庫として抱えることになる。その時の掛け率もおおよその基準はあるものの、ケースごとに決められていく。場合によっては、売り場作りも、年間を通じての細かい品揃えも、接客販売もすべてメーカー側が負担・運営するという条件もある。メーカー側にはこのような条件が一見不利に見えるが、実際には売場をメーカー側のコンセプトどおりに展開できること、価格主導権を持てること、情報発信が可能であり顧客の情報も得られること、百貨店の集客力や信頼を利用できることなどメーカー側にとっての利益の方が多く、売上を伸ばしていったのである。この消化仕入は物が売れたバブル景気下では、百貨店の売り場担当者がほとんど何もしなくても順調に売上がはじきだされる仕組みであったが、バブルの崩壊と共に、右肩上がりの売上がもはや見込めなくなると、売り場のあらゆることをメーカー側に任せていた百貨店では、客が物を買わなくなって売上が落ちてきても、新たな策を講じるノウハウが蓄積されていなかった。それどころか、消費市場の変化に気づかず、バブル時代の売り場をそのまま継続している百貨店も少なくなかったのである。売上が落ちているのに、どんな策を講じていいのかわからない。多くの百貨店は目先の売上を取るために、売れ筋を追いかけること奔走する。不利な条件にも関わらず、スーパーブランドを導入したり、アパレルが週単位で売れ筋を迅速に追加投入するシステムを確立し始めたりしたのである。このようにして百貨店は始めて経験した厳しい市場環境に対応しようとした結果、品揃えが同質化してしまい、一店舗独自の個性が見られなくなってしまったのである。かつては、ブランドと契約して百貨店ごとに独自の商品を持ち、その品揃えや様相は個々にさまざまなものを持っていたが、品揃えが同質化してしまった百貨店には魅力を感じられず、消費者に「百貨店はどこに行っても同じ」という感覚を植えつけてしまったのである。
第三に「メーカーの販売能力に頼りすぎて貸し場業的存在になっている」点が挙げられる。前述のように、バブル景気下の百貨店はメーカーに頼りっきりの経営を行っていた。しかし、バブルが崩壊すると同時に、メーカーからの派遣社員制度により百貨店販売員の能力の低さ、知識の無さ、販売ノウハウの無さが浮き彫りになっていった。例として百貨店販売員は顧客に対し、サイズがろくに合っていないのに、「裾が長ければめくって着るとおしゃれですよ。」あるいは「今はこれくらい大きめが流行りですから。」といった強引なセールストークで押し切ろうとするケースが頻繁にみられる。また、顧客にとっては、必要なときに来て欲しいというのが販売員に対する要望であるのに、実状はいて欲しくないときに来て、来て欲しいときにいないというものになってしまっている。必要なときに必要な知識を提供して欲しいという顧客のニーズに応えるため、販売員は、顧客の立場に立った接客をすることに努力していくことが必要である。また、時代が進むにつれ、顧客はもはや大量に消費しなくなり、マーケットの主導権は消費者に移行し、より魅力のあるもの、本当にほしいものしか買わなくなった。百貨店の売り場に魅力を感じなければ商品を買わないのである。メーカーに頼りっきりの経営を行っていた百貨店は顧客サイドに立った魅力的な売り場作りをするノウハウがなかった。現在の販売能力のない販売員では、減少していく売上を食い止めることもできなければ、売り場を魅力的にし、顧客を引き付けることもできない。
もともと、買取制とはメーカーから商品を買い取り百貨店が売る形式である。これであると消化仕入に比べ人件費が少なく、百貨店自らの価格設定ができ利益はあがるのが一番の特徴である。またメーカーに「〜して欲しい」と指示できるのである。いわばメーカーよりも立場は上なのである。そのため百貨店の販売員は商品知識・販売ノウハウが必要になり、消化仕入に比べ販売責任が重くなる。それと売れ残りリスクがあり、もちろん売れ残ったら百貨店が買い取ったものなので百貨店が処理しなくてはならない。メーカーに頼らず、買取制を行い、自らの販売員で販売を行おうという百貨店も出てきたが、販売能力の乏しい販売員では、売上をあげることができず、結局またメーカーに頼らざるを得なくなってしまったという事例もある。今までどおりメーカー頼りの消化仕入を行うことによって品揃えを豊富にし、顧客のニーズに応えることができ、人的コストも削減することができる。しかし、消化仕入のままでは、百貨店の利益が少なくなるばかりでなく、メーカーを超えての顧客への提案ができなくなる。かといって、今のまま買取制に移行すると逆に損失を出してしまう可能性の方が高い。したがって百貨店は現在の貸し場業的存在を改め、売れ筋ばかり追いかけるのではなく、コンセプトにあった売り場作りを心がけることが大切である。
第四に「衣料品の質が低下している」という点が挙げられる。衣料品の国内生産が減少し、海外生産が増大しているということも関係しているが、本来百貨店はメーカーと協力して独自の製品を作っていたため、多少高額になったとしても、質の高い商品を提供することができた。しかし、現在は消化仕入を採用しているので、商品の質がそのまま価格に反映されているわけではない。価格設定の内訳には、販売経費や売れ残り分のコストなどが上乗せされるのである。また、消化仕入の場合はメーカー側に全てを任せているので、商品管理を百貨店が行わない。したがって、メーカー基準の管理しかできないのである。メーカーと協力して独自に製品を開発していた時代では、質がそのまま価格に反映されていたため、消費者には「高級品ほど安心・安全である」という観念を持った人も少なくなかった。しかし、そのような人々が現在の百貨店の商品を見て、質がいいとは思えないのである。低品質の商品の価格がコスト分上乗せされているので、高価格の商品の質がいいとは、一概に言えなくなってしまったのである。また、メーカーによる商品管理もSCMなどの導入により簡潔化されてきた。最終段階で販売員が検品しないのであるから、商品の搬送途中などに傷がついてしまった場合、傷物が店頭にならんでしまう。こうした衣料品の質の低下は百貨店の信頼を欠くことにつながってしまう。この問題を打開するためには、百貨店がメーカーと協力し、価格に見合った商品を提供できるようなシステムを作ること、また、販売員による最終段階での商品の検品の徹底などを行う必要がある。百貨店には今まで培ってきた信頼と実績がある。消費者の満足を得るためにも商品の質を落として信頼を落とすようなことは決してあってはならないことである。
第三章 百貨店の魅力を向上させるには
第二章で述べた衰退の原因、欠点を改善させる必要があり、現在十分な集客パワーを持ち合わせ、強力であるカテゴリーキラーやショッピングセンター等のライバルとの差別化を図り、その失われた百貨店全体の魅力を再び向上させ、存在価値を高める必要があると言えよう。その後、ある程度百貨店のビジョンが確立され、安定した後に個々の百貨店の差別化を行えば、十分な相乗効果が得られるに違いない。前者が第一段階であり、後者がそれを基盤として構築する第二段階とでも言おう。これらの2ステップを踏むことでより力強いものとなるであろう。この章では第一段階において効果的と推測される我々の策を挙げていくことにする。
まず百貨店の現在の欠点を改善させるためにはやはり対象とするターゲット層を絞り、なおかつ他の百貨店との差別化を図ることが望ましいであろう。まずターゲットの限定についてであるが、従来の一般的ニーズを平均的に満たそうとするコンシューマー発想から、一点集中の「こういう客」というようにターゲットを具体化し、コンセプトを確立するカスタマー発想へとのシフトが望ましいと言えよう。まず現在「2007年問題」として取り上げられているように、団塊の世代と言われる方たちが一斉に定年退職を迎えると言われている60代以降、いわゆるシニア層が挙げられるであろう。このような社会現象を各業界も着目している。定年退職を迎えることで余暇も増え、また退職金等の給付により、現役世代と比較して時間と資金にも余裕が出てくるため、これらの世代をうまく刺激することで、これらの財力は莫大な可能性を秘めていると見込むことが十分可能であるからである。また次に、子供がある程度自立し、学費などの負担も比較的軽減され始める40〜50代いわゆるマチュア層が挙げられる。前者のシニア層にも共通して言えることであるが、これらの中高年と言われる年齢層、いわゆるマチュア層とシニア層を含む40〜60代は、商品等に対する高級志向・ホンモノ志向が強い傾向が見られ、また「美」に対する意識も高いため、実年齢よりも若い世代のものを身に付けていることも多く、様々なことに興味を持っているのである。そのため、このような年代はファッションや趣味等に対して出費を惜しまないため、少々値が張っても、高品質・信頼性が保証されているものであれば購入するのである。このように十分な需要が予測可能であるからこそ、ターゲットとする年齢層を絞り、本来百貨店の方針の根源にある「高級」というイメージを再確立し、このような世代に提供していけば、本来の百貨店の魅力を十分に発揮することができ、成功ビジョンは具体化されると言っても過言はないであろう。そのためにはコンセプトを明確にし、百貨店のイメージというものをも明確にしていく必要があると言えよう。この場合のコンセプトとは、やはり「高級さ」であり、どの業界もこの深刻な不況下において価格競争を強いられ、いかに低価格で販売するかに重点をおいているのが現状であるが、このような時代であるからこそ他との差別化が必要であるのである。「高級」をコンセプトとしている商業施設はない状況下で、百貨店の持ち合わせる「高級感」という要素は差別化を行う上で、最強のツールであろう。だからこそ「高級さ」の定義を徹底して定めて実現させる必要があるのである。現在の百貨店においても、高級さを感じさせる要素はない訳ではないが、中途半端で建前だけになっている点が多々見られる。そういった部分が現在の百貨店の低迷に少なくともリンクしているとも言えよう。まず、取り扱う商品が重要となるが、安売りというイメージのあるバーゲンを廃止し、高価ではあるが高品質である商品を取り揃えることで、価格競争下にあるスーパーなどで見られる「EDLP(Every Day Low Price)」という恒常的に低価格の商品を提供するスタイルと対極をなす、「EDHP(Every Day High Price)」という恒常的に高価格の商品を提供するスタイルを維持し、より一層『高級感』を追求していくのが望ましいと言えよう。こういったスタイルを取ることで、過剰な広告費が削減されるというメリットも持ち合わせている。またより安定したコンセプト確立の徹底のためには取り扱う商品はもちろんのこと、製品の品質詳細表示の徹底による安全保障やトイレなどの施設の充実や定員の対応・マナーの教育等に関しても、徹底して取り組むべきであろう。これらを行うことで「百貨店=高級」の方程式が成り立つに違いない。
ここで我々が考えた差別化を図る案を述べることにしよう。まず、中年層をターゲットにするからにはやはり、長時間百貨店に滞在しても疲労回復や息抜き、食事が可能である「いこいの場」が必要であろう。現在レストランは上層階に配置されている傾向が見られるが、体力面等を配慮するとやはり下層階が望ましいであろう。休憩スペースと言っても通路に設置されているベンチ程度である。この点に関して言うと、現在の百貨店においていこいの場が絶対的に不足していると言えよう。せっかく中高年の人々が高級志向で購買意欲を持っているのにも関わらず、そういった設備や施設が不十分であるがゆえに、非行動的になり、意欲を喪失してしまうという悪循環に陥ってしまっているのである。だから現在設置されているベンチとは別に、ターゲットである中年層の嗜好や環境に合わせて、いこいの場を設けるべきではないだろうか。そのような配慮が魅力の向上にリンクするのである。また次に、品質の安全性を向上させることが顧客の安心感を生み、信用・信頼される百貨店という概念を定着させることが必要であろう。その1つとして、製品の品質表示の徹底が挙げられる。品物によって表示方法や程度が異なるが、その品物に適した品質表示を行うことが望ましい。例えば、アパレル関係の製品であれば国名や性質、食品であれば産地や生産者などのように製品によって表示方法・要素を変化させる必要があると言えよう。ただ表示する、ただ多くの情報を載せるのではなく、必要な情報がパッと見ただけですぐに分かるような工夫を行うべきである。次に提案する案として、販売員の質の向上が挙げられる。現在の百貨店の場合、百貨店にテナントとして入っている店舗においてメーカーから派遣された従業員によって構成されている傾向にある。このような場合、自社ブランド製品を販売し、自社の売上高やマージンを増加させることだけに執着し、ご来店される顧客に見合うファッションをコーディネートするなどの本来のサービスを提供する点においては二の次になり、十分に行えていないという事態に陥ってしまい、販売員の質の低下が信頼性を低下させてしまう可能性がある。こういった事態を阻止するべく、現在の販売員に欠落しているコーディネート能力の強化やブランドの枠を超えて様々なブランドの商品の中からアイテムを抽出し、コーディネートを行う専門的なスキルを持った人材の育成を行う必要がある。現在このようなコーディネーターは数少なく、このようなスキルを十分身に付けるまでにはかなりの経験と時間を要することはやむを得ない。しかし、百貨店というフィールドにおいてコーディネーターの必要性・需要は絶大である。だからこそコーディネーターの育成を徹底して行い、様々な顧客の好み、ニーズに応じたファッションスタイルの提供を行うことで、顧客の信頼を得て確実な需要を得る必要があるのである。これらのコーディネートをサポートするべく、テナントの販売員はトレンドのアイテム情報をより正確にかつ迅速にコーディネーターに対して、また顧客に対して提供することが重要となってくるのである。こういった一人ひとりの顧客を対象に提供するサービスは美意識が高く高級志向の中高年に対してはかなり好感を抱かれ、自分専用のサービスを心地よく思うに違いない。サービス提供の面での差別化は効果的であろう。次にサービス提供に関連して、やはり百貨店の現在のメリットである交通面における利便性を徹底させるべきである。現在、商業施設と都心を循環するバスを定期的に運行させたり、購入金額がある一定の額を超えたら片道分の賃金が無料となったり、商業施設と交通機関の提携サービスが実施されているが、交通機関が充実している絶好の立地に位置する百貨店が十分な集客が期待できるサービスを提供することで、集客面において絶大な効果を発揮することが可能であると言っても過言ではないだろう。さらに現在導入され、普及し始めているインターネットを媒体とするネットショッピングについて述べることにしよう。やはり最大の難関はターゲットとする中高年がパソコンやインターネットに疎く、馴染みが希薄であるという点である。しかし、そういった年代の方々が利用したくなるような充実した機能・サービス・利便性を提供することでネット利用の意欲を向上させ、難関と思われた弱みが一転して強みに変わる可能性をも秘めているのではないだろうか。また、カテゴリーキラーやショッピングセンター(SC)のメリットとも言えるエンターテイメント性の要素を徹底追求し、百貨店にも導入することで明確なビジョン形成に効果的であると言えよう。
以上で述べたような策を実践し、より追求していくことによって、百貨店全体の魅力を向上させることが可能となり、現在客足が遠のいている百貨店に再び賑わいが戻ることを期待したい。
第四章 個々の百貨店の差別化
ここからは第三章で挙げたような案を実践し、百貨店全体の魅力を向上させた後、個々の百貨店における差別化つまり第二段階として行うべき案を述べていく。他の百貨店との差別化についてであるが、現在の百貨店を見て一目瞭然であるように、どこの百貨店も多少の差はあってもおおまかなスタンスに関してはどんぐりの背比べ状態であるのは言うまでもなかろう。このような同質化が百貨店の魅力を低迷させている要因のひとつとして挙げられる。これらの深刻な同質化を打開するべく、各々の百貨店が他にはない個性・魅力を際立たせる必要があるのである。
まず、メーカーとコラボレーションをして生み出す百貨店独自のPB(プライベート・ブランド)商品が挙げられる。百貨店業界で不動の一位を確立し、君臨する伊勢丹は顧客の声から生まれ、顧客の声と一緒に成長するというテーマで「オンリーアイ」というフレーズを用いて、厳選された商品を提供している。そこに行かなければ購入することのできないPB商品は言わば、他の百貨店との差別化を行う上でかなり強力なツールと言っても過言ではないだろう。現在PB商品を持っている百貨店は少ないし、また持ってはいても伸び悩み、その強力なツールをうまく活用しきれていない傾向が見られる。PB商品という強力なツールをうまく活用せずにいるのは宝の持ち腐れである。PB商品の本来の潜在能力を発揮するためには独自開発ももちろん良いが、百貨店はやはりPB商品開発においては能力的に劣る点があるため、様々なブランドとコラボレーションをすることで支援による安定した財政面におけるサポートやブランドが有するカリスマ性、ブランド側のアイデアを大いにフル活用することで、魅力のあるPB商品を協力し合って作成し、消費者の購買意欲を刺激し、結果的に百貨店の魅力を引き出すこともなし得るであろう。各百貨店が各々PB商品を提供することで、差別化はより一層明確になり、個々の輪郭が鮮明に形成されるに違いない。これらによって同質化されたどんぐりの背比べ状態も解消され、各々の百貨店がそれぞれ輝きを放つことも十分実現可能であろう。
また中高年をターゲットとするからには起床時間が早い等のライフスタイルを考慮して、開閉時間の調節を行うことも効果的であろう。
さらに、百貨店全体の魅力の向上においても挙げたが、「いこいの場」の雰囲気作りやコンセプト次第で全体だけでなく、個々の百貨店の差別化も図れるのではなかろうか。例えば、同世代の人たちと語らうコミュニケーションの場を設けるなどはどうであろうか。そこでは催し物や展示会をステージなどで行ったり、地域に根付いた新鮮な農産物や水産物を用いて調理した料理などをバイキング感覚で振る舞ったり、産地直送の産物を販売したりして、かしこまった感じではなく、一人で来られる方やうまく馴染むことが苦手な方でも気軽に足を運べて、様々な方に「体と心のリラックス」をして頂くことが可能な雰囲気作りを心掛けることが効果的であろう。このようにその地域によってテーマ設定を行い、百貨店における同質化を回避すべきである。ただひとつこの案には考慮すべき点がある。それは快適なコミュニケーションの場を提供するため、アットホームな雰囲気作りが行き過ぎると地域色が濃くなりすぎて、先に述べた「高級さ」の追求に関してはかけ離れてしまうという問題が危惧されるという点である。これらの矛盾点を回避するためには、過剰にならない程度に地域性を取り入れつつ、かつ適度に規律付けを行い、いこいの場の雰囲気作りとして建具や壁紙、照明、家具等で高級感を醸し出すことが重要となってくるのである。こういった雰囲気作りを行うことで中年層の意欲を刺激し、憩いを求めて足を運ぶ方やそういった施設があるということでゆっくりと買い物をされる方など、様々な面で能動的に作用するのである。
またカテゴリーキラーやSC等のライバルが持ち合わせるメリットであるエンターテイメント性の要素を導入することが挙げられる。これも全体の魅力を向上させる案として挙げたが、個々の百貨店における差別化においても効果的なツールだろう。例として、そごう横浜店のダイニングパーク横浜が挙げられる。単なるレストラン街ではなく、「百貨店=高級」というイメージを崩すことなくエンターテイメント性をうまく盛り込み、新しい施設を誕生させている。フロアの内装はヨーロッパの街並み等を模し、店内中央には庭園を設置しているのである。この庭園は一日の時間の流れを演出するため、照明を夕方になると明かりが落ちるなど横浜の日照とリンクさせて調整している。また店内にはこの庭園を眺めながら食事を楽しむことのできる店舗や、庭園とは別に横浜の港を眺望できる店舗などを設置している。このように従来の百貨店に欠落していたエンターテイメント性を大きく反映させると同時に、横浜でしか出来ない、その場所でしか味わうことの出来ないという他の百貨店との差別化も確立されていると言えよう。
第五章 将来の百貨店の展望
それでは、百貨店がどうしたら衰退の危機を脱出し、活気を取り戻すかを一章からの流れにそって簡単に説明したい。
百貨店の差別化により、徹底した高級感が口コミで広がり、イメージがアップする。すると今までは百貨店からアパレルメーカーに出店を希望していたものが、逆にメーカー側からこの百貨店に入店を希望するようになる。もちろん高級路線を行く百貨店に入店を希望ということは有名なブランドである。その有名ブランドとコラボレーションを組みPBの開発をする。ここがターニングポイントでそれまでは消化仕入を行うが、この有名ブランドからの入店があった頃から買取制に移行し百貨店側がメーカーに指示を出せるようにする。また、コラボレーションで作ったPBを期間限定発売するなどこの店にしかないPBにプラスαを加えることにより購買意欲が増し、百貨店のイメージはさらにアップするのである。買取制による最大のリスクである、売れ残りをどうするかについては百貨店とは別にアウトレットモールとの提携を組み百貨店の中でなくそこで売るという形を取れば問題は解決される。
以上、対象とするターゲット層の限定と差別化を軸に具体案などを用いて三章と四章で二段階構成で論じてきたが、百貨店自体は以前のように活気を取り戻して輝きを放ち、魅力のあるものへと再び返り咲く力は十分持ち合わせているので、現在のスタイルにおける欠点を正面から捉えて、我々が思案したような改善策を見出し実現していくことで、百貨店が再び「百貨店」らしさを取り戻し、誰にも真似しがたい不動のものとなる日が到来することを心待ちにしている。
参考引用・文献
石原武政・矢作敏行著『日本の流通100年』有斐閣、2004年、380pp
川島蓉子著『伊勢丹な人々』日本済新聞社、2005年、216pp
11251文字
|
|
|
|
|
|
|
|
植木ゼミなんだよ〜 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-