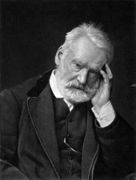14歳の頃、韻文悲劇「イルタメーヌ」創作(出版ではない)1816年
15歳でアカデミー・フランセーズの詩のコンクールで選外佳作 1817年
17歳でアカデミー・デ・ジュー・フロローの詩のコンクールで1等賞。
《コンセルヴァトゥール・リテレール(文学の保守)》誌創刊 1819年
フランス・ロマン派の父である王党派の名士シャトーブリアンの《コンセルヴァトゥール(保守)》誌にあやかったもの。後に刊行する「ビュグ・ジャルガルの乱」などを寄稿。
オード・雑詠集 Odes et Poésies Diverses, 1822
20才の頃の刊行。これより前から王室の目に留まりやがて桂冠詩人となっている。国王から奨励金を年金でもらえるようになり、幼馴染のアデール・フーシェと結婚。
尚、神秘的な象徴詩と言えばロマン派ではネルヴァルなどが有名だが、ユゴーの詩も初期から神秘・象徴主義的なものを含んでいる。
アイスランドの巨人ハン HAN D'ISLANDE, 1823 - Hans of Iceland / The Demon of the North
故郷ブザンソンのオカルト結社のリーダー格であるシャルル・ノディエの影響などで書いた怪物もの。やたらと装飾好きで嘘と空々しさに満ちた擬古典派には、グロテスクと揶揄される種類のものだった。
《ミューズ・フランセーズ》誌創刊。1823年
新オード集 NOUVELLES ODES, 1824
父親がナポレオン軍の将軍だったため、次第に影響を受け、結婚後、父親と和解したユゴーは、ナポレオンを旧姓のブォナパルテで呼んでいたのが、ブルボン王党派でありながら皇帝としてナポレオンを誉めるようになっていく。それが詩にも現れ、王党派・ナポレオン派問わずフランス中の人気を集め、フランス人の結束をうながす事となる。ただ行き過ぎて、旧ドイツ領の貴族が新しいフランス領になっての地名で名乗らないと威嚇するような詩も書いている。
《ミューズ・フランセーズ》誌のセナークルがノディエのアルスナル図書館サロンに会合の場所を定める。1824年
23歳でラマルチーヌと共にレジヨン・ド・ヌール勲章を授けられる。1825年
ビュグ・ジャルガルの乱 BUG-JARGAL, 1826 - The Slave-King
王党派とは言いながらも、初期から一般大衆を主人公にしたりしている。スパルタクスの乱、ジャックリーの乱、ワット・タイラーの乱のような話らしいですがきちんと読んだ事はありません。だいたいフランス語は苦手なので(おい)日本語訳がないのはきついです。決まった用語の出てくる後期の神秘詩の方が私にとってはまだいいです。
オード・バラァド集 ODES ET BALLADES, 1826
《グローブ》紙の書評でサント=ブーヴがユゴーの詩を誉める。2人の交流によりスタンダールら自由主義のロマン派と、ユゴーら王党派のロマン派が連合し、ユゴーはロマン派のリーダーとなった。この時、ゲーテもユゴーを認めた事がエッカーマンの「ゲーテとの対話」(1827年1月4日)にも書き残されている。
ちなみに、後の作家たちがユゴーはマンゾーニ程度でしかなかったのだと揶揄したのは、この時ゲーテが若い頃のユゴーをイタリアの詩人マンゾーニと比べたためと思われる。
ロマン派のセナークルはアルスナル図書館のノディエのサロンでなくユゴーの家で開かれるようになる。25歳。1827年
戯曲クロムウェル CROMWELL, 1827
作品自体より、序文でのロマン派論が有名。以前はクラシックとロマンティックの区別など無意味、よいものと悪いものがあるだけだとしていたが、ロマン主義を掲げるスタンダールらと連合してリーダーとなったため、悲劇と喜劇を分けないドラマを主張している。そもそも悲劇と喜劇の完全な区分け、場所の一致といった戯曲の原則は古典派の代表的な作家コルネイユ、モリエール、ラシーヌなどもあまり守ってはいない。尚、スタンダールの「ラシーヌとシェークスピア」も古典派への批判として有名。(最初に自らロマン主義宣言したのは、写実主義に分類されているスタンダールだった。 )
オリエンタル詩集 LES ORIENTALES, 1829
ロマン派の仲間から突出しすぎる前の、たくさん人が集まっていた絶頂期、仲間と散歩しては夕日を眺めていた頃の詩集。東洋趣味。父がナポレオンの兄スペイン王ジョゼフの将軍だったため子供の頃にスペインでいろいろアラビア風の風景を見たのも影響しているらしい。
マリオン・ド・ロルム MARION DE LORME, 1829
死刑囚最期の日 LE DERNIER JOUR D'UN CONDAMNÉ, 1829 - Last Day of Condemned Man - Kuolemaantuomitun viimeinen päivä
序文での法官批判にユゴーの思想がよく現れている。実際に刑務所を取材して、内なる声、良心の声、神に従って書いたもの。内なる良心は神、というのは感興・熱情は内なる神というフランス・ロマン派の母・スタール夫人と通じるものがある。後のボーヴォワールの「無関心の不安」とも共通する。岩波文庫に入ってます。
戯曲エルナーニ HERNANI, 1830
エル・シィドに影響を受けたもの。これも作品自体よりも、上演の際に擬古典派の保守勢力の野次とロマン派の反撃・・・「エルナニの戦い」「エルナニ事件」にテオフィル・ゴーティエなどの若者が参加した事で有名。ユゴーは28歳だった。後にベルディがオペラ化した。
秋の木の葉詩集 LES FEUILLES D'AUTOMME, 1831 - Autumn's Leaves
幼馴染で妻のアデールがユゴーの亭主関白ぶりに愚痴を言う内に親友のサント=ブーヴと不倫関係になってしまったのが暗い影を落としていると言われる。この後、ユゴーは100人以上の女性と関係を持ったという。実質上は正妻アデールよりも愛人ジュリエット・ドルーエと深く結ばれるようになった。ジュリエットはパリの今でいうセレブどもの愛人として渡り歩いてきた舞台女優だったが、この後ずっとユゴーの実質上の正妻として勤めてきた。
ノートル=ダム・ド・パリ NOTRE-DAME DE PARIS, 1831
ウォルト・ディズニー社の映画「ノートルダムの鐘」The Hunchback of Notre Dame の原作。ジプシー(ロマ)の踊り子エスメラルダとせむしのカジモドという2人の下層の人々と、今で言うセレブな悪僧侶(原作では役人ではなく僧侶が悪役である)の対比。原作はハッピー・エンドではなく、リアルな悲劇で、社会風刺、問題提起である。なおユゴーは建物自体に敬意を払っている。戦国の名将が名城に敬意を表したのと似ている。
逸楽の王 LE ROI S'AMUSE, 1832 - (Verdi's opera Rigoletto is based on this verse drama)
ベルディのオペラ「リゴレット」の原作
ルクレツィア・ボルジャ LERCRÉCE BORGIA, 1833 - Lucrezia Borgia, suom. Juhani Aho 1907
メアリー・チューダー Marie Tudor, 1833
ミラボー論 Étude sur Mirabeau, 1834
文学と哲学 Littérature et philosophie mêlées, 1834
クロード・グー CLAUDE GUEUX,1834
アンジェロ Angelo, 1835
明澄歌集 LES CHATS DU CRÉPUSCULE, 1835 - Twilight Songs
心が澄んでいるほど光が透き通るというような、東洋的な内省が根拠にあります。・・・といっても現代では「東洋人」より欧米人の方が分かってる気がします。
内なる声の詩集 LES VOIX INTÉRIEURES, 1837 - Inner Voices
戯曲リュイ・ブラース Ruy Blas, 1838
光と影の詩集 Les Rayons et les ombres, 1840
1841年、39歳でアカデミー・フランセーズ会員に当選。7月王政の王太子オルレアン公と交際。
友人への手紙 LE RHIN, LETTRES À UN AMI, 1841 - Excursions Along the Banks of Rhine
ライン河幻想紀行 Le Rhin, 1842
後にユゴーを批判するようになったバルザックが、このライン河と、レ・ミゼラブルのワーテルローの戦いの場面だけ誉めたためか、日本でも訳本が出ている。
1842年、アカデミー・フランセーズの院長としてオルレアン公追悼。
城主 Les Burgraves, 1843
この戯曲の失敗がロマン派の失墜の時と言われている。
さらに娘のレオポルディーヌが夫と共にヨット転覆で溺死。
1845年、ルイ=フィリップ王により子爵に叙せられ、貴族院議員になる。翌年雄弁家としてデビュー、貴族院で多くの重要な演説を行う。レ・ミゼール(後のレ・ミゼラブルの初稿)を書き始める。
1848年のヨーロッパ中での革命の先駆けとなる2月革命でルイ=フィリップ王退位。街頭でオルレアン公妃の摂政制を訴えるが、暴力革命を収めきれず撤退。ラマルチーヌは共和制への参加を呼びかけたがユゴーは断った。選挙で一度落選後、補欠選挙で保守層の支持を得てパリ選出議員となる。
ルイ=ナポレオン・ボナパルトがユゴーを訪ね、ナポレオンよりもワシントンのようにありたいと民主主義をアピール。
ユゴーの息子たちや弟子たちの新聞《エヴェヌマン》紙はルイ=ナポレオンを応援。選挙では優勢だったラマルチーヌを大差で破る。
1849年、パリで開かれた国際平和会議で議長を務める。
1850年、カトリックの教育支配をもくろむファルー法に反対。
1851年、はっきりと反ルイ=ナポレオンの立場をとるようになる。次男、三男は死刑廃止などを訴えたため投獄され、《エヴェヌマン》紙は発行禁止された。ルイ=ナポレオンのクーデターに対するユゴーら議員が抵抗運動組織。ブリュッセルに亡命。
1852年、ロンドンを経てジャージー島に移住。
(ジャージー島は古代の遺跡がある島で、フランスに近いがイギリス領)
http://
「サタンの終わり」を書くが出版者エッツェルは一般に理解されないと判断。
小ナポレオン Napoléon le Petit, 1852
詐欺師・裏切り者のファシスト・ナポレオン3世を批判したもの。複数の新聞社を持つナポレオン信奉者のユゴーに民主主義者の顔をして近づいて来た、ナポレオンの血を引かない甥は、豹変して独裁者となったので。ユゴーは普仏戦争で帝政が終わるまで20年ほど亡命していた。
懲罰詩集 LES CHÂTIMENTS, 1853 - The Punishments
同上
1855年5月、叙事詩「神」を書き始める。
ルイ=ナポレオンへの手紙 Lettres à Louis Bonaparte, 1855
同上
イギリス政府からジャージー島立ち退きを命じられ、ガーンジー島に移住。
観想詩集 LES CONTEMPLATIONS, 1856
非常に神秘色が強くなってくる。というより、評論家たちが理解出来なくなって来ただけかも知れない。ランボーの「幻視集(イリュミナシオン)」などの元祖とも言える。ちなみに、同じロマン派で王党派で社会参加好きなラマルチーヌには瞑想詩集(メディタシオン・ポーエティックス)というのがある。
亡命先でユゴーは日本の陶磁器を集めたり、泳いだり、瞑想したり、交霊術にはまったりしていた。最初は懐疑的だったのだが、はまった原因は死んだ娘の霊が出てきたため。伝記作家のモーロワによれば、霊の中にはユゴーの言いそうな事ばかり言う霊もいるのに、聴いてるユゴーが高い教えに驚いていたという事なので、もともとインスピレーションを与えてくださっていた守護の神霊の導きもあったかも知れない。また瞑想する自分の写真に、ユゴーは「神と対話するヴィクトール・ユゴー」と記したりしている。
諸世紀の伝説 LA LÉGENDE DES SIÉCLES I-II, 1859, 1877 - The Legend of Centuries
人類の堕落と進歩を描いた神話・伝承のような詩集。日本で言えば長歌ないし七五調で書いた神示の人間版のようなもの。天使の堕落と進歩というのはユゴーのテーマの一つである。ユゴーの詩は古典派の規則こそ破っているものの、散文詩ではなくアレクサンドラン(12音節詩)です。しかしロマン派が型を破った事で後のフランス散文詩があるとも言えます。
1860年、12年ぶりに「レ・ミゼラブル」の執筆開始。
レ・ミゼラブル(ああ無情)LES MISÉRABLES, 1862
ユゴーの代表作。亡命前から構想を練って書き進めていた。亡命していたユゴーは出版社に「?」という世界で一番短い手紙を送り、その返事は「!」だったという。「売れ行きはどうかな?」「大好評ですよ!」という事。
被買春婦のファンティーヌ、健康な暮らしができない彼女の背中に雪をつめこんで病気にして結果として殺したふざけた一般市民、娘のコゼットの苦労と、コゼットの養育者となった詐欺師夫妻、その娘のエポニーヌの恋と死、ユゴー自身の分身である若者マリウス、啓発革命結社ABC友の会の火のようなアンジョルラスと水のようなグランテール、ナポレオンのワーテルローの敗戦、小さな弟たちのために一切れのパンを盗んで投獄され、脱走を何度も試みて刑期が20年にもなった荒んだ囚人ジャン・ヴァルジャンと、教会に泊まった際に銀の食器を盗んだ彼に銀の燭台をも与えたミリエル神父、改心してマドレーヌ市長となったジャン・ヴァルジャンに忍び寄る生真面目な警察官ジャヴェール、彼を逃がすために初めて嘘をついた、嘘をつかない尼僧(家臣の弁慶が敢えて義経を殴って「これなら義経と弁慶のはずがない」と思わせたのと同じ)。冤罪で処刑されそうな男がいるのを知って自分がジャン・ヴァルジャンだと名乗り出るマドレーヌ市長・・・罪人だからと義娘コゼットと婚約者マリウスから離れようとするジャン・ヴァルジャンの葛藤。煙突掃除少年ガブローシュ。激動のフランスのあらゆる階層の人々を描いた「憐れなるものたち」。日本では明治20〜30年頃のロマン主義運動の中で、土井晩翠の先駆的な紹介でユゴーの存在が知られるようになった後、1902年(明治35年)に黒岩涙香の名訳『ああ無情』で人気を博した。
ミリエル神父はユゴー自身の瞑想体験とか、親交のあったラムネー神父などをモデルとしていると思われる。このラムネーという人がまた変わった人で、カトリック教会に従わない事もあったようです。またユゴーが仏教やブラフマナ(バラモン)教に関心を持っていた事も作品に現れています。あらすじだけ読んでもおもしろいですが、原作を読むと論文がたくさん入ってるのが分かると思います。
シェークスピア論 WILLIAM SHAKESPEARE, 1864
街と森の歌集 LES CHANSONS DES RUES ET DES BOIS, 1865
海に働く人々 LES TRAVAILLEURS DE LA MER, 1866 - The Toilers of the Sea - Meren ahertajat
イジドール・デュカス(筆名ロートレアモン伯爵)の詩に蛸が出てくるのはこの小説の流行のせいかも知れない。
パリ・ガイド Paris-Guide, 1867
LA VOIX DE GUERNESEY, 1867
笑う男 L'HOMME QUI RIT, 1869 - The Man Who Laughs - Nauruihminen - film 1927, dir. by Paul Leni
1870年、普仏戦争でルイ=ナポレオンが捕えられ、ユゴーは凱旋帰国。「ドイツ人に訴える」「フランス人に訴える」などを発表。
1871年、国民議会パリ選出議員に当選したが、議会の政策に反対して辞職。
恐るべき年 L'ANNÉE TERRIBLE, 1872- The Terrible Year
QUATRE-VINGTTREIZE, 1874 - Ninety-Three - Yhdeksänkymmentäkolme
ナポレオン3世のクーデターかマァク=マオンを批判したものだったはず。
1873年、マァク=マオン、大統領となる。
93年 Quatrevingt-Treize, 1874
フランス革命を題材にしたもの。
息子たち Mes Fils, 1874
言行録 Actes et paroles - Avant l'exil, 1875
7月革命の際にバリケード前で民衆を制止するために行った演説とか、議会での発言、アカデミー・フランセーズでの発言などを集めたもの。ヨーロッパ合州国の提案など。
Actes et paroles - Pendant l'exil, 1875
同上
Actes et paroles - Depuis l'exil, 1876
同上
よいお爺ちゃんぶり L'ART D'ÊTRE GRANDPÉRE, 1877
孫への溺愛ぶりを自画自賛したもの。
諸世紀の伝説(続編)LA LÉGENDE DES SIÈCLES 2e série, 1877
1859年参照の事。後のマラルメの詩に出てきそうなパン神などは半神半獣の人間の葛藤・苦悩を示している。また、魂の奥深くの良心を観想する者は、自らも見られるなどといった、瞑想体験からの詩集。おそらくマラルメやサルトルでないと読めない。
ある犯罪の物語 HISTOIRE D'UN CRIME, 1877-78
ナポレオン3世のクーデターを批判したもので、マァク=マオン大統領を牽制したもの。
教皇 LE PAPE, 1878
至上の憐憫 LA PITIÉ SUPRÊME, 1879
真宗教と似非宗教 Religions et religion, 1880
ちなみにユゴーは「自分はカトリックでもプロテスタントでもモルモンでも・・(中略)・・でもないが神を信じているというと人々は驚く」みたいな事を言っています。マグダラのマリアを崇拝する結社の総長だったという疑惑はありますが、実際の所は不明です。もし事実なら、ゲーテやマラルメがフリー・メイソンだったのと同じですが。
http://
ロバ L'Âne, 1880
フランス語でいうロバは、日本語で言う馬鹿に当たる。
しかし堅忍のロバは愚かな人よりも賢者だとユゴーはかなり初期の詩から称えていた。逆に言えば、人がそれだけ堕落しているという事でもある。
精神の四方の風 LES QUATRE VENTS DE L'ESPIRIT, 1881
トルケマーダ TORQUEMADA, 1882
諸世紀の伝説(終編)La Légende des siècles - Tome III, 1883
科学の進歩と霊性の進歩によりユートピアが完成した後、神の栄光が訪れるという、アセンション・福千年の予想。それを20世紀に設定していたが、世界大戦の世紀となっていったため、ロマン派を信奉する青少年たちからは脱落者、懐疑的になるものが続出した。
イギリス海峡の群島 L'Archipel de la Manche, 1883
1885年、孫たちに看取られて死亡。凱旋門下に安置された後、国葬で200万のフランス人に送られてパンテオン(偉人廟)に移される。
後の出版は遺稿・詩集の総集編・未公開の手紙などである。
自由の劇 LE THÉÂTRE EN LIBERTÉ, 1886
サタンの終わり LA FIN DE SATAN, 1886
堕落したサタンが自由の女神に導かれ天使に還るという神秘主義的なストーリーだったかな。堕落・改心・進歩というユゴーのテーマを「レ・ミゼラブル」とは違った神話の形で描いたもの。
Choses vues - 1re série, 1887
Alpes et Pyrénées, 1890
竪琴の限りに toute la lyre, 1888
神 Dieu, 1891
これもマラルメやサルトル級でなければ読めないのかも。
大学の研究室に入ってたユゴー全集にもなかったような・・・。
フランスとベルギー France et Belgique, 1892
竪琴の限りに(新シリーズ)Toute la lyre - nouvelle série, 1893
多分ユゴーに限った事ではないですが、詩人が楽器を抱いて吟遊していたりドルイド僧だったりした過去の意識があると思います。
作品集 ŒUVRES 1885-97
書簡集1 Correspondances - Tome I(1815-82), 1896
書簡集2 Correspondances - Tome II(1896-98), 1898
Les années funestes, 1898
Choses vues - 2e série(1887-1900), 1900
Post-scriptum de ma vie, 1901
婚約者への手紙 LETTRES À LA FIANCÉE, 1820-22, 1901
最後の詩の束 Dernière Gerbe, 1902
全作品集 ŒUVRES COMPLÈTES, 1904-52
Mille francs de récompense, 1934
Océan. Tas de pierres, 1942
Pierres, 1951
全詩集 POÉSIES COMPLÈTES, 1961
ロマネスク作品集 ŒUVRES ROMANESQUES, 1962
戯曲集 THÉÂTRE, 1963
詩作集 ŒUVRES POÉTIQUES, 1964
政治作集 ŒUVRES POLITIQUES, 1964
日々の日記 JOURNAL DE CE QUE J'APPRENDS CHAQUE JOUR, 1965
シャルル・ノディエとの往復書簡 CORRESPONDANCE CROISÉE, 1986 (with Charles Nodier)
ジュリエット・ドルーエとの手紙 LETTRES DE VICTOR HUGO À JULIETTE DROUET, LETTRES DE JULIETTE DROUET À VICTOR HUGO, 2001
15歳でアカデミー・フランセーズの詩のコンクールで選外佳作 1817年
17歳でアカデミー・デ・ジュー・フロローの詩のコンクールで1等賞。
《コンセルヴァトゥール・リテレール(文学の保守)》誌創刊 1819年
フランス・ロマン派の父である王党派の名士シャトーブリアンの《コンセルヴァトゥール(保守)》誌にあやかったもの。後に刊行する「ビュグ・ジャルガルの乱」などを寄稿。
オード・雑詠集 Odes et Poésies Diverses, 1822
20才の頃の刊行。これより前から王室の目に留まりやがて桂冠詩人となっている。国王から奨励金を年金でもらえるようになり、幼馴染のアデール・フーシェと結婚。
尚、神秘的な象徴詩と言えばロマン派ではネルヴァルなどが有名だが、ユゴーの詩も初期から神秘・象徴主義的なものを含んでいる。
アイスランドの巨人ハン HAN D'ISLANDE, 1823 - Hans of Iceland / The Demon of the North
故郷ブザンソンのオカルト結社のリーダー格であるシャルル・ノディエの影響などで書いた怪物もの。やたらと装飾好きで嘘と空々しさに満ちた擬古典派には、グロテスクと揶揄される種類のものだった。
《ミューズ・フランセーズ》誌創刊。1823年
新オード集 NOUVELLES ODES, 1824
父親がナポレオン軍の将軍だったため、次第に影響を受け、結婚後、父親と和解したユゴーは、ナポレオンを旧姓のブォナパルテで呼んでいたのが、ブルボン王党派でありながら皇帝としてナポレオンを誉めるようになっていく。それが詩にも現れ、王党派・ナポレオン派問わずフランス中の人気を集め、フランス人の結束をうながす事となる。ただ行き過ぎて、旧ドイツ領の貴族が新しいフランス領になっての地名で名乗らないと威嚇するような詩も書いている。
《ミューズ・フランセーズ》誌のセナークルがノディエのアルスナル図書館サロンに会合の場所を定める。1824年
23歳でラマルチーヌと共にレジヨン・ド・ヌール勲章を授けられる。1825年
ビュグ・ジャルガルの乱 BUG-JARGAL, 1826 - The Slave-King
王党派とは言いながらも、初期から一般大衆を主人公にしたりしている。スパルタクスの乱、ジャックリーの乱、ワット・タイラーの乱のような話らしいですがきちんと読んだ事はありません。だいたいフランス語は苦手なので(おい)日本語訳がないのはきついです。決まった用語の出てくる後期の神秘詩の方が私にとってはまだいいです。
オード・バラァド集 ODES ET BALLADES, 1826
《グローブ》紙の書評でサント=ブーヴがユゴーの詩を誉める。2人の交流によりスタンダールら自由主義のロマン派と、ユゴーら王党派のロマン派が連合し、ユゴーはロマン派のリーダーとなった。この時、ゲーテもユゴーを認めた事がエッカーマンの「ゲーテとの対話」(1827年1月4日)にも書き残されている。
ちなみに、後の作家たちがユゴーはマンゾーニ程度でしかなかったのだと揶揄したのは、この時ゲーテが若い頃のユゴーをイタリアの詩人マンゾーニと比べたためと思われる。
ロマン派のセナークルはアルスナル図書館のノディエのサロンでなくユゴーの家で開かれるようになる。25歳。1827年
戯曲クロムウェル CROMWELL, 1827
作品自体より、序文でのロマン派論が有名。以前はクラシックとロマンティックの区別など無意味、よいものと悪いものがあるだけだとしていたが、ロマン主義を掲げるスタンダールらと連合してリーダーとなったため、悲劇と喜劇を分けないドラマを主張している。そもそも悲劇と喜劇の完全な区分け、場所の一致といった戯曲の原則は古典派の代表的な作家コルネイユ、モリエール、ラシーヌなどもあまり守ってはいない。尚、スタンダールの「ラシーヌとシェークスピア」も古典派への批判として有名。(最初に自らロマン主義宣言したのは、写実主義に分類されているスタンダールだった。 )
オリエンタル詩集 LES ORIENTALES, 1829
ロマン派の仲間から突出しすぎる前の、たくさん人が集まっていた絶頂期、仲間と散歩しては夕日を眺めていた頃の詩集。東洋趣味。父がナポレオンの兄スペイン王ジョゼフの将軍だったため子供の頃にスペインでいろいろアラビア風の風景を見たのも影響しているらしい。
マリオン・ド・ロルム MARION DE LORME, 1829
死刑囚最期の日 LE DERNIER JOUR D'UN CONDAMNÉ, 1829 - Last Day of Condemned Man - Kuolemaantuomitun viimeinen päivä
序文での法官批判にユゴーの思想がよく現れている。実際に刑務所を取材して、内なる声、良心の声、神に従って書いたもの。内なる良心は神、というのは感興・熱情は内なる神というフランス・ロマン派の母・スタール夫人と通じるものがある。後のボーヴォワールの「無関心の不安」とも共通する。岩波文庫に入ってます。
戯曲エルナーニ HERNANI, 1830
エル・シィドに影響を受けたもの。これも作品自体よりも、上演の際に擬古典派の保守勢力の野次とロマン派の反撃・・・「エルナニの戦い」「エルナニ事件」にテオフィル・ゴーティエなどの若者が参加した事で有名。ユゴーは28歳だった。後にベルディがオペラ化した。
秋の木の葉詩集 LES FEUILLES D'AUTOMME, 1831 - Autumn's Leaves
幼馴染で妻のアデールがユゴーの亭主関白ぶりに愚痴を言う内に親友のサント=ブーヴと不倫関係になってしまったのが暗い影を落としていると言われる。この後、ユゴーは100人以上の女性と関係を持ったという。実質上は正妻アデールよりも愛人ジュリエット・ドルーエと深く結ばれるようになった。ジュリエットはパリの今でいうセレブどもの愛人として渡り歩いてきた舞台女優だったが、この後ずっとユゴーの実質上の正妻として勤めてきた。
ノートル=ダム・ド・パリ NOTRE-DAME DE PARIS, 1831
ウォルト・ディズニー社の映画「ノートルダムの鐘」The Hunchback of Notre Dame の原作。ジプシー(ロマ)の踊り子エスメラルダとせむしのカジモドという2人の下層の人々と、今で言うセレブな悪僧侶(原作では役人ではなく僧侶が悪役である)の対比。原作はハッピー・エンドではなく、リアルな悲劇で、社会風刺、問題提起である。なおユゴーは建物自体に敬意を払っている。戦国の名将が名城に敬意を表したのと似ている。
逸楽の王 LE ROI S'AMUSE, 1832 - (Verdi's opera Rigoletto is based on this verse drama)
ベルディのオペラ「リゴレット」の原作
ルクレツィア・ボルジャ LERCRÉCE BORGIA, 1833 - Lucrezia Borgia, suom. Juhani Aho 1907
メアリー・チューダー Marie Tudor, 1833
ミラボー論 Étude sur Mirabeau, 1834
文学と哲学 Littérature et philosophie mêlées, 1834
クロード・グー CLAUDE GUEUX,1834
アンジェロ Angelo, 1835
明澄歌集 LES CHATS DU CRÉPUSCULE, 1835 - Twilight Songs
心が澄んでいるほど光が透き通るというような、東洋的な内省が根拠にあります。・・・といっても現代では「東洋人」より欧米人の方が分かってる気がします。
内なる声の詩集 LES VOIX INTÉRIEURES, 1837 - Inner Voices
戯曲リュイ・ブラース Ruy Blas, 1838
光と影の詩集 Les Rayons et les ombres, 1840
1841年、39歳でアカデミー・フランセーズ会員に当選。7月王政の王太子オルレアン公と交際。
友人への手紙 LE RHIN, LETTRES À UN AMI, 1841 - Excursions Along the Banks of Rhine
ライン河幻想紀行 Le Rhin, 1842
後にユゴーを批判するようになったバルザックが、このライン河と、レ・ミゼラブルのワーテルローの戦いの場面だけ誉めたためか、日本でも訳本が出ている。
1842年、アカデミー・フランセーズの院長としてオルレアン公追悼。
城主 Les Burgraves, 1843
この戯曲の失敗がロマン派の失墜の時と言われている。
さらに娘のレオポルディーヌが夫と共にヨット転覆で溺死。
1845年、ルイ=フィリップ王により子爵に叙せられ、貴族院議員になる。翌年雄弁家としてデビュー、貴族院で多くの重要な演説を行う。レ・ミゼール(後のレ・ミゼラブルの初稿)を書き始める。
1848年のヨーロッパ中での革命の先駆けとなる2月革命でルイ=フィリップ王退位。街頭でオルレアン公妃の摂政制を訴えるが、暴力革命を収めきれず撤退。ラマルチーヌは共和制への参加を呼びかけたがユゴーは断った。選挙で一度落選後、補欠選挙で保守層の支持を得てパリ選出議員となる。
ルイ=ナポレオン・ボナパルトがユゴーを訪ね、ナポレオンよりもワシントンのようにありたいと民主主義をアピール。
ユゴーの息子たちや弟子たちの新聞《エヴェヌマン》紙はルイ=ナポレオンを応援。選挙では優勢だったラマルチーヌを大差で破る。
1849年、パリで開かれた国際平和会議で議長を務める。
1850年、カトリックの教育支配をもくろむファルー法に反対。
1851年、はっきりと反ルイ=ナポレオンの立場をとるようになる。次男、三男は死刑廃止などを訴えたため投獄され、《エヴェヌマン》紙は発行禁止された。ルイ=ナポレオンのクーデターに対するユゴーら議員が抵抗運動組織。ブリュッセルに亡命。
1852年、ロンドンを経てジャージー島に移住。
(ジャージー島は古代の遺跡がある島で、フランスに近いがイギリス領)
http://
「サタンの終わり」を書くが出版者エッツェルは一般に理解されないと判断。
小ナポレオン Napoléon le Petit, 1852
詐欺師・裏切り者のファシスト・ナポレオン3世を批判したもの。複数の新聞社を持つナポレオン信奉者のユゴーに民主主義者の顔をして近づいて来た、ナポレオンの血を引かない甥は、豹変して独裁者となったので。ユゴーは普仏戦争で帝政が終わるまで20年ほど亡命していた。
懲罰詩集 LES CHÂTIMENTS, 1853 - The Punishments
同上
1855年5月、叙事詩「神」を書き始める。
ルイ=ナポレオンへの手紙 Lettres à Louis Bonaparte, 1855
同上
イギリス政府からジャージー島立ち退きを命じられ、ガーンジー島に移住。
観想詩集 LES CONTEMPLATIONS, 1856
非常に神秘色が強くなってくる。というより、評論家たちが理解出来なくなって来ただけかも知れない。ランボーの「幻視集(イリュミナシオン)」などの元祖とも言える。ちなみに、同じロマン派で王党派で社会参加好きなラマルチーヌには瞑想詩集(メディタシオン・ポーエティックス)というのがある。
亡命先でユゴーは日本の陶磁器を集めたり、泳いだり、瞑想したり、交霊術にはまったりしていた。最初は懐疑的だったのだが、はまった原因は死んだ娘の霊が出てきたため。伝記作家のモーロワによれば、霊の中にはユゴーの言いそうな事ばかり言う霊もいるのに、聴いてるユゴーが高い教えに驚いていたという事なので、もともとインスピレーションを与えてくださっていた守護の神霊の導きもあったかも知れない。また瞑想する自分の写真に、ユゴーは「神と対話するヴィクトール・ユゴー」と記したりしている。
諸世紀の伝説 LA LÉGENDE DES SIÉCLES I-II, 1859, 1877 - The Legend of Centuries
人類の堕落と進歩を描いた神話・伝承のような詩集。日本で言えば長歌ないし七五調で書いた神示の人間版のようなもの。天使の堕落と進歩というのはユゴーのテーマの一つである。ユゴーの詩は古典派の規則こそ破っているものの、散文詩ではなくアレクサンドラン(12音節詩)です。しかしロマン派が型を破った事で後のフランス散文詩があるとも言えます。
1860年、12年ぶりに「レ・ミゼラブル」の執筆開始。
レ・ミゼラブル(ああ無情)LES MISÉRABLES, 1862
ユゴーの代表作。亡命前から構想を練って書き進めていた。亡命していたユゴーは出版社に「?」という世界で一番短い手紙を送り、その返事は「!」だったという。「売れ行きはどうかな?」「大好評ですよ!」という事。
被買春婦のファンティーヌ、健康な暮らしができない彼女の背中に雪をつめこんで病気にして結果として殺したふざけた一般市民、娘のコゼットの苦労と、コゼットの養育者となった詐欺師夫妻、その娘のエポニーヌの恋と死、ユゴー自身の分身である若者マリウス、啓発革命結社ABC友の会の火のようなアンジョルラスと水のようなグランテール、ナポレオンのワーテルローの敗戦、小さな弟たちのために一切れのパンを盗んで投獄され、脱走を何度も試みて刑期が20年にもなった荒んだ囚人ジャン・ヴァルジャンと、教会に泊まった際に銀の食器を盗んだ彼に銀の燭台をも与えたミリエル神父、改心してマドレーヌ市長となったジャン・ヴァルジャンに忍び寄る生真面目な警察官ジャヴェール、彼を逃がすために初めて嘘をついた、嘘をつかない尼僧(家臣の弁慶が敢えて義経を殴って「これなら義経と弁慶のはずがない」と思わせたのと同じ)。冤罪で処刑されそうな男がいるのを知って自分がジャン・ヴァルジャンだと名乗り出るマドレーヌ市長・・・罪人だからと義娘コゼットと婚約者マリウスから離れようとするジャン・ヴァルジャンの葛藤。煙突掃除少年ガブローシュ。激動のフランスのあらゆる階層の人々を描いた「憐れなるものたち」。日本では明治20〜30年頃のロマン主義運動の中で、土井晩翠の先駆的な紹介でユゴーの存在が知られるようになった後、1902年(明治35年)に黒岩涙香の名訳『ああ無情』で人気を博した。
ミリエル神父はユゴー自身の瞑想体験とか、親交のあったラムネー神父などをモデルとしていると思われる。このラムネーという人がまた変わった人で、カトリック教会に従わない事もあったようです。またユゴーが仏教やブラフマナ(バラモン)教に関心を持っていた事も作品に現れています。あらすじだけ読んでもおもしろいですが、原作を読むと論文がたくさん入ってるのが分かると思います。
シェークスピア論 WILLIAM SHAKESPEARE, 1864
街と森の歌集 LES CHANSONS DES RUES ET DES BOIS, 1865
海に働く人々 LES TRAVAILLEURS DE LA MER, 1866 - The Toilers of the Sea - Meren ahertajat
イジドール・デュカス(筆名ロートレアモン伯爵)の詩に蛸が出てくるのはこの小説の流行のせいかも知れない。
パリ・ガイド Paris-Guide, 1867
LA VOIX DE GUERNESEY, 1867
笑う男 L'HOMME QUI RIT, 1869 - The Man Who Laughs - Nauruihminen - film 1927, dir. by Paul Leni
1870年、普仏戦争でルイ=ナポレオンが捕えられ、ユゴーは凱旋帰国。「ドイツ人に訴える」「フランス人に訴える」などを発表。
1871年、国民議会パリ選出議員に当選したが、議会の政策に反対して辞職。
恐るべき年 L'ANNÉE TERRIBLE, 1872- The Terrible Year
QUATRE-VINGTTREIZE, 1874 - Ninety-Three - Yhdeksänkymmentäkolme
ナポレオン3世のクーデターかマァク=マオンを批判したものだったはず。
1873年、マァク=マオン、大統領となる。
93年 Quatrevingt-Treize, 1874
フランス革命を題材にしたもの。
息子たち Mes Fils, 1874
言行録 Actes et paroles - Avant l'exil, 1875
7月革命の際にバリケード前で民衆を制止するために行った演説とか、議会での発言、アカデミー・フランセーズでの発言などを集めたもの。ヨーロッパ合州国の提案など。
Actes et paroles - Pendant l'exil, 1875
同上
Actes et paroles - Depuis l'exil, 1876
同上
よいお爺ちゃんぶり L'ART D'ÊTRE GRANDPÉRE, 1877
孫への溺愛ぶりを自画自賛したもの。
諸世紀の伝説(続編)LA LÉGENDE DES SIÈCLES 2e série, 1877
1859年参照の事。後のマラルメの詩に出てきそうなパン神などは半神半獣の人間の葛藤・苦悩を示している。また、魂の奥深くの良心を観想する者は、自らも見られるなどといった、瞑想体験からの詩集。おそらくマラルメやサルトルでないと読めない。
ある犯罪の物語 HISTOIRE D'UN CRIME, 1877-78
ナポレオン3世のクーデターを批判したもので、マァク=マオン大統領を牽制したもの。
教皇 LE PAPE, 1878
至上の憐憫 LA PITIÉ SUPRÊME, 1879
真宗教と似非宗教 Religions et religion, 1880
ちなみにユゴーは「自分はカトリックでもプロテスタントでもモルモンでも・・(中略)・・でもないが神を信じているというと人々は驚く」みたいな事を言っています。マグダラのマリアを崇拝する結社の総長だったという疑惑はありますが、実際の所は不明です。もし事実なら、ゲーテやマラルメがフリー・メイソンだったのと同じですが。
http://
ロバ L'Âne, 1880
フランス語でいうロバは、日本語で言う馬鹿に当たる。
しかし堅忍のロバは愚かな人よりも賢者だとユゴーはかなり初期の詩から称えていた。逆に言えば、人がそれだけ堕落しているという事でもある。
精神の四方の風 LES QUATRE VENTS DE L'ESPIRIT, 1881
トルケマーダ TORQUEMADA, 1882
諸世紀の伝説(終編)La Légende des siècles - Tome III, 1883
科学の進歩と霊性の進歩によりユートピアが完成した後、神の栄光が訪れるという、アセンション・福千年の予想。それを20世紀に設定していたが、世界大戦の世紀となっていったため、ロマン派を信奉する青少年たちからは脱落者、懐疑的になるものが続出した。
イギリス海峡の群島 L'Archipel de la Manche, 1883
1885年、孫たちに看取られて死亡。凱旋門下に安置された後、国葬で200万のフランス人に送られてパンテオン(偉人廟)に移される。
後の出版は遺稿・詩集の総集編・未公開の手紙などである。
自由の劇 LE THÉÂTRE EN LIBERTÉ, 1886
サタンの終わり LA FIN DE SATAN, 1886
堕落したサタンが自由の女神に導かれ天使に還るという神秘主義的なストーリーだったかな。堕落・改心・進歩というユゴーのテーマを「レ・ミゼラブル」とは違った神話の形で描いたもの。
Choses vues - 1re série, 1887
Alpes et Pyrénées, 1890
竪琴の限りに toute la lyre, 1888
神 Dieu, 1891
これもマラルメやサルトル級でなければ読めないのかも。
大学の研究室に入ってたユゴー全集にもなかったような・・・。
フランスとベルギー France et Belgique, 1892
竪琴の限りに(新シリーズ)Toute la lyre - nouvelle série, 1893
多分ユゴーに限った事ではないですが、詩人が楽器を抱いて吟遊していたりドルイド僧だったりした過去の意識があると思います。
作品集 ŒUVRES 1885-97
書簡集1 Correspondances - Tome I(1815-82), 1896
書簡集2 Correspondances - Tome II(1896-98), 1898
Les années funestes, 1898
Choses vues - 2e série(1887-1900), 1900
Post-scriptum de ma vie, 1901
婚約者への手紙 LETTRES À LA FIANCÉE, 1820-22, 1901
最後の詩の束 Dernière Gerbe, 1902
全作品集 ŒUVRES COMPLÈTES, 1904-52
Mille francs de récompense, 1934
Océan. Tas de pierres, 1942
Pierres, 1951
全詩集 POÉSIES COMPLÈTES, 1961
ロマネスク作品集 ŒUVRES ROMANESQUES, 1962
戯曲集 THÉÂTRE, 1963
詩作集 ŒUVRES POÉTIQUES, 1964
政治作集 ŒUVRES POLITIQUES, 1964
日々の日記 JOURNAL DE CE QUE J'APPRENDS CHAQUE JOUR, 1965
シャルル・ノディエとの往復書簡 CORRESPONDANCE CROISÉE, 1986 (with Charles Nodier)
ジュリエット・ドルーエとの手紙 LETTRES DE VICTOR HUGO À JULIETTE DROUET, LETTRES DE JULIETTE DROUET À VICTOR HUGO, 2001
|
|
|
|
|
|
|
|
ヴィクトール・ユゴーVictorHugo 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-