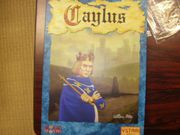|
|
|
|
コメント(10)
SGCで4人プレイ。インストから4時間ほどプレイして中盤戦で協議終了しました。
拡大再生産メカニクス、タイル配置メカニクス、市場売買メカニクスの複合体でルールの分量は多目で、シンプルと言うのはどうかという気がします。ただし、それぞれはどこかで見たことのあるようなものなので、分量の割には理解しやすく、プレイで戸惑うということは少ないでしょう。
4人だったのが問題なのか、初見者が3人もいたのが問題なのかはわかりませんが、昨日は4時間ではまだ中盤戦でした。完全に終わるまでプレイすると6時間もしくはそれ以上掛かったのではないかという気がします。
どの工業が強力かはプレイの展開次第かという気がします。昨日は序盤では、資本(黒)と鉱石(白)が設定通りに希少でしたが、すぐに労働力(赤)がもっともタイトになり、次は労働力の増加により食料とエネルギーが希少になるという風に移り変わっていきました。
協議終了となったのは、金融3タイルを一気に建てたプレイヤーが出た時点で他の3人が勝算なしと認めたためでした。
拡大再生産系の常として序盤で転んだ遅れを挽回するのが難しいゲームだと思います。交渉は市場売買より有利なので重要ですが市場売買が常に可能で借金が無制限なので、カタンの開拓に比較すると相対的な重要度は低い気がします。
裏を返せば交渉停止によりトップをスローダウンすることに限界がある訳で、リードしたプレイヤーを止めるのが難しい気がしました。
結果としてプレイ負荷が重く、一旦リードを許すと逆転の余地が少ないゲームになっているのかなという気がしました。そのことを認めて協議終了するという前提に立てば、確かにそれほど長時間でなく終結するのかも知れません。
拡大再生産メカニクス、タイル配置メカニクス、市場売買メカニクスの複合体でルールの分量は多目で、シンプルと言うのはどうかという気がします。ただし、それぞれはどこかで見たことのあるようなものなので、分量の割には理解しやすく、プレイで戸惑うということは少ないでしょう。
4人だったのが問題なのか、初見者が3人もいたのが問題なのかはわかりませんが、昨日は4時間ではまだ中盤戦でした。完全に終わるまでプレイすると6時間もしくはそれ以上掛かったのではないかという気がします。
どの工業が強力かはプレイの展開次第かという気がします。昨日は序盤では、資本(黒)と鉱石(白)が設定通りに希少でしたが、すぐに労働力(赤)がもっともタイトになり、次は労働力の増加により食料とエネルギーが希少になるという風に移り変わっていきました。
協議終了となったのは、金融3タイルを一気に建てたプレイヤーが出た時点で他の3人が勝算なしと認めたためでした。
拡大再生産系の常として序盤で転んだ遅れを挽回するのが難しいゲームだと思います。交渉は市場売買より有利なので重要ですが市場売買が常に可能で借金が無制限なので、カタンの開拓に比較すると相対的な重要度は低い気がします。
裏を返せば交渉停止によりトップをスローダウンすることに限界がある訳で、リードしたプレイヤーを止めるのが難しい気がしました。
結果としてプレイ負荷が重く、一旦リードを許すと逆転の余地が少ないゲームになっているのかなという気がしました。そのことを認めて協議終了するという前提に立てば、確かにそれほど長時間でなく終結するのかも知れません。
9月15日に文京区でやりました。初め昔のウェルスオブネーションかと思ったのですが、全く違うゲームでした。同じ名前は避けてほしいと思いました。
5人でプレーしてインストから最後の計算終了まで3時間半でした。私には長すぎますが、長時間というほどではないでしょう。
私好みではありませんが、よくできたゲームだと思います。電気も食料も人間も鉄鉱石も資本もそしてお金もみな必要で、値上がりする一歩前に手をつけるのがコツのようです。5人の作戦が違ったためか、交渉は頻繁に起き、殆ど短時間で纏まりました。
展開のせいか計算してみるまで誰が勝っているか分からず、逆に方針に困りました。結局、実際のトッププレーヤーが早く終了させるプレーを選択して終わりました。私ももう1ターンあれば勝てたかも知れません。
最後の精算も面倒で、繰り返しますが私の好みではないのですが、よいゲームだと思います。
5人でプレーしてインストから最後の計算終了まで3時間半でした。私には長すぎますが、長時間というほどではないでしょう。
私好みではありませんが、よくできたゲームだと思います。電気も食料も人間も鉄鉱石も資本もそしてお金もみな必要で、値上がりする一歩前に手をつけるのがコツのようです。5人の作戦が違ったためか、交渉は頻繁に起き、殆ど短時間で纏まりました。
展開のせいか計算してみるまで誰が勝っているか分からず、逆に方針に困りました。結局、実際のトッププレーヤーが早く終了させるプレーを選択して終わりました。私ももう1ターンあれば勝てたかも知れません。
最後の精算も面倒で、繰り返しますが私の好みではないのですが、よいゲームだと思います。
どこでプレイ時間の差が生じたのか良くわからなくなりました。
一昨日のプレイでも交渉は短時間でまとまりました。以下の理由によると思います。
1:一人で全部の資源を生産することは非効率で非現実的であることを全員が理解した
2:結果として各自の獲得資源が異なるため、一方が持つ資源は他方にとって不足、逆に他方の持つ資源は一方にとって不足なので、win−winの交渉が成立するため合意に達しやすかった。
3:市場を通して売買するとバンカーに利鞘を持っていかれることになるだけということを全員が理解しており積極的に交渉を利用した
4:交渉価格の目安が示されている。
というところでしょうか。
インストの部分は不要になるとして30分くらいは縮むと思うのですが、それでも5時間コースかなという気がしています。逆に5人いる方が1ターンに得られる場全体での資源が多いので、もしかすると終了までのターン数が短くて早く終わるのかも知れませんね。
わたしは草場師匠とは逆で、とても好みのゲームなのですが、市場との取引が1アクションで資源1個に制限されているため延々と何週もアクションが続いていくのが遅延デザインだという気がして、デザインの詰めが悪いゲームだという印象を持ちました。
一昨日のプレイでも交渉は短時間でまとまりました。以下の理由によると思います。
1:一人で全部の資源を生産することは非効率で非現実的であることを全員が理解した
2:結果として各自の獲得資源が異なるため、一方が持つ資源は他方にとって不足、逆に他方の持つ資源は一方にとって不足なので、win−winの交渉が成立するため合意に達しやすかった。
3:市場を通して売買するとバンカーに利鞘を持っていかれることになるだけということを全員が理解しており積極的に交渉を利用した
4:交渉価格の目安が示されている。
というところでしょうか。
インストの部分は不要になるとして30分くらいは縮むと思うのですが、それでも5時間コースかなという気がしています。逆に5人いる方が1ターンに得られる場全体での資源が多いので、もしかすると終了までのターン数が短くて早く終わるのかも知れませんね。
わたしは草場師匠とは逆で、とても好みのゲームなのですが、市場との取引が1アクションで資源1個に制限されているため延々と何週もアクションが続いていくのが遅延デザインだという気がして、デザインの詰めが悪いゲームだという印象を持ちました。
新人です
先週の名古屋EJFのテストプレイ会でプレイ。
内容はEJFのコミュに書いてあります。
六人で5時間。
六人とも長時間ゲームの上手く出来る人間が集まったので早くできたと思う。
僕は一回、バネストでも六人でテストプレイしてますので感覚はわかりました。
名古屋方面は電力プレッシャーが勝つジンクスがあるみたい。
インスト面はしやすい方かなあ。経験者が多いから流れがわかれば面白いかなあ。
秋には二ヶ月連続で長時間ゲーム祭がありますのでまたこのゲームは立つかなあ。
ちなみに同名ゲームはTHEが付くみたいです。名古屋ではウンタラネーションと呼んでいます。
また、プレイしたら報告します。
先週の名古屋EJFのテストプレイ会でプレイ。
内容はEJFのコミュに書いてあります。
六人で5時間。
六人とも長時間ゲームの上手く出来る人間が集まったので早くできたと思う。
僕は一回、バネストでも六人でテストプレイしてますので感覚はわかりました。
名古屋方面は電力プレッシャーが勝つジンクスがあるみたい。
インスト面はしやすい方かなあ。経験者が多いから流れがわかれば面白いかなあ。
秋には二ヶ月連続で長時間ゲーム祭がありますのでまたこのゲームは立つかなあ。
ちなみに同名ゲームはTHEが付くみたいです。名古屋ではウンタラネーションと呼んでいます。
また、プレイしたら報告します。
プレイ時間をまとめてみると、
文京区:5人:3時間半
SGC:4人:5時間くらい(予想)
EJF:6人:5時間
9/14:5人:7時間
と言ったところでしょうか。
今のところは初見者が多いと思うので、経験者ばかりになれば縮んでくるのかも知れませんが、3〜7時間コースというところのようですね。中を取って5時間というのは、現状では普通の水準なのかなという気がしてきました。
わたしの印象としては、確実に4時間で終わると見通せるならかなり良いゲーム、確実に3時間で終わるなら傑作だと言う気がします。選択肢が多く、技術(資源)の歴史的な展開がある拡大再生産型ゲームなので、3時間くらい掛かるのは仕方がないかなという気がしています。2時間以下で遊びたい時は近いテイストのゲームならアウトポストをやるでしょうか。
文京区:5人:3時間半
SGC:4人:5時間くらい(予想)
EJF:6人:5時間
9/14:5人:7時間
と言ったところでしょうか。
今のところは初見者が多いと思うので、経験者ばかりになれば縮んでくるのかも知れませんが、3〜7時間コースというところのようですね。中を取って5時間というのは、現状では普通の水準なのかなという気がしてきました。
わたしの印象としては、確実に4時間で終わると見通せるならかなり良いゲーム、確実に3時間で終わるなら傑作だと言う気がします。選択肢が多く、技術(資源)の歴史的な展開がある拡大再生産型ゲームなので、3時間くらい掛かるのは仕方がないかなという気がしています。2時間以下で遊びたい時は近いテイストのゲームならアウトポストをやるでしょうか。
ここ最近ハマっており、身内で5回ほどやりました。
最も最近のプレイでは5人プレイで1人初プレイ、それ以外は全員経験者という条件でプレイ時間は3時間半でした。
全員が経験者なら3時間で終わるかな、という感じでした。
私よりも頻繁に遊んでいる知人は「4人プレイなら2時間、5人なら3時間で終わる」と言っています。
全員が初プレイのときは5人で5〜6時間かかっているので、うちのメンバーが特別思考時間が短いわけではないと思います。
早めに終わる理由としては
1)全員がルールを把握している
・ルールに関する質問などがゲーム中に発生しない
・機械化や産業の移転を効率的に使用できるため、産業がスムーズに発展する
2)全員が生産物のレシピを暗記している
・このタイルを生産するにはどの資源が必要か、を皆が暗記している
・それにより生産計画を立てる時間が短くなるだけでなく、いわゆる「計画間違い」が減少するため、あとで「やっぱり電力が1個必要だった」といった余計な取引が減る
3)全員が借金の必要性を理解している
・初回プレイではみな借金を渋るため、産業がなかなか発展しない
・慣れてくると「ある程度の借金はどうせ必要だから」と1ターン目に4〜5枚借金を行い、序盤で最低限必要な産業を発展させるため、結果的に生産計画がスムーズに進み、収益も増える
4)全員が取引の相場やコツをつかんでいる
・無駄に悩むことがなく、他のプレイヤーの取引中に自分の計画を思考するクセがつく
5)全員が効率的な生産方法を把握している
・非効率的なことを避けるため自然と選択肢が狭まり、自分のターンで長考をしなくなる
といったところでしょうか。
だいたいの生産計画さえ立てられればプレイヤーの選択肢自体は多くないゲームなので、参加者のルール把握や経験が高まれば劇的にプレイ時間が短くなるゲームだと思います。
最も最近のプレイでは5人プレイで1人初プレイ、それ以外は全員経験者という条件でプレイ時間は3時間半でした。
全員が経験者なら3時間で終わるかな、という感じでした。
私よりも頻繁に遊んでいる知人は「4人プレイなら2時間、5人なら3時間で終わる」と言っています。
全員が初プレイのときは5人で5〜6時間かかっているので、うちのメンバーが特別思考時間が短いわけではないと思います。
早めに終わる理由としては
1)全員がルールを把握している
・ルールに関する質問などがゲーム中に発生しない
・機械化や産業の移転を効率的に使用できるため、産業がスムーズに発展する
2)全員が生産物のレシピを暗記している
・このタイルを生産するにはどの資源が必要か、を皆が暗記している
・それにより生産計画を立てる時間が短くなるだけでなく、いわゆる「計画間違い」が減少するため、あとで「やっぱり電力が1個必要だった」といった余計な取引が減る
3)全員が借金の必要性を理解している
・初回プレイではみな借金を渋るため、産業がなかなか発展しない
・慣れてくると「ある程度の借金はどうせ必要だから」と1ターン目に4〜5枚借金を行い、序盤で最低限必要な産業を発展させるため、結果的に生産計画がスムーズに進み、収益も増える
4)全員が取引の相場やコツをつかんでいる
・無駄に悩むことがなく、他のプレイヤーの取引中に自分の計画を思考するクセがつく
5)全員が効率的な生産方法を把握している
・非効率的なことを避けるため自然と選択肢が狭まり、自分のターンで長考をしなくなる
といったところでしょうか。
だいたいの生産計画さえ立てられればプレイヤーの選択肢自体は多くないゲームなので、参加者のルール把握や経験が高まれば劇的にプレイ時間が短くなるゲームだと思います。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
長時間ボードゲーム 更新情報
長時間ボードゲームのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 77419人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 209453人
- 3位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19956人