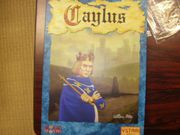鬼才フィリップ・エクランドの最新作(2007)。
彼の今までの多くの作品と異なり、ユーロゲーム並みのきちんとしたボックスに入っていて、フルカラーのマップやカードが付いていて、木製キューブが入っていたりするので馴染みの人ほど面食らうのではないか?
ゲームは、ネアンデルタール人、クロマニヨン人、北京原人、ホビットなどからスタートして石器時代、銅器時代、青銅器時代などを経て文明化された社会を築き上げるまでの12万年間をプレイする。
プレイヤーターン方式で進行し、アクションカードの取得、その使用、人口アクションの実施、安定度のチェック、飢餓のチェックを順に行っていく。エクランド作品の常として学術的な資料価値が高い作りになっており、プレイして楽しいことよりも、文化人類学的な知見を得られることを重視している。
しかしながら、彼の以前の作品と異なり、オリジナルのままのルールで問題なく破綻することなく半日でプレイは決着することができる。その意味で意外であり、ある意味では期待はずれだとも言える。
彼の今までの多くの作品と異なり、ユーロゲーム並みのきちんとしたボックスに入っていて、フルカラーのマップやカードが付いていて、木製キューブが入っていたりするので馴染みの人ほど面食らうのではないか?
ゲームは、ネアンデルタール人、クロマニヨン人、北京原人、ホビットなどからスタートして石器時代、銅器時代、青銅器時代などを経て文明化された社会を築き上げるまでの12万年間をプレイする。
プレイヤーターン方式で進行し、アクションカードの取得、その使用、人口アクションの実施、安定度のチェック、飢餓のチェックを順に行っていく。エクランド作品の常として学術的な資料価値が高い作りになっており、プレイして楽しいことよりも、文化人類学的な知見を得られることを重視している。
しかしながら、彼の以前の作品と異なり、オリジナルのままのルールで問題なく破綻することなく半日でプレイは決着することができる。その意味で意外であり、ある意味では期待はずれだとも言える。
|
|
|
|
コメント(19)
先週のSGC例会で全員初見の状態で4人でプレイ。
途中ルールミスが発見されリセットしたのが15時くらいか、そこから再スタートして完全決着が着いたのが19時半くらい。したがって、4時間半くらいで初見の4人で終わりまでプレイできたことになる。これはエクランド作品として今までで一番短いのではないか?
競技ゲームとしてはかなり問題があり、土着化ダイスの成否の影響がクリティカルに大きいので人事を尽くして天命を待つゲーム。しかし、本作はむしろ勝敗などとは関係なく、各原人が様々な進歩/退歩をすることで、その勢力の帰趨が激変する様を文化人類学的に楽しむものだという気がする。その意味ではアメリカンメガファウナと同系列の作品と言える。
プレイヤーを極端に選ぶゲームであることは事実。ゲームと言うのは勝敗を争うものだと言う尺度しか持っていない人は手を出さないのが賢明かと思う。
途中ルールミスが発見されリセットしたのが15時くらいか、そこから再スタートして完全決着が着いたのが19時半くらい。したがって、4時間半くらいで初見の4人で終わりまでプレイできたことになる。これはエクランド作品として今までで一番短いのではないか?
競技ゲームとしてはかなり問題があり、土着化ダイスの成否の影響がクリティカルに大きいので人事を尽くして天命を待つゲーム。しかし、本作はむしろ勝敗などとは関係なく、各原人が様々な進歩/退歩をすることで、その勢力の帰趨が激変する様を文化人類学的に楽しむものだという気がする。その意味ではアメリカンメガファウナと同系列の作品と言える。
プレイヤーを極端に選ぶゲームであることは事実。ゲームと言うのは勝敗を争うものだと言う尺度しか持っていない人は手を出さないのが賢明かと思う。
1で紹介してあるサイトの管理人です。リンク元からたどりつきました。
昨年末からこのゲームにはまって、ルールを訳したり、開発者BBSに参加するようになったり、訳をBBGにアップしたり、攻略同人誌まで作ったり、挙句の果てにSherraMadreGamesと交渉してまとめて輸入してゲームマーケットに出展したりしております。
>ゲームと言うのは勝敗を争うものだと言う尺度しか持っていない人は手を出さないのが賢明かと思う。
これは激しく同意ですね。他人を蹴落として自分が勝つ方法は禁止されていないんだけど、それはやらないで協力して「レース」を楽しんだほうが吉というのが底流にあります。
このへんは同人誌でも書きました。
ゲームマーケットのブースでお待ちしております。
昨年末からこのゲームにはまって、ルールを訳したり、開発者BBSに参加するようになったり、訳をBBGにアップしたり、攻略同人誌まで作ったり、挙句の果てにSherraMadreGamesと交渉してまとめて輸入してゲームマーケットに出展したりしております。
>ゲームと言うのは勝敗を争うものだと言う尺度しか持っていない人は手を出さないのが賢明かと思う。
これは激しく同意ですね。他人を蹴落として自分が勝つ方法は禁止されていないんだけど、それはやらないで協力して「レース」を楽しんだほうが吉というのが底流にあります。
このへんは同人誌でも書きました。
ゲームマーケットのブースでお待ちしております。
自社サイトの書き出しが
>Since 1992, Sierra Madre Games Company is a producer of educational family boardgames that covers a broad range of subjects in science, history, prehistory, and natural history.
ですから、それは同社の基本路線としてあるのでしょう。
ただ、それも結局デザイナーのPhilの好みなのだとは思います。
たとえば現時点でのデザインとして「3人プレイで第1ターンでアルファがクロマニヨンかネアンデルタールを奴隷にすることを阻止できない」という問題?があり、かつ「奴隷を持つデメリットがほぼない」ので「他人に勝つ」ことを最優先にするプレイヤーがアルファを担当すると、これを行う誘惑を捨てがたいというものがありますが、この点についても(指摘され対策は考えられなくもないのですが)放置だったり。
ぶっちゃけプレイヤーに対して一度は「時代Iで家畜を巡って全面戦争をしてしまってグダグダになる」という展開をプレイさせたい、という意志が働いているように思えます。一度それを経験したプレイヤーは次からは「分け合う」プレイを心がけるようになる(そのほうが明らかに展開は順調)とも思うので…。
だから何も知らない初心者が集まってプレイするとグダグダになって酷評する可能性があったり(笑)。
>Since 1992, Sierra Madre Games Company is a producer of educational family boardgames that covers a broad range of subjects in science, history, prehistory, and natural history.
ですから、それは同社の基本路線としてあるのでしょう。
ただ、それも結局デザイナーのPhilの好みなのだとは思います。
たとえば現時点でのデザインとして「3人プレイで第1ターンでアルファがクロマニヨンかネアンデルタールを奴隷にすることを阻止できない」という問題?があり、かつ「奴隷を持つデメリットがほぼない」ので「他人に勝つ」ことを最優先にするプレイヤーがアルファを担当すると、これを行う誘惑を捨てがたいというものがありますが、この点についても(指摘され対策は考えられなくもないのですが)放置だったり。
ぶっちゃけプレイヤーに対して一度は「時代Iで家畜を巡って全面戦争をしてしまってグダグダになる」という展開をプレイさせたい、という意志が働いているように思えます。一度それを経験したプレイヤーは次からは「分け合う」プレイを心がけるようになる(そのほうが明らかに展開は順調)とも思うので…。
だから何も知らない初心者が集まってプレイするとグダグダになって酷評する可能性があったり(笑)。
otakutalker@土モ07aさんに教えてもらってやりました。
確かに勝敗を競うというより、原始人から初めて進化を楽しむという育成系ゲームの感じ
がした。歴史か生物の授業みたいな感じ。アメリカンメガファウナと同じ作者
だそうだが、なんとなく雰囲気に相通じるものがある。アメリカンメガファウナとオリジンを
合体させて遊ぶこともできるそうだがどうなるんだ。
転変地位でクロマニオン人がアフリカから出れなくなる。その後も転変地位が続き、どこも
通れなくなる。ネアンデルタール人になって動物の土着化を狙うが失敗。火山の噴火なども
ありさんざんだが、しょうがないので2の時代に突入して家畜の襲撃でエネルギー1を得る。
その後大西洋を渡り、アメリカ大陸に着く。そこで5都市まで作り成人も増やす。
混乱させて時代3に行きたがったがこういう時に限ってダイスの目が大きくて成功しない。
石油の採掘を試したらうまくいってエネルギー2を得ることができた。混乱させて時代3に進め、
すぐゴールデンエージに進める。なぜか蛮族の襲来で他の人に使っているので、私も模倣して
他の人のポイントを削って混乱させて勝利した。
すごい面白いとまでは思わなかったが、各原始人の種族を能力を解放して進化させるところなど、
他にはない独特の味がある。模倣や家畜の襲撃など遅れないような仕組みが取り入れられているが
それだけに種族差があまり生まれない気がする。逆に最終ポイントの計算が3の時代までしか行かない
と文化や政治は再大3点なのに対して成人の数はそれ以上取れるので有利な気がした。
確かに勝敗を競うというより、原始人から初めて進化を楽しむという育成系ゲームの感じ
がした。歴史か生物の授業みたいな感じ。アメリカンメガファウナと同じ作者
だそうだが、なんとなく雰囲気に相通じるものがある。アメリカンメガファウナとオリジンを
合体させて遊ぶこともできるそうだがどうなるんだ。
転変地位でクロマニオン人がアフリカから出れなくなる。その後も転変地位が続き、どこも
通れなくなる。ネアンデルタール人になって動物の土着化を狙うが失敗。火山の噴火なども
ありさんざんだが、しょうがないので2の時代に突入して家畜の襲撃でエネルギー1を得る。
その後大西洋を渡り、アメリカ大陸に着く。そこで5都市まで作り成人も増やす。
混乱させて時代3に行きたがったがこういう時に限ってダイスの目が大きくて成功しない。
石油の採掘を試したらうまくいってエネルギー2を得ることができた。混乱させて時代3に進め、
すぐゴールデンエージに進める。なぜか蛮族の襲来で他の人に使っているので、私も模倣して
他の人のポイントを削って混乱させて勝利した。
すごい面白いとまでは思わなかったが、各原始人の種族を能力を解放して進化させるところなど、
他にはない独特の味がある。模倣や家畜の襲撃など遅れないような仕組みが取り入れられているが
それだけに種族差があまり生まれない気がする。逆に最終ポイントの計算が3の時代までしか行かない
と文化や政治は再大3点なのに対して成人の数はそれ以上取れるので有利な気がした。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
長時間ボードゲーム 更新情報
長時間ボードゲームのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 77419人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 209453人
- 3位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19956人