柏木巻を読み終えましたので、横笛巻に入ります。
横笛巻の読みはこちらのトピックで進めてまいります。
柏木巻についてのご感想などは下記トピックに書き込んでください。
まだまだ話し足りないことなどありましたら是非どうぞ。
柏木巻を読む
https:/
輪読に当たっては、最初に「宿題申請」としてどこからどこまでを読むか申告してください。
その後、訳が出来上がったら原文と現代語訳を書き込んでください。
他の方が担当なさった箇所への感想や疑問も歓迎いたします。
別トピックに「【読み】の進め方」として、基本的なルールをまとめましたので、こちらもご一読いただければと思います。
https:/
横笛巻の読みはこちらのトピックで進めてまいります。
柏木巻についてのご感想などは下記トピックに書き込んでください。
まだまだ話し足りないことなどありましたら是非どうぞ。
柏木巻を読む
https:/
輪読に当たっては、最初に「宿題申請」としてどこからどこまでを読むか申告してください。
その後、訳が出来上がったら原文と現代語訳を書き込んでください。
他の方が担当なさった箇所への感想や疑問も歓迎いたします。
別トピックに「【読み】の進め方」として、基本的なルールをまとめましたので、こちらもご一読いただければと思います。
https:/
|
|
|
|
コメント(57)
>>[17]
お忙しい中の素早い読み、お疲れ様です。
率直に本当のことだけを話せたらどんなに楽だろうと思いますね。
朱雀院「おんどりゃ、大事の娘を粗末に扱いおって。どこまでワシをコケにすれば気がすむのや」
源氏「出来の悪い娘を押し付けて、おのれだけ悠々と出家しくさって、その言い草はなんじゃ。こっちは娘の不始末まで尻ぬぐいしとるのや、分っとるんか、ボケ」
女三の宮「うちは何も悪いことしてへん。知らん男が忍んできたんは小侍従が悪いんや、嫌味言われ続けてかなわんからおもうさまのとこ行かせて」
もともとかしずかれるだけの人形のような女三の宮、自分の意思を通したのは出家だけで、それも辛い状況をその場逃れしただけでした。言い方は悪いけど知能もあまり発達していなかったと思われ、女二の宮みたいにしっかりした母親もない状況では、私が朱雀院でも源氏に白羽の矢を立てると思います。うっかり若い公達に嫁がせたりしたらどんな扱いをされるやら。
源氏の元にやってとりあえず生活の場だけ保障されたことに満足しておけばよかったのに、紫の上の立場を危うくするような挙に出たことが間違いでしたね。
「これでは到底紫の上に叶うはずもない」
と思ったなら、頭を下げてこんな娘でもどうか許してやってくださいとお願いするのが筋でしょうに。
でもそれができないのが帝というものなので、帝・内親王であるからにはどんなに不出来でもあがめられて当然という意識があったのでしょう。
若くてあまり世間を知らない女性が男に手籠めにされて辛い目に遭う話は古今東西山ほどあるし、今でも珍しいことでもなく、そういう意味では女三の宮にはとても同情していますが、魅力は感じませんね。柏木は幻に恋して幻に殺されたんだよね、と思っています。
お忙しい中の素早い読み、お疲れ様です。
率直に本当のことだけを話せたらどんなに楽だろうと思いますね。
朱雀院「おんどりゃ、大事の娘を粗末に扱いおって。どこまでワシをコケにすれば気がすむのや」
源氏「出来の悪い娘を押し付けて、おのれだけ悠々と出家しくさって、その言い草はなんじゃ。こっちは娘の不始末まで尻ぬぐいしとるのや、分っとるんか、ボケ」
女三の宮「うちは何も悪いことしてへん。知らん男が忍んできたんは小侍従が悪いんや、嫌味言われ続けてかなわんからおもうさまのとこ行かせて」
もともとかしずかれるだけの人形のような女三の宮、自分の意思を通したのは出家だけで、それも辛い状況をその場逃れしただけでした。言い方は悪いけど知能もあまり発達していなかったと思われ、女二の宮みたいにしっかりした母親もない状況では、私が朱雀院でも源氏に白羽の矢を立てると思います。うっかり若い公達に嫁がせたりしたらどんな扱いをされるやら。
源氏の元にやってとりあえず生活の場だけ保障されたことに満足しておけばよかったのに、紫の上の立場を危うくするような挙に出たことが間違いでしたね。
「これでは到底紫の上に叶うはずもない」
と思ったなら、頭を下げてこんな娘でもどうか許してやってくださいとお願いするのが筋でしょうに。
でもそれができないのが帝というものなので、帝・内親王であるからにはどんなに不出来でもあがめられて当然という意識があったのでしょう。
若くてあまり世間を知らない女性が男に手籠めにされて辛い目に遭う話は古今東西山ほどあるし、今でも珍しいことでもなく、そういう意味では女三の宮にはとても同情していますが、魅力は感じませんね。柏木は幻に恋して幻に殺されたんだよね、と思っています。
【読み】 薫君、筍をかじる(前半)
長い段なので二回に分けます。
また【原文】【訳】と【語句】【感想】も分けますので、全部で四回の投稿となります。
今日のところは前半部分でご容赦ください。後半は来週にでも!
【原文】渋谷栄一氏校訂「源氏物語の世界」
若君は、乳母のもとに寝たまへりける、起きて這ひ出でたまひて、御袖を引きまつはれたてまつりたまふさま、いとうつくし。
白き羅に、唐の小紋の紅梅の御衣の裾、いと長くしどけなげに引きやられて、御身はいとあらはにて、うしろの限りに着なしたまへるさまは、例のことなれど、いとらうたげに白くそびやかに、柳を削りて作りたらむやうなり。
頭は露草してことさらに色どりたらむ心地して、口つきうつくしうにほひ、まみのびらかに、恥づかしう薫りたるなどは、なほいとよく思ひ出でらるれど、
「かれは、いとかやうに際離れたるきよらはなかりしものを、いかでかからむ。宮にも似たてまつらず、今より気高くものものしう、さま異に見えたまへるけしきなどは、わが御鏡の影にも似げなからず」見なされたまふ。
わづかに歩みなどしたまふほどなり。この筍の櫑子に、何とも知らず立ち寄りて、いとあわたたしう取り散らして、食ひかなぐりなどしたまへば、
「あな、らうがはしや。いと不便なり。かれ取り隠せ。食ひ物に目とどめたまふと、もの言ひさがなき女房もこそ言ひなせ」
とて、笑ひたまふ。かき抱きたまひて、
「この君のまみのいとけしきあるかな。小さきほどの稚児を、あまた見ねばにやあらむ、かばかりのほどは、ただいはけなきものとのみ見しを、今よりいとけはひ異なるこそ、わづらはしけれ。女宮ものしたまふめるあたりに、かかる人生ひ出でて、心苦しきこと、誰がためにもありなむかし。あはれ、そのおのおのの生ひゆく末までは、見果てむとすらむやは。花の盛りは、ありなめど」
と、うちまもりきこえたまふ。
「うたて、ゆゆしき御ことにも」
と、人びとは聞こゆ。
【大猫 訳】
若君は乳母の元で寝ていたのですが、起きて這い這いして出ていらっしゃいました。源氏の大殿のお袖を引いたりまとわりついたりするのが、すごくお可愛らしい様子です。
白い薄物の上に唐織の小紋の紅梅色のお召し物ですが、這い這いするものですから、裾を長々としどけなく引きずり、着物は後ろへ寄ってしまって御身体が丸見えです。そういうことは、このくらいの赤ん坊にはよくあることなのですが、この君はひときわ可愛らしくて色白でほっそりしていて、まるで柳を削ってこしらえたようです。
剃りたてのおつむは露草でわざわざ色を付けたように青々として、口元は愛らしさに溢れ、お目はゆったりと切れ長で気高さが薫るようで、やはりあの亡き人を思い出されるのですが、
源氏「彼はこんなにも水際立って美しくはなかったものを、なぜこの子はこれほどの器量なのか。母宮にも似ていない。今から気品があり悠々として、明らかに常人とは違う美貌は、鏡の中の私の姿に似ていないでもないかな」と見ておられます。
ちょっと歩き始められた頃です。筍を置いた櫑子に何心もなくよちよち立ち寄って、せわしげに取り散らかしては食いかじったりしておられるので、
源氏「なんだ、お行儀の悪い。だめじゃないか。あれを片付けなさい。食い物に目を付ける子だと口の悪い女房が言い出しかねない」
とお笑いなさいます。そうして若君を抱き取られて、
源氏「この子の目元は何とも言えない色気があるな。小さな子をあまり見たことがないからかもしれないが、このくらいの子はただ幼いだけと思っていたのだけど、この子は今からまるで人と違って見えるじゃないか。やっかいなことだね。女宮がいらっしゃる近くに、こんな美男が育っていては、お互いにまずい事態が起きてしまうかもしれないよ。まあもっとも、そう言う私が子供たちが大きくなるのを見届けることができるかな。『花の盛りはありなめど』、だね」
と、若君の顔を見守りながらおっしゃいました。
女房たち「いやだわ、縁起でもないことを」
と御前の人々は申し上げます。
長い段なので二回に分けます。
また【原文】【訳】と【語句】【感想】も分けますので、全部で四回の投稿となります。
今日のところは前半部分でご容赦ください。後半は来週にでも!
【原文】渋谷栄一氏校訂「源氏物語の世界」
若君は、乳母のもとに寝たまへりける、起きて這ひ出でたまひて、御袖を引きまつはれたてまつりたまふさま、いとうつくし。
白き羅に、唐の小紋の紅梅の御衣の裾、いと長くしどけなげに引きやられて、御身はいとあらはにて、うしろの限りに着なしたまへるさまは、例のことなれど、いとらうたげに白くそびやかに、柳を削りて作りたらむやうなり。
頭は露草してことさらに色どりたらむ心地して、口つきうつくしうにほひ、まみのびらかに、恥づかしう薫りたるなどは、なほいとよく思ひ出でらるれど、
「かれは、いとかやうに際離れたるきよらはなかりしものを、いかでかからむ。宮にも似たてまつらず、今より気高くものものしう、さま異に見えたまへるけしきなどは、わが御鏡の影にも似げなからず」見なされたまふ。
わづかに歩みなどしたまふほどなり。この筍の櫑子に、何とも知らず立ち寄りて、いとあわたたしう取り散らして、食ひかなぐりなどしたまへば、
「あな、らうがはしや。いと不便なり。かれ取り隠せ。食ひ物に目とどめたまふと、もの言ひさがなき女房もこそ言ひなせ」
とて、笑ひたまふ。かき抱きたまひて、
「この君のまみのいとけしきあるかな。小さきほどの稚児を、あまた見ねばにやあらむ、かばかりのほどは、ただいはけなきものとのみ見しを、今よりいとけはひ異なるこそ、わづらはしけれ。女宮ものしたまふめるあたりに、かかる人生ひ出でて、心苦しきこと、誰がためにもありなむかし。あはれ、そのおのおのの生ひゆく末までは、見果てむとすらむやは。花の盛りは、ありなめど」
と、うちまもりきこえたまふ。
「うたて、ゆゆしき御ことにも」
と、人びとは聞こゆ。
【大猫 訳】
若君は乳母の元で寝ていたのですが、起きて這い這いして出ていらっしゃいました。源氏の大殿のお袖を引いたりまとわりついたりするのが、すごくお可愛らしい様子です。
白い薄物の上に唐織の小紋の紅梅色のお召し物ですが、這い這いするものですから、裾を長々としどけなく引きずり、着物は後ろへ寄ってしまって御身体が丸見えです。そういうことは、このくらいの赤ん坊にはよくあることなのですが、この君はひときわ可愛らしくて色白でほっそりしていて、まるで柳を削ってこしらえたようです。
剃りたてのおつむは露草でわざわざ色を付けたように青々として、口元は愛らしさに溢れ、お目はゆったりと切れ長で気高さが薫るようで、やはりあの亡き人を思い出されるのですが、
源氏「彼はこんなにも水際立って美しくはなかったものを、なぜこの子はこれほどの器量なのか。母宮にも似ていない。今から気品があり悠々として、明らかに常人とは違う美貌は、鏡の中の私の姿に似ていないでもないかな」と見ておられます。
ちょっと歩き始められた頃です。筍を置いた櫑子に何心もなくよちよち立ち寄って、せわしげに取り散らかしては食いかじったりしておられるので、
源氏「なんだ、お行儀の悪い。だめじゃないか。あれを片付けなさい。食い物に目を付ける子だと口の悪い女房が言い出しかねない」
とお笑いなさいます。そうして若君を抱き取られて、
源氏「この子の目元は何とも言えない色気があるな。小さな子をあまり見たことがないからかもしれないが、このくらいの子はただ幼いだけと思っていたのだけど、この子は今からまるで人と違って見えるじゃないか。やっかいなことだね。女宮がいらっしゃる近くに、こんな美男が育っていては、お互いにまずい事態が起きてしまうかもしれないよ。まあもっとも、そう言う私が子供たちが大きくなるのを見届けることができるかな。『花の盛りはありなめど』、だね」
と、若君の顔を見守りながらおっしゃいました。
女房たち「いやだわ、縁起でもないことを」
と御前の人々は申し上げます。
【読み】 薫君、筍をかじる(前半)
【語句】
●羅 うすものと読む。薄い絹織物。羅や紗。ここでは薫君が下着に着ています。デリケートな赤ん坊の肌に相応しいですね。
●唐の小紋の紅梅の御衣
唐は唐織、中国産の絹織物または中国風の絹織物。
唐織と言うと能楽の衣装や西陣織のような絢爛豪華なものを思い出しますが、それは後世のものと思われます。
小紋は今と用法が同じで細かい模様のことで、細かい模様の入った紅梅色のお召し物の意味です。
子供らしく可愛らしい色合いです。
●うしろの限りに着なしたまへる
子供なので衣装はゆるやかで、もちろん袴も履いていません。這い這いして移動するので前ははだけて襟は背中へ寄り、袖だけ残った丸裸に近い状態になっていたと思われます。おむつは付けていたのかな?
筍の頃だから春先でまだ寒さが残る頃です。早く服を着せてあげて! 若君が冷えちゃうよ、お腹壊しちゃうよ、熱出しちゃうよ、と心で叫んでしまいました。
●頭は露草してことさらに色どりたらむ
当時、幼児は頭を剃っていました。病気の予防と髪が豊かに伸びるようにと願いを込めてのようです。
三歳くらいで「髪置(かみおき)」の儀式を行い髪を伸ばし始めたそうです。これが七五三の三の由来で、ちなみに五歳は「袴着」、七歳は「帯解き」です。子供の死亡率が高かった時代、七歳まで育てばちょっと安心できたのでしょう。
中国にも幼児の頭を剃る習慣がありますが、額の上だけちょっびっと一塊の毛を残したりするのは、儒教の教えを守る意味があるらしいです。「身体髪膚これを父母に受くあえて毀傷せざるは孝の始めなり」と言われてしまうので、父母からもらった髪の毛は丸坊主にはしていませんよと言う言い訳だったとか。
●まみのびらかに
感想でも述べますが、ここでは「ゆったり切れ長」と訳してみます。
●小さきほどの稚児を、あまた見ねばにやあらむ
「柏木」巻の若君の五十日の祝いで、
「いと心やすくうち笑みて、つぶつぶと肥えて白ううつくし。大将などの稚児生ひ、ほのかに思し出づるには似たまはず。女御の御宮たち、はた、父帝の御方ざまに、王気づきて気高うこそおはしませ、ことにすぐれてめでたうしもおはせず」
とあるので、赤ん坊を見たことがないわけでもないのです。今まで見てきた最高の血筋の赤ん坊よりも、この子は美しいと源氏は認めています。
●花の盛りはありなめど
春ごとに花の盛りはありなめどあひ見むことは命なりけり
(『古今和歌集』巻二春下、読人しらず)
花の盛り=子供たちが成長した頃
あひ見むことは命なりけり=それを見届けることができるかどうかは寿命しだいだ。
という意味を込めています。
【感想】
若君の五十日の祝いは三月でしたので、お誕生日は一月中旬でしょうか。筍の季節になっていますから、今満一歳と一ヶ月くらいでしょうかね。このくらいの子供は本当に可愛いです。まだ言葉はちゃんと話せませんが表情が豊かで、日一日とできることが増えていきます。
ねんねして、おっきして、はいはいして、よちよち歩きして、バイバイして、トントンして、バンザイして。。。赤ちゃんの薫君はとてもお利口です。寝起きだと泣き騒ぐ子もいるのですが、機嫌よく高速這い這いでまっすぐ源氏の君のもとへ来てじゃれついて笑っています。
さて、醜貌の描写は容赦なく具体的に描く『源氏物語』ですが、美しい顔の具体的描写はあんまりありません。今回はその貴重な描写が見られます。
「口つきうつくしうにほひ、まみのびらかに、恥づかしう薫りたる」
口元は「にほひ」、目元は「薫る」、どちらも艶やかで美しい様を表します。
五十日の祝いの際にも再三、目の美しさが強調されています。
「この君、いとあてなるに添へて、愛敬づき、まみの薫りて、笑がちなるなどを、いとあはれと見たまふ。思ひなしにや、なほ、いとようおぼえたりかし。ただ今ながら、眼居ののどかに恥づかしきさまも、やう離れて、薫りをかしき顔ざまなり。」
まずは色白。顔はふっくらいしている。
目元は上品な切れ長で目つきはゆったりと大人風。
口は上品に小さく、つやつやしている。
が美男美女の条件のようですね。
となると『国宝・源氏物語絵巻』の引目鉤鼻の人物になってしまいますね。
待てよ……これはどこかで見た顔だな。
うん、なんだかいつもこんな顔を見ている気がする。
誰だろう? 誰だっけ?
そうだ、お相撲さんだ!
稀勢の里、鶴竜、熱海富士。
どうです。みなさんの引目鉤鼻っぷりは!
このまま烏帽子を被せたらまんま絵巻の登場人物じゃないですか。
と、脱線はここまでにして後半の読みに入ります。
一週間ほどお時間下さい。
【語句】
●羅 うすものと読む。薄い絹織物。羅や紗。ここでは薫君が下着に着ています。デリケートな赤ん坊の肌に相応しいですね。
●唐の小紋の紅梅の御衣
唐は唐織、中国産の絹織物または中国風の絹織物。
唐織と言うと能楽の衣装や西陣織のような絢爛豪華なものを思い出しますが、それは後世のものと思われます。
小紋は今と用法が同じで細かい模様のことで、細かい模様の入った紅梅色のお召し物の意味です。
子供らしく可愛らしい色合いです。
●うしろの限りに着なしたまへる
子供なので衣装はゆるやかで、もちろん袴も履いていません。這い這いして移動するので前ははだけて襟は背中へ寄り、袖だけ残った丸裸に近い状態になっていたと思われます。おむつは付けていたのかな?
筍の頃だから春先でまだ寒さが残る頃です。早く服を着せてあげて! 若君が冷えちゃうよ、お腹壊しちゃうよ、熱出しちゃうよ、と心で叫んでしまいました。
●頭は露草してことさらに色どりたらむ
当時、幼児は頭を剃っていました。病気の予防と髪が豊かに伸びるようにと願いを込めてのようです。
三歳くらいで「髪置(かみおき)」の儀式を行い髪を伸ばし始めたそうです。これが七五三の三の由来で、ちなみに五歳は「袴着」、七歳は「帯解き」です。子供の死亡率が高かった時代、七歳まで育てばちょっと安心できたのでしょう。
中国にも幼児の頭を剃る習慣がありますが、額の上だけちょっびっと一塊の毛を残したりするのは、儒教の教えを守る意味があるらしいです。「身体髪膚これを父母に受くあえて毀傷せざるは孝の始めなり」と言われてしまうので、父母からもらった髪の毛は丸坊主にはしていませんよと言う言い訳だったとか。
●まみのびらかに
感想でも述べますが、ここでは「ゆったり切れ長」と訳してみます。
●小さきほどの稚児を、あまた見ねばにやあらむ
「柏木」巻の若君の五十日の祝いで、
「いと心やすくうち笑みて、つぶつぶと肥えて白ううつくし。大将などの稚児生ひ、ほのかに思し出づるには似たまはず。女御の御宮たち、はた、父帝の御方ざまに、王気づきて気高うこそおはしませ、ことにすぐれてめでたうしもおはせず」
とあるので、赤ん坊を見たことがないわけでもないのです。今まで見てきた最高の血筋の赤ん坊よりも、この子は美しいと源氏は認めています。
●花の盛りはありなめど
春ごとに花の盛りはありなめどあひ見むことは命なりけり
(『古今和歌集』巻二春下、読人しらず)
花の盛り=子供たちが成長した頃
あひ見むことは命なりけり=それを見届けることができるかどうかは寿命しだいだ。
という意味を込めています。
【感想】
若君の五十日の祝いは三月でしたので、お誕生日は一月中旬でしょうか。筍の季節になっていますから、今満一歳と一ヶ月くらいでしょうかね。このくらいの子供は本当に可愛いです。まだ言葉はちゃんと話せませんが表情が豊かで、日一日とできることが増えていきます。
ねんねして、おっきして、はいはいして、よちよち歩きして、バイバイして、トントンして、バンザイして。。。赤ちゃんの薫君はとてもお利口です。寝起きだと泣き騒ぐ子もいるのですが、機嫌よく高速這い這いでまっすぐ源氏の君のもとへ来てじゃれついて笑っています。
さて、醜貌の描写は容赦なく具体的に描く『源氏物語』ですが、美しい顔の具体的描写はあんまりありません。今回はその貴重な描写が見られます。
「口つきうつくしうにほひ、まみのびらかに、恥づかしう薫りたる」
口元は「にほひ」、目元は「薫る」、どちらも艶やかで美しい様を表します。
五十日の祝いの際にも再三、目の美しさが強調されています。
「この君、いとあてなるに添へて、愛敬づき、まみの薫りて、笑がちなるなどを、いとあはれと見たまふ。思ひなしにや、なほ、いとようおぼえたりかし。ただ今ながら、眼居ののどかに恥づかしきさまも、やう離れて、薫りをかしき顔ざまなり。」
まずは色白。顔はふっくらいしている。
目元は上品な切れ長で目つきはゆったりと大人風。
口は上品に小さく、つやつやしている。
が美男美女の条件のようですね。
となると『国宝・源氏物語絵巻』の引目鉤鼻の人物になってしまいますね。
待てよ……これはどこかで見た顔だな。
うん、なんだかいつもこんな顔を見ている気がする。
誰だろう? 誰だっけ?
そうだ、お相撲さんだ!
稀勢の里、鶴竜、熱海富士。
どうです。みなさんの引目鉤鼻っぷりは!
このまま烏帽子を被せたらまんま絵巻の登場人物じゃないですか。
と、脱線はここまでにして後半の読みに入ります。
一週間ほどお時間下さい。
>>[25]
脱線ついでに(笑)
「襁褓」なんてもう字面からして中国から伝わりました感満載なので、早速調べてみました。
唐代の張守節『史記正義』に「襁、長尺二寸、闊八寸、以約小児於背、褓、小児被也」とありました。
襁は赤ん坊を背負うための幅広の布、帯のこと。
褓は赤ん坊を包むための布団。
要するにおんぶ紐とおくるみですね。
赤ちゃんのお世話グッズとして紹介され、「これは便利だ」と使うようになって、そのうちに赤ん坊の着る物がひとまとめで「襁褓」になっていったのかもしれませんね。
「襁褓」は一歳未満の赤ん坊のことを指すようにもなったようです。
ちなみに「嬰児」は生まれたての赤子、「襁褓」は一歳以下の赤ん坊でちゃんと区別があったのですね。
大横綱白鵬について言及ありがとうございます。
お相撲さんはみんな清潔で綺麗なんですが、白鵬はその中でも抜きんでて美しかったです。
本場所中の朝稽古を見せてもらったことがあるのですが、寒い中、湯気が出るまで鍛錬していました。拝みたいくらいに美しい背中でしたよ!
脱線ついでに(笑)
「襁褓」なんてもう字面からして中国から伝わりました感満載なので、早速調べてみました。
唐代の張守節『史記正義』に「襁、長尺二寸、闊八寸、以約小児於背、褓、小児被也」とありました。
襁は赤ん坊を背負うための幅広の布、帯のこと。
褓は赤ん坊を包むための布団。
要するにおんぶ紐とおくるみですね。
赤ちゃんのお世話グッズとして紹介され、「これは便利だ」と使うようになって、そのうちに赤ん坊の着る物がひとまとめで「襁褓」になっていったのかもしれませんね。
「襁褓」は一歳未満の赤ん坊のことを指すようにもなったようです。
ちなみに「嬰児」は生まれたての赤子、「襁褓」は一歳以下の赤ん坊でちゃんと区別があったのですね。
大横綱白鵬について言及ありがとうございます。
お相撲さんはみんな清潔で綺麗なんですが、白鵬はその中でも抜きんでて美しかったです。
本場所中の朝稽古を見せてもらったことがあるのですが、寒い中、湯気が出るまで鍛錬していました。拝みたいくらいに美しい背中でしたよ!
>>[27]
更に脱線して(笑)
おむつ的なものはあったかもしれませんが、保水力など無きに等しく、ウンチを漏らさないようにするための当て布くらいの役割でしょうか。おしっこなら洗えばいいですが、大だとさすがに……(笑)新生児の便は黄疸とか出ていてけっこう強烈だし。
>「御衣」が一番中に着る肌着で、「襁褓」が重ね着する産着の類、「おしく>くみ」は襁褓の上から更に包むもの、という感じなのかもしれません。
そうですね。ひょっとしたら「御衣」は上半身から着せて「襁褓」はおむつ的に下から当てたのかもしれません。それを「おしくくみ」でくるんで赤ちゃんを固定して抱っこをしたのかも。お世話をするには三点セットが揃うのが合理的だと思います。
更に脱線して(笑)
おむつ的なものはあったかもしれませんが、保水力など無きに等しく、ウンチを漏らさないようにするための当て布くらいの役割でしょうか。おしっこなら洗えばいいですが、大だとさすがに……(笑)新生児の便は黄疸とか出ていてけっこう強烈だし。
>「御衣」が一番中に着る肌着で、「襁褓」が重ね着する産着の類、「おしく>くみ」は襁褓の上から更に包むもの、という感じなのかもしれません。
そうですね。ひょっとしたら「御衣」は上半身から着せて「襁褓」はおむつ的に下から当てたのかもしれません。それを「おしくくみ」でくるんで赤ちゃんを固定して抱っこをしたのかも。お世話をするには三点セットが揃うのが合理的だと思います。
お待たせしました。後半読みます!
【読み】 薫君、筍をかじる(後半)
【原文】渋谷栄一氏校訂「源氏物語の世界」
御歯の生ひ出づるに食ひ当てむとて、筍をつと握り待ちて、雫もよよと食ひ濡らしたまへば、
「いとねぢけたる色好みかな」とて、
「憂き節も忘れずながら呉竹の
こは捨て難きものにぞありける」
と、率て放ちて、のたまひかくれど、うち笑ひて、何とも思ひたらず、いとそそかしう、這ひ下り騷ぎたまふ。
月日に添へて、この君のうつくしうゆゆしきまで生ひまさりたまふに、まことに、この憂き節、皆思し忘れぬべし。
「この人の出でものしたまふべき契りにて、さる思ひの外の事もあるにこそはありけめ。逃れ難かなるわざぞかし」
と、すこしは思し直さる。みづからの御宿世も、なほ飽かぬこと多かり。
「あまた集へたまへる中にも、この宮こそは、かたほなる思ひまじらず、人の御ありさまも、思ふに飽かぬところなくてものしたまふべきを、かく思はざりしさまにて見たてまつること」
と思すにつけてなむ、過ぎにし罪許し難く、なほ口惜しかりける。
【大猫 訳】
若君は歯が生え始めた頃でむずがゆいので、噛み当てようと筍を握り持ったままよだれをたらたら流しながらかじっておられます。
源氏「これはまた妙な色好みもあったものだ」と仰り、
源氏「忌まわしいことは忘れぬものの
竹の子を無心にかじるこの子、
これは可愛くて捨てられないな」
と、筍を取り上げて、話しかけられるのですが、若君はニコニコ無心な御様子で、慌ただしくお膝から這い下りて、あちこち動き回っていらっしゃいます。
月日が経つにつれ、この君が愛らしくも不吉なほど美しく成長なさるので、本当にこの「憂き節」も全部忘れてしまいそうです。
源氏「この子が生まれるべき前世からの約束で、あの心外な事件も起こったということかもしれぬ。逃れ難い運めだったのだろう」
と、少し思い直されたりもします。
ご自身の宿命についても満足できないことも多いのです。
源氏「多くの女人が集まったその中でも、この宮こそは、我が正妻として文句のつけようもなく、御自身も六条院の正妻として何不自由ない境遇でいらっしゃるはずだったのに、思いもよらぬ尼姿でお世話することになるとは」
と、お思いになるにつけて、過去の罪はやはり許しがたく、口惜しい思いをなさるのでした。
【読み】 薫君、筍をかじる(後半)
【原文】渋谷栄一氏校訂「源氏物語の世界」
御歯の生ひ出づるに食ひ当てむとて、筍をつと握り待ちて、雫もよよと食ひ濡らしたまへば、
「いとねぢけたる色好みかな」とて、
「憂き節も忘れずながら呉竹の
こは捨て難きものにぞありける」
と、率て放ちて、のたまひかくれど、うち笑ひて、何とも思ひたらず、いとそそかしう、這ひ下り騷ぎたまふ。
月日に添へて、この君のうつくしうゆゆしきまで生ひまさりたまふに、まことに、この憂き節、皆思し忘れぬべし。
「この人の出でものしたまふべき契りにて、さる思ひの外の事もあるにこそはありけめ。逃れ難かなるわざぞかし」
と、すこしは思し直さる。みづからの御宿世も、なほ飽かぬこと多かり。
「あまた集へたまへる中にも、この宮こそは、かたほなる思ひまじらず、人の御ありさまも、思ふに飽かぬところなくてものしたまふべきを、かく思はざりしさまにて見たてまつること」
と思すにつけてなむ、過ぎにし罪許し難く、なほ口惜しかりける。
【大猫 訳】
若君は歯が生え始めた頃でむずがゆいので、噛み当てようと筍を握り持ったままよだれをたらたら流しながらかじっておられます。
源氏「これはまた妙な色好みもあったものだ」と仰り、
源氏「忌まわしいことは忘れぬものの
竹の子を無心にかじるこの子、
これは可愛くて捨てられないな」
と、筍を取り上げて、話しかけられるのですが、若君はニコニコ無心な御様子で、慌ただしくお膝から這い下りて、あちこち動き回っていらっしゃいます。
月日が経つにつれ、この君が愛らしくも不吉なほど美しく成長なさるので、本当にこの「憂き節」も全部忘れてしまいそうです。
源氏「この子が生まれるべき前世からの約束で、あの心外な事件も起こったということかもしれぬ。逃れ難い運めだったのだろう」
と、少し思い直されたりもします。
ご自身の宿命についても満足できないことも多いのです。
源氏「多くの女人が集まったその中でも、この宮こそは、我が正妻として文句のつけようもなく、御自身も六条院の正妻として何不自由ない境遇でいらっしゃるはずだったのに、思いもよらぬ尼姿でお世話することになるとは」
と、お思いになるにつけて、過去の罪はやはり許しがたく、口惜しい思いをなさるのでした。
【読み】 薫君、筍をかじる(後半)
【語句】
●よよ
「よよと泣く」と表現しますが、ヨダレが流れるのも「よよ」なんですね。
水が流れる様子を表しているのでしょうか。
●憂き節も忘れずながら呉竹のこは捨て難きものにぞありける
「憂き節」とはこの子の父が柏木であること。
「呉竹のこは」と「子は」を掛けています。
元歌
今さらに何生ひ出づらむ竹の子の憂き節しげき世とは知らずや
古今集巻十八雑下、もの思ひける時いとけなき子を見てよめる
凡河内躬恒
蓬生巻の冒頭にも、「竹の子の世の憂き節を、時々につけてあつかひきこえたまふに」とあり、元歌では「憂き節」は政治的不遇、生活の困難を指すようです。
●率て放ちて
難解に感じました。
何を「率て」何を「放ちて」なのか。
「率て」を若君を抱き上げてとする翻訳もあるようですが、前半で若君を「かき抱きたまひて」いるので、筍を「率て」「放ちて」と解釈しました。
●ゆゆしきまで生ひまさりたまふ
あまりに美しい人は早死にすると思われていたようです。
紅葉賀で弘徽殿女御がこんなこと言ってますね。
「神など、空にめでつべき容貌かな。うたてゆゆし」
昔の中国では子供、特に男の子に「醜児」とか「石頭」とか「犬子」など、わざと変な幼名を付けて、「これはみっともない子供です」と神様に連れて行かないようにアピールしたと聞きます。
『千夜一夜物語』を読んでいると、美しい子供に恵まれた父母が、魔神に連れ去れるのを恐れるあまり、地下室に閉じ込めて育てるみたいな話もありました。
これも子供の死亡率が高かった時代だからこそと思います。
●集へたまへる
これは四段活用ではなく下二段活用の他動詞か。
集ひたまへるではなく集へたまへるなので、女君が集まったのではなく女君を集めたのですね。
四十年ぶりに受験でもした気分です。
でも、源氏自身のセリフに入れたので、敬語は取り外しました。
●かたほなる思ひ
不十分な思い、光源氏という男の配偶者として不十分に思える点。
紫の上は親王の娘(女王)とは言え、嫡出ではないので「かたほなり」だったということですかね。たとえ嫡出の娘であったとしても内親王には叶わないということでしょう。
【感想】
「憂き節も忘れずながら」って皆がいる前で言うかなと思いました。
それとも若君だけに聞こえるように詠んだのかな。
直前に「花の盛りはありなめど」なんて言ったから、何も知らない女房は自分の寿命を気にしているのかと勘違いしたかもしれません。
女三の宮が聞いていたとしたら、「また例によって嫌味を言ってるよ」と思ったに違いありません。「子は捨て難ききものにぞありける」と言ってくれているのにね。
「この宮こそは、かたほなる思ひまじらず」とは、どの口が言ってるんだと思ってしまいます。紫の上を苦しめたことをあれほど後悔しておいて、女三の宮の尼姿を見てまたまた悔しがる。
もっともそれは源氏の本音でもあったのでしょう。
若菜上で、女三の宮処遇に悩む朱雀院に、左中弁が源氏自身の言葉であるとしてこんなこと言ってるし。
「この世の栄え、末の世に過ぎて、身に心もとなきことはなきを、女の筋にてなむ、人のもどきをも負ひ、わが心にも飽かぬこともある」
勝手な言い草です。
紫の上を誰よりも愛していながらも「北の方」にはしなかった、ていうか親の許可のない結婚だからできなかったのですが、それもこれも自らがなしたことです。
それもまた源氏のありのままの姿で、矛盾だらけ後悔だらけでも生きていくしかない。
幼い薫君の無邪気な姿だけが救いですが、天使のようなこの子は、生まれながらに辛い宿命を負っています。
つくづくひどい話だなあ。
この巻はこの後も子供たちが活躍しますね。千年前も子供のすることは同じなんだなとほほえましくなります。後の巻で活躍する人々の愛らしい姿を目に焼き付けておきましょう。
【語句】
●よよ
「よよと泣く」と表現しますが、ヨダレが流れるのも「よよ」なんですね。
水が流れる様子を表しているのでしょうか。
●憂き節も忘れずながら呉竹のこは捨て難きものにぞありける
「憂き節」とはこの子の父が柏木であること。
「呉竹のこは」と「子は」を掛けています。
元歌
今さらに何生ひ出づらむ竹の子の憂き節しげき世とは知らずや
古今集巻十八雑下、もの思ひける時いとけなき子を見てよめる
凡河内躬恒
蓬生巻の冒頭にも、「竹の子の世の憂き節を、時々につけてあつかひきこえたまふに」とあり、元歌では「憂き節」は政治的不遇、生活の困難を指すようです。
●率て放ちて
難解に感じました。
何を「率て」何を「放ちて」なのか。
「率て」を若君を抱き上げてとする翻訳もあるようですが、前半で若君を「かき抱きたまひて」いるので、筍を「率て」「放ちて」と解釈しました。
●ゆゆしきまで生ひまさりたまふ
あまりに美しい人は早死にすると思われていたようです。
紅葉賀で弘徽殿女御がこんなこと言ってますね。
「神など、空にめでつべき容貌かな。うたてゆゆし」
昔の中国では子供、特に男の子に「醜児」とか「石頭」とか「犬子」など、わざと変な幼名を付けて、「これはみっともない子供です」と神様に連れて行かないようにアピールしたと聞きます。
『千夜一夜物語』を読んでいると、美しい子供に恵まれた父母が、魔神に連れ去れるのを恐れるあまり、地下室に閉じ込めて育てるみたいな話もありました。
これも子供の死亡率が高かった時代だからこそと思います。
●集へたまへる
これは四段活用ではなく下二段活用の他動詞か。
集ひたまへるではなく集へたまへるなので、女君が集まったのではなく女君を集めたのですね。
四十年ぶりに受験でもした気分です。
でも、源氏自身のセリフに入れたので、敬語は取り外しました。
●かたほなる思ひ
不十分な思い、光源氏という男の配偶者として不十分に思える点。
紫の上は親王の娘(女王)とは言え、嫡出ではないので「かたほなり」だったということですかね。たとえ嫡出の娘であったとしても内親王には叶わないということでしょう。
【感想】
「憂き節も忘れずながら」って皆がいる前で言うかなと思いました。
それとも若君だけに聞こえるように詠んだのかな。
直前に「花の盛りはありなめど」なんて言ったから、何も知らない女房は自分の寿命を気にしているのかと勘違いしたかもしれません。
女三の宮が聞いていたとしたら、「また例によって嫌味を言ってるよ」と思ったに違いありません。「子は捨て難ききものにぞありける」と言ってくれているのにね。
「この宮こそは、かたほなる思ひまじらず」とは、どの口が言ってるんだと思ってしまいます。紫の上を苦しめたことをあれほど後悔しておいて、女三の宮の尼姿を見てまたまた悔しがる。
もっともそれは源氏の本音でもあったのでしょう。
若菜上で、女三の宮処遇に悩む朱雀院に、左中弁が源氏自身の言葉であるとしてこんなこと言ってるし。
「この世の栄え、末の世に過ぎて、身に心もとなきことはなきを、女の筋にてなむ、人のもどきをも負ひ、わが心にも飽かぬこともある」
勝手な言い草です。
紫の上を誰よりも愛していながらも「北の方」にはしなかった、ていうか親の許可のない結婚だからできなかったのですが、それもこれも自らがなしたことです。
それもまた源氏のありのままの姿で、矛盾だらけ後悔だらけでも生きていくしかない。
幼い薫君の無邪気な姿だけが救いですが、天使のようなこの子は、生まれながらに辛い宿命を負っています。
つくづくひどい話だなあ。
この巻はこの後も子供たちが活躍しますね。千年前も子供のすることは同じなんだなとほほえましくなります。後の巻で活躍する人々の愛らしい姿を目に焼き付けておきましょう。
>>[38]
いろいろ大変な中での読み、ありがとうございました。
いよいよ夕霧が中心の物語が展開しますね。
これまでずっとオブザーバーの位置にいた夕霧が主役となって活躍します。
短い間とは言え、源氏中心の視点ではない物語が本格化する感があります。
聞いてみたくてたまらないけど、下手に持って行くとヤバいし、何かそれっぽいきっかけがあるといいんだけどな、って感じがすごくよく出ています。「そうだ、夕霧、行け、突っ込め」と当時の読者も思っていたことでしょう。
>●聞こしめさむ
現代語の感覚だと「聞こしめさむ」は「聞こしめさせむ」の方がしっくり来ますね。主語が変わらずに済むし。でも文章の途中で主語が変わるなんて『源氏物語』では当たり前ですので分かりませんね。
雲居雁の家と藤典侍の家は両方とも子供が大勢いて、いつも賑やかなことでしょうね。それがどれほど幸せか、分っていないわけではないでしょうが、落ちぶれた境遇の女宮、秋の気配、しみじみと奥ゆかしい暮らしぶりと、今まであまり味わったことのない大人の女性の雰囲気に惹かれてしまったのですね。
勝手と言えば勝手ですが、よくあることと言えばよくあることで。「まめ人」とは言えそこは源氏の息子だなと思ったり。
新しい読み手が待たれますね。
どなたか次をお読みくださいませんか。
いろいろ大変な中での読み、ありがとうございました。
いよいよ夕霧が中心の物語が展開しますね。
これまでずっとオブザーバーの位置にいた夕霧が主役となって活躍します。
短い間とは言え、源氏中心の視点ではない物語が本格化する感があります。
聞いてみたくてたまらないけど、下手に持って行くとヤバいし、何かそれっぽいきっかけがあるといいんだけどな、って感じがすごくよく出ています。「そうだ、夕霧、行け、突っ込め」と当時の読者も思っていたことでしょう。
>●聞こしめさむ
現代語の感覚だと「聞こしめさむ」は「聞こしめさせむ」の方がしっくり来ますね。主語が変わらずに済むし。でも文章の途中で主語が変わるなんて『源氏物語』では当たり前ですので分かりませんね。
雲居雁の家と藤典侍の家は両方とも子供が大勢いて、いつも賑やかなことでしょうね。それがどれほど幸せか、分っていないわけではないでしょうが、落ちぶれた境遇の女宮、秋の気配、しみじみと奥ゆかしい暮らしぶりと、今まであまり味わったことのない大人の女性の雰囲気に惹かれてしまったのですね。
勝手と言えば勝手ですが、よくあることと言えばよくあることで。「まめ人」とは言えそこは源氏の息子だなと思ったり。
新しい読み手が待たれますね。
どなたか次をお読みくださいませんか。
週末、間に合いました。読みます。
【原文】渋谷栄一氏校訂「源氏物語の世界」
和琴を引き寄せたまへれば、律に調べられて、いとよく弾きならしたる、人香にしみて、なつかしうおぼゆ。
「かやうなるあたりに、思ひのままなる好き心ある人は、静むることなくて、さま悪しきけはひをもあらはし、さるまじき名をも立つるぞかし」
など、思ひ続けつつ、掻き鳴らしたまふ。
故君の常に弾きたまひし琴なりけり。をかしき手一つなど、すこし弾きたまひて、
「あはれ、いとめづらかなる音に掻き鳴らしたまひしはや。この御琴にも籠もりてはべらむかし。承りあらはしてしがな」
とのたまへば、
「琴の緒絶えにし後より、昔の御童遊びの名残をだに、思ひ出でたまはずなむなりにてはべめる。院の御前にて、女宮たちのとりどりの御琴ども、試みきこえたまひしにも、かやうの方は、おぼめかしからずものしたまふとなむ、定めきこえたまふめりしを、あらぬさまにほれぼれしうなりて、眺め過ぐしたまふめれば、世の憂きつまにといふやうになむ見たまふる」
と聞こえたまへば、
「いとことわりの御思ひなりや。限りだにある」
と、うち眺めて、琴は押しやりたまへれば、
「かれ、なほさらば、声に伝はることもやと、聞きわくばかり鳴らさせたまへ。ものむつかしう思うたまへ沈める耳をだに、明きらめはべらむ」
と聞こえたまふを、
「しか伝はる中の緒は、異にこそははべらめ。それをこそ承らむとは聞こえつれ」
とて、御簾のもと近く押し寄せたまへど、とみにしも受けひきたまふまじきことなれば、しひても聞こえたまはず。
【大猫 訳】
夕霧の大将様が和琴をお引き寄せになると、律に整えられております。よく弾き込まれており、その人の移り香が匂い立ってなんとも心惹かれます。
夕霧「こんな感じの女所帯で、気ままにあだ心のある人だったとしたら、心を抑えられなくてみっともないことをしでかして悪い評判を立てることになるんだろうな」
などと思い続けながら掻き鳴らします。
これは亡き柏木様が弾き慣らした和琴なのでした。夕霧様は面白い一節を少しお弾きになって、
夕霧「ああ、あの人が弾く音色は本当に素晴らしかったなあ。この琴にも彼の音が籠っているのでしょうね。お聞かせいただきたいものです」
と仰いました。
御息所「殿が亡くなられた後は、昔の子供の頃のお遊びさえ思い起こされることもない有様でございまして。父院の御前で女宮様方がそれぞれ御琴を競われた時には、この方面では悪くないだろうと御判定されたようなのですが、今はもう別人のように呆けてしまって毎日思い悩んでお過ごしのようですから、この琴も辛い思い出の品になってしまったものと存じます」
と申し上げます。
夕霧「辛い物思いはもっともなこと。古歌にも『限りだにある』と申しますし」
と、しばらく物思いに沈んだ様子になり、琴を御息所の方へ押しやられます。
御息所「この琴は、やはりあなた様がお弾きくださいませ。亡き人の音色が伝わるものならば、それと聞き分けられるほどにお鳴らしください。憂鬱に思い沈んだこの耳だけでもはっきりいたしましょう」
と申し上げなさいました。
しかし大将は、
夕霧「夫婦の仲に伝わる音色こそ格別なものでございましょう。それをこそ拝聴したいと申し上げているのです」
と言って、和琴を御簾の近くまで押し寄せなさいますが、急にはお引き受けなさいそうもないことですから、無理じいはなさいません。
【原文】渋谷栄一氏校訂「源氏物語の世界」
和琴を引き寄せたまへれば、律に調べられて、いとよく弾きならしたる、人香にしみて、なつかしうおぼゆ。
「かやうなるあたりに、思ひのままなる好き心ある人は、静むることなくて、さま悪しきけはひをもあらはし、さるまじき名をも立つるぞかし」
など、思ひ続けつつ、掻き鳴らしたまふ。
故君の常に弾きたまひし琴なりけり。をかしき手一つなど、すこし弾きたまひて、
「あはれ、いとめづらかなる音に掻き鳴らしたまひしはや。この御琴にも籠もりてはべらむかし。承りあらはしてしがな」
とのたまへば、
「琴の緒絶えにし後より、昔の御童遊びの名残をだに、思ひ出でたまはずなむなりにてはべめる。院の御前にて、女宮たちのとりどりの御琴ども、試みきこえたまひしにも、かやうの方は、おぼめかしからずものしたまふとなむ、定めきこえたまふめりしを、あらぬさまにほれぼれしうなりて、眺め過ぐしたまふめれば、世の憂きつまにといふやうになむ見たまふる」
と聞こえたまへば、
「いとことわりの御思ひなりや。限りだにある」
と、うち眺めて、琴は押しやりたまへれば、
「かれ、なほさらば、声に伝はることもやと、聞きわくばかり鳴らさせたまへ。ものむつかしう思うたまへ沈める耳をだに、明きらめはべらむ」
と聞こえたまふを、
「しか伝はる中の緒は、異にこそははべらめ。それをこそ承らむとは聞こえつれ」
とて、御簾のもと近く押し寄せたまへど、とみにしも受けひきたまふまじきことなれば、しひても聞こえたまはず。
【大猫 訳】
夕霧の大将様が和琴をお引き寄せになると、律に整えられております。よく弾き込まれており、その人の移り香が匂い立ってなんとも心惹かれます。
夕霧「こんな感じの女所帯で、気ままにあだ心のある人だったとしたら、心を抑えられなくてみっともないことをしでかして悪い評判を立てることになるんだろうな」
などと思い続けながら掻き鳴らします。
これは亡き柏木様が弾き慣らした和琴なのでした。夕霧様は面白い一節を少しお弾きになって、
夕霧「ああ、あの人が弾く音色は本当に素晴らしかったなあ。この琴にも彼の音が籠っているのでしょうね。お聞かせいただきたいものです」
と仰いました。
御息所「殿が亡くなられた後は、昔の子供の頃のお遊びさえ思い起こされることもない有様でございまして。父院の御前で女宮様方がそれぞれ御琴を競われた時には、この方面では悪くないだろうと御判定されたようなのですが、今はもう別人のように呆けてしまって毎日思い悩んでお過ごしのようですから、この琴も辛い思い出の品になってしまったものと存じます」
と申し上げます。
夕霧「辛い物思いはもっともなこと。古歌にも『限りだにある』と申しますし」
と、しばらく物思いに沈んだ様子になり、琴を御息所の方へ押しやられます。
御息所「この琴は、やはりあなた様がお弾きくださいませ。亡き人の音色が伝わるものならば、それと聞き分けられるほどにお鳴らしください。憂鬱に思い沈んだこの耳だけでもはっきりいたしましょう」
と申し上げなさいました。
しかし大将は、
夕霧「夫婦の仲に伝わる音色こそ格別なものでございましょう。それをこそ拝聴したいと申し上げているのです」
と言って、和琴を御簾の近くまで押し寄せなさいますが、急にはお引き受けなさいそうもないことですから、無理じいはなさいません。
【語句など】
●和琴
日本固有の絃楽器。別名倭琴、大和琴、東琴など。
若菜下の女楽で紫の上が弾いた楽器です。また到仕大臣、その息子の柏木が名人級の腕前であることが語られています。
柏木が日頃弾いていた和琴であり、柏木亡き後は女二の宮が弾いていると思われます。
参考までに東儀秀樹氏による和琴演奏も聴いてみてください。
冒頭で琴柱にあたる楓の枝と絃を調整していたりして興味深いです。
https://www.youtube.com/watch?v=BdsEUmsOVSI
●律
唐楽の音律は理論上は八十四調もあったそうですが、実際に楽曲として使われたのは二十八調で、そのうちの十二調ほどが日本に伝わったと考えられています。
受容から発展の過程で下記の六調が後世に伝わりました。音階の違いから呂(≒長調)と律(≒短調)に分けられ、さらに陰陽五行説と結びついて各調子が季節に紐づけられました。
呂
壱越調 主音≒D
双調 主音≒G
太食調 主音≒E
律
平調 主音≒E
黄鐘調 主音≒A
盤渉調 主音≒B
中央に壱越調
それを囲んで
東(春)は双調
南(夏)は黄鐘調
秋(西)は平調
北(冬)は盤渉調
このあたりの説明は↓をどうぞ。
https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc22/naritachi/kangen/on1.html
この場面で律と言われているのは秋の調べ平調です。西洋音楽だとホ短調に近いのですが、譜面にするとホ短調はファのところに#記号が付きますが、平調はファとドに#です。
東京楽所の「平調の音取」。最後の方で絃楽器の音色が聴けますので、これで少し雰囲気がつかめます。
https://www.youtube.com/watch?v=R4ukUbz9NUI
●かやうなるあたりに思ひのままなる好き心ある人は
軽い女だったらたちまち身を持ち崩すんだろうなあ、ここの宮様はそんな方じゃなさそうだな。でも誘ったら靡くかな、ってなところですかね。和琴弾きながら何考えてるんだか。俗念丸出しです。
●琴の緒絶えにし後
伯牙絶絃の故事を踏まえる。呂氏春秋「知音」あるいは列子湯問篇「高山流水」より。
琴の名手である伯牙は、自分の一番の理解者であり、親友だった鐘子期が亡くなり、自分の琴を理解してくれる人はもういないといい、琴の弦を切って、二度と弾くことはなかったという故事から。
ここでは柏木が亡くなったことを指します。
そう言えば中国にも『高山流水』という筝の名曲があります。
●おぼめかしからず
「おぼめかし」は曖昧で不安な様子。
「おぼめかし」からずなので、安定してしっかりしている意味になります。
●つま(端)
きっかけ、手がかり
●限りだにある
恋しさの限りだにある世なりせば年へて物は思はざらまし(続古今坂上是則 )
●中の緒
和琴の第二絃のことを指すが、併せて夫婦仲のことをほのめかします。
●とみにしも受けひきたまふまじきこと
家族でもない男に求められてはいはいと楽器を弾くなんてはしたないこと。夕霧の言うところの「好き心ある人」とみなされかねないのだと思われます。
【感想】
故人の追想にことよせてじわじわにじり寄る夕霧。困惑しつつもよもやそんな下心があるとは思わず、つい、「娘は和琴が弾けないわけではなく、父院に褒められたこともある腕前なのだ」、と言い訳がましいことを言ってしまう御息所。御簾の奥は無音のまま。
悲しみに暮れつつも静かに慎ましく暮らす未亡人の家、秋の夕暮れが夜に移り、静かな邸内に和琴が響く。物悲しい秋の調べ平調。音色に名手・柏木の面影を探そうと、夫婦の仲だからこそ伝わる音がある、お弾きくださいと迫る夕霧。もちろん本当に聴きたいのは宮自身の音色です。
夫が妻に伝えた音色とは、なんだか閨の睦言のようでもあり、とてもプライベートな二人だけの秘密のようでもあります。その妻の手から夫の音色を聞きたいと懇願するのも、禁断の秘密に触れるような趣があってエロティシズムを感じてしまいました。私だけかもしれませんが。
御息所のセリフではないけれど、心が弱っている時は音楽など耳にも入らなくなるし、楽しいことも楽しくなくなってしまうものですね。慰めてくれる人がいるのは本当にありがたいけれど、その人に下心があったとしたら……
次の段、静かな独奏、合奏が続きます。
どなたかお読みになりませんか。
●和琴
日本固有の絃楽器。別名倭琴、大和琴、東琴など。
若菜下の女楽で紫の上が弾いた楽器です。また到仕大臣、その息子の柏木が名人級の腕前であることが語られています。
柏木が日頃弾いていた和琴であり、柏木亡き後は女二の宮が弾いていると思われます。
参考までに東儀秀樹氏による和琴演奏も聴いてみてください。
冒頭で琴柱にあたる楓の枝と絃を調整していたりして興味深いです。
https://www.youtube.com/watch?v=BdsEUmsOVSI
●律
唐楽の音律は理論上は八十四調もあったそうですが、実際に楽曲として使われたのは二十八調で、そのうちの十二調ほどが日本に伝わったと考えられています。
受容から発展の過程で下記の六調が後世に伝わりました。音階の違いから呂(≒長調)と律(≒短調)に分けられ、さらに陰陽五行説と結びついて各調子が季節に紐づけられました。
呂
壱越調 主音≒D
双調 主音≒G
太食調 主音≒E
律
平調 主音≒E
黄鐘調 主音≒A
盤渉調 主音≒B
中央に壱越調
それを囲んで
東(春)は双調
南(夏)は黄鐘調
秋(西)は平調
北(冬)は盤渉調
このあたりの説明は↓をどうぞ。
https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc22/naritachi/kangen/on1.html
この場面で律と言われているのは秋の調べ平調です。西洋音楽だとホ短調に近いのですが、譜面にするとホ短調はファのところに#記号が付きますが、平調はファとドに#です。
東京楽所の「平調の音取」。最後の方で絃楽器の音色が聴けますので、これで少し雰囲気がつかめます。
https://www.youtube.com/watch?v=R4ukUbz9NUI
●かやうなるあたりに思ひのままなる好き心ある人は
軽い女だったらたちまち身を持ち崩すんだろうなあ、ここの宮様はそんな方じゃなさそうだな。でも誘ったら靡くかな、ってなところですかね。和琴弾きながら何考えてるんだか。俗念丸出しです。
●琴の緒絶えにし後
伯牙絶絃の故事を踏まえる。呂氏春秋「知音」あるいは列子湯問篇「高山流水」より。
琴の名手である伯牙は、自分の一番の理解者であり、親友だった鐘子期が亡くなり、自分の琴を理解してくれる人はもういないといい、琴の弦を切って、二度と弾くことはなかったという故事から。
ここでは柏木が亡くなったことを指します。
そう言えば中国にも『高山流水』という筝の名曲があります。
●おぼめかしからず
「おぼめかし」は曖昧で不安な様子。
「おぼめかし」からずなので、安定してしっかりしている意味になります。
●つま(端)
きっかけ、手がかり
●限りだにある
恋しさの限りだにある世なりせば年へて物は思はざらまし(続古今坂上是則 )
●中の緒
和琴の第二絃のことを指すが、併せて夫婦仲のことをほのめかします。
●とみにしも受けひきたまふまじきこと
家族でもない男に求められてはいはいと楽器を弾くなんてはしたないこと。夕霧の言うところの「好き心ある人」とみなされかねないのだと思われます。
【感想】
故人の追想にことよせてじわじわにじり寄る夕霧。困惑しつつもよもやそんな下心があるとは思わず、つい、「娘は和琴が弾けないわけではなく、父院に褒められたこともある腕前なのだ」、と言い訳がましいことを言ってしまう御息所。御簾の奥は無音のまま。
悲しみに暮れつつも静かに慎ましく暮らす未亡人の家、秋の夕暮れが夜に移り、静かな邸内に和琴が響く。物悲しい秋の調べ平調。音色に名手・柏木の面影を探そうと、夫婦の仲だからこそ伝わる音がある、お弾きくださいと迫る夕霧。もちろん本当に聴きたいのは宮自身の音色です。
夫が妻に伝えた音色とは、なんだか閨の睦言のようでもあり、とてもプライベートな二人だけの秘密のようでもあります。その妻の手から夫の音色を聞きたいと懇願するのも、禁断の秘密に触れるような趣があってエロティシズムを感じてしまいました。私だけかもしれませんが。
御息所のセリフではないけれど、心が弱っている時は音楽など耳にも入らなくなるし、楽しいことも楽しくなくなってしまうものですね。慰めてくれる人がいるのは本当にありがたいけれど、その人に下心があったとしたら……
次の段、静かな独奏、合奏が続きます。
どなたかお読みになりませんか。
>>[44]
コメントありがとうございます。
> ●かやうなるあたりに思ひのままなる好き心ある人は
ああ、そうですね。好き心ある人、は男の立場の方がしっくりきますね。読んだ時は女のことを言っているのだと疑いもしませんでした。
僕ちゃん、世の中の男とは違うもんね、って自分で自分に言っている時点で下心ありありなんだけど。
御息所が言うように、楽器の腕前が良かったのなら、柏木との合奏などもあったのかもしれません。でも柏木から秘伝を教わるほどの仲でもなかったのでしょうね。「落葉を何に拾ひけむ」なんて言われようじゃ。
父院は妹の三の宮を偏愛しているし、結婚した相手は自分に興味を示さず、その上先立たれて世間の物笑いになってしまい。自己評価はボロボロ、それこそ世を捨てたいと考えていたことでしょう。
落葉宮の物語は始まったばかり。肉声を早く聞きたいですね。
コメントありがとうございます。
> ●かやうなるあたりに思ひのままなる好き心ある人は
ああ、そうですね。好き心ある人、は男の立場の方がしっくりきますね。読んだ時は女のことを言っているのだと疑いもしませんでした。
僕ちゃん、世の中の男とは違うもんね、って自分で自分に言っている時点で下心ありありなんだけど。
御息所が言うように、楽器の腕前が良かったのなら、柏木との合奏などもあったのかもしれません。でも柏木から秘伝を教わるほどの仲でもなかったのでしょうね。「落葉を何に拾ひけむ」なんて言われようじゃ。
父院は妹の三の宮を偏愛しているし、結婚した相手は自分に興味を示さず、その上先立たれて世間の物笑いになってしまい。自己評価はボロボロ、それこそ世を捨てたいと考えていたことでしょう。
落葉宮の物語は始まったばかり。肉声を早く聞きたいですね。
>>[49]
お忙しい中、またお疲れのところ、読みありがとうございました。
一年半かけてちょっとだけ合奏できるまでに近づいた。とは言え、宮側は夕霧を「とても良くしてくれる亡き夫の友人」以上には見なさず、夕霧もそれを重々承知している段階ですね。
「ほのかに掻き鳴らしたまへる」、これですね。「チラ見せ」(チラ聞かせ?)が、男心をそそるのは昔からなんですね。
末摘花巻でも「ほのかに掻き鳴らしたまふ、をかしう聞こゆ。何ばかり深き手ならねど」とあって、大した腕前でもないと言われていますが、今回は「奥深き声なるに」と、チラ聞かせでも落葉宮の腕前が本物であることが語られていますね。瞬時に悩殺される夕霧にどこまでもつつましい女宮。
大人っぽい雰囲気漂う名場面でした。
お忙しい中、またお疲れのところ、読みありがとうございました。
一年半かけてちょっとだけ合奏できるまでに近づいた。とは言え、宮側は夕霧を「とても良くしてくれる亡き夫の友人」以上には見なさず、夕霧もそれを重々承知している段階ですね。
「ほのかに掻き鳴らしたまへる」、これですね。「チラ見せ」(チラ聞かせ?)が、男心をそそるのは昔からなんですね。
末摘花巻でも「ほのかに掻き鳴らしたまふ、をかしう聞こゆ。何ばかり深き手ならねど」とあって、大した腕前でもないと言われていますが、今回は「奥深き声なるに」と、チラ聞かせでも落葉宮の腕前が本物であることが語られていますね。瞬時に悩殺される夕霧にどこまでもつつましい女宮。
大人っぽい雰囲気漂う名場面でした。
>>[56]
落葉宮邸の長い描写も終わりましたね。お疲れ様でした。
秘密の子・薫の物語の構想が進むにつれて、父柏木にもいろいろとエピソードが増えて行く感がありますね。一年半かけて、亡き柏木の秘密が少しずつ明らかになりつつ、落葉宮への思慕も深まって行く、物語の進行はゆるやかですがドラマチックな高まりを見せつつありますね。
当時、音楽の音色は親子で遺伝すると考えられていたようですね。また音色が人柄そのものを映し出すとも。もちろん一定以上の技量に到達してからの話ですが。音楽は楽曲の解釈と音色への展開が人により違い、それは性格が占める部分も多いらしいので、あながち荒唐無稽とも言い切れないと思います。
ちなみに私が父親から受け継いだのは下手くそな字です。父とは生涯数度しか会ったことがないほど縁が薄かったのに、周囲の人いわく下手くそ加減がそっくりなのだそうです。ロマンのかけらもないなあ。
>横笛の調べはことに変はらぬをむなしくなりし音こそ尽きせね
和歌の掛け言葉や縁語は現代語訳が難しいですが、
>故人の吹き鳴らされた音色は尽きることなく
尽きることなく、「こと」をここに持ってきたのですね。
お見事です。
次の読みは6月上旬になってからになりそうです。
少々お時間をください。
落葉宮邸の長い描写も終わりましたね。お疲れ様でした。
秘密の子・薫の物語の構想が進むにつれて、父柏木にもいろいろとエピソードが増えて行く感がありますね。一年半かけて、亡き柏木の秘密が少しずつ明らかになりつつ、落葉宮への思慕も深まって行く、物語の進行はゆるやかですがドラマチックな高まりを見せつつありますね。
当時、音楽の音色は親子で遺伝すると考えられていたようですね。また音色が人柄そのものを映し出すとも。もちろん一定以上の技量に到達してからの話ですが。音楽は楽曲の解釈と音色への展開が人により違い、それは性格が占める部分も多いらしいので、あながち荒唐無稽とも言い切れないと思います。
ちなみに私が父親から受け継いだのは下手くそな字です。父とは生涯数度しか会ったことがないほど縁が薄かったのに、周囲の人いわく下手くそ加減がそっくりなのだそうです。ロマンのかけらもないなあ。
>横笛の調べはことに変はらぬをむなしくなりし音こそ尽きせね
和歌の掛け言葉や縁語は現代語訳が難しいですが、
>故人の吹き鳴らされた音色は尽きることなく
尽きることなく、「こと」をここに持ってきたのですね。
お見事です。
次の読みは6月上旬になってからになりそうです。
少々お時間をください。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
源氏物語を味わう 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
源氏物語を味わうのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37834人
- 2位
- 酒好き
- 170662人
- 3位
- マイミク募集はここで。
- 89527人
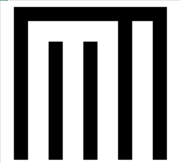













![[公式]mixiからの質問に答えよう](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/8/93/6370893_167s.jpg)






