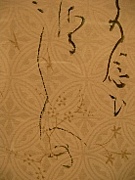小さい頃は、書道教室の先生がお手本を書いてくださいましたが、
いつしか「臨書」というものを経験することになります。
みなさんが、初めて臨書したのは何でしたか?
また、お弟子さんが初めて臨書するときの課題は、何を選びましたか?
既に出ているものでもOKです。どんどん書き込んでください。
そこから、臨書についての皆さんのお話を伺いたいと思っています。
<既出> 年代順
●東晋:蘭亭序(王羲之)
●隋:千字文(智永)
●唐:九成宮 醴泉銘(欧陽詢)http://
●唐:孟法師碑(褚遂良)http://
◎平安:御所本三十六人集<興風集>
◎平安:関戸本古今集(天)
◎平安:高野切第一種
◎平安:高野切第三種
<コメント−抜粋>
自由に話を展開してしてくださってOKですが、
話のきっかけに、既出のコメントの抜粋を載せておきます。(ひ)
♪臨書の入門書って、どのあたりなのかなー って思ったの。
♪私の先生は高野切れに入って、高野切れに戻るとおっしゃっています。
♪私は競書で断片的にはいろいろやりましたが、全臨は「高野切第一種」が初めてです
♪古筆でも、今の流行り廃りとか、ありますか?あれば、今は何が流行ですか?
♪まずは、臨書とは?古筆とは?といったあたりから
一緒に巡っていきたいのですが、どうでしょう。
♪臨書って、絵で言うところのデッサンだと思うんです。
♪ちなみに、私は最初に九成宮をやりました。碑を見に中国にも行きましたが、
実際のものは本で見るより線が柔らかいものでしたよ!!
♪書の場合は眼を正す唯一の方法は古典臨書しかないと思うので
何よりも大切なものだと思っています。
♪碑は立体で3Dの世界ですが、拓本は写し取られた平面の世界なので、
特に中国の拓本は黒白を鮮明にしますから、線が硬く、もしくは強くなるでしょうね。
♪彫りの問題もありますね。薬研彫りという彫り方だとやわらかく感じます。
♪子供のころのお習字から書道へ変わった第一歩は『九成宮』でした。
大人になった!と感じました。と同時に筆遣いの難しさ、
特徴を捉えるための観察の大切さなどを知ったことを思い出します。
♪そのうち、あまり好きではない字体の臨書をすすめられましたが、
はじめは抵抗がありました。好き嫌いはどういうところで分かれるのでしょうか。
♪最近、初めて臨書をした方や、高校や大学で授業を受けている方の
お話も伺ってみたいですね。
♪その書体に合った音楽(リズム)もありますねえ。
九成宮はクラシック、龍門はヘビーメタル?私はどうも賑やかなのが好きみたいです。
♪形にばかりとらわれると、そのほかのことが見えなくなったりします。
先人は、木簡を見ても分かるように、かなりリズミカルに字を書いていたと思います。
いつしか「臨書」というものを経験することになります。
みなさんが、初めて臨書したのは何でしたか?
また、お弟子さんが初めて臨書するときの課題は、何を選びましたか?
既に出ているものでもOKです。どんどん書き込んでください。
そこから、臨書についての皆さんのお話を伺いたいと思っています。
<既出> 年代順
●東晋:蘭亭序(王羲之)
●隋:千字文(智永)
●唐:九成宮 醴泉銘(欧陽詢)http://
●唐:孟法師碑(褚遂良)http://
◎平安:御所本三十六人集<興風集>
◎平安:関戸本古今集(天)
◎平安:高野切第一種
◎平安:高野切第三種
<コメント−抜粋>
自由に話を展開してしてくださってOKですが、
話のきっかけに、既出のコメントの抜粋を載せておきます。(ひ)
♪臨書の入門書って、どのあたりなのかなー って思ったの。
♪私の先生は高野切れに入って、高野切れに戻るとおっしゃっています。
♪私は競書で断片的にはいろいろやりましたが、全臨は「高野切第一種」が初めてです
♪古筆でも、今の流行り廃りとか、ありますか?あれば、今は何が流行ですか?
♪まずは、臨書とは?古筆とは?といったあたりから
一緒に巡っていきたいのですが、どうでしょう。
♪臨書って、絵で言うところのデッサンだと思うんです。
♪ちなみに、私は最初に九成宮をやりました。碑を見に中国にも行きましたが、
実際のものは本で見るより線が柔らかいものでしたよ!!
♪書の場合は眼を正す唯一の方法は古典臨書しかないと思うので
何よりも大切なものだと思っています。
♪碑は立体で3Dの世界ですが、拓本は写し取られた平面の世界なので、
特に中国の拓本は黒白を鮮明にしますから、線が硬く、もしくは強くなるでしょうね。
♪彫りの問題もありますね。薬研彫りという彫り方だとやわらかく感じます。
♪子供のころのお習字から書道へ変わった第一歩は『九成宮』でした。
大人になった!と感じました。と同時に筆遣いの難しさ、
特徴を捉えるための観察の大切さなどを知ったことを思い出します。
♪そのうち、あまり好きではない字体の臨書をすすめられましたが、
はじめは抵抗がありました。好き嫌いはどういうところで分かれるのでしょうか。
♪最近、初めて臨書をした方や、高校や大学で授業を受けている方の
お話も伺ってみたいですね。
♪その書体に合った音楽(リズム)もありますねえ。
九成宮はクラシック、龍門はヘビーメタル?私はどうも賑やかなのが好きみたいです。
♪形にばかりとらわれると、そのほかのことが見えなくなったりします。
先人は、木簡を見ても分かるように、かなりリズミカルに字を書いていたと思います。
|
|
|
|
コメント(30)
まさこさん、こんにちは。やはり、高野切ですか。
私は一種が好きです。
全臨して巻子とは、素敵ですね。
公募展などの作品は大きくて、家ではなかなか飾ってみることもないですが、臨書は手にとって見ることができますし、綺麗に巻子や製本すれば、達成感も違いますよね。
私も今年こそ課題の臨書を早めにとりかからなくちゃ。
GWはゆっくり時間がとれるのでお互いがんばりましょう。
ちなみに、横浜近辺はわからないのですが、最近は
東京駅の「こきん」京都の「龍枝堂」の筆を愛用しています。
送料がかかるかもしれませんが、電話で注文もできますよ。
●こきん
03-3271-3868 日本橋3−4−11中川ビル1F
●龍枝堂(東京)
03-3239-0733 飯田橋4−2−2
横浜の近くにお住まいの方がいらっしゃいましたら
情報の提供をおねがいします〜
私は一種が好きです。
全臨して巻子とは、素敵ですね。
公募展などの作品は大きくて、家ではなかなか飾ってみることもないですが、臨書は手にとって見ることができますし、綺麗に巻子や製本すれば、達成感も違いますよね。
私も今年こそ課題の臨書を早めにとりかからなくちゃ。
GWはゆっくり時間がとれるのでお互いがんばりましょう。
ちなみに、横浜近辺はわからないのですが、最近は
東京駅の「こきん」京都の「龍枝堂」の筆を愛用しています。
送料がかかるかもしれませんが、電話で注文もできますよ。
●こきん
03-3271-3868 日本橋3−4−11中川ビル1F
●龍枝堂(東京)
03-3239-0733 飯田橋4−2−2
横浜の近くにお住まいの方がいらっしゃいましたら
情報の提供をおねがいします〜
タピオカさん、はじめまして。
高野切の全臨に取り組まれているのですね。
展覧会の作品制作で創作に取り組んでいると、
ついつい自己流の癖がへんに出てきてしまいます。
まだまだ個性といえるものではありません。
そんなときに高野切や自分の好きな古筆を眺めたり、臨書することで、芯のようなものが自分の中にできて、かつ柔軟に作品制作に向かえるような気がします。
うまく言えませんけど。
全臨したら、綺麗に製本して記念にとっておきたいですね。
最初のページから書いていくと、はじめとおわりで、随分上達しているのがわかります。
何度臨書しても、必ずどこかが良くなっていくのが不思議です。どこかというのは、線の速度や墨の具合、圧のかけ方やその他色々です。
「孟法師碑」は褚遂良ですね。楷書、むずかしいです。
パソコンなどのフォントに見慣れてしまい、手書きの楷書はよっぽど頑張らないと・・いけませんね。でも、誰が見ても、いいなー、美しいなーと思ってもらえるようなものがあるはずで、そこを目指してみたいです。褚遂良は雁塔聖教序を全臨しました。
他にも、いろいろトピックがありますので、
展覧会のお知らせなどありましたら情報提供をお願いします。
高野切の全臨に取り組まれているのですね。
展覧会の作品制作で創作に取り組んでいると、
ついつい自己流の癖がへんに出てきてしまいます。
まだまだ個性といえるものではありません。
そんなときに高野切や自分の好きな古筆を眺めたり、臨書することで、芯のようなものが自分の中にできて、かつ柔軟に作品制作に向かえるような気がします。
うまく言えませんけど。
全臨したら、綺麗に製本して記念にとっておきたいですね。
最初のページから書いていくと、はじめとおわりで、随分上達しているのがわかります。
何度臨書しても、必ずどこかが良くなっていくのが不思議です。どこかというのは、線の速度や墨の具合、圧のかけ方やその他色々です。
「孟法師碑」は褚遂良ですね。楷書、むずかしいです。
パソコンなどのフォントに見慣れてしまい、手書きの楷書はよっぽど頑張らないと・・いけませんね。でも、誰が見ても、いいなー、美しいなーと思ってもらえるようなものがあるはずで、そこを目指してみたいです。褚遂良は雁塔聖教序を全臨しました。
他にも、いろいろトピックがありますので、
展覧会のお知らせなどありましたら情報提供をお願いします。
こんにちは。
社長は・・・、高齢で、お体も万全ではないので、お店には出ておられませんよ。
だけど、飯塚さんは、社長がとても信頼されている方なので、いろいろお力になってくださると思います。
私も約20年前に入門をお願いに上がったときも、本当はもう新しい弟子をお取りになっていず、ご無理を申し上げ、入れていただいたのです。
ですので、今はお稽古にも殆ど行っておりません。
自分で、写経と臨書だけやってます。
ところで、質問ですが、古筆でも、今の流行り廃りとか、ありますか?あれば、今は何が流行ですか?
私の先生は、とても古筆を大切にしておられ、好きなものをすればいいとおっしゃいますが、友だちに相談されたので、おススメしたら、それは、今の流行じゃないから、もっと流行のものがいい!とか・・・、別の友だちは、臨書を本ではなく、先生の手本だったり、結構びっくりすることも多いです。
これからも、アドヴァイス、よろしくお願いします。
社長は・・・、高齢で、お体も万全ではないので、お店には出ておられませんよ。
だけど、飯塚さんは、社長がとても信頼されている方なので、いろいろお力になってくださると思います。
私も約20年前に入門をお願いに上がったときも、本当はもう新しい弟子をお取りになっていず、ご無理を申し上げ、入れていただいたのです。
ですので、今はお稽古にも殆ど行っておりません。
自分で、写経と臨書だけやってます。
ところで、質問ですが、古筆でも、今の流行り廃りとか、ありますか?あれば、今は何が流行ですか?
私の先生は、とても古筆を大切にしておられ、好きなものをすればいいとおっしゃいますが、友だちに相談されたので、おススメしたら、それは、今の流行じゃないから、もっと流行のものがいい!とか・・・、別の友だちは、臨書を本ではなく、先生の手本だったり、結構びっくりすることも多いです。
これからも、アドヴァイス、よろしくお願いします。
少し、話のきっかけになればと思い、続けさせていただきます。
書との関わり方は、きっと、このコミュニティに参加してくださっている方の中でも色々あると思います。
古筆の臨書を中心にしていらっしゃる方
先生のお手本に倣って稽古していらっしゃる方
公募展に出品していらっしゃる方
綺麗な手紙が書きたいとペン字を始めた方
自分のイメージの表現方法として書を用いている方
研究対象や参考文献として書と関わっている方
・・・
他にも私が思いつかないくらい多種多様にあるいは組み合わせて、書と関わっていらっしゃるのではないかとおもわれます。
そこで、まずは、臨書とは?古筆とは?といったあたりから
一緒に巡っていきたいのですが、どうでしょう。
話がそれてもかまいませんし、閑話休題、初めて臨書したものを書き込んでくださってもOKです。
数ヶ月かけて、のんびりでもスレが伸びていったらうれしいです。よろしくー。
書との関わり方は、きっと、このコミュニティに参加してくださっている方の中でも色々あると思います。
古筆の臨書を中心にしていらっしゃる方
先生のお手本に倣って稽古していらっしゃる方
公募展に出品していらっしゃる方
綺麗な手紙が書きたいとペン字を始めた方
自分のイメージの表現方法として書を用いている方
研究対象や参考文献として書と関わっている方
・・・
他にも私が思いつかないくらい多種多様にあるいは組み合わせて、書と関わっていらっしゃるのではないかとおもわれます。
そこで、まずは、臨書とは?古筆とは?といったあたりから
一緒に巡っていきたいのですが、どうでしょう。
話がそれてもかまいませんし、閑話休題、初めて臨書したものを書き込んでくださってもOKです。
数ヶ月かけて、のんびりでもスレが伸びていったらうれしいです。よろしくー。
これまた、面白いコメントありがとうございます。
ピッポさんがおっしゃった九成宮については、書道用語コミュに載っていました。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=3503072&comm_id=496363&page=all
☆九成宮醴泉銘(きゅうせいきゅうれいせんのめい)☆
☆楷書(かいしょ)☆
ついでに、「古筆」についても記載がありましたよ。
☆古筆(こひつ)☆
色々面白くて、もうずいぶんパソコンの前に座っているのだけど、普段、先生が何気なく使っているから、自分も何気なく使っている言葉でも、こう改めて解説を読むとへえーって目からウロコだった今日この頃、皆さんいかが休日をお過ごしですか?
九成宮は碑石から採っていて、字の部分を彫ってあるから拓本は字の部分が白いですね。ちなみに臨書されるような碑で字の部分が黒い朱文の古文ってあるのでしょうか?
拓本についてはこちらも↓
http://www.takuhon.com/nani.htm
つまり、私たちは紙に写しとられた拓本を見ているわけですが、ピッポさんが、実際に碑を見て線がやわらかいと感じられたことについて興味があります。
今のところ、日本の仮名が生まれる前の中国の文字についての話ですね。私もまだまだ未知な世界です。色々話が膨らみますね。
momoharuさんの、「眼を正す」も面白いですよね。
もう少し掘り下げてお話を伺いたいとおもっています!
ちなみに、臨書は、料理でたとえるなら、
味の基本、方向性を決めるダシってところでしょうか。
(どうしても言ってみたかった笑)
ピッポさんがおっしゃった九成宮については、書道用語コミュに載っていました。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=3503072&comm_id=496363&page=all
☆九成宮醴泉銘(きゅうせいきゅうれいせんのめい)☆
☆楷書(かいしょ)☆
ついでに、「古筆」についても記載がありましたよ。
☆古筆(こひつ)☆
色々面白くて、もうずいぶんパソコンの前に座っているのだけど、普段、先生が何気なく使っているから、自分も何気なく使っている言葉でも、こう改めて解説を読むとへえーって目からウロコだった今日この頃、皆さんいかが休日をお過ごしですか?
九成宮は碑石から採っていて、字の部分を彫ってあるから拓本は字の部分が白いですね。ちなみに臨書されるような碑で字の部分が黒い朱文の古文ってあるのでしょうか?
拓本についてはこちらも↓
http://www.takuhon.com/nani.htm
つまり、私たちは紙に写しとられた拓本を見ているわけですが、ピッポさんが、実際に碑を見て線がやわらかいと感じられたことについて興味があります。
今のところ、日本の仮名が生まれる前の中国の文字についての話ですね。私もまだまだ未知な世界です。色々話が膨らみますね。
momoharuさんの、「眼を正す」も面白いですよね。
もう少し掘り下げてお話を伺いたいとおもっています!
ちなみに、臨書は、料理でたとえるなら、
味の基本、方向性を決めるダシってところでしょうか。
(どうしても言ってみたかった笑)
はじめまして。私も九成宮の全臨を師匠に勧められて始めたものの、作品制作の合間にちびちびやっているので、全然進んでいません。私は少し苦手な書体です。
最近、顔眞卿の楷書、木簡、隷書、空海の行書の4作品を半切に臨書しました。どれも割と好きな書体だったので、楽しくできました。
師匠から「臨書は字の形ではなく動きや呼吸を習うように」と言われています。好き嫌いはそこにあるのではないでしょうか?
ピッポさんの言うように、絵のデッサンと言うのも同感ですが、臨書はダンスのステップのようなものだとも思います。「ワルツは得意だけどタンゴは苦手」みたいな感じ。自分の書が書けるようなる=自由に踊れると考えると、苦手な臨書(=苦手なステップ)をマスターできれば書も自由に踊り出す♪♪
他にはその書体に合った音楽(リズム)もありますねえ。九成宮はクラシック、龍門はヘビーメタル?私はどうも賑やかなのが好きみたいです。
最近、顔眞卿の楷書、木簡、隷書、空海の行書の4作品を半切に臨書しました。どれも割と好きな書体だったので、楽しくできました。
師匠から「臨書は字の形ではなく動きや呼吸を習うように」と言われています。好き嫌いはそこにあるのではないでしょうか?
ピッポさんの言うように、絵のデッサンと言うのも同感ですが、臨書はダンスのステップのようなものだとも思います。「ワルツは得意だけどタンゴは苦手」みたいな感じ。自分の書が書けるようなる=自由に踊れると考えると、苦手な臨書(=苦手なステップ)をマスターできれば書も自由に踊り出す♪♪
他にはその書体に合った音楽(リズム)もありますねえ。九成宮はクラシック、龍門はヘビーメタル?私はどうも賑やかなのが好きみたいです。
はじめは…
中学生の時、王羲之の集王聖教序だったような…。
高校生の時は、像造記のがちっとっした造形に魅力を感じ習いました。
かん*かんさんが今取り組んでおられる、李邕さんの麓山寺碑の風化した感じが好きで。古本屋に探しに行ったこともあります
仮名もすきですが、不学で苦手です…
初めの頃は、高野切れ一種、枡色紙などが好きでしたが、今は香紙切れが好きです。
最近は自分にないものを求めて色々あさっています。
基本的に臨書。大好きです。
余計なことを考えないでいいので
書く時は雰囲気を大切に書いています。
古典はそれぞれに多様な趣を備えていて、見ていても飽きません。
書法はたいせつですが、それ以上に見た時感じたもの、印象というものが人をひきつけるように思います。
また、作品を創るとき、古典の文字をそのまま写し取って並べたところで作品にはなりません。
原理、あるいは雰囲気を学び取ることが大事な気がします。
そのためには忠実に、形や線の呼吸を再現して学ぶ必要がありますね
やってみて初めて分かる良さ、というのも多分に有るようです。
文人画や文人の手紙などの呼吸も面白いですよ。
すごく自然で豊かです。
何でも決め付けずに、いいものはスポンジのように取り込みたいものですね。
教える法帖ですが、特に決めてはいません。
ぼくが何種類かをチョイスし、その中から選んでもらっています。
ただ、固定観念の強い方には、特徴のわかりやすいもの。
ない方には、上品なものを勧めています。
こんなところでしょうか…
お邪魔しました。。
中学生の時、王羲之の集王聖教序だったような…。
高校生の時は、像造記のがちっとっした造形に魅力を感じ習いました。
かん*かんさんが今取り組んでおられる、李邕さんの麓山寺碑の風化した感じが好きで。古本屋に探しに行ったこともあります
仮名もすきですが、不学で苦手です…
初めの頃は、高野切れ一種、枡色紙などが好きでしたが、今は香紙切れが好きです。
最近は自分にないものを求めて色々あさっています。
基本的に臨書。大好きです。
余計なことを考えないでいいので
書く時は雰囲気を大切に書いています。
古典はそれぞれに多様な趣を備えていて、見ていても飽きません。
書法はたいせつですが、それ以上に見た時感じたもの、印象というものが人をひきつけるように思います。
また、作品を創るとき、古典の文字をそのまま写し取って並べたところで作品にはなりません。
原理、あるいは雰囲気を学び取ることが大事な気がします。
そのためには忠実に、形や線の呼吸を再現して学ぶ必要がありますね
やってみて初めて分かる良さ、というのも多分に有るようです。
文人画や文人の手紙などの呼吸も面白いですよ。
すごく自然で豊かです。
何でも決め付けずに、いいものはスポンジのように取り込みたいものですね。
教える法帖ですが、特に決めてはいません。
ぼくが何種類かをチョイスし、その中から選んでもらっています。
ただ、固定観念の強い方には、特徴のわかりやすいもの。
ない方には、上品なものを勧めています。
こんなところでしょうか…
お邪魔しました。。
海外で書道を再開しようとしている者です。
書道仲間がおらず、まったくの独学になりそうですので、
ネットが頼り・・の今日この頃です。
臨書の課題について、みなさんのお話、とても参考になりました!!
課題とはお話がずれるのですが、
お手本にする市販の臨書本について教えてください。
臨書は書道教室で少しやりましたが、いったい誰のどの作品を臨書したのかも記憶にないほどはるか昔のことになっています・・・。
今、あらためて、お習字から創作の世界に挑戦したいと思っていますが、
まずは臨書をしっかりやりたい、と考えています。
師がおりませんので、本を購入してそれをお手本とし、
地道に臨書をしていきたいのですが、海外にいるため、
本屋さんで実際に吟味することができません。
みなさんはどんな本を購入し、お手本とされていますか。
おすすめのもの、使いやすかった本、などなど、
なんでもいいので本を選ぶときのアドバイスをいただけたら、と
思います。
独学者の教本をかねたようなものなら、さらにいいかなと思っています。
こんど帰国して購入する際、参考にしたいので、
どうぞよろしくお願いします!
書道仲間がおらず、まったくの独学になりそうですので、
ネットが頼り・・の今日この頃です。
臨書の課題について、みなさんのお話、とても参考になりました!!
課題とはお話がずれるのですが、
お手本にする市販の臨書本について教えてください。
臨書は書道教室で少しやりましたが、いったい誰のどの作品を臨書したのかも記憶にないほどはるか昔のことになっています・・・。
今、あらためて、お習字から創作の世界に挑戦したいと思っていますが、
まずは臨書をしっかりやりたい、と考えています。
師がおりませんので、本を購入してそれをお手本とし、
地道に臨書をしていきたいのですが、海外にいるため、
本屋さんで実際に吟味することができません。
みなさんはどんな本を購入し、お手本とされていますか。
おすすめのもの、使いやすかった本、などなど、
なんでもいいので本を選ぶときのアドバイスをいただけたら、と
思います。
独学者の教本をかねたようなものなら、さらにいいかなと思っています。
こんど帰国して購入する際、参考にしたいので、
どうぞよろしくお願いします!
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
書道を愉しむ会 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-