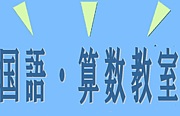メルトダウン寸前の日本経済――自分の将来をどう守るか
東京電力・福島第一原子力発電所の事故は依然として予断を許さない状況が続いているが、今回はテーマを変えてみることにしよう。実は日本にはもう一つの「メルトダウン」寸前のものがある。それは日本経済そのものだ。
東日本大震災により企業活動が寸断され、日本経済に大きな影響を与えているが、それについて語ろうとしているのではない。「失われた20年」などと言われ、日本経済が長らく低迷しているわけだが、それは「成熟国家ゆえの低成長では決してない」ということについて論じたいと思う。
詳細はBBT757チャンネルで放映した番組のYouTube版「日本経済メルトダウン寸前の危機!」をご覧いただきたい。
家計所得が日本のように減少傾向の国はない
最初に日本の家計所得のトレンドを把握しておこう。下のグラフを見てほしい。これは日本、米国、英国、フランスの家計所得(受取額)の推移を示したものだ。
一見してお分かりの通り、米国、英国、フランスともに家計所得は、20年前に比べて2.0〜2.5倍に増えている。ところが日本だけは、はっきりと減少傾向にある。もちろん新興国は米英仏より、もっと伸び率が高い。日本のように減少傾向にある国は他に見あたらないのである。
http://
「一人負け」の原因は、少子高齢化と統治機構にある
我々日本人は漠然と「成長著しい新興国に比べれば伸び率は低いだろう」「成熟国なら、どこでも同じようなもの」と考えているが、その認識は間違っている。日本は明らかに「一人負けの状態」なのだ。
このように日本が元気を失っている原因は二つある。まずは、この国をデモグラフィー(人口統計学)的に見れば、極端な少子高齢化に見舞われていること。そしてもう一つは統治機構のありようにある。私は20年以上前から「道州制」にしたうえで世界のマネーを呼び込むべきだ、と主張してきた。
平成元年に発売した『平成維新』(講談社)の中でも、2005年までに統治機構を含めた平成の大改革をやらなければ、日本はスペインやポルトガルのように長期衰退の道をたどることになる、と警告し、「平成維新の会」を結成して「生活者主権の国造り」を進めてきた。現在の中央集権的な統治機構を改めない限り、地方全体が活気を取り戻し、日本全体が「繁栄しよう」という意欲など持てないのである。
この23年前の著作で恐れていたような結果になってしまったのだが、それは偶然でも不幸でもない。分かっていたことをやらなかった政治と行政、そして国民有権者の怠慢、と言う他ない。
しかし、12年間も都知事をやりながら何の成果も出していない石原慎太郎氏が築地移転利権を確保するために突然引退宣言を撤回して楽勝したように、選挙民は依然として何も分かってないし、改革を要求する気配もない。この衰退には依然として歯止めがかかっていない、と思われる。
http://
「一億総下流」の時代が到来した
減少する家計所得について深刻なのは、これが若年層に限ったことではなく、すべての世代に共通して言える問題であることだ。このため消費も伸びず、資産価値の目減りも進んでいる。つい先ごろまでは「高齢者はお金を持っている」というイメージがあったが、実態はそうではない。昭和を代表するジャーナリストである大宅壮一の言葉をもじって言えば、「一億総下流」時代が到来したのだ。
下のグラフは家計資産残高の国際比較である。不動産をはじめとした非金融資産、金融資産、そして両者を合計した総資産の推移を示している。
米国、英国、フランスの非金融資産は過去20年間で2.5〜3倍になっているのに対して、日本はここでもまた一貫してジリ貧状態にある。1990年比で45%もダウンしている。金融資産は多少伸びてはいるものの、しかし、その額は他国よりはるかに低い水準にある。総資産は日本だけがマイナス12ポイントという状態だ。これが日本の置かれた厳しい現実なのである。
http://
生活が一番苦しいのは「夫婦、子持ち、住宅ローンあり」
日本は、資産の目減りが世界でも群を抜いて激しい。たとえば、昨日5000万円で買ったマンションを今日売ろうとすると、一体いくらになるか? おそらく1000万円は価値が減少しているだろう。600万円で買った新車は所有した途端に400万円の値段でしか売れない。
これは成長期の「提供者」の論理がまだ支配的で、銀行や自動車メーカーなどが自分たちに都合の良い評価システムを長年の間に築き上げてきたからだ。「生活者が第一」という政権ができて間もなく2年が経とうとしているが、改善の兆しはない。
もう一つ生活者側の問題としては日本には「初物」を尊ぶ風潮がいまだに残っている、という点が挙げられる。これは、日本人の生活パターンが経済成長期のままだという証左でもある。これを改めない限り、我々の生活の先行きは暗いと言える。
いま日本で生活が一番苦しいのは「夫婦、子持ち、住宅ローンあり」という世帯だ。世帯収入が減っているにもかかわらず、住宅ローンはそっくりそのまま残っている。子どもの教育費は横ばいで、下がる見通しはない。現在、このパターンの家庭では世帯収入の50%以上を住宅ローンの支払いと教育費に充てている。20年前は30%ほどだったから、収入に対しては20%もの負担増になっている。
若い単身者も割をくっている。所得の低下が著しく、消費はもとより貯蓄もできない。日本人は貯金好きと言われるが、それは昔の話だ。20年ほど前は日本の家計貯蓄率は約15%だったが、2007年には1.7%まで低下。その後、2009年には米国が5.9%、日本が5.5%となっている(内閣府国民経済計算による)。リーマンショック以降、米国では貯蓄意欲が高まり、日本を上回っているのである。
一方、これから次第に定年を迎える人たちも安泰ではない。退職金は減っているし、年金の支給年齢も今後上がっていく。実際、「年金の支給を65歳よりもさらに引き上げないと年金制度が破綻する」と主張する識者もいるくらいだ。
会社を定年退職してから年金が支給されるまでの期間を「魔の5年」と呼ぶことがあるが、これが「魔の7年」になりつつあるのだ。「魔の10年」になったら明らかに高齢者の生活は破壊されることになる。
http://
ライフプランを設計して自衛せよ
このような状況の中、我々がとり得る自衛手段は何か。
私が提案したいのはライフプランを設計することだ。たとえば家計で大きな負担になるのは住宅ローンと教育費、そしてマイカーの購入費(維持・管理費)である。この三つをうまくやりくりした人とそうでない人とでは、生涯に1億円くらいの差が生じることもある。逆に言えば、いま「生活が苦しくて貯蓄ができない」と思っている人でも、やり方次第で数千万円の余裕を生み出すことも可能になるということだ。
たとえば、住宅。多くの人にとって住宅は「一生に一度の買い物」という感覚だろうと思う。35歳で35年ローンを組んでいれば、それも「むべなるかな」であり、「不動産に縛りつけられる」ことになる。転職も、あるいは海外に新天地を見つけることもできず、後ろ向きになり余裕を失ってしまうわけだ。
また日本人の傾向として、子供の教育費にお金をかけ過ぎることも挙げられる。親の情として、それは理解できなくはないが、しかし教育を仮に「投資」として見た場合、それはあまりにもリターンが低いやり方である。
私はむしろ、子どもにかける教育費の半分でもいいから、自分あるいは配偶者に投資すべきだと考える。それにより世帯としての「稼ぐ力」が上がり、結果的にはより良い教育を子どもに授けることができるようになるからだ。
http://
1日2時間、5年間勉強すれば世界に通用する人材になれる
「自分への投資」はどんなに高いものでも1000万円はしない。私立に通わせた場合、子供には2300万円の投資になる。すべて公立なら1000万円で済むので、その差額の一部でも自分と配偶者に向けるべきではないか、というのが私の提案する「自衛策」である。
もう一つ投資を時間で測ることもできる。だいたいどんな人でも年間700時間(つまり1日に2時間)の勉強を5年間続ければ、世界に通用する人材に必ずなれる。しかし残念ながら、こういう発想をする人はあまりにも少ない。
ライフプランというと、我々は「いかに節約や貯蓄をして老後に備えるか」というところから思考を進めてしまう。しかし、それはライフプランの立て方としてはまずい。節約や貯蓄すること自体が目的化してしまい、精神的にすぐに疲弊してしまうからだ。
大切なことは、最初に「自分はどのような人生を送りたいのか」を決定し、そこから「何を所有すべきで、何を所有すべきでないのか」「自分への投資はどの分野にどれだけ必要なのか」「そのお金はどのようにして確保するのか」と逆算して、メリハリのあるプランを作っていくことである。
http://
定年後の9万時間をどう生きるか
日本では、きちんとしたライフプランを持っている人は少ない。ある調査によれば、「ほとんど設計できている」という人はわずか0.9%に過ぎないという。「ほぼゼロ」と言っていいだろう。
なぜライフプランを設計しないのか。アンケート結果によると、最大の理由は「現在の生活だけで精一杯」で、これが全体の60%以上を占めている。余裕のない生活を改善していくためにライフプランがあるのであり、本末が転倒している。
ライフプランは何も経済的な理由のみで必要になるのではない。物心両面から人生を豊かにするために活用されるべきものだ。たとえば、あなたが60歳で退職して80歳で生涯を閉じるとする。自由な時間が1日12時間あるとすると、実に約9万時間もの「自由時間」が与えられることになる。この時間を有効に使わない手はない。
最後に「あぁ、私の人生は素晴らしかった」と言って人生を終えるためには、この部分に関しても若い頃から「計画」をもつことが大切だ。計画と言わないまでも、ある種の「心づもり」と準備が必要なのだ。
私の考えでは、9万時間を有意義に使うためには最低でも「20のやりたいこと」が必要だ。そのうち半分はインドア、残り半分はアウトドアでできることが望ましい。さらにインドア、アウトドアとも「一人でできること」「グループでできること」の二つに振り分けられればなおよい。さて、あなたは「20のやりたいこと」を挙げることができるだろうか?
http://
国と自分の運命をいかに「同期」させないか、が肝心
「そんなものは退職してから考えればいい」と思っていても、そうはいかない。若い頃から「やりたいこと」をやっていないと体力、気力の面からできないものだ。9万時間を無為に過ごさないようにするためにも、「自分は今後どのような人生を歩みたいのか」をきちんと整理して、ライフプランをしっかり立てることが大切である。「国に任せていれば安心」という成長期の幻想がなくなったが、これからは国と自分の運命をいかに「同期」させないか、が肝心だ。
今の政府や役人が統治機構まで含めた「平成維新」を実現してくれるかどうかは20年経った今、かなり疑問となってきている。それよりも、「日本が20年間衰退している唯一の先進国」という実態に日本の多くの人が危機感を持っていない。つまり、革命の前提となる怒りや危機感がない。
私自身はまだあきらめないでこれからも「維新」を訴え続ける覚悟であるが、自分だけでも「運命を集団から切り分けてやろう」と考える人のために、この後半部分を書いてみた。YouTube版の映像と合わせて参考にしてもらいたい。その作業が、あなたのこれからの人生を大きく左右することを肝に銘じてほしい。
http://
東京電力・福島第一原子力発電所の事故は依然として予断を許さない状況が続いているが、今回はテーマを変えてみることにしよう。実は日本にはもう一つの「メルトダウン」寸前のものがある。それは日本経済そのものだ。
東日本大震災により企業活動が寸断され、日本経済に大きな影響を与えているが、それについて語ろうとしているのではない。「失われた20年」などと言われ、日本経済が長らく低迷しているわけだが、それは「成熟国家ゆえの低成長では決してない」ということについて論じたいと思う。
詳細はBBT757チャンネルで放映した番組のYouTube版「日本経済メルトダウン寸前の危機!」をご覧いただきたい。
家計所得が日本のように減少傾向の国はない
最初に日本の家計所得のトレンドを把握しておこう。下のグラフを見てほしい。これは日本、米国、英国、フランスの家計所得(受取額)の推移を示したものだ。
一見してお分かりの通り、米国、英国、フランスともに家計所得は、20年前に比べて2.0〜2.5倍に増えている。ところが日本だけは、はっきりと減少傾向にある。もちろん新興国は米英仏より、もっと伸び率が高い。日本のように減少傾向にある国は他に見あたらないのである。
http://
「一人負け」の原因は、少子高齢化と統治機構にある
我々日本人は漠然と「成長著しい新興国に比べれば伸び率は低いだろう」「成熟国なら、どこでも同じようなもの」と考えているが、その認識は間違っている。日本は明らかに「一人負けの状態」なのだ。
このように日本が元気を失っている原因は二つある。まずは、この国をデモグラフィー(人口統計学)的に見れば、極端な少子高齢化に見舞われていること。そしてもう一つは統治機構のありようにある。私は20年以上前から「道州制」にしたうえで世界のマネーを呼び込むべきだ、と主張してきた。
平成元年に発売した『平成維新』(講談社)の中でも、2005年までに統治機構を含めた平成の大改革をやらなければ、日本はスペインやポルトガルのように長期衰退の道をたどることになる、と警告し、「平成維新の会」を結成して「生活者主権の国造り」を進めてきた。現在の中央集権的な統治機構を改めない限り、地方全体が活気を取り戻し、日本全体が「繁栄しよう」という意欲など持てないのである。
この23年前の著作で恐れていたような結果になってしまったのだが、それは偶然でも不幸でもない。分かっていたことをやらなかった政治と行政、そして国民有権者の怠慢、と言う他ない。
しかし、12年間も都知事をやりながら何の成果も出していない石原慎太郎氏が築地移転利権を確保するために突然引退宣言を撤回して楽勝したように、選挙民は依然として何も分かってないし、改革を要求する気配もない。この衰退には依然として歯止めがかかっていない、と思われる。
http://
「一億総下流」の時代が到来した
減少する家計所得について深刻なのは、これが若年層に限ったことではなく、すべての世代に共通して言える問題であることだ。このため消費も伸びず、資産価値の目減りも進んでいる。つい先ごろまでは「高齢者はお金を持っている」というイメージがあったが、実態はそうではない。昭和を代表するジャーナリストである大宅壮一の言葉をもじって言えば、「一億総下流」時代が到来したのだ。
下のグラフは家計資産残高の国際比較である。不動産をはじめとした非金融資産、金融資産、そして両者を合計した総資産の推移を示している。
米国、英国、フランスの非金融資産は過去20年間で2.5〜3倍になっているのに対して、日本はここでもまた一貫してジリ貧状態にある。1990年比で45%もダウンしている。金融資産は多少伸びてはいるものの、しかし、その額は他国よりはるかに低い水準にある。総資産は日本だけがマイナス12ポイントという状態だ。これが日本の置かれた厳しい現実なのである。
http://
生活が一番苦しいのは「夫婦、子持ち、住宅ローンあり」
日本は、資産の目減りが世界でも群を抜いて激しい。たとえば、昨日5000万円で買ったマンションを今日売ろうとすると、一体いくらになるか? おそらく1000万円は価値が減少しているだろう。600万円で買った新車は所有した途端に400万円の値段でしか売れない。
これは成長期の「提供者」の論理がまだ支配的で、銀行や自動車メーカーなどが自分たちに都合の良い評価システムを長年の間に築き上げてきたからだ。「生活者が第一」という政権ができて間もなく2年が経とうとしているが、改善の兆しはない。
もう一つ生活者側の問題としては日本には「初物」を尊ぶ風潮がいまだに残っている、という点が挙げられる。これは、日本人の生活パターンが経済成長期のままだという証左でもある。これを改めない限り、我々の生活の先行きは暗いと言える。
いま日本で生活が一番苦しいのは「夫婦、子持ち、住宅ローンあり」という世帯だ。世帯収入が減っているにもかかわらず、住宅ローンはそっくりそのまま残っている。子どもの教育費は横ばいで、下がる見通しはない。現在、このパターンの家庭では世帯収入の50%以上を住宅ローンの支払いと教育費に充てている。20年前は30%ほどだったから、収入に対しては20%もの負担増になっている。
若い単身者も割をくっている。所得の低下が著しく、消費はもとより貯蓄もできない。日本人は貯金好きと言われるが、それは昔の話だ。20年ほど前は日本の家計貯蓄率は約15%だったが、2007年には1.7%まで低下。その後、2009年には米国が5.9%、日本が5.5%となっている(内閣府国民経済計算による)。リーマンショック以降、米国では貯蓄意欲が高まり、日本を上回っているのである。
一方、これから次第に定年を迎える人たちも安泰ではない。退職金は減っているし、年金の支給年齢も今後上がっていく。実際、「年金の支給を65歳よりもさらに引き上げないと年金制度が破綻する」と主張する識者もいるくらいだ。
会社を定年退職してから年金が支給されるまでの期間を「魔の5年」と呼ぶことがあるが、これが「魔の7年」になりつつあるのだ。「魔の10年」になったら明らかに高齢者の生活は破壊されることになる。
http://
ライフプランを設計して自衛せよ
このような状況の中、我々がとり得る自衛手段は何か。
私が提案したいのはライフプランを設計することだ。たとえば家計で大きな負担になるのは住宅ローンと教育費、そしてマイカーの購入費(維持・管理費)である。この三つをうまくやりくりした人とそうでない人とでは、生涯に1億円くらいの差が生じることもある。逆に言えば、いま「生活が苦しくて貯蓄ができない」と思っている人でも、やり方次第で数千万円の余裕を生み出すことも可能になるということだ。
たとえば、住宅。多くの人にとって住宅は「一生に一度の買い物」という感覚だろうと思う。35歳で35年ローンを組んでいれば、それも「むべなるかな」であり、「不動産に縛りつけられる」ことになる。転職も、あるいは海外に新天地を見つけることもできず、後ろ向きになり余裕を失ってしまうわけだ。
また日本人の傾向として、子供の教育費にお金をかけ過ぎることも挙げられる。親の情として、それは理解できなくはないが、しかし教育を仮に「投資」として見た場合、それはあまりにもリターンが低いやり方である。
私はむしろ、子どもにかける教育費の半分でもいいから、自分あるいは配偶者に投資すべきだと考える。それにより世帯としての「稼ぐ力」が上がり、結果的にはより良い教育を子どもに授けることができるようになるからだ。
http://
1日2時間、5年間勉強すれば世界に通用する人材になれる
「自分への投資」はどんなに高いものでも1000万円はしない。私立に通わせた場合、子供には2300万円の投資になる。すべて公立なら1000万円で済むので、その差額の一部でも自分と配偶者に向けるべきではないか、というのが私の提案する「自衛策」である。
もう一つ投資を時間で測ることもできる。だいたいどんな人でも年間700時間(つまり1日に2時間)の勉強を5年間続ければ、世界に通用する人材に必ずなれる。しかし残念ながら、こういう発想をする人はあまりにも少ない。
ライフプランというと、我々は「いかに節約や貯蓄をして老後に備えるか」というところから思考を進めてしまう。しかし、それはライフプランの立て方としてはまずい。節約や貯蓄すること自体が目的化してしまい、精神的にすぐに疲弊してしまうからだ。
大切なことは、最初に「自分はどのような人生を送りたいのか」を決定し、そこから「何を所有すべきで、何を所有すべきでないのか」「自分への投資はどの分野にどれだけ必要なのか」「そのお金はどのようにして確保するのか」と逆算して、メリハリのあるプランを作っていくことである。
http://
定年後の9万時間をどう生きるか
日本では、きちんとしたライフプランを持っている人は少ない。ある調査によれば、「ほとんど設計できている」という人はわずか0.9%に過ぎないという。「ほぼゼロ」と言っていいだろう。
なぜライフプランを設計しないのか。アンケート結果によると、最大の理由は「現在の生活だけで精一杯」で、これが全体の60%以上を占めている。余裕のない生活を改善していくためにライフプランがあるのであり、本末が転倒している。
ライフプランは何も経済的な理由のみで必要になるのではない。物心両面から人生を豊かにするために活用されるべきものだ。たとえば、あなたが60歳で退職して80歳で生涯を閉じるとする。自由な時間が1日12時間あるとすると、実に約9万時間もの「自由時間」が与えられることになる。この時間を有効に使わない手はない。
最後に「あぁ、私の人生は素晴らしかった」と言って人生を終えるためには、この部分に関しても若い頃から「計画」をもつことが大切だ。計画と言わないまでも、ある種の「心づもり」と準備が必要なのだ。
私の考えでは、9万時間を有意義に使うためには最低でも「20のやりたいこと」が必要だ。そのうち半分はインドア、残り半分はアウトドアでできることが望ましい。さらにインドア、アウトドアとも「一人でできること」「グループでできること」の二つに振り分けられればなおよい。さて、あなたは「20のやりたいこと」を挙げることができるだろうか?
http://
国と自分の運命をいかに「同期」させないか、が肝心
「そんなものは退職してから考えればいい」と思っていても、そうはいかない。若い頃から「やりたいこと」をやっていないと体力、気力の面からできないものだ。9万時間を無為に過ごさないようにするためにも、「自分は今後どのような人生を歩みたいのか」をきちんと整理して、ライフプランをしっかり立てることが大切である。「国に任せていれば安心」という成長期の幻想がなくなったが、これからは国と自分の運命をいかに「同期」させないか、が肝心だ。
今の政府や役人が統治機構まで含めた「平成維新」を実現してくれるかどうかは20年経った今、かなり疑問となってきている。それよりも、「日本が20年間衰退している唯一の先進国」という実態に日本の多くの人が危機感を持っていない。つまり、革命の前提となる怒りや危機感がない。
私自身はまだあきらめないでこれからも「維新」を訴え続ける覚悟であるが、自分だけでも「運命を集団から切り分けてやろう」と考える人のために、この後半部分を書いてみた。YouTube版の映像と合わせて参考にしてもらいたい。その作業が、あなたのこれからの人生を大きく左右することを肝に銘じてほしい。
http://
|
|
|
|
|
|
|
|
国語・算数教室 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
国語・算数教室のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6461人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19244人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208299人