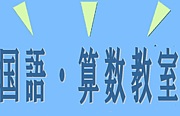ガロア通信第18号のテーマは「気づき」です。
去る1月25日、読谷中学校で興南高校の我喜屋監督による講演会がありました。
みなさんご存知のように、我喜屋監督率いる興南高校は去年、甲子園大会で史上6校目となる春夏連覇を成し遂げました。
興南高校の選手たちは、「ちびっこ軍団」と呼ばれるほど他の学校の選手たちより身長も低く体力もそれほど優(すぐ)れているというものではありませんでした。ところが、ピンチにも動じない強い精神力と冷静な試合運びは、全国一レベルの高いものでした。
例えば、夏の大会準決勝の報徳学園との試合では、連投の島袋投手が打たれて2回までに0−5とリードされていました。しかし、興南高校の選手たちはガッカリしたり動揺したりしませんでした。3回以降島袋投手は配球を修正して立ち直り、他の選手たちも報徳学園のピッチャーの球にタイミングを合わせていき6−5で逆転勝ちしました。
私は、興南高校の選手たちが他の学校の選手たちに比べて、ピンチでも動揺しない強い精神力を持ち試合運びもうまいのに驚き、「いったいどんな練習をしてきたのだろう」と強い関心を持っていました。
それで、我喜屋監督の講演だけでなく、インターネットでも調べて、やっとその理由が分かってきました。
毎日の体操やボール拾い、道端に落ちているゴミを拾うなど、誰でもできることを全力
でやる選手は大きな事ができる!
『興南高校野球部では、小さなことに気付く習慣を身につけさせるために、毎朝6時10分から好きなところを散歩させる。五感を研(と)ぎ澄ますために一人で歩きながら何かを見て、感じてくる。花でも草でも、指でつまんで匂(にお)いをかいでくる。そして、帰って来てから1分間スピーチをする。そのうち、散歩中にゴミが落ちていることに気づき拾ってくる生徒が出てきた。そして、散歩中にゴミ拾いをする選手が増えると、試合での選手たちの送りバントの成功率があがった。』
(以上は、我喜屋監督の話をまとめたものです。)
「散歩やゴミ拾い」と「バントの成功率」の関係は「気づき」である!
「散歩やゴミ拾いと、バントの成功率の間に何の関係があるんだ」と疑問に思う人もいると思いますが、それが大ありなのです。
とてもよく似た双子に初めて会った場合、最初は2人の「違い」に気づかず、見分けることが難しいものです。しかし、何度も会ったりしているうちに次第に2人の間の「違い」に気づき、見分けることができるようになってきます。このとき「気づく力=感覚の鋭い人」は、2人の間の「違い」にすぐに気づき、2人を見分けることができるのです。
この「気づき」を得るための五感の訓練が、興南高校の朝の散歩だったのです。
ただ漫然(まんぜん)と道を歩いていたのでは、道端に花が咲いていようとゴミが落ちていようと気づかないことが多いものです。ましてや、道端に咲いている花や草の匂(にお)いなどには気づくはずもありません。さらに、それらが日によってどう「変化」していくかということにもなかなか気づくものではありません。
しかし、生徒たちは後で1分間スピーチをしないといけないので、周囲を一生けんめい観察しながら散歩せざるを得ない。そしてその結果、生徒たちの観察眼は鍛錬(たんれん)され、試合でも生かされるようになったというわけです。
興南高校の生徒たちは、バントや盗塁をするにも監督の指示でやるのではなく、選手自身が相手の選手の状況を見て判断してやっているとのことです。選手の状態は、遠くにいる監督よりすぐ近くにいる選手たちの方がよく気づくことができ臨機応変(りんきおうへん)に対応できるからです。
ヒットを打たれた後やエラーした後などに相手の選手たちが動揺(どうよう)していたら、バントしたり盗塁したりしてさらに相手をかく乱する。また、味方の選手がミスをおかしたりしたら、すぐさま励ましの声をかけてあげたりアドバイスしたりするのです。
ちなみに、プロ野球の名選手と呼ばれた人たちの話を聞くと、ピッチャーが投球前に手をグラブに突っ込んだ時の腕の筋肉の「動き」を見て次投げる球種が分かったり、塁(るい)にいる選手のクセをつかんで盗塁しようとしているかいないかを見分けたりしていたこともあるようです。そういうことは、相手をよく観察し、そのことに気づく感覚を養っていたからできた技(わざ)なのです。
また、我喜屋監督は「試合中にはガッツポーズをしたりするな」と指導しています。ガッツポーズをしたりすると、その間相手の「変化」や「動き」に注意を払うことができないからです。常に試合の状況を把握(はあく)し、次どう行動するか判断するためには、ガッツポーズなどしているヒマは無いということです。
自分から進んでやる「あいさつ」や「ゴミ拾い」が、「ピンチに動じない強い精神力」を生む!
次に、興南高校の選手たちの「ピンチにも動じない強い精神力」が、どう養成(ようせい)されたかについて説明します。それはなんと、
「人が見ていようといまいと、ゴミが落ちていたらゴミを拾う」「相手が誰であろうと、自分からあいさつする」つまり、「状況や相手に関係なく、やるべきことをちゃんとやる」という日頃からの姿勢と実践(じっせん)が、「ピンチに動じない強い精神力」を生んでいたのです。
ゴミ拾いも、みんなとはやるが、一人のときや家ではやらないというのは、もちろん駄目なわけです。
試合でも、相手が弱いチームだからとなめてかかったり手を抜いたりしない。逆に相手が強いチームだからと力(りき)んだりしない。相手がどんなチームであろうと、ただ漫然(まんぜん)と相手や味方を見るのではなく、感覚を磨くために、小さな「変化」や「動き」も見逃さないように全力で注意を払う。
これらのことは、野球だけでなく、他のスポーツや人間関係、勉強などにも言える非常に大切なことです。
親や先生が見ていたらまじめにやるが見てないときは怠(なま)けたりするような陰日向(かげひなた)のある態度では、対戦相手や状況が変わると動揺したりするピンチに弱い人間になってしまいます。
また、クラスメートがカワイくてもカワイくなくても、イケメンでもイケメンでなくても同じように接する。相手が怖い上級生でもペコペコせず、また相手が弱い下級生であっても威張(いば)ったりしないで同じように接する。
テストで悪い成績をとってもガッカリして落ち込んだりしない。逆に良い成績をとっても喜び過ぎて慢心(まんしん)したりしない。このように、スポーツでも勉強でも、どんな状況であろうと、どんな結果であろうと、やるべきことに意識を集中する。これらの日頃の積み重ねが、「ピンチに動じない強い精神力」を養成することになるのです。
興南高校では、「眉毛(まゆ)を剃(そ)ったりしない」ということも指導しています。「他人にどう見えているか。どう言われているか」などと気にしているようでは、相手や状況によっては力を発揮できない人間になってしまうからです。
ただ、マナーはちゃんと守り、「身だしなみ」や「言葉遣(ことばづか)い」はきちんとやるようにとも指導されています。
「眉毛を剃る」のは、人目を気にしてのことなのですが、「身だしなみ」や「言葉遣い」をきちんとするのは、相手に対する敬意(けいい)を表すことだからです。「人目を気にする」行為と「相手に対して敬意を表す」行為とには、大きな「違い」があるのです。
去る1月25日、読谷中学校で興南高校の我喜屋監督による講演会がありました。
みなさんご存知のように、我喜屋監督率いる興南高校は去年、甲子園大会で史上6校目となる春夏連覇を成し遂げました。
興南高校の選手たちは、「ちびっこ軍団」と呼ばれるほど他の学校の選手たちより身長も低く体力もそれほど優(すぐ)れているというものではありませんでした。ところが、ピンチにも動じない強い精神力と冷静な試合運びは、全国一レベルの高いものでした。
例えば、夏の大会準決勝の報徳学園との試合では、連投の島袋投手が打たれて2回までに0−5とリードされていました。しかし、興南高校の選手たちはガッカリしたり動揺したりしませんでした。3回以降島袋投手は配球を修正して立ち直り、他の選手たちも報徳学園のピッチャーの球にタイミングを合わせていき6−5で逆転勝ちしました。
私は、興南高校の選手たちが他の学校の選手たちに比べて、ピンチでも動揺しない強い精神力を持ち試合運びもうまいのに驚き、「いったいどんな練習をしてきたのだろう」と強い関心を持っていました。
それで、我喜屋監督の講演だけでなく、インターネットでも調べて、やっとその理由が分かってきました。
毎日の体操やボール拾い、道端に落ちているゴミを拾うなど、誰でもできることを全力
でやる選手は大きな事ができる!
『興南高校野球部では、小さなことに気付く習慣を身につけさせるために、毎朝6時10分から好きなところを散歩させる。五感を研(と)ぎ澄ますために一人で歩きながら何かを見て、感じてくる。花でも草でも、指でつまんで匂(にお)いをかいでくる。そして、帰って来てから1分間スピーチをする。そのうち、散歩中にゴミが落ちていることに気づき拾ってくる生徒が出てきた。そして、散歩中にゴミ拾いをする選手が増えると、試合での選手たちの送りバントの成功率があがった。』
(以上は、我喜屋監督の話をまとめたものです。)
「散歩やゴミ拾い」と「バントの成功率」の関係は「気づき」である!
「散歩やゴミ拾いと、バントの成功率の間に何の関係があるんだ」と疑問に思う人もいると思いますが、それが大ありなのです。
とてもよく似た双子に初めて会った場合、最初は2人の「違い」に気づかず、見分けることが難しいものです。しかし、何度も会ったりしているうちに次第に2人の間の「違い」に気づき、見分けることができるようになってきます。このとき「気づく力=感覚の鋭い人」は、2人の間の「違い」にすぐに気づき、2人を見分けることができるのです。
この「気づき」を得るための五感の訓練が、興南高校の朝の散歩だったのです。
ただ漫然(まんぜん)と道を歩いていたのでは、道端に花が咲いていようとゴミが落ちていようと気づかないことが多いものです。ましてや、道端に咲いている花や草の匂(にお)いなどには気づくはずもありません。さらに、それらが日によってどう「変化」していくかということにもなかなか気づくものではありません。
しかし、生徒たちは後で1分間スピーチをしないといけないので、周囲を一生けんめい観察しながら散歩せざるを得ない。そしてその結果、生徒たちの観察眼は鍛錬(たんれん)され、試合でも生かされるようになったというわけです。
興南高校の生徒たちは、バントや盗塁をするにも監督の指示でやるのではなく、選手自身が相手の選手の状況を見て判断してやっているとのことです。選手の状態は、遠くにいる監督よりすぐ近くにいる選手たちの方がよく気づくことができ臨機応変(りんきおうへん)に対応できるからです。
ヒットを打たれた後やエラーした後などに相手の選手たちが動揺(どうよう)していたら、バントしたり盗塁したりしてさらに相手をかく乱する。また、味方の選手がミスをおかしたりしたら、すぐさま励ましの声をかけてあげたりアドバイスしたりするのです。
ちなみに、プロ野球の名選手と呼ばれた人たちの話を聞くと、ピッチャーが投球前に手をグラブに突っ込んだ時の腕の筋肉の「動き」を見て次投げる球種が分かったり、塁(るい)にいる選手のクセをつかんで盗塁しようとしているかいないかを見分けたりしていたこともあるようです。そういうことは、相手をよく観察し、そのことに気づく感覚を養っていたからできた技(わざ)なのです。
また、我喜屋監督は「試合中にはガッツポーズをしたりするな」と指導しています。ガッツポーズをしたりすると、その間相手の「変化」や「動き」に注意を払うことができないからです。常に試合の状況を把握(はあく)し、次どう行動するか判断するためには、ガッツポーズなどしているヒマは無いということです。
自分から進んでやる「あいさつ」や「ゴミ拾い」が、「ピンチに動じない強い精神力」を生む!
次に、興南高校の選手たちの「ピンチにも動じない強い精神力」が、どう養成(ようせい)されたかについて説明します。それはなんと、
「人が見ていようといまいと、ゴミが落ちていたらゴミを拾う」「相手が誰であろうと、自分からあいさつする」つまり、「状況や相手に関係なく、やるべきことをちゃんとやる」という日頃からの姿勢と実践(じっせん)が、「ピンチに動じない強い精神力」を生んでいたのです。
ゴミ拾いも、みんなとはやるが、一人のときや家ではやらないというのは、もちろん駄目なわけです。
試合でも、相手が弱いチームだからとなめてかかったり手を抜いたりしない。逆に相手が強いチームだからと力(りき)んだりしない。相手がどんなチームであろうと、ただ漫然(まんぜん)と相手や味方を見るのではなく、感覚を磨くために、小さな「変化」や「動き」も見逃さないように全力で注意を払う。
これらのことは、野球だけでなく、他のスポーツや人間関係、勉強などにも言える非常に大切なことです。
親や先生が見ていたらまじめにやるが見てないときは怠(なま)けたりするような陰日向(かげひなた)のある態度では、対戦相手や状況が変わると動揺したりするピンチに弱い人間になってしまいます。
また、クラスメートがカワイくてもカワイくなくても、イケメンでもイケメンでなくても同じように接する。相手が怖い上級生でもペコペコせず、また相手が弱い下級生であっても威張(いば)ったりしないで同じように接する。
テストで悪い成績をとってもガッカリして落ち込んだりしない。逆に良い成績をとっても喜び過ぎて慢心(まんしん)したりしない。このように、スポーツでも勉強でも、どんな状況であろうと、どんな結果であろうと、やるべきことに意識を集中する。これらの日頃の積み重ねが、「ピンチに動じない強い精神力」を養成することになるのです。
興南高校では、「眉毛(まゆ)を剃(そ)ったりしない」ということも指導しています。「他人にどう見えているか。どう言われているか」などと気にしているようでは、相手や状況によっては力を発揮できない人間になってしまうからです。
ただ、マナーはちゃんと守り、「身だしなみ」や「言葉遣(ことばづか)い」はきちんとやるようにとも指導されています。
「眉毛を剃る」のは、人目を気にしてのことなのですが、「身だしなみ」や「言葉遣い」をきちんとするのは、相手に対する敬意(けいい)を表すことだからです。「人目を気にする」行為と「相手に対して敬意を表す」行為とには、大きな「違い」があるのです。
|
|
|
|
|
|
|
|
国語・算数教室 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
国語・算数教室のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6474人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19244人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208299人