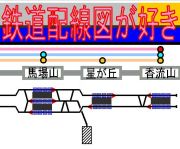|
|
|
|
コメント(19)
今さらですがちょっと考えてみました。
といっても、2:さざなみ みさき さんが挙げた項目にほぼ賛同、
という形ですが。
自分の記憶にある限りでは、やはり予算をあまりかけたくない路線
(と僕が勝手に想像しているだけですが)
にはあまりクロスポイントは使われていませんね。
同じく2:でさざなみさんが書かれていた「以前の東急大井町線」も、
東急電鉄からすれば開発の優先度は東横・新玉/田園に続いて
3番目だろうと想像しています。
また、当時はそれ以上に優先度が低かった(と思いこんでいる)
南北線開通前の目蒲線目黒駅もシングル×2だったはずですし、
池上線五反田駅(大崎広小路駅?)もシングル×2ですよね。
それから、やはり乗り心地(振動)の差は大きいと思います。
これは、本線を引き込み線などが横切る場合に
切り替え可能なクロスを使用していることからも
容易に想像のつく問題だと思います。
そういうわけで、
むしろクロスポイントは「場所がない時の逃げ道」
なのかなぁ、と想像してしまうのです。
場所さえ確保できれば、
故障率はあきらかにシングル×2の方が低いですし、
クロス部の予備在庫も必要ありません
(ポイントは共通だし、中間部は切り出せばよい)
ので。
といっても、2:さざなみ みさき さんが挙げた項目にほぼ賛同、
という形ですが。
自分の記憶にある限りでは、やはり予算をあまりかけたくない路線
(と僕が勝手に想像しているだけですが)
にはあまりクロスポイントは使われていませんね。
同じく2:でさざなみさんが書かれていた「以前の東急大井町線」も、
東急電鉄からすれば開発の優先度は東横・新玉/田園に続いて
3番目だろうと想像しています。
また、当時はそれ以上に優先度が低かった(と思いこんでいる)
南北線開通前の目蒲線目黒駅もシングル×2だったはずですし、
池上線五反田駅(大崎広小路駅?)もシングル×2ですよね。
それから、やはり乗り心地(振動)の差は大きいと思います。
これは、本線を引き込み線などが横切る場合に
切り替え可能なクロスを使用していることからも
容易に想像のつく問題だと思います。
そういうわけで、
むしろクロスポイントは「場所がない時の逃げ道」
なのかなぁ、と想像してしまうのです。
場所さえ確保できれば、
故障率はあきらかにシングル×2の方が低いですし、
クロス部の予備在庫も必要ありません
(ポイントは共通だし、中間部は切り出せばよい)
ので。
>9: ondyさん
いい質問です!(^o^
答えとしては、Y字ポイントの記述については、
描き方によって異なる、ということになります(^^;;
たとえば管理者のさざなみ みさきさんや僕の配線図は、
知りうる限り「どちら側が本線でどちら側が分岐か」を
分かるように描いてあります。
(ここで言う「本線」とは、
例えばもっとも一般的なポイントでの直線の側を指します。
さざなみ みさきさんの言葉をお借りすると、
「通過するときに揺れを感じる」方が分岐側、ということになります)
このような配線図では、Y字ポイントはどちらも角度を持って
枝分かれするように描かれているので区別が可能です。
一方で、長いホームに短い編成が停車するときの停車位置や、
単線区間における信号機の設置位置などにこだわった配線図、
単に線路の接続状況を分かりやすく示した配線図も
このコミュにアップされています。
どちらがいい、ということはなくて、
描いた人がどのように描きたかったか、というだけです。
長い割に大した答えになっていませんが(^^;
いい質問です!(^o^
答えとしては、Y字ポイントの記述については、
描き方によって異なる、ということになります(^^;;
たとえば管理者のさざなみ みさきさんや僕の配線図は、
知りうる限り「どちら側が本線でどちら側が分岐か」を
分かるように描いてあります。
(ここで言う「本線」とは、
例えばもっとも一般的なポイントでの直線の側を指します。
さざなみ みさきさんの言葉をお借りすると、
「通過するときに揺れを感じる」方が分岐側、ということになります)
このような配線図では、Y字ポイントはどちらも角度を持って
枝分かれするように描かれているので区別が可能です。
一方で、長いホームに短い編成が停車するときの停車位置や、
単線区間における信号機の設置位置などにこだわった配線図、
単に線路の接続状況を分かりやすく示した配線図も
このコミュにアップされています。
どちらがいい、ということはなくて、
描いた人がどのように描きたかったか、というだけです。
長い割に大した答えになっていませんが(^^;
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
鉄道線路配線図が好き 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
鉄道線路配線図が好きのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90063人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208309人
- 3位
- 酒好き
- 170692人