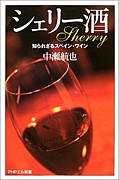シェリーコミュからの移行です。
質問者にはメールにて許可を頂いております。
1.ヴェネンシアもデキャンタも、同じ空気と触れ合う事を促進させてるように見えますが、結果として、違っているのはなぜでしょうか?
また、物理的変化による結果として、味に変化はあるのでしょうか?
(飲み手としては、これが一番大事です。)
ヴェネンシアしない方が良いシェリーもあるということは、最寄の自由が丘のヴェネンシアドールに聞きました。
2.ヴェネンシアの起源がギリシャとは知りませんでした。
どういう由来なんでしょう?
言語的な由来と、事象的な由来と知りたいです。
(〜dorというのは、スペイン語で後天的に付いたという事でしょうか?)
蛇足>バーテンダーは理容師的で、先祖は外科医・薬剤師
ソムリエは美容師的で、先祖は商人・カウンセラー
→自分は、髪型にはあまり頓着しないので、理容師、美容師という区分では理解しにくいのですが、薬剤師と商人という感覚で捉えると納得できました。
自分なりの解釈だと、バーテンダーは体育教師で、ソムリエはスポーツインストラクターって感じでしょうか?(ジムなんか行った事無いけど)
質問者にはメールにて許可を頂いております。
1.ヴェネンシアもデキャンタも、同じ空気と触れ合う事を促進させてるように見えますが、結果として、違っているのはなぜでしょうか?
また、物理的変化による結果として、味に変化はあるのでしょうか?
(飲み手としては、これが一番大事です。)
ヴェネンシアしない方が良いシェリーもあるということは、最寄の自由が丘のヴェネンシアドールに聞きました。
2.ヴェネンシアの起源がギリシャとは知りませんでした。
どういう由来なんでしょう?
言語的な由来と、事象的な由来と知りたいです。
(〜dorというのは、スペイン語で後天的に付いたという事でしょうか?)
蛇足>バーテンダーは理容師的で、先祖は外科医・薬剤師
ソムリエは美容師的で、先祖は商人・カウンセラー
→自分は、髪型にはあまり頓着しないので、理容師、美容師という区分では理解しにくいのですが、薬剤師と商人という感覚で捉えると納得できました。
自分なりの解釈だと、バーテンダーは体育教師で、ソムリエはスポーツインストラクターって感じでしょうか?(ジムなんか行った事無いけど)
|
|
|
|
コメント(8)
Q1にお答えします。
ワインのデカンタージュとシェリーのヴェネンシアは全くの別物です。
ワインは酸化を基本的に嫌います。
が、ややこしいのですが、一方で熟成とは酸化を意味します。
で、ワインには白ワインは主に酸、
赤ワインは主にタンニン、
強いて言えばスパークリングは炭酸が
それぞれ天然の酸化防止剤としてその役目を果たしています。
ですので、デカンタージュ(またはスワリング)は空気に触れさせて
酸化させ酸化した時に現れる味や香りを引き出す為に行います。
が、余計な事を言いますと、デカンタージュによる酸化は
ワインに取って理想ではありません。
可能な限り時間軸によるゆっくりとした酸化(熟成)が好ましく、
その次に飲む時間を逆算して抜栓するのが理想的です。
デカンタージュは究極的な意味ではただの応急処置です。。。
まそれはさておき、、、
つまりワインは空気と触れることでまず天然の酸化防止剤が酸化することで
一種のバリアが敗れ、中に隠れていた香味を引き出す、いわば化学変化です。
そこへ行くとシェリーはまず、酸化から身を守るために、
酸やタンニンなどの葡萄由来の酸化防止効果ではなく、
アルコールという別の外的要因(とは言っても葡萄由来ですが)を用いて
結果的に過度の酸化、別の言い方をすれば好ましくない酸化から
身を守ることで成立したいわゆる強化ワインです。
最も好ましくない酸化は乳酸の好ましくない酸化です。
やや専門的に言えば液中のピルビン酸が
ダイアセチルなどになってしまうのが好ましくない酸化です。
一部例外でこれが脂肪酸と反応するとプラス要因になるんですが・・・
まぁこの話はやめておきます。。。
で、アルコール度数が18%以上でこのピルビン酸の酸化を抑制出来ます。
(注:ピルビン酸≠乳酸。ピルビン酸(一部)⇒乳酸に変化⇒酸化×)
故、大航海時代のシェリーは18%−25%でした。
が、一方で空気に触れながら好ましい酸化(熟成)をします。
これがオロロソです。
好ましい酸化とは主としてアミノ酸や糖類、
それに微量のタンニンの酸化を意味し、これらが香ばしい香味を作り出します。
これはマディラやトゥニーポートも基本同様です。
ある意味、長熟タイプの(スティル)ワインもこれを目指していたんですが、
最近は長期熟成ワインというものの評価が低くなった、
いえ評価出来る人が減ったんですが・・・ま、これもここでやめておきます。
次にフィノに関してですが、
これはフロールという天然の酸化防止的酵母(膜)の働きで、
時間軸が長くても空気を遮断することで酸化を抑えるばかりか、
酵母の特性から液中の酸素を資化(使い)し還元状態にする働きがあります。
ちょっと難しいでしょうかね。。。
が、その間、酸化環境になった場合に変化する要因が、
酵母によって資化される、つまりエサ(エネルギー源)として使われるので、
仮に酸化環境になってもワインのような変化はほとんど起こりません。
このエサというのは主にオロロソで触れたアミノ酸や糖類です。
故、「オロロソは既に酸化している」ので、
「フィノ系は酸化しても変化する要因が非常に少ない」ので、
かつ「共にアルコールが結果的に最強の酸化防止剤として働いている」ので、
開封後も3カ月ー1年もつのです。
つまり、シェリーをデカンタしてもワインのような変化は起こりません。
逆に簡単に変化するようなワインだったら航海には向きませんのでね…
ということで、ヴェネンシアはデカンタージュとは全くの別物です。
ではヴェネンシアの変化とは何か、、、
これは簡単に言うと、アイスクリームがソフトクリームになったような、
コーヒーゼリーをぐちゃぐちゃにしたような、
そういう物理的変化で、酸化が全く無いとは言いませんが、
デキャンタージュの化学的変化とは全く別物です。
上記のいずれも後者が口当たりが優しく香り高くなるのと
ヴェネンシアしたシェリーが柔らかく香り立つのは同じです。
ただ以上に挙げたのは基礎編ですが、、、ま、この辺で・・・
少しお分かりいただけましたでしょうか??
難しかったらスミマセン。。。
つづき、Q−2はまた後で・・・
ワインのデカンタージュとシェリーのヴェネンシアは全くの別物です。
ワインは酸化を基本的に嫌います。
が、ややこしいのですが、一方で熟成とは酸化を意味します。
で、ワインには白ワインは主に酸、
赤ワインは主にタンニン、
強いて言えばスパークリングは炭酸が
それぞれ天然の酸化防止剤としてその役目を果たしています。
ですので、デカンタージュ(またはスワリング)は空気に触れさせて
酸化させ酸化した時に現れる味や香りを引き出す為に行います。
が、余計な事を言いますと、デカンタージュによる酸化は
ワインに取って理想ではありません。
可能な限り時間軸によるゆっくりとした酸化(熟成)が好ましく、
その次に飲む時間を逆算して抜栓するのが理想的です。
デカンタージュは究極的な意味ではただの応急処置です。。。
まそれはさておき、、、
つまりワインは空気と触れることでまず天然の酸化防止剤が酸化することで
一種のバリアが敗れ、中に隠れていた香味を引き出す、いわば化学変化です。
そこへ行くとシェリーはまず、酸化から身を守るために、
酸やタンニンなどの葡萄由来の酸化防止効果ではなく、
アルコールという別の外的要因(とは言っても葡萄由来ですが)を用いて
結果的に過度の酸化、別の言い方をすれば好ましくない酸化から
身を守ることで成立したいわゆる強化ワインです。
最も好ましくない酸化は乳酸の好ましくない酸化です。
やや専門的に言えば液中のピルビン酸が
ダイアセチルなどになってしまうのが好ましくない酸化です。
一部例外でこれが脂肪酸と反応するとプラス要因になるんですが・・・
まぁこの話はやめておきます。。。
で、アルコール度数が18%以上でこのピルビン酸の酸化を抑制出来ます。
(注:ピルビン酸≠乳酸。ピルビン酸(一部)⇒乳酸に変化⇒酸化×)
故、大航海時代のシェリーは18%−25%でした。
が、一方で空気に触れながら好ましい酸化(熟成)をします。
これがオロロソです。
好ましい酸化とは主としてアミノ酸や糖類、
それに微量のタンニンの酸化を意味し、これらが香ばしい香味を作り出します。
これはマディラやトゥニーポートも基本同様です。
ある意味、長熟タイプの(スティル)ワインもこれを目指していたんですが、
最近は長期熟成ワインというものの評価が低くなった、
いえ評価出来る人が減ったんですが・・・ま、これもここでやめておきます。
次にフィノに関してですが、
これはフロールという天然の酸化防止的酵母(膜)の働きで、
時間軸が長くても空気を遮断することで酸化を抑えるばかりか、
酵母の特性から液中の酸素を資化(使い)し還元状態にする働きがあります。
ちょっと難しいでしょうかね。。。
が、その間、酸化環境になった場合に変化する要因が、
酵母によって資化される、つまりエサ(エネルギー源)として使われるので、
仮に酸化環境になってもワインのような変化はほとんど起こりません。
このエサというのは主にオロロソで触れたアミノ酸や糖類です。
故、「オロロソは既に酸化している」ので、
「フィノ系は酸化しても変化する要因が非常に少ない」ので、
かつ「共にアルコールが結果的に最強の酸化防止剤として働いている」ので、
開封後も3カ月ー1年もつのです。
つまり、シェリーをデカンタしてもワインのような変化は起こりません。
逆に簡単に変化するようなワインだったら航海には向きませんのでね…
ということで、ヴェネンシアはデカンタージュとは全くの別物です。
ではヴェネンシアの変化とは何か、、、
これは簡単に言うと、アイスクリームがソフトクリームになったような、
コーヒーゼリーをぐちゃぐちゃにしたような、
そういう物理的変化で、酸化が全く無いとは言いませんが、
デキャンタージュの化学的変化とは全く別物です。
上記のいずれも後者が口当たりが優しく香り高くなるのと
ヴェネンシアしたシェリーが柔らかく香り立つのは同じです。
ただ以上に挙げたのは基礎編ですが、、、ま、この辺で・・・
少しお分かりいただけましたでしょうか??
難しかったらスミマセン。。。
つづき、Q−2はまた後で・・・
Q2にお答えします。
ギリシャ時代の名称は不明ですが、
継承されたローマ時代の名称は「キアトゥス」と言います。
プリニウスの博物誌などにも出てきます。
バーテンダーの方々が用いるバースプーンのルーツです。
当時のキアトゥスは柄杓以外にも
「量り」や「二重アンフォラ冷却用マドラー」などの用途がありました。
ヴェネンシア自体はスペイン語で、
いつ頃、名称が誕生したかは不明ですが、
契約を意味するアヴェネンシアから派生しました。
・ヴェネンシア:道具の名称。
・ヴェネンシアール:動詞形で、ヴェネンシアする事/動作。
・ヴェネンシアドール:名詞でヴェネンシアする人を指します。
西語の「〜dor」は英語の「〜er」と同様です。
ギリシャ時代の名称は不明ですが、
継承されたローマ時代の名称は「キアトゥス」と言います。
プリニウスの博物誌などにも出てきます。
バーテンダーの方々が用いるバースプーンのルーツです。
当時のキアトゥスは柄杓以外にも
「量り」や「二重アンフォラ冷却用マドラー」などの用途がありました。
ヴェネンシア自体はスペイン語で、
いつ頃、名称が誕生したかは不明ですが、
契約を意味するアヴェネンシアから派生しました。
・ヴェネンシア:道具の名称。
・ヴェネンシアール:動詞形で、ヴェネンシアする事/動作。
・ヴェネンシアドール:名詞でヴェネンシアする人を指します。
西語の「〜dor」は英語の「〜er」と同様です。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
シェリー専門 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
シェリー専門のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37839人
- 2位
- 酒好き
- 170669人
- 3位
- マイミク募集はここで。
- 89536人