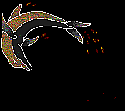飛騨から美濃の山岳地帯には、いたるところに巨石信仰の跡が残されています。
どこの山頂にも磐座(イワクラ)があったり、尾張の平野部にいたっても巨石信仰の多いこの地域ですが、巨石はとき川の氾濫による濁流で自然に運ばれたり、あるいは人為的に船で運ばれてきました。
古墳やお城が造営された場所も当時の川沿いであることがよくわかります。
海から河へ、そして山へとめぐる巨石。
例えば関西では、天の磐船伝説から貴船伝説までこんな例も...
http://
川を通じて伝わった、そんな石の物語をここへまとめていこうと思います!
▼金山巨石群の古代太陽暦
http://
▼冬至の陽光が差し込む神秘の巨石(加茂郡白川町)
http://
▼朝鳥明神の冬至祭(岐阜県揖斐川町)
http://
※参考コミュ
奇岩・巨石・磐座 >> 東海地方の岩談義 トピック
http://
...
どこの山頂にも磐座(イワクラ)があったり、尾張の平野部にいたっても巨石信仰の多いこの地域ですが、巨石はとき川の氾濫による濁流で自然に運ばれたり、あるいは人為的に船で運ばれてきました。
古墳やお城が造営された場所も当時の川沿いであることがよくわかります。
海から河へ、そして山へとめぐる巨石。
例えば関西では、天の磐船伝説から貴船伝説までこんな例も...
http://
川を通じて伝わった、そんな石の物語をここへまとめていこうと思います!
▼金山巨石群の古代太陽暦
http://
▼冬至の陽光が差し込む神秘の巨石(加茂郡白川町)
http://
▼朝鳥明神の冬至祭(岐阜県揖斐川町)
http://
※参考コミュ
奇岩・巨石・磐座 >> 東海地方の岩談義 トピック
http://
...
|
|
|
|
コメント(7)
愛知県稲沢市の尾張大國霊神社(通称:国府宮)にある『磐境』です。
拝殿の奥にある本殿の中に祭祀してありますので、左の写真の通り覗いてしか見ることができません。
なので、右の写真は公式サイトから拝借してきました。
そのサイト内では磐境の岩石は五体とうたっていますが、実際には七体あるそうです。
注連縄に囲まれ、古代さながらに円形に並べられています。
ここは毎年、旧暦の1月13日に有名なはだか祭(儺追神事)が行われます。
今年は明日の2月7日が旧暦1月13日。
厄年の私は、このご神体と一体となる予定です(笑)
ちなみに、ここから北の方にも「七つ石」と呼ばれるストーンサークルがあります。
そちらの写真は探すのが大変な状況ですので、また見つかったら載せたいと思いますが、そのいわれだけ書いておきます。
別名を「剣研石(けんとぎいし)」といい、ヤマトタケルが熱田の森(熱田神宮)から伊吹山に向かう途中ここで剣を研いだという伝説が残っています...
拝殿の奥にある本殿の中に祭祀してありますので、左の写真の通り覗いてしか見ることができません。
なので、右の写真は公式サイトから拝借してきました。
そのサイト内では磐境の岩石は五体とうたっていますが、実際には七体あるそうです。
注連縄に囲まれ、古代さながらに円形に並べられています。
ここは毎年、旧暦の1月13日に有名なはだか祭(儺追神事)が行われます。
今年は明日の2月7日が旧暦1月13日。
厄年の私は、このご神体と一体となる予定です(笑)
ちなみに、ここから北の方にも「七つ石」と呼ばれるストーンサークルがあります。
そちらの写真は探すのが大変な状況ですので、また見つかったら載せたいと思いますが、そのいわれだけ書いておきます。
別名を「剣研石(けんとぎいし)」といい、ヤマトタケルが熱田の森(熱田神宮)から伊吹山に向かう途中ここで剣を研いだという伝説が残っています...
愛知県一宮市起にある大明神社の『祓所』
木曽川沿いにある鳥居の場所は、起渡船場跡(宮河戸跡)です。
起渡船場三ヵ所のうち宮河戸と呼ばれ、かつては大明神社の御手洗に用いられ、水筋変更または通行混雑のとき渡船に使用されました。
祭神は天兒屋根命(アメノコヤネ)。
祝詞の神、出世の神、春日権現、藤原氏の祖神。
神話では天照大神が岩戸隠れした際、岩戸の前で祝詞をあげた。
河内国一宮の枚岡神社第一殿の祭神。
第二殿の比賣大神とともに配祀され、西日本に広く信仰されていた。
中臣鎌足によって春日大社の第三殿と第四殿に勧請された。
また全国の大鳥神社の祭神と同神ともいわれている。
この大明神社は愛知県北部に多いようですが、尾張物部氏が祀った神社だろうと推測しています...
木曽川沿いにある鳥居の場所は、起渡船場跡(宮河戸跡)です。
起渡船場三ヵ所のうち宮河戸と呼ばれ、かつては大明神社の御手洗に用いられ、水筋変更または通行混雑のとき渡船に使用されました。
祭神は天兒屋根命(アメノコヤネ)。
祝詞の神、出世の神、春日権現、藤原氏の祖神。
神話では天照大神が岩戸隠れした際、岩戸の前で祝詞をあげた。
河内国一宮の枚岡神社第一殿の祭神。
第二殿の比賣大神とともに配祀され、西日本に広く信仰されていた。
中臣鎌足によって春日大社の第三殿と第四殿に勧請された。
また全国の大鳥神社の祭神と同神ともいわれている。
この大明神社は愛知県北部に多いようですが、尾張物部氏が祀った神社だろうと推測しています...
ここは八神の八剱神社。
田んぼに囲まれた八神の森は、まるで海に浮かぶ島のよう。
そこへつづく道はこの鳥居から。
ここには、先週お祭りだった石刀神社の旧跡とされる石が祀つられている。
http://photo.mixi.jp/view_album.pl?album_id=500000017472038&owner_id=4857509
愛知県一宮市今伊勢に尾張国中島郡の式内社「石刀(イワト)神社」がある。
この岐阜県羽島市桑原町八神の八剱神社も、式内論社「石刀神社」の一つ。
ちなみに羽島は羽栗(葉栗)郡と中島郡の合併による地名。
この2つの神社は距離的にも離れていますが、境川が氾濫して現在の位置に木曽川が固定されるまで同じ中島郡だったのでしょう。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=34401775&comm_id=3180326
石刀というくらいなので、石にまつわる信仰が何か残されているのではないかと思い行ってきました…(続く)
田んぼに囲まれた八神の森は、まるで海に浮かぶ島のよう。
そこへつづく道はこの鳥居から。
ここには、先週お祭りだった石刀神社の旧跡とされる石が祀つられている。
http://photo.mixi.jp/view_album.pl?album_id=500000017472038&owner_id=4857509
愛知県一宮市今伊勢に尾張国中島郡の式内社「石刀(イワト)神社」がある。
この岐阜県羽島市桑原町八神の八剱神社も、式内論社「石刀神社」の一つ。
ちなみに羽島は羽栗(葉栗)郡と中島郡の合併による地名。
この2つの神社は距離的にも離れていますが、境川が氾濫して現在の位置に木曽川が固定されるまで同じ中島郡だったのでしょう。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=34401775&comm_id=3180326
石刀というくらいなので、石にまつわる信仰が何か残されているのではないかと思い行ってきました…(続く)
八剱神社本殿の左手には石が祀られており「式内石刀神社旧跡」とある。
古代の磐座祭祀の痕跡として、この磐の表面にはあきらかに人工的な施しがされている。
この八剱神社こと石刀神社のご祭神は櫛岩窓(クシイワマド)神という門守(かどもり)の神。
櫛岩窓神の亦の名は豊岩窓(トヨイワマド)神。
その亦の名を天石門別(アメノイワトワケ)神という。
ホツマツタヱ天の巻14アヤには、クシマド(櫛石窓)は宮の日の門(ひのしま)を警護し、イワマド(豊石窓)は月の門(つきのしま)を守ったとある。
つまり、鎮座地の八神は岩神からの変化で、石門=石刀(イワト)の社号から発生した地名。
当社が本来は石刀神社で、石神→岩神→八神への地名変化と相関して八剱の社号へ変化したのでしょう。
古代の磐座祭祀の痕跡として、この磐の表面にはあきらかに人工的な施しがされている。
この八剱神社こと石刀神社のご祭神は櫛岩窓(クシイワマド)神という門守(かどもり)の神。
櫛岩窓神の亦の名は豊岩窓(トヨイワマド)神。
その亦の名を天石門別(アメノイワトワケ)神という。
ホツマツタヱ天の巻14アヤには、クシマド(櫛石窓)は宮の日の門(ひのしま)を警護し、イワマド(豊石窓)は月の門(つきのしま)を守ったとある。
つまり、鎮座地の八神は岩神からの変化で、石門=石刀(イワト)の社号から発生した地名。
当社が本来は石刀神社で、石神→岩神→八神への地名変化と相関して八剱の社号へ変化したのでしょう。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
飛騨*美濃*尾張∞火と水の調和 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
飛騨*美濃*尾張∞火と水の調和のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37839人
- 2位
- 酒好き
- 170669人
- 3位
- マイミク募集はここで。
- 89536人