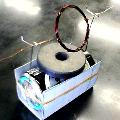先日、同じ学校の初任者の悩みを聞きました。
「クラスの子が、話を聞かないんです。」
という話でした。
みなさんは、話を聞けない子がいたらどうしていますか?
クラスでの取り組み、指導の仕方など、自由にお書きください。
****************************
【スライドゲーム】
子どもの注意を引くための、楽しいゲームです。
「手と手が重なったところで、拍手を一回してね。」
といいます。
支援者は、参加者に向かってローマ字の「K」のような形になります。
両手を上下に移動(スライド)させ、両手のひらが一瞬重なるようにします。
初めは、参加者がなれていないので、拍手がバラバラです。
「みなさん、息が合っていませんね。」
「もっと良く見ないとね。」
などと、励まし、動機付けをします。
続けてやると、拍手が合ってきます。
参加者がのってきたな、と思うところで、
両手のひらが重なる寸前で、止めてみます。
参加者は、重なると思い拍手します。
ここでひとこと、
「だめですよ、良く見ないと。」
低学年であれば、「先生もういっかい!」
などと言って、楽しく注目を集めることができます。
「クラスの子が、話を聞かないんです。」
という話でした。
みなさんは、話を聞けない子がいたらどうしていますか?
クラスでの取り組み、指導の仕方など、自由にお書きください。
****************************
【スライドゲーム】
子どもの注意を引くための、楽しいゲームです。
「手と手が重なったところで、拍手を一回してね。」
といいます。
支援者は、参加者に向かってローマ字の「K」のような形になります。
両手を上下に移動(スライド)させ、両手のひらが一瞬重なるようにします。
初めは、参加者がなれていないので、拍手がバラバラです。
「みなさん、息が合っていませんね。」
「もっと良く見ないとね。」
などと、励まし、動機付けをします。
続けてやると、拍手が合ってきます。
参加者がのってきたな、と思うところで、
両手のひらが重なる寸前で、止めてみます。
参加者は、重なると思い拍手します。
ここでひとこと、
「だめですよ、良く見ないと。」
低学年であれば、「先生もういっかい!」
などと言って、楽しく注目を集めることができます。
|
|
|
|
コメント(5)
はじめまして〜。
小学校で講師をしているものです。
私はクラス担任ではなく、授業だけを担当しているので
ちょっと的外れな意見になってしまったらすいません。
「話を聞かない子」と「話しが聞けない子」だとだいぶ
意味が違ってくるような気がしますが、なかなか話に
集中しずらい子はいますね。
私は周りの立派な態度の子たちを見つけてほめますね。
そうすると段々とクラス全体が話しを聞く姿勢になって
いきます。そうしたらまたすかさずほめますね。
話をするときは、短く簡潔に。細切れに。できるだけ
話を聞きやすいようにするなどはよくやったりしますね〜。
授業中では、漢字や算数に集中させるために、ちょっとした
ゲームをやったりしますね。
分数ゲームや、漢字カルタ、部首オリンピックなどなど。
何だかホントに的外れな意見でしたらすいません。
小学校で講師をしているものです。
私はクラス担任ではなく、授業だけを担当しているので
ちょっと的外れな意見になってしまったらすいません。
「話を聞かない子」と「話しが聞けない子」だとだいぶ
意味が違ってくるような気がしますが、なかなか話に
集中しずらい子はいますね。
私は周りの立派な態度の子たちを見つけてほめますね。
そうすると段々とクラス全体が話しを聞く姿勢になって
いきます。そうしたらまたすかさずほめますね。
話をするときは、短く簡潔に。細切れに。できるだけ
話を聞きやすいようにするなどはよくやったりしますね〜。
授業中では、漢字や算数に集中させるために、ちょっとした
ゲームをやったりしますね。
分数ゲームや、漢字カルタ、部首オリンピックなどなど。
何だかホントに的外れな意見でしたらすいません。
こんにちは
「話を聞く」ということについて
教師も深く考えないといけないかもしれません。
教師が前に立ち話せば,聞けるのがあたりまえなのか・・。
もしかしたら「聞けない」「聞かない」というような
分析も必要でしょう。
それと,聞けない原因が教師自身にないのか・・
話し方,話すタイミング,話す内容,学級経営とか環境
よく
「話を聞けるようにするために」って
我々もそれなりの手立てを(ゲームやスキルアップ的活動で)
行うこともありますが,意外に教師自身の「話」については
何ら向上がなかったりすることもありますね。
「話に集中して聞けない子を聞かせるような話し方」
をマスターすれば,全員がすんなり聞けるようになると
思います。
それが何かと言われれば。。困ってしまいますが 男鹿人
「話を聞く」ということについて
教師も深く考えないといけないかもしれません。
教師が前に立ち話せば,聞けるのがあたりまえなのか・・。
もしかしたら「聞けない」「聞かない」というような
分析も必要でしょう。
それと,聞けない原因が教師自身にないのか・・
話し方,話すタイミング,話す内容,学級経営とか環境
よく
「話を聞けるようにするために」って
我々もそれなりの手立てを(ゲームやスキルアップ的活動で)
行うこともありますが,意外に教師自身の「話」については
何ら向上がなかったりすることもありますね。
「話に集中して聞けない子を聞かせるような話し方」
をマスターすれば,全員がすんなり聞けるようになると
思います。
それが何かと言われれば。。困ってしまいますが 男鹿人
みなさん、お忙しい中書き込みありがとうございます。
>りくりさん、
確かに、「話を聞かない子」と「話しが聞けない子」、中身が違うぶん、一人ひとりの実態をつかむことが大切ですよね。
ほめることで、特に低学年は周りの子がまねしますよね。
>みっつさん、
聞いていなかった子に厳しく注意することもあるようですが、「できるだけこれ以外の方法」とは、どんなものなのか教えていただきたいと思いました。
>男鹿人さん、
子どもを「よく聞ける子」に育てること、また、教師自身が「話し上手」になること、課題ですね。
先日、教室で子どもたちにしたはなしがあります。
テーマは、「自分だけならいいや。」は許されるのか、と言う物です。
<話の内容>
ある小さな島に、中学校があった。その学校の先生の中に、生徒のだれからも信頼されている先生がいた。いつも生徒の悩みに親身になって相談に乗ったり、励ましていたからだ。
そして、島の人たちからも頼りにされていた。その先生は、村に出るたび、村の人々が頼むことを嫌な顔一つせず、やってくれるのである。
しかし、年月が経ち、その先生は転勤することになった。島の人たちは、お別れに、何かプレゼントをしようと考えた。
その島は、葡萄が特産品で、島の財政を担っていた。それぞれ、葡萄畑をもち、育てて出荷していた。島の人々は、その高価な葡萄で、葡萄酒をつくって先生にプレゼントすることにした。一人、びんに一本葡萄酒を入れて持ち寄り、それを樽の中にいれた。
とうとうお別れの時、先生は、島の人々のプレゼントに感激し、心から感謝して島を去った。
そしてその後、先生は、島の人々からもらった樽いっぱいの葡萄酒を、飲むことにした。グラスにそそいだそれは、「水」だった。
さて、どうして樽には「水」しか入っていなかったのだろうか。
それは、島の人々は、高価な葡萄を先生にあげるのが惜しくなったのだ。そこで、「自分だけならいいだろう」「樽の中に、一本だけ水でもばれないだろう」そう思って、樽に水しか入れなかったのである。
「自分一人がなまけても」という気持ちで、全員が行動したらどうなるのか、
子どもたちと一緒に考えてみてください。
>りくりさん、
確かに、「話を聞かない子」と「話しが聞けない子」、中身が違うぶん、一人ひとりの実態をつかむことが大切ですよね。
ほめることで、特に低学年は周りの子がまねしますよね。
>みっつさん、
聞いていなかった子に厳しく注意することもあるようですが、「できるだけこれ以外の方法」とは、どんなものなのか教えていただきたいと思いました。
>男鹿人さん、
子どもを「よく聞ける子」に育てること、また、教師自身が「話し上手」になること、課題ですね。
先日、教室で子どもたちにしたはなしがあります。
テーマは、「自分だけならいいや。」は許されるのか、と言う物です。
<話の内容>
ある小さな島に、中学校があった。その学校の先生の中に、生徒のだれからも信頼されている先生がいた。いつも生徒の悩みに親身になって相談に乗ったり、励ましていたからだ。
そして、島の人たちからも頼りにされていた。その先生は、村に出るたび、村の人々が頼むことを嫌な顔一つせず、やってくれるのである。
しかし、年月が経ち、その先生は転勤することになった。島の人たちは、お別れに、何かプレゼントをしようと考えた。
その島は、葡萄が特産品で、島の財政を担っていた。それぞれ、葡萄畑をもち、育てて出荷していた。島の人々は、その高価な葡萄で、葡萄酒をつくって先生にプレゼントすることにした。一人、びんに一本葡萄酒を入れて持ち寄り、それを樽の中にいれた。
とうとうお別れの時、先生は、島の人々のプレゼントに感激し、心から感謝して島を去った。
そしてその後、先生は、島の人々からもらった樽いっぱいの葡萄酒を、飲むことにした。グラスにそそいだそれは、「水」だった。
さて、どうして樽には「水」しか入っていなかったのだろうか。
それは、島の人々は、高価な葡萄を先生にあげるのが惜しくなったのだ。そこで、「自分だけならいいだろう」「樽の中に、一本だけ水でもばれないだろう」そう思って、樽に水しか入れなかったのである。
「自分一人がなまけても」という気持ちで、全員が行動したらどうなるのか、
子どもたちと一緒に考えてみてください。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
教材研究*ネタ 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
教材研究*ネタのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90013人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208279人
- 3位
- 暮らしを楽しむ
- 75470人