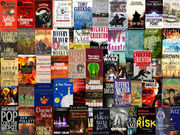|
|
|
|
コメント(56)
■ John Doe
これも私のブログで掲載したものですが、話のネタとして書いてみます。
トム・クルーズ主演の「マイノリティリポート」をぼ〜っと英語で聞いていたら、"Killer is John Doe." のような John Doe という表現が何度も聞こえてきました。意味は分かりましたが、何だか語源が気になって辞書を引きました。名前が分からない犯罪人を指すのに John Doe と言いますが、女性であれば Jane Doe だそうですね。
Google で調べていたら、アメリカ?のテレビ番組で John Doe (http://www.tvtome.com/tvtome/servlet/ShowMainServlet/showid-9049/) という人気番組があるようです。なかなか面白そうなテレビドラマですが、日本では見ることができないので残念。
同じくGoogle で見つけた World Wide Words (www.worldwidewords.org/qa/qa-joh2.htm) で語源を調べると、古くは14世紀辺りまでさかのぼれるようです。まあ、誰が言い出したかはっきりしない言葉だと言えそうです。
Jeffery Deaver の Lincoln Rhyme シリーズでは、John Doe ではなく、単に犯罪者の意味で perp (perpetrator) という言葉を使用していますね。
覚える気などなくても、何度も何度も繰り返して出てくると自然と身に付いてきます。このような効果を狙って、漫然と本を読んだり、DVDを見たり(聞いたり)しているので、時間はかかりますが確実?な不確定性知識が頭にインプットされていきます。
これも私のブログで掲載したものですが、話のネタとして書いてみます。
トム・クルーズ主演の「マイノリティリポート」をぼ〜っと英語で聞いていたら、"Killer is John Doe." のような John Doe という表現が何度も聞こえてきました。意味は分かりましたが、何だか語源が気になって辞書を引きました。名前が分からない犯罪人を指すのに John Doe と言いますが、女性であれば Jane Doe だそうですね。
Google で調べていたら、アメリカ?のテレビ番組で John Doe (http://www.tvtome.com/tvtome/servlet/ShowMainServlet/showid-9049/) という人気番組があるようです。なかなか面白そうなテレビドラマですが、日本では見ることができないので残念。
同じくGoogle で見つけた World Wide Words (www.worldwidewords.org/qa/qa-joh2.htm) で語源を調べると、古くは14世紀辺りまでさかのぼれるようです。まあ、誰が言い出したかはっきりしない言葉だと言えそうです。
Jeffery Deaver の Lincoln Rhyme シリーズでは、John Doe ではなく、単に犯罪者の意味で perp (perpetrator) という言葉を使用していますね。
覚える気などなくても、何度も何度も繰り返して出てくると自然と身に付いてきます。このような効果を狙って、漫然と本を読んだり、DVDを見たり(聞いたり)しているので、時間はかかりますが確実?な不確定性知識が頭にインプットされていきます。
>ねねさん
な〜るほど、Nickel Machineでしたか?それではいくら考えても分かりませんね。2年前にラスベガスに行った時は、Caesar's Palaceに泊まったので、そこのスロットマシンを試してみましたが、そこのマシンは25セントからスタートしていました。向かいにあったイルミネーションのきれいなホテル(名前は忘れました)では、確かに5セントのマシンがあったのを覚えています。
思い出しましたが、半日かけて、Moneyrailと書かれた真っ赤なモノレールに乗って、有名どころのホテルを片っ端からはしごして、スフィンクスとピラミッドがあるルクソールホテルやらMGMのホテルやら、中性のお城のようなホテルなどを見て、最後にラスベガスヒルトンのある駅で、Star TrekのBorgの声のアナウンスにしびれながら、Star Trekの世界を堪能しましたね。そのホテルのすべてにカジノがありました(当たり前なんでしょうが)。
な〜るほど、Nickel Machineでしたか?それではいくら考えても分かりませんね。2年前にラスベガスに行った時は、Caesar's Palaceに泊まったので、そこのスロットマシンを試してみましたが、そこのマシンは25セントからスタートしていました。向かいにあったイルミネーションのきれいなホテル(名前は忘れました)では、確かに5セントのマシンがあったのを覚えています。
思い出しましたが、半日かけて、Moneyrailと書かれた真っ赤なモノレールに乗って、有名どころのホテルを片っ端からはしごして、スフィンクスとピラミッドがあるルクソールホテルやらMGMのホテルやら、中性のお城のようなホテルなどを見て、最後にラスベガスヒルトンのある駅で、Star TrekのBorgの声のアナウンスにしびれながら、Star Trekの世界を堪能しましたね。そのホテルのすべてにカジノがありました(当たり前なんでしょうが)。
■ 遠縁にあたる
1951年制作でビーンクロスビー主演の「花婿来る」という映画を見た事があります。それは字幕付きだったので、ついつい字幕を見てしまいました(見たくないと思っても目に入りますね)が、「遠縁にあたる」という表現が何度も出てきて、いったい、どういう英語なのかが気になりました。正確には覚えていませんが、kissing cousin だったか kissing relation とか何とか言っていました。kiss との関係が分からなかったので、終わってから辞書を引くと・・・。
kissing kin: 会えばキスのあいさつを交わす程度の遠縁の者(kissing cousin など)
とありました。なるほどと思いましたね。
キスに関する新しい表現としては、次の表現が、どこかの本で見かけたか、外国で見かけたか忘れましたが、とにかく頭の中に残っています。
kiss-and-ride (sstem) 〔話〕 キス・アンド・ライド(システム) ((最寄り駅まで配偶者・恋人に車で送られ,キスしてから通勤列車・バスに乗る通勤方法)).
キス・アンド・ライド・スペースというのが、(日本ではない)どこかの駅前にあったと思いました。
1951年制作でビーンクロスビー主演の「花婿来る」という映画を見た事があります。それは字幕付きだったので、ついつい字幕を見てしまいました(見たくないと思っても目に入りますね)が、「遠縁にあたる」という表現が何度も出てきて、いったい、どういう英語なのかが気になりました。正確には覚えていませんが、kissing cousin だったか kissing relation とか何とか言っていました。kiss との関係が分からなかったので、終わってから辞書を引くと・・・。
kissing kin: 会えばキスのあいさつを交わす程度の遠縁の者(kissing cousin など)
とありました。なるほどと思いましたね。
キスに関する新しい表現としては、次の表現が、どこかの本で見かけたか、外国で見かけたか忘れましたが、とにかく頭の中に残っています。
kiss-and-ride (sstem) 〔話〕 キス・アンド・ライド(システム) ((最寄り駅まで配偶者・恋人に車で送られ,キスしてから通勤列車・バスに乗る通勤方法)).
キス・アンド・ライド・スペースというのが、(日本ではない)どこかの駅前にあったと思いました。
■ Scrabble: 英単語力を発揮できるゲーム
ボードゲームの1種で、7個の駒を持ち、その駒の組み合わせで単語を作り、15X15の升目に縦、横、斜めに並べていくことができます。既に置かれている駒につなげることや、間に既存の駒を挟むこともでき、駒自体が持っている点数(A:1点、F:4点、Z:10点等)の合計と、升目の属性(そこに置かれた駒の点数を2倍(double letter score)、3倍とする、そこに置かれる単語の点数を2倍、3倍(triple word score)とする)による点数とを組み合わせて、劇的な高得点を狙う楽しみがあります。単語力があるほど、容易に高い点数を狙うことができ、楽しさも増えます。2〜4人でプレイできますので、このゲームには何かしら特別の魅力があり、参加者で楽しい一時が過ごせます。
ルール等については、http://www.toride.com/~yamazaki/scrabble/ などに詳しく書かれています。このボードゲームはパソコン用のゲームにもなっているので、手軽に遊ぶことができますが、Windows XPなどに対応したフリーウェアがあるかどうかは分かりません。私も探しています。ご存じの方がいらっしゃったら、教えて頂ければ幸いです。
このゲームを本格的に始めると、クロスワード用の辞書などが欲しくなると思います。この世界にはまると、ADやUSAなどの短い略語や、文字を並べ替えるanagramを追求するようになり、site という文字が、sit、tie、ties、it、set、its、ie、es、is といった単語に見えるようになってきますね。
ボードゲームの1種で、7個の駒を持ち、その駒の組み合わせで単語を作り、15X15の升目に縦、横、斜めに並べていくことができます。既に置かれている駒につなげることや、間に既存の駒を挟むこともでき、駒自体が持っている点数(A:1点、F:4点、Z:10点等)の合計と、升目の属性(そこに置かれた駒の点数を2倍(double letter score)、3倍とする、そこに置かれる単語の点数を2倍、3倍(triple word score)とする)による点数とを組み合わせて、劇的な高得点を狙う楽しみがあります。単語力があるほど、容易に高い点数を狙うことができ、楽しさも増えます。2〜4人でプレイできますので、このゲームには何かしら特別の魅力があり、参加者で楽しい一時が過ごせます。
ルール等については、http://www.toride.com/~yamazaki/scrabble/ などに詳しく書かれています。このボードゲームはパソコン用のゲームにもなっているので、手軽に遊ぶことができますが、Windows XPなどに対応したフリーウェアがあるかどうかは分かりません。私も探しています。ご存じの方がいらっしゃったら、教えて頂ければ幸いです。
このゲームを本格的に始めると、クロスワード用の辞書などが欲しくなると思います。この世界にはまると、ADやUSAなどの短い略語や、文字を並べ替えるanagramを追求するようになり、site という文字が、sit、tie、ties、it、set、its、ie、es、is といった単語に見えるようになってきますね。
●挨拶
英語学習本で『How are you?』は日本語の『元気でござるか?』に当たるってかいてあってのを立ち読みしたことがありますが、そうではない気がします。
ネイティブは意外と使ってますよね。
オーストラリアではなまって『How are ya?』(ハぁワィあ)という感じでしょうか、
といってましたよ。スーパーのやる気のないお姉ちゃんも、NO Smileでコレでした。
あと『What have you up to?』と言う人もたくさんいましたが、Haveがあるからbeenとか間に入らないのかなぁ?と疑問です。聞き取れてないダケ?かな?
●食べ物
ハリーポッターのなかでCrumpet(パンケーキみたいなもの。焼いてマーガリンをつけるとうまい!!)が出てきて、ほんとに食べたくなりました。
外国のお菓子って本当に甘い!ですよね。コーラもキットカットの日本のものより甘かったです。(オーストラリアで)
キットカットの発音はキットキャットでした。インテリアShopのイケヤもアイキアって言ってました。多分、オーストラリアだけかな??
●Scrabble
よくやりましたが、語彙の少ないわたしには酷でした
題名はわからないのですが、サンドラ・ブロックが出てた映画でScrabble Clubeみたいなところでおじいちゃんとおばあちゃん達でプレイしてましたよ。
●Jon Doe
アメリカでは身元の分からない死体を(たしか、ニュースなどでも)ポピュラーな名前で呼ぶって聞いたことがありますが・・・、それとは関係ないんですかねぇ?忘れてしまいましたが、まさにJonとかJaneとかありふれた名前でした。
自分の子供にはNanaとはつけたくないですね〜。おばあちゃんだから。
英語学習本で『How are you?』は日本語の『元気でござるか?』に当たるってかいてあってのを立ち読みしたことがありますが、そうではない気がします。
ネイティブは意外と使ってますよね。
オーストラリアではなまって『How are ya?』(ハぁワィあ)という感じでしょうか、
といってましたよ。スーパーのやる気のないお姉ちゃんも、NO Smileでコレでした。
あと『What have you up to?』と言う人もたくさんいましたが、Haveがあるからbeenとか間に入らないのかなぁ?と疑問です。聞き取れてないダケ?かな?
●食べ物
ハリーポッターのなかでCrumpet(パンケーキみたいなもの。焼いてマーガリンをつけるとうまい!!)が出てきて、ほんとに食べたくなりました。
外国のお菓子って本当に甘い!ですよね。コーラもキットカットの日本のものより甘かったです。(オーストラリアで)
キットカットの発音はキットキャットでした。インテリアShopのイケヤもアイキアって言ってました。多分、オーストラリアだけかな??
●Scrabble
よくやりましたが、語彙の少ないわたしには酷でした
題名はわからないのですが、サンドラ・ブロックが出てた映画でScrabble Clubeみたいなところでおじいちゃんとおばあちゃん達でプレイしてましたよ。
●Jon Doe
アメリカでは身元の分からない死体を(たしか、ニュースなどでも)ポピュラーな名前で呼ぶって聞いたことがありますが・・・、それとは関係ないんですかねぇ?忘れてしまいましたが、まさにJonとかJaneとかありふれた名前でした。
自分の子供にはNanaとはつけたくないですね〜。おばあちゃんだから。
>ちかこさん
はじめましてこんにちは^^
>>IKEA
アメリカでもアイキアですよ〜^^
日本でみんながイケアって呼ぶの、馴染めません(><)
あと、トイザラスも最初は許せなかったな〜。
>>Crampet
Crampetはハリー・ポッターを読んでから憧れてる食べ物のひとつです。
>>Scrabble
アメリカにいた時にはまりました!バイト先で、クリスマスに何が欲しい?と聞かれ「Scrabbleのゲーム!」と答えて、買ってもらいました(笑)
でも日本に帰ってきてから一度も使ってません.........。
(だって一緒に遊んでくれる人がいないんだもんっ)
>>Nana
最近おばあちゃんになったうちの母(妹に子供ができた)は、「絶対におばあちゃんとは呼ばせないわよ!」と息まいていて、「じゃあなんて呼ばせるの?」って聞いたら、「Nanaだよ!」って。Nanaってアンタ..........。
うちは親子そろってアメリカかぶれなのであった..........(笑)。
はじめましてこんにちは^^
>>IKEA
アメリカでもアイキアですよ〜^^
日本でみんながイケアって呼ぶの、馴染めません(><)
あと、トイザラスも最初は許せなかったな〜。
>>Crampet
Crampetはハリー・ポッターを読んでから憧れてる食べ物のひとつです。
>>Scrabble
アメリカにいた時にはまりました!バイト先で、クリスマスに何が欲しい?と聞かれ「Scrabbleのゲーム!」と答えて、買ってもらいました(笑)
でも日本に帰ってきてから一度も使ってません.........。
(だって一緒に遊んでくれる人がいないんだもんっ)
>>Nana
最近おばあちゃんになったうちの母(妹に子供ができた)は、「絶対におばあちゃんとは呼ばせないわよ!」と息まいていて、「じゃあなんて呼ばせるの?」って聞いたら、「Nanaだよ!」って。Nanaってアンタ..........。
うちは親子そろってアメリカかぶれなのであった..........(笑)。
>フジタさん
>あ!コストコが一番許せない!!(笑)
私の行動範囲には、コストコなる店がありませんので、キョトンとしてしまいましたが、ふと、Time誌の 2007.11.26日号を見ると、写真のようなWikipediaの創始者の話が載っていました。それで気になって、Wikipediaを調べたら、日本にコストコが進出しようとした時、既に中国系のコスコなる別系統の店が進出していて、その名前が使えず、やむを得ず、コストコにした、という記事がありました。
イケアの発音についても、スウェーデン生まれの店なので、現地の発音は何とも良く分かりませんが、ドイツとオランダではイケアと発音しているらしいです。
トイザらスも、"We are toys"にしなかったのは、創業者の姓の「ラザラス(Lazarus)」に発音が近かったからという俗説もある、なんてWikipediaには書いてありますね。名前と読み方、日本での親しみやすさなど、いろいろと工夫はしているんでしょうけど、人間が慣れ親しんだ名前や発音と違うと違和感を感じるのは仕方ないでしょう。これこそ、文化・習慣の違いに起因する問題ですね。
>あ!コストコが一番許せない!!(笑)
私の行動範囲には、コストコなる店がありませんので、キョトンとしてしまいましたが、ふと、Time誌の 2007.11.26日号を見ると、写真のようなWikipediaの創始者の話が載っていました。それで気になって、Wikipediaを調べたら、日本にコストコが進出しようとした時、既に中国系のコスコなる別系統の店が進出していて、その名前が使えず、やむを得ず、コストコにした、という記事がありました。
イケアの発音についても、スウェーデン生まれの店なので、現地の発音は何とも良く分かりませんが、ドイツとオランダではイケアと発音しているらしいです。
トイザらスも、"We are toys"にしなかったのは、創業者の姓の「ラザラス(Lazarus)」に発音が近かったからという俗説もある、なんてWikipediaには書いてありますね。名前と読み方、日本での親しみやすさなど、いろいろと工夫はしているんでしょうけど、人間が慣れ親しんだ名前や発音と違うと違和感を感じるのは仕方ないでしょう。これこそ、文化・習慣の違いに起因する問題ですね。
■ Never, Never Land
ちょっと前になりますが、「トリビアの泉」というテレビ番組がありました。私が持っている本の中に"Super Trivia" というものがあります。頭に "The Complete Unabridged" 後には "Encyclopedia" が付いている、破天荒に面白い本です(発行年は本当に古い 1977年!!)。サンフランシスコで買ったと思うのですが、内容はアメリカのテレビや映画や日常生活をテーマにしていて、アメリカ! という文化が全面に押し出されています。しかし、中には "Ultra-Man" なんて項目もあります。日本のウルトラマンなんですが、早田隊員(だったですよね)が、なぜか Iyata になって登場しています。昔懐かしいスパイの 0011 ナポレオンソロのU.N.C.L.E(知っている人の方が少ない?)が何の略称かも書いてあります。United Network Command for Law and Enforcement らしいです。スパイ活動って、そんな活動をするものなんですかね?
そんな中でとても意外だったのが、ピーターパンのネバーランドです。ディズニーがネバーランドと言ったからか、それが広まっています。しかし、元は Never, Never Land らしいです。よ〜く考えてみると、ああいう実在しない世界だから Never Land なのではなく、Never ということはない (Never で二重否定)所で、何でも可能な世界という意味に解釈できます。しかし、日本で普及させる場合にもネバーネバーランドでは、ねばねばしてしまうので都合が悪いのか、ネバーランドと親しみ深い名前にしたのでしょう。
本当の所、どうなのかはよく分かりませんが、何となくもっともらしい感じです。
ちょっと前になりますが、「トリビアの泉」というテレビ番組がありました。私が持っている本の中に"Super Trivia" というものがあります。頭に "The Complete Unabridged" 後には "Encyclopedia" が付いている、破天荒に面白い本です(発行年は本当に古い 1977年!!)。サンフランシスコで買ったと思うのですが、内容はアメリカのテレビや映画や日常生活をテーマにしていて、アメリカ! という文化が全面に押し出されています。しかし、中には "Ultra-Man" なんて項目もあります。日本のウルトラマンなんですが、早田隊員(だったですよね)が、なぜか Iyata になって登場しています。昔懐かしいスパイの 0011 ナポレオンソロのU.N.C.L.E(知っている人の方が少ない?)が何の略称かも書いてあります。United Network Command for Law and Enforcement らしいです。スパイ活動って、そんな活動をするものなんですかね?
そんな中でとても意外だったのが、ピーターパンのネバーランドです。ディズニーがネバーランドと言ったからか、それが広まっています。しかし、元は Never, Never Land らしいです。よ〜く考えてみると、ああいう実在しない世界だから Never Land なのではなく、Never ということはない (Never で二重否定)所で、何でも可能な世界という意味に解釈できます。しかし、日本で普及させる場合にもネバーネバーランドでは、ねばねばしてしまうので都合が悪いのか、ネバーランドと親しみ深い名前にしたのでしょう。
本当の所、どうなのかはよく分かりませんが、何となくもっともらしい感じです。
>■ John Doe
多読をはじめて6日目に John Doe という題の本を読んだことがあります。
Cambridge English Reaeders の Level1 で、4,800語くらいの薄い本でした。
そのときは、なんにも考えずにただ読んで終わり、だったのですが。。
その2年半後に、Penguin Readers の seven という本を読んでいたら、
またもや John Doe に出会いました。
"John Doe" is a general name used to talk about the ordinary man in the street
when you do not know his real name.
ここでやっと、最初の本で、なぜ、名前のわからない患者をドクターがJohn Doeと
読んだのかわかって、おもしろいなーと思った記憶があります。
女の人の場合は、Jane Doe っていうんだだそうですね。
Janeといえば、G.I.Janeという映画もありましたね。
多読をはじめて6日目に John Doe という題の本を読んだことがあります。
Cambridge English Reaeders の Level1 で、4,800語くらいの薄い本でした。
そのときは、なんにも考えずにただ読んで終わり、だったのですが。。
その2年半後に、Penguin Readers の seven という本を読んでいたら、
またもや John Doe に出会いました。
"John Doe" is a general name used to talk about the ordinary man in the street
when you do not know his real name.
ここでやっと、最初の本で、なぜ、名前のわからない患者をドクターがJohn Doeと
読んだのかわかって、おもしろいなーと思った記憶があります。
女の人の場合は、Jane Doe っていうんだだそうですね。
Janeといえば、G.I.Janeという映画もありましたね。
>Sunita Senさん
旧ねねさんですよね。どなたでしたっけ?としばらく考え込んでしまいました。mixi内部のすべての情報が書き換わってしまうので、元の名前がサッパリ分からなくなります。かろうじて、過去の会話のやりとりから判定できますが、ほとんど何も発言していない人だったら、それこそ分からないでしょうねぇ。
私がダイエット中に名前を変えるとしたら、8310(Yasai-maru)なんかにするかも知れません。これで思い出した事がありますが、2004年6月20日に、日本工業規格 JIS X 8341-3というものが制定されました。これは「高齢者・障害者等配慮設計指針 − 情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス 」という内容ですが、8341は「人にやさしい」という語呂合わせで採番されています。
アメリカの場合には、こういった、語呂合わせのようなものって、日常生活ではどんなものがありましたっけ?今、少し頭が働かないので、スッと出てきませんが・・・。
旧ねねさんですよね。どなたでしたっけ?としばらく考え込んでしまいました。mixi内部のすべての情報が書き換わってしまうので、元の名前がサッパリ分からなくなります。かろうじて、過去の会話のやりとりから判定できますが、ほとんど何も発言していない人だったら、それこそ分からないでしょうねぇ。
私がダイエット中に名前を変えるとしたら、8310(Yasai-maru)なんかにするかも知れません。これで思い出した事がありますが、2004年6月20日に、日本工業規格 JIS X 8341-3というものが制定されました。これは「高齢者・障害者等配慮設計指針 − 情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス 」という内容ですが、8341は「人にやさしい」という語呂合わせで採番されています。
アメリカの場合には、こういった、語呂合わせのようなものって、日常生活ではどんなものがありましたっけ?今、少し頭が働かないので、スッと出てきませんが・・・。
コストコ、アイケア、やめろよホセ オフテンついでにバルガルキン
以前サンフランシスコの近くに住んでいたのですが、そのあたりでは移民がとにかく多くて、メキシコ中国インドなどからたくさんの人がごっちゃに暮らしていました。英語がまったく話せないまま何年も住みついている人もたくさんいました。
私の狭い生活範囲の中で半分くらいの人がコスコといい、残りの半分がコストコといってました。たいていの人がコスコと言ってもコストコって言っても通じました。どっちが正しいかというより、「通じる」ことが基本なので、なんていったか聞き返されることはあっても、「違う」という拒否にあったことはありませんでした。
IKEAはイケアでもアイキヤでもなくアイケアという人が一番多かったと思います。でもどれでも皆の共通認識として、そういう言い方をする人がいる、というのがありました。
話題になっているトイザらスは何がいけないのでしょうか。たしか、トイザラアスというように「あ」を強く言ってました。
バーガーキングをインドの人はバルガルキンと言ってました。これはさすがにわかりませんでしたが、わかる限りはどんないいかたでもOKだったように思います。
Oftenをオフテンという人もたくさんいて、オークランドエーズの中継中にアナウンサーがオフテンと言ったのに驚いたことがあります。
冗談よせ、とか、そんなバカな、というような言い方に No way Jose(ノーウェイホセ)というのがあって、なんでホセ?と思いました。
私、きっとずいぶん「なまってる」んでしょうねぇ。
以前サンフランシスコの近くに住んでいたのですが、そのあたりでは移民がとにかく多くて、メキシコ中国インドなどからたくさんの人がごっちゃに暮らしていました。英語がまったく話せないまま何年も住みついている人もたくさんいました。
私の狭い生活範囲の中で半分くらいの人がコスコといい、残りの半分がコストコといってました。たいていの人がコスコと言ってもコストコって言っても通じました。どっちが正しいかというより、「通じる」ことが基本なので、なんていったか聞き返されることはあっても、「違う」という拒否にあったことはありませんでした。
IKEAはイケアでもアイキヤでもなくアイケアという人が一番多かったと思います。でもどれでも皆の共通認識として、そういう言い方をする人がいる、というのがありました。
話題になっているトイザらスは何がいけないのでしょうか。たしか、トイザラアスというように「あ」を強く言ってました。
バーガーキングをインドの人はバルガルキンと言ってました。これはさすがにわかりませんでしたが、わかる限りはどんないいかたでもOKだったように思います。
Oftenをオフテンという人もたくさんいて、オークランドエーズの中継中にアナウンサーがオフテンと言ったのに驚いたことがあります。
冗談よせ、とか、そんなバカな、というような言い方に No way Jose(ノーウェイホセ)というのがあって、なんでホセ?と思いました。
私、きっとずいぶん「なまってる」んでしょうねぇ。
>>ねねさん
>>37
アメリカ日常生活で使われる、語呂合わせのようなもの。。。
すぐ思い浮かんだのは、See you later, alligater くらい。。。(笑)
最初ESLで教えてもらっと時は、「え〜、そんなの使う人ほんとにいるん??」と思ったので、実際に実生活で聞いた時は、軽い感動を覚えました(笑)
でも、たまに聞きますよね。。。
残念ながら、No way, Jose.は実際に使ってる人に遭遇した事がまだないです。。。。
(あまり私の周りに、そんなベタな表現を使う人々がいなかっただけかも。)
あ、Rhyming slungだと習いました^^
語呂合わせ的な言葉ってまだまだたくさんあったような?思い出したら、また書き込みしま〜す。
あ、Oftenはアメリカでも結構、オフトュンと発音する方結構いますね。
留学当初(西海岸)でこの発音を聞いた時にすごくショッキングだったのですが(なんせ先生がそう発音してたので)、「これは、オフンと発音する人とオフトュンと発音する人がいて、オフンのほうがメジャーだけど、両方ともあっているの」と説明され、その時は「でも納得いかないっしょ!!」(←頑固だなぁw)と心の中で思っていたのですが、結局、折々にその発音の人に出会うので(アメリカでも出身の違いによるんですかねぇ?)、5年ちょいアメリカに住んでる間に慣れてしまいました。
最初に習ったものと違う内容のことって、受け入れるのに最初はかなり抵抗あったりしますね^^
>>なまり。。。
今は日本で仕事をしている私ですが、お仕事で出会う外国のお客さんによく、「カリフォルニア訛りがあるね!!」と言われます。だもんで、イギリス人のお客さんとかと話してる時はちょっとドキドキしてしまう自分がいます(笑)
>>37
アメリカ日常生活で使われる、語呂合わせのようなもの。。。
すぐ思い浮かんだのは、See you later, alligater くらい。。。(笑)
最初ESLで教えてもらっと時は、「え〜、そんなの使う人ほんとにいるん??」と思ったので、実際に実生活で聞いた時は、軽い感動を覚えました(笑)
でも、たまに聞きますよね。。。
残念ながら、No way, Jose.は実際に使ってる人に遭遇した事がまだないです。。。。
(あまり私の周りに、そんなベタな表現を使う人々がいなかっただけかも。)
あ、Rhyming slungだと習いました^^
語呂合わせ的な言葉ってまだまだたくさんあったような?思い出したら、また書き込みしま〜す。
あ、Oftenはアメリカでも結構、オフトュンと発音する方結構いますね。
留学当初(西海岸)でこの発音を聞いた時にすごくショッキングだったのですが(なんせ先生がそう発音してたので)、「これは、オフンと発音する人とオフトュンと発音する人がいて、オフンのほうがメジャーだけど、両方ともあっているの」と説明され、その時は「でも納得いかないっしょ!!」(←頑固だなぁw)と心の中で思っていたのですが、結局、折々にその発音の人に出会うので(アメリカでも出身の違いによるんですかねぇ?)、5年ちょいアメリカに住んでる間に慣れてしまいました。
最初に習ったものと違う内容のことって、受け入れるのに最初はかなり抵抗あったりしますね^^
>>なまり。。。
今は日本で仕事をしている私ですが、お仕事で出会う外国のお客さんによく、「カリフォルニア訛りがあるね!!」と言われます。だもんで、イギリス人のお客さんとかと話してる時はちょっとドキドキしてしまう自分がいます(笑)
>Often
私もt発音派です。というか私の住んでいた英国北部ヨークシャー及びロンドンあたりでであった人たちは9割がた発音していた気がします。もちろんあってもなくてもいいのですが。
>IKEA
これもアイケアですねぇ。アイキアっぽい発音もあるんですね、初めて知りました(もの知らず)。
>Crumpet
おいしいですよね。だんだん恋しくなってきたのでそのうち作ろうかと考えているところでした。
生活の中の英語というと英国にいた間に、印象的だったあいさつ表現がいろいろありました。まねしてみたいと思いつつ、なかなか使えなかったりするのですが(状況としてふさわしくなかったり、タイミングを逃したりいろいろな理由によりますが)。
まずは Jolly Good! そして次が Cheerio!
これ、どっちもちょっとオールドファッションな言い回しなんですよね。だから使っているのはたいてい年配の方(特に女性)なのですが、響きがやわらかくてとても好きなのです。もうちょっと年をとったら使ってもおかしくなくなるかなぁ?(笑
私もt発音派です。というか私の住んでいた英国北部ヨークシャー及びロンドンあたりでであった人たちは9割がた発音していた気がします。もちろんあってもなくてもいいのですが。
>IKEA
これもアイケアですねぇ。アイキアっぽい発音もあるんですね、初めて知りました(もの知らず)。
>Crumpet
おいしいですよね。だんだん恋しくなってきたのでそのうち作ろうかと考えているところでした。
生活の中の英語というと英国にいた間に、印象的だったあいさつ表現がいろいろありました。まねしてみたいと思いつつ、なかなか使えなかったりするのですが(状況としてふさわしくなかったり、タイミングを逃したりいろいろな理由によりますが)。
まずは Jolly Good! そして次が Cheerio!
これ、どっちもちょっとオールドファッションな言い回しなんですよね。だから使っているのはたいてい年配の方(特に女性)なのですが、響きがやわらかくてとても好きなのです。もうちょっと年をとったら使ってもおかしくなくなるかなぁ?(笑
フジタさん>Oftenはアメリカでも結構、オフトュンと発音・・・(西海岸)でこの発音を聞いた時に・・・
私が住んでいたのもアメリカの西です。カリフォルニアの上のはじっこ、サンフランシスコの近くでした。でもオフトュンでなく「おふてん」でした。
地元の学校の先生は「オフテン」多かったです。
あの辺、スペイン語の方がめっちゃ多いので、JOSEは「ほせ」でしたね。
postageを「ポッセージ」と言う人と「ポステージ」という人がいて、いまだにどっちが標準の発音なのかわかりません。
といざらあす、だと思っていたのは「といざうらす」だったのでしょうか?
私、話し言葉と単語がちゃんと合ってなくて、耳から覚えた言葉のつづりを知らないことがよくあるので。。。。。
私が住んでいたのもアメリカの西です。カリフォルニアの上のはじっこ、サンフランシスコの近くでした。でもオフトュンでなく「おふてん」でした。
地元の学校の先生は「オフテン」多かったです。
あの辺、スペイン語の方がめっちゃ多いので、JOSEは「ほせ」でしたね。
postageを「ポッセージ」と言う人と「ポステージ」という人がいて、いまだにどっちが標準の発音なのかわかりません。
といざらあす、だと思っていたのは「といざうらす」だったのでしょうか?
私、話し言葉と単語がちゃんと合ってなくて、耳から覚えた言葉のつづりを知らないことがよくあるので。。。。。
続けておじゃまします。
昔、アメリカの大学の掲示板で「テキサス向けのパソコンが間違ってカリフォルニアに出荷された。下記の特徴をもったパソコンに心当たりがあったら、無償交換するので連絡ほしい。」というのがあり、「Yes⇒Yap, No⇒Nope」などとなっていました。テキサスでは本当にそんなしゃべり方するのでしょうか?てゆーか、パソコンの言葉づかいまでそんなんなんでしょうか?
生徒に向かって「Folks」と呼びかける先生はシカゴから来たそうで、シカゴではマクドナルドのお姉ちゃんはWelcomeなんか言いやしねぇ、「Whadayawant!」だ、という話をしてました。それ本当?
昔、アメリカの大学の掲示板で「テキサス向けのパソコンが間違ってカリフォルニアに出荷された。下記の特徴をもったパソコンに心当たりがあったら、無償交換するので連絡ほしい。」というのがあり、「Yes⇒Yap, No⇒Nope」などとなっていました。テキサスでは本当にそんなしゃべり方するのでしょうか?てゆーか、パソコンの言葉づかいまでそんなんなんでしょうか?
生徒に向かって「Folks」と呼びかける先生はシカゴから来たそうで、シカゴではマクドナルドのお姉ちゃんはWelcomeなんか言いやしねぇ、「Whadayawant!」だ、という話をしてました。それ本当?
>とっこさん
レスが遅れてすみません。
しょっちゅうMixisぼってるので。。。(汗)
>>often オフテン/オフトュン
これは、両方同じものなんじゃないですか?英語の発音をそのまま正確に日本語のカタカナに直すっていうのがムリ(とうか難しい、というか)があるので、oftenのtを発音する言葉を聴いて、ある人はそれを日本語で「オフテン」と書いて、またる人は「オフトュン」と認識して、という違いだけで、もとは同じ音を聞いているんじゃないか、というのが私の予想です。
だから、IKEAもアイキアとアイケアは同じことなんだと思ってます。違うかな?
>>Yep, Nope
これ、カリフォルニアで普通にみんなが使ってる気がしますけどね〜。私も、相手によっては普通に使ってました。
。。。日本語でも外国語でも、話し方がカジュアルになりすぎるきらいがあるフジタでした〜^^
レスが遅れてすみません。
しょっちゅうMixisぼってるので。。。(汗)
>>often オフテン/オフトュン
これは、両方同じものなんじゃないですか?英語の発音をそのまま正確に日本語のカタカナに直すっていうのがムリ(とうか難しい、というか)があるので、oftenのtを発音する言葉を聴いて、ある人はそれを日本語で「オフテン」と書いて、またる人は「オフトュン」と認識して、という違いだけで、もとは同じ音を聞いているんじゃないか、というのが私の予想です。
だから、IKEAもアイキアとアイケアは同じことなんだと思ってます。違うかな?
>>Yep, Nope
これ、カリフォルニアで普通にみんなが使ってる気がしますけどね〜。私も、相手によっては普通に使ってました。
。。。日本語でも外国語でも、話し方がカジュアルになりすぎるきらいがあるフジタでした〜^^
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
楽しく洋書を味わう 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-