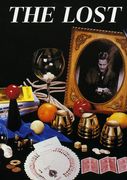クロースアップマジックというものが確立されて来たのはほんの100年くらいの事だそうで比較的マジックの中では新しいジャンルだそうです。日本においてもせいぜい20年くらいではないでしょうか。それもあってか、未だにクロースアップマジックというものがこうだ、という定義付けがなされていません。
人によってはフローティングテーブルを目の前で2〜3人の観客の前でも行う人がいるでしょう。あるいはボーリングの球をほんの50センチ前で出す人もいるかも知れません。
そうかと思えば何百人の前でシガレットペーパーの復活をする人もいます。
もしかすると10人のマジシャンがいたら10個の考え方があるかも知れません。
どういう道具を使うのか、どういう場所や状況で行うのか、皆さんはクロースアップマジックをどう定義づけますか。教えて頂けないでしょうか?
人によってはフローティングテーブルを目の前で2〜3人の観客の前でも行う人がいるでしょう。あるいはボーリングの球をほんの50センチ前で出す人もいるかも知れません。
そうかと思えば何百人の前でシガレットペーパーの復活をする人もいます。
もしかすると10人のマジシャンがいたら10個の考え方があるかも知れません。
どういう道具を使うのか、どういう場所や状況で行うのか、皆さんはクロースアップマジックをどう定義づけますか。教えて頂けないでしょうか?
|
|
|
|
コメント(24)
クロースアップでボーリングの玉を出しちゃったり、ほんの2〜3人相手にテーブルを浮かせたり、シチュエーション次第ではアリだとは「一応」思う側です。そういった場で自らにゴーサインを出したりストップをかけたりするのは、その人のバランス感覚というか美学次第なような気がしますよね。
ジャンル分けや定義は、ものごとを捕まえるのにとても便利な考え方ですが、逆に思考や表現を制限してしまうシロモノでもあるように思います。逆に、発想の自由だ!とばかりに暴走しても、見慣れない、異質感を覚えるような演技になりそうな気もします。
こまかーい事ですが、最近がコインの分野でフィッチパームが流行っているようですが、立って演じるならまだしも、座った状態でまでこのポジションをとってしまうのは基本的にどうかと思います。が、それをねじ伏せる空気を出す事も可能でしょうし、これもまさにバランス感覚と言えるのではないでしょうか。
「空気読め」という台詞がありますが、その空気には残念ながら正解は無いので、「より多くの人と共有しうる常識感」を持つ、「普通」を知っている事が、演技を暴走させないコツではないかと思います。到達はできません。努めるのみです。
ジャンル分けや定義は、ものごとを捕まえるのにとても便利な考え方ですが、逆に思考や表現を制限してしまうシロモノでもあるように思います。逆に、発想の自由だ!とばかりに暴走しても、見慣れない、異質感を覚えるような演技になりそうな気もします。
こまかーい事ですが、最近がコインの分野でフィッチパームが流行っているようですが、立って演じるならまだしも、座った状態でまでこのポジションをとってしまうのは基本的にどうかと思います。が、それをねじ伏せる空気を出す事も可能でしょうし、これもまさにバランス感覚と言えるのではないでしょうか。
「空気読め」という台詞がありますが、その空気には残念ながら正解は無いので、「より多くの人と共有しうる常識感」を持つ、「普通」を知っている事が、演技を暴走させないコツではないかと思います。到達はできません。努めるのみです。
プロとして演じる場合はどんなマジックをしてもありだと感じてしまいます。特に今はクロースアップがはやっており、お客さん側(ようは事務所)は、派手なのをやってくれ、とか、うけるのをやってくれ、とかという要望がままあり、そうした事をやらざる終えない場合もありますよね。
ただ、コンテストの場合は関係者が判断するわけですから、反則技に感じるのは全くもって同感です。
これはあくまで自分のイメージなのですが、昔、松田さんの本で『即席マジック入門』って筑摩書房からでていたと思うんです。(タイトル間違っていたらごめんなさい。)
その即席マジックに対してルビがふってあり、それがクロースアップマジックという言葉だったんです。
つまり、即席マジック、もしくは即席に見えるマジックが、自分にとってのクロースアップマジックですね。
もし、普段からなにげに使っているテーブルがあって、友達が部屋に遊びに来た時に行う、そして改められる、のであればクロースアップだな、とも思いますね。
どうなんでしょう?
まあ、確かに空気を読む、それが一番大事で、なおかつそれが一番難しい事ですよね。
ただ、コンテストの場合は関係者が判断するわけですから、反則技に感じるのは全くもって同感です。
これはあくまで自分のイメージなのですが、昔、松田さんの本で『即席マジック入門』って筑摩書房からでていたと思うんです。(タイトル間違っていたらごめんなさい。)
その即席マジックに対してルビがふってあり、それがクロースアップマジックという言葉だったんです。
つまり、即席マジック、もしくは即席に見えるマジックが、自分にとってのクロースアップマジックですね。
もし、普段からなにげに使っているテーブルがあって、友達が部屋に遊びに来た時に行う、そして改められる、のであればクロースアップだな、とも思いますね。
どうなんでしょう?
まあ、確かに空気を読む、それが一番大事で、なおかつそれが一番難しい事ですよね。
クロースアップ、ステージの分類をするとき、その間にパーラー(日本だとサロン?)というのがありますね。
私としては、微妙なものは結構ここに入るように思います。
たとえば2〜3人相手にフローティングテーブルをやるというのは上記の感覚で行けばパーラーに分類されるのではないでしょうか。
私のイメージでは、立って、テーブルを使わないで行う演技というのは全てパーラーに押し込めても、そう間違いはないような感覚です。
例えばアールネルソンの3本リングもそうですし、コインの3フライやカードToポケットなども、パーラーに含めることが可能かと思います。
かと言って、これらをクロースアップから除外するかどうかというのはまた難しい話ですが。
私としては、微妙なものは結構ここに入るように思います。
たとえば2〜3人相手にフローティングテーブルをやるというのは上記の感覚で行けばパーラーに分類されるのではないでしょうか。
私のイメージでは、立って、テーブルを使わないで行う演技というのは全てパーラーに押し込めても、そう間違いはないような感覚です。
例えばアールネルソンの3本リングもそうですし、コインの3フライやカードToポケットなども、パーラーに含めることが可能かと思います。
かと言って、これらをクロースアップから除外するかどうかというのはまた難しい話ですが。
本来のクロースアップと云う言い方は間違っていたかもしれません。決してカウントの時に立ち上がるとか、ポケットの場合に立ち上がるとか(これはジェニングス師や小生の場合のお腹の問題があると思いますが・・・)がいけないなどと言っている訳ではありません。
もともとクロースアップマジックってのは数人を前にして見せるマジックでありましょうから、それをコンテスト用に何十人も見せると所謂スタンディングアップクロースアップになるし、数名ずつ何度も見せようとするとテーブルホップになるだろうしという様に変遷せざるを得なかったと思うのです。
小生は決して否定する訳ではないが、マニアとしては結局、喫茶店の片隅でコソコソっと見せられてヒェーって云うのが一番好きだって話です。(^^;)
もともとクロースアップマジックってのは数人を前にして見せるマジックでありましょうから、それをコンテスト用に何十人も見せると所謂スタンディングアップクロースアップになるし、数名ずつ何度も見せようとするとテーブルホップになるだろうしという様に変遷せざるを得なかったと思うのです。
小生は決して否定する訳ではないが、マニアとしては結局、喫茶店の片隅でコソコソっと見せられてヒェーって云うのが一番好きだって話です。(^^;)
すごく参考になったので、書き込みさせて頂きました。
>Table Magic は、日常品、とくに仕掛けのないと思われる、その場の人から借りたもので演じるマジックです。
>Close-up Magic の定義は、日常品らしきものを使い、観客の近くで演じられるマジックで、技巧的であり巧妙な手順を有するもの、それがClose-up Magicです。
立っているか、坐っているかは関係ありません。
本来はそういう風に分類されていたのですか!!
まるっきり知りませんでした、BJさんありがとうございます!!
日常品らしき物・・・だから、カードマジックはClose-upに含まれるんですね!!
先日、「手品」と「マジック」の違いは?って言うのをテレビでやっていたのを思い出してしまいました。
普段は、特に気にせずに使っていた言葉でも、実際は間違って使っている事って結構有るんですよね!!
勉強になりました(^^)
>Table Magic は、日常品、とくに仕掛けのないと思われる、その場の人から借りたもので演じるマジックです。
>Close-up Magic の定義は、日常品らしきものを使い、観客の近くで演じられるマジックで、技巧的であり巧妙な手順を有するもの、それがClose-up Magicです。
立っているか、坐っているかは関係ありません。
本来はそういう風に分類されていたのですか!!
まるっきり知りませんでした、BJさんありがとうございます!!
日常品らしき物・・・だから、カードマジックはClose-upに含まれるんですね!!
先日、「手品」と「マジック」の違いは?って言うのをテレビでやっていたのを思い出してしまいました。
普段は、特に気にせずに使っていた言葉でも、実際は間違って使っている事って結構有るんですよね!!
勉強になりました(^^)
手持ちの書籍から以下を探し出しました。
ご参考までに。
The Encyclopedia of Magic and Magicians,1988,T.A.Waters では、"Close-Up Magic"の定義が以下のようになっていました。
「数人の観客に、ごく近くで見せる現象。演者は、しばしば観客に囲まれ座って演技する。その場合、現象は"角度に強い"ことが条件で、広い会場に適したものよりも小さな品々(コインやダイス)が用いられる。大人数を対象としたものと比べてプロットが念入りで、現象は繊細である。そして殆どの現象は、観客を参加者として巻き込む。」
また、The Perfomance of Close-Up Magic,1987,Eugene Burger and Richard Kaufman の中で、今回のトピックのように"Close-Up Magic" の歴史や、定義について論じられています。
歴史事項として Eugene Burger が聞き及んだところによると、
「Close-Up Magic は1926年から1932年の間にニューヨークで形作られた。当時はPocket MagicとかTable Magicと呼ばれていた。というのは、ポケットの中に入るもので、皆がテーブルに着いているときに演じられたからだ。1940年の英国では"Close-Quarter(接近とか接戦の意) Magic"とも呼ばれていた。」とのこと。
この記述の後で、いわゆる"Close-Up Magic"に分類されているものがStageで演じられたり、"Stage Magic"に分類されているものが"Close-Up Magic"として演じられており、筆者自身本当のところどうなのかはっきりしないと述べています。
その上で、結局の所、"Close-Up Magic"とは観客がとても近くに(Very Close)にいるという一点であるといい、コンベンション等で行われる"Close-Up Magic"はまやかしにすぎないと断じています。
彼にとっての"Close-Up Magic"は、2人から4人の観客を相手に、直にふれあうことが出来る(しかも演技の中でしばしば実際に観客に触れる)距離で見せるマジックだと言っています。
ご参考までに。
The Encyclopedia of Magic and Magicians,1988,T.A.Waters では、"Close-Up Magic"の定義が以下のようになっていました。
「数人の観客に、ごく近くで見せる現象。演者は、しばしば観客に囲まれ座って演技する。その場合、現象は"角度に強い"ことが条件で、広い会場に適したものよりも小さな品々(コインやダイス)が用いられる。大人数を対象としたものと比べてプロットが念入りで、現象は繊細である。そして殆どの現象は、観客を参加者として巻き込む。」
また、The Perfomance of Close-Up Magic,1987,Eugene Burger and Richard Kaufman の中で、今回のトピックのように"Close-Up Magic" の歴史や、定義について論じられています。
歴史事項として Eugene Burger が聞き及んだところによると、
「Close-Up Magic は1926年から1932年の間にニューヨークで形作られた。当時はPocket MagicとかTable Magicと呼ばれていた。というのは、ポケットの中に入るもので、皆がテーブルに着いているときに演じられたからだ。1940年の英国では"Close-Quarter(接近とか接戦の意) Magic"とも呼ばれていた。」とのこと。
この記述の後で、いわゆる"Close-Up Magic"に分類されているものがStageで演じられたり、"Stage Magic"に分類されているものが"Close-Up Magic"として演じられており、筆者自身本当のところどうなのかはっきりしないと述べています。
その上で、結局の所、"Close-Up Magic"とは観客がとても近くに(Very Close)にいるという一点であるといい、コンベンション等で行われる"Close-Up Magic"はまやかしにすぎないと断じています。
彼にとっての"Close-Up Magic"は、2人から4人の観客を相手に、直にふれあうことが出来る(しかも演技の中でしばしば実際に観客に触れる)距離で見せるマジックだと言っています。
私のような若輩者がしゃしゃり出るのもアレなんですが‥‥
ことばの出典についてはいろいろとあるでしょうが、マジックが『演じる』ものである以上、見て頂く方々がどうとらえるか、というところが結局ポイントになるのではないかと思います。つまり、お客さんが
「ああ、最近TVでよく見るクロースアップマジックってやつを見たな」
と思うなら、それこそ居酒屋で本からハトを出してもクロースアップでしょう。逆に、目の前でカードtoポケットをやってみせても
「この間TVで誰かがステージに客を上げてやってたやつだな」
と思ったらステージマジックでしょう。
※後者のような例はまず無いと思いますが(^^;
ですから、演じる側の分類としては、『きっとお客さんはクロースアップマジックというふうに認識するだろう』というものがクロースアップということになるんではないかと、漠然とですが、思っています。
ことばの出典についてはいろいろとあるでしょうが、マジックが『演じる』ものである以上、見て頂く方々がどうとらえるか、というところが結局ポイントになるのではないかと思います。つまり、お客さんが
「ああ、最近TVでよく見るクロースアップマジックってやつを見たな」
と思うなら、それこそ居酒屋で本からハトを出してもクロースアップでしょう。逆に、目の前でカードtoポケットをやってみせても
「この間TVで誰かがステージに客を上げてやってたやつだな」
と思ったらステージマジックでしょう。
※後者のような例はまず無いと思いますが(^^;
ですから、演じる側の分類としては、『きっとお客さんはクロースアップマジックというふうに認識するだろう』というものがクロースアップということになるんではないかと、漠然とですが、思っています。
はじめまして、スティングです。
このコミュでは初めての書き込みです。
BJさんのさまざまな書き込みを興味深く読んでいます。
USAのマジック事情に精通されている上に、日本語で論理的にコメントされているので、とても勉強になります。
私の大好きなDavid Copperfieldの話題が出てきたので、少しコメントします。
>ついでですが、皮肉なことに、Frank Garcia が、 Close-up Magic が米国で人気になり広がって行った原因を、David Copperfield だとしています。
>彼のTV-Showで演じたcigarettes through the borrowed(?) quarterで、全米が驚愕したわけです。
cigarettes through the quarterということは、1979年の第2回TVスペシャルからというわけですね。日本では翌年の1980年3月1日に最初のTVスペシャルが放送され、その時以来、私は彼のマジックの虜(とりこ)になりました。
>もちろん、David Copperfield はClose-up Magicianではありませんよ。
David Copperfield は、イリュージョニストと自称していますが、このイリュージョニストという呼び方を彼以前に使っていたマジシャンは、いるのでしょうか?
ご存知でしたら、教えてください。
このコミュでは初めての書き込みです。
BJさんのさまざまな書き込みを興味深く読んでいます。
USAのマジック事情に精通されている上に、日本語で論理的にコメントされているので、とても勉強になります。
私の大好きなDavid Copperfieldの話題が出てきたので、少しコメントします。
>ついでですが、皮肉なことに、Frank Garcia が、 Close-up Magic が米国で人気になり広がって行った原因を、David Copperfield だとしています。
>彼のTV-Showで演じたcigarettes through the borrowed(?) quarterで、全米が驚愕したわけです。
cigarettes through the quarterということは、1979年の第2回TVスペシャルからというわけですね。日本では翌年の1980年3月1日に最初のTVスペシャルが放送され、その時以来、私は彼のマジックの虜(とりこ)になりました。
>もちろん、David Copperfield はClose-up Magicianではありませんよ。
David Copperfield は、イリュージョニストと自称していますが、このイリュージョニストという呼び方を彼以前に使っていたマジシャンは、いるのでしょうか?
ご存知でしたら、教えてください。
早速入って、初の発言です。 書き終わって推敲したら、なんとも長いなあ。俺がこうも書くことになるとは、と自分でも。
まったくここまでの流れとは異なる観点ですが、歴史的に大きな転回を迎えたトピックとして大きく二つあると思っています。それがスライディーニと、マイケルアマーの出現です。
スライディーニのスタイルは、およそそれ以前とは異なり、大ステージの上で、四角い机を斜めに置いて、マジシャンとお客様の顔がそれぞれ客席から見えるようにすわり、マジシャンはあくまで隣に座ったお客様に小さい手品を見せ、そのお客様はそれを見て楽しみ、満座のお客様はそれを離れた位置からいわば傍観して楽しむ、というものです。
このことは奇術研究に、若き気賀康夫が海外大会参加レポートして書いた記事に(日本ではおそらく初めて)でてきます。このスタイルで、実際見せる際に抱かれかねないあまりにもの不思議に対する懐疑や、ちょっとした被害者意識の発生を構造的に押さえ込み、満座は自分が安全地帯に置かれた安心から何のストレスもなく楽しむことができる、というわけです。
このスタイルが何と呼称されたかはわかりませんが、少なくてもステージ、パーラーとはいわれなかったには違いない。
もっと言えば、このスタイルは現在日本でも見られる。それが、誰あろう前田さんに代表される現在のテレビでのクロースアップ放送。この構造は意図せずして、まったくスライディーニのそれと同じであることが、こうしてみれば明らかとなり、これは私が今こうして書き込むうちに発見したことで、ほんの今気づいた自分も驚愕の事実であった!!
このくらい古いフィルムで、若きダイバーノンが、ちょっとしたパーティの席のような机に座った状態で、周りに座る数人にカップアンドボールを見せていたのを見たことがあり、これは明らかにクロースアップ。
しかし、対象にする人数が明らかに違い、スライディーニの客数でも、テレビの前田さんでも、クロースアップそれ自体であるといえるのでは。
もうひとつの転回が、マイケルアマーによってもたらされたのは、立ってやるクロースアップというスタイルで、これはおそらくこの時期同時発生的に定着したものと思われるが、はっきりしたのがアダムフレッシャーが出版したマジカルアートジャーナル誌(これも日本語訳がでていた!)におけるマイケルの論文「どこに立ちますか?」だったと思う。
ここでは確か、これまではラッピングの都合上どう座るかどこに座るかがこれまでの問題点だったことに対して、立ちのスタイルの発見によってマジシャンのアクティングエリアや表現方法は大きく広がり、このお客様に対するアドバンテージの大きさはラッピングなどの座りのテクニックを捨てるに値する大きな転回であり、だからいまやマジシャンはどこに座るかではなくどこに立つのかが大きな問題なのだ、といったものだったと思う。
ここではより多数のお客様に見せるためではなく、あくまでも表現方法のひとつとして立ちを選択する、といった書き方だったと思う。実際、副産物として(?)多数の観客を相手にすることができることとなり現在に至る。
実際の「クロースアップ」の定義としては、カズカタヤマが東京堂の本に書いたように、余技としてちょこっと小さく見せる、というのが狭義ながら当たっているようにも思えるが、このトピにトニーとマイケルがでてこないのは不当だと思ったので、書き込んだしだい。
やる方、見る方の視点の違いも、クロースアップの定義を左右するのではないか、ということです。
ズルを言えば、これはクロースアップだといえばクロースアップだし、見るほうがそう認めればクロースアップ。これはステージでもサロンでもパーラーでもないよね、と思われるもの、『きっとお客さんはクロースアップマジックというふうに認識するだろう』というものがクロースアップ(kushioさん)ということになるんではないかと、これは完全にずぼらな(だが外れてはいない)定義。ということでどうでしょう。
と、これを書くのに、1時間半かかった。以上です。
まったくここまでの流れとは異なる観点ですが、歴史的に大きな転回を迎えたトピックとして大きく二つあると思っています。それがスライディーニと、マイケルアマーの出現です。
スライディーニのスタイルは、およそそれ以前とは異なり、大ステージの上で、四角い机を斜めに置いて、マジシャンとお客様の顔がそれぞれ客席から見えるようにすわり、マジシャンはあくまで隣に座ったお客様に小さい手品を見せ、そのお客様はそれを見て楽しみ、満座のお客様はそれを離れた位置からいわば傍観して楽しむ、というものです。
このことは奇術研究に、若き気賀康夫が海外大会参加レポートして書いた記事に(日本ではおそらく初めて)でてきます。このスタイルで、実際見せる際に抱かれかねないあまりにもの不思議に対する懐疑や、ちょっとした被害者意識の発生を構造的に押さえ込み、満座は自分が安全地帯に置かれた安心から何のストレスもなく楽しむことができる、というわけです。
このスタイルが何と呼称されたかはわかりませんが、少なくてもステージ、パーラーとはいわれなかったには違いない。
もっと言えば、このスタイルは現在日本でも見られる。それが、誰あろう前田さんに代表される現在のテレビでのクロースアップ放送。この構造は意図せずして、まったくスライディーニのそれと同じであることが、こうしてみれば明らかとなり、これは私が今こうして書き込むうちに発見したことで、ほんの今気づいた自分も驚愕の事実であった!!
このくらい古いフィルムで、若きダイバーノンが、ちょっとしたパーティの席のような机に座った状態で、周りに座る数人にカップアンドボールを見せていたのを見たことがあり、これは明らかにクロースアップ。
しかし、対象にする人数が明らかに違い、スライディーニの客数でも、テレビの前田さんでも、クロースアップそれ自体であるといえるのでは。
もうひとつの転回が、マイケルアマーによってもたらされたのは、立ってやるクロースアップというスタイルで、これはおそらくこの時期同時発生的に定着したものと思われるが、はっきりしたのがアダムフレッシャーが出版したマジカルアートジャーナル誌(これも日本語訳がでていた!)におけるマイケルの論文「どこに立ちますか?」だったと思う。
ここでは確か、これまではラッピングの都合上どう座るかどこに座るかがこれまでの問題点だったことに対して、立ちのスタイルの発見によってマジシャンのアクティングエリアや表現方法は大きく広がり、このお客様に対するアドバンテージの大きさはラッピングなどの座りのテクニックを捨てるに値する大きな転回であり、だからいまやマジシャンはどこに座るかではなくどこに立つのかが大きな問題なのだ、といったものだったと思う。
ここではより多数のお客様に見せるためではなく、あくまでも表現方法のひとつとして立ちを選択する、といった書き方だったと思う。実際、副産物として(?)多数の観客を相手にすることができることとなり現在に至る。
実際の「クロースアップ」の定義としては、カズカタヤマが東京堂の本に書いたように、余技としてちょこっと小さく見せる、というのが狭義ながら当たっているようにも思えるが、このトピにトニーとマイケルがでてこないのは不当だと思ったので、書き込んだしだい。
やる方、見る方の視点の違いも、クロースアップの定義を左右するのではないか、ということです。
ズルを言えば、これはクロースアップだといえばクロースアップだし、見るほうがそう認めればクロースアップ。これはステージでもサロンでもパーラーでもないよね、と思われるもの、『きっとお客さんはクロースアップマジックというふうに認識するだろう』というものがクロースアップ(kushioさん)ということになるんではないかと、これは完全にずぼらな(だが外れてはいない)定義。ということでどうでしょう。
と、これを書くのに、1時間半かかった。以上です。
「現在におけるクロースアップマジックの礎を築いたのは、アメリカにおいてはトニー・スライディーニ、イギリスにおいてはジョン・ラムジーである。」
そう説いたのは、アメリカの研究家であり著述家のカール・ファルブスです。
先だってのザ・マジック誌においても前田知洋氏もインタビューでスライディーニのその功績について語っています。
しかし、面白い事にスライディーニがアメリカのマジック界で発見され、評価されたのは、1940年代の後半です。
クロースアップマジックと云うマジックが認知されつつあったのは20世紀の初頭でしょう。
そして確立されて来たのが、Tangoさんがこのトピで発表なさったように70〜80年ほど前かと思われます。
ところが、この時代のマジシャンやマジックは、必ずしもテーブル上で現象を行っていないのです。
スタンディング式のクロースアップが流行するようになった立役者の一人がマイケル・アマーである事は自分も同意しますが、じつは元々のクロースアップマジック自体がスタンディング式だったのではないかと思われます。
実際、ネイト・ライプチッヒ、マックス・マリニ、エミール・ジャローなどは、演じているマジックのジャンルはクロースアップであったのにも関わらず、スタンディングであり、大勢の観客を相手に行っています。
アメリカにおいてはむしろギャンブルの歴史との融合においてテーブル上でのマジックが盛んになっていった可能性があります。
1920年代においてのデイリー博士や、新聞記者であったフレドリック・ブロウなどのアマチュアマジシャンが、クロースアップのカードマジックを深く研究し、広まっていったのではないでしょうか。
ダイ・バーノンも当時は研究家でありました。
後にイギリス・ヨーロッパレクチャーを行った際には、ほとんどがスタンディングのクロースアップであった事は、その演目より推測出来ます。
そう説いたのは、アメリカの研究家であり著述家のカール・ファルブスです。
先だってのザ・マジック誌においても前田知洋氏もインタビューでスライディーニのその功績について語っています。
しかし、面白い事にスライディーニがアメリカのマジック界で発見され、評価されたのは、1940年代の後半です。
クロースアップマジックと云うマジックが認知されつつあったのは20世紀の初頭でしょう。
そして確立されて来たのが、Tangoさんがこのトピで発表なさったように70〜80年ほど前かと思われます。
ところが、この時代のマジシャンやマジックは、必ずしもテーブル上で現象を行っていないのです。
スタンディング式のクロースアップが流行するようになった立役者の一人がマイケル・アマーである事は自分も同意しますが、じつは元々のクロースアップマジック自体がスタンディング式だったのではないかと思われます。
実際、ネイト・ライプチッヒ、マックス・マリニ、エミール・ジャローなどは、演じているマジックのジャンルはクロースアップであったのにも関わらず、スタンディングであり、大勢の観客を相手に行っています。
アメリカにおいてはむしろギャンブルの歴史との融合においてテーブル上でのマジックが盛んになっていった可能性があります。
1920年代においてのデイリー博士や、新聞記者であったフレドリック・ブロウなどのアマチュアマジシャンが、クロースアップのカードマジックを深く研究し、広まっていったのではないでしょうか。
ダイ・バーノンも当時は研究家でありました。
後にイギリス・ヨーロッパレクチャーを行った際には、ほとんどがスタンディングのクロースアップであった事は、その演目より推測出来ます。
いまやすでに、2月13日、です。
先に書き込んだ都合上、こちらで発言をいたします。
こうしたコミュは、本来の研究をつきつめる場になりうると同時に、あらゆる人のさまざまな発言を見ることができることで、たとえそれがある人には無意味であいまいなものであったとしても、ある人にとっては価値を発見することができる、さまざまなアイデア、真理へのインキュベーター(孵化させる機械)のような役割を果たすものと思います。
こうした気づきは所謂「悟り」というようなものです。
悟れない人は悟れないが、悟る人は悟ってしまう。
だから、『モラル、倫理の問題を抜きにして』、こうした場での発言に無駄なものは基本的にはないと考えます。
事実、先の私のあいまいな上に論旨も不明解な文章に、RYUSEIさんは見事な関連事項をアップされたではないですか。何もなしではアップもありえなかったというべきでしょう。
あってもなくても、いずれアップは真実としてなされるというようであれば、はなからこうしたコミュの必要性は消失します。迷路のようにあちこちに試行錯誤して行き止まり戻りつするうちについにたどり着くのがゴールなはず。
そもそも、文章自体に意味が内包されているという考え方を、私はとりません。それを読む人が、そこに意味を発見していくのであって、結果意味が発見されたからといって、文章に意味があったわけではなく、実は書く人さえも、書いたとたんにそれを読むことでその意味を認識し、自分が書いたのはこういうことだと納得する、という経過をたどるものだと考えています。
さて、思いついてちょっと書き込もうと考えた人が、後から血の気が引くような反駁を受ける思いに発言を控える、といった事態はこうした場の健全性を阻害するものだと思います。
また、組織を運営するノウハウというのも、昔の軍隊式系統に沿ったものから、参画型マネジメントへと変わってきていることは、社会人にはおなじみのはず(軍隊式が人間の感情に一切考慮せず指示系統と権威、権限の徹底で組織を運営するのに対して、参画型は感情を無視して組織は運営できない、とする考え方)。正しいかどうか以前に、人の感情は無視してはならないとするこの組織論は、別にあいまいなあなあ好きな日本のオリジナルな発想ではなく、軍隊式に疑問を抱いた米国の社会心理学者あたりが構築した理論です。
といったことで、先の私の発言を自ら擁護するとともに、『今後も当コミュを運営する上で、かならずしもあるひとのコメントが有益とは言えない、という結論に達しようとしています』という他所での発言に同意するものであります。同時に削除されていく可能性にはもったいなさと残念をも感じます。
しかし、先日私は、削除されているという夢を見た!!
以上です。
先に書き込んだ都合上、こちらで発言をいたします。
こうしたコミュは、本来の研究をつきつめる場になりうると同時に、あらゆる人のさまざまな発言を見ることができることで、たとえそれがある人には無意味であいまいなものであったとしても、ある人にとっては価値を発見することができる、さまざまなアイデア、真理へのインキュベーター(孵化させる機械)のような役割を果たすものと思います。
こうした気づきは所謂「悟り」というようなものです。
悟れない人は悟れないが、悟る人は悟ってしまう。
だから、『モラル、倫理の問題を抜きにして』、こうした場での発言に無駄なものは基本的にはないと考えます。
事実、先の私のあいまいな上に論旨も不明解な文章に、RYUSEIさんは見事な関連事項をアップされたではないですか。何もなしではアップもありえなかったというべきでしょう。
あってもなくても、いずれアップは真実としてなされるというようであれば、はなからこうしたコミュの必要性は消失します。迷路のようにあちこちに試行錯誤して行き止まり戻りつするうちについにたどり着くのがゴールなはず。
そもそも、文章自体に意味が内包されているという考え方を、私はとりません。それを読む人が、そこに意味を発見していくのであって、結果意味が発見されたからといって、文章に意味があったわけではなく、実は書く人さえも、書いたとたんにそれを読むことでその意味を認識し、自分が書いたのはこういうことだと納得する、という経過をたどるものだと考えています。
さて、思いついてちょっと書き込もうと考えた人が、後から血の気が引くような反駁を受ける思いに発言を控える、といった事態はこうした場の健全性を阻害するものだと思います。
また、組織を運営するノウハウというのも、昔の軍隊式系統に沿ったものから、参画型マネジメントへと変わってきていることは、社会人にはおなじみのはず(軍隊式が人間の感情に一切考慮せず指示系統と権威、権限の徹底で組織を運営するのに対して、参画型は感情を無視して組織は運営できない、とする考え方)。正しいかどうか以前に、人の感情は無視してはならないとするこの組織論は、別にあいまいなあなあ好きな日本のオリジナルな発想ではなく、軍隊式に疑問を抱いた米国の社会心理学者あたりが構築した理論です。
といったことで、先の私の発言を自ら擁護するとともに、『今後も当コミュを運営する上で、かならずしもあるひとのコメントが有益とは言えない、という結論に達しようとしています』という他所での発言に同意するものであります。同時に削除されていく可能性にはもったいなさと残念をも感じます。
しかし、先日私は、削除されているという夢を見た!!
以上です。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
クラシックマジック研究 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-